21 / 23
おまけ
羽素未世と佐坂智也のお料理日和
しおりを挟む
これは私が十和さんの家で暮らすことになって一週間ほど経ったある日のお話。
学校からの帰りに、私と智也くんはスーパーに寄ってから帰宅した。
私の手には夕食の材料が入った買い物袋がある。まだ、ギプスをつけている智也くんに持たせるわけにはいかない。スーパーで一悶着あったが、私が持つことで智也くんも納得してくれた。
「ただいま」
そう言って私と智也くんは家に入る。十和さんの家に帰ってくるのは、まだ慣れなくてなんだか不思議な気分だ。
私たちは買い物袋をキッチンのあるダイニングテーブルに置くと、二階に上がっていく。
「それじゃあ、一息ついたら始めよっか」
「うん」
そんな会話をして、私たちはそれぞれのネームプレートが付いた部屋に入っていった。私の部屋と智也くんの部屋は隣同士だ。二階にはまだたくさん空き部屋があった。
私の部屋には、もともとあったベッドと机と鏡付きのクローゼットがあるだけだ。まだ暮らし始めて一週間ほどしか経っていないので、殺風景なのは仕方ない。最も、私自身の私物はきわめて少なかった。ホテルから運んできた僅かな私物は服と教科書などの学習用品と化粧道具だけ。生活するのに必要最低限なものしかない。
ホテルに暮らしていた時は気にならなかったが、今思うと高校生とは思えないくらい少ない。
ため息をつきながら、私は制服から部屋着に着替える。白いセーターに、薄茶色のコットンパンツとラフな格好だ。
着替え終えると、私はベッドに仰向けに倒れ込む。
クッションからくる反動が心地よい。疲れた身体を癒やすように、私は全体重をベッドに預ける。
なんだかひどく疲れていた。原因はわかっている。でも、それは私が望んでやっていることだから、言い訳にはできない。だから、私が今すべきことは、この後のためにできる限り休むことだった。
部屋にはカチカチと時計の音が響いていた。規則的な時計の針の音は眠気を誘う。
今日あったことを思い返しながら、うとうとと意識がまどろみに沈んでいく。
時間の流れがゆっくり感じる。
嫌な感じはしない。
とても穏やかな時間だった。
こんな風に生活できるとは、あの頃は思わなかった。
そんな時だった。
部屋がコンコンとノックされる。
「はーい」
私が返事すると、扉が開いて智也くんが現れる。グレーのフリースに、黒のスウェットと彼もラフな部屋着になっていた。
「そろそろ始めるけど……あっ、ごめん。寝てた?」
智也くんは慌てて、扉を閉めようとする。
「うんん。ちょっと休んでいただけ。大丈夫」
「そう。病み上がりなんだから無理しないでね」
「うん。ありがとう」
そんな風に言う智也くんはまだ左腕にギプスをしている。どうやら全治三週間ぐらいかかるらしい。だから、私はまず彼の左腕になることにした。それが彼を傷つけた私の償いだった。多分、智也くんは気にしないでというだろう。でも、自分で納得はできない。だから、半ば強引に私は私の罪を償っていた。
私はいつかした小さな誓いの通り、智也くんのためにできることならなんでもするつもりだった。重たい荷物を持ったり、彼が何かをするとき手伝ったり、学校でも家でも彼の姿をずっと追っていた。そのせいでひどく疲れたのは彼には内緒だ。
「じゃあ、始めよっか」
私はそう言ってベッドなら立ち上がる。そして、智也くんと部屋からでて、ダイニングに向かった。
私たちはこれから晩御飯を作ろうとしていた。
十和さんの方針で、この家ではただで住める代わりに家事をすることになっていた。そのため、智也くんはこの家の料理を全てまかなっていた。ちなみに、私は洗濯担当である。男物のパンツだろうが、何だろうが気にせずまとめて洗って干している。
料理をするには両手が必要になってくる。でも、今、智也くんは左腕が使えない。だから、私も手伝っていた。
智也くんと料理をしていると、昔、お母さんの手伝いをしたことを思い出す。
懐かしい思い出。同時に、二度と戻らない日々は、私の心の琴線に触れる。心が泣きたくなる前に、私は思い出に蓋をした。
「今日は何を作るの?」
緑色のエプロンを着けながら、私は今日の晩御飯を尋ねた。
「最近、鍋が続いているから別の物にしようと思うんだ」
智也くんはエプロンをつけながら、答えた。ちなみに、エプロンはシンプルな青一色である。
「別の物?」
私が疑問の声をあげると、智也くんは買い物袋の中から、豚のロース肉を取り出した。
「これを使います」
「とんかつ?」
智也くんは一瞬押し黙る。そして、ロース肉を見ると、私に尋ねた。
「……もしかして、とんかつが食べたかった?」
「えっ?いや、そうじゃないけど」
どうやら違うらしい。でも、他には思い浮かばなかった。
「豚のしょうが焼きなんかどうかなと思って」
「ああー」
それ以外のリアクションが浮かばない。微妙というわけではない。でも、可でもなく、不可でもなく。なんというか地味だった。
そんなリアクションを見て、智也くんはもう一度豚肉を見る。そして、豚肉をダイニングテーブルの上に置くと、
「パン粉と油買ってくる」
と言ってエプロンをはずし始めた。
「いや、いいから」
私は慌てて智也くんを止める。
「えっ、でも」
「とんかつとしょうが焼きなら、しょうが焼きの方が好きだから」
嘘だった。本当はどっちでもいい。でも、智也くんを止めるために背に腹は代えられない。人間の言葉というものは時々、本当にいい加減で、適当だ。
「本当に?」
智也くんは疑いの目で見てくる。めんどくさい。仕方なく私は、智也くんに納得してもらうため、わざとらしく明るい声を上げた。
「本当!本当だから。しょうが焼きだーい好き」
自分で言ってて悲しくなる。
あれ?私こんなキャラだっけ?
「そっか」
智也くんはなんとか納得してくれる。今のどこに納得できるポイントがあるのかわからないが、私はほっとする。同時に脳裏には一つの疑問が浮かんでいた。
本当は智也くんってアホなんじゃないだろうか?
その答えは考えないことにする。
「じゃあ、しょうが焼きと、大根のみそ汁、それから湯豆腐とキュウリとワカメの酢の物を作ろう」
さらっと湯豆腐を入れてくるところが智也くんらしい。鍋にも入れるし、朝の味噌汁にも入れるし、気がつくと豆腐が出てくる。よくよく考えたら毎日豆腐を食べていた。そのうち、お弁当にも豆腐が出てきそうで、若干恐ろしくなる。水気のある豆腐をどうやってお弁当に詰めるのかは想像がつかないが、智也くんならやりかねないと思った。さすがにそんなことはないと思いたいけど、ありえそうなのが智也くんだ。
そういえば、一昨日は朝食から湯豆腐を出すという高級料亭みたいなことをしていた。
智也くん曰く、朝から湯豆腐を食べると気持ちが豊かになるらしいが、私にはよくわからない。後で十和さんに聞いたのだが、この考えは長期連載していた某料理漫画に影響を受けているらしい。そのうち、智也くんと一緒にご飯を食べに行ったら「おかみを呼べ」と怒鳴り出さないか心配になる。
さらに、この前は湯豆腐に合う醤油を自作していた。濃口醤油に鰹節とみりん、酒を入れて煮詰めると、土佐醤油というものができるらしい。これをかけた湯豆腐は本当に美味しかった。お金が取れるくらいの味だった。
こんな風に料理に関しての彼の情熱は私の想像を軽く超えている。正直、時々どん引きするくらいだ。
どうやら智也くんは好きなものはとことん極めるタイプらしい。
智也くんが前にぽつりと言っていたが、もしラーメンにはまったら、豚骨から煮込むところから始めるらしい。ただ、美味しい出汁を取るためには、何時間も煮込まないといけないから膨大なガス代と手間がかかるそうだ。だから、はまらないようにしているとのことだった。正直、麺の材料となる小麦から自作するために畑を耕そうという無茶を言い出さなくて本当によかったと思うが、その言葉自体がフラグに思えてしかたがない。嫌な予感しかしないが、ここは智也くんの自制心を信じようと思う。
とにかく、私と智也くんは晩御飯を作り始めることにした。
「羽素さんは、まずしょうがをおろして」
「うん、わかった」
私はしょうがとおろし金を取り出すと、おろし始める。
「待って」
「え?」
しかし、乾燥わかめを水に浸していた智也くんにいきなり止められた。
「皮を剥いてからおろして。スプーンで剥けるから」
そう言って智也くんはスプーンを差し出す。
「そうなの?」
「うん。やってみて」
私は首をかしげながら、智也くんからスプーンを受け取る。スプーンで皮をむくという行為がよくわからないが、とりあえず言われた通りやってみる。スプーンでこそぐように、皮を剥く。案外、簡単に剥けた。
「できるだけ薄く剥くといいみたい」
「どうして?」
「確か皮のすぐ下にしょうがの美味しい部分があるからだったかな」
「そうなんだ」
そんな風に話しながら私たちは料理する。おかげで料理の知識はどんどん増えていった。
すぐにしょうがの皮は剥き終わった。次にさっき用意したおろし金でしょうがをおろし始める。円を描くようにおろすといいと何かで聞いたことを思い出し、丁寧に円を描く。すると、智也くんが口を開いた。
「しょうがは表面の線のような部分を垂直にしておろすといいよ」
「円を描くようにじゃないの?」
私は首をかしげる。垂直におろすやり方はよくないと何かで聞いたことがある気がした。
「大根とかだとそれでいいんだけど、しょうがは繊維を切った方が舌触りがいいから」
「へぇー」
もはや私は頷くことしかできない。こういう知識は一体どこから仕入れているんだろうと思う。
智也くんのアドバイス通りに、私は垂直にしょうがをすりおろしていった。
「こんな感じでいい?」
おろし終えたしょうがを智也くんに見せる。
「うん、いい感じ。ありがとう」
そう言ってもらえると嬉しくて、つい口元が緩む。
「次はどうしたらいい?」
堪えきれないように笑顔を浮かべながら、私は次の指示を仰いだ。
「野菜と豆腐を切ってくれる」
「はーい」
私の主な役目は材料を切ることである。切ることは片手ではできないからだ。
まな板と包丁を取り出し、大根、キュウリ、キャベツを切っていく。大根はいちょう切り、キュウリは薄切り、キャベツは千切り、豆腐は六等分にする。手伝い始めて数日経つが、まだ慣れない私は一つひとつの材料をゆっくりと切っていった。
一方、智也くんは出汁をとったり、生姜焼きのたれを作ったり、煮たり、焼いたりしている。味付けと仕上げは彼の担当だ。
私が材料を切って、智也くんが調理する。私が手伝うようになってからは、基本的にはそう役割分担していた。そんな風に一緒に何かをするのはとても楽しくて、嬉しくて、心地よい。
私は野菜を切り終えると、それぞれボウルに移した。
「野菜切れたよ」
「ありがとう。次はお肉をお願い」
「どうしたらいいの?」
「お肉に切れ目を入れて」
「切れ目?」
「うん。切れ目を入れてたれを染みこみやすくするんだ」
「そうなんだ」
私は頷くと、豚肉を手に取った。一枚、一枚まな板の上に広げる。
そういえば智也くんと一緒に料理するようになってからは、鍋が続きずっと野菜ばかり切っていたので、お肉を切るのは初めてだった。でも、お母さんを手伝っていたときにやったことがあるので簡単にできると思う。
私は豚肉を押さえて包丁で切れ目を入れようとする。肉に包丁の刃が当たると、柔らかいような、弾力のあるような感触が包丁を通じて私の手に伝わってきた。
その感触は、いつかの悪夢を想起させた。
途端に、フラッシュバックのように智也くんを刺した時の映像が脳裏に浮かぶ。
手には二度と思い出したくないあの感触が蘇ってきた。
その瞬間、胃の中から何かが戻ってくる。
慌てて包丁から手を離すと、私は口を押さえた。口内に胃液の味が広がる。酸っぱいような、生臭いような味が広がる。何度も味わった味なのに、いつまで経っても慣れない味だった。
「うぐっ」
反射的に目に涙が浮かぶ。
「羽素さん」
慌てて私はダイニングを出てトイレに駆け込んだ。
急いでトイレの便座を上げると、私は吐いた。
朝食べた朝食も、お昼に食べたお弁当も、全て吐いた。
せっかく智也くんが作ってくれた食事を全て吐いた。
胃の中が空になるまで吐いた。
何度もえづきながら私は吐いた。
なんでこんなことになってしまったのか、私はわかっていた。
自分勝手な理由で智也くんを刺した罰だ。だから、これは自業自得。
私は吐き終えると、ぼう然と吐瀉物を見つめた。汚いはずのそれは智也くんが作った料理だったというだけで、もったいなく感じる。
でも、問題はそんなことではない。
肉に切れ目を入れるという簡単な仕事すらできない。
智也くんの力になれない。そんな無力な自分に私は心底絶望した。
「羽素さん」
佐坂智也は走り去る未世に声をかけることしかできなかった。
ダイニングにはまな板に広げられた豚肉と包丁がある。
未世に何が起こったのか智也はわからなかった。ただ、肉を切ろうとしたら、いきなり口元に手を当て、走り出していた。
気持ち悪くなった?具合が悪い?
脳裏に疑問が浮かぶが確証は得ない。だから、智也は大根の味噌汁を作っていた鍋の火を止めると未世を追いかけた。
未世はトイレに入っていた。廊下にまで未世が吐く音が漏れている。あまり見られたくないだろうと思って智也は、彼女が落ち着くのを待った。
どれくらい待ったのかわからない。一分かもしれないし、十分以上待ったような気もする。それくらい智也にとっては長く感じる時間だった。
音が止むのを確認すると、智也はトイレの戸をノックした。
「羽素さん、どうしたの?」
「…………」
声は返ってこない。
「大丈夫?」
もう一度、声をかける。すると、扉が開いた。中から未世が現れる。その顔は青白い。ただでさえ、痩せていて、不健康そうな未世の顔は今にも死んでしまいそうにやつれていた。
「うん、大丈夫」
未世は引きつった笑顔を浮かべながら答えるが、とても大丈夫そうには見えなかった。
「具合が悪いのなら休んだら?」
「大丈夫。ちょっとトイレに行きたかっただけだから」
「でも、とても大丈夫そうには見えないけど」
「大丈夫だから。私に手伝わせて、お願い」
未世は今にも泣きそうな声で言った。
なぜ未世が突然トイレに駆け込んだのか智也はわからなかった。でも、未世の悲痛なまでに必死な思いを断れなかった。
「無理しないでね」
それでもせめてと思いながら、智也は優しさを振りまく。それが無意味なものと知りながら、自分にできることはこれぐらいしかないと思っていた。
「うん。大丈夫。大丈夫だから」
まるで自分に言い聞かせるような未世の言葉に、智也は「待って」と言いたくなる。しかし、思いは言葉にならない。
智也と未世はダイニングに戻った。
智也は鍋を火にかける。そして、横目で未世を見た。
未世は手をよく洗うと、まな板に広げた豚肉を手で押さえる。そして、包丁を手に取ると豚肉に切れ目を入れようと刃先をそっと押し当てた。その途端、びくっと身体を震わせ、包丁を豚肉から離す。
かぶりを振って頷くと、未世はまた包丁の刃を豚肉に押し当てる。そして、震えながら刃を離す。それを何度も繰り返していた。その身体はずっと小刻みに震えていた。
そのうち、彼女は何かをつぶやき始める。
「ご…………い。…………な……い。ご……ん……さ……。…………なさ……」
まるで呪文のように未世は何度もつぶやいていた。しかし、不明瞭な言葉ははっきりとは聞こえない。
智也は食材を取る振りをして、未世に近づく。すると、はっきりと聞こえた。
「ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい」
未世は謝っていた。それが誰に対する謝罪かわからない。ただ、彼女は謝りながら豚肉に包丁の刃を当てていた。
それは傍目に見たら、異様な状態だった。
智也は見ていられなくなって、わざとらしく大きな声を上げる。
「あっ、間違えた」
「え?」
まるで幽鬼のように虚ろな目で未世は智也を見る。
「切れ目を入れなくてよかったんだ。だから、肉は切らなくていいよ。ごめん。間違えちゃった」
「あ……」
未世は何一つ切れ目のついていない豚肉を見る。
「そのままたれに漬け込むから、お肉をここに入れてくれる?」
智也はしょうが焼きのたれを入れたボールを未世に手渡す。未世はぼんやりとしていたが、こくりと頷くとボールを受け取った。
「どうやって漬け込んだらいいの?」
「できる限り肉の表面にたれがつくように、縦と横に重ねていって」
「うん。わかった」
未世は肉を一枚一枚縦、横と交互に重ねながらたれに漬ける。そして、スプーンでボウルの下に溜まったたれを上から何度もかけた。仕事はすぐに終わる。
「次は何をしたらいい?」
「うん。ありがとう。あとは大丈夫だから休んでて」
「そっか」
寂しそうに未世はつぶやく。
「じゃあ、隣にいるから何かあったらいつでも呼んでね」
「うん。ありがとう」
未世はのろのろと隣のリビングへ向かう。その口がぽつりとつぶやく。
「ごめんなさい」
智也は未世の方へ振り向く。彼女の後ろ姿は弱々しく、今にも消えてしまうそうに儚かった。
「羽素さん」
智也は未世を呼び止める。未世は足を止めると、顔だけを智也の方に向けた。
智也は未世に何か言葉をかけたかった。でも、何を言ったらいいのかわからなかった。少し考えて口からついて出た言葉は、結局、ありきたりな言葉だった。
「ありがとう」
未世はこくりと頷くと、そのままダイニングを出て行った。
一人になった智也は調理を再開する。未世が材料を切ってくれたので、あとは片手でもできた。
そんな時だった。
リビングから堪えるような嗚咽が聞こえてきた。
智也は動かしていた手を止める。
そして、居ても経ってもられなくなって、火を止めるとリビングへ向かった。
未世はリビングのソファーに座っていた。その両手は俯いた顔を覆っている。その指と指の隙間から嗚咽が漏れていた。
「羽素さん」
智也が声を掛けると、未世ははっと気づいて、顔を手でぬぐうと智也を見た。
「どうしたの?」
未世はきょとんとした顔で尋ねる。その瞳は真っ赤に染まり、濡れていた。
智也はそんな未世を見て、腹が立っていた。彼女を守りたいと思うだけでなにもできない自分に心底腹が立っていた。くそっと心の中で悪態をつくと、智也は未世の目の前にあるソファーに腰掛けた。
「料理はいいの?」
未世は不思議そうに首をかしげる。
「今はそれよりも大事なことがあるの」
智也ははっきりと言い放った。
「大事なこと?」
「羽素さん、何があったの?」
智也の言葉に未世は首を振る。
「何もないよ」
「泣いている」
「え?あっ、これはちょっと眠たくて」
未世は目をそらして困ったような笑顔を浮かべる。
「嘘だ。さっきから変だよ」
智也は未世を真っ直ぐに見つめると、はっきり言った。
「………………………………」
未世は何も言わない。ただ黙って顔を伏せていた。
「肉を切ったときに何かあったの?」
智也が優しく尋ねる。しかし、未世は黙ったままだった。
二人の間に沈黙が流れる。
いつもと変わらないはずなのに、時間がゆっくりと流れるように感じる。ともすれば、耐えがたいような時間。しかし、智也は未世の言葉をじっと待った。いつまでも待つつもりだった。
未世は俯いたまま何も答えない。ただ、小刻みに震えていた。
どれくらい経っただろうか、未世が震える声でぽつりと答えた。
「……………………智也くんを刺した時の感触を思い出したの」
その言葉で未世がなぜ口元を押さえてトイレに駆け込んだのか、智也はようやく理解した。
「私のせいで智也くんを傷つけた。絶対に取り返しが付かないことをしてしまった。だから、私はその償いのために智也くんの力になりたかった。でも、それもできない。じゃあ、私はどうやって智也くんに償ったらいいのかな」
未世はまるで懺悔でもするかのように言葉を続ける。
智也は未世がどんな気持ちで自分の手伝いを買って出たのかを理解した。同時に、自分の考えのなさに情けなくなる。未世にそんな悲痛な思いがあったことなど思いも寄らなかった。
「罪を償えない私は生きていていいのかな。生きている価値があるのかな。それならいっそのこと――」
「――そんなこと言うな」
智也は慌てて未世の言葉を遮る。
「言わないよ。だって死にたくないもの」
未世は笑顔を浮かべた。それは悲しい悲しい笑顔だった。
「ねぇ、智也くん。私って最低なんだ。生き汚くて、何もできない。そのくせ死にたくないって周りに迷惑ばかりかける。最低な人間なんだ。だから、優しくしないで。ほっといて。料理を続けて。智也くんはできるんだから」
未世はそう言って顔を伏せた。
智也は何も言えなかった。言える言葉はたくさんある。慰める言葉、否定する言葉、前向きな言葉。でも、何を言っても薄っぺらく感じた。
だから、智也は告白することにした。胸の中にずっとしまっていた、二度と出すことはないだろうと思っていた、ある思いを。
「羽素さん。僕が君に殺されてもいいって思った時のことを覚えている?」
未世は顔を上げた。
「うん。あの時、智也くんは僕のせいだって言ってた。でも、本当はポニアードが全て悪くて」
「そう。僕はあの時、羽素さんが言ってくれた『僕は悪くない』って言葉に救われたんだ。でも、今でも僕は僕が悪いって思っている」
「どうして?」
「僕が最初にポニアードを殺しておけば羽素さんが苦しむことはなかったから。酷い目にあうこともなかった」
智也は言葉を絞り出す。心の奥底にしまっていた言葉は一度あふれ出すと止まらない。
「それに羽素さんの家族だって死ぬことはなかった。僕が殺したも同然だ」
「それは違う。全然違うよ。智也くんはお母さんを殺してない」
「わかってる。でも、ずっとずっと後悔していた。なんであの時ポニアードを殺さなかったんだって。羽素さんが苦しんだのは、家族が殺されたのは僕のせいだって」
未世が智也を刺した傷を見て悲しそうな顔をする度に、智也は言いようのない罪悪感に襲われていた。そんな顔をさせてしまった原因は自分にあることを理解していた。でも、どう言っていいのかわからなかった。もし、その気持ちを言ったとしても、未世はそうではないと言うこともわかっていた。
だから、いつも心の中にしまっていた。自分が全ての元凶であるという取り返しのつかない後悔を心の奥底にしまっていた。
「違う。智也くんのせいじゃない。悪いのはポニアードだよ」
未世はぶんぶんと首を振った。
「うん。ありがとう。羽素さんならそう言うと思っていた。でも、それなら羽素さんが僕を刺したことも悪くない。全部ポニアードにやらされていたことだ。だから、そんな風に苦しむことはない」
「あ……」
未世は声を上げる。
「でも、そんな簡単に納得できないだろ。自分は悪くないなんて思えないだろ」
未世はこくりと頷いた。
「僕もだ」
その言葉に未世は目を見開く。
「……智也くんも?」
「うん」
「でも」
未世は納得できないように首を振る。そんな未世に智也は優しく語りかけた。
「羽素さんは優しいね」
「え?」
「そんな風に背負わなくてもいい罪を背負おうとしている。だから、羽素さんは優しくて、強くて、素敵だと思う。さっき最低な人間だって言ったけど、そんなことない。絶対にそんなことない」
智也の言葉に未世は目を見開いた。震える身体はいつの間にか治まっていた。その瞳には涙が浮かぶ。さっきとは違う温かい涙だった。
「……それなら智也くんだって優しいことになるよ。同じように、背負わなくてもいい罪を背負おうとしているんだから」
未世はそう言って笑った。
「あっ」
「もしかして、気づいてなかった?」
「……うん」
智也は恥ずかしそうに頷いた。しかし、すぐに顔を上げると、真剣な表情で未世を見つめた。
「羽素さん、一つ約束してくれない?」
「何?」
「多分、これからもこんな風に苦しいときってあると思う。だから、そんな時は一人で我慢せずに話し合おう。どんな些細なことでもいいからさ」
「それは智也くんも話してくれるの?」
「もちろん」
「わかった。約束する」
「じゃあ、指切りしよう」
そう言って智也は未世に小指を差し出す。
「え?子どもっぽいよ」
「うん。でも、形にしておきたいんだ。忘れないために」
「わかった」
未世も小指を差し出す。そして、二人で指切りをした。
約束を決して破らないと誓いながら。
二度と一人で苦しまないと誓いながら。
二度と一人で苦しませないと誓いながら。
指切りを終えると、智也と未世は笑いあった。
「それじゃあ戻るね」
智也はソファーから立ち上がる。そして、ふと口を開いた。
「ねぇ」
「ねぇ」
同時に未世も口を開いていた。二人は一瞬顔を見合わせ、笑ってしまう。
「智也くん、先に言って」
「いいよ。羽素さんから言って」
お互いに譲り合う。らちが空かなかった。
「じゃあ、じゃんけんで勝った方が先に言うのはどう?」
「うん」
未世の提案に智也はこくりと頷く。そして、じゃんけんを始めた。
「最初はグー、じゃんけんっぽん」
未世はパーを、智也はグーを出した。未世の勝ちだった。
「じゃあ、私から言うね」
未世は一つ息を吐くと、口を開いた。
「私にできることがあればもう少し手伝いたいの。絶対に無理はしないから」
智也はその言葉を聞いて目を見開く。しかし、すぐに小さく笑うと、口を開いた。
「それじゃあ、しょうが焼きを焼いてくれる」
「うん。わかった」
未世は笑顔で頷くと、ソファーから立ち上がった。
「じゃあ、今度は智也くんの番だね。なんだったの?」
「もういいんだ」
「え?」
「同じ事を考えてた」
「それって」
「うん。なんだか照れくさいね」
智也は頬が熱くなるのを感じながら、ごまかすように笑った。未世も一緒に笑い出す。
その頬は赤く染まっていた。
そして、智也と未世はダイニングへ戻っていく。
二人で料理をするために。
『羽素未世と佐坂智也のお料理日和』(了)
学校からの帰りに、私と智也くんはスーパーに寄ってから帰宅した。
私の手には夕食の材料が入った買い物袋がある。まだ、ギプスをつけている智也くんに持たせるわけにはいかない。スーパーで一悶着あったが、私が持つことで智也くんも納得してくれた。
「ただいま」
そう言って私と智也くんは家に入る。十和さんの家に帰ってくるのは、まだ慣れなくてなんだか不思議な気分だ。
私たちは買い物袋をキッチンのあるダイニングテーブルに置くと、二階に上がっていく。
「それじゃあ、一息ついたら始めよっか」
「うん」
そんな会話をして、私たちはそれぞれのネームプレートが付いた部屋に入っていった。私の部屋と智也くんの部屋は隣同士だ。二階にはまだたくさん空き部屋があった。
私の部屋には、もともとあったベッドと机と鏡付きのクローゼットがあるだけだ。まだ暮らし始めて一週間ほどしか経っていないので、殺風景なのは仕方ない。最も、私自身の私物はきわめて少なかった。ホテルから運んできた僅かな私物は服と教科書などの学習用品と化粧道具だけ。生活するのに必要最低限なものしかない。
ホテルに暮らしていた時は気にならなかったが、今思うと高校生とは思えないくらい少ない。
ため息をつきながら、私は制服から部屋着に着替える。白いセーターに、薄茶色のコットンパンツとラフな格好だ。
着替え終えると、私はベッドに仰向けに倒れ込む。
クッションからくる反動が心地よい。疲れた身体を癒やすように、私は全体重をベッドに預ける。
なんだかひどく疲れていた。原因はわかっている。でも、それは私が望んでやっていることだから、言い訳にはできない。だから、私が今すべきことは、この後のためにできる限り休むことだった。
部屋にはカチカチと時計の音が響いていた。規則的な時計の針の音は眠気を誘う。
今日あったことを思い返しながら、うとうとと意識がまどろみに沈んでいく。
時間の流れがゆっくり感じる。
嫌な感じはしない。
とても穏やかな時間だった。
こんな風に生活できるとは、あの頃は思わなかった。
そんな時だった。
部屋がコンコンとノックされる。
「はーい」
私が返事すると、扉が開いて智也くんが現れる。グレーのフリースに、黒のスウェットと彼もラフな部屋着になっていた。
「そろそろ始めるけど……あっ、ごめん。寝てた?」
智也くんは慌てて、扉を閉めようとする。
「うんん。ちょっと休んでいただけ。大丈夫」
「そう。病み上がりなんだから無理しないでね」
「うん。ありがとう」
そんな風に言う智也くんはまだ左腕にギプスをしている。どうやら全治三週間ぐらいかかるらしい。だから、私はまず彼の左腕になることにした。それが彼を傷つけた私の償いだった。多分、智也くんは気にしないでというだろう。でも、自分で納得はできない。だから、半ば強引に私は私の罪を償っていた。
私はいつかした小さな誓いの通り、智也くんのためにできることならなんでもするつもりだった。重たい荷物を持ったり、彼が何かをするとき手伝ったり、学校でも家でも彼の姿をずっと追っていた。そのせいでひどく疲れたのは彼には内緒だ。
「じゃあ、始めよっか」
私はそう言ってベッドなら立ち上がる。そして、智也くんと部屋からでて、ダイニングに向かった。
私たちはこれから晩御飯を作ろうとしていた。
十和さんの方針で、この家ではただで住める代わりに家事をすることになっていた。そのため、智也くんはこの家の料理を全てまかなっていた。ちなみに、私は洗濯担当である。男物のパンツだろうが、何だろうが気にせずまとめて洗って干している。
料理をするには両手が必要になってくる。でも、今、智也くんは左腕が使えない。だから、私も手伝っていた。
智也くんと料理をしていると、昔、お母さんの手伝いをしたことを思い出す。
懐かしい思い出。同時に、二度と戻らない日々は、私の心の琴線に触れる。心が泣きたくなる前に、私は思い出に蓋をした。
「今日は何を作るの?」
緑色のエプロンを着けながら、私は今日の晩御飯を尋ねた。
「最近、鍋が続いているから別の物にしようと思うんだ」
智也くんはエプロンをつけながら、答えた。ちなみに、エプロンはシンプルな青一色である。
「別の物?」
私が疑問の声をあげると、智也くんは買い物袋の中から、豚のロース肉を取り出した。
「これを使います」
「とんかつ?」
智也くんは一瞬押し黙る。そして、ロース肉を見ると、私に尋ねた。
「……もしかして、とんかつが食べたかった?」
「えっ?いや、そうじゃないけど」
どうやら違うらしい。でも、他には思い浮かばなかった。
「豚のしょうが焼きなんかどうかなと思って」
「ああー」
それ以外のリアクションが浮かばない。微妙というわけではない。でも、可でもなく、不可でもなく。なんというか地味だった。
そんなリアクションを見て、智也くんはもう一度豚肉を見る。そして、豚肉をダイニングテーブルの上に置くと、
「パン粉と油買ってくる」
と言ってエプロンをはずし始めた。
「いや、いいから」
私は慌てて智也くんを止める。
「えっ、でも」
「とんかつとしょうが焼きなら、しょうが焼きの方が好きだから」
嘘だった。本当はどっちでもいい。でも、智也くんを止めるために背に腹は代えられない。人間の言葉というものは時々、本当にいい加減で、適当だ。
「本当に?」
智也くんは疑いの目で見てくる。めんどくさい。仕方なく私は、智也くんに納得してもらうため、わざとらしく明るい声を上げた。
「本当!本当だから。しょうが焼きだーい好き」
自分で言ってて悲しくなる。
あれ?私こんなキャラだっけ?
「そっか」
智也くんはなんとか納得してくれる。今のどこに納得できるポイントがあるのかわからないが、私はほっとする。同時に脳裏には一つの疑問が浮かんでいた。
本当は智也くんってアホなんじゃないだろうか?
その答えは考えないことにする。
「じゃあ、しょうが焼きと、大根のみそ汁、それから湯豆腐とキュウリとワカメの酢の物を作ろう」
さらっと湯豆腐を入れてくるところが智也くんらしい。鍋にも入れるし、朝の味噌汁にも入れるし、気がつくと豆腐が出てくる。よくよく考えたら毎日豆腐を食べていた。そのうち、お弁当にも豆腐が出てきそうで、若干恐ろしくなる。水気のある豆腐をどうやってお弁当に詰めるのかは想像がつかないが、智也くんならやりかねないと思った。さすがにそんなことはないと思いたいけど、ありえそうなのが智也くんだ。
そういえば、一昨日は朝食から湯豆腐を出すという高級料亭みたいなことをしていた。
智也くん曰く、朝から湯豆腐を食べると気持ちが豊かになるらしいが、私にはよくわからない。後で十和さんに聞いたのだが、この考えは長期連載していた某料理漫画に影響を受けているらしい。そのうち、智也くんと一緒にご飯を食べに行ったら「おかみを呼べ」と怒鳴り出さないか心配になる。
さらに、この前は湯豆腐に合う醤油を自作していた。濃口醤油に鰹節とみりん、酒を入れて煮詰めると、土佐醤油というものができるらしい。これをかけた湯豆腐は本当に美味しかった。お金が取れるくらいの味だった。
こんな風に料理に関しての彼の情熱は私の想像を軽く超えている。正直、時々どん引きするくらいだ。
どうやら智也くんは好きなものはとことん極めるタイプらしい。
智也くんが前にぽつりと言っていたが、もしラーメンにはまったら、豚骨から煮込むところから始めるらしい。ただ、美味しい出汁を取るためには、何時間も煮込まないといけないから膨大なガス代と手間がかかるそうだ。だから、はまらないようにしているとのことだった。正直、麺の材料となる小麦から自作するために畑を耕そうという無茶を言い出さなくて本当によかったと思うが、その言葉自体がフラグに思えてしかたがない。嫌な予感しかしないが、ここは智也くんの自制心を信じようと思う。
とにかく、私と智也くんは晩御飯を作り始めることにした。
「羽素さんは、まずしょうがをおろして」
「うん、わかった」
私はしょうがとおろし金を取り出すと、おろし始める。
「待って」
「え?」
しかし、乾燥わかめを水に浸していた智也くんにいきなり止められた。
「皮を剥いてからおろして。スプーンで剥けるから」
そう言って智也くんはスプーンを差し出す。
「そうなの?」
「うん。やってみて」
私は首をかしげながら、智也くんからスプーンを受け取る。スプーンで皮をむくという行為がよくわからないが、とりあえず言われた通りやってみる。スプーンでこそぐように、皮を剥く。案外、簡単に剥けた。
「できるだけ薄く剥くといいみたい」
「どうして?」
「確か皮のすぐ下にしょうがの美味しい部分があるからだったかな」
「そうなんだ」
そんな風に話しながら私たちは料理する。おかげで料理の知識はどんどん増えていった。
すぐにしょうがの皮は剥き終わった。次にさっき用意したおろし金でしょうがをおろし始める。円を描くようにおろすといいと何かで聞いたことを思い出し、丁寧に円を描く。すると、智也くんが口を開いた。
「しょうがは表面の線のような部分を垂直にしておろすといいよ」
「円を描くようにじゃないの?」
私は首をかしげる。垂直におろすやり方はよくないと何かで聞いたことがある気がした。
「大根とかだとそれでいいんだけど、しょうがは繊維を切った方が舌触りがいいから」
「へぇー」
もはや私は頷くことしかできない。こういう知識は一体どこから仕入れているんだろうと思う。
智也くんのアドバイス通りに、私は垂直にしょうがをすりおろしていった。
「こんな感じでいい?」
おろし終えたしょうがを智也くんに見せる。
「うん、いい感じ。ありがとう」
そう言ってもらえると嬉しくて、つい口元が緩む。
「次はどうしたらいい?」
堪えきれないように笑顔を浮かべながら、私は次の指示を仰いだ。
「野菜と豆腐を切ってくれる」
「はーい」
私の主な役目は材料を切ることである。切ることは片手ではできないからだ。
まな板と包丁を取り出し、大根、キュウリ、キャベツを切っていく。大根はいちょう切り、キュウリは薄切り、キャベツは千切り、豆腐は六等分にする。手伝い始めて数日経つが、まだ慣れない私は一つひとつの材料をゆっくりと切っていった。
一方、智也くんは出汁をとったり、生姜焼きのたれを作ったり、煮たり、焼いたりしている。味付けと仕上げは彼の担当だ。
私が材料を切って、智也くんが調理する。私が手伝うようになってからは、基本的にはそう役割分担していた。そんな風に一緒に何かをするのはとても楽しくて、嬉しくて、心地よい。
私は野菜を切り終えると、それぞれボウルに移した。
「野菜切れたよ」
「ありがとう。次はお肉をお願い」
「どうしたらいいの?」
「お肉に切れ目を入れて」
「切れ目?」
「うん。切れ目を入れてたれを染みこみやすくするんだ」
「そうなんだ」
私は頷くと、豚肉を手に取った。一枚、一枚まな板の上に広げる。
そういえば智也くんと一緒に料理するようになってからは、鍋が続きずっと野菜ばかり切っていたので、お肉を切るのは初めてだった。でも、お母さんを手伝っていたときにやったことがあるので簡単にできると思う。
私は豚肉を押さえて包丁で切れ目を入れようとする。肉に包丁の刃が当たると、柔らかいような、弾力のあるような感触が包丁を通じて私の手に伝わってきた。
その感触は、いつかの悪夢を想起させた。
途端に、フラッシュバックのように智也くんを刺した時の映像が脳裏に浮かぶ。
手には二度と思い出したくないあの感触が蘇ってきた。
その瞬間、胃の中から何かが戻ってくる。
慌てて包丁から手を離すと、私は口を押さえた。口内に胃液の味が広がる。酸っぱいような、生臭いような味が広がる。何度も味わった味なのに、いつまで経っても慣れない味だった。
「うぐっ」
反射的に目に涙が浮かぶ。
「羽素さん」
慌てて私はダイニングを出てトイレに駆け込んだ。
急いでトイレの便座を上げると、私は吐いた。
朝食べた朝食も、お昼に食べたお弁当も、全て吐いた。
せっかく智也くんが作ってくれた食事を全て吐いた。
胃の中が空になるまで吐いた。
何度もえづきながら私は吐いた。
なんでこんなことになってしまったのか、私はわかっていた。
自分勝手な理由で智也くんを刺した罰だ。だから、これは自業自得。
私は吐き終えると、ぼう然と吐瀉物を見つめた。汚いはずのそれは智也くんが作った料理だったというだけで、もったいなく感じる。
でも、問題はそんなことではない。
肉に切れ目を入れるという簡単な仕事すらできない。
智也くんの力になれない。そんな無力な自分に私は心底絶望した。
「羽素さん」
佐坂智也は走り去る未世に声をかけることしかできなかった。
ダイニングにはまな板に広げられた豚肉と包丁がある。
未世に何が起こったのか智也はわからなかった。ただ、肉を切ろうとしたら、いきなり口元に手を当て、走り出していた。
気持ち悪くなった?具合が悪い?
脳裏に疑問が浮かぶが確証は得ない。だから、智也は大根の味噌汁を作っていた鍋の火を止めると未世を追いかけた。
未世はトイレに入っていた。廊下にまで未世が吐く音が漏れている。あまり見られたくないだろうと思って智也は、彼女が落ち着くのを待った。
どれくらい待ったのかわからない。一分かもしれないし、十分以上待ったような気もする。それくらい智也にとっては長く感じる時間だった。
音が止むのを確認すると、智也はトイレの戸をノックした。
「羽素さん、どうしたの?」
「…………」
声は返ってこない。
「大丈夫?」
もう一度、声をかける。すると、扉が開いた。中から未世が現れる。その顔は青白い。ただでさえ、痩せていて、不健康そうな未世の顔は今にも死んでしまいそうにやつれていた。
「うん、大丈夫」
未世は引きつった笑顔を浮かべながら答えるが、とても大丈夫そうには見えなかった。
「具合が悪いのなら休んだら?」
「大丈夫。ちょっとトイレに行きたかっただけだから」
「でも、とても大丈夫そうには見えないけど」
「大丈夫だから。私に手伝わせて、お願い」
未世は今にも泣きそうな声で言った。
なぜ未世が突然トイレに駆け込んだのか智也はわからなかった。でも、未世の悲痛なまでに必死な思いを断れなかった。
「無理しないでね」
それでもせめてと思いながら、智也は優しさを振りまく。それが無意味なものと知りながら、自分にできることはこれぐらいしかないと思っていた。
「うん。大丈夫。大丈夫だから」
まるで自分に言い聞かせるような未世の言葉に、智也は「待って」と言いたくなる。しかし、思いは言葉にならない。
智也と未世はダイニングに戻った。
智也は鍋を火にかける。そして、横目で未世を見た。
未世は手をよく洗うと、まな板に広げた豚肉を手で押さえる。そして、包丁を手に取ると豚肉に切れ目を入れようと刃先をそっと押し当てた。その途端、びくっと身体を震わせ、包丁を豚肉から離す。
かぶりを振って頷くと、未世はまた包丁の刃を豚肉に押し当てる。そして、震えながら刃を離す。それを何度も繰り返していた。その身体はずっと小刻みに震えていた。
そのうち、彼女は何かをつぶやき始める。
「ご…………い。…………な……い。ご……ん……さ……。…………なさ……」
まるで呪文のように未世は何度もつぶやいていた。しかし、不明瞭な言葉ははっきりとは聞こえない。
智也は食材を取る振りをして、未世に近づく。すると、はっきりと聞こえた。
「ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい」
未世は謝っていた。それが誰に対する謝罪かわからない。ただ、彼女は謝りながら豚肉に包丁の刃を当てていた。
それは傍目に見たら、異様な状態だった。
智也は見ていられなくなって、わざとらしく大きな声を上げる。
「あっ、間違えた」
「え?」
まるで幽鬼のように虚ろな目で未世は智也を見る。
「切れ目を入れなくてよかったんだ。だから、肉は切らなくていいよ。ごめん。間違えちゃった」
「あ……」
未世は何一つ切れ目のついていない豚肉を見る。
「そのままたれに漬け込むから、お肉をここに入れてくれる?」
智也はしょうが焼きのたれを入れたボールを未世に手渡す。未世はぼんやりとしていたが、こくりと頷くとボールを受け取った。
「どうやって漬け込んだらいいの?」
「できる限り肉の表面にたれがつくように、縦と横に重ねていって」
「うん。わかった」
未世は肉を一枚一枚縦、横と交互に重ねながらたれに漬ける。そして、スプーンでボウルの下に溜まったたれを上から何度もかけた。仕事はすぐに終わる。
「次は何をしたらいい?」
「うん。ありがとう。あとは大丈夫だから休んでて」
「そっか」
寂しそうに未世はつぶやく。
「じゃあ、隣にいるから何かあったらいつでも呼んでね」
「うん。ありがとう」
未世はのろのろと隣のリビングへ向かう。その口がぽつりとつぶやく。
「ごめんなさい」
智也は未世の方へ振り向く。彼女の後ろ姿は弱々しく、今にも消えてしまうそうに儚かった。
「羽素さん」
智也は未世を呼び止める。未世は足を止めると、顔だけを智也の方に向けた。
智也は未世に何か言葉をかけたかった。でも、何を言ったらいいのかわからなかった。少し考えて口からついて出た言葉は、結局、ありきたりな言葉だった。
「ありがとう」
未世はこくりと頷くと、そのままダイニングを出て行った。
一人になった智也は調理を再開する。未世が材料を切ってくれたので、あとは片手でもできた。
そんな時だった。
リビングから堪えるような嗚咽が聞こえてきた。
智也は動かしていた手を止める。
そして、居ても経ってもられなくなって、火を止めるとリビングへ向かった。
未世はリビングのソファーに座っていた。その両手は俯いた顔を覆っている。その指と指の隙間から嗚咽が漏れていた。
「羽素さん」
智也が声を掛けると、未世ははっと気づいて、顔を手でぬぐうと智也を見た。
「どうしたの?」
未世はきょとんとした顔で尋ねる。その瞳は真っ赤に染まり、濡れていた。
智也はそんな未世を見て、腹が立っていた。彼女を守りたいと思うだけでなにもできない自分に心底腹が立っていた。くそっと心の中で悪態をつくと、智也は未世の目の前にあるソファーに腰掛けた。
「料理はいいの?」
未世は不思議そうに首をかしげる。
「今はそれよりも大事なことがあるの」
智也ははっきりと言い放った。
「大事なこと?」
「羽素さん、何があったの?」
智也の言葉に未世は首を振る。
「何もないよ」
「泣いている」
「え?あっ、これはちょっと眠たくて」
未世は目をそらして困ったような笑顔を浮かべる。
「嘘だ。さっきから変だよ」
智也は未世を真っ直ぐに見つめると、はっきり言った。
「………………………………」
未世は何も言わない。ただ黙って顔を伏せていた。
「肉を切ったときに何かあったの?」
智也が優しく尋ねる。しかし、未世は黙ったままだった。
二人の間に沈黙が流れる。
いつもと変わらないはずなのに、時間がゆっくりと流れるように感じる。ともすれば、耐えがたいような時間。しかし、智也は未世の言葉をじっと待った。いつまでも待つつもりだった。
未世は俯いたまま何も答えない。ただ、小刻みに震えていた。
どれくらい経っただろうか、未世が震える声でぽつりと答えた。
「……………………智也くんを刺した時の感触を思い出したの」
その言葉で未世がなぜ口元を押さえてトイレに駆け込んだのか、智也はようやく理解した。
「私のせいで智也くんを傷つけた。絶対に取り返しが付かないことをしてしまった。だから、私はその償いのために智也くんの力になりたかった。でも、それもできない。じゃあ、私はどうやって智也くんに償ったらいいのかな」
未世はまるで懺悔でもするかのように言葉を続ける。
智也は未世がどんな気持ちで自分の手伝いを買って出たのかを理解した。同時に、自分の考えのなさに情けなくなる。未世にそんな悲痛な思いがあったことなど思いも寄らなかった。
「罪を償えない私は生きていていいのかな。生きている価値があるのかな。それならいっそのこと――」
「――そんなこと言うな」
智也は慌てて未世の言葉を遮る。
「言わないよ。だって死にたくないもの」
未世は笑顔を浮かべた。それは悲しい悲しい笑顔だった。
「ねぇ、智也くん。私って最低なんだ。生き汚くて、何もできない。そのくせ死にたくないって周りに迷惑ばかりかける。最低な人間なんだ。だから、優しくしないで。ほっといて。料理を続けて。智也くんはできるんだから」
未世はそう言って顔を伏せた。
智也は何も言えなかった。言える言葉はたくさんある。慰める言葉、否定する言葉、前向きな言葉。でも、何を言っても薄っぺらく感じた。
だから、智也は告白することにした。胸の中にずっとしまっていた、二度と出すことはないだろうと思っていた、ある思いを。
「羽素さん。僕が君に殺されてもいいって思った時のことを覚えている?」
未世は顔を上げた。
「うん。あの時、智也くんは僕のせいだって言ってた。でも、本当はポニアードが全て悪くて」
「そう。僕はあの時、羽素さんが言ってくれた『僕は悪くない』って言葉に救われたんだ。でも、今でも僕は僕が悪いって思っている」
「どうして?」
「僕が最初にポニアードを殺しておけば羽素さんが苦しむことはなかったから。酷い目にあうこともなかった」
智也は言葉を絞り出す。心の奥底にしまっていた言葉は一度あふれ出すと止まらない。
「それに羽素さんの家族だって死ぬことはなかった。僕が殺したも同然だ」
「それは違う。全然違うよ。智也くんはお母さんを殺してない」
「わかってる。でも、ずっとずっと後悔していた。なんであの時ポニアードを殺さなかったんだって。羽素さんが苦しんだのは、家族が殺されたのは僕のせいだって」
未世が智也を刺した傷を見て悲しそうな顔をする度に、智也は言いようのない罪悪感に襲われていた。そんな顔をさせてしまった原因は自分にあることを理解していた。でも、どう言っていいのかわからなかった。もし、その気持ちを言ったとしても、未世はそうではないと言うこともわかっていた。
だから、いつも心の中にしまっていた。自分が全ての元凶であるという取り返しのつかない後悔を心の奥底にしまっていた。
「違う。智也くんのせいじゃない。悪いのはポニアードだよ」
未世はぶんぶんと首を振った。
「うん。ありがとう。羽素さんならそう言うと思っていた。でも、それなら羽素さんが僕を刺したことも悪くない。全部ポニアードにやらされていたことだ。だから、そんな風に苦しむことはない」
「あ……」
未世は声を上げる。
「でも、そんな簡単に納得できないだろ。自分は悪くないなんて思えないだろ」
未世はこくりと頷いた。
「僕もだ」
その言葉に未世は目を見開く。
「……智也くんも?」
「うん」
「でも」
未世は納得できないように首を振る。そんな未世に智也は優しく語りかけた。
「羽素さんは優しいね」
「え?」
「そんな風に背負わなくてもいい罪を背負おうとしている。だから、羽素さんは優しくて、強くて、素敵だと思う。さっき最低な人間だって言ったけど、そんなことない。絶対にそんなことない」
智也の言葉に未世は目を見開いた。震える身体はいつの間にか治まっていた。その瞳には涙が浮かぶ。さっきとは違う温かい涙だった。
「……それなら智也くんだって優しいことになるよ。同じように、背負わなくてもいい罪を背負おうとしているんだから」
未世はそう言って笑った。
「あっ」
「もしかして、気づいてなかった?」
「……うん」
智也は恥ずかしそうに頷いた。しかし、すぐに顔を上げると、真剣な表情で未世を見つめた。
「羽素さん、一つ約束してくれない?」
「何?」
「多分、これからもこんな風に苦しいときってあると思う。だから、そんな時は一人で我慢せずに話し合おう。どんな些細なことでもいいからさ」
「それは智也くんも話してくれるの?」
「もちろん」
「わかった。約束する」
「じゃあ、指切りしよう」
そう言って智也は未世に小指を差し出す。
「え?子どもっぽいよ」
「うん。でも、形にしておきたいんだ。忘れないために」
「わかった」
未世も小指を差し出す。そして、二人で指切りをした。
約束を決して破らないと誓いながら。
二度と一人で苦しまないと誓いながら。
二度と一人で苦しませないと誓いながら。
指切りを終えると、智也と未世は笑いあった。
「それじゃあ戻るね」
智也はソファーから立ち上がる。そして、ふと口を開いた。
「ねぇ」
「ねぇ」
同時に未世も口を開いていた。二人は一瞬顔を見合わせ、笑ってしまう。
「智也くん、先に言って」
「いいよ。羽素さんから言って」
お互いに譲り合う。らちが空かなかった。
「じゃあ、じゃんけんで勝った方が先に言うのはどう?」
「うん」
未世の提案に智也はこくりと頷く。そして、じゃんけんを始めた。
「最初はグー、じゃんけんっぽん」
未世はパーを、智也はグーを出した。未世の勝ちだった。
「じゃあ、私から言うね」
未世は一つ息を吐くと、口を開いた。
「私にできることがあればもう少し手伝いたいの。絶対に無理はしないから」
智也はその言葉を聞いて目を見開く。しかし、すぐに小さく笑うと、口を開いた。
「それじゃあ、しょうが焼きを焼いてくれる」
「うん。わかった」
未世は笑顔で頷くと、ソファーから立ち上がった。
「じゃあ、今度は智也くんの番だね。なんだったの?」
「もういいんだ」
「え?」
「同じ事を考えてた」
「それって」
「うん。なんだか照れくさいね」
智也は頬が熱くなるのを感じながら、ごまかすように笑った。未世も一緒に笑い出す。
その頬は赤く染まっていた。
そして、智也と未世はダイニングへ戻っていく。
二人で料理をするために。
『羽素未世と佐坂智也のお料理日和』(了)
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

職業、種付けおじさん
gulu
キャラ文芸
遺伝子治療や改造が当たり前になった世界。
誰もが整った外見となり、病気に少しだけ強く体も丈夫になった。
だがそんな世界の裏側には、遺伝子改造によって誕生した怪物が存在していた。
人権もなく、悪人を法の外から裁く種付けおじさんである。
明日の命すら保障されない彼らは、それでもこの世界で懸命に生きている。
※小説家になろう、カクヨムでも連載中
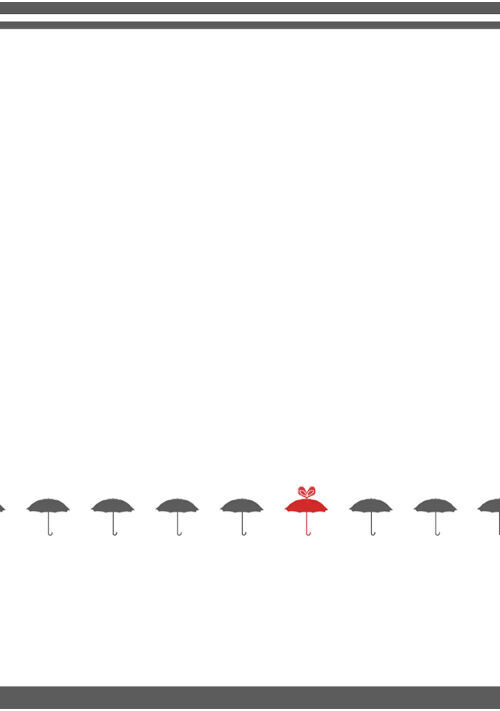
こちら夢守市役所あやかしよろず相談課
木原あざみ
キャラ文芸
異動先はまさかのあやかしよろず相談課!? 変人ばかりの職場で始まるほっこりお役所コメディ
✳︎✳︎
三崎はな。夢守市役所に入庁して三年目。はじめての異動先は「旧館のもじゃおさん」と呼ばれる変人が在籍しているよろず相談課。一度配属されたら最後、二度と異動はないと噂されている夢守市役所の墓場でした。 けれど、このよろず相談課、本当の名称は●●よろず相談課で――。それっていったいどういうこと? みたいな話です。
第7回キャラ文芸大賞奨励賞ありがとうございました。


これもなにかの縁ですし 〜あやかし縁結びカフェとほっこり焼き物めぐり
枢 呂紅
キャラ文芸
★第5回キャラ文芸大賞にて奨励賞をいただきました!応援いただきありがとうございます★
大学一年生の春。夢の一人暮らしを始めた鈴だが、毎日謎の不幸が続いていた。
悪運を祓うべく通称:縁結び神社にお参りした鈴は、そこで不思議なイケメンに衝撃の一言を放たれてしまう。
「だって君。悪い縁(えにし)に取り憑かれているもの」
彼に連れて行かれたのは、妖怪だけが集うノスタルジックなカフェ、縁結びカフェ。
そこで鈴は、妖狐と陰陽師を先祖に持つという不思議なイケメン店長・狐月により、自分と縁を結んだ『貧乏神』と対峙するけども……?
人とあやかしの世が別れた時代に、ひとと妖怪、そして店主の趣味のほっこり焼き物が交錯する。
これは、偶然に出会い結ばれたひととあやかしを繋ぐ、優しくあたたかな『縁結び』の物語。

お好み焼き屋さんのおとなりさん
菱沼あゆ
キャラ文芸
熱々な鉄板の上で、ジュウジュウなお好み焼きには、キンキンのビールでしょうっ!
ニートな砂月はお好み焼き屋に通い詰め、癒されていたが。
ある日、驚くようなイケメンと相席に。
それから、毎度、相席になる彼に、ちょっぴり運命を感じるが――。
「それ、運命でもなんでもなかったですね……」
近所のお医者さん、高秀とニートな砂月の運命(?)の恋。


猫の喫茶店『ねこみや』
壬黎ハルキ
キャラ文芸
とあるアラサーのキャリアウーマンは、毎日の仕事で疲れ果てていた。
珍しく早く帰れたその日、ある住宅街の喫茶店を発見。
そこは、彼女と同い年くらいの青年が一人で仕切っていた。そしてそこには看板猫が存在していた。
猫の可愛さと青年の心優しさに癒される彼女は、店の常連になるつもりでいた。
やがて彼女は、一匹の白い子猫を保護する。
その子猫との出会いが、彼女の人生を大きく変えていくことになるのだった。
※4話と5話は12/30に更新します。
※6話以降は連日1話ずつ(毎朝8:00)更新していきます。
※第4回キャラ文芸大賞にエントリーしました。よろしくお願いします<(_ _)>

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















