12 / 22
第十二話 十三夜(二)
しおりを挟む
既に悲報を受けた米沢の城の中は騒然としていた。
政宗は、青ざめた面を殊更に硬く、ぐ---と口許を結び、父の遺体を丁寧に清めさせ、葬儀の手配を整え、自室に戻った。
息が、止まりそうだった。胸が千切れるかと思うほど締め付けられ、脇息に置いた手は、わなわなと震えが止まらなかった。
---と、するすると衣擦れの音が近付いてきた。
政宗は、一層、身体を強張らせた。
「入りますよ。」
大御台さま、今は---と制止する小十郎を意にも止めず、その背が政宗の居室に滑り込んだ。
「葬儀の手配は済みましたか?」
義姫は、政宗の前に座ると、落ちついた声音で、言った。さすがに顔は血の気を失い、唇もひどく青ざめていたが、その声音に乱れは無かった。
政宗は、あまりに意外な言葉に、ピクリ---と身を震わせた。
「は---既に整えました。」
と答えると、義姫は、そう---とひとこと言って立ち上がった。
「なれば---あとは、成すべきことは、わかってますね。」
政宗は、無言で頷いた。
「武運を---祈っていますよ。」
義姫は、それだけ言って、政宗の居室を出た。
そして---平伏する小十郎に、―政宗を頼みます---―と言い置いて、立ち去った。
小十郎は改めて、その後ろ姿に平伏した。
―強い---お人だ。―
息子が夫を殺した。
だが、それより他に手立てが無かったことを、しっかりと正面から受け止めている。
―先へ進まねばならぬ。―
その事を、少ない言葉で政宗に見事に伝えた。
―しかし、政宗さまのお心は---―
と、その背に問おうとして、小十郎は、はっ---と気付いた。
―頼みます---―
という義姫の言葉が、胸に刺さった。
やや暫しして、小十郎は、静かに主の居室の戸を開けた。
政宗は、脇息を握りしめたまま、俯いて、ただただ唇を噛みしめていた。
小十郎は、一歩二歩、政宗ににじり寄った。
―小十郎---―
政宗は、ほんの僅かに顔を上げた。白蝋のように血の気を喪った面---虚ろな瞳---間近に寄ると、小刻みに、かすかに身体が震えているのがわかる。
―政宗さま---梵天丸さま---―
小十郎が、躊躇いがちに、かすかにその肩に触れると、政宗の身体の震えがひと際大きくなった。
―おひとりで苦しまれますな---。申し上げたはずです。
お悲しいことあらば、この小十郎に、梵天丸さまの悲しみをお預けください---と。―
政宗の眼が、小十郎の顔を見上げ、差し伸べられたもう一方の手を見た。
そして---倒れるように小十郎の胸元に手を掛け、襟元を鷲掴みにした。
―こ---じゅう---ろう---―
魂の奥底から搾り出すような、今にも息絶えそうな---唸りとも呻きともつかぬ声だった。
遮二無に、小十郎の襟元を縋るように掻き掴み、頭を強く押し付け、肩を大きく震わせていた。
幾度も幾度も、唸り、呻き---泣けぬ苦しさを搾り出し---だが、その頬を幾度も、滴が伝って落ちたことを、小十郎は見ぬふりをした。
そ---と、触れるか触れないかほどの優しさで、その背に両手を回し、政宗を懊惱ごと包み込むように抱えた。
「済まな---かった---」
政宗がやっと顔を上げたのは、陽が傾きかけた頃だった。小十郎は、いいえ---と小さく応えた。やっと幾ばくか生気を取り戻した面に、安堵して、さりげなく両手を膝に戻した。
政宗は、小十郎の襟元から手を離し、背中越しに顔を擦って身を翻し、元の座に戻った。
―夕餉は、いかがいたしますか?―
と、小十郎が問うと、半ば驚いたように、―そんな刻限か---―と呟き、
―飯はいらん。酒を持ってきてくれ。―
と吐息とともに漏らした。
―いけませぬ。朝から何も口にされてはないではありませんか---―
仕方のない---と諌めるも、哀しげに口許を歪め、
―食いたくない---。―
と呻く政宗に、それ以上の箴言も憚られて、受けるしかなかった。
―では、何か某が肴を見繕ってお持ちしましょう―
小十郎は、そう言って政宗の居室を下がり、厨に向かった。
―月が、赤いのぅ---―
飯炊きの老爺のもそりとした戯言が、やけに耳に残った。
政宗は、青ざめた面を殊更に硬く、ぐ---と口許を結び、父の遺体を丁寧に清めさせ、葬儀の手配を整え、自室に戻った。
息が、止まりそうだった。胸が千切れるかと思うほど締め付けられ、脇息に置いた手は、わなわなと震えが止まらなかった。
---と、するすると衣擦れの音が近付いてきた。
政宗は、一層、身体を強張らせた。
「入りますよ。」
大御台さま、今は---と制止する小十郎を意にも止めず、その背が政宗の居室に滑り込んだ。
「葬儀の手配は済みましたか?」
義姫は、政宗の前に座ると、落ちついた声音で、言った。さすがに顔は血の気を失い、唇もひどく青ざめていたが、その声音に乱れは無かった。
政宗は、あまりに意外な言葉に、ピクリ---と身を震わせた。
「は---既に整えました。」
と答えると、義姫は、そう---とひとこと言って立ち上がった。
「なれば---あとは、成すべきことは、わかってますね。」
政宗は、無言で頷いた。
「武運を---祈っていますよ。」
義姫は、それだけ言って、政宗の居室を出た。
そして---平伏する小十郎に、―政宗を頼みます---―と言い置いて、立ち去った。
小十郎は改めて、その後ろ姿に平伏した。
―強い---お人だ。―
息子が夫を殺した。
だが、それより他に手立てが無かったことを、しっかりと正面から受け止めている。
―先へ進まねばならぬ。―
その事を、少ない言葉で政宗に見事に伝えた。
―しかし、政宗さまのお心は---―
と、その背に問おうとして、小十郎は、はっ---と気付いた。
―頼みます---―
という義姫の言葉が、胸に刺さった。
やや暫しして、小十郎は、静かに主の居室の戸を開けた。
政宗は、脇息を握りしめたまま、俯いて、ただただ唇を噛みしめていた。
小十郎は、一歩二歩、政宗ににじり寄った。
―小十郎---―
政宗は、ほんの僅かに顔を上げた。白蝋のように血の気を喪った面---虚ろな瞳---間近に寄ると、小刻みに、かすかに身体が震えているのがわかる。
―政宗さま---梵天丸さま---―
小十郎が、躊躇いがちに、かすかにその肩に触れると、政宗の身体の震えがひと際大きくなった。
―おひとりで苦しまれますな---。申し上げたはずです。
お悲しいことあらば、この小十郎に、梵天丸さまの悲しみをお預けください---と。―
政宗の眼が、小十郎の顔を見上げ、差し伸べられたもう一方の手を見た。
そして---倒れるように小十郎の胸元に手を掛け、襟元を鷲掴みにした。
―こ---じゅう---ろう---―
魂の奥底から搾り出すような、今にも息絶えそうな---唸りとも呻きともつかぬ声だった。
遮二無に、小十郎の襟元を縋るように掻き掴み、頭を強く押し付け、肩を大きく震わせていた。
幾度も幾度も、唸り、呻き---泣けぬ苦しさを搾り出し---だが、その頬を幾度も、滴が伝って落ちたことを、小十郎は見ぬふりをした。
そ---と、触れるか触れないかほどの優しさで、その背に両手を回し、政宗を懊惱ごと包み込むように抱えた。
「済まな---かった---」
政宗がやっと顔を上げたのは、陽が傾きかけた頃だった。小十郎は、いいえ---と小さく応えた。やっと幾ばくか生気を取り戻した面に、安堵して、さりげなく両手を膝に戻した。
政宗は、小十郎の襟元から手を離し、背中越しに顔を擦って身を翻し、元の座に戻った。
―夕餉は、いかがいたしますか?―
と、小十郎が問うと、半ば驚いたように、―そんな刻限か---―と呟き、
―飯はいらん。酒を持ってきてくれ。―
と吐息とともに漏らした。
―いけませぬ。朝から何も口にされてはないではありませんか---―
仕方のない---と諌めるも、哀しげに口許を歪め、
―食いたくない---。―
と呻く政宗に、それ以上の箴言も憚られて、受けるしかなかった。
―では、何か某が肴を見繕ってお持ちしましょう―
小十郎は、そう言って政宗の居室を下がり、厨に向かった。
―月が、赤いのぅ---―
飯炊きの老爺のもそりとした戯言が、やけに耳に残った。
0
お気に入りに追加
29
あなたにおすすめの小説
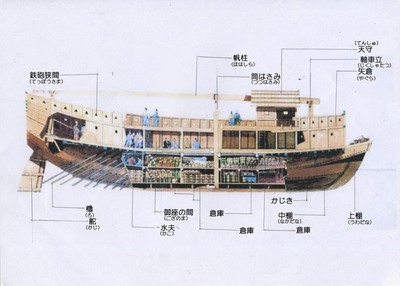

徳川家基、不本意!
克全
歴史・時代
幻の11代将軍、徳川家基が生き残っていたらどのような世の中になっていたのか?田沼意次に取立てられて、徳川家基の住む西之丸御納戸役となっていた長谷川平蔵が、田沼意次ではなく徳川家基に取り入って出世しようとしていたらどうなっていたのか?徳川家治が、次々と死んでいく自分の子供の死因に疑念を持っていたらどうなっていたのか、そのような事を考えて創作してみました。

思い出乞ひわずらい
水城真以
歴史・時代
――これは、天下人の名を継ぐはずだった者の物語――
ある日、信長の嫡男、奇妙丸と知り合った勝蔵。奇妙丸の努力家な一面に惹かれる。
一方奇妙丸も、媚びへつらわない勝蔵に特別な感情を覚える。
同じく奇妙丸のもとを出入りする勝九朗や於泉と交流し、友情をはぐくんでいくが、ある日を境にその絆が破綻してしまって――。
織田信長の嫡男・信忠と仲間たちの幼少期のお話です。以前公開していた作品が長くなってしまったので、章ごとに区切って加筆修正しながら更新していきたいと思います。

真田源三郎の休日
神光寺かをり
歴史・時代
信濃の小さな国衆(豪族)に過ぎない真田家は、甲斐の一大勢力・武田家の庇護のもと、どうにかこうにか生きていた。
……のだが、頼りの武田家が滅亡した!
家名存続のため、真田家当主・昌幸が選んだのは、なんと武田家を滅ぼした織田信長への従属!
ところがところが、速攻で本能寺の変が発生、織田信長は死亡してしまう。
こちらの選択によっては、真田家は――そして信州・甲州・上州の諸家は――あっという間に滅亡しかねない。
そして信之自身、最近出来たばかりの親友と槍を合わせることになる可能性が出てきた。
16歳の少年はこの連続ピンチを無事に乗り越えられるのか?

織田信長IF… 天下統一再び!!
華瑠羅
歴史・時代
日本の歴史上最も有名な『本能寺の変』の当日から物語は足早に流れて行く展開です。
この作品は「もし」という概念で物語が進行していきます。
主人公【織田信長】が死んで、若返って蘇り再び活躍するという作品です。
※この物語はフィクションです。

戦国九州三国志
谷鋭二
歴史・時代
戦国時代九州は、三つの勢力が覇権をかけて激しい争いを繰り返しました。南端の地薩摩(鹿児島)から興った鎌倉以来の名門島津氏、肥前(現在の長崎、佐賀)を基盤にした新興の龍造寺氏、そして島津同様鎌倉以来の名門で豊後(大分県)を中心とする大友家です。この物語ではこの三者の争いを主に大友家を中心に描いていきたいと思います。

16世紀のオデュッセイア
尾方佐羽
歴史・時代
【第12章を週1回程度更新します】世界の海が人と船で結ばれていく16世紀の遥かな旅の物語です。
12章では16世紀後半のヨーロッパが舞台になります。
※このお話は史実を参考にしたフィクションです。

くじら斗りゅう
陸 理明
歴史・時代
捕鯨によって空前の繁栄を謳歌する太地村を領内に有する紀伊新宮藩は、藩の財政を活性化させようと新しく藩直営の鯨方を立ち上げた。はぐれ者、あぶれ者、行き場のない若者をかき集めて作られた鵜殿の村には、もと武士でありながら捕鯨への情熱に満ちた権藤伊左馬という巨漢もいた。このままいけば新たな捕鯨の中心地となったであろう鵜殿であったが、ある嵐の日に突然現れた〈竜〉の如き巨大な生き物を獲ってしまったことから滅びへの運命を歩み始める…… これは、愛憎と欲望に翻弄される若き鯨猟夫たちの青春譚である。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















