7 / 22
第七話 弓張月
しおりを挟む
城はその日、新緑に相応しく慶事に沸いていた。
青葉が陽に照り映えるなか、正装に身を包んだ政宗は、輿が到着するのを複雑な面持ちで待っていた。
傍らに控えていた小十郎は、主の初々しいその姿に微笑みながら、言った。
「ご心配には、及びませんよ。」
政宗はいささか硬くなりつつも、うん---と頷いた。一生に一度の儀式である。---元服の時とは違う緊張感がある。
―三春からの輿が着きましてございます。―
近習の者が、小走りで、控えの間にいる彼らのもとに花嫁の到着の報せを告げた。
―愛姫さま、無事お着きでございます。―
さぁ---。小十郎に背中を押され、政宗は出迎えの途につく。
花嫁は三春の田村氏の息女、愛姫。齢十二歳。政宗は十三歳。
並んで座ると、まんま雛人形のようである。
―目出度きことよ。―
小十郎は、宴席のやや末席に近いあたりに控えて、婚儀の儀式に臨む初々しいふたりを見詰めていた。
花嫁は、若々しい---というより、可愛いらしくあどけない。咲き初めた桃花のようである。
政宗も心なしか、頬を上気させ、横目で何度も姫の姿を見遣っている。
小十郎は、内心、ほっ---としていた。なかなかに、似合いで、何より花嫁は、優し気な笑みで政宗を見ていた。
戦国の世のこと、当たり前の政略結婚ではある。
だが、それでも、互いに慈しみ合える夫婦であって欲しい---。小十郎は心の底からそう願っていた。
幼少期から---あの事があって、片眼を失ってから、人の愛から遠く離れ、孤独な日々を過ごしていた政宗である。
実際のところ、「あの事」があってから、周囲の者の多くが、政宗から離れていった。容姿を嫌うものもあれば、素行の荒々しさに耐えかねて離れていった者もいる。
―如何にも人というものは、物事の表面のみに捉われやすい---―
師の虎哉宗乙の言うまでもなく、政宗は人の心の頼りなさを良く知っている。
―だからこそ---―
人の心は頼りない。だからこそ、心底から信じ合える存在を必要とする。
政宗は賢い。勇敢であり、その性根は繊細で愛情深く、優しい。
だからこそ、この殺伐たる戦国の世ので人の上に立ち、天下を目指すためには、強くならねばならぬ。
けれど、強くなるためには、多くのものを失わねばならない。
尚更、その心を志を支え、護るものが要る。
―愛姫さまには、どうか政宗のお心を癒やせる方であって欲しい---。―
小十郎は、嫡子の誕生とともに、この若い---というより幼い花嫁に、切に願って止まなかった。いつ敵に回るかわからない---、命を狙われることもある。
けれど---叶うなら、互いに真に支えあう夫婦になって欲しい。
小十郎は心底、祈らずにはおれなかった。
宴もたけなわになってきた頃、小十郎は密かに、宴席を抜け出した。
新郎新婦は、既に場を離れている。城を出て、兄の社に馬を走らせた先に使いは出してある。
今宵、少なくとも政宗は館には戻らない。
まだ若い夫婦ゆえ、形ばかりとはいえ、同衾して契りを交わす---筈である。
―どうすりゃ、いいんだ。―
尋ねる政宗に、小十郎は、
―その気にならずとも、手を取り合って眠るくらいのことはなさい。―
と教えてある。実際の手解きは綱元に任せて、然るべき女人と済ませてある---筈である。
ただ---
―『あの事』はまだ明かしてはなりません。あの方は、まだ伊達の家の方ではない。---しばらくは伏せておいでなさい。―
とだけは釘を差しておいた。
月が、東の空に姿を見せ始めた頃、小十郎は潔斎を済ませ、兄の待つ拝殿に入った。宴席でも酒の一滴も口にせず、膳にも箸を着けなかった。
白の一重と袴に着替え、---神事に臨む小十郎の顔には、これまでとは異なる決意が覗いている。
「本当に、良いのか?」
狩衣を着け、烏帽子を被り、正式な装束で儀式に臨む兄とて、初めて---のことである。
小十郎は黙って頷いた。
大幣を振り、場を清め、まず祓詞を奏上する。
そして「ひふみ祝詞」---魂振りの祝詞を唱え、小十郎の裡に居る黒龍を呼び覚ます。
小十郎の大柄な身体が震え、両の手が膝をきつく掴む。かなりの苦痛が体内を奔っていることは一目瞭然だった。
兄は小十郎の背後に爛と光るこの世ならぬ眼を見留めると、おもむろに龍神祝詞を奏上し、宥めて、呼び覚ましたことを詫び、意図を告げる。
それは---
―政宗の受ける穢れの全ては、自分が引き受ける。―という誓約であった。
あの日、自分が人外のものを内に宿している---と、龍の宿りと知った時、政宗は怯むことなく、前を見て進んでいくことを決めた。
小十郎は、その背中を何処までも護っていくことを改めて心に誓った。
小十郎にとって、政宗は希望であり、光だった。同じ龍の宿りとして、その辛苦を知るただ一人の存在。伴にその辛苦を乗り越えていくことが、小十郎にとっても唯一の希望であった。
幸いにも---小十郎の身の内の黒龍もそれを希んでいるように思えた。
自らが、天上界に帰ることが叶わずとも、この龍の貴公子と限りなく上昇していきたいと願っていることを小十郎は確かに感じていた。
この無謀とも思える誓いは、しかし、思わぬ形で却下された。
―ワシが祓うてやるわぇ。―
つ---と眩しい光が降り立ち、中空から声が響いた。少なくとも、兄と小十郎にはそい聞こえた。
―八幡---様?―
と呟く小十郎の身の内から、黒龍の野太い声がせり上がってきた。
―たわけ、八大龍王さまじゃ。―
八幡神の謇属の龍神---であるという。
つまりは、系統は違うが、龍属の御子の修行に一役買おう---ということらしい。
兄は平伏し、ひたすら祈っていたが、その耳には、
―龍の宿りどもには、人の穢れは寄らぬ。ただひたすらに道を進め。なれど、違えれば、お叱りはきつい。よぅ心せよ。―
と荘厳な声で語られた---と儀式の後に語った。
小十郎は黒龍が八大龍王の謇属であったこと、とある理由で逐われたこと---をこの時、初めて知った。
―ワシの元に戻るも、あちらに従うも、そなたが選べ。―と、黒龍は八大龍王に詰め寄られた---らしい。
そして、黒龍が出した答えは、
―こやつが、今、心の内に持つ願いを成就せしめたら---その時にお答え致します―
というものだった。
―お前、狡いぞ。―
と小十郎は思ったが、龍王は、―諾―---と赦したらしい。その黒い身体が畝り、脈打ち、耀変するように光った---ように思えた。
どれくらいの時間だったのか---一瞬だったのか、その光が去り、再び静寂に戻ったとき、兄弟はまったく言葉を失い、その場に崩折れていた。
―玄姶(げんおう)---だそうだ。―
―え?―
―お前の龍の名前。そう
呼び掛けてたぞ。あの光の主―
帰り際に疲れきった体の兄が、やっと口を開いて教えてくれた。
―ありがとう、済まなかった。―
―無茶はするなよ。―
―わかってる。―
兄弟は、ありきたりの言葉を投げ合いながら、ただ、その面は此れから---の重さをしみじみと噛み締めていた。
館へと帰る小十郎の目に、ひときわ大きく、弦月が光を放っていた。
青葉が陽に照り映えるなか、正装に身を包んだ政宗は、輿が到着するのを複雑な面持ちで待っていた。
傍らに控えていた小十郎は、主の初々しいその姿に微笑みながら、言った。
「ご心配には、及びませんよ。」
政宗はいささか硬くなりつつも、うん---と頷いた。一生に一度の儀式である。---元服の時とは違う緊張感がある。
―三春からの輿が着きましてございます。―
近習の者が、小走りで、控えの間にいる彼らのもとに花嫁の到着の報せを告げた。
―愛姫さま、無事お着きでございます。―
さぁ---。小十郎に背中を押され、政宗は出迎えの途につく。
花嫁は三春の田村氏の息女、愛姫。齢十二歳。政宗は十三歳。
並んで座ると、まんま雛人形のようである。
―目出度きことよ。―
小十郎は、宴席のやや末席に近いあたりに控えて、婚儀の儀式に臨む初々しいふたりを見詰めていた。
花嫁は、若々しい---というより、可愛いらしくあどけない。咲き初めた桃花のようである。
政宗も心なしか、頬を上気させ、横目で何度も姫の姿を見遣っている。
小十郎は、内心、ほっ---としていた。なかなかに、似合いで、何より花嫁は、優し気な笑みで政宗を見ていた。
戦国の世のこと、当たり前の政略結婚ではある。
だが、それでも、互いに慈しみ合える夫婦であって欲しい---。小十郎は心の底からそう願っていた。
幼少期から---あの事があって、片眼を失ってから、人の愛から遠く離れ、孤独な日々を過ごしていた政宗である。
実際のところ、「あの事」があってから、周囲の者の多くが、政宗から離れていった。容姿を嫌うものもあれば、素行の荒々しさに耐えかねて離れていった者もいる。
―如何にも人というものは、物事の表面のみに捉われやすい---―
師の虎哉宗乙の言うまでもなく、政宗は人の心の頼りなさを良く知っている。
―だからこそ---―
人の心は頼りない。だからこそ、心底から信じ合える存在を必要とする。
政宗は賢い。勇敢であり、その性根は繊細で愛情深く、優しい。
だからこそ、この殺伐たる戦国の世ので人の上に立ち、天下を目指すためには、強くならねばならぬ。
けれど、強くなるためには、多くのものを失わねばならない。
尚更、その心を志を支え、護るものが要る。
―愛姫さまには、どうか政宗のお心を癒やせる方であって欲しい---。―
小十郎は、嫡子の誕生とともに、この若い---というより幼い花嫁に、切に願って止まなかった。いつ敵に回るかわからない---、命を狙われることもある。
けれど---叶うなら、互いに真に支えあう夫婦になって欲しい。
小十郎は心底、祈らずにはおれなかった。
宴もたけなわになってきた頃、小十郎は密かに、宴席を抜け出した。
新郎新婦は、既に場を離れている。城を出て、兄の社に馬を走らせた先に使いは出してある。
今宵、少なくとも政宗は館には戻らない。
まだ若い夫婦ゆえ、形ばかりとはいえ、同衾して契りを交わす---筈である。
―どうすりゃ、いいんだ。―
尋ねる政宗に、小十郎は、
―その気にならずとも、手を取り合って眠るくらいのことはなさい。―
と教えてある。実際の手解きは綱元に任せて、然るべき女人と済ませてある---筈である。
ただ---
―『あの事』はまだ明かしてはなりません。あの方は、まだ伊達の家の方ではない。---しばらくは伏せておいでなさい。―
とだけは釘を差しておいた。
月が、東の空に姿を見せ始めた頃、小十郎は潔斎を済ませ、兄の待つ拝殿に入った。宴席でも酒の一滴も口にせず、膳にも箸を着けなかった。
白の一重と袴に着替え、---神事に臨む小十郎の顔には、これまでとは異なる決意が覗いている。
「本当に、良いのか?」
狩衣を着け、烏帽子を被り、正式な装束で儀式に臨む兄とて、初めて---のことである。
小十郎は黙って頷いた。
大幣を振り、場を清め、まず祓詞を奏上する。
そして「ひふみ祝詞」---魂振りの祝詞を唱え、小十郎の裡に居る黒龍を呼び覚ます。
小十郎の大柄な身体が震え、両の手が膝をきつく掴む。かなりの苦痛が体内を奔っていることは一目瞭然だった。
兄は小十郎の背後に爛と光るこの世ならぬ眼を見留めると、おもむろに龍神祝詞を奏上し、宥めて、呼び覚ましたことを詫び、意図を告げる。
それは---
―政宗の受ける穢れの全ては、自分が引き受ける。―という誓約であった。
あの日、自分が人外のものを内に宿している---と、龍の宿りと知った時、政宗は怯むことなく、前を見て進んでいくことを決めた。
小十郎は、その背中を何処までも護っていくことを改めて心に誓った。
小十郎にとって、政宗は希望であり、光だった。同じ龍の宿りとして、その辛苦を知るただ一人の存在。伴にその辛苦を乗り越えていくことが、小十郎にとっても唯一の希望であった。
幸いにも---小十郎の身の内の黒龍もそれを希んでいるように思えた。
自らが、天上界に帰ることが叶わずとも、この龍の貴公子と限りなく上昇していきたいと願っていることを小十郎は確かに感じていた。
この無謀とも思える誓いは、しかし、思わぬ形で却下された。
―ワシが祓うてやるわぇ。―
つ---と眩しい光が降り立ち、中空から声が響いた。少なくとも、兄と小十郎にはそい聞こえた。
―八幡---様?―
と呟く小十郎の身の内から、黒龍の野太い声がせり上がってきた。
―たわけ、八大龍王さまじゃ。―
八幡神の謇属の龍神---であるという。
つまりは、系統は違うが、龍属の御子の修行に一役買おう---ということらしい。
兄は平伏し、ひたすら祈っていたが、その耳には、
―龍の宿りどもには、人の穢れは寄らぬ。ただひたすらに道を進め。なれど、違えれば、お叱りはきつい。よぅ心せよ。―
と荘厳な声で語られた---と儀式の後に語った。
小十郎は黒龍が八大龍王の謇属であったこと、とある理由で逐われたこと---をこの時、初めて知った。
―ワシの元に戻るも、あちらに従うも、そなたが選べ。―と、黒龍は八大龍王に詰め寄られた---らしい。
そして、黒龍が出した答えは、
―こやつが、今、心の内に持つ願いを成就せしめたら---その時にお答え致します―
というものだった。
―お前、狡いぞ。―
と小十郎は思ったが、龍王は、―諾―---と赦したらしい。その黒い身体が畝り、脈打ち、耀変するように光った---ように思えた。
どれくらいの時間だったのか---一瞬だったのか、その光が去り、再び静寂に戻ったとき、兄弟はまったく言葉を失い、その場に崩折れていた。
―玄姶(げんおう)---だそうだ。―
―え?―
―お前の龍の名前。そう
呼び掛けてたぞ。あの光の主―
帰り際に疲れきった体の兄が、やっと口を開いて教えてくれた。
―ありがとう、済まなかった。―
―無茶はするなよ。―
―わかってる。―
兄弟は、ありきたりの言葉を投げ合いながら、ただ、その面は此れから---の重さをしみじみと噛み締めていた。
館へと帰る小十郎の目に、ひときわ大きく、弦月が光を放っていた。
0
お気に入りに追加
29
あなたにおすすめの小説
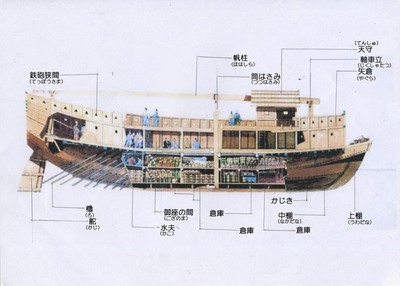

徳川家基、不本意!
克全
歴史・時代
幻の11代将軍、徳川家基が生き残っていたらどのような世の中になっていたのか?田沼意次に取立てられて、徳川家基の住む西之丸御納戸役となっていた長谷川平蔵が、田沼意次ではなく徳川家基に取り入って出世しようとしていたらどうなっていたのか?徳川家治が、次々と死んでいく自分の子供の死因に疑念を持っていたらどうなっていたのか、そのような事を考えて創作してみました。

思い出乞ひわずらい
水城真以
歴史・時代
――これは、天下人の名を継ぐはずだった者の物語――
ある日、信長の嫡男、奇妙丸と知り合った勝蔵。奇妙丸の努力家な一面に惹かれる。
一方奇妙丸も、媚びへつらわない勝蔵に特別な感情を覚える。
同じく奇妙丸のもとを出入りする勝九朗や於泉と交流し、友情をはぐくんでいくが、ある日を境にその絆が破綻してしまって――。
織田信長の嫡男・信忠と仲間たちの幼少期のお話です。以前公開していた作品が長くなってしまったので、章ごとに区切って加筆修正しながら更新していきたいと思います。

真田源三郎の休日
神光寺かをり
歴史・時代
信濃の小さな国衆(豪族)に過ぎない真田家は、甲斐の一大勢力・武田家の庇護のもと、どうにかこうにか生きていた。
……のだが、頼りの武田家が滅亡した!
家名存続のため、真田家当主・昌幸が選んだのは、なんと武田家を滅ぼした織田信長への従属!
ところがところが、速攻で本能寺の変が発生、織田信長は死亡してしまう。
こちらの選択によっては、真田家は――そして信州・甲州・上州の諸家は――あっという間に滅亡しかねない。
そして信之自身、最近出来たばかりの親友と槍を合わせることになる可能性が出てきた。
16歳の少年はこの連続ピンチを無事に乗り越えられるのか?

織田信長IF… 天下統一再び!!
華瑠羅
歴史・時代
日本の歴史上最も有名な『本能寺の変』の当日から物語は足早に流れて行く展開です。
この作品は「もし」という概念で物語が進行していきます。
主人公【織田信長】が死んで、若返って蘇り再び活躍するという作品です。
※この物語はフィクションです。

戦国九州三国志
谷鋭二
歴史・時代
戦国時代九州は、三つの勢力が覇権をかけて激しい争いを繰り返しました。南端の地薩摩(鹿児島)から興った鎌倉以来の名門島津氏、肥前(現在の長崎、佐賀)を基盤にした新興の龍造寺氏、そして島津同様鎌倉以来の名門で豊後(大分県)を中心とする大友家です。この物語ではこの三者の争いを主に大友家を中心に描いていきたいと思います。

16世紀のオデュッセイア
尾方佐羽
歴史・時代
【第12章を週1回程度更新します】世界の海が人と船で結ばれていく16世紀の遥かな旅の物語です。
12章では16世紀後半のヨーロッパが舞台になります。
※このお話は史実を参考にしたフィクションです。

くじら斗りゅう
陸 理明
歴史・時代
捕鯨によって空前の繁栄を謳歌する太地村を領内に有する紀伊新宮藩は、藩の財政を活性化させようと新しく藩直営の鯨方を立ち上げた。はぐれ者、あぶれ者、行き場のない若者をかき集めて作られた鵜殿の村には、もと武士でありながら捕鯨への情熱に満ちた権藤伊左馬という巨漢もいた。このままいけば新たな捕鯨の中心地となったであろう鵜殿であったが、ある嵐の日に突然現れた〈竜〉の如き巨大な生き物を獲ってしまったことから滅びへの運命を歩み始める…… これは、愛憎と欲望に翻弄される若き鯨猟夫たちの青春譚である。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















