5 / 22
第五話 上弦(二)
しおりを挟む
米沢城を出て、新しく設けられた館に梵天丸と小十郎が居をうつしのは、春もまだ浅い頃だった。
必要最低限の設えで従者も下男-下女が二人ずつ---。
城中の暮らしとは雲泥の差だった。
が、梵天丸は、むしろこの暮らしが気にいったようだった。
大変なのは、小十郎のほうだった。
人手を減らしたぶん、梵天丸の身の回りの世話は全て、小十郎の仕事となった。
―こりゃあ、大層な『子育て』だな---。―
当初から覚悟はしていたものの、思うよりも難儀なことの多い日々だった。
何せ、放ったらかしにされていたぶん、我が儘である。気紛れなうえに、利かん気も半端ではない。
目を離すと、すぐに学問をサボって庭先に逃亡して遊び出す。その代わり、史書や兵法書は貪るように読む。剣の稽古も、負けても負けても食らいついてくる。
実のところ、小十郎は一切、手加減をしなかった。
風呂に入れると、いつも擦り傷が滲みると文句を言われた。青アザも消える間もなく、増える。
だが、稽古が嫌だとは一言も言わなかった。
仲の良い従兄弟、時宗丸が時々やってきて、一緒に稽古、手合わせしてくれるからかもしれない。
「小十郎は大人だから、今は勝てないかもしれない。
けど、きっと勝つ。」
とふたりして言い切っている。時宗丸との手合わせは、五分。---一つ年下だが、食が細く偏食の激しい梵天丸より、一回り体格が良かった。
小十郎の一番の頭痛の種は、この「食事」だった。嫌いなものは、まず食べない。箸も付けない。
始めは嗜めたが、聞くわけがない。膳の前から逃げようとするのを、力づくで引き摺り戻して、食べ終わるまで、動くことを許さなかった。
ぽろぽろと涙を溢しながら、小十郎を上目遣いで睨むが、小十郎は表情も変えず見下ろしている。
体格が良いうえに、周囲いわく「強面」である。
作りは派手ではないが、角ばった長四角の顔、つり上がったはっきりした眉と奥底から光る眼、固く結んだ口許---真顔で睨み付けられると大概の者は竦み上がる。
―---俺の中に居る黒龍のせいだ。―
と、小十郎は思っているが、愛想の無さは本性だ、と喜多には言われる。
小十郎自身の幼少期も決して恵まれたものでは無かった。両親を早くに無くし、養子に行ったものの、養親に実の子が出来て返され、居場所の無い思いを抱えていた。喜多は厳しくも優しかったが、小十郎が十歳の時には、梵天丸の乳母として城に上がり、反りの合わない兄の妻とは顔を合わせたくないがため、社の傍らにあった粗末な小屋で寝起きしていた。
孤独ではあった---が、社の日々の勤めと剣の稽古が慰めになっていた。
「あなたのために、某が作ったのです。お食べください。」
とズイと膝を進めると、嫌々ながらも食べるようになったのは、厨で小十郎が四苦八苦しながら、作っている背中を見ていたからかもしれない。
似合わぬ襷掛けで、大柄な身体を屈めて、梵天丸の嫌いな野菜をなんとか食べやすく---と苦慮する真剣な横顔を黙ってじっと見ていることも、しばしばあった。
そして、小十郎はそんな梵天丸の視線に気付くと、途端に優しく顔で笑い掛ける。
梵天丸は、見つかったことが面映ゆくて、たいがいは一目散に姿を消すのだが、好物のずんだや小豆の煮物を「味見しますか?」と言われた時には、実に嬉しそうに、指先で掬って口許に運んだ。
そのうち、考えあぐねた小十郎は、庭の一部に畑を作り、野菜を育てることにした。種から苗、新芽から双葉へ作物へと育つ様を楽しげに眺めるようになって、梵天丸の偏食はかなり改善された。
時には、川に魚捕りにも出掛けた。最初の頃は、小十郎の言うとおり、大人しく川岸でキラキラ光る水面を眺めているのだが、早盤飽きて、水遊びを始める。
小十郎は、梵天丸が深みに嵌まらぬよう眼を配りながら、とりあえず夕餉の膳のぶんを釣り上げる。
そして、袴の半ばまで水浸しになった梵天丸を抱えて馬の背に乗せ、日の傾きかけた中を館に帰る。
十になったばかりの頃は、決まってはしゃぎすぎた梵天丸は、途中で小十郎に寄りかかって寝こけてしまうので、館に着くと、起こさないよう気をつけて、馬から下ろし、夕餉の支度が済むまで、床に寝かせておくのだった。無論、濡れた着物を起こさないよう、慎重に着替えさせて---だが。
―お前さまが、そのように子育て上手とは知らなんだわ---―
と、時折、様子を見に来る喜多は感心したように、呆れたように言った。
―何を仰せになる、姉上。
本来ならば、梵天丸さまの身の回りの世話は、乳母であるあなたの役目なのですぞ。―
梵天丸が、稽古中に派手に転んで破った袴の繕いをしながら、小十郎は喜多にむっとした口振りで言った。
喜多は素知らぬ顔で、師の宗乙に講義を受けている梵天丸の方を見やって言った。
「乳母の仕事は、元服までじゃ。後は、傅役であるそなたの役目であろう。」
ぐ---と小十郎は言葉を詰まらせた。この館に移って間もなく、父-輝宗は梵天丸を元服させた。
―自分の館を構えるようになったのだから---―
と、伊達家中興の祖、第九代大膳大夫政宗より、その名前をいただき、梵天丸に『政宗』と名乗らせた。
そして、満面の笑みを湛え、
―そなたは、わしだけの子ではない。龍神の和子でもある。しかと励めよ。―
と告げた。が、その笑みの片隅に寂しげな色が漂っていたのを誰ひとり知る由もなかった。
「小十郎、何処じゃ。」
講義を終えた梵天丸が、スタスタと濃藍の袴の裾を翻しながら近づいてきた。
「ここにございます、梵天丸さま。如何なされました?」
丁重に頭を下げる小十郎に不服そうに口を尖らせて、梵天丸が抗議した。
「政宗じゃ。我れは、もう童ではない。」
「これは失礼つかまつりました。---して、如何がされました、政宗さま。」
一層丁重に頭を下げる小十郎に、梵天丸もとい政宗は、胸を張って言った。
「今日は、宗乙に褒められたぞ。褒美に、一曲、奏して聞かせぃ。」
「承知致しました。」
にっこり微笑んで、懐から『秋月』を取り出し、小十郎は唇に充てた。
―まだまだ、お可愛い。―
こっそりと喜多と小十郎が目配せをしたことに気付くこともなく、政宗は、柔らかな音色が秋空の青に溶けていくさまに、うっとりと聞き惚れていた。
必要最低限の設えで従者も下男-下女が二人ずつ---。
城中の暮らしとは雲泥の差だった。
が、梵天丸は、むしろこの暮らしが気にいったようだった。
大変なのは、小十郎のほうだった。
人手を減らしたぶん、梵天丸の身の回りの世話は全て、小十郎の仕事となった。
―こりゃあ、大層な『子育て』だな---。―
当初から覚悟はしていたものの、思うよりも難儀なことの多い日々だった。
何せ、放ったらかしにされていたぶん、我が儘である。気紛れなうえに、利かん気も半端ではない。
目を離すと、すぐに学問をサボって庭先に逃亡して遊び出す。その代わり、史書や兵法書は貪るように読む。剣の稽古も、負けても負けても食らいついてくる。
実のところ、小十郎は一切、手加減をしなかった。
風呂に入れると、いつも擦り傷が滲みると文句を言われた。青アザも消える間もなく、増える。
だが、稽古が嫌だとは一言も言わなかった。
仲の良い従兄弟、時宗丸が時々やってきて、一緒に稽古、手合わせしてくれるからかもしれない。
「小十郎は大人だから、今は勝てないかもしれない。
けど、きっと勝つ。」
とふたりして言い切っている。時宗丸との手合わせは、五分。---一つ年下だが、食が細く偏食の激しい梵天丸より、一回り体格が良かった。
小十郎の一番の頭痛の種は、この「食事」だった。嫌いなものは、まず食べない。箸も付けない。
始めは嗜めたが、聞くわけがない。膳の前から逃げようとするのを、力づくで引き摺り戻して、食べ終わるまで、動くことを許さなかった。
ぽろぽろと涙を溢しながら、小十郎を上目遣いで睨むが、小十郎は表情も変えず見下ろしている。
体格が良いうえに、周囲いわく「強面」である。
作りは派手ではないが、角ばった長四角の顔、つり上がったはっきりした眉と奥底から光る眼、固く結んだ口許---真顔で睨み付けられると大概の者は竦み上がる。
―---俺の中に居る黒龍のせいだ。―
と、小十郎は思っているが、愛想の無さは本性だ、と喜多には言われる。
小十郎自身の幼少期も決して恵まれたものでは無かった。両親を早くに無くし、養子に行ったものの、養親に実の子が出来て返され、居場所の無い思いを抱えていた。喜多は厳しくも優しかったが、小十郎が十歳の時には、梵天丸の乳母として城に上がり、反りの合わない兄の妻とは顔を合わせたくないがため、社の傍らにあった粗末な小屋で寝起きしていた。
孤独ではあった---が、社の日々の勤めと剣の稽古が慰めになっていた。
「あなたのために、某が作ったのです。お食べください。」
とズイと膝を進めると、嫌々ながらも食べるようになったのは、厨で小十郎が四苦八苦しながら、作っている背中を見ていたからかもしれない。
似合わぬ襷掛けで、大柄な身体を屈めて、梵天丸の嫌いな野菜をなんとか食べやすく---と苦慮する真剣な横顔を黙ってじっと見ていることも、しばしばあった。
そして、小十郎はそんな梵天丸の視線に気付くと、途端に優しく顔で笑い掛ける。
梵天丸は、見つかったことが面映ゆくて、たいがいは一目散に姿を消すのだが、好物のずんだや小豆の煮物を「味見しますか?」と言われた時には、実に嬉しそうに、指先で掬って口許に運んだ。
そのうち、考えあぐねた小十郎は、庭の一部に畑を作り、野菜を育てることにした。種から苗、新芽から双葉へ作物へと育つ様を楽しげに眺めるようになって、梵天丸の偏食はかなり改善された。
時には、川に魚捕りにも出掛けた。最初の頃は、小十郎の言うとおり、大人しく川岸でキラキラ光る水面を眺めているのだが、早盤飽きて、水遊びを始める。
小十郎は、梵天丸が深みに嵌まらぬよう眼を配りながら、とりあえず夕餉の膳のぶんを釣り上げる。
そして、袴の半ばまで水浸しになった梵天丸を抱えて馬の背に乗せ、日の傾きかけた中を館に帰る。
十になったばかりの頃は、決まってはしゃぎすぎた梵天丸は、途中で小十郎に寄りかかって寝こけてしまうので、館に着くと、起こさないよう気をつけて、馬から下ろし、夕餉の支度が済むまで、床に寝かせておくのだった。無論、濡れた着物を起こさないよう、慎重に着替えさせて---だが。
―お前さまが、そのように子育て上手とは知らなんだわ---―
と、時折、様子を見に来る喜多は感心したように、呆れたように言った。
―何を仰せになる、姉上。
本来ならば、梵天丸さまの身の回りの世話は、乳母であるあなたの役目なのですぞ。―
梵天丸が、稽古中に派手に転んで破った袴の繕いをしながら、小十郎は喜多にむっとした口振りで言った。
喜多は素知らぬ顔で、師の宗乙に講義を受けている梵天丸の方を見やって言った。
「乳母の仕事は、元服までじゃ。後は、傅役であるそなたの役目であろう。」
ぐ---と小十郎は言葉を詰まらせた。この館に移って間もなく、父-輝宗は梵天丸を元服させた。
―自分の館を構えるようになったのだから---―
と、伊達家中興の祖、第九代大膳大夫政宗より、その名前をいただき、梵天丸に『政宗』と名乗らせた。
そして、満面の笑みを湛え、
―そなたは、わしだけの子ではない。龍神の和子でもある。しかと励めよ。―
と告げた。が、その笑みの片隅に寂しげな色が漂っていたのを誰ひとり知る由もなかった。
「小十郎、何処じゃ。」
講義を終えた梵天丸が、スタスタと濃藍の袴の裾を翻しながら近づいてきた。
「ここにございます、梵天丸さま。如何なされました?」
丁重に頭を下げる小十郎に不服そうに口を尖らせて、梵天丸が抗議した。
「政宗じゃ。我れは、もう童ではない。」
「これは失礼つかまつりました。---して、如何がされました、政宗さま。」
一層丁重に頭を下げる小十郎に、梵天丸もとい政宗は、胸を張って言った。
「今日は、宗乙に褒められたぞ。褒美に、一曲、奏して聞かせぃ。」
「承知致しました。」
にっこり微笑んで、懐から『秋月』を取り出し、小十郎は唇に充てた。
―まだまだ、お可愛い。―
こっそりと喜多と小十郎が目配せをしたことに気付くこともなく、政宗は、柔らかな音色が秋空の青に溶けていくさまに、うっとりと聞き惚れていた。
0
お気に入りに追加
29
あなたにおすすめの小説
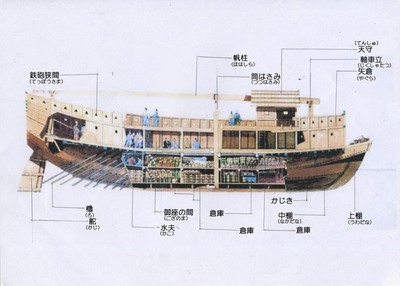

徳川家基、不本意!
克全
歴史・時代
幻の11代将軍、徳川家基が生き残っていたらどのような世の中になっていたのか?田沼意次に取立てられて、徳川家基の住む西之丸御納戸役となっていた長谷川平蔵が、田沼意次ではなく徳川家基に取り入って出世しようとしていたらどうなっていたのか?徳川家治が、次々と死んでいく自分の子供の死因に疑念を持っていたらどうなっていたのか、そのような事を考えて創作してみました。

思い出乞ひわずらい
水城真以
歴史・時代
――これは、天下人の名を継ぐはずだった者の物語――
ある日、信長の嫡男、奇妙丸と知り合った勝蔵。奇妙丸の努力家な一面に惹かれる。
一方奇妙丸も、媚びへつらわない勝蔵に特別な感情を覚える。
同じく奇妙丸のもとを出入りする勝九朗や於泉と交流し、友情をはぐくんでいくが、ある日を境にその絆が破綻してしまって――。
織田信長の嫡男・信忠と仲間たちの幼少期のお話です。以前公開していた作品が長くなってしまったので、章ごとに区切って加筆修正しながら更新していきたいと思います。

真田源三郎の休日
神光寺かをり
歴史・時代
信濃の小さな国衆(豪族)に過ぎない真田家は、甲斐の一大勢力・武田家の庇護のもと、どうにかこうにか生きていた。
……のだが、頼りの武田家が滅亡した!
家名存続のため、真田家当主・昌幸が選んだのは、なんと武田家を滅ぼした織田信長への従属!
ところがところが、速攻で本能寺の変が発生、織田信長は死亡してしまう。
こちらの選択によっては、真田家は――そして信州・甲州・上州の諸家は――あっという間に滅亡しかねない。
そして信之自身、最近出来たばかりの親友と槍を合わせることになる可能性が出てきた。
16歳の少年はこの連続ピンチを無事に乗り越えられるのか?

織田信長IF… 天下統一再び!!
華瑠羅
歴史・時代
日本の歴史上最も有名な『本能寺の変』の当日から物語は足早に流れて行く展開です。
この作品は「もし」という概念で物語が進行していきます。
主人公【織田信長】が死んで、若返って蘇り再び活躍するという作品です。
※この物語はフィクションです。

戦国九州三国志
谷鋭二
歴史・時代
戦国時代九州は、三つの勢力が覇権をかけて激しい争いを繰り返しました。南端の地薩摩(鹿児島)から興った鎌倉以来の名門島津氏、肥前(現在の長崎、佐賀)を基盤にした新興の龍造寺氏、そして島津同様鎌倉以来の名門で豊後(大分県)を中心とする大友家です。この物語ではこの三者の争いを主に大友家を中心に描いていきたいと思います。

16世紀のオデュッセイア
尾方佐羽
歴史・時代
【第12章を週1回程度更新します】世界の海が人と船で結ばれていく16世紀の遥かな旅の物語です。
12章では16世紀後半のヨーロッパが舞台になります。
※このお話は史実を参考にしたフィクションです。

くじら斗りゅう
陸 理明
歴史・時代
捕鯨によって空前の繁栄を謳歌する太地村を領内に有する紀伊新宮藩は、藩の財政を活性化させようと新しく藩直営の鯨方を立ち上げた。はぐれ者、あぶれ者、行き場のない若者をかき集めて作られた鵜殿の村には、もと武士でありながら捕鯨への情熱に満ちた権藤伊左馬という巨漢もいた。このままいけば新たな捕鯨の中心地となったであろう鵜殿であったが、ある嵐の日に突然現れた〈竜〉の如き巨大な生き物を獲ってしまったことから滅びへの運命を歩み始める…… これは、愛憎と欲望に翻弄される若き鯨猟夫たちの青春譚である。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















