1 / 1
第1章
夏休み前のホームルーム 1
しおりを挟む
――走るの、好きか?
「……それじゃ、体育委員から休み明けの体育祭のことについて……頼んだわ」
えっ、という女子生徒の声も聞かずに、担任の丹波先生は教室の前のドアを開けてどこかに行ってしまった。相変わらずこのおっちゃんは自由奔放な性格だ。
周囲の鳴り止まないおしゃべりを背に、体育委員の上本はしばらくフリーズしていたが、気を取り直したかのように咳払いを一つすると、自分の席を立ち黒板の前に出て声を張り上げた。
「スマン、みんな私の話を聞いてく……人の話を聞けーっ」
上本の叫びにより教室内の音量は半分くらいになったが、それでもまだ何人か私語をやめない。
上本はこの八幡実業高校の進学クラスの1つ、3年3組40人の中でも一、二を争うほど成績優秀な秀才でいて、性格も非常にまじめだ。ただ、本人はいたって真剣なのにどこか抜けているところがあり、それが、ともすれば人を遠ざけがちなまじめさを持った上本に対する親しみやすさを演出している。
「そういえばさ、冷房って壊れてんだっけ?暑いんだけど」
前に立った上本に対して話しかけたのは一番前の真ん中の席に座っている、乃木である。野球部を引退してさらに髪が伸びている。
「いや……28℃を下回らない設定に固定されているだけだよ」
乃木はそれを聞くと首を窓の方に向けて明らかに不機嫌そうに舌打ちした。上本は思わず眉を持ち上げたが、乃木の言い分もわからないではない。季節は梅雨が明けたばかりの7月の下旬、蒸し暑い外に比べれば教室内はもちろん快適ではあるが、それでもこの狭い空間の中に40人というのは人口密度が高すぎる。
俺も乃木につられて窓ごしに外の景色を見た。午前中は本降りの雨が降っていたが昼前には止んで、今はだんだん雲が切れて日が射してきている。明日は今日以上に蒸し暑そうだ。
ふと自分のスポーツウォッチに目を落としてみる。14:10。……あと40分。
「……もういいわ。話を始めます」と独り言のようにつぶやいた後、上本は手に持ったプリントに視線を落として、内容を読み始めようとした。が、その前に思い出したように顔を上げて、教室の後ろに向かって「山井君も出てきてよ!」と呼んだ。山井、と呼ばれた長身痩躯の男子生徒は、やっぱり俺も前に出なきゃだめ?といった感じで舌を出しながらのそりのそりと席を立って歩いてきた。山井は身長185センチメートル、ほどよく伸びた長髪は全体的に明るい茶色という目立つ出で立ちだ。山井はゆっくりと、もう一人の体育委員である上本の横に着き、「上本さん、さあ、どうぞ」と、お話を聞く準備はできましたとばかりに目配せする。
「……はい、じゃあ話を始めます。来週から夏休みに入りますが、夏休み明けの週末にある体育祭の各個人種目、誰がどの競技に出場するかを今日のホームルームで決めてほしい……という体育委員会からのお願いです。要するに、今日は体育祭の種目決めをしたいと思います」
上本は一息ついてまた話し始めた。
「もう3年目だしみんなわかってると思うんだけど、種目は、男子女子共にフットサル、バスケ、バレーボール。それぞれ人数は6、7、7人ね。で、3年生はクラス対抗種目として大縄跳び、それから代表を4人選んでのスウェーデンリレーがあります。で……」
上本は話しながらすらすらと黒板に、種目の名前と人数を書いていく。さっき上本は、みんな3年目、と言っていたが、俺だけはあてはまらない。去年部活動の新人戦で体育祭を公欠した俺は2年目である――
というくだらない揚げ足取りを頭で考えているうちに、フットサル、バスケ、バレーボールの希望調査が始まってしまった。第1希望の種目を紙に書いて体育委員に渡し、開票して制限人数以下なら決定、オーバーするようなら希望者同士での話し合いという形だ。
確か2年前のこの時には、誰もが体育祭のことを心のどこかで楽しみに、わくわくしたような雰囲気が流れていた気がするが、今回はあまりそんな感じがしない。1年生と3年生は違う。これからの自分の進路、受験勉強、そういった類のものが学校行事へのやる気を奪ってしまっている。また、こういうものに一心不乱に熱くなれるほど、みんなもう子供ではないのかもしれない。男子と女子のバスケがオーバーしたが、熱心に譲らないつもりの生徒はほとんどいないようで、あっさり話はまとまってしまった。
「みんなの協力ですぐに決めることができたわ、ありがとう」
上本は少しだけ微笑んで、教室に向かってそう言った。みんなのやる気がなさそうなのをやはり感じているのか、やや残念そうな微笑だ。
「それで、あとスウェーデンリレーの代表を決めなくちゃいけないんだけど」
腕時計は14:30と表示している。あと20分。
「誰か出てくれる?」
上本は全体にそう問いかけたが、手が挙がらない。何人かの話し声も完全に静まった。ま、そりゃそうか……と思う。受験を間近に控えるこの時期に、どうして好き好んで全力疾走しなきゃいけない、運動部に所属していない生徒の多いうちのクラスならなおさらだ。球技ですらモチベーションが低いのに、志願制のリレーに出たい人がいる道理がないのだ。
「まず山井が出ればいいだろ」
「えっ……俺ぇ?」
窓際でさっきまでしゃべっていた島崎が山井を推薦する。……さっきは聞き逃していたが、そういえばスウェーデンリレーっていうのも、ウチの体育祭にはあったか。
「いやでも俺走るの専門じゃないし」
「そんなこと言ったってお前バスケ部の主力じゃんかよ」
「走る専門だったら、ほら、江崎君がいるからさ」
唐突に、江崎君、と、他人行儀に呼ばれたので、思わず辺りを見回してしまった。いや、どこを見回しても江崎という苗字はこのクラスにたった一人、
「は、走る専門っつっても……俺の専門はセンゴとゴセンなんだけど……」
咄嗟に山井に言い返す。スウェーデンリレーは、100m、200m、300m、400mの合計1000mを4人で走る、変則的なリレー競技だ。この競技は、インターハイや日本選手権、オリンピックといった大きな大会で行われるものではなく、こういった学校の体育祭の一種目としてときどき行われている。走る距離はいわゆる“短距離”に分類され、俺が陸上部で取り組んでいた1500m(センゴ)や5000m(ゴセン)といった“中長距離”とはそもそも異なるものである。
が、陸上競技に専門的に携わっていない人にとっては同じように思えるのかもしれない。しかし、こいつの場合は知らないふりをしている。
「だって江崎、あのリクブに3年間着いて行ってたわけでしょ?絶対走れるって」
山井は、さらに詰め寄ってくる。確かに、練習で400mを20本などといったことをやったりはするから、走れないわけではないし、むしろそのくらいの距離をこのクラスで一番速く走れないようでは、自分の6年間に納得できないし、【あいつ】から認めてもらうなんてとうてい無理な話だったと思う。
山井の問いかけにうんともいやとも言わないでいると、山井は「じゃあ江崎は決定な!」と勝手に宣言してしまった。
「ちょっ、勝手に決めんなバカ」
山井は俺の言うことになんか全く構っていない。山井につられてまばらに拍手が起こる。
「そんじゃああとは……」
と、山井の視線は、このクラスで50m走のタイムが最も速かった、一番前の乃木に向いた。その気配を察知してか、
「俺はお断りだ」
間髪入れずに乃木が反駁した。
「なんで!」
「走るのが嫌だからっていう理由以外ないだろ」
乃木の言葉を聞いて俺の鼓動が早くなる。
――走るの、好きじゃない?
「全く困ったやつだな」
乃木の気性はわかっているのか、俺の時とは違って山井はあっさりと引いた。乃木には強く言えないが、俺のことは舐めている。
「えーっと……ホントに、誰も、いない?」
山井は頭をボリボリと掻きながら、いかにも、まいったなあ、といったふうな表情をしている。
「いないとおにいさん、困っちゃうんだけどなあ」
山井には頼まれたが、はっきり言うと俺も出たくない。3年間、阿呆みたいに走った。全てを擲って走った。山井、だからもう走るのは――
「そ、そんなにみんな走りたくない……なら、私、走ろうかな……」
さっきから山井の隣でうつむいていた上本が、訥々と、いつもの明るい調子ではなく消え入るような声でつぶやいた。
「えっ、マジで」
山井が驚いた声を上げた。俺も顔を上げた。
「女子が出ちゃいけないっていう規定は、なかったはずだし」
「で、でもなあ」
「だって、みんなどうでもいいと思ってるんでしょ」
クラスのメンバーも一様に驚いた表情をしているが、特に異論は差し挟まれない。
「だけど、それじゃ勝てな……」
「だって、みんなどうでもいいと思ってるんでしょ!」
と、上本は語気を荒らげた。
「私も3年間ずっとがんばってやってきたんだし、そりゃスポ薦のところは無理だろうけど、普通の進学クラスなら割といい勝負ができると思うんだけど。それに、やりたくない人に無理にやってもらうのは、お互いにとって不幸だよ」
「ん……まあ確かに、進学クラスの運動部所属率は……」
「いいんじゃない。上本運動神経あるし」
さっきの乃木もぼさぼさの頭を持ち上げて、眠たそうにつぶやいた。
「乃木!お前しっかりしてくれよ……」
「走りたい奴が走り、走りたくない奴は走らない。それでいいじゃねえの。50m走るのが速い遅いっていうだけで代表が選ばれるんじゃ、選ばれる側に全く人権がないと思うね。結果なんてどうでもいいだろ、たかが体育祭でさ」
「なにその言い方!私だと結果が出せないって言うの?やってみなきゃわかんないじゃん!」
乃木に対して、上本が珍しく怒りの色を露わにした。成績優秀、真面目、運動も(スポーツ推薦組に比べればもちろんたいしたことはないが)できる、気も利いていつも穏やかな上本が、ここまで誰かに対して怒気をむき出しにしたのを、同じクラスになって3年目にして初めて見た。
乃木は上本の方をちらっと見て、鼻でふっ、と笑った後、黒板の右上にかかっている時計を指さし、
「体育委員、もう6限終わるから、帰っていいかな。もういいだろ」
と言って、机の横にかかっている自分のカバンをひったくって、その質問の答えも聞かずに出て行ってしまった。
あとに残された上本、山井は何も言わないまま憮然として立っていた。乃木が出てから10秒もしないうちに6限の終わりを告げるチャイムが校内に鳴った。
――14:50。【あいつ】の、最後の出走時刻。
「……それじゃ、体育委員から休み明けの体育祭のことについて……頼んだわ」
えっ、という女子生徒の声も聞かずに、担任の丹波先生は教室の前のドアを開けてどこかに行ってしまった。相変わらずこのおっちゃんは自由奔放な性格だ。
周囲の鳴り止まないおしゃべりを背に、体育委員の上本はしばらくフリーズしていたが、気を取り直したかのように咳払いを一つすると、自分の席を立ち黒板の前に出て声を張り上げた。
「スマン、みんな私の話を聞いてく……人の話を聞けーっ」
上本の叫びにより教室内の音量は半分くらいになったが、それでもまだ何人か私語をやめない。
上本はこの八幡実業高校の進学クラスの1つ、3年3組40人の中でも一、二を争うほど成績優秀な秀才でいて、性格も非常にまじめだ。ただ、本人はいたって真剣なのにどこか抜けているところがあり、それが、ともすれば人を遠ざけがちなまじめさを持った上本に対する親しみやすさを演出している。
「そういえばさ、冷房って壊れてんだっけ?暑いんだけど」
前に立った上本に対して話しかけたのは一番前の真ん中の席に座っている、乃木である。野球部を引退してさらに髪が伸びている。
「いや……28℃を下回らない設定に固定されているだけだよ」
乃木はそれを聞くと首を窓の方に向けて明らかに不機嫌そうに舌打ちした。上本は思わず眉を持ち上げたが、乃木の言い分もわからないではない。季節は梅雨が明けたばかりの7月の下旬、蒸し暑い外に比べれば教室内はもちろん快適ではあるが、それでもこの狭い空間の中に40人というのは人口密度が高すぎる。
俺も乃木につられて窓ごしに外の景色を見た。午前中は本降りの雨が降っていたが昼前には止んで、今はだんだん雲が切れて日が射してきている。明日は今日以上に蒸し暑そうだ。
ふと自分のスポーツウォッチに目を落としてみる。14:10。……あと40分。
「……もういいわ。話を始めます」と独り言のようにつぶやいた後、上本は手に持ったプリントに視線を落として、内容を読み始めようとした。が、その前に思い出したように顔を上げて、教室の後ろに向かって「山井君も出てきてよ!」と呼んだ。山井、と呼ばれた長身痩躯の男子生徒は、やっぱり俺も前に出なきゃだめ?といった感じで舌を出しながらのそりのそりと席を立って歩いてきた。山井は身長185センチメートル、ほどよく伸びた長髪は全体的に明るい茶色という目立つ出で立ちだ。山井はゆっくりと、もう一人の体育委員である上本の横に着き、「上本さん、さあ、どうぞ」と、お話を聞く準備はできましたとばかりに目配せする。
「……はい、じゃあ話を始めます。来週から夏休みに入りますが、夏休み明けの週末にある体育祭の各個人種目、誰がどの競技に出場するかを今日のホームルームで決めてほしい……という体育委員会からのお願いです。要するに、今日は体育祭の種目決めをしたいと思います」
上本は一息ついてまた話し始めた。
「もう3年目だしみんなわかってると思うんだけど、種目は、男子女子共にフットサル、バスケ、バレーボール。それぞれ人数は6、7、7人ね。で、3年生はクラス対抗種目として大縄跳び、それから代表を4人選んでのスウェーデンリレーがあります。で……」
上本は話しながらすらすらと黒板に、種目の名前と人数を書いていく。さっき上本は、みんな3年目、と言っていたが、俺だけはあてはまらない。去年部活動の新人戦で体育祭を公欠した俺は2年目である――
というくだらない揚げ足取りを頭で考えているうちに、フットサル、バスケ、バレーボールの希望調査が始まってしまった。第1希望の種目を紙に書いて体育委員に渡し、開票して制限人数以下なら決定、オーバーするようなら希望者同士での話し合いという形だ。
確か2年前のこの時には、誰もが体育祭のことを心のどこかで楽しみに、わくわくしたような雰囲気が流れていた気がするが、今回はあまりそんな感じがしない。1年生と3年生は違う。これからの自分の進路、受験勉強、そういった類のものが学校行事へのやる気を奪ってしまっている。また、こういうものに一心不乱に熱くなれるほど、みんなもう子供ではないのかもしれない。男子と女子のバスケがオーバーしたが、熱心に譲らないつもりの生徒はほとんどいないようで、あっさり話はまとまってしまった。
「みんなの協力ですぐに決めることができたわ、ありがとう」
上本は少しだけ微笑んで、教室に向かってそう言った。みんなのやる気がなさそうなのをやはり感じているのか、やや残念そうな微笑だ。
「それで、あとスウェーデンリレーの代表を決めなくちゃいけないんだけど」
腕時計は14:30と表示している。あと20分。
「誰か出てくれる?」
上本は全体にそう問いかけたが、手が挙がらない。何人かの話し声も完全に静まった。ま、そりゃそうか……と思う。受験を間近に控えるこの時期に、どうして好き好んで全力疾走しなきゃいけない、運動部に所属していない生徒の多いうちのクラスならなおさらだ。球技ですらモチベーションが低いのに、志願制のリレーに出たい人がいる道理がないのだ。
「まず山井が出ればいいだろ」
「えっ……俺ぇ?」
窓際でさっきまでしゃべっていた島崎が山井を推薦する。……さっきは聞き逃していたが、そういえばスウェーデンリレーっていうのも、ウチの体育祭にはあったか。
「いやでも俺走るの専門じゃないし」
「そんなこと言ったってお前バスケ部の主力じゃんかよ」
「走る専門だったら、ほら、江崎君がいるからさ」
唐突に、江崎君、と、他人行儀に呼ばれたので、思わず辺りを見回してしまった。いや、どこを見回しても江崎という苗字はこのクラスにたった一人、
「は、走る専門っつっても……俺の専門はセンゴとゴセンなんだけど……」
咄嗟に山井に言い返す。スウェーデンリレーは、100m、200m、300m、400mの合計1000mを4人で走る、変則的なリレー競技だ。この競技は、インターハイや日本選手権、オリンピックといった大きな大会で行われるものではなく、こういった学校の体育祭の一種目としてときどき行われている。走る距離はいわゆる“短距離”に分類され、俺が陸上部で取り組んでいた1500m(センゴ)や5000m(ゴセン)といった“中長距離”とはそもそも異なるものである。
が、陸上競技に専門的に携わっていない人にとっては同じように思えるのかもしれない。しかし、こいつの場合は知らないふりをしている。
「だって江崎、あのリクブに3年間着いて行ってたわけでしょ?絶対走れるって」
山井は、さらに詰め寄ってくる。確かに、練習で400mを20本などといったことをやったりはするから、走れないわけではないし、むしろそのくらいの距離をこのクラスで一番速く走れないようでは、自分の6年間に納得できないし、【あいつ】から認めてもらうなんてとうてい無理な話だったと思う。
山井の問いかけにうんともいやとも言わないでいると、山井は「じゃあ江崎は決定な!」と勝手に宣言してしまった。
「ちょっ、勝手に決めんなバカ」
山井は俺の言うことになんか全く構っていない。山井につられてまばらに拍手が起こる。
「そんじゃああとは……」
と、山井の視線は、このクラスで50m走のタイムが最も速かった、一番前の乃木に向いた。その気配を察知してか、
「俺はお断りだ」
間髪入れずに乃木が反駁した。
「なんで!」
「走るのが嫌だからっていう理由以外ないだろ」
乃木の言葉を聞いて俺の鼓動が早くなる。
――走るの、好きじゃない?
「全く困ったやつだな」
乃木の気性はわかっているのか、俺の時とは違って山井はあっさりと引いた。乃木には強く言えないが、俺のことは舐めている。
「えーっと……ホントに、誰も、いない?」
山井は頭をボリボリと掻きながら、いかにも、まいったなあ、といったふうな表情をしている。
「いないとおにいさん、困っちゃうんだけどなあ」
山井には頼まれたが、はっきり言うと俺も出たくない。3年間、阿呆みたいに走った。全てを擲って走った。山井、だからもう走るのは――
「そ、そんなにみんな走りたくない……なら、私、走ろうかな……」
さっきから山井の隣でうつむいていた上本が、訥々と、いつもの明るい調子ではなく消え入るような声でつぶやいた。
「えっ、マジで」
山井が驚いた声を上げた。俺も顔を上げた。
「女子が出ちゃいけないっていう規定は、なかったはずだし」
「で、でもなあ」
「だって、みんなどうでもいいと思ってるんでしょ」
クラスのメンバーも一様に驚いた表情をしているが、特に異論は差し挟まれない。
「だけど、それじゃ勝てな……」
「だって、みんなどうでもいいと思ってるんでしょ!」
と、上本は語気を荒らげた。
「私も3年間ずっとがんばってやってきたんだし、そりゃスポ薦のところは無理だろうけど、普通の進学クラスなら割といい勝負ができると思うんだけど。それに、やりたくない人に無理にやってもらうのは、お互いにとって不幸だよ」
「ん……まあ確かに、進学クラスの運動部所属率は……」
「いいんじゃない。上本運動神経あるし」
さっきの乃木もぼさぼさの頭を持ち上げて、眠たそうにつぶやいた。
「乃木!お前しっかりしてくれよ……」
「走りたい奴が走り、走りたくない奴は走らない。それでいいじゃねえの。50m走るのが速い遅いっていうだけで代表が選ばれるんじゃ、選ばれる側に全く人権がないと思うね。結果なんてどうでもいいだろ、たかが体育祭でさ」
「なにその言い方!私だと結果が出せないって言うの?やってみなきゃわかんないじゃん!」
乃木に対して、上本が珍しく怒りの色を露わにした。成績優秀、真面目、運動も(スポーツ推薦組に比べればもちろんたいしたことはないが)できる、気も利いていつも穏やかな上本が、ここまで誰かに対して怒気をむき出しにしたのを、同じクラスになって3年目にして初めて見た。
乃木は上本の方をちらっと見て、鼻でふっ、と笑った後、黒板の右上にかかっている時計を指さし、
「体育委員、もう6限終わるから、帰っていいかな。もういいだろ」
と言って、机の横にかかっている自分のカバンをひったくって、その質問の答えも聞かずに出て行ってしまった。
あとに残された上本、山井は何も言わないまま憮然として立っていた。乃木が出てから10秒もしないうちに6限の終わりを告げるチャイムが校内に鳴った。
――14:50。【あいつ】の、最後の出走時刻。
0
お気に入りに追加
1
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

忘れられない約束
雪苺
青春
ねぇ、あなたは覚えていますか?
あの日交わした約束を・・・。
表紙イラストはミカスケ様
http://misoko.net/
小説家になろう、エブリスタ、カクヨムにも掲載しています。

この手が動かなくなるまで。
Rua もかもか
青春
私、ハナジマミユキは美術部の中学2年生。
絵を書くことが大好きで、コンテストで沢山優勝をしてるの。
私の彼氏、ヤマダケントとは
去年の宿泊学習で告白されて付き合うことになりました。
ある日部活をしていたら倒れてしまい、入院してしまうことに…
病院の先生に告げられたのは…

燦歌を乗せて
河島アドミ
青春
「燦歌彩月第六作――」その先の言葉は夜に消える。
久慈家の名家である天才画家・久慈色助は大学にも通わず怠惰な毎日をダラダラと過ごす。ある日、久慈家を勘当されホームレス生活がスタートすると、心を奪われる被写体・田中ゆかりに出会う。
第六作を描く。そう心に誓った色助は、己の未熟とホームレス生活を満喫しながら作品へ向き合っていく。

無敵のイエスマン
春海
青春
主人公の赤崎智也は、イエスマンを貫いて人間関係を完璧に築き上げ、他生徒の誰からも敵視されることなく高校生活を送っていた。敵がいない、敵無し、つまり無敵のイエスマンだ。赤崎は小学生の頃に、いじめられていた初恋の女の子をかばったことで、代わりに自分がいじめられ、二度とあんな目に遭いたくないと思い、無敵のイエスマンという人格を作り上げた。しかし、赤崎は自分がかばった女の子と再会し、彼女は赤崎の人格を変えようとする。そして、赤崎と彼女の勝負が始まる。赤崎が無敵のイエスマンを続けられるか、彼女が無敵のイエスマンである赤崎を変えられるか。これは、無敵のイエスマンの悲哀と恋と救いの物語。

代役だってやればできる!!
えび
青春
「付き合ってくれませんか?」
その一言で俺、石田由之の人生は急展開を迎える、と思ったのだかどうして彼氏の代役なんてやらねばならんのだ。
そう学校でも有名な石井薫に告白?されたが、好きだからではなく彼氏の代役をやって欲しいとのことだった。
由之と薫のドタバタなラブコメが展開されていく。果たして由之はどうなるのか?

貴方を救いたい、ただそれだけ。
天之奏詩(そらのかなた)
青春
死んだ姉が話してくれた【独りぼっちの世界】を求めて離れた街の神社に来た涼だったが、そこで彼は、誰にも認識されない少女、千里と出会う。彼にだけ彼女が認識できた理由、そして、彼女の正体とは一体。
千里を育てた行方不明の男は、彼女に言った。「後はお前が誰かを救ってあげること。親父からお前に託す、最後の使命だ」
涼に大きな影響を及ぼすその真相は、絡まっていた何本もの紐をほどき、纏めて一本の糸となって、ストーリーを縫い綴る。
驚きのラストを、是非あなたに届けたい。届け、この想い。
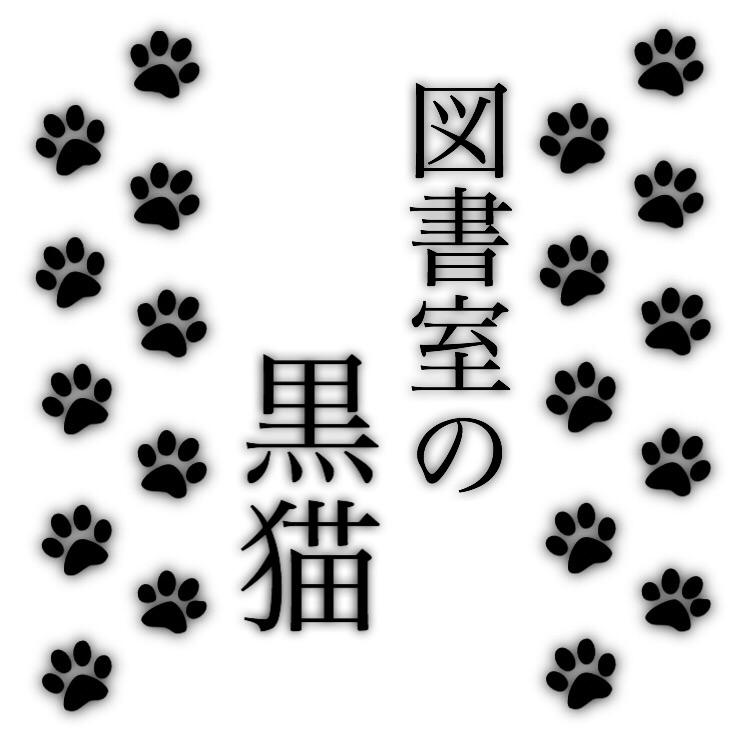

転校して来た美少女が前幼なじみだった件。
ながしょー
青春
ある日のHR。担任の呼び声とともに教室に入ってきた子は、とてつもない美少女だった。この世とはかけ離れた美貌に、男子はおろか、女子すらも言葉を詰まらせ、何も声が出てこない模様。モデルでもやっていたのか?そんなことを思いながら、彼女の自己紹介などを聞いていると、担任の先生がふと、俺の方を……いや、隣の席を指差す。今朝から気になってはいたが、彼女のための席だったということに今知ったのだが……男子たちの目線が異様に悪意の籠ったものに感じるが気のせいか?とにもかくにも隣の席が学校一の美少女ということになったわけで……。
このときの俺はまだ気づいていなかった。この子を軸として俺の身の回りが修羅場と化すことに。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















