20 / 30
四、翅鳥
(五)
しおりを挟む
「このようなところで、何をしているのです、ジェス」
「は、母上……」
突然現れた、ここに似つかわしくない、きらびやかな女性。その付き従う人の多さ、豪華すぎる衣装、そしてなにより、厳しすぎる声色に、独楽を持ったままのジェスが、ビクンと体を震わせた。
ジェスだけじゃない。膳夫たちは硬い土の床に額をこすりつけるように頭を下げて恐縮しきり。もちろん、オレだって――ジェスの母上って言ったら皇后様じゃねえか! ってことで膳夫たちほどじゃねえけど、女性らしく腰をかがめて頭を下げる。
「何をしているのか、訊いているのです、ジェス」
答えない息子に、皇后が一層低い声で訊ねた。
「ご、ごめんなさ……」
「謝罪は結構」
ジェスの言葉を皇后がピシャリと遮った。うわ、容赦ねえ。
「アナタはこの国の将来を担う大切な皇子なのですよ。このような場所に通い詰めるよりほかに、もっとやるべきことがあるでしょう」
正論。
正論かもしれねえけど、うつむいて唇を噛んだジェスを見てると、切なくなってくる。
「このような卑しい所。さあ、帰りますよ、ジェス」
息子の答えなど聞かない。一方的に叱り続ける皇后。ってか、この母親も厨房を「卑しい」って言うのかよ。
おそらくだけど、ジェスの周りの連中は、膳夫司を汚い場所、膳夫を卑しい身分の者と普段からバカにしているだろう。身分の高い人は、料理はおろか、自分が飲む茶すら淹れたりしないから。ルーシュンは、自分のことは自分でするけど、基本、身分ある人は衣に袖を通すことすら誰かにやってもらう。だから、膳夫だけが卑しいんじゃなく、働かねばならぬ者はすべて卑しいって認識なんだろう。ムカつくけど。
「――ジェス」
そして、自分の息子にまで居丈高。すっげえムカつくけど――我慢、がまん。オレの立場からは、皇后に向かってどうこう言うことは出来ない。ずっと頭を下げてるしかない。
ジェスは、叱られて萎縮しちまったのか、一歩も動かない。独楽を抱えてジッとうつむいたままだ。
すると、皇后が軽く鼻で息を吐いて、近くにいた年配の侍女に目で指示を出す。一つ頭を下げて厨房に入ってきた侍女たち。ジェスを取り囲み、ここから出ていくことを促すと――え?
ポイッと投げ捨てられた独楽。それが弧を描き、火のついた竈のなかに……。
「――――――ッ!」
とっさに伸ばした手。でも間に合わず火のなかにボトッと落ちた独楽。
「クソッ! って、ゥアチッ!」
「リュカ!」
ジェスが叫ぶ。
「だ、大丈夫。独楽は無事」
竈のなかに手を突っ込んで取り戻した独楽。まだ調理前の熾火だったのと、すぐに取り出したから、独楽に火はついてない。熱かったけど。手の中の独楽ごと、フーフーと息で冷ます。真っ赤になったオレの手。火傷しちまったかな。手、痛いし。
それでも、強引に連れ去られてくジェスに「大丈夫だ」と笑いかける。本当はすぐにでも冷たい水に手を浸したいところだけど、そうするとアイツが心配するから、笑って平気なふりをしてジェスを見送る。
「だ、大丈夫ですかい」
嵐のような皇后たちが去ってからしばらくして、膳夫が声をかけてきた。
「大丈夫じゃねえ。イテテテ……」
「こ、これをっ!」
火傷に慣れているのか。膳夫の一人が盥に水を汲んできてくれた。独楽ごとその盥に手を突っ込む。あ~、水が冷たくて気持ちい~。
しばらくこのまま冷やして、痛みが治まったら、軟膏を塗って。確か、行李のなかに入れてあったよな。
あ、それより独楽だ、独楽。よし。どこも焦げてない。ついた煤を指でこすると、元の木地が見えた。火にそこまで勢いがなかったことが幸いしたな。すぐ取り出したし。
オレの手も火傷はしたけど、問題なく動くし。あー、でも衣の袖焦がしちまったな。煤がついちゃったし。オッサン、怒るかなあ。面倒だなあ。
「――リュカ!」
へ?
「皇子? どうしてここに」
厨房に飛び込んできたのは、ルーシュン皇子。その後ろにはオレの行李を持ったオッサンと膳夫。あ、オレが大変だってことで呼びに行ったのか。
「大丈夫だって。こうして冷やしておけば問題ないし。独楽だって無事だぜ?」
「バカッ!」
叩きつけるような皇子の声。
おい、バカってなんだよ。バカって。
「そんな火傷を負ってまで独楽だと? バカだバカだと思っていたが、そこまでバカだと思わなかったぞ」
「うるせえな。この独楽だって大事だろうが」
バカバカ言われて、口がゆがむ。
「この独楽はなあ、ジェスが楽しそうに練習していた独楽なんだぞ? お前と勝負をするんだって、負けないぞって。それに何より、兄ちゃんであるお前が贈った大切な独楽じゃねえか」
言葉をかわすことも、一緒にいることもない兄弟。その兄弟をつないだのがこの独楽だ。
「それを燃やされてたまるかってんだ」
「――リュカ」
皇后のあの勢いじゃ、二度とジェスはここに遊びにこれないかもしれない。それでも、この独楽は失くしたくない。
「だからって、竈に手を突っ込むのはいかがなものかと思いますよ、リュカ」
ドスンと行李を机の上におろしたオッサン。あ、結構怒ってる感じか?
「熾火だったし、いけるかなって……」
アハハハハ。
あの時は無我夢中で、火勢なんて気にしてなかったけど。思えばかなり危ないことをしたんじゃねえか、オレ。
「『いけるかな』じゃありませんよ、まったく」
言いながら、オッサンが行李を開けた。
「薬を貸せ。僕がやる」
へ? 皇子が?
驚いたけど、中から火傷用の軟膏を出してもらうと、素直に手当も頼んだ。
とっさに独楽を掴んだのは利き手である右。自分で軟膏を塗るのは難しい。盥から手を出して、痛みが引いたことを確認すると、皇子に軟膏を塗ってもらった。
オレの右手全体に、黙々とベッタリ軟膏を塗り込んでいく皇子。
――どうしてここまで。
かすかに聞こえた声。
その声に息を吐き出すと、目の前にあった皇子の頭を撫でるように軽く叩いた。
「は、母上……」
突然現れた、ここに似つかわしくない、きらびやかな女性。その付き従う人の多さ、豪華すぎる衣装、そしてなにより、厳しすぎる声色に、独楽を持ったままのジェスが、ビクンと体を震わせた。
ジェスだけじゃない。膳夫たちは硬い土の床に額をこすりつけるように頭を下げて恐縮しきり。もちろん、オレだって――ジェスの母上って言ったら皇后様じゃねえか! ってことで膳夫たちほどじゃねえけど、女性らしく腰をかがめて頭を下げる。
「何をしているのか、訊いているのです、ジェス」
答えない息子に、皇后が一層低い声で訊ねた。
「ご、ごめんなさ……」
「謝罪は結構」
ジェスの言葉を皇后がピシャリと遮った。うわ、容赦ねえ。
「アナタはこの国の将来を担う大切な皇子なのですよ。このような場所に通い詰めるよりほかに、もっとやるべきことがあるでしょう」
正論。
正論かもしれねえけど、うつむいて唇を噛んだジェスを見てると、切なくなってくる。
「このような卑しい所。さあ、帰りますよ、ジェス」
息子の答えなど聞かない。一方的に叱り続ける皇后。ってか、この母親も厨房を「卑しい」って言うのかよ。
おそらくだけど、ジェスの周りの連中は、膳夫司を汚い場所、膳夫を卑しい身分の者と普段からバカにしているだろう。身分の高い人は、料理はおろか、自分が飲む茶すら淹れたりしないから。ルーシュンは、自分のことは自分でするけど、基本、身分ある人は衣に袖を通すことすら誰かにやってもらう。だから、膳夫だけが卑しいんじゃなく、働かねばならぬ者はすべて卑しいって認識なんだろう。ムカつくけど。
「――ジェス」
そして、自分の息子にまで居丈高。すっげえムカつくけど――我慢、がまん。オレの立場からは、皇后に向かってどうこう言うことは出来ない。ずっと頭を下げてるしかない。
ジェスは、叱られて萎縮しちまったのか、一歩も動かない。独楽を抱えてジッとうつむいたままだ。
すると、皇后が軽く鼻で息を吐いて、近くにいた年配の侍女に目で指示を出す。一つ頭を下げて厨房に入ってきた侍女たち。ジェスを取り囲み、ここから出ていくことを促すと――え?
ポイッと投げ捨てられた独楽。それが弧を描き、火のついた竈のなかに……。
「――――――ッ!」
とっさに伸ばした手。でも間に合わず火のなかにボトッと落ちた独楽。
「クソッ! って、ゥアチッ!」
「リュカ!」
ジェスが叫ぶ。
「だ、大丈夫。独楽は無事」
竈のなかに手を突っ込んで取り戻した独楽。まだ調理前の熾火だったのと、すぐに取り出したから、独楽に火はついてない。熱かったけど。手の中の独楽ごと、フーフーと息で冷ます。真っ赤になったオレの手。火傷しちまったかな。手、痛いし。
それでも、強引に連れ去られてくジェスに「大丈夫だ」と笑いかける。本当はすぐにでも冷たい水に手を浸したいところだけど、そうするとアイツが心配するから、笑って平気なふりをしてジェスを見送る。
「だ、大丈夫ですかい」
嵐のような皇后たちが去ってからしばらくして、膳夫が声をかけてきた。
「大丈夫じゃねえ。イテテテ……」
「こ、これをっ!」
火傷に慣れているのか。膳夫の一人が盥に水を汲んできてくれた。独楽ごとその盥に手を突っ込む。あ~、水が冷たくて気持ちい~。
しばらくこのまま冷やして、痛みが治まったら、軟膏を塗って。確か、行李のなかに入れてあったよな。
あ、それより独楽だ、独楽。よし。どこも焦げてない。ついた煤を指でこすると、元の木地が見えた。火にそこまで勢いがなかったことが幸いしたな。すぐ取り出したし。
オレの手も火傷はしたけど、問題なく動くし。あー、でも衣の袖焦がしちまったな。煤がついちゃったし。オッサン、怒るかなあ。面倒だなあ。
「――リュカ!」
へ?
「皇子? どうしてここに」
厨房に飛び込んできたのは、ルーシュン皇子。その後ろにはオレの行李を持ったオッサンと膳夫。あ、オレが大変だってことで呼びに行ったのか。
「大丈夫だって。こうして冷やしておけば問題ないし。独楽だって無事だぜ?」
「バカッ!」
叩きつけるような皇子の声。
おい、バカってなんだよ。バカって。
「そんな火傷を負ってまで独楽だと? バカだバカだと思っていたが、そこまでバカだと思わなかったぞ」
「うるせえな。この独楽だって大事だろうが」
バカバカ言われて、口がゆがむ。
「この独楽はなあ、ジェスが楽しそうに練習していた独楽なんだぞ? お前と勝負をするんだって、負けないぞって。それに何より、兄ちゃんであるお前が贈った大切な独楽じゃねえか」
言葉をかわすことも、一緒にいることもない兄弟。その兄弟をつないだのがこの独楽だ。
「それを燃やされてたまるかってんだ」
「――リュカ」
皇后のあの勢いじゃ、二度とジェスはここに遊びにこれないかもしれない。それでも、この独楽は失くしたくない。
「だからって、竈に手を突っ込むのはいかがなものかと思いますよ、リュカ」
ドスンと行李を机の上におろしたオッサン。あ、結構怒ってる感じか?
「熾火だったし、いけるかなって……」
アハハハハ。
あの時は無我夢中で、火勢なんて気にしてなかったけど。思えばかなり危ないことをしたんじゃねえか、オレ。
「『いけるかな』じゃありませんよ、まったく」
言いながら、オッサンが行李を開けた。
「薬を貸せ。僕がやる」
へ? 皇子が?
驚いたけど、中から火傷用の軟膏を出してもらうと、素直に手当も頼んだ。
とっさに独楽を掴んだのは利き手である右。自分で軟膏を塗るのは難しい。盥から手を出して、痛みが引いたことを確認すると、皇子に軟膏を塗ってもらった。
オレの右手全体に、黙々とベッタリ軟膏を塗り込んでいく皇子。
――どうしてここまで。
かすかに聞こえた声。
その声に息を吐き出すと、目の前にあった皇子の頭を撫でるように軽く叩いた。
0
お気に入りに追加
32
あなたにおすすめの小説

【完結】泡の消えゆく、その先に。〜人魚の恋のはなし〜
N2O
BL
人間×人魚の、恋の話。
表紙絵
⇨ 元素🪦 様 X(@10loveeeyy)
※独自設定です
※◎は視点が変わります(俯瞰、攻め視点etc)

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

初恋はおしまい
佐治尚実
BL
高校生の朝好にとって卒業までの二年間は奇跡に満ちていた。クラスで目立たず、一人の時間を大事にする日々。そんな朝好に、クラスの頂点に君臨する修司の視線が絡んでくるのが不思議でならなかった。人気者の彼の一方的で執拗な気配に朝好の気持ちは高ぶり、ついには卒業式の日に修司を呼び止める所までいく。それも修司に無神経な言葉をぶつけられてショックを受ける。彼への思いを知った朝好は成人式で修司との再会を望んだ。
高校時代の初恋をこじらせた二人が、成人式で再会する話です。珍しく攻めがツンツンしています。
※以前投稿した『初恋はおしまい』を大幅に加筆修正して再投稿しました。現在非公開の『初恋はおしまい』にお気に入りや♡をくださりありがとうございました!こちらを読んでいただけると幸いです。
今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。

虐げられている魔術師少年、悪魔召喚に成功したところ国家転覆にも成功する
あかのゆりこ
BL
主人公のグレン・クランストンは天才魔術師だ。ある日、失われた魔術の復活に成功し、悪魔を召喚する。その悪魔は愛と性の悪魔「ドーヴィ」と名乗り、グレンに契約の代償としてまさかの「口づけ」を提示してきた。
領民を守るため、王家に囚われた姉を救うため、グレンは致し方なく自分の唇(もちろん未使用)を差し出すことになる。
***
王家に虐げられて不遇な立場のトラウマ持ち不幸属性主人公がスパダリ系悪魔に溺愛されて幸せになるコメディの皮を被ったそこそこシリアスなお話です。
・ハピエン
・CP左右固定(リバありません)
・三角関係及び当て馬キャラなし(相手違いありません)
です。
べろちゅーすらないキスだけの健全ピュアピュアなお付き合いをお楽しみください。
***
2024.10.18 第二章開幕にあたり、第一章の2話~3話の間に加筆を行いました。小数点付きの話が追加分ですが、別に読まなくても問題はありません。
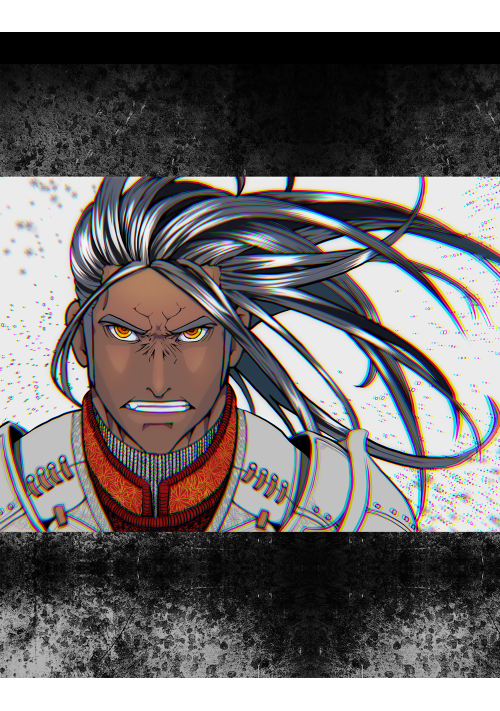
皇帝の寵愛
たろう
BL
※後宮小説もどきです。女の人が出てきます。最近BLだけどサスペンス?時代小説?要素が混じってきているような……?
若き皇帝×平民の少年
無力の皇帝と平民の少年が権力者たちの思惑が渦巻く宮中で幸福な結末を目指すお話。
※別サイトにも投稿してます
※R-15です。

いつかコントローラーを投げ出して
せんぷう
BL
オメガバース。世界で男女以外に、アルファ・ベータ・オメガと性別が枝分かれした世界で新たにもう一つの性が発見された。
世界的にはレアなオメガ、アルファ以上の神に選別されたと言われる特異種。
バランサー。
アルファ、ベータ、オメガになるかを自らの意思で選択でき、バランサーの状態ならどのようなフェロモンですら影響を受けない、むしろ自身のフェロモンにより周囲を調伏できる最強の性別。
これは、バランサーであることを隠した少年の少し不運で不思議な出会いの物語。
裏社会のトップにして最強のアルファ攻め
×
最強種バランサーであることをそれとなく隠して生活する兄弟想いな受け
※オメガバース特殊設定、追加性別有り
.

夢では溺愛騎士、現実ではただのクラスメイト
春音優月
BL
真面目でおとなしい性格の藤村歩夢は、武士と呼ばれているクラスメイトの大谷虎太郎に密かに片想いしている。
クラスではほとんど会話も交わさないのに、なぜか毎晩歩夢の夢に出てくる虎太郎。しかも夢の中での虎太郎は、歩夢を守る騎士で恋人だった。
夢では溺愛騎士、現実ではただのクラスメイト。夢と現実が交錯する片想いの行方は――。
2024.02.23〜02.27
イラスト:かもねさま

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















