13 / 30
三、慈鳥
(三)
しおりを挟む
(これ、どんだけ少ないんだよ……)
室に戻ったオレは、たいして記されてない紙を前に絶句する。
〝皇子の食べられるもの一覧〟
書けと言って書き出させたら、あまりの早さで書き終えて、どんなもんかと読んでみたら……。
(ほとんど白紙じゃねえか)
書くのを面倒くさがったわけじゃないと思う。紙面を埋め尽くすほど書けない。それほど食べられるものが少ないんだ。
幸い、一番必要な米と麦は記されてるからなんとかなるとして。
(魚? 肉? ほとんどダメなもんばっかりだな)
これじゃあ、生きることは維持できても、育つことまでは難しい。でも。
――殿下のお食事ですか? 殿下は、いつもきれいに完食なさっておいでですよ。
帰る途中、訪れた膳夫司で聞いたこと。
毎食、皇子の室に届けられた料理は、すべて器が空になって戻ってくるという。
――殿下は、好き嫌いなさらない、いいお方ですよ。あんなに全部召し上がっていただいてたら、こっちも作りがいがあるってもんですよ。
つまみ食いのしすぎか、太っちょ膳夫司長が、出っ張りすぎてる腹を揺らして笑ってた。
――好き嫌い激しくて面倒なのは、弟皇子のほうでさ。ちょーっとつまんだだけで「いらない」「不味い」で返してくるんだもんな。
――でも、そのおかげで、残り物を食えるんだからいいけどな。
――ちげえねえ。
部下の膳夫たちが笑い合う。
よく食べる兄皇子と、好き嫌いだらけの弟皇子。膳夫司ではそういう認識らしい。
――ですから、姫さまが何を作ろうと、殿下は美味しく召し上がってくださいますよ。
オレが男なら、背中をバンバン叩いてきそうな励まし。
――そうそう。姫の愛情たっぷりですからねえ。殿下もいつにもまして、たくさん召し上がってくださるんじゃないですか?
いや、だからオレ、〝姫〟じゃねえし。
殿下のご寵姫が、愛する殿下に差し上げるため、手ずから料理をお作りあそばされる――。
オレが皇子のために料理をするってことが、さっそく膳夫司伝わっているらしい。〝殿下のご寵姫が気持ちよく料理ができるよう、新たな竈、厨房を用意せよ〟とかなんとか。で、その愛しの姫さまが膳夫司を確認しに来たと。オレが立ち寄った理由をそう勘違いされた。
――愛の力だねえ。
それが膳夫たちの感想。
本気で勘弁してほしい。
「殿下はね、あまりお召しになりませんから。代わりに俺が食べて空にしてるんですよ」
「オッサンが?」
オレが膳夫司で抱えた疑問の正解を、オッサンが教えてくれた。
「食べ残したりして、『体の弱い皇太子』と思われてはいけませんからね。せっかく作ったものを残したら、膳夫たちもかわいそうですし、食材を献上した者の立場もありませんから」
「めんどくせえんだな、皇宮って」
飢えて栄養失調になる庶民と違って、暴飲暴食、贅沢に食べ放題なんだって思ってた。
食べたくなくても食べたようにしなくちゃいけなくて、好き嫌いがあるなんて弱みは誰にも見せられない。
「それが上に立つ者ってことなんですよ。食べたいものを好きなだけ食べることも、食べたくないものを拒否することもできません。好悪の感情だけで動いていたら、下の者が仕事を失ったりして、路頭に迷ってしまいます」
「ふぅん」
だから、皇子が全部平らげたように思わせるため、こっそりオッサンが食べていたのか。
「のわりにはオッサン、腹が出てねえな」
とてもじゃないが、毎回二人分食ってる腹には見えない。
「それはまあ……。あの殿下にお仕えしてますとですねえ……」
軽く腹をさすったオッサン。なるほど。二人分食っても、それが身になる前に胃痛から腹痛になって出て行ってしまうってわけか。それかただの食あたり。食い過ぎによる腹下し。
「それでリュカ姫、殿下のための献立はできそうですか?」
オッサンが話題を変えた。
「んー、まあ。食べられる食材は少ねえけど、なんとかなるだろ。豪華な食事にはなりそうにねえけど」
あれも食べられない、これも食べられないでは、食材をふんだんに使った料理は見込めない。だけど、ちゃんと栄養の摂れる食事を作ることはできる。
「さっきも言ったけど、貧血を治すために、なにも動物の肝ばっかり食べりゃあいいってもんじゃない。他にも豆とか青菜からでも摂ることはできるし。問題ねえよ」
肉がダメなら豆とか卵とか。人参がダメなら南瓜で補う。どれか一つの食材が食べられなくても、別のものが食べられれば問題ない。
「あとは……、そうだな。皇子、茘枝が好きなのか?」
紙面に連ねられた食材のなかで、ひときわそれが目を引いた。心なしか、ちょっとだけ字が大きいような気もする。
「そうですね。茘枝は幼い頃から好まれてますよ」
「贅沢なやつだなぁ」
素直にそう思う。
この国の南方でしか産出しない茘枝。
茘枝は、「枝を離れるや、一日で色が変わり、二日で香りが失せ、三日ですべてが失われてしまう」と言われる果物。赤い鱗のような棘は、鮮度が落ちるとともに、あっという間にシナシナになるらしい。
だから南方で暮らしているか、早馬で届けさせることのできる金持ち、身分ある者しか食べることのできない幻の果物。それを好物って言えるなんて。
(やっぱアイツ、皇子さまなんだな)
好物って言えるものの基準が庶民と違う。
オレなんて名前は知ってるけど、見たこともなければ食ったこともないってのに。
「僕がなんだって?」
室に響く、軽い叩扉の音と声。
「せっかくだから姫と散策したいなって誘いに来たんだけど――何?」
いたずら心満載、にこやかに近づいてきた皇子の顔色が、微妙に変化した。オレが、丸薬を差し出したからだ。
「今日はまずこれを呑め」
「これは?」
「お前の貧血を治す薬。ちゃんとお前用に甘く作ってある」
「僕のために?」
「そうだよ。お前、苦いの、苦手だろ?」
毒を経験している者からしてみれば、自然の苦味も恐怖の対象になるって、じいちゃんから教えてもらったことがある。苦味は毒。普通の自然界にあるような苦味も毒かもしれないって思ってしまうんだってさ。
皇子がその症例に当てはまるのかどうかは知らねえけど、好きなもの、食べられるもののなかに「苦瓜」が入ってないことから、「苦味は嫌い」と判断した。
「僕の……ために」
コロンとその手のひらの上に丸薬を転がしてやると、なぜか、それを眺めながら呟きがくり返された。
「その丸薬を呑み続けるだけで、体調はかなり改善されるはずだ」
とりあえず、立ってるだけで襲ってくる目眩は治まる。オレに胸倉つかまれただけでぶっ倒れるなんてことはなくなる。
「ああ、あと、それ。呑んだら便秘気味になったり、ウンコが黒くなったりするけど、問題ないからな」
「なっ……! ウン……!」
皇子が思いっきり顔をしかめた。
「これも治癒師として説明しとかなきゃいけないことなんだよ。説明ナシに呑ませて、後から『ウンコが出なくなった!』とか『黒くなった! 病気だ!』って騒がれたらたまらないからな」
そうならないように、予め説明しておく。
「だからって、その格好で『ウンコ』はないと思いますよ」
皇子の代わりにオッサンが非難の声を上げた。
まあ、これでも一応オレ、〝姫〟だし? ヒラヒラの格好したヤツの言う言葉じゃないわな、〝ウンコ〟。
でもさ。
「それ呑んで、腹苦しいとかあったら言えよ? 下剤もちゃんと用意してやる。ムリして出そうとすると、今度は痔になるからな」
オレは〝姫〟である前に〝治癒師〟なんだよ。格好どうこう言う前に、治癒師としてちゃんと伝える義務があるんだ。
室に戻ったオレは、たいして記されてない紙を前に絶句する。
〝皇子の食べられるもの一覧〟
書けと言って書き出させたら、あまりの早さで書き終えて、どんなもんかと読んでみたら……。
(ほとんど白紙じゃねえか)
書くのを面倒くさがったわけじゃないと思う。紙面を埋め尽くすほど書けない。それほど食べられるものが少ないんだ。
幸い、一番必要な米と麦は記されてるからなんとかなるとして。
(魚? 肉? ほとんどダメなもんばっかりだな)
これじゃあ、生きることは維持できても、育つことまでは難しい。でも。
――殿下のお食事ですか? 殿下は、いつもきれいに完食なさっておいでですよ。
帰る途中、訪れた膳夫司で聞いたこと。
毎食、皇子の室に届けられた料理は、すべて器が空になって戻ってくるという。
――殿下は、好き嫌いなさらない、いいお方ですよ。あんなに全部召し上がっていただいてたら、こっちも作りがいがあるってもんですよ。
つまみ食いのしすぎか、太っちょ膳夫司長が、出っ張りすぎてる腹を揺らして笑ってた。
――好き嫌い激しくて面倒なのは、弟皇子のほうでさ。ちょーっとつまんだだけで「いらない」「不味い」で返してくるんだもんな。
――でも、そのおかげで、残り物を食えるんだからいいけどな。
――ちげえねえ。
部下の膳夫たちが笑い合う。
よく食べる兄皇子と、好き嫌いだらけの弟皇子。膳夫司ではそういう認識らしい。
――ですから、姫さまが何を作ろうと、殿下は美味しく召し上がってくださいますよ。
オレが男なら、背中をバンバン叩いてきそうな励まし。
――そうそう。姫の愛情たっぷりですからねえ。殿下もいつにもまして、たくさん召し上がってくださるんじゃないですか?
いや、だからオレ、〝姫〟じゃねえし。
殿下のご寵姫が、愛する殿下に差し上げるため、手ずから料理をお作りあそばされる――。
オレが皇子のために料理をするってことが、さっそく膳夫司伝わっているらしい。〝殿下のご寵姫が気持ちよく料理ができるよう、新たな竈、厨房を用意せよ〟とかなんとか。で、その愛しの姫さまが膳夫司を確認しに来たと。オレが立ち寄った理由をそう勘違いされた。
――愛の力だねえ。
それが膳夫たちの感想。
本気で勘弁してほしい。
「殿下はね、あまりお召しになりませんから。代わりに俺が食べて空にしてるんですよ」
「オッサンが?」
オレが膳夫司で抱えた疑問の正解を、オッサンが教えてくれた。
「食べ残したりして、『体の弱い皇太子』と思われてはいけませんからね。せっかく作ったものを残したら、膳夫たちもかわいそうですし、食材を献上した者の立場もありませんから」
「めんどくせえんだな、皇宮って」
飢えて栄養失調になる庶民と違って、暴飲暴食、贅沢に食べ放題なんだって思ってた。
食べたくなくても食べたようにしなくちゃいけなくて、好き嫌いがあるなんて弱みは誰にも見せられない。
「それが上に立つ者ってことなんですよ。食べたいものを好きなだけ食べることも、食べたくないものを拒否することもできません。好悪の感情だけで動いていたら、下の者が仕事を失ったりして、路頭に迷ってしまいます」
「ふぅん」
だから、皇子が全部平らげたように思わせるため、こっそりオッサンが食べていたのか。
「のわりにはオッサン、腹が出てねえな」
とてもじゃないが、毎回二人分食ってる腹には見えない。
「それはまあ……。あの殿下にお仕えしてますとですねえ……」
軽く腹をさすったオッサン。なるほど。二人分食っても、それが身になる前に胃痛から腹痛になって出て行ってしまうってわけか。それかただの食あたり。食い過ぎによる腹下し。
「それでリュカ姫、殿下のための献立はできそうですか?」
オッサンが話題を変えた。
「んー、まあ。食べられる食材は少ねえけど、なんとかなるだろ。豪華な食事にはなりそうにねえけど」
あれも食べられない、これも食べられないでは、食材をふんだんに使った料理は見込めない。だけど、ちゃんと栄養の摂れる食事を作ることはできる。
「さっきも言ったけど、貧血を治すために、なにも動物の肝ばっかり食べりゃあいいってもんじゃない。他にも豆とか青菜からでも摂ることはできるし。問題ねえよ」
肉がダメなら豆とか卵とか。人参がダメなら南瓜で補う。どれか一つの食材が食べられなくても、別のものが食べられれば問題ない。
「あとは……、そうだな。皇子、茘枝が好きなのか?」
紙面に連ねられた食材のなかで、ひときわそれが目を引いた。心なしか、ちょっとだけ字が大きいような気もする。
「そうですね。茘枝は幼い頃から好まれてますよ」
「贅沢なやつだなぁ」
素直にそう思う。
この国の南方でしか産出しない茘枝。
茘枝は、「枝を離れるや、一日で色が変わり、二日で香りが失せ、三日ですべてが失われてしまう」と言われる果物。赤い鱗のような棘は、鮮度が落ちるとともに、あっという間にシナシナになるらしい。
だから南方で暮らしているか、早馬で届けさせることのできる金持ち、身分ある者しか食べることのできない幻の果物。それを好物って言えるなんて。
(やっぱアイツ、皇子さまなんだな)
好物って言えるものの基準が庶民と違う。
オレなんて名前は知ってるけど、見たこともなければ食ったこともないってのに。
「僕がなんだって?」
室に響く、軽い叩扉の音と声。
「せっかくだから姫と散策したいなって誘いに来たんだけど――何?」
いたずら心満載、にこやかに近づいてきた皇子の顔色が、微妙に変化した。オレが、丸薬を差し出したからだ。
「今日はまずこれを呑め」
「これは?」
「お前の貧血を治す薬。ちゃんとお前用に甘く作ってある」
「僕のために?」
「そうだよ。お前、苦いの、苦手だろ?」
毒を経験している者からしてみれば、自然の苦味も恐怖の対象になるって、じいちゃんから教えてもらったことがある。苦味は毒。普通の自然界にあるような苦味も毒かもしれないって思ってしまうんだってさ。
皇子がその症例に当てはまるのかどうかは知らねえけど、好きなもの、食べられるもののなかに「苦瓜」が入ってないことから、「苦味は嫌い」と判断した。
「僕の……ために」
コロンとその手のひらの上に丸薬を転がしてやると、なぜか、それを眺めながら呟きがくり返された。
「その丸薬を呑み続けるだけで、体調はかなり改善されるはずだ」
とりあえず、立ってるだけで襲ってくる目眩は治まる。オレに胸倉つかまれただけでぶっ倒れるなんてことはなくなる。
「ああ、あと、それ。呑んだら便秘気味になったり、ウンコが黒くなったりするけど、問題ないからな」
「なっ……! ウン……!」
皇子が思いっきり顔をしかめた。
「これも治癒師として説明しとかなきゃいけないことなんだよ。説明ナシに呑ませて、後から『ウンコが出なくなった!』とか『黒くなった! 病気だ!』って騒がれたらたまらないからな」
そうならないように、予め説明しておく。
「だからって、その格好で『ウンコ』はないと思いますよ」
皇子の代わりにオッサンが非難の声を上げた。
まあ、これでも一応オレ、〝姫〟だし? ヒラヒラの格好したヤツの言う言葉じゃないわな、〝ウンコ〟。
でもさ。
「それ呑んで、腹苦しいとかあったら言えよ? 下剤もちゃんと用意してやる。ムリして出そうとすると、今度は痔になるからな」
オレは〝姫〟である前に〝治癒師〟なんだよ。格好どうこう言う前に、治癒師としてちゃんと伝える義務があるんだ。
0
お気に入りに追加
31
あなたにおすすめの小説
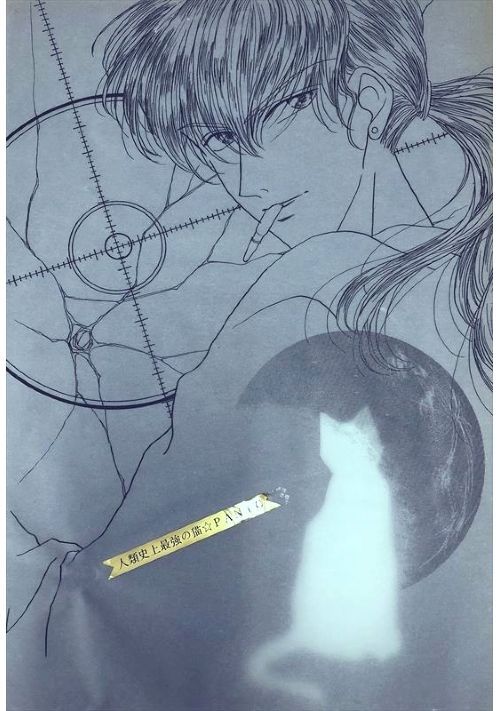
【完結】帝王様は、表でも裏でも有名な飼い猫を溺愛する
綾雅(要らない悪役令嬢1巻重版)
BL
離地暦201年――人類は地球を離れ、宇宙で新たな生活を始め200年近くが経過した。貧困の差が広がる地球を捨て、裕福な人々は宇宙へ進出していく。
狙撃手として裏で名を馳せたルーイは、地球での狙撃の帰りに公安に拘束された。逃走経路を疎かにした結果だ。表では一流モデルとして有名な青年が裏路地で保護される、滅多にない事態に公安は彼を疑うが……。
表も裏もひっくるめてルーイの『飼い主』である権力者リューアは公安からの問い合わせに対し、彼の保護と称した強制連行を指示する。
権力者一族の争いに巻き込まれるルーイと、ひたすらに彼に甘いリューアの愛の行方は?
【重複投稿】エブリスタ、アルファポリス、小説家になろう
【注意】※印は性的表現有ります

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語
紅林
BL
『桜田門学院高等学校』
日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ
しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ
そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である


【完結】運命さんこんにちは、さようなら
ハリネズミ
BL
Ωである神楽 咲(かぐら さき)は『運命』と出会ったが、知らない間に番になっていたのは別の人物、影山 燐(かげやま りん)だった。
とある誤解から思うように優しくできない燐と、番=家族だと考え、家族が欲しかったことから簡単に受け入れてしまったマイペースな咲とのちぐはぐでピュアなラブストーリー。
==========
完結しました。ありがとうございました。

学園と夜の街での鬼ごっこ――標的は白の皇帝――
天海みつき
BL
族の総長と副総長の恋の話。
アルビノの主人公――聖月はかつて黒いキャップを被って目元を隠しつつ、夜の街を駆け喧嘩に明け暮れ、いつしか"皇帝"と呼ばれるように。しかし、ある日突然、姿を晦ました。
その後、街では聖月は死んだという噂が蔓延していた。しかし、彼の族――Nukesは実際に遺体を見ていないと、その捜索を止めていなかった。
「どうしようかなぁ。……そぉだ。俺を見つけて御覧。そしたら捕まってあげる。これはゲームだよ。俺と君たちとの、ね」
学園と夜の街を巻き込んだ、追いかけっこが始まった。
族、学園、などと言っていますが全く知識がないため完全に想像です。何でも許せる方のみご覧下さい。
何とか完結までこぎつけました……!番外編を投稿完了しました。楽しんでいただけたら幸いです。

闘乱世界ユルヴィクス -最弱と最強神のまったり世直し旅!?-
mao
BL
力と才能が絶対的な存在である世界ユルヴィクスに生まれながら、何の力も持たずに生まれた無能者リーヴェ。
無能であるが故に散々な人生を送ってきたリーヴェだったが、ある日、将来を誓い合った婚約者ティラに事故を装い殺されかけてしまう。崖下に落ちたところを不思議な男に拾われたが、その男は「神」を名乗るちょっとヤバそうな男で……?
天才、秀才、凡人、そして無能。
強者が弱者を力でねじ伏せ支配するユルヴィクス。周りをチート化させつつ、世界の在り方を変えるための世直し旅が、今始まる……!?
※一応はバディモノですがBL寄りなので苦手な方はご注意ください。果たして愛は芽生えるのか。
のんびりまったり更新です。カクヨム、なろうでも連載してます。
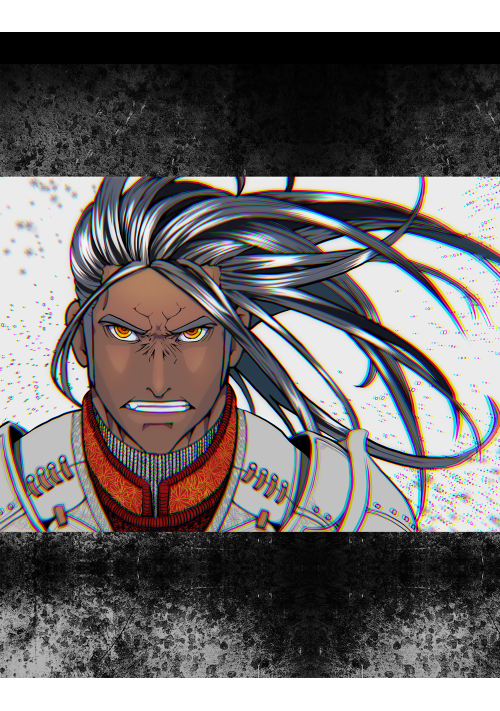
皇帝の寵愛
たろう
BL
※後宮小説もどきです。女の人が出てきます。最近BLだけどサスペンス?時代小説?要素が混じってきているような……?
若き皇帝×平民の少年
無力の皇帝と平民の少年が権力者たちの思惑が渦巻く宮中で幸福な結末を目指すお話。
※別サイトにも投稿してます
※R-15です。

好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















