11 / 30
三、慈鳥
(一)
しおりを挟む
「じゃあ、さっそくだけど、治療、初めていくからな」
通された皇子の室。そこでオレは腰に手を当て、フンスと背を反らせる。
皇子から指示された女装は解けないままだけど、室のなかという、オッサンと皇子以外に誰もいない空間でなら、素の自分でいていいという許可はもらった。だから、ちょっとぐらい女らしくない言動をとっても、オッサンのゲンコツは落ちてこない。
「貧血も栄養失調も、一番いいのは『食べること』だけど、今回はそれ以外の方法も併用することにする」
「それ以外の方法?」
皇子が首をかしげた。
「長いこと少食だった体は、ドカッと飯を出して『食え!』って言っても受けつけないからな。食事は少しずつ量を増やすとして、それまでの間は薬も使って体を支えていくんだよ」
「へえ……」
大人しく座ったままオレの話を聞く皇子。もっと嫌がるかと思ったけど、意外と素直に治療を受け入れてる。オレがこうして訪れてるのも、皇子から来いって言われたからなんだけど。――なんか悪いことの前触れか? ちょっとだけ警戒。
「基本は食事とその扶けとなる薬だが……。あとは体を動かすことも追加してやる」
「体を動かす?」
「そうだよ。お前、そのままじゃヒョロヒョロの真っ白じゃん。だから、少し外に出て体を動かす。体を動かせばその分筋肉がつく。そして腹が減る。腹が減りゃあ飯も多く食べられる。そういう良い循環ができるんだよ」
「なるほど」
そばで聞いていたオッサンが頷いた。
「だけどまあ、体を動かすったって、そんな急には無理だろうから、最初はあの庭園をそぞろ歩く程度だな」
栄養の乏しい、今のままでは走ったりなんてできない。すぐに体力が尽きてぶっ倒れる。
「まずは、そうやってゆっくりでいいから体を動かして、お前の好きなものからでいいからちゃんと食事を取って。そこから少しずつ前へ進んでいく。いいな」
「その庭園の散歩は、きみもついてくるのか?」
「当たり前だろ? オレは治癒師なんだぜ? 患者の体調を見ながら補助するのはオレの役目だよ」
「……なるほど」
「ああ、それと。お前、ちゃんと寝ろよ」
「寝る?」
「お前、しっかり眠れてねえだろ」
顔色が青白いのは、栄養不足、運動不足だけじゃない。寝不足も加わって、せっかくのきれいな顔なのに、目の下がほんのり黒っぽくなってる。
「ちゃんと動いて、ちゃんと食べれば、グッスリ眠れるようになる。グッスリ眠れたら体力も回復して、体を動かしやすくなる。そういう循環の輪を作れば、自然と体は持ち直す」
「薬で治すのではないのか?」
「薬はあくまで補助。人の体ってのは意外と強い。放って置いてもひとりでに良くなっていくこともできれば、悪くなっていくこともできる。薬ってのは、その悪くなってく輪にハマった体を支え、良い方へすすむ流れに乗せ替えるキッカケを作るだけなんだ」
「そういうものなのか?」
「そういうもんなんだ」
なんでもかんでも薬でなんとかしようってのは間違ってる。そりゃあ、どうしようもないぐらい弱ってるとかなら薬に頼ることもあるけど、そうじゃない場合、自然の、体の持つ治癒力を引き出す方がいい。薬でムリに引き出された健康じゃなく、自分で作り出した健康だから、後々まで継続して健康でいられる。
この間の蕃茄事件。あの時、オレが呑んだ丸薬も、吐き気を抑えて消化を促進してくれるけど、最終的に体のなかのもん全部排泄するのは体の仕事。薬じゃない。
「薬はすべてを治すものではないのだな」
「あー、その誤解、マジでやめて欲しい」
皇子の言葉に、思わずボリボリと頭を掻く。
「たまにいるんだよな。風邪ひいたって患者に薬だすとさ、『これを呑めば明日には治るのか』とか言ってくるヤツ。薬で病は治らねえ。薬は症状を抑えて体力を回復させる程度の力しか持ち合わせてねえんだよ。ケガの薬も同じだぞ。あれは傷口を清めるだけで、最終的に治癒を行うのは患者の体なんだよ」
それをなにか勘違いしてるから、「明日には……」的な言葉が出てくる。そんな万能薬があるなら、治すまで患者に寄り添い続ける〝治癒師〟なんて職業は、とっくの昔に廃れてる。どんな病気だってケガだって治って、誰も死んだりしねえ。
「とりあえず、お前のその貧血を改善するために薬も出すけど、本当は食事で治してほしいんだよな」
「食事で?」
「ああ。だけどお前、どうせ牛の肝とか食べないだろ?」
牛だけじゃない。他にも鳥の肝とか豚の肝とか。血の味がするとかなんとかで、苦手とする人も多い肉。実のところ、オレもあんまり好きじゃない。
「まあ、好きではないな」
「だから薬でそのあたりを補うんだよ」
獣の肝が苦手なら、豆とか青菜を取るって手もあるけど、ここは手っ取り早く薬を使う。
「それと、もし眠れねえってのなら、薬を処方する。これも、循環を作り上げる基礎、体を今より悪くしない、回復に向かうために必要だからな」
「ふぅん」
「軽い運動と、睡眠。それから少しずつでいいから食べられるものを増やす。いい流れに乗るまでは、薬も使う。それがオレの治療方針だけど……、なんか質問あるか?」
「いや、そうだな……」
皇子が軽く思案した。
「眠りに関しては薬はいらない。今夜からでもグッスリ眠れるはずだ」
「そうなのか?」
寝不足は、ただの夜更かしだったとか?
「ああ。姫が添い寝をしてくれたらよく眠れるに違いない」
「へ?」
「『患者の体調を見ながら補助するのが役目』なんだろう?」
「いや、それは……」
「それに姫は僕の閨事指南役なんだ。一緒に寝るのは当たり前のことじゃないか」
「なっ……!」
慌てるオレに、青い目が、いたずらっぽくニッと細められた。
「ともに庭を散策し、ともに食し、ともに寝る。日に体を治しつつ、夜に面倒な閨事も学ぶ。一石二鳥じゃないか」
「んなわけあるかっ! オレ、男だぞ!」
遊ばれてるってわかってるけど、反論せずにはいられない。
「別にどっちだっていいじゃないか。男だろうが女だろうが、穴は穴。気持ちよくなれるかどうか、試してみるか?」
「絶対嫌だ! 断る!」
カタンと、椅子から立ち上がった皇子。青い目でオレを捉えながら近づいてくる。その間近に迫ってくる姿に、思わずキュッとなった尻を押さえて後ずさる。
「殿下。リュカ姫。そんなふうに思われるまで仲良くなられるとは……」
室の片隅にいたオッサンが感慨深そうに頷いて、目元を拭う仕草をする。――って。
「泣いてねえで助けろ、オッサン!」
オレのケツ穴、最大の危機!
通された皇子の室。そこでオレは腰に手を当て、フンスと背を反らせる。
皇子から指示された女装は解けないままだけど、室のなかという、オッサンと皇子以外に誰もいない空間でなら、素の自分でいていいという許可はもらった。だから、ちょっとぐらい女らしくない言動をとっても、オッサンのゲンコツは落ちてこない。
「貧血も栄養失調も、一番いいのは『食べること』だけど、今回はそれ以外の方法も併用することにする」
「それ以外の方法?」
皇子が首をかしげた。
「長いこと少食だった体は、ドカッと飯を出して『食え!』って言っても受けつけないからな。食事は少しずつ量を増やすとして、それまでの間は薬も使って体を支えていくんだよ」
「へえ……」
大人しく座ったままオレの話を聞く皇子。もっと嫌がるかと思ったけど、意外と素直に治療を受け入れてる。オレがこうして訪れてるのも、皇子から来いって言われたからなんだけど。――なんか悪いことの前触れか? ちょっとだけ警戒。
「基本は食事とその扶けとなる薬だが……。あとは体を動かすことも追加してやる」
「体を動かす?」
「そうだよ。お前、そのままじゃヒョロヒョロの真っ白じゃん。だから、少し外に出て体を動かす。体を動かせばその分筋肉がつく。そして腹が減る。腹が減りゃあ飯も多く食べられる。そういう良い循環ができるんだよ」
「なるほど」
そばで聞いていたオッサンが頷いた。
「だけどまあ、体を動かすったって、そんな急には無理だろうから、最初はあの庭園をそぞろ歩く程度だな」
栄養の乏しい、今のままでは走ったりなんてできない。すぐに体力が尽きてぶっ倒れる。
「まずは、そうやってゆっくりでいいから体を動かして、お前の好きなものからでいいからちゃんと食事を取って。そこから少しずつ前へ進んでいく。いいな」
「その庭園の散歩は、きみもついてくるのか?」
「当たり前だろ? オレは治癒師なんだぜ? 患者の体調を見ながら補助するのはオレの役目だよ」
「……なるほど」
「ああ、それと。お前、ちゃんと寝ろよ」
「寝る?」
「お前、しっかり眠れてねえだろ」
顔色が青白いのは、栄養不足、運動不足だけじゃない。寝不足も加わって、せっかくのきれいな顔なのに、目の下がほんのり黒っぽくなってる。
「ちゃんと動いて、ちゃんと食べれば、グッスリ眠れるようになる。グッスリ眠れたら体力も回復して、体を動かしやすくなる。そういう循環の輪を作れば、自然と体は持ち直す」
「薬で治すのではないのか?」
「薬はあくまで補助。人の体ってのは意外と強い。放って置いてもひとりでに良くなっていくこともできれば、悪くなっていくこともできる。薬ってのは、その悪くなってく輪にハマった体を支え、良い方へすすむ流れに乗せ替えるキッカケを作るだけなんだ」
「そういうものなのか?」
「そういうもんなんだ」
なんでもかんでも薬でなんとかしようってのは間違ってる。そりゃあ、どうしようもないぐらい弱ってるとかなら薬に頼ることもあるけど、そうじゃない場合、自然の、体の持つ治癒力を引き出す方がいい。薬でムリに引き出された健康じゃなく、自分で作り出した健康だから、後々まで継続して健康でいられる。
この間の蕃茄事件。あの時、オレが呑んだ丸薬も、吐き気を抑えて消化を促進してくれるけど、最終的に体のなかのもん全部排泄するのは体の仕事。薬じゃない。
「薬はすべてを治すものではないのだな」
「あー、その誤解、マジでやめて欲しい」
皇子の言葉に、思わずボリボリと頭を掻く。
「たまにいるんだよな。風邪ひいたって患者に薬だすとさ、『これを呑めば明日には治るのか』とか言ってくるヤツ。薬で病は治らねえ。薬は症状を抑えて体力を回復させる程度の力しか持ち合わせてねえんだよ。ケガの薬も同じだぞ。あれは傷口を清めるだけで、最終的に治癒を行うのは患者の体なんだよ」
それをなにか勘違いしてるから、「明日には……」的な言葉が出てくる。そんな万能薬があるなら、治すまで患者に寄り添い続ける〝治癒師〟なんて職業は、とっくの昔に廃れてる。どんな病気だってケガだって治って、誰も死んだりしねえ。
「とりあえず、お前のその貧血を改善するために薬も出すけど、本当は食事で治してほしいんだよな」
「食事で?」
「ああ。だけどお前、どうせ牛の肝とか食べないだろ?」
牛だけじゃない。他にも鳥の肝とか豚の肝とか。血の味がするとかなんとかで、苦手とする人も多い肉。実のところ、オレもあんまり好きじゃない。
「まあ、好きではないな」
「だから薬でそのあたりを補うんだよ」
獣の肝が苦手なら、豆とか青菜を取るって手もあるけど、ここは手っ取り早く薬を使う。
「それと、もし眠れねえってのなら、薬を処方する。これも、循環を作り上げる基礎、体を今より悪くしない、回復に向かうために必要だからな」
「ふぅん」
「軽い運動と、睡眠。それから少しずつでいいから食べられるものを増やす。いい流れに乗るまでは、薬も使う。それがオレの治療方針だけど……、なんか質問あるか?」
「いや、そうだな……」
皇子が軽く思案した。
「眠りに関しては薬はいらない。今夜からでもグッスリ眠れるはずだ」
「そうなのか?」
寝不足は、ただの夜更かしだったとか?
「ああ。姫が添い寝をしてくれたらよく眠れるに違いない」
「へ?」
「『患者の体調を見ながら補助するのが役目』なんだろう?」
「いや、それは……」
「それに姫は僕の閨事指南役なんだ。一緒に寝るのは当たり前のことじゃないか」
「なっ……!」
慌てるオレに、青い目が、いたずらっぽくニッと細められた。
「ともに庭を散策し、ともに食し、ともに寝る。日に体を治しつつ、夜に面倒な閨事も学ぶ。一石二鳥じゃないか」
「んなわけあるかっ! オレ、男だぞ!」
遊ばれてるってわかってるけど、反論せずにはいられない。
「別にどっちだっていいじゃないか。男だろうが女だろうが、穴は穴。気持ちよくなれるかどうか、試してみるか?」
「絶対嫌だ! 断る!」
カタンと、椅子から立ち上がった皇子。青い目でオレを捉えながら近づいてくる。その間近に迫ってくる姿に、思わずキュッとなった尻を押さえて後ずさる。
「殿下。リュカ姫。そんなふうに思われるまで仲良くなられるとは……」
室の片隅にいたオッサンが感慨深そうに頷いて、目元を拭う仕草をする。――って。
「泣いてねえで助けろ、オッサン!」
オレのケツ穴、最大の危機!
0
お気に入りに追加
31
あなたにおすすめの小説

いとしの生徒会長さま
もりひろ
BL
大好きな親友と楽しい高校生活を送るため、急きょアメリカから帰国した俺だけど、編入した学園は、とんでもなく変わっていた……!
しかも、生徒会長になれとか言われるし。冗談じゃねえっつの!

夢では溺愛騎士、現実ではただのクラスメイト
春音優月
BL
真面目でおとなしい性格の藤村歩夢は、武士と呼ばれているクラスメイトの大谷虎太郎に密かに片想いしている。
クラスではほとんど会話も交わさないのに、なぜか毎晩歩夢の夢に出てくる虎太郎。しかも夢の中での虎太郎は、歩夢を守る騎士で恋人だった。
夢では溺愛騎士、現実ではただのクラスメイト。夢と現実が交錯する片想いの行方は――。
2024.02.23〜02.27
イラスト:かもねさま

なり代わり貴妃は皇弟の溺愛から逃げられません
めがねあざらし
BL
貴妃・蘇璃月が後宮から忽然と姿を消した。
家門の名誉を守るため、璃月の双子の弟・煌星は、彼女の身代わりとして後宮へ送り込まれる。
しかし、偽りの貴妃として過ごすにはあまりにも危険が多すぎた。
調香師としての鋭い嗅覚を武器に、後宮に渦巻く陰謀を暴き、皇帝・景耀を狙う者を探り出せ――。
だが、皇帝の影に潜む男・景翊の真意は未だ知れず。
煌星は龍の寝所で生き延びることができるのか、それとも――!?
///////////////////////////////
※以前に掲載していた「成り代わり貴妃は龍を守る香」を加筆修正したものです。
///////////////////////////////

【完結】雨降らしは、腕の中。
N2O
BL
獣人の竜騎士 × 特殊な力を持つ青年
Special thanks
illustration by meadow(@into_ml79)
※素人作品、ご都合主義です。温かな目でご覧ください。

イケメン俳優は万年モブ役者の鬼門です
はねビト
BL
演技力には自信があるけれど、地味な役者の羽月眞也は、2年前に共演して以来、大人気イケメン俳優になった東城湊斗に懐かれていた。
自分にはない『華』のある東城に対するコンプレックスを抱えるものの、どうにも東城からのお願いには弱くて……。
ワンコ系年下イケメン俳優×地味顔モブ俳優の芸能人BL。
外伝完結、続編連載中です。
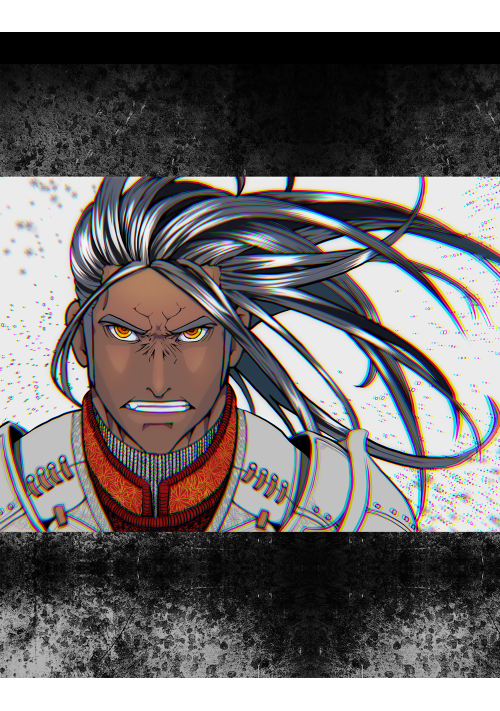
皇帝の寵愛
たろう
BL
※後宮小説もどきです。女の人が出てきます。最近BLだけどサスペンス?時代小説?要素が混じってきているような……?
若き皇帝×平民の少年
無力の皇帝と平民の少年が権力者たちの思惑が渦巻く宮中で幸福な結末を目指すお話。
※別サイトにも投稿してます
※R-15です。

出戻り聖女はもう泣かない
たかせまこと
BL
西の森のとば口に住むジュタは、元聖女。
男だけど元聖女。
一人で静かに暮らしているジュタに、王宮からの使いが告げた。
「王が正室を迎えるので、言祝ぎをお願いしたい」
出戻りアンソロジー参加作品に加筆修正したものです。
ムーンライト・エブリスタにも掲載しています。
表紙絵:CK2さま

虐げられている魔術師少年、悪魔召喚に成功したところ国家転覆にも成功する
あかのゆりこ
BL
主人公のグレン・クランストンは天才魔術師だ。ある日、失われた魔術の復活に成功し、悪魔を召喚する。その悪魔は愛と性の悪魔「ドーヴィ」と名乗り、グレンに契約の代償としてまさかの「口づけ」を提示してきた。
領民を守るため、王家に囚われた姉を救うため、グレンは致し方なく自分の唇(もちろん未使用)を差し出すことになる。
***
王家に虐げられて不遇な立場のトラウマ持ち不幸属性主人公がスパダリ系悪魔に溺愛されて幸せになるコメディの皮を被ったそこそこシリアスなお話です。
・ハピエン
・CP左右固定(リバありません)
・三角関係及び当て馬キャラなし(相手違いありません)
です。
べろちゅーすらないキスだけの健全ピュアピュアなお付き合いをお楽しみください。
***
2024.10.18 第二章開幕にあたり、第一章の2話~3話の間に加筆を行いました。小数点付きの話が追加分ですが、別に読まなくても問題はありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















