1 / 30
一、碧鳥
(一)
しおりを挟む
キレイだなって思った。
単純に。そして純粋に、キレイだって思った。
それを「キレイ」以外の言葉で表せるほどオレは言葉を知らないし、知っていたとしても「キレイ」以外の言葉で表せないと思った。
知り合いのオッサンに連れてこられた皇宮。
荘厳なたたずまい。圧倒されそうなほど大きな建物。案内してくれてるオッサンがいなければ、すぐに迷子になりそうなほどデカくて広い。かくれんぼなんてしたら、一生見つけてもらえない。そんな気がする。
それほど巨大で広大な皇宮。
何度もなんども回廊を曲がって、いくつもいくつも建物を過ぎた先にそれはあった。
明るい日差しを浴びて緑を濃くした庭園。
終りが見えないほど大きな庭なのに、枯れ葉一つ落ちてない。どこまでも色とりどりの花が咲き乱れ、満開の美しさを競い合っている。普段、街の狭い路地や、扱う地味な色の薬草しか見てないオレからしてみれば、そこは楽園。天上の世界のようにも思えた。鳴いてる鳥の声も軽やかで美しく、カラスの「カア」なんて雑な音は、どこからも聞こえてこない。
(天女がいる……)
庭園もさることながら、それよりオレが「キレイ」だと思ったのは、咲き乱れる藤の下にたたずむ人の姿だった。
とても華奢な体。抜けるように白い肌。日の光に輝くつやのある黒髪。
天女みたいだって思ったけど、よく見ればそれは髪を後頭部で結い上げた少年だった。天女のような領巾はなく、袍をまとい、裳のかわりに白袴を穿いていた。線の細い色白の少年。
(うわ……)
きれいなのはその姿だけじゃない。
近づくオレたちに気づいて向けられた視線。その瞳がとんでもなく青くて、透き通ってて。静かな湖面のようで、夏の空のようで。
吸い込まれそうなほどキレイで……。
「誰?」
少年の発した誰何に応えるのを忘れそうで――って。
「お、オレはリュカと言います! 殿下の専属治癒師として、こちらに罷り越しましてございます!」
やっべ。
うっかり口上を忘れるとこだった。あわ食ったせいで、前半部分、「オレ」になっちまったけど。ちょっとカッコつけて「私」って言うんだって決めてたのに。
「殿下と年の近い私なら、殿下もお心安く治療を受けてくださるのではないかと、近侍のセイハ殿の紹介で参りました。年若くはありますが、治癒師である祖父の元で修行しておりましたので、安心してお任せください」
何回も練習しきたとおりに。
そう。
オレがここに来たのは、地上の楽園のような庭を見に来たわけでもなければ、遊びに来たわけでもない。
――俺のお仕えする殿下のお身体を診てあげてほしい。
そう、頼まれたから。
頼んできたのは、じいちゃんの患者、セイハってオッサン。ただの腰痛、胃痛、頭痛持ちのオッサン、万年うだつの上がらない中間管理職だと思ってたら、なんと宮中で働く、皇子付きの近侍だったんだ。
――殿下と同い年で治癒師の男。きみなら、殿下の出した条件にピッタリなんだよ、リュカ。
オッサンの仕える殿下の出したという条件。同い年で治癒師の男。その条件に、オレとじいちゃんはそろって首を傾げた。
――なんで治癒師? 皇宮にはれっきとした医師もいるだろうに。
――それがねえ。殿下が皇宮の医師は嫌だとおっしゃるんだよ。
――なんで男?
――それはねえ。殿下が女はうっとおしいから嫌いだとおっしゃるんだよ。
――なんで十三歳?
――同じ年頃なら、心安くいられると殿下がおっしゃったんだ。高名な治癒師の孫である君なら適任だと思うんだ。
そう言われて悪い気はしない。
実際、オレのじいちゃんは、この国で最高の治癒師だし、そのもとで暮らしてずっとじいちゃんの仕事を見てきたオレも、それなりの腕を持っていると自負している。
皇子殿下の診察、治療。
それがオレの治癒師としての初仕事。
皇子がどんな病を抱えてるのか知らねえけど、じいちゃんから教わった技で、チョチョイっと治してやるぜ。
「殿下、このリュカ殿の腕は、俺が保証いたしますよ」
オレを連れてきた近侍のオッサンがつけ加えた。
「なんたって、俺の万年腰痛、胃痛を治してくださってる高名な治癒師の孫で、最高の弟子ですからね。殿下のお身体の不具合も、あっという間に……」
「――いらない」
は?
「必要ない」
にべもない皇子の言葉。
おい。
それがわざわざここまで足を運んだ者に対する言葉か、コラ。プイッとそむけられた横顔に思わずムッとする。
「殿下、そのようなことをおっしゃらずに。一度、診察だけでもお受けいただいてですねぇ」
メチャクチャ低姿勢なオッサン。取り付く島もない皇子と、カチンときてるオレの、まさしく中間、板挟み。胃痛が再発したのか、無意識にみぞおちに手を当ててる。
「このところ、おかげんもよろしくないようですし。宮廷医がダメならせめて、こちらの治癒師に見ていただくなど……、その……」
皇子にキッと睨まれて、シドロモドロ。オレたちの倍ぐらい生きてそうなのに、カッコ悪。
「セイハ、お前はこんな得体の知れないやつに、僕の体に触れさせようというのか?」
「い、いや、得体は知ってましてですねぇ。私もかかってる高名な治癒師の孫なんですよ。腕のほどは確かだと……」
「お前のその胃痛を完治出来ない程度の腕で高名?」
「いや、これは、その……、クセみたいなものでして……」
オッサンの言い訳を、ハッと皇子が鼻で笑いとばした。
胃痛を治してくれた名治癒師の話をしてて、胃に手を当ててたら、まあその腕を疑われるよな。治ってねえじゃねえか、と。
「僕を診せたいと言うのなら、百歩譲って、その高名な治癒師とやらを連れてこい。胃痛すら治せてない治癒師の孫なんかに診られたくない」
皇子ド正論。
そうだよな。仮に皇子が病気だったとして。診せるなら普通、じいちゃんを頼るよな。オレみたいな若造じゃなくって。
けど、けどさ。
「せっかくここまで出向いてやったのに、何様だ、テメエッ!」
「いや、皇子殿下だけど。この国の第一皇子……」
ブチ切れたオレに、小さくオッサンのツッコミ。
「オッサンの胃痛は、お前が原因だろうがっ!」
オレのじいちゃんは、ちゃんと適切な治癒を行った。行ったけど。
「胃痛の症状は薬で治めることができるけど、その原因を取り除かなきゃ、何度だって再発するんだよ! 胃痛を起こさせてるのは、お前だろうが!」
そう。
オッサンの万年胃痛、頭痛、腰痛の原因はこの皇子だ。
天女のようにキレイだけど、天女と違って辛辣で容赦ない毒皇子。この皇子に仕えてるせいで、オッサンは万年胃痛、頭痛、腰痛持ちになっちまって、じいちゃんのお得意様になってしまっている。
「皇子だなんだって威張りくさるなら、部下の体も守ってやれ!」
言いたいことは言い切った。
フンスッと鼻息を荒らしたオレに、オッサンが「あちゃあ」と、額に手を当て天を見上げた。
あ。今のでオッサン、頭痛も併発した……か?
単純に。そして純粋に、キレイだって思った。
それを「キレイ」以外の言葉で表せるほどオレは言葉を知らないし、知っていたとしても「キレイ」以外の言葉で表せないと思った。
知り合いのオッサンに連れてこられた皇宮。
荘厳なたたずまい。圧倒されそうなほど大きな建物。案内してくれてるオッサンがいなければ、すぐに迷子になりそうなほどデカくて広い。かくれんぼなんてしたら、一生見つけてもらえない。そんな気がする。
それほど巨大で広大な皇宮。
何度もなんども回廊を曲がって、いくつもいくつも建物を過ぎた先にそれはあった。
明るい日差しを浴びて緑を濃くした庭園。
終りが見えないほど大きな庭なのに、枯れ葉一つ落ちてない。どこまでも色とりどりの花が咲き乱れ、満開の美しさを競い合っている。普段、街の狭い路地や、扱う地味な色の薬草しか見てないオレからしてみれば、そこは楽園。天上の世界のようにも思えた。鳴いてる鳥の声も軽やかで美しく、カラスの「カア」なんて雑な音は、どこからも聞こえてこない。
(天女がいる……)
庭園もさることながら、それよりオレが「キレイ」だと思ったのは、咲き乱れる藤の下にたたずむ人の姿だった。
とても華奢な体。抜けるように白い肌。日の光に輝くつやのある黒髪。
天女みたいだって思ったけど、よく見ればそれは髪を後頭部で結い上げた少年だった。天女のような領巾はなく、袍をまとい、裳のかわりに白袴を穿いていた。線の細い色白の少年。
(うわ……)
きれいなのはその姿だけじゃない。
近づくオレたちに気づいて向けられた視線。その瞳がとんでもなく青くて、透き通ってて。静かな湖面のようで、夏の空のようで。
吸い込まれそうなほどキレイで……。
「誰?」
少年の発した誰何に応えるのを忘れそうで――って。
「お、オレはリュカと言います! 殿下の専属治癒師として、こちらに罷り越しましてございます!」
やっべ。
うっかり口上を忘れるとこだった。あわ食ったせいで、前半部分、「オレ」になっちまったけど。ちょっとカッコつけて「私」って言うんだって決めてたのに。
「殿下と年の近い私なら、殿下もお心安く治療を受けてくださるのではないかと、近侍のセイハ殿の紹介で参りました。年若くはありますが、治癒師である祖父の元で修行しておりましたので、安心してお任せください」
何回も練習しきたとおりに。
そう。
オレがここに来たのは、地上の楽園のような庭を見に来たわけでもなければ、遊びに来たわけでもない。
――俺のお仕えする殿下のお身体を診てあげてほしい。
そう、頼まれたから。
頼んできたのは、じいちゃんの患者、セイハってオッサン。ただの腰痛、胃痛、頭痛持ちのオッサン、万年うだつの上がらない中間管理職だと思ってたら、なんと宮中で働く、皇子付きの近侍だったんだ。
――殿下と同い年で治癒師の男。きみなら、殿下の出した条件にピッタリなんだよ、リュカ。
オッサンの仕える殿下の出したという条件。同い年で治癒師の男。その条件に、オレとじいちゃんはそろって首を傾げた。
――なんで治癒師? 皇宮にはれっきとした医師もいるだろうに。
――それがねえ。殿下が皇宮の医師は嫌だとおっしゃるんだよ。
――なんで男?
――それはねえ。殿下が女はうっとおしいから嫌いだとおっしゃるんだよ。
――なんで十三歳?
――同じ年頃なら、心安くいられると殿下がおっしゃったんだ。高名な治癒師の孫である君なら適任だと思うんだ。
そう言われて悪い気はしない。
実際、オレのじいちゃんは、この国で最高の治癒師だし、そのもとで暮らしてずっとじいちゃんの仕事を見てきたオレも、それなりの腕を持っていると自負している。
皇子殿下の診察、治療。
それがオレの治癒師としての初仕事。
皇子がどんな病を抱えてるのか知らねえけど、じいちゃんから教わった技で、チョチョイっと治してやるぜ。
「殿下、このリュカ殿の腕は、俺が保証いたしますよ」
オレを連れてきた近侍のオッサンがつけ加えた。
「なんたって、俺の万年腰痛、胃痛を治してくださってる高名な治癒師の孫で、最高の弟子ですからね。殿下のお身体の不具合も、あっという間に……」
「――いらない」
は?
「必要ない」
にべもない皇子の言葉。
おい。
それがわざわざここまで足を運んだ者に対する言葉か、コラ。プイッとそむけられた横顔に思わずムッとする。
「殿下、そのようなことをおっしゃらずに。一度、診察だけでもお受けいただいてですねぇ」
メチャクチャ低姿勢なオッサン。取り付く島もない皇子と、カチンときてるオレの、まさしく中間、板挟み。胃痛が再発したのか、無意識にみぞおちに手を当ててる。
「このところ、おかげんもよろしくないようですし。宮廷医がダメならせめて、こちらの治癒師に見ていただくなど……、その……」
皇子にキッと睨まれて、シドロモドロ。オレたちの倍ぐらい生きてそうなのに、カッコ悪。
「セイハ、お前はこんな得体の知れないやつに、僕の体に触れさせようというのか?」
「い、いや、得体は知ってましてですねぇ。私もかかってる高名な治癒師の孫なんですよ。腕のほどは確かだと……」
「お前のその胃痛を完治出来ない程度の腕で高名?」
「いや、これは、その……、クセみたいなものでして……」
オッサンの言い訳を、ハッと皇子が鼻で笑いとばした。
胃痛を治してくれた名治癒師の話をしてて、胃に手を当ててたら、まあその腕を疑われるよな。治ってねえじゃねえか、と。
「僕を診せたいと言うのなら、百歩譲って、その高名な治癒師とやらを連れてこい。胃痛すら治せてない治癒師の孫なんかに診られたくない」
皇子ド正論。
そうだよな。仮に皇子が病気だったとして。診せるなら普通、じいちゃんを頼るよな。オレみたいな若造じゃなくって。
けど、けどさ。
「せっかくここまで出向いてやったのに、何様だ、テメエッ!」
「いや、皇子殿下だけど。この国の第一皇子……」
ブチ切れたオレに、小さくオッサンのツッコミ。
「オッサンの胃痛は、お前が原因だろうがっ!」
オレのじいちゃんは、ちゃんと適切な治癒を行った。行ったけど。
「胃痛の症状は薬で治めることができるけど、その原因を取り除かなきゃ、何度だって再発するんだよ! 胃痛を起こさせてるのは、お前だろうが!」
そう。
オッサンの万年胃痛、頭痛、腰痛の原因はこの皇子だ。
天女のようにキレイだけど、天女と違って辛辣で容赦ない毒皇子。この皇子に仕えてるせいで、オッサンは万年胃痛、頭痛、腰痛持ちになっちまって、じいちゃんのお得意様になってしまっている。
「皇子だなんだって威張りくさるなら、部下の体も守ってやれ!」
言いたいことは言い切った。
フンスッと鼻息を荒らしたオレに、オッサンが「あちゃあ」と、額に手を当て天を見上げた。
あ。今のでオッサン、頭痛も併発した……か?
2
お気に入りに追加
31
あなたにおすすめの小説

コネクト
大波小波
BL
オメガの少年・加古 青葉(かこ あおば)は、安藤 智貴(あんどう ともたか)に仕える家事使用人だ。
18歳の誕生日に、青葉は智貴と結ばれることを楽しみにしていた。
だがその当日に、青葉は智貴の客人であるアルファ男性・七浦 芳樹(ななうら よしき)に多額の融資と引き換えに連れ去られてしまう。
一時は芳樹を恨んだ青葉だが、彼の明るく優しい人柄に、ほだされて行く……。
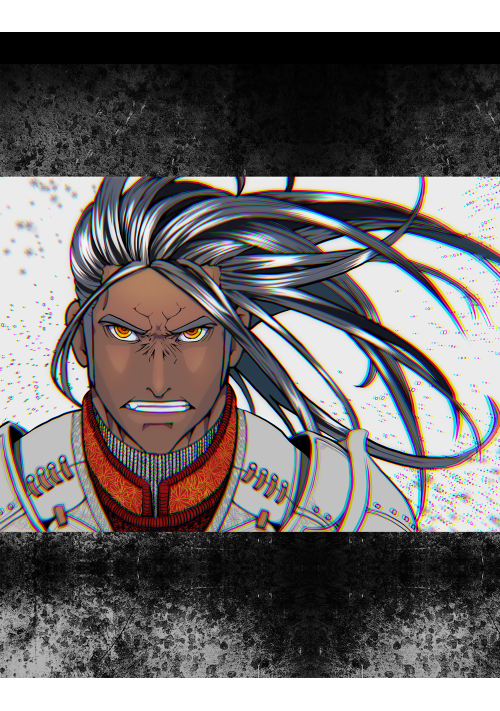
皇帝の寵愛
たろう
BL
※後宮小説もどきです。女の人が出てきます。最近BLだけどサスペンス?時代小説?要素が混じってきているような……?
若き皇帝×平民の少年
無力の皇帝と平民の少年が権力者たちの思惑が渦巻く宮中で幸福な結末を目指すお話。
※別サイトにも投稿してます
※R-15です。

【完結】イケメン騎士が僕に救いを求めてきたので呪いをかけてあげました
及川奈津生
BL
気づいたら十四世紀のフランスに居た。百年戦争の真っ只中、どうやら僕は密偵と疑われているらしい。そんなわけない!と誤解をとこうと思ったら、僕を尋問する騎士が現代にいるはずの恋人にそっくりだった。全3話。
※pome村さんがXで投稿された「#イラストを投げたら文字書きさんが引用rtでssを勝手に添えてくれる」向けに書いたものです。元イラストを表紙に設定しています。投稿元はこちら→https://x.com/pomemura_/status/1792159557269303476?t=pgeU3dApwW0DEeHzsGiHRg&s=19

キンモクセイは夏の記憶とともに
広崎之斗
BL
弟みたいで好きだった年下αに、外堀を埋められてしまい意を決して番になるまでの物語。
小山悠人は大学入学を機に上京し、それから実家には帰っていなかった。
田舎故にΩであることに対する風当たりに我慢できなかったからだ。
そして10年の月日が流れたある日、年下で幼なじみの六條純一が突然悠人の前に現われる。
純一はずっと好きだったと告白し、10年越しの想いを伝える。
しかし純一はαであり、立派に仕事もしていて、なにより見た目だって良い。
「俺になんてもったいない!」
素直になれない年下Ωと、執着系年下αを取り巻く人達との、ハッピーエンドまでの物語。
性描写のある話は【※】をつけていきます。

学園と夜の街での鬼ごっこ――標的は白の皇帝――
天海みつき
BL
族の総長と副総長の恋の話。
アルビノの主人公――聖月はかつて黒いキャップを被って目元を隠しつつ、夜の街を駆け喧嘩に明け暮れ、いつしか"皇帝"と呼ばれるように。しかし、ある日突然、姿を晦ました。
その後、街では聖月は死んだという噂が蔓延していた。しかし、彼の族――Nukesは実際に遺体を見ていないと、その捜索を止めていなかった。
「どうしようかなぁ。……そぉだ。俺を見つけて御覧。そしたら捕まってあげる。これはゲームだよ。俺と君たちとの、ね」
学園と夜の街を巻き込んだ、追いかけっこが始まった。
族、学園、などと言っていますが全く知識がないため完全に想像です。何でも許せる方のみご覧下さい。
何とか完結までこぎつけました……!番外編を投稿完了しました。楽しんでいただけたら幸いです。

好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」

騎士団で一目惚れをした話
菫野
BL
ずっと側にいてくれた美形の幼馴染×主人公
憧れの騎士団に見習いとして入団した主人公は、ある日出会った年上の騎士に一目惚れをしてしまうが妻子がいたようで爆速で失恋する。

君のことなんてもう知らない
ぽぽ
BL
早乙女琥珀は幼馴染の佐伯慶也に毎日のように告白しては振られてしまう。
告白をOKする素振りも見せず、軽く琥珀をあしらう慶也に憤りを覚えていた。
だがある日、琥珀は記憶喪失になってしまい、慶也の記憶を失ってしまう。
今まで自分のことをあしらってきた慶也のことを忘れて、新たな恋を始めようとするが…
「お前なんて知らないから」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















