48 / 63
第2章 《蜘蛛の意図決戦》
第2章20『蝙蝠と詐欺師とミイラと』
しおりを挟む
「はあ、はぁ。やっと、着いた……」
足を止めることなく駆け、ボクはやっとの思いで見覚えのある門の前に辿り着いた。《幽霊館》でお馴染み、そろそろ氷雨邸と呼びたいボクの自宅。今更ながら、その無駄に大きな門に手をかける。そして、力を込めて、
「ユリィ、ただい──」
「───やあ、レイ君じゃないか。こんなに遅くに帰ってきてー、補導対象だよ?」
「ぎゃああああ! 何で、ここに先生が!」
「まるでおいしい展開が待ってるようなセリフを吐きますね、レイ君」
「わーレイ君だー。こんな時間まで寄り道?」
ちょうど二十一時半をまわった大時計。だが、開口一番目に入ったのは、耳に入ったのは、それではなかった。
「た、倒生先生……何故ここに」
ボクの担任教師、倒生ランジ。何故彼がボクの自宅の階段にもたれているのかは、不明である。ボクはゆっくりと辺りを見回し、そして。知っている顔ぶれが、倒生先生だけではないと確認した。白野つくしと木先はるか。この二人も、倒生先生の隣でニヤニヤとボクを見下ろしていたのだ。
「掃除ならこの間、済んだはずだろうが」
と、ボクは小さく呟いた。この絶対プライベート空間に居る部外者三名。いや、同じ部活に所属しているのだから、部内者かもしれないが、赤の他人三匹。さらに、未だに姿を見せてくれないボクの唯一の同居人。
これ、どういう状況だ。ただ、不可解極まりないのは確かで。
「いやいやいや、はるかとつくしはボクの友達枠だから何となく分かる。でも」
「はるかさん、聞きました? お友達ですって」
「聞いた聞いた、今のはデレだね、レイ君の!」
「そこ、静かに!」
「しゅん……」
「何だよ、子犬みたいな顔しても響かないからな!」
「じゃなくて、何です?」
「何で、ボクの担任がここに居るんだ。普通教師が生徒の家に来ることは無い! ありえないー!」
「え、これ家庭訪問だからね? 正当な訪問だよ。そんな、噂の《幽霊館》を見てみたいーっていう、ミーハーな理由じゃありません」
「後半は十分不純な動機だ! それに、家庭訪問っつったって、ここには、保護者なんか……」
「わたしのこと忘れて、ずっーとお喋りして……」
論争に幕を下ろしたのは、聞き覚えのある少女の声で。
「あ。ゆ、ユリィ……」
ボクの同居人、白髪の三つ編みミイラ──ユリィが、そこに現れた。まるで、冷蔵庫の中に放置してあった一ヶ月前の肉でも見るように、つくしたちの影からボクを見下ろしている。このままだと、ボクが3枚に下ろされそうな勢いである。
しゅうしゅうと、白蛇のような三つ編みを全て逆立て、彼女はらしくもなく首を鳴らした。
「あんまり帰りが遅いから、寂しくて不思議部のみんなを呼んじゃったの、夕食にね」
「え、じゃ、ボクの夕飯は……」
あんなに頑張ったのに。シオンさんやらエコトちゃんやら、未知の存在に遭遇しながら情報集めたのに。ボクは、さっきから壊れたラッパみたく鳴っている腹を、きつく抑えた。夕餉抜きは地獄だ。でも、激怒ユリィの仕打ちがその程度で済むなら良いのだが。
「はあ……夕食ならあります。ただし」
「た、ただし?」
鋭い視線を向けられて、ボクはごくりと唾を飲んだ。一体、このボクにどんな拷問が────?
「──残ってるのはわたしの手作りだけなんだけど」
「ひ」
「僕たちは冷凍食品パーティだったもんねー、ツクシちゃん」
「今って本当、レパートリー豊富なんですね。どれも美味しかったです」
「食べるわよね。食べて、くれるのよね、レイ」
彼女の圧に押し負け、ボクはしぶしぶ首を縦に引いたのだった。この日から、ユリィが自分の手料理を武器にし始めたことを、ここに明記しておこう。
そして、今日が冷凍食品記念日になったことも。
◆◆◆
「うぷ、……ごちそ、さま。ユリィ」
「美味しかった?」
「う、うん。まぁ、いつも通りに」
致死量の黒炭を食べきったボクは、目を輝かせるユリィに苦笑いを返した。ああ、生きてることを褒めてほしい。
「はいはい偉い偉い。じゃ、わたし、お皿洗ってくるから」
「ありがと、ユリィ」
ユリィに皿を渡して、ボクも席を立った。まったく、掃除も選択も皿洗いも完璧なクセして、どうして料理だけは苦手なのか。ちなみに、いつもはボクが台所を担当している。
ユリィとつくしよりかは、料理うまいんだぞ、ボク。
「さらに言えば、我の方が料理うまいんだけどねー」
「身辺詐欺教師……。その三ツ星シェフの免許も偽造ですか?」
不服なのは変わりないが、まだ腹に余裕が出来ないので、ボクはソファに腰掛けた。何を隠そう、ソファにはボクの苦手な教師が座っているのだから。なんだこの教師、自宅のようにくつろぎやがって。
「レイ君家のテレビって古いねー。古臭いねー。あ! また画面が揺れてる。何これ、心霊現象?」
「悪いことは言いません、先生、地べたに座ってください」
「や、がっつり悪いこと言ってるじゃんレイ君。先生泣いちゃうよ?」
「勝手に泣いてください」
「うわ、ひど」
使えないと分かったのか、彼はがっかりしたようにリモコンを手放した。テレビくらい、自分の家に帰ってみればいいものを。
「あれ、つくしとはるかは?」
「ん、確かお風呂見てくるって……」
「泊まる気かよあいつら!」
「だってレイ君の家、めっちゃ空き部屋あるじゃん。我も泊めてもらおっかなー」
「アンタは帰れ! 月に帰れ! 地元に帰れっ!!」
「えーん差別だぁ」
中年の泣き真似にも飽きたところで、ボクは、
「で、どうでしょう」
と、聞いた。彼は気だるそうに、もったりとした前髪を掻き分ける。
「シオンさんのことについて? 君の会った子について? どっち?」
「どっちにも、心当たりがあるんですか?」
エコトという幽霊にも、シオンさんの呪いにも。話したのだ、この人に。今日、今までの出来事全てを。ツクシとハルカには、シオンさん宅への訪問しか話していない。だが、この変人教師には、エコトのことまで話してしまった。何故か、舌が踊るように、洗いざらい語り尽くしていたのだ。タオセイ先生は、フッと笑った。
「幽霊ちゃんの方ならね、有名人だから」
この場合は、有名霊って言った方が良いのかな。
と、置いて。
「でも、今は置いておこう。また今度教えてあげる」
「……じゃあ、“イトモクハルサメ”について、教えてくれませんか」
エコトという幽霊が言っていた、蜘蛛痣を持つ者の名前。彼は、しばし目をはためかせて、
「そっちも、我が知ってると思っているのかな」
「知らないんですね?」
「お生憎だけど、万能万全な我にだって、知らないことくらいあるさ」
「万能万全というより、個人情報法のスペシャリストだから聞いたんです」
「やだなぁ、そんな非公式な異名付けちゃって~。我だってまだプロには遠く及ばないよぉ」
「握ってる情報の量が、常軌を逸してるんですよ、この変人教師!」
「照れるぅ~」
「照れるな!」
くねくねとソファを軋ませる彼に、ボクは横から指で攻撃を入れた。まるでこんにゃくみたいだ、全てかわしやがって!
「まあ、生徒のことを知り尽くしてるボクでも、知らないことは知らないよ。ごめんね、レイ君」
「……そうですか。いいですよ、大図書館に行けばいいだけですから」
「まさか、会いに行くのかい!? “イトモクハルサメ”に……!」
「え、あ、はい」
ソファから落ちそうな勢いで、彼は、がしっと肩を掴んだ。
「我は、本当に立派な教師でないから、まともなことは言えないし、言わない」
「知ってます知ってます」
「けど言わせてもらう!」
「えええ」
「──君は、情報に踊らされすぎだ」
神妙な面持ちで、彼はそう言った。どこか、ボクを食い止めるような調子で。そのまま、先生は続ける。
「なんでもかんでも情報を鵜呑みにするな。それをもたらした者は、本当に信用できるか? ただ一度軽口を交わした仲、しかも幽霊を自称してるやつなんだよ」
「でも、彼女はボクと約束を……!」
「何を根拠に? イトモクハルサメなんて本当に実在する人間なのかい? 写真は? 女性職員という以外の特徴は?」
質問の雨が、絶え間なく降り注ぐ。違った。さっきまでとまったく違う、強い口調で。言葉の弾丸が、ボクの心を真っ直ぐに貫く。息をする間もなく、無数に。落ち着いてください、とも言えずに。
「情報を疑え。疑って、疑って見極めろ。じゃなきゃ、無駄足を踏むだけだ……」
「先生……」
怖い、くらいだった。この人は、何に急かされて、何に追い詰められて、ボクにこう説くのか、分からなかった。彼は少し俯くと、早口で続けた。
「レイ君、君はこの町のことだってまだよく知らないだろう。そんな子に、この町の不思議は暴けない。不思議部部長なんて、到底務まらないよ」
「……そんなこと! あなたには言われたくありませんが」
口だけの反論は意味も成さない。彼は、言葉すらも易々とかわした。
「この件が解決したら、この町のことをちゃんと聞くんだ。キヨタ君とか、ミイロちゃんとかに」
「つくしやはるかでは、駄目なんですか?」
「経験者から聞いた方が良い。だからお願いだよ、レイ君。──情報の波に呑まれないで」
「……分かり、ました」
「うん、よろしい」
妙な説教タイムは、ボクの了承と満足そうな彼の言葉で終わった。
「で、明日の放課後くらいに大図書館に」
「今の話聞いてないでしょレイ君! 情報を見極めろってあれだけ……!」
「いや、見極めた末ですよ。今のボクがすべきことは大図書館に行くことです。じゃなきゃ、状況は変わらない」
「それなら、せめて休日にしてよ! 明日の放課後は会議が入っちゃってるんだ!」
「それが、何か?」
「我、行けないじゃん!」
「いいですよ、ボクたちだけで行くんで」
「いやいやいや顧問の我が同伴しないと」
「大丈夫ですって、ただ人に会いに行くだけですから」
「ああもう! これだからレイ君は」
「───あの、その作戦会議、わたしも混ざって良い?」
「あ………ユリィ。どうした?」
「ううん、あのね。ちょっと、話しておかなきゃいけないことがあって」
ドアからちょこんと顔を出したユリィを引き入れ、ボクたちの作戦会議が始まった。
足を止めることなく駆け、ボクはやっとの思いで見覚えのある門の前に辿り着いた。《幽霊館》でお馴染み、そろそろ氷雨邸と呼びたいボクの自宅。今更ながら、その無駄に大きな門に手をかける。そして、力を込めて、
「ユリィ、ただい──」
「───やあ、レイ君じゃないか。こんなに遅くに帰ってきてー、補導対象だよ?」
「ぎゃああああ! 何で、ここに先生が!」
「まるでおいしい展開が待ってるようなセリフを吐きますね、レイ君」
「わーレイ君だー。こんな時間まで寄り道?」
ちょうど二十一時半をまわった大時計。だが、開口一番目に入ったのは、耳に入ったのは、それではなかった。
「た、倒生先生……何故ここに」
ボクの担任教師、倒生ランジ。何故彼がボクの自宅の階段にもたれているのかは、不明である。ボクはゆっくりと辺りを見回し、そして。知っている顔ぶれが、倒生先生だけではないと確認した。白野つくしと木先はるか。この二人も、倒生先生の隣でニヤニヤとボクを見下ろしていたのだ。
「掃除ならこの間、済んだはずだろうが」
と、ボクは小さく呟いた。この絶対プライベート空間に居る部外者三名。いや、同じ部活に所属しているのだから、部内者かもしれないが、赤の他人三匹。さらに、未だに姿を見せてくれないボクの唯一の同居人。
これ、どういう状況だ。ただ、不可解極まりないのは確かで。
「いやいやいや、はるかとつくしはボクの友達枠だから何となく分かる。でも」
「はるかさん、聞きました? お友達ですって」
「聞いた聞いた、今のはデレだね、レイ君の!」
「そこ、静かに!」
「しゅん……」
「何だよ、子犬みたいな顔しても響かないからな!」
「じゃなくて、何です?」
「何で、ボクの担任がここに居るんだ。普通教師が生徒の家に来ることは無い! ありえないー!」
「え、これ家庭訪問だからね? 正当な訪問だよ。そんな、噂の《幽霊館》を見てみたいーっていう、ミーハーな理由じゃありません」
「後半は十分不純な動機だ! それに、家庭訪問っつったって、ここには、保護者なんか……」
「わたしのこと忘れて、ずっーとお喋りして……」
論争に幕を下ろしたのは、聞き覚えのある少女の声で。
「あ。ゆ、ユリィ……」
ボクの同居人、白髪の三つ編みミイラ──ユリィが、そこに現れた。まるで、冷蔵庫の中に放置してあった一ヶ月前の肉でも見るように、つくしたちの影からボクを見下ろしている。このままだと、ボクが3枚に下ろされそうな勢いである。
しゅうしゅうと、白蛇のような三つ編みを全て逆立て、彼女はらしくもなく首を鳴らした。
「あんまり帰りが遅いから、寂しくて不思議部のみんなを呼んじゃったの、夕食にね」
「え、じゃ、ボクの夕飯は……」
あんなに頑張ったのに。シオンさんやらエコトちゃんやら、未知の存在に遭遇しながら情報集めたのに。ボクは、さっきから壊れたラッパみたく鳴っている腹を、きつく抑えた。夕餉抜きは地獄だ。でも、激怒ユリィの仕打ちがその程度で済むなら良いのだが。
「はあ……夕食ならあります。ただし」
「た、ただし?」
鋭い視線を向けられて、ボクはごくりと唾を飲んだ。一体、このボクにどんな拷問が────?
「──残ってるのはわたしの手作りだけなんだけど」
「ひ」
「僕たちは冷凍食品パーティだったもんねー、ツクシちゃん」
「今って本当、レパートリー豊富なんですね。どれも美味しかったです」
「食べるわよね。食べて、くれるのよね、レイ」
彼女の圧に押し負け、ボクはしぶしぶ首を縦に引いたのだった。この日から、ユリィが自分の手料理を武器にし始めたことを、ここに明記しておこう。
そして、今日が冷凍食品記念日になったことも。
◆◆◆
「うぷ、……ごちそ、さま。ユリィ」
「美味しかった?」
「う、うん。まぁ、いつも通りに」
致死量の黒炭を食べきったボクは、目を輝かせるユリィに苦笑いを返した。ああ、生きてることを褒めてほしい。
「はいはい偉い偉い。じゃ、わたし、お皿洗ってくるから」
「ありがと、ユリィ」
ユリィに皿を渡して、ボクも席を立った。まったく、掃除も選択も皿洗いも完璧なクセして、どうして料理だけは苦手なのか。ちなみに、いつもはボクが台所を担当している。
ユリィとつくしよりかは、料理うまいんだぞ、ボク。
「さらに言えば、我の方が料理うまいんだけどねー」
「身辺詐欺教師……。その三ツ星シェフの免許も偽造ですか?」
不服なのは変わりないが、まだ腹に余裕が出来ないので、ボクはソファに腰掛けた。何を隠そう、ソファにはボクの苦手な教師が座っているのだから。なんだこの教師、自宅のようにくつろぎやがって。
「レイ君家のテレビって古いねー。古臭いねー。あ! また画面が揺れてる。何これ、心霊現象?」
「悪いことは言いません、先生、地べたに座ってください」
「や、がっつり悪いこと言ってるじゃんレイ君。先生泣いちゃうよ?」
「勝手に泣いてください」
「うわ、ひど」
使えないと分かったのか、彼はがっかりしたようにリモコンを手放した。テレビくらい、自分の家に帰ってみればいいものを。
「あれ、つくしとはるかは?」
「ん、確かお風呂見てくるって……」
「泊まる気かよあいつら!」
「だってレイ君の家、めっちゃ空き部屋あるじゃん。我も泊めてもらおっかなー」
「アンタは帰れ! 月に帰れ! 地元に帰れっ!!」
「えーん差別だぁ」
中年の泣き真似にも飽きたところで、ボクは、
「で、どうでしょう」
と、聞いた。彼は気だるそうに、もったりとした前髪を掻き分ける。
「シオンさんのことについて? 君の会った子について? どっち?」
「どっちにも、心当たりがあるんですか?」
エコトという幽霊にも、シオンさんの呪いにも。話したのだ、この人に。今日、今までの出来事全てを。ツクシとハルカには、シオンさん宅への訪問しか話していない。だが、この変人教師には、エコトのことまで話してしまった。何故か、舌が踊るように、洗いざらい語り尽くしていたのだ。タオセイ先生は、フッと笑った。
「幽霊ちゃんの方ならね、有名人だから」
この場合は、有名霊って言った方が良いのかな。
と、置いて。
「でも、今は置いておこう。また今度教えてあげる」
「……じゃあ、“イトモクハルサメ”について、教えてくれませんか」
エコトという幽霊が言っていた、蜘蛛痣を持つ者の名前。彼は、しばし目をはためかせて、
「そっちも、我が知ってると思っているのかな」
「知らないんですね?」
「お生憎だけど、万能万全な我にだって、知らないことくらいあるさ」
「万能万全というより、個人情報法のスペシャリストだから聞いたんです」
「やだなぁ、そんな非公式な異名付けちゃって~。我だってまだプロには遠く及ばないよぉ」
「握ってる情報の量が、常軌を逸してるんですよ、この変人教師!」
「照れるぅ~」
「照れるな!」
くねくねとソファを軋ませる彼に、ボクは横から指で攻撃を入れた。まるでこんにゃくみたいだ、全てかわしやがって!
「まあ、生徒のことを知り尽くしてるボクでも、知らないことは知らないよ。ごめんね、レイ君」
「……そうですか。いいですよ、大図書館に行けばいいだけですから」
「まさか、会いに行くのかい!? “イトモクハルサメ”に……!」
「え、あ、はい」
ソファから落ちそうな勢いで、彼は、がしっと肩を掴んだ。
「我は、本当に立派な教師でないから、まともなことは言えないし、言わない」
「知ってます知ってます」
「けど言わせてもらう!」
「えええ」
「──君は、情報に踊らされすぎだ」
神妙な面持ちで、彼はそう言った。どこか、ボクを食い止めるような調子で。そのまま、先生は続ける。
「なんでもかんでも情報を鵜呑みにするな。それをもたらした者は、本当に信用できるか? ただ一度軽口を交わした仲、しかも幽霊を自称してるやつなんだよ」
「でも、彼女はボクと約束を……!」
「何を根拠に? イトモクハルサメなんて本当に実在する人間なのかい? 写真は? 女性職員という以外の特徴は?」
質問の雨が、絶え間なく降り注ぐ。違った。さっきまでとまったく違う、強い口調で。言葉の弾丸が、ボクの心を真っ直ぐに貫く。息をする間もなく、無数に。落ち着いてください、とも言えずに。
「情報を疑え。疑って、疑って見極めろ。じゃなきゃ、無駄足を踏むだけだ……」
「先生……」
怖い、くらいだった。この人は、何に急かされて、何に追い詰められて、ボクにこう説くのか、分からなかった。彼は少し俯くと、早口で続けた。
「レイ君、君はこの町のことだってまだよく知らないだろう。そんな子に、この町の不思議は暴けない。不思議部部長なんて、到底務まらないよ」
「……そんなこと! あなたには言われたくありませんが」
口だけの反論は意味も成さない。彼は、言葉すらも易々とかわした。
「この件が解決したら、この町のことをちゃんと聞くんだ。キヨタ君とか、ミイロちゃんとかに」
「つくしやはるかでは、駄目なんですか?」
「経験者から聞いた方が良い。だからお願いだよ、レイ君。──情報の波に呑まれないで」
「……分かり、ました」
「うん、よろしい」
妙な説教タイムは、ボクの了承と満足そうな彼の言葉で終わった。
「で、明日の放課後くらいに大図書館に」
「今の話聞いてないでしょレイ君! 情報を見極めろってあれだけ……!」
「いや、見極めた末ですよ。今のボクがすべきことは大図書館に行くことです。じゃなきゃ、状況は変わらない」
「それなら、せめて休日にしてよ! 明日の放課後は会議が入っちゃってるんだ!」
「それが、何か?」
「我、行けないじゃん!」
「いいですよ、ボクたちだけで行くんで」
「いやいやいや顧問の我が同伴しないと」
「大丈夫ですって、ただ人に会いに行くだけですから」
「ああもう! これだからレイ君は」
「───あの、その作戦会議、わたしも混ざって良い?」
「あ………ユリィ。どうした?」
「ううん、あのね。ちょっと、話しておかなきゃいけないことがあって」
ドアからちょこんと顔を出したユリィを引き入れ、ボクたちの作戦会議が始まった。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

【完結】疫病神がうちに来まして~不幸せにするために、まずはあなたを幸せにします~
mazecco
キャラ文芸
「ようこそ、本厄!」
三十三歳の誕生日に、突如現れた謎の少年。
彼が差し出したのは、「疫病神団体 マル派 ムミィ」と記された名刺。
疫病神は、最上の不幸をプレゼントするために、まずは主人公を幸せにしようとする。
「ジェットコースターと同じで、高いところからズドーンッて落とすのが一番効くでしょ!?」
「真白さん。必ず僕が、あなたを幸せにしてみます」
「そして必ず僕が、あなたにとって最上の不幸をプレゼントしますから!」
◆表紙イラスト:薬袋もさ様◆

おきつね様の溺愛!? 美味ごはん作れば、もふもふ認定撤回かも? ~妖狐(ようこ)そ! あやかしアパートへ~
にけみ柚寿
キャラ文芸
1人暮らしを始めることになった主人公・紗季音。
アパートの近くの神社で紗季音が出会ったあやかしは、美形の妖狐!?
妖狐の興恒(おきつね)は、紗季音のことを「自分の恋人」が人型に変身している、とカン違いしているらしい。
紗季音は、自分が「谷沼 紗季音(たにぬま さきね)」というただの人間であり、キツネが化けているわけではないと伝えるが……。
興恒いわく、彼の恋人はキツネのあやかしではなくタヌキのあやかし。種族の違いから周囲に恋路を邪魔され、ずっと会えずにいたそうだ。
「タヌキでないなら、なぜ『谷沼 紗季音』などと名乗る。その名、順序を変えれば『まさにたぬきね』。つまり『まさにタヌキね』ではないか」
アパートに居すわる気満々の興恒に紗季音は……

sweet!!
仔犬
BL
バイトに趣味と毎日を楽しく過ごしすぎてる3人が超絶美形不良に溺愛されるお話です。
「バイトが楽しすぎる……」
「唯のせいで羞恥心がなくなっちゃって」
「……いや、俺が媚び売れるとでも思ってんの?」

ショタパパ ミハエルくん(耳の痛い話バージョン)あるいは、(とっ散らかったバージョン)
京衛武百十
キャラ文芸
もう収集つかないくらいにとっ散らかってしまって試行錯誤を続けて、ひたすら迷走したまま終わることになりました。その分、「マイルドバージョン」の方でなんとかまとめたいと思います。
なお、こちらのバージョンは、出だしと最新話とではまったく方向性が違ってしまっている上に<ネタバレ>はおおよそ関係ない構成になっていますので、まずは最新話を読んでから合う合わないを判断されることをお勧めします。
なろうとカクヨムにも掲載しています。
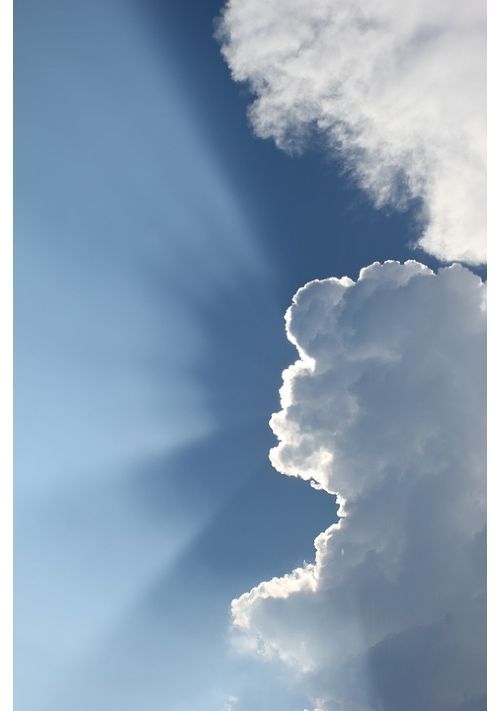
君との空へ【BL要素あり・短編おまけ完結】
Motoki
ホラー
一年前に親友を亡くした高橋彬は、体育の授業中、その親友と同じ癖をもつ相沢隆哉という生徒の存在を知る。その日から隆哉に付きまとわれるようになった彬は、「親友が待っている」という言葉と共に、親友の命を奪った事故現場へと連れて行かれる。そこで彬が見たものは、あの事故の時と同じ、血に塗れた親友・時任俊介の姿だった――。
※ホラー要素は少し薄めかも。BL要素ありです。人が死ぬ場面が出てきますので、苦手な方はご注意下さい。

天道商店街の端にありますー再生屋ー
光城 朱純
キャラ文芸
天道商店街にある再生屋。
看板も出ていない。ぱっと見はただの一軒家。この建物が店だなんて、一体誰が知っているだろうか。
その名の通り、どんなものでも再生させてくれるらしい。
まるで都市伝説の様なその店の噂は、どこからともなく広まって、いつしかその店を必要としてる者の耳に届く。
本当にどんなものでも直してくれるのか?お代はどれだけかかるのか?
謎に包まれたままのその店に、今日も客が訪れる。
再生屋は、それが必要な人の目にしかその店構えを見せることはない。
その姿を見ることができるのは、幸せなのか。果たして不幸なのか。

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。

纏足に花
花籠しずく
キャラ文芸
翠子には身体の弱い弟の寿和がいる。両親の愛を一心に受けて育った彼はやがて己の身体の弱さを使って家を支配することを覚える。寿和が求めたのは翠子の愛。やがて翠子は弟の愛に囚われていく。
※近親愛・近親相姦
※R18 にするほどではありませんが際どい描写があります。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















