57 / 77
第三幕 神は天に居まし、人の世は神も無し
57.シーン3-23(彼)
しおりを挟む
答えられずに黙って折れた布団叩きの柄を構え続けている私に向かって、彼は再度そこをどけと要求した。それでもだんまりを決め込む私に、彼の目が細くなる。
「なぜ邪魔をする? その男は生かしておくべきではない」
彼の口から出てくる意見に、私は落胆せざるを得ない。なぜこう面倒な話題を今ここで展開せねばならぬのだ。どこかの熱血刑事だって、なぜ現場に血が流れるのかと叫んでいたではあるまいか。もちろん現場だからである。いやいや、そう意味ではない。とにもかくにも、今この場で私が言いたいこととは、血を流さずに穏便に解決しようと思わないのか、ということだ。これは敵味方に限っている話ではない。
「なんで? もうすぐ捕まるよ?」
問いに問いで返してばかりの私に彼はしばし険しい顔で間を置いたが、しかし私の方からろくな答えは得られないと見限ったのか、自分の方から口を割った。
「……然るべき処置が取られる保証は無い」
「なぜそこまで殺すことにこだわるの? 何か、生きていられると都合の悪いことでもあるのかな?」
ここまですっかり収束している場においてなお異常なまでに手を下すことに固執されれば、魔力云々とはまた別の方向で彼の身を疑いたくもなってしまう。もし彼に何らかの不都合があった場合、それが日の光を当てられぬような道であれば、さすがの私も借金だなんだと絡むことができなくなる。
一瞬、彼の目つきが厳しさを増す。そのまましばらく私を睨み続けていたが、彼にも彼なりに思うところがあるというのは事実のようだ。
「すでにかなりの人間が殺されている」
なるほど、彼は魔力使いの少女をわき道から追っていった私たちとは違い、ここへ来るまでの間に大通りの惨状を目撃しているのだろう。彼は話を続けた。
「その男はマナの歪みを増幅させる」
私は軽くつまずいた。彼の思考は一般人のそれよりも少し斜めを往くらしい。
「……ごめん、なぜそこで突然マナの話になるのかが分からないんだけど」
「そいつが死ねば、マナの共振が片方途絶え、余った方が歪み、淀む。そして世界の調和を乱す。だが、生きているとそれより多くの命が消え、歪みも大きくなるだろう。世界の調和を乱す元凶を始末して何が悪い。だから俺はこいつを生かしておくべきではないと判断したまでだ」
「ああ! なるほどね……って、いやいや」
彼は非常に、いや全くもって実に律儀な答えをくれた。合点がいって思わず一人納得してしまったではないか。慌てて訂正してみたりと、淡々と語る彼に対して私ときたら忙しい。
「悪いけど、私は目の前で誰かが殺されるところをあまり見たくないんだよね。それに、泣いている女の子の目の前で無理やりとどめを刺すような悪趣味も持ち合わせていないかな」
例え自分と彼らに何の関係もなかろうと、強盗犯にしがみついて泣きじゃくる少女の声をずっと背に受け続ければ、良い気分にはなれないというものだ。
「そんなくだらない理由で邪魔をするな」
ただ一言、彼はさらりとそう言った。思わず殴りとばしてやろうかと思ったが、私はぐっと踏みとどまった。彼にとっては、まさしくその一言で方が付く問題だということだろう。
「その二人は共振者ではない。共にいる意味は無い」
落ち着き払った至極真面目で静かな彼の物言いに、背筋が冷えた。そう言えば、昨日もそのようなことがあった。いや、もっと思い返してみるなら、他にもあったのではないか。大聖堂で、彼が口を開いたと思いきや、出てきた言葉はそれだった。不気味なほど共振者に固執している彼の思想を恐ろしいと感じるのは、はたして私だけだろうか。
雑然とした路地の片隅に倒れる男の不幸に、彼とは何の魔力の繋がりもないはずの少女が悲しみの涙を流している。裕福な家の娘と労働者の少年が、例え周囲からは良く思われずとも笑って話し合っている。彼らが共に同じ時を過ごしているのは、決してマナが、天の理が取り決めた仲だからなのではない。この世界にも、マナの鎖などでは覆せない人の心の喜びや悲しみの繋がりが、きっとどこかに存在するのだ。
「君、それ以外に判断基準がないの?」
「他に何がある」
そうきっぱりと真顔で言い切られてしまうと、私としても何というか非常に困る。判断基準と判断材料がまるで具のない味噌汁のように随分とまあさっぱりしているではないか。そこまでくると純粋に味噌汁として清々しいっちゃ清々しいが、出汁も無ければ味気も無いので私は一応具が欲しい。
「たとえ共振者じゃなくても、大事な人は沢山いる。家族とか友人とか、親しい人がいなくなれば君もきっとつらいんじゃない?」
「お前に俺の何がわかる。それに、家族などとうに死んだ」
なぜいきなりそんな答えになるのだろうか。私はひとまず何故こんな話題になったのかという小さな疑問と、具のない味噌汁の図を頭の隅に押しやった。
いつもいつも答えるごとに、お前には関係ないだとか教える必要はないだとか何とか、そんなことしか言わないやつはどこの誰だと思っているのだ。しかしまあその、なんだ、やはりというか、一応彼にも人には理解しがたい悩みがあるようだ。ここまであからさまに他と足並みがずれているのだから、当然と言えば当然かもしれない。
「そうだね、ごめん。君のことはよくわからない。けど、それでも他の人にはそういう大事な人がいるかもしれない。それに、そうじゃなくても目の前で人が死んだらやっぱり嫌だし悲しいでしょう」
「いるかどうかもわからない人間など……全体を考慮した際、それは優先すべきではない。悲しい? 一時の感情で物事をはかるな。そのようなくだらないものに振り回されて不安定になるからこそ、その男やその子供や、聖都とこの街に留まるあの歪みの原因のようになるのだろう。そんなものは己を正しく保つことにおいて必要はない」
私は内心ため息をついた。君は孤独な人だ。
一時の不安定な感情から、周囲の調和を乱してしまう。心を捨て、人の心を慮らず、良かれと思いやったことが、結果、周囲の調和を乱してしまう。彼が言う客観的な見方をした時、その表層に生じる事象にどれほどの差があると言えよう。だというのなら、喜びや悲しみの心を謳い、自分が確かにここにいると叫ぶことが悪しきことだと、私には思えない。
細やかな感情表現は、人類が厳しい世界において社会を作って生き抜くために、長い長い時間の中でようやく勝ち得た特殊で貴重な能力だ。そんなに身をこそぎ落として、あとどれほどのものが人に残されているだろう。それとも彼は必要分すら積み込めぬほど、何かの荷物で過積載だというのだろうか。それはそれで難儀なものだ。
「とにかく、くじやトロッコばかりを展開するのもほどほどにしておかないと、君もいつか恨みを持たれて刺されちゃうかもしれないよ」
刺されちゃうかもしれないよ、なんてうっかり物騒なことを言ってしまったからなのか、彼は再び目を細めると、訝しみながら私の挙動を逐一観察するように睨みつけた。
「お前こそ、その男が死んで何か困ることでもあるのか?」
はじめに私がしたものと似た疑いの問いをされて、私は少しむっとした。私のどこに疑う余地があろうものか。あからさまに怪しい君ならともかく、そんなもの私の身辺を考えればすぐにわかるものではないかと思ったところで、私は思い至った事実に不覚にも笑ってしまった。
彼にしてみれば、私は半ば騙す形で借金をふっかけてきた最悪の人物である。彼にとっては、なるほど確かにその辺の小賢しい賊と似たようなものかもしれない。そりゃあ、疑いたくもなるものだ。
「何がおかしい」
ふっと口元を緩めてしまったところを見抜かれ、彼の険しい表情がより微かに険しさを増す。笑うところではないと分かっていても、ついついおかしな発見をしてしまったものだから、致し方ない。
「いや、面白いこと言うなあと思っただけだよ」
「何が面白い」
彼は変わらず険しい顔で、冷たい眼差しとともに短刀を私へ向けて構えている。
「一言だけ言わせてもらうなら」
流石に身の潔白を疑われたままでは癪だ。私は、未だ私を警戒し続けている彼へ向けていた布団叩きの切っ先を、静かに下げた。
「私は、君なんかよりは余程身元の知れた平凡な小娘だよ」
そう言ってみたところで、彼が手に持つ刃が向かっている先は変わらない。
どうにもこうにも彼には私が信用ままならないらしい。無理もないといえば無理もない。しかしながら、今この場においてのみ述べるならば、私が彼の下手に出る必要性は何一つとして存在しない。そうとも、心ゆくまで私を疑い、思う存分私の粗を探せば良い。君には何も見つからない。
「なぜ邪魔をする? その男は生かしておくべきではない」
彼の口から出てくる意見に、私は落胆せざるを得ない。なぜこう面倒な話題を今ここで展開せねばならぬのだ。どこかの熱血刑事だって、なぜ現場に血が流れるのかと叫んでいたではあるまいか。もちろん現場だからである。いやいや、そう意味ではない。とにもかくにも、今この場で私が言いたいこととは、血を流さずに穏便に解決しようと思わないのか、ということだ。これは敵味方に限っている話ではない。
「なんで? もうすぐ捕まるよ?」
問いに問いで返してばかりの私に彼はしばし険しい顔で間を置いたが、しかし私の方からろくな答えは得られないと見限ったのか、自分の方から口を割った。
「……然るべき処置が取られる保証は無い」
「なぜそこまで殺すことにこだわるの? 何か、生きていられると都合の悪いことでもあるのかな?」
ここまですっかり収束している場においてなお異常なまでに手を下すことに固執されれば、魔力云々とはまた別の方向で彼の身を疑いたくもなってしまう。もし彼に何らかの不都合があった場合、それが日の光を当てられぬような道であれば、さすがの私も借金だなんだと絡むことができなくなる。
一瞬、彼の目つきが厳しさを増す。そのまましばらく私を睨み続けていたが、彼にも彼なりに思うところがあるというのは事実のようだ。
「すでにかなりの人間が殺されている」
なるほど、彼は魔力使いの少女をわき道から追っていった私たちとは違い、ここへ来るまでの間に大通りの惨状を目撃しているのだろう。彼は話を続けた。
「その男はマナの歪みを増幅させる」
私は軽くつまずいた。彼の思考は一般人のそれよりも少し斜めを往くらしい。
「……ごめん、なぜそこで突然マナの話になるのかが分からないんだけど」
「そいつが死ねば、マナの共振が片方途絶え、余った方が歪み、淀む。そして世界の調和を乱す。だが、生きているとそれより多くの命が消え、歪みも大きくなるだろう。世界の調和を乱す元凶を始末して何が悪い。だから俺はこいつを生かしておくべきではないと判断したまでだ」
「ああ! なるほどね……って、いやいや」
彼は非常に、いや全くもって実に律儀な答えをくれた。合点がいって思わず一人納得してしまったではないか。慌てて訂正してみたりと、淡々と語る彼に対して私ときたら忙しい。
「悪いけど、私は目の前で誰かが殺されるところをあまり見たくないんだよね。それに、泣いている女の子の目の前で無理やりとどめを刺すような悪趣味も持ち合わせていないかな」
例え自分と彼らに何の関係もなかろうと、強盗犯にしがみついて泣きじゃくる少女の声をずっと背に受け続ければ、良い気分にはなれないというものだ。
「そんなくだらない理由で邪魔をするな」
ただ一言、彼はさらりとそう言った。思わず殴りとばしてやろうかと思ったが、私はぐっと踏みとどまった。彼にとっては、まさしくその一言で方が付く問題だということだろう。
「その二人は共振者ではない。共にいる意味は無い」
落ち着き払った至極真面目で静かな彼の物言いに、背筋が冷えた。そう言えば、昨日もそのようなことがあった。いや、もっと思い返してみるなら、他にもあったのではないか。大聖堂で、彼が口を開いたと思いきや、出てきた言葉はそれだった。不気味なほど共振者に固執している彼の思想を恐ろしいと感じるのは、はたして私だけだろうか。
雑然とした路地の片隅に倒れる男の不幸に、彼とは何の魔力の繋がりもないはずの少女が悲しみの涙を流している。裕福な家の娘と労働者の少年が、例え周囲からは良く思われずとも笑って話し合っている。彼らが共に同じ時を過ごしているのは、決してマナが、天の理が取り決めた仲だからなのではない。この世界にも、マナの鎖などでは覆せない人の心の喜びや悲しみの繋がりが、きっとどこかに存在するのだ。
「君、それ以外に判断基準がないの?」
「他に何がある」
そうきっぱりと真顔で言い切られてしまうと、私としても何というか非常に困る。判断基準と判断材料がまるで具のない味噌汁のように随分とまあさっぱりしているではないか。そこまでくると純粋に味噌汁として清々しいっちゃ清々しいが、出汁も無ければ味気も無いので私は一応具が欲しい。
「たとえ共振者じゃなくても、大事な人は沢山いる。家族とか友人とか、親しい人がいなくなれば君もきっとつらいんじゃない?」
「お前に俺の何がわかる。それに、家族などとうに死んだ」
なぜいきなりそんな答えになるのだろうか。私はひとまず何故こんな話題になったのかという小さな疑問と、具のない味噌汁の図を頭の隅に押しやった。
いつもいつも答えるごとに、お前には関係ないだとか教える必要はないだとか何とか、そんなことしか言わないやつはどこの誰だと思っているのだ。しかしまあその、なんだ、やはりというか、一応彼にも人には理解しがたい悩みがあるようだ。ここまであからさまに他と足並みがずれているのだから、当然と言えば当然かもしれない。
「そうだね、ごめん。君のことはよくわからない。けど、それでも他の人にはそういう大事な人がいるかもしれない。それに、そうじゃなくても目の前で人が死んだらやっぱり嫌だし悲しいでしょう」
「いるかどうかもわからない人間など……全体を考慮した際、それは優先すべきではない。悲しい? 一時の感情で物事をはかるな。そのようなくだらないものに振り回されて不安定になるからこそ、その男やその子供や、聖都とこの街に留まるあの歪みの原因のようになるのだろう。そんなものは己を正しく保つことにおいて必要はない」
私は内心ため息をついた。君は孤独な人だ。
一時の不安定な感情から、周囲の調和を乱してしまう。心を捨て、人の心を慮らず、良かれと思いやったことが、結果、周囲の調和を乱してしまう。彼が言う客観的な見方をした時、その表層に生じる事象にどれほどの差があると言えよう。だというのなら、喜びや悲しみの心を謳い、自分が確かにここにいると叫ぶことが悪しきことだと、私には思えない。
細やかな感情表現は、人類が厳しい世界において社会を作って生き抜くために、長い長い時間の中でようやく勝ち得た特殊で貴重な能力だ。そんなに身をこそぎ落として、あとどれほどのものが人に残されているだろう。それとも彼は必要分すら積み込めぬほど、何かの荷物で過積載だというのだろうか。それはそれで難儀なものだ。
「とにかく、くじやトロッコばかりを展開するのもほどほどにしておかないと、君もいつか恨みを持たれて刺されちゃうかもしれないよ」
刺されちゃうかもしれないよ、なんてうっかり物騒なことを言ってしまったからなのか、彼は再び目を細めると、訝しみながら私の挙動を逐一観察するように睨みつけた。
「お前こそ、その男が死んで何か困ることでもあるのか?」
はじめに私がしたものと似た疑いの問いをされて、私は少しむっとした。私のどこに疑う余地があろうものか。あからさまに怪しい君ならともかく、そんなもの私の身辺を考えればすぐにわかるものではないかと思ったところで、私は思い至った事実に不覚にも笑ってしまった。
彼にしてみれば、私は半ば騙す形で借金をふっかけてきた最悪の人物である。彼にとっては、なるほど確かにその辺の小賢しい賊と似たようなものかもしれない。そりゃあ、疑いたくもなるものだ。
「何がおかしい」
ふっと口元を緩めてしまったところを見抜かれ、彼の険しい表情がより微かに険しさを増す。笑うところではないと分かっていても、ついついおかしな発見をしてしまったものだから、致し方ない。
「いや、面白いこと言うなあと思っただけだよ」
「何が面白い」
彼は変わらず険しい顔で、冷たい眼差しとともに短刀を私へ向けて構えている。
「一言だけ言わせてもらうなら」
流石に身の潔白を疑われたままでは癪だ。私は、未だ私を警戒し続けている彼へ向けていた布団叩きの切っ先を、静かに下げた。
「私は、君なんかよりは余程身元の知れた平凡な小娘だよ」
そう言ってみたところで、彼が手に持つ刃が向かっている先は変わらない。
どうにもこうにも彼には私が信用ままならないらしい。無理もないといえば無理もない。しかしながら、今この場においてのみ述べるならば、私が彼の下手に出る必要性は何一つとして存在しない。そうとも、心ゆくまで私を疑い、思う存分私の粗を探せば良い。君には何も見つからない。
0
お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説

【完結】もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」
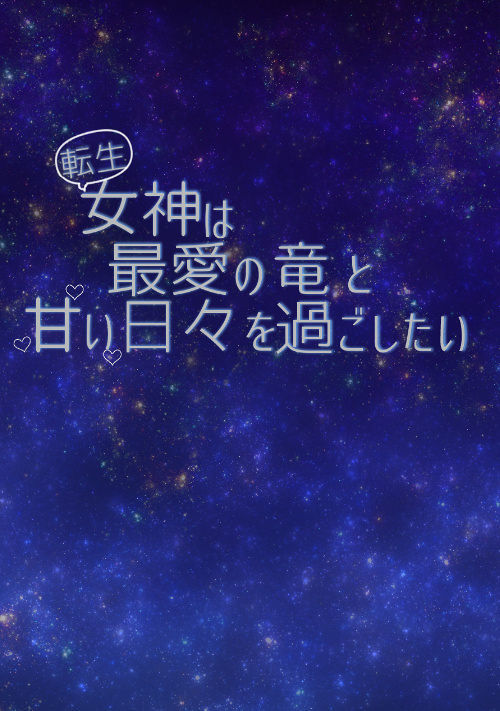
転生女神は最愛の竜と甘い日々を過ごしたい
紅乃璃雨-こうの りう-
ファンタジー
気が付いたら女神へと転生していたミーフェリアスは、秩序無き混沌でグランヴァイルスという竜と出会う。何もないその場所を二人で広げていき、世界を作り上げた。
しかし、順調であった世界は神々と魔の争いによって滅びの危機を向かえる。なんとかしてこの危機を避けようと、考えた策をグランヴァイルスらと実行したが、力の消耗が激しく二人は眠りに就いてしまう。
そして、一万年の時が経ったとある日に二人は目覚め、人の世界でのんびりと暮らすことを決める。
はじまりの女神ミーフェリアスとはじまりの竜グランヴァイルスの穏やかで甘い日々の話。
*10月21日に性描写を削除しました。
*ムーンライトノベルズにも投稿しています(性描写有)

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


骸骨と呼ばれ、生贄になった王妃のカタの付け方
ウサギテイマーTK
恋愛
骸骨娘と揶揄され、家で酷い扱いを受けていたマリーヌは、国王の正妃として嫁いだ。だが結婚後、国王に愛されることなく、ここでも幽閉に近い扱いを受ける。側妃はマリーヌの義姉で、公式行事も側妃が請け負っている。マリーヌに与えられた最後の役割は、海の神への生贄だった。
注意:地震や津波の描写があります。ご注意を。やや残酷な描写もあります。

アルバートの屈辱
プラネットプラント
恋愛
妻の姉に恋をして妻を蔑ろにするアルバートとそんな夫を愛するのを諦めてしまった妻の話。
『詰んでる不憫系悪役令嬢はチャラ男騎士として生活しています』の10年ほど前の話ですが、ほぼ無関係なので単体で読めます。


断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















