お気に入りに追加
9
あなたにおすすめの小説

【完結】もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」
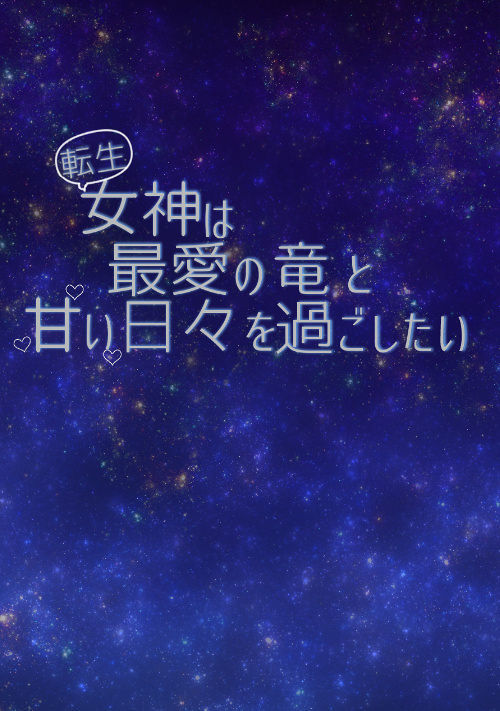
転生女神は最愛の竜と甘い日々を過ごしたい
紅乃璃雨-こうの りう-
ファンタジー
気が付いたら女神へと転生していたミーフェリアスは、秩序無き混沌でグランヴァイルスという竜と出会う。何もないその場所を二人で広げていき、世界を作り上げた。
しかし、順調であった世界は神々と魔の争いによって滅びの危機を向かえる。なんとかしてこの危機を避けようと、考えた策をグランヴァイルスらと実行したが、力の消耗が激しく二人は眠りに就いてしまう。
そして、一万年の時が経ったとある日に二人は目覚め、人の世界でのんびりと暮らすことを決める。
はじまりの女神ミーフェリアスとはじまりの竜グランヴァイルスの穏やかで甘い日々の話。
*10月21日に性描写を削除しました。
*ムーンライトノベルズにも投稿しています(性描写有)

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。


骸骨と呼ばれ、生贄になった王妃のカタの付け方
ウサギテイマーTK
恋愛
骸骨娘と揶揄され、家で酷い扱いを受けていたマリーヌは、国王の正妃として嫁いだ。だが結婚後、国王に愛されることなく、ここでも幽閉に近い扱いを受ける。側妃はマリーヌの義姉で、公式行事も側妃が請け負っている。マリーヌに与えられた最後の役割は、海の神への生贄だった。
注意:地震や津波の描写があります。ご注意を。やや残酷な描写もあります。

アルバートの屈辱
プラネットプラント
恋愛
妻の姉に恋をして妻を蔑ろにするアルバートとそんな夫を愛するのを諦めてしまった妻の話。
『詰んでる不憫系悪役令嬢はチャラ男騎士として生活しています』の10年ほど前の話ですが、ほぼ無関係なので単体で読めます。


断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















