この作品の感想を投稿する
みんなの感想(1件)
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
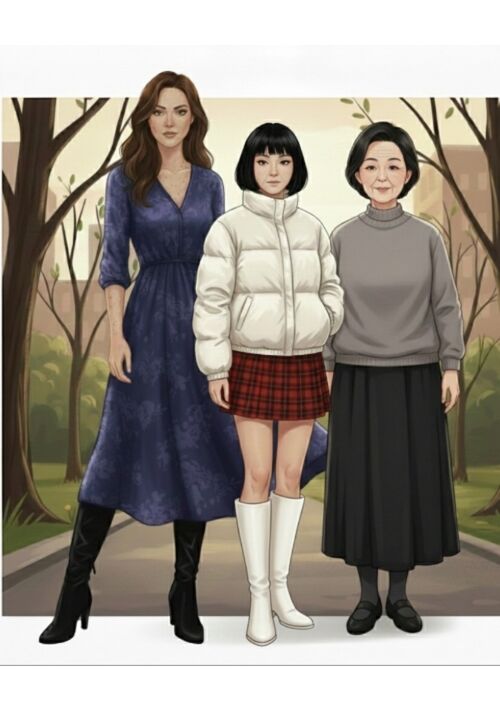
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。


JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
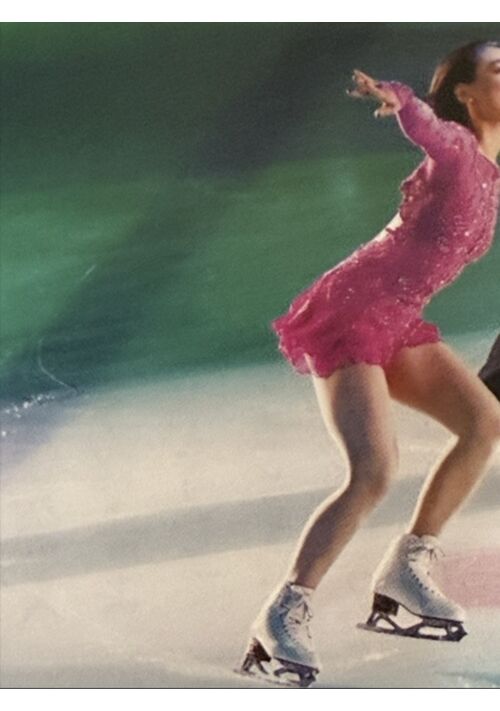
あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















退会済ユーザのコメントです
岡本さん初めまして
ありがとうございます(*^^*)
何かと忙しい毎日ですが、いなり横丁でホッと息抜きをしていただければ幸いです♪