13 / 33
~夏の終わりの線香花火~
しおりを挟む
夏の終わりは夕焼けに似ている。
世界の色は暖色から寒色へ少しずつグラデーションの様に変化してゆく黄昏の刻、人々は哀愁を感じる者が多かった。
「これ、みんなで遊びませんか?」
小料理屋に現れた小僧さんは入ってくるなり、持ってきた『花火』と書かれた箱をカウンターに置いた。それを見た女将が「あら、花火じゃない」と嬉しそうな笑顔を浮かべる。
「おまけの残りなんです」
花火は小僧さんのお店でお客さんにサービスしていた販売促進のおまけらしかった。秋の気配が漂い始めたのでみんなで遊んで使い切ろうと思ったらしい。
「花火懐かしいですね」
店の奥の指定席にいた天狗さんがそう言ってにっこりと笑う。
「来年まで置いておく訳にもいきませんから…」
「火薬が湿気ちゃうものね」
「捨てるのももったいないですし、今年の夏の終わりの思い出になればと思いまして」
小僧さんは少年の様にニカっと笑う。
大人になると、身近に小さな子供がいないと手持ち花火で遊ぶ機会などめったにないので、小僧さんのアイディアはみんな大歓迎だった。
「花火はいろいろあります」と言って、花火の箱の底から小僧さんが様々な種類の花火を出して並べ出した。
長めの数種類の手持ち花火に定番の線香花火、ねずみ花火はわかるが、蛇玉まであったので、それを見た者から笑いが起きる。
「蛇玉懐かしい~」
女将がはしゃいだ声をあげた。
「——昔よく、兄たちとお小遣いを出し合って蛇玉を箱買いして、中身を全部その箱に入れて点火するって遊びをやったわ」と女将はそう言うと、「箱からうねうね出てくる大量の蛇玉が気持ち悪いのよね」と思い出し笑いをする。
そんな女将に天狗さんが「やんちゃな遊びしてますねぇ」と少し呆れたような様子で笑った。
「今夜は雨、大丈夫そうだし、後でみんなでやりましょうね」
そう言うと女将はおしぼりとお通しのサツマイモの甘露煮の小鉢を小僧さんの前に出した。
「今日のおすすめは焼きなすです」
「じゃあ、ビールと焼きナスを…」
小僧さんはそう言うと天狗さんや私が先に食べていた焼きナスを見て「うまそう」とよだれを垂らしそうな様子で呟いた。
「家で焼きナスって作らないから嬉しいですよね」
私の言葉に小僧さんや天狗さんが頷く。
「料理は得意じゃないですし、この店は旬のものの料理を食べられるんでありがたい」
天狗さんが女将に向かって手を合わせた。そんな天狗さんに女将が「そんな大したものじゃないですよ」と微笑んだ。
天狗さんが言うようにこの店の料理は旬の食材を使ったものや素朴な家庭料理が多く、味が濃く油ものが多い食事をする事が多い料理下手の我々にとっては非常にありがたい存在だった。
「しかも酒に合うものばかりだから晩酌にいいし」
小僧さんがそう言うと、ビールを美味しそうに飲みながら甘露煮をつつきだした。
「日本の夏と言えば花火ですよね。大きな打ち上げ花火が見られる花火大会もいいんですが、ちょっと人が多すぎるんで私は苦手なんですよね…」
カウンターに置かれたままの花火を見ながら天狗さんがぼやく。
「私もよ――最近、有名な花火大会はテレビやネットでライブ中継をしてくれるから、もっぱらそっちで楽しむ事にしてるわ」
「花火鑑賞のビールのお供にはうちのたこ焼きを是非」
「ちゃっかりしてるわね」
勝手知ったる仲間たちの言葉のキャッチボールは、この小料理屋の楽しみの一つでもあった。
数時間後、小料理屋の前にはほろ酔いでいい気分になった私や天狗さん小僧さんが店から女将が出てくるのを待っていた。
「遊び終わった花火はこのバケツに浸けてね」
店の中から水が入ったブリキのバケツを手にした女将が出てくると、バケツを私たちの前に置いた。ブリキのバケツは赤く塗装されていて、『防火』と大きく黒い文字が書かれている。その横に小僧さんがみかんの缶詰めの空き缶を置き、その中に火を付けたろうそくを翳して蝋を底に垂らすと蠟が固まらないうちにろうそくをそっと立てた。
「準備完了」
その声を合図にそれぞれ好きな花火を手にして、花火遊びを始めた。
普通に持って光と音を楽しんでみたり、火を点けた花火を持って円を描くように腕を回して、光の残像を楽しんでみたりと遊び方はさまざまである。
花火で遊ぶ私たちを見て、通りがかりの人たちが微笑ましいものを見たような表情を浮かべる。
「空き瓶にロケット花火を刺して飛ばしたりもしましたよね」
「ああ、空き地や公園でよくやったね」
小僧さんの言葉に天狗さんが懐かしそうな表情になり合槌をうつ。
最近の花火は趣向を凝らしたものも多いが、シンプルなものは飽きが来ないのか今も昔もあまり変わらないが根強い人気がある。
「僕の時代にはUFOの形をした吊り下げ花火なんかもあったので、鉄棒にぶら下げて遊んでました」と私が言うと、世代の違いか天狗さんは吊り下げ花火を知らなかった。
吊り下げ花火は円盤型の本体の淵に花火が付いていて、それに点火すると光りながら飛んでいるUFOの様に見えるという趣向の花火だった。
「発想が面白いね」
「ピンクレディーのUFOが流行した時に売り出された花火でした」
私が解説すると、天狗さんが「なるほど」と納得した。
一世風靡した流行りものがあると、必ず様々な便乗商品が登場するのは今も昔も変わらないのかもしれなかった。
「そろそろ線香花火やろうか」
小僧さんが花火の箱の中を覗き込んで仲間たちに声をかける。童心に帰って遊んでいるうちに、いつのまにやら箱の中に残っているのは線香花火だけになっていた。面白いもので最後の〆の花火は線香花火という暗黙の了解があるのか、打ち合わせしたのではないが誰も今まで線香花火には手を付けていなかった。
「この線香花火は長手なのね」
線香花火を手にした女将が言った。
線香花火には主に2種類あって、東日本に多いのは「長手」と呼ばれる和紙のこよりの先に火薬が包まれているタイプで、西日本で多いのは「すぽ手」という、藁や竹ひごの先に火薬が付けられたタイプだった。
「僕は線香花火はずっと和紙の奴でしたので」
「私はすぽ手育ちなのよね…小さい頃は極細の竹ひごの線香花火しかなかったし」
やはり出身地によって違いがあるようだった。
「…まあ、どちらも線香花火ですがね」
河童さんと女将を取り持つように天狗さんがそう言うと、持っていた線香花火に火を点けた。それに続くように他の者も自分の線香花火に火を点け、少し離れた所で輪になる様にしゃがみ込む。
点火された線香花火は最初「蕾」と呼ばれる、直径5ミリほどの火球を花火の先に出来る。次に「牡丹」と呼ばれる、火球から少しずつ牡丹の花びらのような火花が散り始め、激しく「松葉」と言われる火花の形を変える。やがて火花に勢いがなくなる「柳」に変化して飛び散る火花の数も少なくなってゆく。最後は花火の先の火球が少しずつ大きくなっていく「散り菊」と呼ばれる状態に。火球から思い出したように飛び出す火花が少しずつ散ってゆく菊の花に似ている事からその名前が付けられたという。
「あ…」
手にしていた線香花火の火球がぽとりと地面に落ちるのを見て、女将が小さな声を出した。
「今回は早かった…次こそは」
そう言いながら女将は次の線香花火に火を点け、線香花火を楽しんでいる輪に加わりしゃがみ込む。
「線香花火の燃焼温度は850℃からはじまって、最後は1000℃になるそうですよ」
「火球を足に落としたら大やけどですね」
天狗さんの言葉を聞いて、裸足でビーチサンダルを履いていた小僧さんがおっかなびっくりといった様子でそっと手を動かし、足先と線香花火の火球との距離をとった。
「線香花火は日本で開発された花火って聞いた事あるけど…」
「江戸時代に子供用のおもちゃとして開発されたそうですよ。安全な手花火だから当時から人気があったとか」
そう言うと天狗さんは線香花火を英語では『Japanese sparklers』と言うのだと教えてくれる。
「日本のキラキラしたもの?」
「直訳するとそうなるね」
海外でも人気の花火で、海外では香炉に刺して火を点けるという日本とは違うスタイルで楽しまれていたらしかった。恐らく鎖国をしていた江戸時代貿易港と言えば長崎の出島だったので、西日本で主流のすぽ手の線香花火が海を渡ったのだろう。
「繊細な花火を開発するのが日本的よね」
海外の花火に情緒があるとは思えないのか一同無言で頷く。
「火薬は戦争の為に使われる事が多いですが、私は平和的利用の花火の方がいいな」
闇の中に咲かせる小さな火の花びらは、見る者の心を癒す不思議な魅力を持っている。
火薬もまた刃物と同じで人を傷付ける事もあれば、助ける事もできる。使うものの心次第なのだから、願わくば他に害を与える使い方はしてほしくないししたくもない。
線香花火の火花を見つめながら、私はそう思わずにはいられなかった。
世界の色は暖色から寒色へ少しずつグラデーションの様に変化してゆく黄昏の刻、人々は哀愁を感じる者が多かった。
「これ、みんなで遊びませんか?」
小料理屋に現れた小僧さんは入ってくるなり、持ってきた『花火』と書かれた箱をカウンターに置いた。それを見た女将が「あら、花火じゃない」と嬉しそうな笑顔を浮かべる。
「おまけの残りなんです」
花火は小僧さんのお店でお客さんにサービスしていた販売促進のおまけらしかった。秋の気配が漂い始めたのでみんなで遊んで使い切ろうと思ったらしい。
「花火懐かしいですね」
店の奥の指定席にいた天狗さんがそう言ってにっこりと笑う。
「来年まで置いておく訳にもいきませんから…」
「火薬が湿気ちゃうものね」
「捨てるのももったいないですし、今年の夏の終わりの思い出になればと思いまして」
小僧さんは少年の様にニカっと笑う。
大人になると、身近に小さな子供がいないと手持ち花火で遊ぶ機会などめったにないので、小僧さんのアイディアはみんな大歓迎だった。
「花火はいろいろあります」と言って、花火の箱の底から小僧さんが様々な種類の花火を出して並べ出した。
長めの数種類の手持ち花火に定番の線香花火、ねずみ花火はわかるが、蛇玉まであったので、それを見た者から笑いが起きる。
「蛇玉懐かしい~」
女将がはしゃいだ声をあげた。
「——昔よく、兄たちとお小遣いを出し合って蛇玉を箱買いして、中身を全部その箱に入れて点火するって遊びをやったわ」と女将はそう言うと、「箱からうねうね出てくる大量の蛇玉が気持ち悪いのよね」と思い出し笑いをする。
そんな女将に天狗さんが「やんちゃな遊びしてますねぇ」と少し呆れたような様子で笑った。
「今夜は雨、大丈夫そうだし、後でみんなでやりましょうね」
そう言うと女将はおしぼりとお通しのサツマイモの甘露煮の小鉢を小僧さんの前に出した。
「今日のおすすめは焼きなすです」
「じゃあ、ビールと焼きナスを…」
小僧さんはそう言うと天狗さんや私が先に食べていた焼きナスを見て「うまそう」とよだれを垂らしそうな様子で呟いた。
「家で焼きナスって作らないから嬉しいですよね」
私の言葉に小僧さんや天狗さんが頷く。
「料理は得意じゃないですし、この店は旬のものの料理を食べられるんでありがたい」
天狗さんが女将に向かって手を合わせた。そんな天狗さんに女将が「そんな大したものじゃないですよ」と微笑んだ。
天狗さんが言うようにこの店の料理は旬の食材を使ったものや素朴な家庭料理が多く、味が濃く油ものが多い食事をする事が多い料理下手の我々にとっては非常にありがたい存在だった。
「しかも酒に合うものばかりだから晩酌にいいし」
小僧さんがそう言うと、ビールを美味しそうに飲みながら甘露煮をつつきだした。
「日本の夏と言えば花火ですよね。大きな打ち上げ花火が見られる花火大会もいいんですが、ちょっと人が多すぎるんで私は苦手なんですよね…」
カウンターに置かれたままの花火を見ながら天狗さんがぼやく。
「私もよ――最近、有名な花火大会はテレビやネットでライブ中継をしてくれるから、もっぱらそっちで楽しむ事にしてるわ」
「花火鑑賞のビールのお供にはうちのたこ焼きを是非」
「ちゃっかりしてるわね」
勝手知ったる仲間たちの言葉のキャッチボールは、この小料理屋の楽しみの一つでもあった。
数時間後、小料理屋の前にはほろ酔いでいい気分になった私や天狗さん小僧さんが店から女将が出てくるのを待っていた。
「遊び終わった花火はこのバケツに浸けてね」
店の中から水が入ったブリキのバケツを手にした女将が出てくると、バケツを私たちの前に置いた。ブリキのバケツは赤く塗装されていて、『防火』と大きく黒い文字が書かれている。その横に小僧さんがみかんの缶詰めの空き缶を置き、その中に火を付けたろうそくを翳して蝋を底に垂らすと蠟が固まらないうちにろうそくをそっと立てた。
「準備完了」
その声を合図にそれぞれ好きな花火を手にして、花火遊びを始めた。
普通に持って光と音を楽しんでみたり、火を点けた花火を持って円を描くように腕を回して、光の残像を楽しんでみたりと遊び方はさまざまである。
花火で遊ぶ私たちを見て、通りがかりの人たちが微笑ましいものを見たような表情を浮かべる。
「空き瓶にロケット花火を刺して飛ばしたりもしましたよね」
「ああ、空き地や公園でよくやったね」
小僧さんの言葉に天狗さんが懐かしそうな表情になり合槌をうつ。
最近の花火は趣向を凝らしたものも多いが、シンプルなものは飽きが来ないのか今も昔もあまり変わらないが根強い人気がある。
「僕の時代にはUFOの形をした吊り下げ花火なんかもあったので、鉄棒にぶら下げて遊んでました」と私が言うと、世代の違いか天狗さんは吊り下げ花火を知らなかった。
吊り下げ花火は円盤型の本体の淵に花火が付いていて、それに点火すると光りながら飛んでいるUFOの様に見えるという趣向の花火だった。
「発想が面白いね」
「ピンクレディーのUFOが流行した時に売り出された花火でした」
私が解説すると、天狗さんが「なるほど」と納得した。
一世風靡した流行りものがあると、必ず様々な便乗商品が登場するのは今も昔も変わらないのかもしれなかった。
「そろそろ線香花火やろうか」
小僧さんが花火の箱の中を覗き込んで仲間たちに声をかける。童心に帰って遊んでいるうちに、いつのまにやら箱の中に残っているのは線香花火だけになっていた。面白いもので最後の〆の花火は線香花火という暗黙の了解があるのか、打ち合わせしたのではないが誰も今まで線香花火には手を付けていなかった。
「この線香花火は長手なのね」
線香花火を手にした女将が言った。
線香花火には主に2種類あって、東日本に多いのは「長手」と呼ばれる和紙のこよりの先に火薬が包まれているタイプで、西日本で多いのは「すぽ手」という、藁や竹ひごの先に火薬が付けられたタイプだった。
「僕は線香花火はずっと和紙の奴でしたので」
「私はすぽ手育ちなのよね…小さい頃は極細の竹ひごの線香花火しかなかったし」
やはり出身地によって違いがあるようだった。
「…まあ、どちらも線香花火ですがね」
河童さんと女将を取り持つように天狗さんがそう言うと、持っていた線香花火に火を点けた。それに続くように他の者も自分の線香花火に火を点け、少し離れた所で輪になる様にしゃがみ込む。
点火された線香花火は最初「蕾」と呼ばれる、直径5ミリほどの火球を花火の先に出来る。次に「牡丹」と呼ばれる、火球から少しずつ牡丹の花びらのような火花が散り始め、激しく「松葉」と言われる火花の形を変える。やがて火花に勢いがなくなる「柳」に変化して飛び散る火花の数も少なくなってゆく。最後は花火の先の火球が少しずつ大きくなっていく「散り菊」と呼ばれる状態に。火球から思い出したように飛び出す火花が少しずつ散ってゆく菊の花に似ている事からその名前が付けられたという。
「あ…」
手にしていた線香花火の火球がぽとりと地面に落ちるのを見て、女将が小さな声を出した。
「今回は早かった…次こそは」
そう言いながら女将は次の線香花火に火を点け、線香花火を楽しんでいる輪に加わりしゃがみ込む。
「線香花火の燃焼温度は850℃からはじまって、最後は1000℃になるそうですよ」
「火球を足に落としたら大やけどですね」
天狗さんの言葉を聞いて、裸足でビーチサンダルを履いていた小僧さんがおっかなびっくりといった様子でそっと手を動かし、足先と線香花火の火球との距離をとった。
「線香花火は日本で開発された花火って聞いた事あるけど…」
「江戸時代に子供用のおもちゃとして開発されたそうですよ。安全な手花火だから当時から人気があったとか」
そう言うと天狗さんは線香花火を英語では『Japanese sparklers』と言うのだと教えてくれる。
「日本のキラキラしたもの?」
「直訳するとそうなるね」
海外でも人気の花火で、海外では香炉に刺して火を点けるという日本とは違うスタイルで楽しまれていたらしかった。恐らく鎖国をしていた江戸時代貿易港と言えば長崎の出島だったので、西日本で主流のすぽ手の線香花火が海を渡ったのだろう。
「繊細な花火を開発するのが日本的よね」
海外の花火に情緒があるとは思えないのか一同無言で頷く。
「火薬は戦争の為に使われる事が多いですが、私は平和的利用の花火の方がいいな」
闇の中に咲かせる小さな火の花びらは、見る者の心を癒す不思議な魅力を持っている。
火薬もまた刃物と同じで人を傷付ける事もあれば、助ける事もできる。使うものの心次第なのだから、願わくば他に害を与える使い方はしてほしくないししたくもない。
線香花火の火花を見つめながら、私はそう思わずにはいられなかった。
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

この町は、きょうもあなたがいるから廻っている。
ヲトブソラ
ライト文芸
親に反対された哲学科へ入学した二年目の夏。
湖径<こみち>は、実家からの仕送りを止められた。
湖径に与えられた選択は、家を継いで畑を耕すか、家を継いでお米を植えるかの二択。
彼は第三の選択をし、その一歩目として激安家賃の長屋に引っ越すことを決める。
山椒魚町河童四丁目三番地にある長屋には、とてもとても個性的な住人だけが住んでいた。
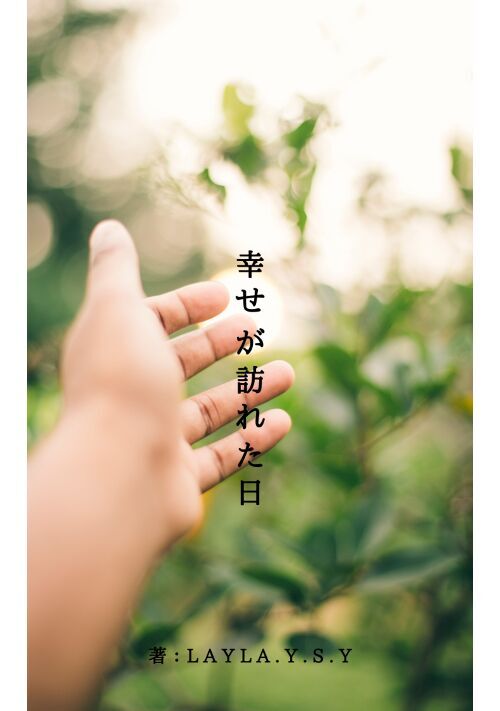
幸せが訪れた日
Layla
恋愛
昭和初期、主人公南菊代は幼くして不運に落ち、祖母、姉、弟達と貧乏でも愛がある生活を送っていた。お金はなくても不幸ではない。そう思っていた菊代だが運命的な出会いにより菊代の人生はどんどん変わっていくのであった。

旅路ー元特攻隊員の願いと希望ー
ぽんた
歴史・時代
舞台は1940年代の日本。
軍人になる為に、学校に入学した
主人公の田中昴。
厳しい訓練、激しい戦闘、苦しい戦時中の暮らしの中で、色んな人々と出会い、別れ、彼は成長します。
そんな彼の人生を、年表を辿るように物語りにしました。
※この作品は、残酷な描写があります。
※直接的な表現は避けていますが、性的な表現があります。
※「小説家になろう」「ノベルデイズ」でも連載しています。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。


夫の色のドレスを着るのをやめた結果、夫が我慢をやめてしまいました
氷雨そら
恋愛
夫の色のドレスは私には似合わない。
ある夜会、夫と一緒にいたのは夫の愛人だという噂が流れている令嬢だった。彼女は夫の瞳の色のドレスを私とは違い完璧に着こなしていた。噂が事実なのだと確信した私は、もう夫の色のドレスは着ないことに決めた。
小説家になろう様にも掲載中です

アンティークショップ幽現屋
鷹槻れん
ミステリー
不思議な物ばかりを商うアンティークショップ幽現屋(ゆうげんや)を舞台にしたオムニバス形式の短編集。
幽現屋を訪れたお客さんと、幽現屋で縁(えにし)を結ばれたアンティークグッズとの、ちょっぴり不思議なアレコレを描いたシリーズです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















