お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく


Observer ー観測者ー
selen
SF
環境問題を巡る第三次世界大戦で、いよいよ地球は人の住める惑星ではなくなってしまった。
人々はロケットに乗り込み、新しい惑星へと飛び立った。
そして各々の進化を遂げた人類が、再び“仲間”を求めだす。
行ったことも無い惑星に居る、自分とは姿かたち、何もかもが違う仲間。
「それでもまた会いたい。」そう願う2人の少女の話。



ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

鋼月の軌跡
チョコレ
SF
月が目覚め、地球が揺れる─廃機で挑む熱狂のロボットバトル!
未知の鉱物ルナリウムがもたらした月面開発とムーンギアバトル。廃棄された機体を修復した少年が、謎の少女ルナと出会い、世界を揺るがす戦いへと挑む近未来SFロボットアクション!
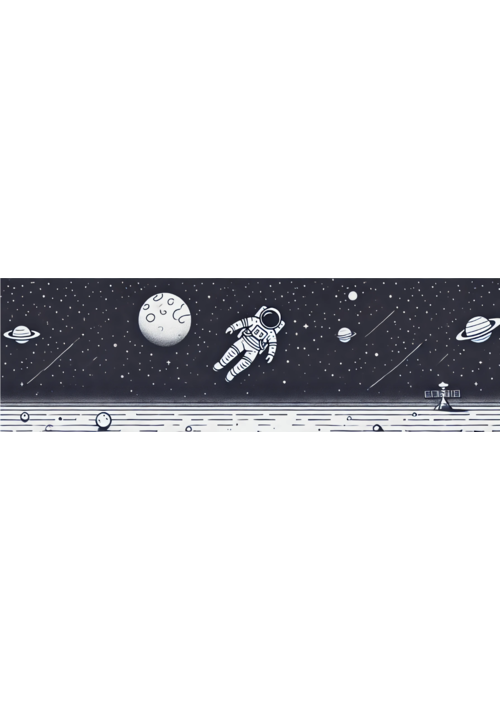
悪辣な推論
てるぼい
SF
男は宇宙の船外調査の折に同僚に突き落とされ、宇宙空間を独りで漂流していた。残り少ない命の中、彼は過去を振り返る。なぜこんな状況に至ったのか。
この絶望的な状況で彼の運命は一体どこに行きつくのだろうか・・・。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















