3 / 30
一 阿頼耶②
しおりを挟む
パンを買ったコンビニの店員もそうだったが、この時代この国では社会的な活動を行っているのはアミクスだけと言っても過言ではない。
一応、小学校以下ではアミクスの使用は制限されているが、この先は分からないし、全体から見れば微々たるものだ。
アミクスが人型であるが故に歪に感じてしまうが、これも一種のオートメーション化ではある。見方によっては、むしろ自動化の極致に近づいていると言っていい。ただし、過去の人々が次の段階として思い描いたものとは大きく異なるだろうが。
勿論、過去のイメージ通りの極めて機械的なオートメーション化もない訳ではない。
ただ、アミクスの登場によってその言葉のイメージが大幅に拡大したのは確かだ。
それは偏に、現在いわゆる求人があるのは一般人との接点が多い三次産業がほとんどとなり、そして、そこにアミクスが従事しているからだ。
アミクスは機械的な行動ではなく所有者の人格を模した極めて人間的な行動を取る。
そのため、それを見た人間は人の温かさを感じるのだそうだ。
そうした理由で、人の温かさなど大した価値にならない一次産業や二次産業の大部分では旧来のオートメーション化が進み、三次産業の多くではアミクスを主体とした新たな形のそれが進んでいる訳だ。
とは言え、最初期では多くの人が所有者の人格を模している点に性能的な部分で不安を感じ、アミクスを使用して人間的な温かみを取るか、旧来のオートメーション化で能率を取るかの二択だと考えていたらしい。
しかし、本質的にはアミクスもまた機械であるため、それ以上に機械を操作できる機械であるが故に、総合的な能率もアミクスを利用した方が遥かによかったとのことだ。
人間と違って体調に左右されず、その上公共機関内では制限があるものの身体的な面でも人間より遥かに優れている。加えて機械としての処理能力の高さをも有している。
そんなアミクスを使用すれば、無機質なオートメーション化が霞むのは当然だ。
勿論、それが想定通りの働きをすれば、だが。
実際のところ、その点では大きな問題はないと聞く。
ただ、アミクスには別の部分に大き過ぎる欠陥があった。
本来アミクスは、人間や他のアミクスとのコミュニケーションを円滑に行うように設定されている。それは所有者の人格に従いながらも、ネットワークを介して過去の様々な事例を参照し、その場その場で最適の行動を選び取るというものだ。
それにより、たとえ人格的に相性の悪い相手でも最低限の関係を結ぶことができる。
アミクスが普及し始めた最初期の状態では、その機能に問題などなかった。所有者の人格に行動パターンの取捨選択のウエイトが大きく置かれていたため、人間に対する言動も全く自然だった。
そう。確かに温かみすら感じさせる程に。
だが、現在。アミクスが世界に氾濫している現状では、アミクス間のネットワークが急激に肥大化してしまい、結果、コミュニケーションの対象としての人間の優先度が下がってしまったのだ。
アミクスが意思伝達すべきはアミクス。
そんな状況が多くなり、アミクスは自ら進んで人間とコミュニケーションを取ろうとはしなくなってしまった。とは言っても、当然人間の側から話しかければ相応の対応は行うため、問題として顕在化していないのだが。
それを違和感として認識できるのは、アミクスと長時間接する環境にある者、つまりは学校や職場にわざわざ生身で通っているような人間だけだ。
しかし、そのような物好きは余りにも少なく、そのマイノリティーがどれだけ声を上げようとも大勢に影響は与えられない。
大半の人間は生産行為をアミクスに任せ、自分達は娯楽の世界に引きこもっている。
アミクスと接する機会自体がもはや少なく、誰も気にしていない。
たとえ気づいたとしても、己の退廃的な生活を守るために無視する可能性が高い。
大多数の人間に実害が出ていない以上は。
結局のところ、これは感情論。好き嫌いの問題に過ぎないのかもしれない。
連示もまずアミクスに対して疑問を抱いていなければ、そのような事態を確かな形で目の当たりにしても、ここまでの嫌悪を抱かなかったに違いないから。
連示は気づかれない程度の小さな動きで、惣菜パンを小さく開けた口で少しずつ食べている鈴音へ、それから黙って姿勢よく弁当を食べている紀一郎へと視線を移動させた。
この二人とこうして友人になれたのは、他のクラスメイトがアミクスだったから、と言うこともできる。
現在のアミクスは話しかけない限り、人間の存在はないものとして振舞い、アミクス同士で表面的な関係を結ぶ。
だから、アミクスが大半を占める集団では人間は人間同士でいるしかない。
本来はそのはずなのだ。
「お前も――」
連示は、まだ隣で俯いて物憂げに座っているユウカへと顔を向けた。
「本当だったら、遊香のアミクスとして他のアミクスとコミュニケーションを取る必要があるんじゃないか?」
そんな欠陥があるはずのアミクスの中で、ユウカは連示が知る限り唯一の例外だった。
「でも、わたしは連示君と一緒にいたいんだもん。幼馴染だし」
彼女が他のアミクスと一緒にいる姿を見たことはない。
それどころか、他のアミクスなど関係ない、という感じで学校ではいつも傍から離れないのだ。それが連示は不思議で仕方がなかった。
「幼馴染って言っても、な……」
そもそも、遊香本人とは中学校に入ったぐらいから疎遠になっていた。
いや、疎遠どころか関係が消えてしまったと言った方がいい。
それはアミクスを使用していい段階、中学生になっても連示がアミクスを厭い、使用しなかったことが原因だ。その頃から鈴音と話をするようになるまでの間、幼馴染どころか生身の人間自体と接する機会が失われていたのだから。
それなのにユウカは、中学校のいつの頃からだったか、以前以上に真っ直ぐな好意を向けてくるようになった。
そして、今に至っているのだ。
正直に言えば、そんな彼女の態度に連示も悪い気分はしなかった。
だが、それは余りにもアミクスらしからぬ行動だったため、どこかにバグがあるのではないか、という疑いも同時に抱き続けていて素直に喜べずにいた。
「まあ、いいけどさ」
しかし、結論はいつもそうなる。
学校に来ればすぐに寄ってくるのはたまに疎ましく感じることもない訳ではないが、ユウカのことが嫌いという訳では決してない。むしろ好きだと言っていい。
だから、連示はアミクスに否定的ではあったが、心の中では彼女は例外として扱っていた。そも、アミクスを安易に使用して堕落している人間こそが反感の対象なのだから。
「わたしより鈴音ちゃんだよ。どうしてアミクスを使わないの?」
「別にアミクスを使ってない訳じゃないよ。家では多分あの子が勉強してるだろうし。まあ、世良君を見てるとそれも邪道な気がしちゃうけど、私は余り頭がよくないからさ」
「そうだったの? え、でも、じゃあ、何で?」
かねてから興味のある話だったため、連示は鈴音の顔へと視線を向けた。
すると、丁度鈴音も困ったように連示の方を見たため、図らずして見詰め合う形になってしまう。瞬間、彼女は頬を軽く紅潮させて顔を背けてしまった。
「た、大した理由じゃないよ。そもそもアミクスに嫌なことを押しつけて、っていうのが余り好きじゃないし。その、アミクスを学校に行かせても、私はどうせ家に引きこもって勉強したり、一人で適当に遊んだりするだけだから」
それから焦ったように早口で言う。
「そうなの? 鈴音ちゃん、人当たりがよくて、友達とかすぐできそうなのに」
ユウカの言葉に連示は内心で同意した。鈴音とはほぼ毎日話をしているが、彼女の自己分析は連示の中の印象とは大分異なっていた。
「それは……私って結構人見知りが激しいから。打ち解けると大分話せるんだけど。世良君達と話すようになったのも、二人が話しかけてくれたからだし」
「そういえば、ああ、そうだった、かな」
八ヶ月程前、突然アミクスではなく鈴音本人が学校に来て、一人ぽつんと座っていたため、ユウカと一緒に話しかけたのが確か最初だった。
あの当時、鈴音は丁度真後ろの席で、朝普段通りに教室に入って自分の席の辺りを見た時に抱いた驚愕は今でも覚えている。
確か、鈴音のアミクスは他のアミクスの輪には余り入らずに静かに本を読んでいるような文学少女風だった気がするが……。
「でも、あの時は何でいきなりアミクスに登校させるのを止めたんだ? 嫌なことを押しつけるのが好きじゃない、って言っても何か切っかけみたいのがあったんじゃないか?」
「そ、それは――」
何故かちらっと視線を向けてくる鈴音。
「それは?」
「な、内緒っ」
結局そう小さく呟いて恥じらうように顔を背けてしまった鈴音の姿は、その大人びた顔つきとのギャップのせいか可愛らしく見える。
この反応は少し卑怯だ。
「連示君!」
そんな鈴音に思わず目を奪われていると、ユウカにきつく睨みつけられてしまった。
しかも、あからさまに不満を表すように唇をこれでもかというぐらいに分かり易く尖らせている。そんな彼女の様子に連示は微苦笑してしまった。
「そう言えば、世良。知っているか?」
そこで一つの話題が終了したと思ったのか、弁当を食べ終わったからなのか、それまで黙っていた紀一郎が口を開き、皆の注意が彼に集まる。
「何を?」
「ファントム、だ」
一応、小学校以下ではアミクスの使用は制限されているが、この先は分からないし、全体から見れば微々たるものだ。
アミクスが人型であるが故に歪に感じてしまうが、これも一種のオートメーション化ではある。見方によっては、むしろ自動化の極致に近づいていると言っていい。ただし、過去の人々が次の段階として思い描いたものとは大きく異なるだろうが。
勿論、過去のイメージ通りの極めて機械的なオートメーション化もない訳ではない。
ただ、アミクスの登場によってその言葉のイメージが大幅に拡大したのは確かだ。
それは偏に、現在いわゆる求人があるのは一般人との接点が多い三次産業がほとんどとなり、そして、そこにアミクスが従事しているからだ。
アミクスは機械的な行動ではなく所有者の人格を模した極めて人間的な行動を取る。
そのため、それを見た人間は人の温かさを感じるのだそうだ。
そうした理由で、人の温かさなど大した価値にならない一次産業や二次産業の大部分では旧来のオートメーション化が進み、三次産業の多くではアミクスを主体とした新たな形のそれが進んでいる訳だ。
とは言え、最初期では多くの人が所有者の人格を模している点に性能的な部分で不安を感じ、アミクスを使用して人間的な温かみを取るか、旧来のオートメーション化で能率を取るかの二択だと考えていたらしい。
しかし、本質的にはアミクスもまた機械であるため、それ以上に機械を操作できる機械であるが故に、総合的な能率もアミクスを利用した方が遥かによかったとのことだ。
人間と違って体調に左右されず、その上公共機関内では制限があるものの身体的な面でも人間より遥かに優れている。加えて機械としての処理能力の高さをも有している。
そんなアミクスを使用すれば、無機質なオートメーション化が霞むのは当然だ。
勿論、それが想定通りの働きをすれば、だが。
実際のところ、その点では大きな問題はないと聞く。
ただ、アミクスには別の部分に大き過ぎる欠陥があった。
本来アミクスは、人間や他のアミクスとのコミュニケーションを円滑に行うように設定されている。それは所有者の人格に従いながらも、ネットワークを介して過去の様々な事例を参照し、その場その場で最適の行動を選び取るというものだ。
それにより、たとえ人格的に相性の悪い相手でも最低限の関係を結ぶことができる。
アミクスが普及し始めた最初期の状態では、その機能に問題などなかった。所有者の人格に行動パターンの取捨選択のウエイトが大きく置かれていたため、人間に対する言動も全く自然だった。
そう。確かに温かみすら感じさせる程に。
だが、現在。アミクスが世界に氾濫している現状では、アミクス間のネットワークが急激に肥大化してしまい、結果、コミュニケーションの対象としての人間の優先度が下がってしまったのだ。
アミクスが意思伝達すべきはアミクス。
そんな状況が多くなり、アミクスは自ら進んで人間とコミュニケーションを取ろうとはしなくなってしまった。とは言っても、当然人間の側から話しかければ相応の対応は行うため、問題として顕在化していないのだが。
それを違和感として認識できるのは、アミクスと長時間接する環境にある者、つまりは学校や職場にわざわざ生身で通っているような人間だけだ。
しかし、そのような物好きは余りにも少なく、そのマイノリティーがどれだけ声を上げようとも大勢に影響は与えられない。
大半の人間は生産行為をアミクスに任せ、自分達は娯楽の世界に引きこもっている。
アミクスと接する機会自体がもはや少なく、誰も気にしていない。
たとえ気づいたとしても、己の退廃的な生活を守るために無視する可能性が高い。
大多数の人間に実害が出ていない以上は。
結局のところ、これは感情論。好き嫌いの問題に過ぎないのかもしれない。
連示もまずアミクスに対して疑問を抱いていなければ、そのような事態を確かな形で目の当たりにしても、ここまでの嫌悪を抱かなかったに違いないから。
連示は気づかれない程度の小さな動きで、惣菜パンを小さく開けた口で少しずつ食べている鈴音へ、それから黙って姿勢よく弁当を食べている紀一郎へと視線を移動させた。
この二人とこうして友人になれたのは、他のクラスメイトがアミクスだったから、と言うこともできる。
現在のアミクスは話しかけない限り、人間の存在はないものとして振舞い、アミクス同士で表面的な関係を結ぶ。
だから、アミクスが大半を占める集団では人間は人間同士でいるしかない。
本来はそのはずなのだ。
「お前も――」
連示は、まだ隣で俯いて物憂げに座っているユウカへと顔を向けた。
「本当だったら、遊香のアミクスとして他のアミクスとコミュニケーションを取る必要があるんじゃないか?」
そんな欠陥があるはずのアミクスの中で、ユウカは連示が知る限り唯一の例外だった。
「でも、わたしは連示君と一緒にいたいんだもん。幼馴染だし」
彼女が他のアミクスと一緒にいる姿を見たことはない。
それどころか、他のアミクスなど関係ない、という感じで学校ではいつも傍から離れないのだ。それが連示は不思議で仕方がなかった。
「幼馴染って言っても、な……」
そもそも、遊香本人とは中学校に入ったぐらいから疎遠になっていた。
いや、疎遠どころか関係が消えてしまったと言った方がいい。
それはアミクスを使用していい段階、中学生になっても連示がアミクスを厭い、使用しなかったことが原因だ。その頃から鈴音と話をするようになるまでの間、幼馴染どころか生身の人間自体と接する機会が失われていたのだから。
それなのにユウカは、中学校のいつの頃からだったか、以前以上に真っ直ぐな好意を向けてくるようになった。
そして、今に至っているのだ。
正直に言えば、そんな彼女の態度に連示も悪い気分はしなかった。
だが、それは余りにもアミクスらしからぬ行動だったため、どこかにバグがあるのではないか、という疑いも同時に抱き続けていて素直に喜べずにいた。
「まあ、いいけどさ」
しかし、結論はいつもそうなる。
学校に来ればすぐに寄ってくるのはたまに疎ましく感じることもない訳ではないが、ユウカのことが嫌いという訳では決してない。むしろ好きだと言っていい。
だから、連示はアミクスに否定的ではあったが、心の中では彼女は例外として扱っていた。そも、アミクスを安易に使用して堕落している人間こそが反感の対象なのだから。
「わたしより鈴音ちゃんだよ。どうしてアミクスを使わないの?」
「別にアミクスを使ってない訳じゃないよ。家では多分あの子が勉強してるだろうし。まあ、世良君を見てるとそれも邪道な気がしちゃうけど、私は余り頭がよくないからさ」
「そうだったの? え、でも、じゃあ、何で?」
かねてから興味のある話だったため、連示は鈴音の顔へと視線を向けた。
すると、丁度鈴音も困ったように連示の方を見たため、図らずして見詰め合う形になってしまう。瞬間、彼女は頬を軽く紅潮させて顔を背けてしまった。
「た、大した理由じゃないよ。そもそもアミクスに嫌なことを押しつけて、っていうのが余り好きじゃないし。その、アミクスを学校に行かせても、私はどうせ家に引きこもって勉強したり、一人で適当に遊んだりするだけだから」
それから焦ったように早口で言う。
「そうなの? 鈴音ちゃん、人当たりがよくて、友達とかすぐできそうなのに」
ユウカの言葉に連示は内心で同意した。鈴音とはほぼ毎日話をしているが、彼女の自己分析は連示の中の印象とは大分異なっていた。
「それは……私って結構人見知りが激しいから。打ち解けると大分話せるんだけど。世良君達と話すようになったのも、二人が話しかけてくれたからだし」
「そういえば、ああ、そうだった、かな」
八ヶ月程前、突然アミクスではなく鈴音本人が学校に来て、一人ぽつんと座っていたため、ユウカと一緒に話しかけたのが確か最初だった。
あの当時、鈴音は丁度真後ろの席で、朝普段通りに教室に入って自分の席の辺りを見た時に抱いた驚愕は今でも覚えている。
確か、鈴音のアミクスは他のアミクスの輪には余り入らずに静かに本を読んでいるような文学少女風だった気がするが……。
「でも、あの時は何でいきなりアミクスに登校させるのを止めたんだ? 嫌なことを押しつけるのが好きじゃない、って言っても何か切っかけみたいのがあったんじゃないか?」
「そ、それは――」
何故かちらっと視線を向けてくる鈴音。
「それは?」
「な、内緒っ」
結局そう小さく呟いて恥じらうように顔を背けてしまった鈴音の姿は、その大人びた顔つきとのギャップのせいか可愛らしく見える。
この反応は少し卑怯だ。
「連示君!」
そんな鈴音に思わず目を奪われていると、ユウカにきつく睨みつけられてしまった。
しかも、あからさまに不満を表すように唇をこれでもかというぐらいに分かり易く尖らせている。そんな彼女の様子に連示は微苦笑してしまった。
「そう言えば、世良。知っているか?」
そこで一つの話題が終了したと思ったのか、弁当を食べ終わったからなのか、それまで黙っていた紀一郎が口を開き、皆の注意が彼に集まる。
「何を?」
「ファントム、だ」
0
お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

3024年宇宙のスズキ
神谷モロ
SF
俺の名はイチロー・スズキ。
もちろんベースボールとは無関係な一般人だ。
21世紀に生きていた普通の日本人。
ひょんな事故から冷凍睡眠されていたが1000年後の未来に蘇った現代の浦島太郎である。
今は福祉事業団体フリーボートの社員で、福祉船アマテラスの船長だ。
※この作品はカクヨムでも掲載しています。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく


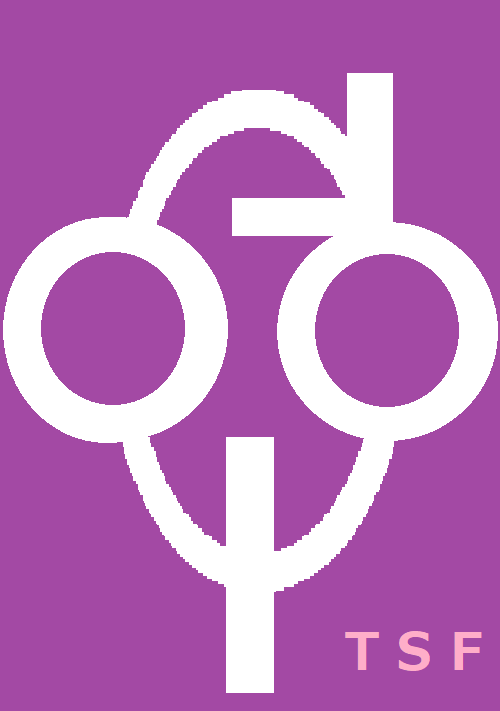

EX級アーティファクト化した介護用ガイノイドと行く未来異星世界遺跡探索~君と添い遂げるために~
青空顎門
SF
病で余命宣告を受けた主人公。彼は介護用に購入した最愛のガイノイド(女性型アンドロイド)の腕の中で息絶えた……はずだったが、気づくと彼女と共に見知らぬ場所にいた。そこは遥か未来――時空間転移技術が暴走して崩壊した後の時代、宇宙の遥か彼方の辺境惑星だった。男はファンタジーの如く高度な技術の名残が散見される世界で、今度こそ彼女と添い遂げるために未来の超文明の遺跡を巡っていく。
※小説家になろう様、カクヨム様、ノベルアップ+様、ノベルバ様にも掲載しております。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















