19 / 64
2巻
2-3
しおりを挟む
それにしても、あと一つ空いた契約可能枠はなにに使おうか。そろそろ空を飛ぶ魔物が欲しいなあ。俺を乗せることができなくてもいいから、高所から偵察とか地形を判断できる奴がいい。
ぼんやりしていると、わらわらと俺に群がってくる狐たち。
右を見ても左を見ても、狐色でいっぱいだ。そして多くの狐が人化術を使用した。中には人化術を持たない地狐もいたから、皆が皆、人化できるわけでもないんだろう。
そうして人の姿になると、誰もが女性である。男性の姿はない。となれば、これが美女がいるという噂の理由だったのだろうか。
彼女たちの後ろで揺れる尻尾が、頭の上で小さく動く狐耳が、人ではないことを知らせてくれる。
しかし、それは些細なことに過ぎないだろう。いや、むしろ彼女たちの魅力を引き立てていると言える。やはり見た目は大事なのである。
この世界に来ることがなければ、絶対にあり得なかった体験だ。俺は存分に味わおうと決意する。
そんな彼女たちを代表して、クーナが頭を下げた。
「ありがとうございました。皆、感謝しています」
「ああ、うまくいってよかったよ」
「はい。では、宿にご案内しますので――」
クーナが出口を示した瞬間、奥から呻き声が上がった。
俺はぎょっとして、そちらに振り向く。なにやら隔離されているらしく、中は見えない。
人里から攫ってきた人に対して、あんなことやこんなことをしている、というのはないだろうが、聞こえてきたのは確かに人のものだ。
狐たちは用がなければ人化しないようだから、なにかある、と見て間違いない。
俺はどうにも気になって、つい視線を泳がせてしまう。クーナと姫さんは困ったように顔を見合わせていたが――
「オークの被害者です」
「怪我をしているのか?」
それならば治せばいいのではないか、と俺は思う。
しかし、そういうわけでもないようだ。実に言いにくそうに、クーナは言葉を濁す。
「ご覧になるのが一番早いでしょう。惨いものですが、それでもよろしいでしょうか?」
そう言われると、不安になってくる。しかし、なにも知らずに呑気に寝ていられるほど、俺は不用心でもなかった。傭兵としての経験がそれなりに長く、依頼で騙されたことがあるのも影響しているのかもしれない。
クーナが先頭を行き、部屋を隔てている幕を引く。元狐の美女たちは、ついてこなかった。そういう場所ではない、ということだろう。
先に中を目の当たりにしたらしい姫さんの表情が暗くなる。そして俺もまた、そこにある光景を見て震え上がった。
腹の膨れた狐たちがいたのだ。そしてたった一人、同様の腹をした狐耳の女性がいる。彼女たちは皆、苦悶の表情を浮かべていた。意識も朦朧としているようで、口から涎を垂らしている者さえいる。
クーナは彼女たちをオークの被害者だと言った。
ともすれば、この原因を作ったのは、間違いなくオークたちである。
「これは……」
「オークはほかの種族に子を寄生させることで、繁殖してきました」
姫さんが言う。声音には、なんの感情も込められていないようでいて、しかしその奥には深い悲しみが見え隠れしている。
ようやく俺は、あらゆる記憶が繋がった。
ここにいる狐たちが怪我をしていたこと。そしてクーナが俺と会ったときに言った、オークたちがほかの魔物を襲って繁殖してきており、動けなくするのが常套手段ということ。理由はすべて、この繁殖様式を取ってきたからだ。
そしてかつて行った、渓谷にあるオーガの洞窟。あそこにあった豚の尻尾は、オークのものだったのだろう。
飛び散っていた血肉は、オークのものだけではない。オークが成長する際、宿主であるオーガの肉を食らったのだ。細長いものはおそらく、臍帯の類だ。
俺はなにも言うことができず、しばし間が空いた。
「オークに寄生された者は、やがて痩せ衰えていきます。自ら命を絶つ者も少なくありません。生まれるときに出血で死に至るばかりか、生き延びても気が触れずにいられる者はほとんどいません」
哺乳類で寄生する動物は聞いたことがないが、そもそも魔物がそのような区分に当てはまると考えるほうがどうかしていよう。
つまるところ、オークは無性生殖の形態を取っていたのだ。仮に雌雄が存在していたとすれば、雌が単為生殖で卵を産みつけたとなる。あるいはすでにある受精卵をほかの動物に寄生させることで、いわゆる托卵のようなものを胎生の形式で行うのかもしれない。
なんにせよ、胸糞悪くなる話であることには違いなかった。
「これは病でも怪我でもありません。ですから、先のようには――」
姫さんが首を横に振る。
俺はこの有様を見て、歯噛みせずにはいられなかった。ほかの集団を淘汰して繁栄することが自然の摂理だとしても、感情的に許せないことがある。
本当に、なにもできないというのだろうか。ならば、俺はいったい、なんのためにここにいるのだろう。なんのために進んできたというのだろう。
出会ったばかりの彼女たちに、そこまでする義理はない。けれど、見捨てていくことができるほど、俺は割り切れる性格でもなかった。
考えろ。あらゆる可能性を探れ。
なにかしらの方法があるはずだ。
目的は、体内のオークを取り除くこと。条件は、地狐を傷つけないことくらいだ。
俺は周りの声が聞こえなくなるほど深く、考えに没頭する。
切開して取り出すのは無理だ。俺にそんな技術はないし、なにより器具がない。狐の生体構造もわからない。
ならば投薬での治療か? オークとの差異があれば、うまくオークだけを仕留めるようなものもできるかもしれない。だが、そんな悠長なことを言ってもいられない。刻一刻と成長しているのだから。
そこで俺はオークの発生にヒントがあるかもしれないと考える。産みつけられた子オークは、宿主の栄養を奪い、体内で成長していく。その過程で、親オークが介入することはない。
そうしてひたすら考えていく。そしてとある考えが浮かんできた。
――あった。こんなにも単純で、俺にしかできないことが。
俺はクーナと姫さんに向き直って告げる。その剣幕に、二人は気圧されてしまったようだ。
「彼女たちの命を、俺に預けてもらえませんか」
迷いはなかった。失敗することが怖くないわけじゃない。けれど、なにもせずに救えないのはもっと嫌だったから。
覚悟は伝わったのだろう。先の実績もある。二人は小さく頷いた。
そして俺は呻く女性へと近づいていく。美しい肢体は無造作に投げ出されており、顔は苦痛に歪んでいる。
もがく彼女は俺を視認することもなく、ただのた打ち回っていた。
俺はこれからするべきことを、俺の意思を、魔物たちに伝える。するとぱたぱたとライムが駆け寄ってきた。ゴブとウルフが入っているケダマがやってきた。
そんな魔物たちの様子を見て、俺は少しばかり安心していた。きっと、これからも協力してくれるから。
ゆっくりと主従契約を発動させる。浮かび上がった魔法陣は、女性の中へと潜っていく。そして一瞬の時間遅れもなしに、魔法陣が下方に出来上がった。契約が成立したということだ。
しかし、そのサイズは女性の体に比するとかなり小さい。
つまり――
「オークとの契約が成立しました」
姫さんが息を呑み、クーナの顔が驚きに染まる。しかし、二人とも一言も発しなかった。俺に任せることにしたからだ。たとえどれほど尋ねたいことがあったとしても、彼女たちはなにも言わなかったに違いない。
オークが寄生しているだけならば、地狐とは別の魔物と認識されると予想したが、果たしてその通りになったのだ。そして女性の肉体が障壁となるかと思ったものの、主従契約のスキルは任意の相手以外には影響を及ぼさないようにできるようだ。
体内にいるオークが拒絶したならば、契約は成立することはなかった。しかし、生まれたての魔物には意思がないため主従契約はいとも容易くなされる、というのを聞いていたこともあって、主従契約さえ発動できればうまくいくはずだと踏んでいた。
まずは一つ目の関門を突破したと言えよう。しかしまだ安心はできない。
俺は一つ息を吐きながら次の行動に移る。いや、正確には俺ではない。俺たちだ。
契約ができたところで、地狐の体内にいるオークに直接干渉することはできない。そこで、魔物同士を合成することにしたのだ。
「魔物合成」は複数の魔物から新しい魔物を合成して強くしたり、一体をベースに経験値を増やしたりするスキルだが、それによって体内からオークを消すことができると考えたのである。
合成した魔物が一体を残して消えていることからそう判断したが、安全性を確認しているわけではなく、かといって今から実験していては間に合わなくなる可能性が高い。それに、このように体内に寄生された状況は、ほかの魔物ではそうそう見られないだろう。
やはりどこかで、決断はしなければならない。危険を承知でやらねばならないときがある。
ライムはそんな俺に、にっこりと微笑み、
「大丈夫」
とだけ告げるなり、魔法陣に触れた。途端、小さかった陣が拡大されていく。いつもよりも少しばかり大きくなったその中で、彼女は変わらずに微笑んでいる。
そしてライムの姿が光に包まれた。
やがて光が消えると、そこには変わらぬライムの姿があった。合成の際、新たな魔物になるのではなく、経験値を得るほうを選んだのだろう。いかに人型とはいえ、豚の特徴を取り込むのは嫌だったに違いない。
「ありがとうな、ライム」
「えへへ」
俺の行為を後押ししてくれたライムに礼を言いつつ女性を見ると、腹の膨らみは多少マシになっていた。呼吸も落ち着きつつある。
しかしだからといって、完全に治りきったと断定はできない。オークが消えたことで、どこかに出血などが起こる可能性があるからだ。
俺は彼女の脈を取ったり、バイタルサインを確認したりする。そうしていると、彼女はぼんやりと、俺のほうを見る。
「大丈夫ですか?」
彼女は小さく頷いた。どうやら、意識は戻ってきており、ひとまずは問題なさそうだ。これで一人目はおそらく助かったのだろう。
彼女の症状の経過を見てから、ほかの狐たちに対応していくほうがいいのだろうが、もうすでに限界まで達しているものもいるようだ。
たとえ問題があろうと、オークが腹を食い破って出てくるよりは出血も少ないはずだ。
俺は姫さんたちに伝え、オークの成長が早い狐から、この手法を行っていくことにした。直接は視認できないため鑑定は使えず、主従契約だけが頼りになる。
今回もスキルを発動させると、魔法陣は外れることはなく吸い込まれていき、契約が成立する。これによってようやく、俺は魔物の正体を確認することができるようになった。
《オークロード Lv1》
ATK33 DEF29 MAT6 MDF11 AGI11
【スキル】
「精力増強」
これは……どうやらオークの上位魔物らしい。オークが成長して進化するのではなく、生まれたときから決まっているようだ。
この魔物、かなり初期ステータスが高い。俺が連れている魔物と違って、野生の魔物ゆえに最大値になっていないことを考えると、これまで遭遇した魔物の中では一番強いかもしれない。
それでもここにいる地狐たちのほうがステータスは上だ。となれば、狐たちが負けた理由はほかにあるのだろう。
たとえば、この繁殖力。数の不利はそう簡単に覆せやしない。
と、そんなことを考えている場合ではなかった。魔物が強力ならばなおさらのこと、早く処置しなければならない。
俺がなにかを言わんとしたときには、すでにゴブが魔法陣に駆け寄っていた。なにやらやる気に満ちているらしい。
大丈夫なんだろうか、こいつで。
そんな疑問を抱いたときには、すでにゴブの姿は光に包まれていた。
しかし、どんな魔物だろうが、これまで合成には成功してきたのだ。失敗する確率はかなり低いだろう。たとえゴブであっても。
光が収まると、そこには容態の落ち着いた地狐と、素潜りゴブリンがいた……いや、違う。こいつ、進化するタイプの合成を選んだようだ。だから張り切っていたのだろう。もしかすると、このパーティで一体だけ弱いことを気にしていたのかもしれない。
だが……どうにも強そうには見えない。
体を覆っていた鱗はなくなり、今は緑というよりは茶色に近い、つるっとした体になっていた。やや大柄にもなっている。
特にそれくらいしか違いが見当たらないな、と思いながら見ていると……重大な違いがあった。
豚鼻になっている!
よく見れば尻尾もあった。くるんと巻いた豚の尻尾だ。
……引き継いだの、ロードのほうじゃなくて、豚の成分かよ。
俺はあまり期待せずに、ゴブのステータスを確認する。
《ブタゴブリン Lv1》
ATK26 DEF25 MAT8 MDF16 AGI25
【スキル】
「土魔法Lv1」「精力増強」
ふざけた名前と見た目のくせに、ステータス高いな。ほかの魔物たちに追いついたかもしれない。
おそらくマーマン成分がなくなっているのだろう。水魔法が消えている。しかしこちらはライムが持っているため、特に問題はない。
しかし、精力増強まで引き継ぐとは……これ、俺にも反映されているようだ。
何事にもやる気で満ち溢れるのはいい。そういうことにしておこう。
俺は地狐の様子を眺める。そもそも狐の肉体に関して詳しいわけでもないので、魔物である地狐に関してはなおさらわからない。
それゆえにクーナたちに状態を確認してもらう。二人は狐に触れたりして具合を確かめ、やがて安心したような表情を浮かべる。どうやらこちらも成功だったらしい。
ぐったりしていた狐は、小さく鳴いた。
それから俺は主従契約を用いて、ほかの地狐に寄生しているオークを取り除いていく。あとは順調に進んでいった。
十数体の地狐に対して契約を終えたとき、俺は精神的にも肉体的にもすっかり疲れ切っていた。もう動くのも嫌になって、そこらの床に大の字に寝転がる。すかさずケダマが転がり込んできて枕になった。
そうなると、強烈な眠気が襲ってくる。どうやら、スキルを使いすぎるとこうなるようだ。体が疲労を取り除くべく、休養を欲している。きっと、強い精神力さえあれば耐えきれるのだろう。しかし、俺はやり遂げた安心感もあって、そのまま心地いい微睡みに身を任せた。
そんな俺をライムが覗き込んで、小さく笑う。
ゴブが頑張って俺の体を持ち上げて、小型化を解除したウルフの背に乗せる。あんなにも頼りなかったというのに、力持ちになったようだ。
そんな奴は張り切っているのか鼻息が荒い。
「ぶひぶひ」
……豚成分、そんなとこにまであったのかよ。
俺はどこか抜けているゴブに呆れつつ、ウルフに運ばれていった。こいつらに任せておけば、大丈夫だろう。
今日は少し、働きすぎたのであった。
3
クーナ・ルイアは社にいた。
彼女の視線の先には、敬愛する姫がいる。けれど、歓談するような雰囲気とは程遠い。
この日、クーナにとってはあまりにも多くのことが起きた。感情と理性のどちらでも、とても理解できないことが一気に押し寄せてきたのだ。
「姫様……申し訳ありませんでした、私のせいで――」
姫は目を伏せる。クーナには、彼女の思いもよくわかった。けれどそれ以上に、自分の不甲斐なさが悔しくて悔しくて仕方がなかった。
今日、クーナは仲間を連れて、侵略してきたオークたちに立ち向かっていった。このままでは、この地すべてを奴らに奪われてしまうことがわかっていたからだ。
オークという種族に対して、地狐は能力的には優れていると言える。そしてクーナはその中でも多くの戦いを経験してきた自負があった。ほかの誰よりもうまく戦える技術があった。
けれど……結果はついてこなかった。
今朝、多くの仲間を引き連れてオークを奇襲すると、快進撃が始まった。そこまでは当初の予定通りで、群がるオークはどれほどいようが、蹴散らせると思っていた。
しかし、それはただの時間稼ぎに過ぎなかったのだろう。
気がついたときには、数体の巨大なオークがいた。奴らは力強く、こちらの攻撃などものとはしなかった。ステータスの差がかなりあったに違いない。
やがて一人、二人と同胞が倒れていく。そのときの光景は今でも目に焼きついて離れない。
彼女たちはきっと、今もオークの住処に捕らわれているだろう。そのことを思うと、クーナはぐっと奥歯を噛み締めた。
それから、クーナは少しでも多くの仲間を助けるために、彼女たちを置いて、無事な者たちとともに逃げたのだ。
その選択が間違いだったとは思わない。けれど、だからといって納得はできやしなかった。なにか別の方法があったのではないかと、ずっと悩み続けている。
「そのようなことをおっしゃらないでください、クーナ。あなたのせいではありません。ただ、私に力がなかった、それだけのことなのです」
姫はそう言って、クーナを慰める。
彼女は、地狐が進化した種族である天狐が年老いてからなる種族、空狐であった。かつては天狐として、絶大な力でこの集落を守ってきた。
しかし、今はどうだろうか。もう戦いに関して十分な力はない。
そのことはクーナもわかっていた。だから、なおさら押し黙るしかできなかった。
しばしの無言。平時ならば、話題は尽きることはなかった。年齢や経験の差など気にならないほど、クーナは姫のことが好きであったし、姫もまたこの友人を我が子のように思っていたからだ。だというのに、今は過ぎゆく時間が重かった。
クーナは今日一日のことを思い返す。どこで間違ったんだろう。どこで失敗したんだろう、と。けれど最後までわからなかった。結局、力がなかった、という一言で片づけてしまうしかないのか。
そうしているうちに、彼女は一つの出来事を思い浮かべた。彼女が囮となって、ほかの地狐たちを逃したあとのことだ。
もちろん、無事で逃げ切れるなんて甘い考えを持っていたわけではない。しかし、運悪く足を怪我してしまったことが影響し、オークたちに追いつかれて利き足をやられた。
奴らの動きは早いとは言い難いが、そのような状況では逃げることなどかなわない。
死を覚悟したとき、飛び込んでくるものがあったのだ。
人間だ。
この里の周辺には霧がかかっている。昔話によれば、かつてここを訪れた魔物使いが、ほかの人間による侵略を受けないように張った結界だそうだ。だからクーナが人を見たのはこれが初めてだった。
そしてその男は、連れている魔物とともに、オークどもを蹴散らした。なんと魔法が使えたのだ。おそらくは魔物を従えるスキルを持つ魔物使いなのだろう。
だからクーナは矜恃をもって言った。人に囚われる気はない、と。
それでも男は引き下がらず、あろうことか、頭まで下げてきた。人間は傲慢だと聞いていたが、とてもそうは見えなかった。
頼りになるばかりか、真剣な表情で接してくる姿を見ると、昔話で魔物使いのことを聞いていたのもあって、つい……ちょっとだけならいいかなあ、と思ってしまった。あとから逃げるのでも遅くはない。
主従契約を受け入れるなり、足の痛みはなくなった。体中の怪我という怪我が治っていたのだ。
驚きはそれだけではなかった。いや、それ以上に大きかったかもしれない。
男はさっさと主従契約を解除してしまったのだ。
そのままにしておけば、恩とともに見返りを求めることだってできたはずだ。しかし、まったくそんな素振りは見せなかった。本当に、ただ助けたいがために行ったことなのだろう。
信頼のおける人だと思った。いいなあ、と思ってしまった。
だから、彼が迷っていると知るなり、里に案内することにした。
しかし、その言葉が出たところは、純粋な歓迎だけではない。
人間よりも自分のほうがよほど不誠実なのではないか、という気がしたが、それでも彼の力ならば、傷ついた同胞を助けられる。
そんな打算――いや、ちょっとした期待、実現しない儚い夢のような思いを抱きながら里に戻ってきたのだが、彼は怪我を治すばかりか、オークに寄生された者たちまで救ってしまった。ここでも、見返りなんて求めることはなかった。
そのときの彼の真剣な横顔を思い出すと、クーナの胸中に満ちていた後悔と不安が、ほんの少しだけ和らいでいく。初めて抱いた感情だった。
姫との間に満ちた重い空気を変えるのにもいいだろう、とクーナは彼について言及する。
「……あの方、いつまでいるのでしょうか?」
この里に用があってきたわけではない。オークに狙われているとわかれば、さっさと帰るのが妥当なところだろうから、その質問はあまり意味をなさなかった。
けれど、姫は優しい笑みを浮かべる。
「いつまでもいてほしい、ということですか?」
「ち、違います! そのようなことは!」
クーナはあからさまに狼狽えた。誰が見てもわかるほどに。顔はすっかり赤らんでいる。
しかしそんな表情もすぐに変わって、小さな声で続ける。
「私はただ……あの方のお力があれば、苦しまずに済む者がいるのではないかと、思うのです」
それは本心だろうか。嘘ではないことは確かだ。
だが、事実をぴたりと言い表しているかといえば、クーナにもよくわからなかった。その正体がわからない感情が、胸の中にあったからだ。
「では、クーナからお願いしてはいただけませんか?」
「私から、ですか?」
「ええ……あれは伝説のようなものですが、今の状況によく似ているでしょう?」
彼女の言う伝説とは、昔あった出来事のことだ。彼女が天狐になったのも、そのときである。
クーナはしばし戸惑ったようだったが、すぐに表情を引き締める。
「わかりました。このクーナ、必ずや、やり遂げてみせましょう」
さながら戦いに赴くときのように、力強く答える。
彼女の迷いはもう消えていた。
退室していく小さな友人を見ながら、姫は目を細めた。
きっと、この集落は長くは持たない。オークに勝てる見込みなんてほとんどないのだから。けれど、姫がここを去るわけにはいかない。長として、誰一人いなくなるまでは、逃げることなどできやしなかった。
だから、クーナには――あの青年にはちょっと悪いかもしれないけれど――一緒に外の世界に行ってくれれば、と思ったのだ。
やがてクーナが退室すると、静寂が訪れた。
姫はいつまでも、彼女が出ていった扉を眺めていた。
ぼんやりしていると、わらわらと俺に群がってくる狐たち。
右を見ても左を見ても、狐色でいっぱいだ。そして多くの狐が人化術を使用した。中には人化術を持たない地狐もいたから、皆が皆、人化できるわけでもないんだろう。
そうして人の姿になると、誰もが女性である。男性の姿はない。となれば、これが美女がいるという噂の理由だったのだろうか。
彼女たちの後ろで揺れる尻尾が、頭の上で小さく動く狐耳が、人ではないことを知らせてくれる。
しかし、それは些細なことに過ぎないだろう。いや、むしろ彼女たちの魅力を引き立てていると言える。やはり見た目は大事なのである。
この世界に来ることがなければ、絶対にあり得なかった体験だ。俺は存分に味わおうと決意する。
そんな彼女たちを代表して、クーナが頭を下げた。
「ありがとうございました。皆、感謝しています」
「ああ、うまくいってよかったよ」
「はい。では、宿にご案内しますので――」
クーナが出口を示した瞬間、奥から呻き声が上がった。
俺はぎょっとして、そちらに振り向く。なにやら隔離されているらしく、中は見えない。
人里から攫ってきた人に対して、あんなことやこんなことをしている、というのはないだろうが、聞こえてきたのは確かに人のものだ。
狐たちは用がなければ人化しないようだから、なにかある、と見て間違いない。
俺はどうにも気になって、つい視線を泳がせてしまう。クーナと姫さんは困ったように顔を見合わせていたが――
「オークの被害者です」
「怪我をしているのか?」
それならば治せばいいのではないか、と俺は思う。
しかし、そういうわけでもないようだ。実に言いにくそうに、クーナは言葉を濁す。
「ご覧になるのが一番早いでしょう。惨いものですが、それでもよろしいでしょうか?」
そう言われると、不安になってくる。しかし、なにも知らずに呑気に寝ていられるほど、俺は不用心でもなかった。傭兵としての経験がそれなりに長く、依頼で騙されたことがあるのも影響しているのかもしれない。
クーナが先頭を行き、部屋を隔てている幕を引く。元狐の美女たちは、ついてこなかった。そういう場所ではない、ということだろう。
先に中を目の当たりにしたらしい姫さんの表情が暗くなる。そして俺もまた、そこにある光景を見て震え上がった。
腹の膨れた狐たちがいたのだ。そしてたった一人、同様の腹をした狐耳の女性がいる。彼女たちは皆、苦悶の表情を浮かべていた。意識も朦朧としているようで、口から涎を垂らしている者さえいる。
クーナは彼女たちをオークの被害者だと言った。
ともすれば、この原因を作ったのは、間違いなくオークたちである。
「これは……」
「オークはほかの種族に子を寄生させることで、繁殖してきました」
姫さんが言う。声音には、なんの感情も込められていないようでいて、しかしその奥には深い悲しみが見え隠れしている。
ようやく俺は、あらゆる記憶が繋がった。
ここにいる狐たちが怪我をしていたこと。そしてクーナが俺と会ったときに言った、オークたちがほかの魔物を襲って繁殖してきており、動けなくするのが常套手段ということ。理由はすべて、この繁殖様式を取ってきたからだ。
そしてかつて行った、渓谷にあるオーガの洞窟。あそこにあった豚の尻尾は、オークのものだったのだろう。
飛び散っていた血肉は、オークのものだけではない。オークが成長する際、宿主であるオーガの肉を食らったのだ。細長いものはおそらく、臍帯の類だ。
俺はなにも言うことができず、しばし間が空いた。
「オークに寄生された者は、やがて痩せ衰えていきます。自ら命を絶つ者も少なくありません。生まれるときに出血で死に至るばかりか、生き延びても気が触れずにいられる者はほとんどいません」
哺乳類で寄生する動物は聞いたことがないが、そもそも魔物がそのような区分に当てはまると考えるほうがどうかしていよう。
つまるところ、オークは無性生殖の形態を取っていたのだ。仮に雌雄が存在していたとすれば、雌が単為生殖で卵を産みつけたとなる。あるいはすでにある受精卵をほかの動物に寄生させることで、いわゆる托卵のようなものを胎生の形式で行うのかもしれない。
なんにせよ、胸糞悪くなる話であることには違いなかった。
「これは病でも怪我でもありません。ですから、先のようには――」
姫さんが首を横に振る。
俺はこの有様を見て、歯噛みせずにはいられなかった。ほかの集団を淘汰して繁栄することが自然の摂理だとしても、感情的に許せないことがある。
本当に、なにもできないというのだろうか。ならば、俺はいったい、なんのためにここにいるのだろう。なんのために進んできたというのだろう。
出会ったばかりの彼女たちに、そこまでする義理はない。けれど、見捨てていくことができるほど、俺は割り切れる性格でもなかった。
考えろ。あらゆる可能性を探れ。
なにかしらの方法があるはずだ。
目的は、体内のオークを取り除くこと。条件は、地狐を傷つけないことくらいだ。
俺は周りの声が聞こえなくなるほど深く、考えに没頭する。
切開して取り出すのは無理だ。俺にそんな技術はないし、なにより器具がない。狐の生体構造もわからない。
ならば投薬での治療か? オークとの差異があれば、うまくオークだけを仕留めるようなものもできるかもしれない。だが、そんな悠長なことを言ってもいられない。刻一刻と成長しているのだから。
そこで俺はオークの発生にヒントがあるかもしれないと考える。産みつけられた子オークは、宿主の栄養を奪い、体内で成長していく。その過程で、親オークが介入することはない。
そうしてひたすら考えていく。そしてとある考えが浮かんできた。
――あった。こんなにも単純で、俺にしかできないことが。
俺はクーナと姫さんに向き直って告げる。その剣幕に、二人は気圧されてしまったようだ。
「彼女たちの命を、俺に預けてもらえませんか」
迷いはなかった。失敗することが怖くないわけじゃない。けれど、なにもせずに救えないのはもっと嫌だったから。
覚悟は伝わったのだろう。先の実績もある。二人は小さく頷いた。
そして俺は呻く女性へと近づいていく。美しい肢体は無造作に投げ出されており、顔は苦痛に歪んでいる。
もがく彼女は俺を視認することもなく、ただのた打ち回っていた。
俺はこれからするべきことを、俺の意思を、魔物たちに伝える。するとぱたぱたとライムが駆け寄ってきた。ゴブとウルフが入っているケダマがやってきた。
そんな魔物たちの様子を見て、俺は少しばかり安心していた。きっと、これからも協力してくれるから。
ゆっくりと主従契約を発動させる。浮かび上がった魔法陣は、女性の中へと潜っていく。そして一瞬の時間遅れもなしに、魔法陣が下方に出来上がった。契約が成立したということだ。
しかし、そのサイズは女性の体に比するとかなり小さい。
つまり――
「オークとの契約が成立しました」
姫さんが息を呑み、クーナの顔が驚きに染まる。しかし、二人とも一言も発しなかった。俺に任せることにしたからだ。たとえどれほど尋ねたいことがあったとしても、彼女たちはなにも言わなかったに違いない。
オークが寄生しているだけならば、地狐とは別の魔物と認識されると予想したが、果たしてその通りになったのだ。そして女性の肉体が障壁となるかと思ったものの、主従契約のスキルは任意の相手以外には影響を及ぼさないようにできるようだ。
体内にいるオークが拒絶したならば、契約は成立することはなかった。しかし、生まれたての魔物には意思がないため主従契約はいとも容易くなされる、というのを聞いていたこともあって、主従契約さえ発動できればうまくいくはずだと踏んでいた。
まずは一つ目の関門を突破したと言えよう。しかしまだ安心はできない。
俺は一つ息を吐きながら次の行動に移る。いや、正確には俺ではない。俺たちだ。
契約ができたところで、地狐の体内にいるオークに直接干渉することはできない。そこで、魔物同士を合成することにしたのだ。
「魔物合成」は複数の魔物から新しい魔物を合成して強くしたり、一体をベースに経験値を増やしたりするスキルだが、それによって体内からオークを消すことができると考えたのである。
合成した魔物が一体を残して消えていることからそう判断したが、安全性を確認しているわけではなく、かといって今から実験していては間に合わなくなる可能性が高い。それに、このように体内に寄生された状況は、ほかの魔物ではそうそう見られないだろう。
やはりどこかで、決断はしなければならない。危険を承知でやらねばならないときがある。
ライムはそんな俺に、にっこりと微笑み、
「大丈夫」
とだけ告げるなり、魔法陣に触れた。途端、小さかった陣が拡大されていく。いつもよりも少しばかり大きくなったその中で、彼女は変わらずに微笑んでいる。
そしてライムの姿が光に包まれた。
やがて光が消えると、そこには変わらぬライムの姿があった。合成の際、新たな魔物になるのではなく、経験値を得るほうを選んだのだろう。いかに人型とはいえ、豚の特徴を取り込むのは嫌だったに違いない。
「ありがとうな、ライム」
「えへへ」
俺の行為を後押ししてくれたライムに礼を言いつつ女性を見ると、腹の膨らみは多少マシになっていた。呼吸も落ち着きつつある。
しかしだからといって、完全に治りきったと断定はできない。オークが消えたことで、どこかに出血などが起こる可能性があるからだ。
俺は彼女の脈を取ったり、バイタルサインを確認したりする。そうしていると、彼女はぼんやりと、俺のほうを見る。
「大丈夫ですか?」
彼女は小さく頷いた。どうやら、意識は戻ってきており、ひとまずは問題なさそうだ。これで一人目はおそらく助かったのだろう。
彼女の症状の経過を見てから、ほかの狐たちに対応していくほうがいいのだろうが、もうすでに限界まで達しているものもいるようだ。
たとえ問題があろうと、オークが腹を食い破って出てくるよりは出血も少ないはずだ。
俺は姫さんたちに伝え、オークの成長が早い狐から、この手法を行っていくことにした。直接は視認できないため鑑定は使えず、主従契約だけが頼りになる。
今回もスキルを発動させると、魔法陣は外れることはなく吸い込まれていき、契約が成立する。これによってようやく、俺は魔物の正体を確認することができるようになった。
《オークロード Lv1》
ATK33 DEF29 MAT6 MDF11 AGI11
【スキル】
「精力増強」
これは……どうやらオークの上位魔物らしい。オークが成長して進化するのではなく、生まれたときから決まっているようだ。
この魔物、かなり初期ステータスが高い。俺が連れている魔物と違って、野生の魔物ゆえに最大値になっていないことを考えると、これまで遭遇した魔物の中では一番強いかもしれない。
それでもここにいる地狐たちのほうがステータスは上だ。となれば、狐たちが負けた理由はほかにあるのだろう。
たとえば、この繁殖力。数の不利はそう簡単に覆せやしない。
と、そんなことを考えている場合ではなかった。魔物が強力ならばなおさらのこと、早く処置しなければならない。
俺がなにかを言わんとしたときには、すでにゴブが魔法陣に駆け寄っていた。なにやらやる気に満ちているらしい。
大丈夫なんだろうか、こいつで。
そんな疑問を抱いたときには、すでにゴブの姿は光に包まれていた。
しかし、どんな魔物だろうが、これまで合成には成功してきたのだ。失敗する確率はかなり低いだろう。たとえゴブであっても。
光が収まると、そこには容態の落ち着いた地狐と、素潜りゴブリンがいた……いや、違う。こいつ、進化するタイプの合成を選んだようだ。だから張り切っていたのだろう。もしかすると、このパーティで一体だけ弱いことを気にしていたのかもしれない。
だが……どうにも強そうには見えない。
体を覆っていた鱗はなくなり、今は緑というよりは茶色に近い、つるっとした体になっていた。やや大柄にもなっている。
特にそれくらいしか違いが見当たらないな、と思いながら見ていると……重大な違いがあった。
豚鼻になっている!
よく見れば尻尾もあった。くるんと巻いた豚の尻尾だ。
……引き継いだの、ロードのほうじゃなくて、豚の成分かよ。
俺はあまり期待せずに、ゴブのステータスを確認する。
《ブタゴブリン Lv1》
ATK26 DEF25 MAT8 MDF16 AGI25
【スキル】
「土魔法Lv1」「精力増強」
ふざけた名前と見た目のくせに、ステータス高いな。ほかの魔物たちに追いついたかもしれない。
おそらくマーマン成分がなくなっているのだろう。水魔法が消えている。しかしこちらはライムが持っているため、特に問題はない。
しかし、精力増強まで引き継ぐとは……これ、俺にも反映されているようだ。
何事にもやる気で満ち溢れるのはいい。そういうことにしておこう。
俺は地狐の様子を眺める。そもそも狐の肉体に関して詳しいわけでもないので、魔物である地狐に関してはなおさらわからない。
それゆえにクーナたちに状態を確認してもらう。二人は狐に触れたりして具合を確かめ、やがて安心したような表情を浮かべる。どうやらこちらも成功だったらしい。
ぐったりしていた狐は、小さく鳴いた。
それから俺は主従契約を用いて、ほかの地狐に寄生しているオークを取り除いていく。あとは順調に進んでいった。
十数体の地狐に対して契約を終えたとき、俺は精神的にも肉体的にもすっかり疲れ切っていた。もう動くのも嫌になって、そこらの床に大の字に寝転がる。すかさずケダマが転がり込んできて枕になった。
そうなると、強烈な眠気が襲ってくる。どうやら、スキルを使いすぎるとこうなるようだ。体が疲労を取り除くべく、休養を欲している。きっと、強い精神力さえあれば耐えきれるのだろう。しかし、俺はやり遂げた安心感もあって、そのまま心地いい微睡みに身を任せた。
そんな俺をライムが覗き込んで、小さく笑う。
ゴブが頑張って俺の体を持ち上げて、小型化を解除したウルフの背に乗せる。あんなにも頼りなかったというのに、力持ちになったようだ。
そんな奴は張り切っているのか鼻息が荒い。
「ぶひぶひ」
……豚成分、そんなとこにまであったのかよ。
俺はどこか抜けているゴブに呆れつつ、ウルフに運ばれていった。こいつらに任せておけば、大丈夫だろう。
今日は少し、働きすぎたのであった。
3
クーナ・ルイアは社にいた。
彼女の視線の先には、敬愛する姫がいる。けれど、歓談するような雰囲気とは程遠い。
この日、クーナにとってはあまりにも多くのことが起きた。感情と理性のどちらでも、とても理解できないことが一気に押し寄せてきたのだ。
「姫様……申し訳ありませんでした、私のせいで――」
姫は目を伏せる。クーナには、彼女の思いもよくわかった。けれどそれ以上に、自分の不甲斐なさが悔しくて悔しくて仕方がなかった。
今日、クーナは仲間を連れて、侵略してきたオークたちに立ち向かっていった。このままでは、この地すべてを奴らに奪われてしまうことがわかっていたからだ。
オークという種族に対して、地狐は能力的には優れていると言える。そしてクーナはその中でも多くの戦いを経験してきた自負があった。ほかの誰よりもうまく戦える技術があった。
けれど……結果はついてこなかった。
今朝、多くの仲間を引き連れてオークを奇襲すると、快進撃が始まった。そこまでは当初の予定通りで、群がるオークはどれほどいようが、蹴散らせると思っていた。
しかし、それはただの時間稼ぎに過ぎなかったのだろう。
気がついたときには、数体の巨大なオークがいた。奴らは力強く、こちらの攻撃などものとはしなかった。ステータスの差がかなりあったに違いない。
やがて一人、二人と同胞が倒れていく。そのときの光景は今でも目に焼きついて離れない。
彼女たちはきっと、今もオークの住処に捕らわれているだろう。そのことを思うと、クーナはぐっと奥歯を噛み締めた。
それから、クーナは少しでも多くの仲間を助けるために、彼女たちを置いて、無事な者たちとともに逃げたのだ。
その選択が間違いだったとは思わない。けれど、だからといって納得はできやしなかった。なにか別の方法があったのではないかと、ずっと悩み続けている。
「そのようなことをおっしゃらないでください、クーナ。あなたのせいではありません。ただ、私に力がなかった、それだけのことなのです」
姫はそう言って、クーナを慰める。
彼女は、地狐が進化した種族である天狐が年老いてからなる種族、空狐であった。かつては天狐として、絶大な力でこの集落を守ってきた。
しかし、今はどうだろうか。もう戦いに関して十分な力はない。
そのことはクーナもわかっていた。だから、なおさら押し黙るしかできなかった。
しばしの無言。平時ならば、話題は尽きることはなかった。年齢や経験の差など気にならないほど、クーナは姫のことが好きであったし、姫もまたこの友人を我が子のように思っていたからだ。だというのに、今は過ぎゆく時間が重かった。
クーナは今日一日のことを思い返す。どこで間違ったんだろう。どこで失敗したんだろう、と。けれど最後までわからなかった。結局、力がなかった、という一言で片づけてしまうしかないのか。
そうしているうちに、彼女は一つの出来事を思い浮かべた。彼女が囮となって、ほかの地狐たちを逃したあとのことだ。
もちろん、無事で逃げ切れるなんて甘い考えを持っていたわけではない。しかし、運悪く足を怪我してしまったことが影響し、オークたちに追いつかれて利き足をやられた。
奴らの動きは早いとは言い難いが、そのような状況では逃げることなどかなわない。
死を覚悟したとき、飛び込んでくるものがあったのだ。
人間だ。
この里の周辺には霧がかかっている。昔話によれば、かつてここを訪れた魔物使いが、ほかの人間による侵略を受けないように張った結界だそうだ。だからクーナが人を見たのはこれが初めてだった。
そしてその男は、連れている魔物とともに、オークどもを蹴散らした。なんと魔法が使えたのだ。おそらくは魔物を従えるスキルを持つ魔物使いなのだろう。
だからクーナは矜恃をもって言った。人に囚われる気はない、と。
それでも男は引き下がらず、あろうことか、頭まで下げてきた。人間は傲慢だと聞いていたが、とてもそうは見えなかった。
頼りになるばかりか、真剣な表情で接してくる姿を見ると、昔話で魔物使いのことを聞いていたのもあって、つい……ちょっとだけならいいかなあ、と思ってしまった。あとから逃げるのでも遅くはない。
主従契約を受け入れるなり、足の痛みはなくなった。体中の怪我という怪我が治っていたのだ。
驚きはそれだけではなかった。いや、それ以上に大きかったかもしれない。
男はさっさと主従契約を解除してしまったのだ。
そのままにしておけば、恩とともに見返りを求めることだってできたはずだ。しかし、まったくそんな素振りは見せなかった。本当に、ただ助けたいがために行ったことなのだろう。
信頼のおける人だと思った。いいなあ、と思ってしまった。
だから、彼が迷っていると知るなり、里に案内することにした。
しかし、その言葉が出たところは、純粋な歓迎だけではない。
人間よりも自分のほうがよほど不誠実なのではないか、という気がしたが、それでも彼の力ならば、傷ついた同胞を助けられる。
そんな打算――いや、ちょっとした期待、実現しない儚い夢のような思いを抱きながら里に戻ってきたのだが、彼は怪我を治すばかりか、オークに寄生された者たちまで救ってしまった。ここでも、見返りなんて求めることはなかった。
そのときの彼の真剣な横顔を思い出すと、クーナの胸中に満ちていた後悔と不安が、ほんの少しだけ和らいでいく。初めて抱いた感情だった。
姫との間に満ちた重い空気を変えるのにもいいだろう、とクーナは彼について言及する。
「……あの方、いつまでいるのでしょうか?」
この里に用があってきたわけではない。オークに狙われているとわかれば、さっさと帰るのが妥当なところだろうから、その質問はあまり意味をなさなかった。
けれど、姫は優しい笑みを浮かべる。
「いつまでもいてほしい、ということですか?」
「ち、違います! そのようなことは!」
クーナはあからさまに狼狽えた。誰が見てもわかるほどに。顔はすっかり赤らんでいる。
しかしそんな表情もすぐに変わって、小さな声で続ける。
「私はただ……あの方のお力があれば、苦しまずに済む者がいるのではないかと、思うのです」
それは本心だろうか。嘘ではないことは確かだ。
だが、事実をぴたりと言い表しているかといえば、クーナにもよくわからなかった。その正体がわからない感情が、胸の中にあったからだ。
「では、クーナからお願いしてはいただけませんか?」
「私から、ですか?」
「ええ……あれは伝説のようなものですが、今の状況によく似ているでしょう?」
彼女の言う伝説とは、昔あった出来事のことだ。彼女が天狐になったのも、そのときである。
クーナはしばし戸惑ったようだったが、すぐに表情を引き締める。
「わかりました。このクーナ、必ずや、やり遂げてみせましょう」
さながら戦いに赴くときのように、力強く答える。
彼女の迷いはもう消えていた。
退室していく小さな友人を見ながら、姫は目を細めた。
きっと、この集落は長くは持たない。オークに勝てる見込みなんてほとんどないのだから。けれど、姫がここを去るわけにはいかない。長として、誰一人いなくなるまでは、逃げることなどできやしなかった。
だから、クーナには――あの青年にはちょっと悪いかもしれないけれど――一緒に外の世界に行ってくれれば、と思ったのだ。
やがてクーナが退室すると、静寂が訪れた。
姫はいつまでも、彼女が出ていった扉を眺めていた。
0
お気に入りに追加
362
あなたにおすすめの小説

【完結】もう…我慢しなくても良いですよね?
アノマロカリス
ファンタジー
マーテルリア・フローレンス公爵令嬢は、幼い頃から自国の第一王子との婚約が決まっていて幼少の頃から厳しい教育を施されていた。
泣き言は許されず、笑みを浮かべる事も許されず、お茶会にすら参加させて貰えずに常に完璧な淑女を求められて教育をされて来た。
16歳の成人の義を過ぎてから王子との婚約発表の場で、事あろうことか王子は聖女に選ばれたという男爵令嬢を連れて来て私との婚約を破棄して、男爵令嬢と婚約する事を選んだ。
マーテルリアの幼少からの血の滲むような努力は、一瞬で崩壊してしまった。
あぁ、今迄の苦労は一体なんの為に…
もう…我慢しなくても良いですよね?
この物語は、「虐げられる生活を曽祖母の秘術でざまぁして差し上げますわ!」の続編です。
前作の登場人物達も多数登場する予定です。
マーテルリアのイラストを変更致しました。

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

どうも、死んだはずの悪役令嬢です。
西藤島 みや
ファンタジー
ある夏の夜。公爵令嬢のアシュレイは王宮殿の舞踏会で、婚約者のルディ皇子にいつも通り罵声を浴びせられていた。
皇子の罵声のせいで、男にだらしなく浪費家と思われて王宮殿の使用人どころか通っている学園でも遠巻きにされているアシュレイ。
アシュレイの誕生日だというのに、エスコートすら放棄して、皇子づきのメイドのミュシャに気を遣うよう求めてくる皇子と取り巻き達に、呆れるばかり。
「幼馴染みだかなんだかしらないけれど、もう限界だわ。あの人達に罰があたればいいのに」
こっそり呟いた瞬間、
《願いを聞き届けてあげるよ!》
何故か全くの別人になってしまっていたアシュレイ。目の前で、アシュレイが倒れて意識不明になるのを見ることになる。
「よくも、義妹にこんなことを!皇子、婚約はなかったことにしてもらいます!」
義父と義兄はアシュレイが状況を理解する前に、アシュレイの体を持ち去ってしまう。
今までミュシャを崇めてアシュレイを冷遇してきた取り巻き達は、次々と不幸に巻き込まれてゆき…ついには、ミュシャや皇子まで…
ひたすら一人づつざまあされていくのを、呆然と見守ることになってしまった公爵令嬢と、怒り心頭の義父と義兄の物語。
はたしてアシュレイは元に戻れるのか?
剣と魔法と妖精の住む世界の、まあまあよくあるざまあメインの物語です。
ざまあが書きたかった。それだけです。

結婚30年、契約満了したので離婚しませんか?
おもちのかたまり
恋愛
恋愛・小説 11位になりました!
皆様ありがとうございます。
「私、旦那様とお付き合いも甘いやり取りもしたことが無いから…ごめんなさい、ちょっと他人事なのかも。もちろん、貴方達の事は心から愛しているし、命より大事よ。」
眉根を下げて笑う母様に、一発じゃあ足りないなこれは。と確信した。幸い僕も姉さん達も祝福持ちだ。父様のような力極振りではないけれど、三対一なら勝ち目はある。
「じゃあ母様は、父様が嫌で離婚するわけではないんですか?」
ケーキを幸せそうに頬張っている母様は、僕の言葉にきょとん。と目を見開いて。…もしかすると、母様にとって父様は、関心を向ける程の相手ではないのかもしれない。嫌な予感に、今日一番の寒気がする。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
20年前に攻略対象だった父親と、悪役令嬢の取り巻きだった母親の現在のお話。
ハッピーエンド・バットエンド・メリーバットエンド・女性軽視・女性蔑視
上記に当てはまりますので、苦手な方、ご不快に感じる方はお気を付けください。

子持ちの私は、夫に駆け落ちされました
月山 歩
恋愛
産まれたばかりの赤子を抱いた私は、砦に働きに行ったきり、帰って来ない夫を心配して、鍛錬場を訪れた。すると、夫の上司は夫が仕事中に駆け落ちしていなくなったことを教えてくれた。食べる物がなく、フラフラだった私は、その場で意識を失った。赤子を抱いた私を気の毒に思った公爵家でお世話になることに。
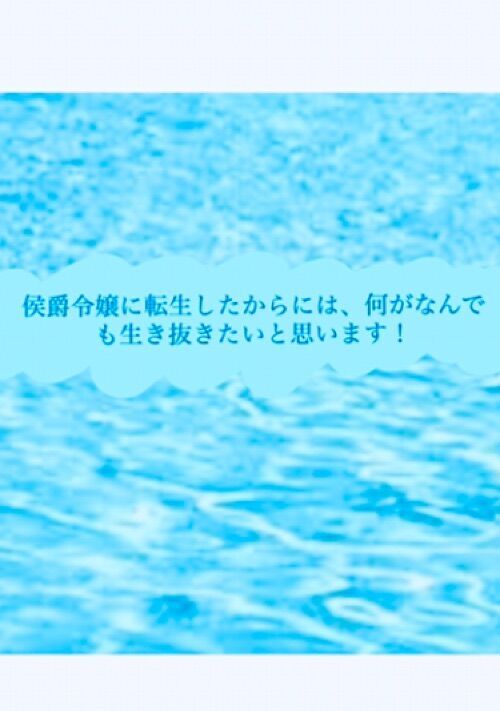
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

【完結】悪役令嬢に転生したけど、王太子妃にならない方が幸せじゃない?
みちこ
ファンタジー
12歳の時に前世の記憶を思い出し、自分が悪役令嬢なのに気が付いた主人公。
ずっと王太子に片思いしていて、将来は王太子妃になることしか頭になかった主人公だけど、前世の記憶を思い出したことで、王太子の何が良かったのか疑問に思うようになる
色々としがらみがある王太子妃になるより、このまま公爵家の娘として暮らす方が幸せだと気が付く

【完結】20年後の真実
ゴールデンフィッシュメダル
恋愛
公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。
マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。
それから20年。
マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。
そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。
おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。
全4話書き上げ済み。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















