8 / 13
実習
しおりを挟む
体育館、と呼ぶにはあまりにも巨大な建造物だった。円形の空間は春にしては肌寒い。遠近感が狂いそうなだだっ広い円周は、闘技場のように観客席で縁取られている。
ここまで広大なのは、単純に多人数が使用するからでもあるが、制職者の運動能力を確かめるには必要な面積というのが実際のところだ。
骨格、筋肉、感覚器官に神経に至るまで科学の手を加えられた改造兵士。それこそが制職者と一般市民を分ける最大の相違であった。
医療から外れた人体改造に対する忌避は未だ根強い。それはある意味で当然の拒否反応と言えよう。生まれながらに障害を持っているならともかく、満足な五体に機械を入れるのは、本能が冒涜と判断する行為だ。だが進歩し続ける兵器に対応するには、人の側にもアップデートが必要なのだ。
その矛盾を自由意思で解決し、噓偽り無く国家に身を捧げた者だけが制職者の地位に上る権利を得られる。それは畏怖と敬意を呼ぶものではあるが、同時に奇異と恐怖を向けられる危険を秘めていた。
一クラス約30名。陸上競技場ほどもある箱ものの中では染みのような点である。
今にも弾けそうな緊張感がみなぎっていた。聞こえる呼吸は浅く、立春並みの寒気は中心に行くと熱を含みうるんでいる。教師が来るまであと数分。監視カメラはあるが、物理的な距離がごまかしを許す。
果たして今やるべきか。その煩悶が念波となって淀んでいた。
余はげっそりした表情を隠しもせず、しかし動きを見せなければやり過ごせるだろうと計算している。会話の機微は知らずとも、こういった空気の読み方は実地で学んでいた。
一触即発ではあるものの、優秀なだけに残った最期の冷静さが暴発を防いでいる。
一欠はそもそも殺気など歯牙にもかけない。彼女に必要なのは結果であって雰囲気などという曖昧不確実な代物ではなかった。
その後ろで三弥子は魂を手放しかけている。睦美は別のクラスのため別れていた。生まれて初めての死線である。それでも大人しくしていたのは賢い判断であろう。
官僚組織というものは大きな功績を上げるよりも失敗を犯さないおを重視するものだが、統制政府はその傾向がより強い。
入学の初めから問題など起こせば、比喩ではなく首が飛ぶかもしれなかった。制職者は最新鋭の技巧が詰まった秘匿されるべき存在。追放はその身体からあらゆる情報を抹消することに他ならない。国家に紐づけられるほかに、道は付けられていないのだ。
それでも人間たる自己認識を失ったわけではない。すなわちあえて愚行を犯す自由を切除された訳ではないのだ。だからこそこの状況下で余の前に進み出るという事が出来る。
ひょろりと背の高い男子と、その後ろに何人か。前にいるのっぽは腕に覚えがありそうだが、その他はおこぼれにあずかろうとしただけだろう。武装に意識を向けすぎている。
「何か用か?」
言い放ってから少しぶっきらぼうに過ぎたかと反省する。一欠の眼が厳しい。まずは会話でもしないとやっていけないのか余の方なのだ。
「別にいいだろう?同級生なんだ。用が無くても話すことだってある。入学したてなんだし」
「もっともな理論です学年序列51番橋本遠矢。学生同士の交流こそこの時代においても実体としての学校が必要な所以」
「うんまあそっすね。でももうすぐ授業だぜ」
遠矢と呼ばれた細長い男は肩をすくめる。
「そう大した話でもないって。雑談なんだからさ。単に懐かしくなって話しかけただけだよ。お前は覚えちゃいないだろうが、昔顔を合わせたことがあったんでね」
「いや、覚えてるよ。去年の八月、確か東海方面だったかな?逃げてるときに待ち伏せ部隊の中にいたな」
具体的な言及に、素直に驚いたようだった。言葉が続かない。余はちょっと呆れたように難詰する。
「なんだよ。人に向かって磁気火薬併用拳銃ぶっ放しておいて忘れられてるとか随分だな。加害者は自分のやったことに自覚的でなくちゃ進歩がないぞ」
「ああ、いや。そうか。覚えてたのか。お前みたいなやつなら命を狙われるなんていつものことだだろうから、意気にしないのかと思ってたよ」
「馬鹿言うな。いちいち覚えてるに決まってるだろ。それに顔の見える距離で撃ち合いなんて両手の指で、いや脚もいるか?ああいや、やっぱりもうちょっと」
「映像記録の残っている範囲で、久世余が現れたよ判定された銃撃戦は68回です」
一欠の迷いない計数にそんなに多かったっけ?と首をかしげる。そういえば月に二回はやっていた記憶が、ぼんやりと漂っているような。
余は考えるのを止めた。殺し合いの場数など自慢にもならない。ここは法治国家日本なのだ。
のっぽの同級生は、しょうもない煩悶を見せる元テロリストの鬼札を微妙な目で眺めていた。あるいは世紀の大犯罪者と真っ向からぶつかった記憶は、彼にとっては一種の財産であったかもしれない。少なくとも武勇伝には困る事はないだろう。当の危険人物はぼやっと突っ立っていたが。
経験というものは得難いものである。百聞は一見に如かず、また一度の体験は百の見聞を上回る。だからこそ実感として久世余の実力を知る遠矢は、余のとぼけた行動を得体の知れないものとして恐れた。
だが戦いを、命のやり取りを体感していない金魚のふん達は、それを弱々しさとして受け止めた。
短距離通信で拍子をとると、一斉に、しかし気取られないよう静かに隊列を横に広げる。
風が砂を散らすような自然な動きだったが、格上に通用する類の技ではない。遠矢が声も無く制止するが、一度やってしまった戦闘行動のはずみを抑えられるほど熟達していない。
一欠が一歩進み出る。監視対象を無用な混乱から隔離するのもまた、彼女の役割だった。
闘志の臭いをかぎ取って、観客だった生徒たちも自然と被弾面積を狭める。ある者は半身に、またある者は身を低く。学友を楯にする者までいた。
誰かが緊張に耐えられなくなって短刀に手をかける。改良された瞬発力をもってすれば、この間合いでは刃物が速度で勝る。
それをいち早く抑え込もうと一欠が動く。いわゆる後の先。攻撃という余分な動作の出を抑えるつもりだ。
だがそれを追いこして余が走った。抑え込むどころではない。体当たりだ。光神経の高速伝達網が満身を刹那の内に同期させ、高分子繊維の収縮が少年の質量に矢の速さを与える。
カウンター。交通事故も同然だった。襟首を掴まれてほとんど回転するように倒れる。だが捨て身過ぎる。自分が隙を見せることも構わない動きだった。真空に流入するように、余の背に攻撃が集中しようとし。
それらの行動の起こりを一弾が消去した。機械の眼でも、音速の弾は流石に線にしか見えない。広大な床が痺れる。とてつもない運動量。間違いなく軍用の威力だった。
ある程度の武装はたしなみとして持ち歩く制職者の卵でも、限度というものがある。対物レベルの銃火器を持ち運ぶのを許可された人員など、この時点では一人しかいない。
つまり時間切れだった。教師が来た。
「久しぶり!余くう~ん?」
声質が不安定な呼び声が耳朶を打った。悲しいことに余の知り合いだった。
ここまで広大なのは、単純に多人数が使用するからでもあるが、制職者の運動能力を確かめるには必要な面積というのが実際のところだ。
骨格、筋肉、感覚器官に神経に至るまで科学の手を加えられた改造兵士。それこそが制職者と一般市民を分ける最大の相違であった。
医療から外れた人体改造に対する忌避は未だ根強い。それはある意味で当然の拒否反応と言えよう。生まれながらに障害を持っているならともかく、満足な五体に機械を入れるのは、本能が冒涜と判断する行為だ。だが進歩し続ける兵器に対応するには、人の側にもアップデートが必要なのだ。
その矛盾を自由意思で解決し、噓偽り無く国家に身を捧げた者だけが制職者の地位に上る権利を得られる。それは畏怖と敬意を呼ぶものではあるが、同時に奇異と恐怖を向けられる危険を秘めていた。
一クラス約30名。陸上競技場ほどもある箱ものの中では染みのような点である。
今にも弾けそうな緊張感がみなぎっていた。聞こえる呼吸は浅く、立春並みの寒気は中心に行くと熱を含みうるんでいる。教師が来るまであと数分。監視カメラはあるが、物理的な距離がごまかしを許す。
果たして今やるべきか。その煩悶が念波となって淀んでいた。
余はげっそりした表情を隠しもせず、しかし動きを見せなければやり過ごせるだろうと計算している。会話の機微は知らずとも、こういった空気の読み方は実地で学んでいた。
一触即発ではあるものの、優秀なだけに残った最期の冷静さが暴発を防いでいる。
一欠はそもそも殺気など歯牙にもかけない。彼女に必要なのは結果であって雰囲気などという曖昧不確実な代物ではなかった。
その後ろで三弥子は魂を手放しかけている。睦美は別のクラスのため別れていた。生まれて初めての死線である。それでも大人しくしていたのは賢い判断であろう。
官僚組織というものは大きな功績を上げるよりも失敗を犯さないおを重視するものだが、統制政府はその傾向がより強い。
入学の初めから問題など起こせば、比喩ではなく首が飛ぶかもしれなかった。制職者は最新鋭の技巧が詰まった秘匿されるべき存在。追放はその身体からあらゆる情報を抹消することに他ならない。国家に紐づけられるほかに、道は付けられていないのだ。
それでも人間たる自己認識を失ったわけではない。すなわちあえて愚行を犯す自由を切除された訳ではないのだ。だからこそこの状況下で余の前に進み出るという事が出来る。
ひょろりと背の高い男子と、その後ろに何人か。前にいるのっぽは腕に覚えがありそうだが、その他はおこぼれにあずかろうとしただけだろう。武装に意識を向けすぎている。
「何か用か?」
言い放ってから少しぶっきらぼうに過ぎたかと反省する。一欠の眼が厳しい。まずは会話でもしないとやっていけないのか余の方なのだ。
「別にいいだろう?同級生なんだ。用が無くても話すことだってある。入学したてなんだし」
「もっともな理論です学年序列51番橋本遠矢。学生同士の交流こそこの時代においても実体としての学校が必要な所以」
「うんまあそっすね。でももうすぐ授業だぜ」
遠矢と呼ばれた細長い男は肩をすくめる。
「そう大した話でもないって。雑談なんだからさ。単に懐かしくなって話しかけただけだよ。お前は覚えちゃいないだろうが、昔顔を合わせたことがあったんでね」
「いや、覚えてるよ。去年の八月、確か東海方面だったかな?逃げてるときに待ち伏せ部隊の中にいたな」
具体的な言及に、素直に驚いたようだった。言葉が続かない。余はちょっと呆れたように難詰する。
「なんだよ。人に向かって磁気火薬併用拳銃ぶっ放しておいて忘れられてるとか随分だな。加害者は自分のやったことに自覚的でなくちゃ進歩がないぞ」
「ああ、いや。そうか。覚えてたのか。お前みたいなやつなら命を狙われるなんていつものことだだろうから、意気にしないのかと思ってたよ」
「馬鹿言うな。いちいち覚えてるに決まってるだろ。それに顔の見える距離で撃ち合いなんて両手の指で、いや脚もいるか?ああいや、やっぱりもうちょっと」
「映像記録の残っている範囲で、久世余が現れたよ判定された銃撃戦は68回です」
一欠の迷いない計数にそんなに多かったっけ?と首をかしげる。そういえば月に二回はやっていた記憶が、ぼんやりと漂っているような。
余は考えるのを止めた。殺し合いの場数など自慢にもならない。ここは法治国家日本なのだ。
のっぽの同級生は、しょうもない煩悶を見せる元テロリストの鬼札を微妙な目で眺めていた。あるいは世紀の大犯罪者と真っ向からぶつかった記憶は、彼にとっては一種の財産であったかもしれない。少なくとも武勇伝には困る事はないだろう。当の危険人物はぼやっと突っ立っていたが。
経験というものは得難いものである。百聞は一見に如かず、また一度の体験は百の見聞を上回る。だからこそ実感として久世余の実力を知る遠矢は、余のとぼけた行動を得体の知れないものとして恐れた。
だが戦いを、命のやり取りを体感していない金魚のふん達は、それを弱々しさとして受け止めた。
短距離通信で拍子をとると、一斉に、しかし気取られないよう静かに隊列を横に広げる。
風が砂を散らすような自然な動きだったが、格上に通用する類の技ではない。遠矢が声も無く制止するが、一度やってしまった戦闘行動のはずみを抑えられるほど熟達していない。
一欠が一歩進み出る。監視対象を無用な混乱から隔離するのもまた、彼女の役割だった。
闘志の臭いをかぎ取って、観客だった生徒たちも自然と被弾面積を狭める。ある者は半身に、またある者は身を低く。学友を楯にする者までいた。
誰かが緊張に耐えられなくなって短刀に手をかける。改良された瞬発力をもってすれば、この間合いでは刃物が速度で勝る。
それをいち早く抑え込もうと一欠が動く。いわゆる後の先。攻撃という余分な動作の出を抑えるつもりだ。
だがそれを追いこして余が走った。抑え込むどころではない。体当たりだ。光神経の高速伝達網が満身を刹那の内に同期させ、高分子繊維の収縮が少年の質量に矢の速さを与える。
カウンター。交通事故も同然だった。襟首を掴まれてほとんど回転するように倒れる。だが捨て身過ぎる。自分が隙を見せることも構わない動きだった。真空に流入するように、余の背に攻撃が集中しようとし。
それらの行動の起こりを一弾が消去した。機械の眼でも、音速の弾は流石に線にしか見えない。広大な床が痺れる。とてつもない運動量。間違いなく軍用の威力だった。
ある程度の武装はたしなみとして持ち歩く制職者の卵でも、限度というものがある。対物レベルの銃火器を持ち運ぶのを許可された人員など、この時点では一人しかいない。
つまり時間切れだった。教師が来た。
「久しぶり!余くう~ん?」
声質が不安定な呼び声が耳朶を打った。悲しいことに余の知り合いだった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

3024年宇宙のスズキ
神谷モロ
SF
俺の名はイチロー・スズキ。
もちろんベースボールとは無関係な一般人だ。
21世紀に生きていた普通の日本人。
ひょんな事故から冷凍睡眠されていたが1000年後の未来に蘇った現代の浦島太郎である。
今は福祉事業団体フリーボートの社員で、福祉船アマテラスの船長だ。
※この作品はカクヨムでも掲載しています。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく



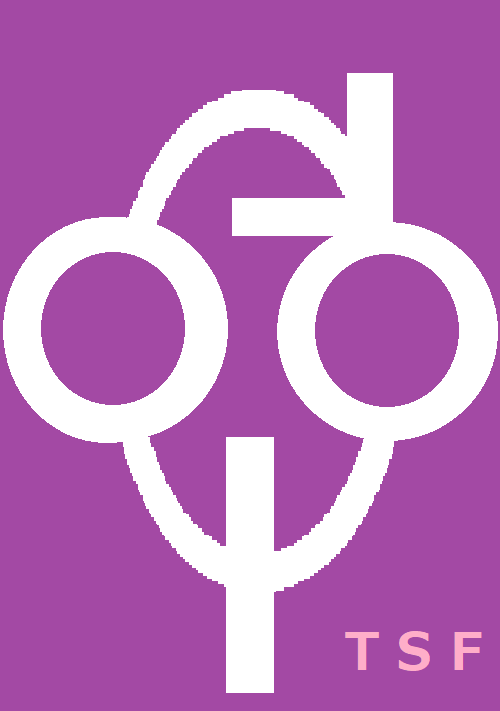

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















