5 / 33
一幕 一級怪異襲来
第5話 眼鏡だけはやめてください
しおりを挟む
K県T駐屯地。
三浦半島における陸上自衛隊の駐屯地の一つであり、『東部方面混成団』が駐屯し、教育隊が置かれ、自衛官を目指す学生の教育が施される地としても知られている。
だが、人類を脅かす悪魔に対処すべく、秘密裏に結成された『第一特殊任務部隊』の本部であることを知る者は極少数の人間だけである。
小暮小隊は『第一特殊任務部隊』に所属する小隊の中でも精鋭中の精鋭として、知られていた。
最も普及したゼファーと異なり、特殊な新型動力機関を使用しているカルキノスとナイトストライカーの配備数は極端に少ない。
小暮小隊には虎の子と言うべき機体が六機も配備されていたのである。
「噂の黒い幽霊プロセルピナですか」
「間違いないだろう。鮮やかな手口といい奴の仕業だ」
スクリーンに映し出されているのはぼんやりとピンボケしている黒い影だ。
辛うじて判別できるのは人と同じように二本の足で大地に立っており、二本の腕があること。
そして、頭部に角を思わせる二本の突起物が生えていることくらいだろう。
「では他の隊を襲ったのは例の黒狼スコルですかね?」
収まりの悪い癖毛を撫でつけながら、珈琲を口に運び、静かに言葉を紡いだのはナイトストライカーを率いていた篁だった。
「それも間違いない。三隊のゼファーは全て、行動不能状態だ」
「動力核を抜き取られたのは01と08NSだけです。08は同刻に全機が……ポーンですよ」
古川が両手を高々と上げ、おどけてみせるがその表情は真剣そのもの。
プロセルピナによって、核を奪われたカルキノスとナイトストライカーだけではなかったのだ。
スコルに行動不能に追い込まれたゼファーの数はざっと三十機。
第一特殊任務部隊に配備された装甲機兵の三割以上が失われたことになる。
「……諏訪湖も鎮まったそうだ」
小暮の漏らしたぼやきにも似た呟き。
あまりに衝撃的な内容に場は沈黙に包まれるのだった。
悠の平凡な日常は遥か、遠くのものとなった。
普通に過ごせる毎日を返して欲しいものだと願う悠だったが、その実現は難しい。
新たに彼の右隣の住人となった勇奈が互いに非干渉を貫いてくれる慎ましい左隣の住人と正反対の存在だったのだ。
「天宮君、今日も忘れちゃったのぉ。見せてくれるよね? いいでしょぉ?」
「あっ……はい」
転校生の教材が揃っていないので隣席の子に協力を願うのは珍しいことではない。
おまけにその転校生がとびきりの美少女であれば、普通の男子高校生は喜ぶところだ。
教科書を共有するという行為は物理的な距離を合法的に縮める手段と言える。
ごく自然に机と椅子が近づくのは仕様がないことだろう。
面倒事を厭う悠だが、元来、他人を慮る性格の少年である。
左隣の少女から、刺すような視線を感じつつも快く、譲歩した。
ところが勇奈はスキンシップというには過剰なほど、不必要に体を密着させようとするのだ。
困った悠は助けを求めるように百合愛の顔を窺った。
常に何にも感情を動かさず、何にも興味を示さない彼女が初めて、眉間に皺を寄せた不機嫌な表情を浮かべているよう見えて、悠の心は激しく、動揺した。
「ねぇねぇ。ここ、分かんないだけどぉ」
そんな悠の心の乱れを知ってか、知らずか、勇奈は桃の色をした髪の先をクルクルと捩じりながら、上目遣いに彼を見つめ、さらに体を密着させていく。
その様は傍目にも明らかに意識をして、悠の腕に体を押し付けているとしか、思えない。
(すごく、当たってるんだが……)
柔らかくて、重量感のある物体を押し付けるように当てられた悠も年頃の男子だ。
直に触ったら、気持ちがいいのだろうかとあらぬ妄想をしてしまったが、左隣から氷を思わせる視線がチクチクと刺してくるので生きた心地がしない。
悠の苦悩は六時限目まで止まることがなかった。
右からは肉体的なストレス、左からは精神的なストレスを与えられ続け、不必要に精神力を削られた悠はいつも以上に疲れを感じていた。
彼は普段から、出来るだけ目立たない学生生活を送っていた。
それが台無しになったのは目立つ転校生・勇奈に付きまとわれていたことが大きい。
あからさまに嫉妬丸出しの『何でお前みたいな奴が』という同級生の視線が面倒極まりないのだ。
さらに彼を疲れさせたのは自分が一方的に想いを寄せていた左隣の少女――百合愛から、不自然なほどの感情をぶつけられた気がしてならないからだった。
しかし、クラスメイトからの嫉妬など、生易しいものだと悠が知るのは放課後に入ってからのことだ。
「ぐっ」
帰り支度を終え、一人廊下を歩いていた悠は首許に強い衝撃を感じた。
襟首を後ろから、無理矢理に引っ張られたのだ。
首が締まり、口から軽く空気が漏れる程度で済んだのは幸運だったと神に感謝するべきだったかもしれない。
それほどに強い力を加えられていた。
下手をすれば、頚椎を損傷するほどのものだったのだ。
悠が体ごと、引き摺り込まれたのは普段、使われていない空き教室だった。
そのまま、彼の体は投げ飛ばされ、床とお友達という状態に陥っている。
後頭部から、倒されているので打ち所が悪ければ、非常に危ない。
悠が『僕で良かったね』と他人事のように考えていると、無理矢理に引き起こされて、鳩尾にきつい一発を貰った。
内履きではなく、より殺傷力が高い革靴を履いて、蹴りを入れたのだ。
「うっ」
痛くないけど痛い振りをしておく。
平然としていたら、それはそれで面倒なことになると嫌というほど、悠は学習していた。
図書委員である百合愛が図書室に向かう姿をつい目で追ったのがいけなかったんだろうか、と変に納得していた。
気が散っていた。
完全に油断していた。
そして、今日は散々な一日だと結論付けようとしていた。
「おいおい。まだまだ、ねんねするのは早いぜ」
一、二……ざっと見て、八人の少年だった。
不良グループに絡まれたと見て、間違いないだろう。
(ああ、面倒だなぁ)
それくらいの感想しか浮かんでこないまま、致命傷を避ける最低限の動作だけを取る悠を前に不良グループは遠慮なく、好き勝手している。
これ以上、絡まれるのは面倒だ、と悠は倒れた振りを続行することにした。
(普通はこれで捨て台詞を残して、どこか行ってくれるんだが……)
そう考えていた悠だったが、今日はとことん、星回りが悪いらしい。
「くそ生意気なんだよ! おめえのようなのがよ!」
倒れた振りをしてる悠に追い打ちをかけるように思い切り、蹴りを入れる。
それも何度も繰り返し、執拗に入れているので肋骨や内臓が損傷していてもおかしくない。
不思議なことにそれだけ、暴力を受け続けているのに床がきれいなままなのだが、誰もその不自然さには気付いていない。
「すかした眼鏡をかけてるんじゃねえよ」
「ち、ちょっと待って。眼鏡は! 眼鏡だけはやめてください」
「うっせえ! この野郎!」
(僕は言ったよ、『眼鏡はやめて』って)
養父の眼鏡が外された瞬間、悠の中でスイッチが切り替わったように何かが目覚めた。
(止めたんだから、僕のせいではないと思うんだ)
目覚めたモノは愉悦に口角を上げ、高らかに宣言した。
(殴っていいのは殴られる覚悟がある奴だ。俺は言ったよね?)
「ふっふっふふふふ。あっはははは。俺は注意したよ? 久しぶりなんだ。楽しませてくれるんだよね?」
「な、なんだ!? こいつ、目の色がぼぎゃ」
暴力を受け続けていた悠は何の前触れもなく、起き上がると眼鏡を取り上げた男子生徒の右手首を掴んでいた。
彼が力を入れるとやや抵抗するように軋んだ男子生徒の手首の骨が軽い音とともに砕け散った。
「うわああああああ」
悠は手首を掴んだまま、無造作にゴミでも捨てるように寄せられていた机の中に投げ捨てた。
突如、起こった異変。
悠の豹変に男子生徒達の様子は目に見えて、怯えているのが分かる。
(ああ。これでは楽しめないか……つまんないな)
目覚めたモノは落胆しつつもその目を細め、これから始まる残虐なショーを少しでも楽しむことにした。
三浦半島における陸上自衛隊の駐屯地の一つであり、『東部方面混成団』が駐屯し、教育隊が置かれ、自衛官を目指す学生の教育が施される地としても知られている。
だが、人類を脅かす悪魔に対処すべく、秘密裏に結成された『第一特殊任務部隊』の本部であることを知る者は極少数の人間だけである。
小暮小隊は『第一特殊任務部隊』に所属する小隊の中でも精鋭中の精鋭として、知られていた。
最も普及したゼファーと異なり、特殊な新型動力機関を使用しているカルキノスとナイトストライカーの配備数は極端に少ない。
小暮小隊には虎の子と言うべき機体が六機も配備されていたのである。
「噂の黒い幽霊プロセルピナですか」
「間違いないだろう。鮮やかな手口といい奴の仕業だ」
スクリーンに映し出されているのはぼんやりとピンボケしている黒い影だ。
辛うじて判別できるのは人と同じように二本の足で大地に立っており、二本の腕があること。
そして、頭部に角を思わせる二本の突起物が生えていることくらいだろう。
「では他の隊を襲ったのは例の黒狼スコルですかね?」
収まりの悪い癖毛を撫でつけながら、珈琲を口に運び、静かに言葉を紡いだのはナイトストライカーを率いていた篁だった。
「それも間違いない。三隊のゼファーは全て、行動不能状態だ」
「動力核を抜き取られたのは01と08NSだけです。08は同刻に全機が……ポーンですよ」
古川が両手を高々と上げ、おどけてみせるがその表情は真剣そのもの。
プロセルピナによって、核を奪われたカルキノスとナイトストライカーだけではなかったのだ。
スコルに行動不能に追い込まれたゼファーの数はざっと三十機。
第一特殊任務部隊に配備された装甲機兵の三割以上が失われたことになる。
「……諏訪湖も鎮まったそうだ」
小暮の漏らしたぼやきにも似た呟き。
あまりに衝撃的な内容に場は沈黙に包まれるのだった。
悠の平凡な日常は遥か、遠くのものとなった。
普通に過ごせる毎日を返して欲しいものだと願う悠だったが、その実現は難しい。
新たに彼の右隣の住人となった勇奈が互いに非干渉を貫いてくれる慎ましい左隣の住人と正反対の存在だったのだ。
「天宮君、今日も忘れちゃったのぉ。見せてくれるよね? いいでしょぉ?」
「あっ……はい」
転校生の教材が揃っていないので隣席の子に協力を願うのは珍しいことではない。
おまけにその転校生がとびきりの美少女であれば、普通の男子高校生は喜ぶところだ。
教科書を共有するという行為は物理的な距離を合法的に縮める手段と言える。
ごく自然に机と椅子が近づくのは仕様がないことだろう。
面倒事を厭う悠だが、元来、他人を慮る性格の少年である。
左隣の少女から、刺すような視線を感じつつも快く、譲歩した。
ところが勇奈はスキンシップというには過剰なほど、不必要に体を密着させようとするのだ。
困った悠は助けを求めるように百合愛の顔を窺った。
常に何にも感情を動かさず、何にも興味を示さない彼女が初めて、眉間に皺を寄せた不機嫌な表情を浮かべているよう見えて、悠の心は激しく、動揺した。
「ねぇねぇ。ここ、分かんないだけどぉ」
そんな悠の心の乱れを知ってか、知らずか、勇奈は桃の色をした髪の先をクルクルと捩じりながら、上目遣いに彼を見つめ、さらに体を密着させていく。
その様は傍目にも明らかに意識をして、悠の腕に体を押し付けているとしか、思えない。
(すごく、当たってるんだが……)
柔らかくて、重量感のある物体を押し付けるように当てられた悠も年頃の男子だ。
直に触ったら、気持ちがいいのだろうかとあらぬ妄想をしてしまったが、左隣から氷を思わせる視線がチクチクと刺してくるので生きた心地がしない。
悠の苦悩は六時限目まで止まることがなかった。
右からは肉体的なストレス、左からは精神的なストレスを与えられ続け、不必要に精神力を削られた悠はいつも以上に疲れを感じていた。
彼は普段から、出来るだけ目立たない学生生活を送っていた。
それが台無しになったのは目立つ転校生・勇奈に付きまとわれていたことが大きい。
あからさまに嫉妬丸出しの『何でお前みたいな奴が』という同級生の視線が面倒極まりないのだ。
さらに彼を疲れさせたのは自分が一方的に想いを寄せていた左隣の少女――百合愛から、不自然なほどの感情をぶつけられた気がしてならないからだった。
しかし、クラスメイトからの嫉妬など、生易しいものだと悠が知るのは放課後に入ってからのことだ。
「ぐっ」
帰り支度を終え、一人廊下を歩いていた悠は首許に強い衝撃を感じた。
襟首を後ろから、無理矢理に引っ張られたのだ。
首が締まり、口から軽く空気が漏れる程度で済んだのは幸運だったと神に感謝するべきだったかもしれない。
それほどに強い力を加えられていた。
下手をすれば、頚椎を損傷するほどのものだったのだ。
悠が体ごと、引き摺り込まれたのは普段、使われていない空き教室だった。
そのまま、彼の体は投げ飛ばされ、床とお友達という状態に陥っている。
後頭部から、倒されているので打ち所が悪ければ、非常に危ない。
悠が『僕で良かったね』と他人事のように考えていると、無理矢理に引き起こされて、鳩尾にきつい一発を貰った。
内履きではなく、より殺傷力が高い革靴を履いて、蹴りを入れたのだ。
「うっ」
痛くないけど痛い振りをしておく。
平然としていたら、それはそれで面倒なことになると嫌というほど、悠は学習していた。
図書委員である百合愛が図書室に向かう姿をつい目で追ったのがいけなかったんだろうか、と変に納得していた。
気が散っていた。
完全に油断していた。
そして、今日は散々な一日だと結論付けようとしていた。
「おいおい。まだまだ、ねんねするのは早いぜ」
一、二……ざっと見て、八人の少年だった。
不良グループに絡まれたと見て、間違いないだろう。
(ああ、面倒だなぁ)
それくらいの感想しか浮かんでこないまま、致命傷を避ける最低限の動作だけを取る悠を前に不良グループは遠慮なく、好き勝手している。
これ以上、絡まれるのは面倒だ、と悠は倒れた振りを続行することにした。
(普通はこれで捨て台詞を残して、どこか行ってくれるんだが……)
そう考えていた悠だったが、今日はとことん、星回りが悪いらしい。
「くそ生意気なんだよ! おめえのようなのがよ!」
倒れた振りをしてる悠に追い打ちをかけるように思い切り、蹴りを入れる。
それも何度も繰り返し、執拗に入れているので肋骨や内臓が損傷していてもおかしくない。
不思議なことにそれだけ、暴力を受け続けているのに床がきれいなままなのだが、誰もその不自然さには気付いていない。
「すかした眼鏡をかけてるんじゃねえよ」
「ち、ちょっと待って。眼鏡は! 眼鏡だけはやめてください」
「うっせえ! この野郎!」
(僕は言ったよ、『眼鏡はやめて』って)
養父の眼鏡が外された瞬間、悠の中でスイッチが切り替わったように何かが目覚めた。
(止めたんだから、僕のせいではないと思うんだ)
目覚めたモノは愉悦に口角を上げ、高らかに宣言した。
(殴っていいのは殴られる覚悟がある奴だ。俺は言ったよね?)
「ふっふっふふふふ。あっはははは。俺は注意したよ? 久しぶりなんだ。楽しませてくれるんだよね?」
「な、なんだ!? こいつ、目の色がぼぎゃ」
暴力を受け続けていた悠は何の前触れもなく、起き上がると眼鏡を取り上げた男子生徒の右手首を掴んでいた。
彼が力を入れるとやや抵抗するように軋んだ男子生徒の手首の骨が軽い音とともに砕け散った。
「うわああああああ」
悠は手首を掴んだまま、無造作にゴミでも捨てるように寄せられていた机の中に投げ捨てた。
突如、起こった異変。
悠の豹変に男子生徒達の様子は目に見えて、怯えているのが分かる。
(ああ。これでは楽しめないか……つまんないな)
目覚めたモノは落胆しつつもその目を細め、これから始まる残虐なショーを少しでも楽しむことにした。
0
お気に入りに追加
27
あなたにおすすめの小説
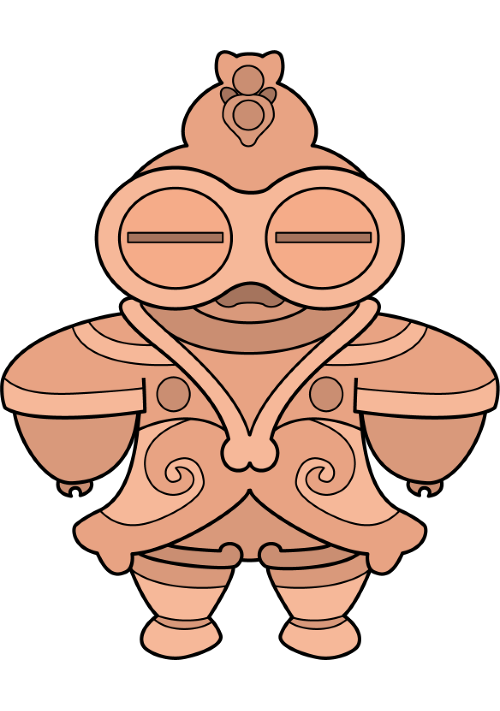

蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。



ヒノモトノタビ
イチ
SF
何故あの日、神は父さんと共に僕を殺してくれなかったのだろう。
何故あの日、僕は母さんと共に死ななかったのだろう。
そんな事を問うならば、早々に自ら命を断てば良いのに、僕は行く当てもないままに…今日も生きている。
最終戦争により文明は崩壊し、突然変異した「獣蟲(じゅうむ)」と呼ばれる生物が闊歩する日本。
かつての姿を失った地を旅する1人の青年。生きる意味を見出せない彼は、この世界をどう生きるのか。

ヴァーチャル美少女キャラにTSおっさん 世紀末なゲーム世界をタクティカルに攻略(&実況)して乗り切ります!
EPIC
SF
――Vtub〇r?ボイス〇イド?……的な美少女になってしまったTSおっさん Fall〇utな世紀末世界観のゲームに転移してしまったので、ゲームの登場人物に成りきってる系(というかなってる系)実況攻略でタクティカルに乗り切ります 特典は、最推し美少女キャラの相棒付き?――
音声合成ソフトキャラクターのゲーム実況動画が好きな、そろそろ三十路のおっさん――未知 星図。
彼はそれに影響され、自分でも音声合成ソフトで実況動画を作ろうとした。
しかし気づけば星図はそのゲームの世界に入り込み、そして最推しの音声合成ソフトキャラクターと一緒にいた。
さらにおまけに――彼自身も、何らかのヴァーチャル美少女キャラクターへとTSしていたのだ。
入り込んでしまったゲーム世界は、荒廃してしまった容赦の無い世紀末な世界観。
果たして二人の運命や如何に?
Vtuberとかボイスロイド実況動画に影響されて書き始めたお話です。


特殊装甲隊 ダグフェロン 『廃帝と永遠の世紀末』 第四部 『魔物の街』
橋本 直
SF
いつものような日常を過ごす司法局実働部隊の面々。
だが彼等の前に現れた嵯峨茜警視正は極秘の資料を彼らの前に示した。
そこには闇で暗躍する法術能力の研究機関の非合法研究の結果製造された法術暴走者の死体と生存し続ける異形の者の姿があった。
部隊長である彼女の父嵯峨惟基の指示のもと茜に協力する神前誠、カウラ・ベルガー、西園寺かなめ、アメリア・クラウゼ。
その中で誠はかなめの過去と魔都・東都租界の状況、そして法術の恐怖を味わう事になる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















