14 / 56
第14話 ロビーの憂鬱
しおりを挟む
(ロベルト第二王子視点)
僕は名ばかりの王子だ。
第二王子という肩書だけで実質、何の権限もない。
むしろ、こうして十四歳になるまで生きていられるだけでも感謝しなくてはいけない身の上にある。
お母様は薄幸の人だったと耳が痛くなるほどに聞かされてきた。
モニカ・ロシツキー。
ロシツキー家は特産品や鉱山もこれといってない平凡な子爵の家だったと言われていた。
当主も夫人も飾るところのない気さくな人柄なだけで取り立てて、優れた能力を有していた訳ではないらしい。
ただ、お母様が一際、目立つ美貌の持ち主だったのが不幸の始まりだったとしか、思えない。
白銀の美しい髪と紫水晶のような瞳は珍しく、それだけでも人目を引く。
お母様の色を強く受け継いだ僕自身が一番、それを分かっている。
お母様にとって不運だったのはお母様を見初めた相手が王太子だったことだ。
その時、既にディアナ様という正妃がいたお父様――ドミニク・チェフはお母様を公妾という身分で迎え入れたんだ。
子爵家の令嬢に過ぎないお母様に断ることなど、出来るはずがない。
お母様にはパネンカ侯爵夫人という称号に広大な敷地を有する屋敷や豪華な贈り物を寵愛を与えられたが、その頃のお母様は全てを諦めていたのだろう。
それなのに運命とは過酷なものだ。
生きたいと望んでいなかったお母様は国王陛下の御寵愛を一身に受け、僕を身籠ってしまった。
お母様はとても優しい人だったのだと思う。
生きる望みもなく、生きているのに僕を生かそうとしてくれたのだから。
僕はお母様の命を奪うようにして、この世に生を受けた。
お父様は僕のことを憎んでいたのかもしれない。
お母様の色を受け継いだ僕を見るあの人の眼差しに愛情の欠片も感じたことはない。
お母様の命を奪った僕のことを嫌いなんだろう……。
僕に手を差し伸べる者など、誰もいない。
そのまま、死んでもおかしくない状況だった。
そんな僕を引き取って、育ててくれたのがミリアム・ネドヴェトだ。
彼女はお母様と友人だった。
ただ、それだけの理由で僕に手を差し伸べて、助けてくれた。
頼る者とて誰一人いなかった僕に家族が出来たのだ。
優しくて、頼りになる姉に囲まれ、僕は幸せだった。
そして、妹が生まれた。
エミーは小さくて、弱々しくて、守ってあげたい大事な妹だった。
マリーやユナは確かに姉ではあったが、そこに見えない壁のような物が存在していなかったか? と問われると『是』と答えるしかない。
いい友人関係ではあったもののどこか、他人行儀なところがあったのだ。
エミーにはそれがなかった。
僕のことを本当の兄のように慕ってくれた。
僕もまた、彼女のことを実の妹のように思っていた。
そんな関係がずっと続くと考えていた僕が子供だったのだろう。
エミーから向けられる視線はいつしか、違うものになっていたのに僕は気が付かない振りをし続けていた。
もしもエミーの想いに応じたら、これまでの関係が終わってしまう。
そう考えてしまったのだ。
それが間違いであるなどと知らなかった……。
「どういうことなんだい?」
その時の僕は恐らく、間抜けな顔をしていたことだろう。
それだけ、彼――ユリアン・ポボルスキーの言葉が理解に苦しむ内容だったから。
「ですから、このままでは取り返しのつかない事態になるんです。是非、御一考ください、殿下」
「しかし、それにしても変な話だとは思わないかい?」
ユリアンは真面目が服を着ているような人間だった。
あまり冗談を言うタイプではない。
そんな彼が真顔で言っているのだから、何か理由があるに違いない。
それにしてもエミーと距離を置かないとエミーの命が危ないとはどういうことだろうか?
どうにも解せない話だ。
「僕を信じてください。この件に関しては妹にも協力を仰いでいます。ネドヴェト嬢と妹が同級生ですから、大丈夫です」
何が大丈夫なんだ? と聞きたいところだがユリアンのあまりに切羽詰まった様子に頷かざるを得なかった。
そのことを後悔することになろうとは……。
クッキーを断った時、エミーはどんな表情をしていたか。
いつも元気なあの子を悲しませるようなことをして、僕は何をしているんだ!
エミーはあの日から、学校にも来ていない。
マリーやユナに聞いても言葉を濁されるので全く、分からない。
そんな中、エミーが登校した。
焦った僕はユリアンとの約束を忘れ、エミーのいる教室に行ってしまった。
エミーを守ろうとして距離を置いたのに何をしているんだと思いながら、居ても立っても居られなかったのだ。
まさか、エミーに拒絶されるとは思わなかった。
彼女の蒼玉のような瞳に僕が映り込んでいる。
それなのに彼女の心に僕は、存在していないとでも言わんばかりに冷たい反応だった。
何てことだ。
僕はエミーを傷つけてしまったんだ。
どんなに後悔しても謝っても許してもらえないかもしれない。
僕はそこから、どうやって自分の教室に戻ったのか、覚えていない。
ふと我に返った時には剣術の授業を受けていた。
ユナがいつも以上に荒れていた。
何に怒りを抱いているのかは分からないが、それを僕にぶつけようとしている。
それだけは確かだった。
考えてみるとユナはこんなにも自制の利かない人だったろうか?
幼い時から一緒だったが、違和感がある。
男勝りで「騎士にあたしはなる!」と棒切れを振り回して、野山を駆け回る元気過ぎる人ではあった。
だが、言い方がぶっきらぼうなだけだ。
家族思いの優しい性格だったことを知っている。
今のユナはまるでエミーのことを嫌っているどころか、憎んでいるようだ。
そればかりではない。
自分自身をも憎んでいるように見える。
どういうことだろうか。
調べてみる必要がありそうだ。
僕は名ばかりの王子だ。
第二王子という肩書だけで実質、何の権限もない。
むしろ、こうして十四歳になるまで生きていられるだけでも感謝しなくてはいけない身の上にある。
お母様は薄幸の人だったと耳が痛くなるほどに聞かされてきた。
モニカ・ロシツキー。
ロシツキー家は特産品や鉱山もこれといってない平凡な子爵の家だったと言われていた。
当主も夫人も飾るところのない気さくな人柄なだけで取り立てて、優れた能力を有していた訳ではないらしい。
ただ、お母様が一際、目立つ美貌の持ち主だったのが不幸の始まりだったとしか、思えない。
白銀の美しい髪と紫水晶のような瞳は珍しく、それだけでも人目を引く。
お母様の色を強く受け継いだ僕自身が一番、それを分かっている。
お母様にとって不運だったのはお母様を見初めた相手が王太子だったことだ。
その時、既にディアナ様という正妃がいたお父様――ドミニク・チェフはお母様を公妾という身分で迎え入れたんだ。
子爵家の令嬢に過ぎないお母様に断ることなど、出来るはずがない。
お母様にはパネンカ侯爵夫人という称号に広大な敷地を有する屋敷や豪華な贈り物を寵愛を与えられたが、その頃のお母様は全てを諦めていたのだろう。
それなのに運命とは過酷なものだ。
生きたいと望んでいなかったお母様は国王陛下の御寵愛を一身に受け、僕を身籠ってしまった。
お母様はとても優しい人だったのだと思う。
生きる望みもなく、生きているのに僕を生かそうとしてくれたのだから。
僕はお母様の命を奪うようにして、この世に生を受けた。
お父様は僕のことを憎んでいたのかもしれない。
お母様の色を受け継いだ僕を見るあの人の眼差しに愛情の欠片も感じたことはない。
お母様の命を奪った僕のことを嫌いなんだろう……。
僕に手を差し伸べる者など、誰もいない。
そのまま、死んでもおかしくない状況だった。
そんな僕を引き取って、育ててくれたのがミリアム・ネドヴェトだ。
彼女はお母様と友人だった。
ただ、それだけの理由で僕に手を差し伸べて、助けてくれた。
頼る者とて誰一人いなかった僕に家族が出来たのだ。
優しくて、頼りになる姉に囲まれ、僕は幸せだった。
そして、妹が生まれた。
エミーは小さくて、弱々しくて、守ってあげたい大事な妹だった。
マリーやユナは確かに姉ではあったが、そこに見えない壁のような物が存在していなかったか? と問われると『是』と答えるしかない。
いい友人関係ではあったもののどこか、他人行儀なところがあったのだ。
エミーにはそれがなかった。
僕のことを本当の兄のように慕ってくれた。
僕もまた、彼女のことを実の妹のように思っていた。
そんな関係がずっと続くと考えていた僕が子供だったのだろう。
エミーから向けられる視線はいつしか、違うものになっていたのに僕は気が付かない振りをし続けていた。
もしもエミーの想いに応じたら、これまでの関係が終わってしまう。
そう考えてしまったのだ。
それが間違いであるなどと知らなかった……。
「どういうことなんだい?」
その時の僕は恐らく、間抜けな顔をしていたことだろう。
それだけ、彼――ユリアン・ポボルスキーの言葉が理解に苦しむ内容だったから。
「ですから、このままでは取り返しのつかない事態になるんです。是非、御一考ください、殿下」
「しかし、それにしても変な話だとは思わないかい?」
ユリアンは真面目が服を着ているような人間だった。
あまり冗談を言うタイプではない。
そんな彼が真顔で言っているのだから、何か理由があるに違いない。
それにしてもエミーと距離を置かないとエミーの命が危ないとはどういうことだろうか?
どうにも解せない話だ。
「僕を信じてください。この件に関しては妹にも協力を仰いでいます。ネドヴェト嬢と妹が同級生ですから、大丈夫です」
何が大丈夫なんだ? と聞きたいところだがユリアンのあまりに切羽詰まった様子に頷かざるを得なかった。
そのことを後悔することになろうとは……。
クッキーを断った時、エミーはどんな表情をしていたか。
いつも元気なあの子を悲しませるようなことをして、僕は何をしているんだ!
エミーはあの日から、学校にも来ていない。
マリーやユナに聞いても言葉を濁されるので全く、分からない。
そんな中、エミーが登校した。
焦った僕はユリアンとの約束を忘れ、エミーのいる教室に行ってしまった。
エミーを守ろうとして距離を置いたのに何をしているんだと思いながら、居ても立っても居られなかったのだ。
まさか、エミーに拒絶されるとは思わなかった。
彼女の蒼玉のような瞳に僕が映り込んでいる。
それなのに彼女の心に僕は、存在していないとでも言わんばかりに冷たい反応だった。
何てことだ。
僕はエミーを傷つけてしまったんだ。
どんなに後悔しても謝っても許してもらえないかもしれない。
僕はそこから、どうやって自分の教室に戻ったのか、覚えていない。
ふと我に返った時には剣術の授業を受けていた。
ユナがいつも以上に荒れていた。
何に怒りを抱いているのかは分からないが、それを僕にぶつけようとしている。
それだけは確かだった。
考えてみるとユナはこんなにも自制の利かない人だったろうか?
幼い時から一緒だったが、違和感がある。
男勝りで「騎士にあたしはなる!」と棒切れを振り回して、野山を駆け回る元気過ぎる人ではあった。
だが、言い方がぶっきらぼうなだけだ。
家族思いの優しい性格だったことを知っている。
今のユナはまるでエミーのことを嫌っているどころか、憎んでいるようだ。
そればかりではない。
自分自身をも憎んでいるように見える。
どういうことだろうか。
調べてみる必要がありそうだ。
163
あなたにおすすめの小説

地味で器量の悪い公爵令嬢は政略結婚を拒んでいたのだが
克全
恋愛
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
心優しいエヴァンズ公爵家の長女アマーリエは自ら王太子との婚約を辞退した。幼馴染でもある王太子の「ブスの癖に図々しく何時までも婚約者の座にいるんじゃない、絶世の美女である妹に婚約者の座を譲れ」という雄弁な視線に耐えられなかったのだ。それにアマーリエにも自覚があった。自分が社交界で悪口陰口を言われるほどブスであることを。だから王太子との婚約を辞退してからは、壁の花に徹していた。エヴァンズ公爵家てもつながりが欲しい貴族家からの政略結婚の申し込みも断り続けていた。このまま静かに領地に籠って暮らしていこうと思っていた。それなのに、常勝無敗、騎士の中の騎士と称えられる王弟で大将軍でもあるアラステアから結婚を申し込まれたのだ。

「帰ったら、結婚しよう」と言った幼馴染みの勇者は、私ではなく王女と結婚するようです
しーしび
恋愛
「結婚しよう」
アリーチェにそう約束したアリーチェの幼馴染みで勇者のルッツ。
しかし、彼は旅の途中、激しい戦闘の中でアリーチェの記憶を失ってしまう。
それでも、アリーチェはルッツに会いたくて魔王討伐を果たした彼の帰還を祝う席に忍び込むも、そこでは彼と王女の婚約が発表されていた・・・
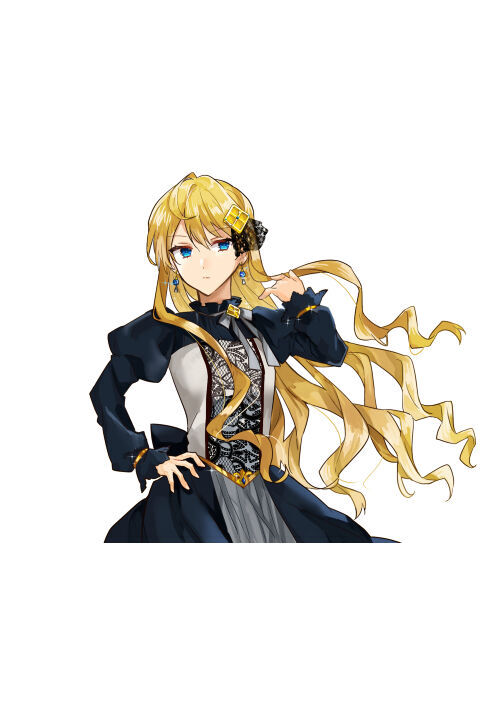
私はどうしようもない凡才なので、天才の妹に婚約者の王太子を譲ることにしました
克全
恋愛
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
フレイザー公爵家の長女フローラは、自ら婚約者のウィリアム王太子に婚約解消を申し入れた。幼馴染でもあるウィリアム王太子は自分の事を嫌い、妹のエレノアの方が婚約者に相応しいと社交界で言いふらしていたからだ。寝食を忘れ、血の滲むほどの努力を重ねても、天才の妹に何一つ敵わないフローラは絶望していたのだ。一日でも早く他国に逃げ出したかったのだ。

可愛い姉より、地味なわたしを選んでくれた王子様。と思っていたら、単に姉と間違えただけのようです。
ふまさ
恋愛
小さくて、可愛くて、庇護欲をそそられる姉。対し、身長も高くて、地味顔の妹のリネット。
ある日。愛らしい顔立ちで有名な第二王子に婚約を申し込まれ、舞い上がるリネットだったが──。
「あれ? きみ、誰?」
第二王子であるヒューゴーは、リネットを見ながら不思議そうに首を傾げるのだった。

わたしの婚約者なんですけどね!
キムラましゅろう
恋愛
わたしの婚約者は王宮精霊騎士団所属の精霊騎士。
この度、第二王女殿下付きの騎士を拝命して誉れ高き近衛騎士に
昇進した。
でもそれにより、婚約期間の延長を彼の家から
告げられて……!
どうせ待つなら彼の側でとわたしは内緒で精霊魔術師団に
入団した。
そんなわたしが日々目にするのは彼を含めたイケメン騎士たちを
我がもの顔で侍らかす王女殿下の姿ばかり……。
彼はわたしの婚約者なんですけどね!
いつもながらの完全ご都合主義、
ノーリアリティのお話です。
少々(?)イライラ事例が発生します。血圧の上昇が心配な方は回れ右をお願いいたします。
小説家になろうさんの方でも投稿しています。

永遠の誓いをあなたに ~何でも欲しがる妹がすべてを失ってからわたしが溺愛されるまで~
畔本グラヤノン
恋愛
両親に愛される妹エイミィと愛されない姉ジェシカ。ジェシカはひょんなことで公爵令息のオーウェンと知り合い、周囲から婚約を噂されるようになる。ある日ジェシカはオーウェンに王族の出席する式典に招待されるが、ジェシカの代わりに式典に出ることを目論んだエイミィは邪魔なジェシカを消そうと考えるのだった。

もっと傲慢でいてください、殿下。──わたしのために。
ふまさ
恋愛
「クラリス。すまないが、今日も仕事を頼まれてくれないか?」
王立学園に入学して十ヶ月が経った放課後。生徒会室に向かう途中の廊下で、この国の王子であるイライジャが、並んで歩く婚約者のクラリスに言った。クラリスが、ですが、と困ったように呟く。
「やはり、生徒会長であるイライジャ殿下に与えられた仕事ですので、ご自分でなされたほうが、殿下のためにもよろしいのではないでしょうか……?」
「そうしたいのはやまやまだが、側妃候補のご令嬢たちと、お茶をする約束をしてしまったんだ。ぼくが王となったときのためにも、愛想はよくしていた方がいいだろう?」
「……それはそうかもしれませんが」
「クラリス。まだぐだぐだ言うようなら──わかっているよね?」
イライジャは足を止め、クラリスに一歩、近付いた。
「王子であるぼくの命に逆らうのなら、きみとの婚約は、破棄させてもらうよ?」
こう言えば、イライジャを愛しているクラリスが、どんな頼み事も断れないとわかったうえでの脅しだった。現に、クラリスは焦ったように顔をあげた。
「そ、それは嫌です!」
「うん。なら、お願いするね。大丈夫。ぼくが一番に愛しているのは、きみだから。それだけは信じて」
イライジャが抱き締めると、クラリスは、はい、と嬉しそうに笑った。
──ああ。何て扱いやすく、便利な婚約者なのだろう。
イライジャはそっと、口角をあげた。
だが。
そんなイライジャの学園生活は、それから僅か二ヶ月後に、幕を閉じることになる。

愛を知らないアレと呼ばれる私ですが……
ミィタソ
恋愛
伯爵家の次女——エミリア・ミーティアは、優秀な姉のマリーザと比較され、アレと呼ばれて馬鹿にされていた。
ある日のパーティで、両親に連れられて行った先で出会ったのは、アグナバル侯爵家の一人息子レオン。
そこで両親に告げられたのは、婚約という衝撃の二文字だった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















