39 / 46
月明かりに照らされて
しおりを挟む
仮面舞踏会の夜、「魔法にかかってみたいか?」と問われたアリシアは、困惑しながらも「まあ、一度はお姫様にもなってみたいかも?」と答えた。バーベナは「そうか」と言ってカラカラと笑い、王宮につけば颯爽と一人で自室に帰ってしまった。
翌日、バーベナに会えぬまま迎えた午後八時。アリシアはイブに来賓用の客室に連れて行かれた。扉を開いた瞬間、部屋の中央に置かれたトルソーが着ているものを見て仰天する。
「わぁ……」
「流行のレースを使ったドレスですね。非常にセンスの良い職人が仕立てたものかと」
よく晴れた青空のような色味が印象的なオフショルダーのドレスには、精緻な花柄模様の白いレースが肩まわりにふんだんに使われている。ウエストの切り替え部分からはボリュームのあるスカートが広がっていて、裾にもレースがあしらわれていた。
「これ、どうしたの?」
「……心あたりはございませんか?」
「あ」
バーベナの顔が浮かぶ。あれは単なる冗談ではなかったのか。
だが、目の前にいるイブは、別の人物を思い浮かべていたらしい。
「セオドア様も、結婚式の前だというのに、どういうつもりでしょう。こんな格好でアラン様を連れ出そうとされるとは」
贈り主は彼ではないのだが。しかしバーベナから贈られたことを気取られるより、話は合わせておいた方がいいかもしれない。それよりも何よりも。
「これを、私が着るの?!」
「そうメモで言付けをいただいております。十時にお迎えが来るそうなので、急ぎませんと」
王子にドレスを着せるなんていう奇想天外な仕事内容では人手を手配することもできないと、イブはせかせかと準備を始めた。アリシアは促されるままに風呂に入り、コルセットを締め上げられ、流れるような彼女の手腕によりみるみるうちに女性へと戻っていく。
「ふう、できました。なんとか十時に間に合いそうです」
「これ、私……?」
鏡の前に立たされたアリシアは、息を呑んだ。
綺麗に巻かれた金色の前髪に、桃色の頬。ドレスに使われているのと同じレースをあしらった髪飾りが可愛らしい。短い髪には付け毛がつけられ、腰まである長髪になっていた。
「お顔立ちはもともと整っていらっしゃいますから、化粧映えがしますね。……もったいないです。女性として生きられたなら、いくらでも着飾る機会が得られたでしょうに」
イブの言葉を聞きながら、アリシアはまだ鏡を覗き込んでいた。
忘れてしまった女心。必死に生きてきて、王子になり代わる前でさえも着飾るなんてことは、とうに諦めていた。
「アリシア様」
本来の自分の名前を呼ばれ、ハッと顔を上げる。
「せっかくですから、楽しんでいらしてください」
「イブ……」
誰かがドアを叩く音がして、イブが応対に出た。お迎えです、と言われて見てみれば、見知らぬ執事が立っている。
「こちらにいらっしゃるご令嬢の案内を仰せつかりました」
若い執事の背について、廊下を歩いていく。途中メンシスの騎士とすれ違い、ヒヤリとしたが。視線を向けられたものの、アリシアがアランであると気付かれることはなかった。
連れられて到着したのは、庭園のガゼボ。綺麗に整えられた緑の生垣、白薔薇が月明かりに照らされている。
「私はここで失礼致します」
執事はそう言って、王宮の中へと戻っていく。
一人残されたアリシアは、ガゼボの下に置かれているテーブルセットに腰掛けた。程なくして背後から、上品なカサブランカの香りがする。
「アリシア」
「……バーベナ?」
振り返って驚く。ドレス姿でも執事の姿でもない。銀糸の刺繍が入った膝まであるコートに青いベスト、首元はクラヴァットで飾られている。ベストと同色のスラックスに、足元はブーツを履いていた。
髪は地毛の銀髪を後ろで結っていて、胸元にはロベリア王家の紋章が刺繍されたエンブレムが飾られている。
まるでロベリアの王子かのような姿のバーベナが、そこには立っていた。
「ど、ど、ど、どうしたの、そのカッコ。カツラは忘れちゃったの?」
「きっちり整えてきたのに、初見の感想がそれ? かっこいいとか素敵~とかないわけ?」
「あっ、ごめん。すごくかっこいいと思う、けど」
バーベナ、いや、今はキリヤと言う方がしっくりくる。
彼がトーナメント以降に見せてきた不機嫌さは、すっかりどこかへ消えてしまったようだ。アリシアは手に持ってきた箱に視線を落とす。
——なんだ。もう機嫌なおったんだ。いらなかったなあ、これ。
仮面舞踏会の夜、さっさと自室に戻られてしまったため、渡しそびれてしまっていた。食事の時に渡そうと、服の中に忍ばせていたのだ。ドレスを着てからは手に持っていた。
「なにそれ」
「トーナメントからずっと機嫌悪かったでしょ。だから、どうにか仲直りできないかなって思って。……キリヤにプレゼントを用意してたんだ」
「……俺に? アラン王子からってことで、バーベナ姫あてのペンダントは受け取ったけど。あれとは別に、『俺』に?」
「うん。城下町まで行って買ってきたの」
「……セオドアと?」
「なんで知ってるの?」
「マジかよ」
ヘナヘナとその場にしゃがみ込み、キリヤは頭を抱える。
「俺はてっきり、デートだと思って」
「まさか! あ、やっぱりあのレストランにいたの、キリヤ?」
「そうだよ! たまたまあんたたちが出かけていくのを見かけて、気になってつけてったんだよ。トーナメントの後、セオドアが告白してから、うまく行っちゃったんじゃないかと思って、俺超焦って」
「そんなわけないでしょ。セオドアはあくまで仕事仲間。突然あんなふうに告白されて、急に男として意識なんかできないよ。っていうか、なんでキリヤが焦るの?」
「……あんた、鈍すぎじゃね? ったく」
キリヤはそう言って、アリシアの手から箱を奪う。
「ちょっと! 渡す前にひったくる? 普通」
「いいだろ、俺のなんだから」
リボンを解き、中身を見た彼は頬を綻ばせた。
「男物、の懐中時計か」
「よく考えたら公費で買った宝石は、持ち出せないなって思って。それは私の個人的なお金で買ったものだから、その、あまりいいものは買えなかったんだけど」
「すげー嬉しい」
グッと腰を抱き寄せられ、キリヤの腕に包まれた。
「あ、あの、キリヤ、ちょっと近いよ。離して」
「やだ、離さない」
「仲良し作戦はやめたんじゃないの?」
「仲良しのふりはやめた」
腕が緩められ、見つめ合う形になる。宝石のような紫の瞳がアリシアをうつす。
これまでふざけてこういうことをされたことはあったが、男の格好でこんなことをされたのは初めてで。恥ずかしくて顔を逸らそうとすれば、「こっちを見て」と囁くように言われた。
「仲良しのふりはやめたって、どういうこと?」
アリシアの言葉に、キリヤの顔が花のように綻ぶ。何かに降参したような、気が緩んだ表情だった。
「俺、アリシアのことが好きみたいなんだよね。まっすぐでお人好しで、誰かのために一生懸命になれるあんたが」
「え」
「セオドアに取られそうになって、自分の気持ちに気づいたんだ。……どんな顔してアリシアと顔を合わせたらいいかわかんなくなっちゃって、あんたと距離取ってた。ごめん」
紅潮したアリシアの頬にキリヤの手が添えられる。近くで見る陶器のような彼の白い肌も、薄く桃色に染まっている。
「言わずに黙って去るべきかとも思った。あんたはここに残る選択をしたから」
「キリヤ……」
「でも言わずにはいられなくなったんだ。あと少ししか一緒にいられないって思ったら。身代わりの姿じゃなく、本来あるべき姿で。あんたに思いを伝えたくて」
すぐそばまで来た彼の鼻が、アリシアの鼻に触れる。
「嫌なら逃げて」
彼の目が細められ、長く白いまつ毛が見えた。
甘くとろけるようなささやきに、アリシアの体は縛られる。
——拒めないよ。だって私も好きだもの。
普通に会話ができなくなって寂しかった。
いつものからかいが恋しかった。
こうして触れ合って、愛されたかった。
できるなら本物の愛情を交わし合って、仮初の関係を捨てて、恋をしたかった。
「アリシア、好きだよ」
あたたかな唇が、アリシアのそれに重ねられる。
穏やかな風が、庭園の白薔薇を揺らしていた。
翌日、バーベナに会えぬまま迎えた午後八時。アリシアはイブに来賓用の客室に連れて行かれた。扉を開いた瞬間、部屋の中央に置かれたトルソーが着ているものを見て仰天する。
「わぁ……」
「流行のレースを使ったドレスですね。非常にセンスの良い職人が仕立てたものかと」
よく晴れた青空のような色味が印象的なオフショルダーのドレスには、精緻な花柄模様の白いレースが肩まわりにふんだんに使われている。ウエストの切り替え部分からはボリュームのあるスカートが広がっていて、裾にもレースがあしらわれていた。
「これ、どうしたの?」
「……心あたりはございませんか?」
「あ」
バーベナの顔が浮かぶ。あれは単なる冗談ではなかったのか。
だが、目の前にいるイブは、別の人物を思い浮かべていたらしい。
「セオドア様も、結婚式の前だというのに、どういうつもりでしょう。こんな格好でアラン様を連れ出そうとされるとは」
贈り主は彼ではないのだが。しかしバーベナから贈られたことを気取られるより、話は合わせておいた方がいいかもしれない。それよりも何よりも。
「これを、私が着るの?!」
「そうメモで言付けをいただいております。十時にお迎えが来るそうなので、急ぎませんと」
王子にドレスを着せるなんていう奇想天外な仕事内容では人手を手配することもできないと、イブはせかせかと準備を始めた。アリシアは促されるままに風呂に入り、コルセットを締め上げられ、流れるような彼女の手腕によりみるみるうちに女性へと戻っていく。
「ふう、できました。なんとか十時に間に合いそうです」
「これ、私……?」
鏡の前に立たされたアリシアは、息を呑んだ。
綺麗に巻かれた金色の前髪に、桃色の頬。ドレスに使われているのと同じレースをあしらった髪飾りが可愛らしい。短い髪には付け毛がつけられ、腰まである長髪になっていた。
「お顔立ちはもともと整っていらっしゃいますから、化粧映えがしますね。……もったいないです。女性として生きられたなら、いくらでも着飾る機会が得られたでしょうに」
イブの言葉を聞きながら、アリシアはまだ鏡を覗き込んでいた。
忘れてしまった女心。必死に生きてきて、王子になり代わる前でさえも着飾るなんてことは、とうに諦めていた。
「アリシア様」
本来の自分の名前を呼ばれ、ハッと顔を上げる。
「せっかくですから、楽しんでいらしてください」
「イブ……」
誰かがドアを叩く音がして、イブが応対に出た。お迎えです、と言われて見てみれば、見知らぬ執事が立っている。
「こちらにいらっしゃるご令嬢の案内を仰せつかりました」
若い執事の背について、廊下を歩いていく。途中メンシスの騎士とすれ違い、ヒヤリとしたが。視線を向けられたものの、アリシアがアランであると気付かれることはなかった。
連れられて到着したのは、庭園のガゼボ。綺麗に整えられた緑の生垣、白薔薇が月明かりに照らされている。
「私はここで失礼致します」
執事はそう言って、王宮の中へと戻っていく。
一人残されたアリシアは、ガゼボの下に置かれているテーブルセットに腰掛けた。程なくして背後から、上品なカサブランカの香りがする。
「アリシア」
「……バーベナ?」
振り返って驚く。ドレス姿でも執事の姿でもない。銀糸の刺繍が入った膝まであるコートに青いベスト、首元はクラヴァットで飾られている。ベストと同色のスラックスに、足元はブーツを履いていた。
髪は地毛の銀髪を後ろで結っていて、胸元にはロベリア王家の紋章が刺繍されたエンブレムが飾られている。
まるでロベリアの王子かのような姿のバーベナが、そこには立っていた。
「ど、ど、ど、どうしたの、そのカッコ。カツラは忘れちゃったの?」
「きっちり整えてきたのに、初見の感想がそれ? かっこいいとか素敵~とかないわけ?」
「あっ、ごめん。すごくかっこいいと思う、けど」
バーベナ、いや、今はキリヤと言う方がしっくりくる。
彼がトーナメント以降に見せてきた不機嫌さは、すっかりどこかへ消えてしまったようだ。アリシアは手に持ってきた箱に視線を落とす。
——なんだ。もう機嫌なおったんだ。いらなかったなあ、これ。
仮面舞踏会の夜、さっさと自室に戻られてしまったため、渡しそびれてしまっていた。食事の時に渡そうと、服の中に忍ばせていたのだ。ドレスを着てからは手に持っていた。
「なにそれ」
「トーナメントからずっと機嫌悪かったでしょ。だから、どうにか仲直りできないかなって思って。……キリヤにプレゼントを用意してたんだ」
「……俺に? アラン王子からってことで、バーベナ姫あてのペンダントは受け取ったけど。あれとは別に、『俺』に?」
「うん。城下町まで行って買ってきたの」
「……セオドアと?」
「なんで知ってるの?」
「マジかよ」
ヘナヘナとその場にしゃがみ込み、キリヤは頭を抱える。
「俺はてっきり、デートだと思って」
「まさか! あ、やっぱりあのレストランにいたの、キリヤ?」
「そうだよ! たまたまあんたたちが出かけていくのを見かけて、気になってつけてったんだよ。トーナメントの後、セオドアが告白してから、うまく行っちゃったんじゃないかと思って、俺超焦って」
「そんなわけないでしょ。セオドアはあくまで仕事仲間。突然あんなふうに告白されて、急に男として意識なんかできないよ。っていうか、なんでキリヤが焦るの?」
「……あんた、鈍すぎじゃね? ったく」
キリヤはそう言って、アリシアの手から箱を奪う。
「ちょっと! 渡す前にひったくる? 普通」
「いいだろ、俺のなんだから」
リボンを解き、中身を見た彼は頬を綻ばせた。
「男物、の懐中時計か」
「よく考えたら公費で買った宝石は、持ち出せないなって思って。それは私の個人的なお金で買ったものだから、その、あまりいいものは買えなかったんだけど」
「すげー嬉しい」
グッと腰を抱き寄せられ、キリヤの腕に包まれた。
「あ、あの、キリヤ、ちょっと近いよ。離して」
「やだ、離さない」
「仲良し作戦はやめたんじゃないの?」
「仲良しのふりはやめた」
腕が緩められ、見つめ合う形になる。宝石のような紫の瞳がアリシアをうつす。
これまでふざけてこういうことをされたことはあったが、男の格好でこんなことをされたのは初めてで。恥ずかしくて顔を逸らそうとすれば、「こっちを見て」と囁くように言われた。
「仲良しのふりはやめたって、どういうこと?」
アリシアの言葉に、キリヤの顔が花のように綻ぶ。何かに降参したような、気が緩んだ表情だった。
「俺、アリシアのことが好きみたいなんだよね。まっすぐでお人好しで、誰かのために一生懸命になれるあんたが」
「え」
「セオドアに取られそうになって、自分の気持ちに気づいたんだ。……どんな顔してアリシアと顔を合わせたらいいかわかんなくなっちゃって、あんたと距離取ってた。ごめん」
紅潮したアリシアの頬にキリヤの手が添えられる。近くで見る陶器のような彼の白い肌も、薄く桃色に染まっている。
「言わずに黙って去るべきかとも思った。あんたはここに残る選択をしたから」
「キリヤ……」
「でも言わずにはいられなくなったんだ。あと少ししか一緒にいられないって思ったら。身代わりの姿じゃなく、本来あるべき姿で。あんたに思いを伝えたくて」
すぐそばまで来た彼の鼻が、アリシアの鼻に触れる。
「嫌なら逃げて」
彼の目が細められ、長く白いまつ毛が見えた。
甘くとろけるようなささやきに、アリシアの体は縛られる。
——拒めないよ。だって私も好きだもの。
普通に会話ができなくなって寂しかった。
いつものからかいが恋しかった。
こうして触れ合って、愛されたかった。
できるなら本物の愛情を交わし合って、仮初の関係を捨てて、恋をしたかった。
「アリシア、好きだよ」
あたたかな唇が、アリシアのそれに重ねられる。
穏やかな風が、庭園の白薔薇を揺らしていた。
0
お気に入りに追加
16
あなたにおすすめの小説

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

後宮の棘
香月みまり
キャラ文芸
蔑ろにされ婚期をのがした25歳皇女がついに輿入り!相手は敵国の禁軍将軍。冷めた姫vs堅物男のチグハグな夫婦は帝国内の騒乱に巻き込まれていく。
☆完結しました☆
スピンオフ「孤児が皇后陛下と呼ばれるまで」の進捗と合わせて番外編を不定期に公開していきます。
第13回ファンタジー大賞特別賞受賞!
ありがとうございました!!

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

先生!放課後の隣の教室から女子の喘ぎ声が聴こえました…
ヘロディア
恋愛
居残りを余儀なくされた高校生の主人公。
しかし、隣の部屋からかすかに女子の喘ぎ声が聴こえてくるのであった。
気になって覗いてみた主人公は、衝撃的な光景を目の当たりにする…
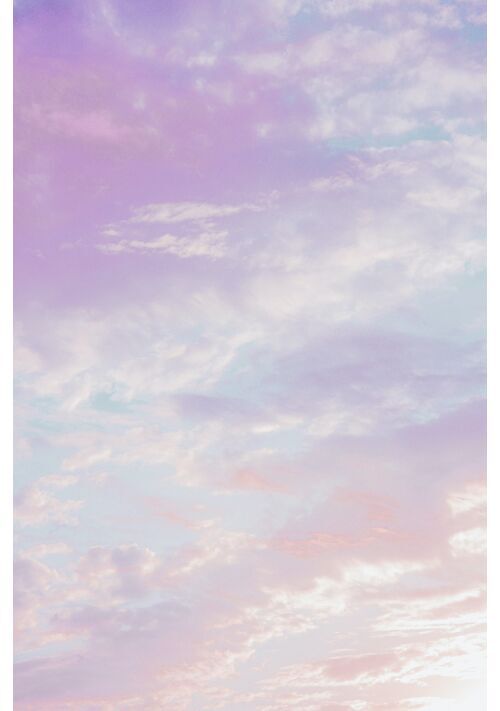
極道に大切に飼われた、お姫様
真木
恋愛
珈涼は父の組のため、生粋の極道、月岡に大切に飼われるようにして暮らすことになる。憧れていた月岡に甲斐甲斐しく世話を焼かれるのも、教え込まれるように夜ごと結ばれるのも、珈涼はただ恐ろしくて殻にこもっていく。繊細で怖がりな少女と、愛情の伝え方が下手な極道の、すれ違いラブストーリー。

冷酷社長に甘く優しい糖分を。
氷萌
恋愛
センター街に位置する高層オフィスビル。
【リーベンビルズ】
そこは
一般庶民にはわからない
高級クラスの人々が生活する、まさに異世界。
リーベンビルズ経営:冷酷社長
【柴永 サクマ】‐Sakuma Shibanaga-
「やるなら文句・質問は受け付けない。
イヤなら今すぐ辞めろ」
×
社長アシスタント兼雑用
【木瀬 イトカ】-Itoka Kise-
「やります!黙ってやりますよ!
やりゃぁいいんでしょッ」
様々な出来事が起こる毎日に
飛び込んだ彼女に待ち受けるものは
夢か現実か…地獄なのか。

イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















