6 / 49
1章(5)
しおりを挟む
将太は弁当が冷めないように、どこにも寄り道することなく一直線で寮まで帰ってきた。部屋の鍵を閉めるのももどかしく、将太は履いていたサンダルを脱ぎ捨てて部屋へ駆け込む。
ちゃぷんと揺れた豚汁の波が収まるのを待ち、そっと蓋を開ける。まだほんのりと温かく、うっすらと湯気が立っている。ショーケースに入っていたおかずは少し冷めていて、将太は電子レンジで温めるか迷った。というのも、温かいタルタルソースはあまり好みではないからだ。しかしすでにかけられたものを別の皿によけるのも面倒である。迷った結果、30秒だけかけることにした。
加熱が終わるまでの30秒で、ご飯の容器も開ける。割り箸で上下を返すと、ほこほことした湯気が上がった。上面にいた米粒は、底の水分を吸って勝手にやわらかくなるというやり方である。コンビニ弁当ばかり食べていると言った時に、寮暮らし5年目の先輩が教えてくれた。
小さなテーブルの上に加熱の終わったおかずとご飯のパック、そして豚汁が並ぶ。
はやる気持ちを抑えて、将太はかすかに湯気の立つ豚汁をすすった。甘めの味噌の風味に、少しだけごま油と生姜の香りがする。箸でかき混ぜると、大きく切られたさつまいもや白菜、こんにゃくなどの具材がこれでもかというほど入っていた。
「おいしい……」
豚肉の量はさほど多くはなかったが、たっぷりと入っている野菜や油揚げのおかげで十分に出汁が出ている。ごま油と生姜の香りだけでも食欲をそそるのに、どうやらにんにくまで入っているらしい。豚肉を噛んだ時に、じゅわっと溢れ出す脂とにんにくの香りが、米に合わないわけがない。
将太は夢中で豚汁をすすり、白米をかき込む。ふと気づいた時には、パックに残るご飯は半分まで減っていた。まだおかずに一切手をつけていないのに。
さつまいもの甘みを噛み締めながら、大きなチキン南蛮を持ち上げる。食べやすいようにカットされてはいるが、それでも重みで箸が震えるほどの大きさだ。
タルタルソースをこぼさないよう気をつけながら、大きく口を開けてかぶりつく。じゅわっと鶏肉の脂が染み出し、温められた甘酢だれの酸味が口と鼻いっぱいに広がる。タルタルソースは玉子と玉ねぎだけというシンプルなもので、酸味はほとんどないため、甘酢だれと合わせて食べやすいようになっていた。タルタルソースというよりは玉子サラダのような雰囲気だが、これはこれでおいしい。
500円という破格だから、てっきり胸肉を使っていると思っていたが、食べてみると皮のついたもも肉だった。それも一枚まるまるである。飲食業に詳しいわけではないが、採算が取れているのか不安になるほどだ。
「あ……もう米ないじゃん」
豚汁とチキン南蛮だけでご飯を平らげてしまった将太は、思い出したかのように副菜に手をつけた。チキン南蛮に添えられていた千切りキャベツは、甘酢だれとタルタルソースが染み込んで絶品だし、いんげんのごま和えも茹で加減がちょうどよく、シャキシャキとしていていい箸休めになる。
そしておそらく自家製らしいポテトサラダには、缶詰のみかんが入っていた。おかずに果物を入れることを嫌う人種がいるのは知っているが、将太は果物入りのおかずが大好きだ。祖母がよく作ってくれたポテトサラダには必ず缶詰のみかんが入っていたし、マカロニサラダにはりんごや柿が入るのが当たり前だった。
ほくほくとしたじゃがいもと、噛むとぷちっと弾けるみかんが将太を祖母の家へと連れ戻す。母子家庭で育った将太は、幼少期のほとんどの時間を祖母の家ですごした。祖母はハンバーグやビーフシチューなんていう洒落た洋食はまったく作らなかったけれど、和食はどれを食べても絶品で、将太の味覚を作ったのは祖母の和食だと言っても過言ではない。
思わぬところで祖母の手料理を思い出し、将太は少しだけ懐かしさとホームシックのような寂しさを覚えた。しかし、そんな寂しさもすぐに心の隅に追いやられる。心も腹も満ち、幸せだけが将太の身を渦巻いている。
片づけもそこそこにベッドに寝転がると、得も言われぬ幸福感が将太を包んだ。幼い頃、お腹いっぱい夕食を食べて、母親が食器を片づけている姿を後ろから眺めていた時のような、大人になってからはそうそう味わえるものではない種類の幸福だ。
「なんか、いい匂いするな」
鍵を閉め忘れたドアから、隣室の小森がひょっこりと顔を出す。どうせ彼女の手作り弁当を自慢しにきたのだろうが、今の将太はそんなものを見せられても羨ましがることはない。
将太は鷹揚に小森を部屋へ上げると、空になった弁当の容器を指した。
ちゃぷんと揺れた豚汁の波が収まるのを待ち、そっと蓋を開ける。まだほんのりと温かく、うっすらと湯気が立っている。ショーケースに入っていたおかずは少し冷めていて、将太は電子レンジで温めるか迷った。というのも、温かいタルタルソースはあまり好みではないからだ。しかしすでにかけられたものを別の皿によけるのも面倒である。迷った結果、30秒だけかけることにした。
加熱が終わるまでの30秒で、ご飯の容器も開ける。割り箸で上下を返すと、ほこほことした湯気が上がった。上面にいた米粒は、底の水分を吸って勝手にやわらかくなるというやり方である。コンビニ弁当ばかり食べていると言った時に、寮暮らし5年目の先輩が教えてくれた。
小さなテーブルの上に加熱の終わったおかずとご飯のパック、そして豚汁が並ぶ。
はやる気持ちを抑えて、将太はかすかに湯気の立つ豚汁をすすった。甘めの味噌の風味に、少しだけごま油と生姜の香りがする。箸でかき混ぜると、大きく切られたさつまいもや白菜、こんにゃくなどの具材がこれでもかというほど入っていた。
「おいしい……」
豚肉の量はさほど多くはなかったが、たっぷりと入っている野菜や油揚げのおかげで十分に出汁が出ている。ごま油と生姜の香りだけでも食欲をそそるのに、どうやらにんにくまで入っているらしい。豚肉を噛んだ時に、じゅわっと溢れ出す脂とにんにくの香りが、米に合わないわけがない。
将太は夢中で豚汁をすすり、白米をかき込む。ふと気づいた時には、パックに残るご飯は半分まで減っていた。まだおかずに一切手をつけていないのに。
さつまいもの甘みを噛み締めながら、大きなチキン南蛮を持ち上げる。食べやすいようにカットされてはいるが、それでも重みで箸が震えるほどの大きさだ。
タルタルソースをこぼさないよう気をつけながら、大きく口を開けてかぶりつく。じゅわっと鶏肉の脂が染み出し、温められた甘酢だれの酸味が口と鼻いっぱいに広がる。タルタルソースは玉子と玉ねぎだけというシンプルなもので、酸味はほとんどないため、甘酢だれと合わせて食べやすいようになっていた。タルタルソースというよりは玉子サラダのような雰囲気だが、これはこれでおいしい。
500円という破格だから、てっきり胸肉を使っていると思っていたが、食べてみると皮のついたもも肉だった。それも一枚まるまるである。飲食業に詳しいわけではないが、採算が取れているのか不安になるほどだ。
「あ……もう米ないじゃん」
豚汁とチキン南蛮だけでご飯を平らげてしまった将太は、思い出したかのように副菜に手をつけた。チキン南蛮に添えられていた千切りキャベツは、甘酢だれとタルタルソースが染み込んで絶品だし、いんげんのごま和えも茹で加減がちょうどよく、シャキシャキとしていていい箸休めになる。
そしておそらく自家製らしいポテトサラダには、缶詰のみかんが入っていた。おかずに果物を入れることを嫌う人種がいるのは知っているが、将太は果物入りのおかずが大好きだ。祖母がよく作ってくれたポテトサラダには必ず缶詰のみかんが入っていたし、マカロニサラダにはりんごや柿が入るのが当たり前だった。
ほくほくとしたじゃがいもと、噛むとぷちっと弾けるみかんが将太を祖母の家へと連れ戻す。母子家庭で育った将太は、幼少期のほとんどの時間を祖母の家ですごした。祖母はハンバーグやビーフシチューなんていう洒落た洋食はまったく作らなかったけれど、和食はどれを食べても絶品で、将太の味覚を作ったのは祖母の和食だと言っても過言ではない。
思わぬところで祖母の手料理を思い出し、将太は少しだけ懐かしさとホームシックのような寂しさを覚えた。しかし、そんな寂しさもすぐに心の隅に追いやられる。心も腹も満ち、幸せだけが将太の身を渦巻いている。
片づけもそこそこにベッドに寝転がると、得も言われぬ幸福感が将太を包んだ。幼い頃、お腹いっぱい夕食を食べて、母親が食器を片づけている姿を後ろから眺めていた時のような、大人になってからはそうそう味わえるものではない種類の幸福だ。
「なんか、いい匂いするな」
鍵を閉め忘れたドアから、隣室の小森がひょっこりと顔を出す。どうせ彼女の手作り弁当を自慢しにきたのだろうが、今の将太はそんなものを見せられても羨ましがることはない。
将太は鷹揚に小森を部屋へ上げると、空になった弁当の容器を指した。
1
お気に入りに追加
16
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

クールな生徒会長のオンとオフが違いすぎるっ!?
ブレイブ
恋愛
政治家、資産家の子供だけが通える高校。上流高校がある。上流高校の一年生にして生徒会長。神童燐は普段は冷静に動き、正確な指示を出すが、家族と、恋人、新の前では

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ヤンデレ美少女転校生と共に体育倉庫に閉じ込められ、大問題になりましたが『結婚しています!』で乗り切った嘘のような本当の話
桜井正宗
青春
――結婚しています!
それは二人だけの秘密。
高校二年の遙と遥は結婚した。
近年法律が変わり、高校生(十六歳)からでも結婚できるようになっていた。だから、問題はなかった。
キッカケは、体育倉庫に閉じ込められた事件から始まった。校長先生に問い詰められ、とっさに誤魔化した。二人は退学の危機を乗り越える為に本当に結婚することにした。
ワケありヤンデレ美少女転校生の『小桜 遥』と”新婚生活”を開始する――。
*結婚要素あり
*ヤンデレ要素あり

独身寮のふるさとごはん まかないさんの美味しい献立
水縞しま
ライト文芸
旧題:独身寮のまかないさん ~おいしい故郷の味こしらえます~
第7回ライト文芸大賞【料理・グルメ賞】作品です。
◇◇◇◇
飛騨高山に本社を置く株式会社ワカミヤの独身寮『杉野館』。まかない担当として働く有村千影(ありむらちかげ)は、決まった予算の中で献立を考え、食材を調達し、調理してと日々奮闘していた。そんなある日、社員のひとりが失恋して落ち込んでしまう。食欲もないらしい。千影は彼の出身地、富山の郷土料理「ほたるいかの酢味噌和え」をこしらえて励まそうとする。
仕事に追われる社員には、熱々がおいしい「味噌煮込みうどん(愛知)」。
退職しようか思い悩む社員には、じんわりと出汁が沁みる「聖護院かぶと鯛の煮物(京都)」。
他にも飛騨高山の「赤かぶ漬け」「みだらしだんご」、大阪の「モダン焼き」など、故郷の味が盛りだくさん。
おいしい故郷の味に励まされたり、癒されたり、背中を押されたりするお話です。
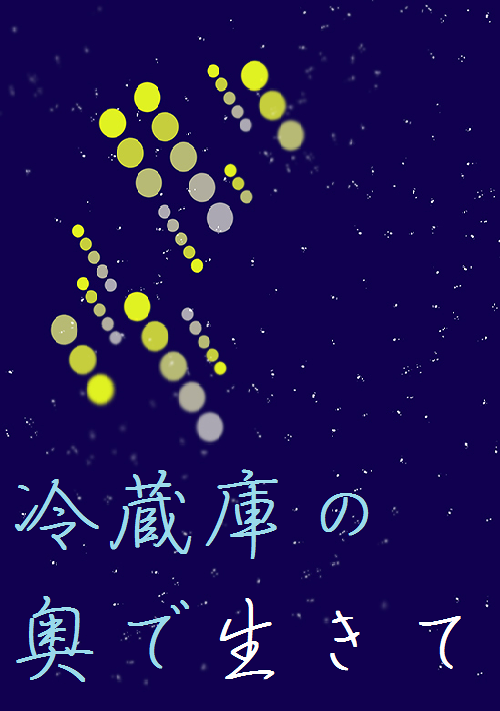
冷蔵庫の奥で生きて
小城るか
ライト文芸
____冷蔵庫の奥にいたのは、かつての恋人で、妹。
専門学生の耕哉には二人の妹がいた。血の繋がらない上の妹、美鈴とは家庭内別居中。唯一の肉親である下の妹、信香は何故か美鈴の味方。
どことなく孤独な日々の中で虚しさを感じていた耕哉は、ある日冷蔵庫が他の家と繋がっていることに気が付く。
それぞれに冷たいものを抱えた、家族達の物語。
※表紙はやまなし様のフリー素材から。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















