11 / 38
3章 明日の刃
3-3
しおりを挟む
時は少しさかのぼり、三日平氏の乱が起きる一月ほど前の鎌倉大倉館の一角。
今はまだ、ただの大きな館でしかないが、後の世ではここを大倉幕府とも呼んでいたとされる。しかし、その一方でこの大倉館の事を陰で大倉院御所と呼ぶ人も居たという。表向きには北条政子の権力に阿る発言だが、その実、北条政子自身は彼女に策を与える娘の存在を抜きには、鎌倉は成り立たなかったとも言ったとか。
さて、その日の鎌倉は、しとしとと秋雨が降る静かな日だった。
数ヶ月前まで、平家打倒の為に田舎から出てきた武士が通りを闊歩し、大声でがなり立て、この一角の住人たる大姫からしたら、気分が悪くなることこの上なかった。
自身が武士の娘であるというのは理解しているが、それでも田舎武士のあの理不尽には閉口する。彼らは彼らで大声を出すのは、それはそれで戦場で名乗りを挙げる為、ひいては武功の為であると理解はしているのだが、気分という物は変えられない。
「はぁ」
大姫は、数ヶ月前の楽しい日々を思い出す。
田舎も田舎、木曽谷生まれの木曽義高。かの人は生まれに引きずられることなく、白い肌と繊細な瞳を持ち、機転も利けば、大学者として高名な大江広元と論を交わせるほどの頭脳の閃きもあった。
それまで大姫は、その様な武士は見たことがなかった。
大姫の中で、武士と言う生き物は、もろ肌脱いで、筋骨隆々とした体を汗で濡らし、大声で叫び、笑い、酒を飲み、下手な歌をがなる粗野で粗雑で、およそ恋とは無縁の存在だった。
ほのかに自分の理想は、平家の公達くらいしか居ないだろうかと思っていたのだが、義高は自分の夫としていきなり。彼女の前に現れた。
ただ現れただけでなく、まるで絵巻の世界から飛び出したかのような凛々しくさわやかな姿でだ。
これを喜ばずして、何を喜びとするのだろうか?
一緒にすごした時間こそ少ないけれど、彼は確かに私の夫だ。
大姫は自身に誓い、母である北条政子にも認めさせた。
当初難色を示していた政子だったが、大姫の執拗な主張と、義高の資質に驚き、しぶしぶと言った呈を装いながらも認めてくれた。
その裏では政子の義経嫌いが作用していた事を大姫は知っているし、むしろ義高を認めさせるために、煽りもした。
大姫の侍女頭、白江から聞いたところ、政子はその実、頼朝亡き後源氏の棟梁は、義経ではまずい。ならば大姫の弟である万寿が跡継ぎに相応しくなるまでの短い期間ならば、一時的に義高に継がせても良いのではないか、と言っていたと知らせてくれた。
まったくお母様の義経殿嫌いは、常軌を逸している。
さすがに理由を大姫は知らないが、政子は出会った瞬間から義経が嫌いだったそうだ。義経が京に出陣し、自侭に戦をしていると聞くと更に顔をしかめ、鎌倉殿たる我が父に
讒言している。
政子直属の女御衆と違い、大姫の周囲にいる女性達は侍女衆と呼ばれている。
政治の表舞台で華やかさを添える女御衆と違い、侍女衆は完全に奥向き専門だ。
本来の役目は、炊事、掃除から書状を作成するための紙や墨の手配。さらには出陣に伴う各種儀式の準備等、見えない部分の全てが仕事だ。
その侍女衆の頭が、大姫お気に入りの白江となる。
当初政子は、白江は侍女衆頭として大姫に仕えているのではなく、あくまで奥向き仕事の一環として大姫の面倒を見ている、と言うのが本来の形としては正しいのだと言い聞かせていた。
しかし言われた方である白江のそんな意識は、大姫に仕えて一週間も立たずに崩壊する。
理由は様々言えるが、一言で言えば畏怖し、臣従したと言うことだ。
そんな白江曰く、義経殿と政子様はお互いに鎌倉殿に対して寵を競っているのだと言う。
そう言われれば、大姫もあまり話した事が無い叔父である義経には、そんな節があったかもと思える。
義経は奥州から、血を分けた兄である頼朝と一緒に戦うためだけに、軍勢も連れずに僅かな数で参じたのだと聞く。
それだけ聞けば、麗しい兄弟の絆と聞こえるだろう。
しかしそれは大姫から見れば欺瞞でしかなく、大姫が気づいている以上に鎌倉殿である頼朝は気づいている。
本来であれば奥州藤原氏を味方につけ、大軍勢を率い、堂々たる参陣をしたほうが、お互いのためだった。頼朝は一兵でも多く武士を味方にしたかったし、何より血縁のある将軍候補がほしかったのだ。
そんな頼朝の期待に気づく事無く、義経は一刻でも早く兄に会いたいが為、鎌倉の背後の脅威である、奥州藤原氏を味方にしての参陣ではなく、身一つ軍勢も連れずに参陣したため、現在の様な微妙な立場となってしまっている。
これも、利で考えるのではなく、女御の恋慕にも似た気持ちと思えばなんとなく腑に落ちるのだ。
利で物事を考え、じわじわと考えた通りに物事を運ぶ頼朝と、思いのままに振舞う義経。
これで義経が愚弟で、なんの才能も無ければまだ救いがあるが、義経は軍事の天才で常勝無敗の将軍なのだ。
「困ったお人だこと」
恋慕を忘れて良い訳ではないと、大姫も思う
しかし、あの父に利ではなく情のみで対したらどうなるか?ましてや常勝将軍の立場で接したら・・・。答えは明白である。
翻って自分はどうなのか?
実際、自分は未だに木曽義高、清水冠者と呼ばれた我が夫を思慕しているし、片時も忘れてはいない。
父である頼朝から義高の死を聞いたときは、即座に命を絶とうとしたが、その為の守り刀を義高に預けてあった故、すぐには自害できなかった。
そのうちに、義高とされる死体が埋葬されたそうだが、何処からも守り刀の話が出てこない。
まさか討ったと主張する者が、守り刀をこっそり懐に入れるとも思えない。あれは源氏嫡流のみが許される装飾が入っているからだ。
もしそんな物を他に見せびらかそうとしたら、即座に通報され、鎌倉殿から掠め取ったと噂されるだろう。
そんな事から考えても、大姫は義高は生存していると信じている。
しかし、それを他に漏らしはしない。
今は、義高の死に悲しみ、満足にも動けない弱い姫である方が都合がよいのだ。
近頃の大姫は、義高が身代わりとして残して行った海野幸氏から、信濃秘伝の薬を処方され、弱かった体は快方に向かっている。
大姫が得ている情報は、頼朝が準備した諸国と鎌倉との情報網を利用して、白江ら侍女衆を使い集めている。彼女等は書簡の管理を任されている武士の下で働いている事もあり、情報は筒抜けだったからだ。
まさかお父様も実はお父様に次いで、私が情報通である事は知らない筈。
布団に入りながら諸国の情報を集め、大姫は正確な現在の源平合戦の状況を、頭の中だけで描いている。
「白江はいる?」
「はい、御前に」
音も無く、大姫の前で両膝をついて出てくる白江。
元は出雲地方の武士の娘となっている白江だが、その、実彼女は出雲大社を守る偲びの一族の出だった。それを知るのは大姫だけで、雇い主であった政子も知らない。
白江が、それだけ大姫に心服している証だ。
「使いをお願い」
「はい大姫様、どちらまで?」
「う~んそうね、本当なら義高殿と言いたい所だけれど、それは難しいわね、いいわ、叔父様、この度判官になられた九朗叔父様に繋ぎをつけて頂戴」
「九朗様ですか?あの京にいる?」
白江が無表情ながら、僅かだけ首を傾げた。そうするとまるで十も若返った様に見える。
大姫はそうだからこそ白江が気に入り、自らの腹心として手元に置いている。
この顔で彼女は武士を誑かして命を奪い、出雲の神器を守ってきたのよねぇ
大姫は飽きるまでそんな白江の顔を観察すると、再度言った。
「ええそうよ、九朗義経叔父様に大姫からの特別の使者として、もちろんわかっていることだけれど、お母様にも、鎌倉殿にも、白江の本当の雇い主である大社と御実家にも内緒よ、出来る?」
「・・・・・・はっ」
大社の名前が出た時に一瞬白江は息が止まりそうになった。彼女の本当の出自は自らがばらしたのだが、未だに繋がりがあり、山陰にあって源家の情報を集めている生家を知られていたとは。
確かに大姫には、情報を集め、分析し、結論を出す能力に非凡な物があると思っていたが、ここまでとは白江は思っていなかった。
まさに、一天万乗の能力と言えるかもしれない。もし世に男女の別が無ければ、原野でも馬上でも大海の上でもなく、布団の上で天下を制するのは我が姫かもしれない。
そんな事を感じる白江だった。
「ふふっこれで、少しは義高殿のためになるかしらん」
頬が紅潮してきた大姫は、顔を半分布団に隠して笑った。
今はまだ、ただの大きな館でしかないが、後の世ではここを大倉幕府とも呼んでいたとされる。しかし、その一方でこの大倉館の事を陰で大倉院御所と呼ぶ人も居たという。表向きには北条政子の権力に阿る発言だが、その実、北条政子自身は彼女に策を与える娘の存在を抜きには、鎌倉は成り立たなかったとも言ったとか。
さて、その日の鎌倉は、しとしとと秋雨が降る静かな日だった。
数ヶ月前まで、平家打倒の為に田舎から出てきた武士が通りを闊歩し、大声でがなり立て、この一角の住人たる大姫からしたら、気分が悪くなることこの上なかった。
自身が武士の娘であるというのは理解しているが、それでも田舎武士のあの理不尽には閉口する。彼らは彼らで大声を出すのは、それはそれで戦場で名乗りを挙げる為、ひいては武功の為であると理解はしているのだが、気分という物は変えられない。
「はぁ」
大姫は、数ヶ月前の楽しい日々を思い出す。
田舎も田舎、木曽谷生まれの木曽義高。かの人は生まれに引きずられることなく、白い肌と繊細な瞳を持ち、機転も利けば、大学者として高名な大江広元と論を交わせるほどの頭脳の閃きもあった。
それまで大姫は、その様な武士は見たことがなかった。
大姫の中で、武士と言う生き物は、もろ肌脱いで、筋骨隆々とした体を汗で濡らし、大声で叫び、笑い、酒を飲み、下手な歌をがなる粗野で粗雑で、およそ恋とは無縁の存在だった。
ほのかに自分の理想は、平家の公達くらいしか居ないだろうかと思っていたのだが、義高は自分の夫としていきなり。彼女の前に現れた。
ただ現れただけでなく、まるで絵巻の世界から飛び出したかのような凛々しくさわやかな姿でだ。
これを喜ばずして、何を喜びとするのだろうか?
一緒にすごした時間こそ少ないけれど、彼は確かに私の夫だ。
大姫は自身に誓い、母である北条政子にも認めさせた。
当初難色を示していた政子だったが、大姫の執拗な主張と、義高の資質に驚き、しぶしぶと言った呈を装いながらも認めてくれた。
その裏では政子の義経嫌いが作用していた事を大姫は知っているし、むしろ義高を認めさせるために、煽りもした。
大姫の侍女頭、白江から聞いたところ、政子はその実、頼朝亡き後源氏の棟梁は、義経ではまずい。ならば大姫の弟である万寿が跡継ぎに相応しくなるまでの短い期間ならば、一時的に義高に継がせても良いのではないか、と言っていたと知らせてくれた。
まったくお母様の義経殿嫌いは、常軌を逸している。
さすがに理由を大姫は知らないが、政子は出会った瞬間から義経が嫌いだったそうだ。義経が京に出陣し、自侭に戦をしていると聞くと更に顔をしかめ、鎌倉殿たる我が父に
讒言している。
政子直属の女御衆と違い、大姫の周囲にいる女性達は侍女衆と呼ばれている。
政治の表舞台で華やかさを添える女御衆と違い、侍女衆は完全に奥向き専門だ。
本来の役目は、炊事、掃除から書状を作成するための紙や墨の手配。さらには出陣に伴う各種儀式の準備等、見えない部分の全てが仕事だ。
その侍女衆の頭が、大姫お気に入りの白江となる。
当初政子は、白江は侍女衆頭として大姫に仕えているのではなく、あくまで奥向き仕事の一環として大姫の面倒を見ている、と言うのが本来の形としては正しいのだと言い聞かせていた。
しかし言われた方である白江のそんな意識は、大姫に仕えて一週間も立たずに崩壊する。
理由は様々言えるが、一言で言えば畏怖し、臣従したと言うことだ。
そんな白江曰く、義経殿と政子様はお互いに鎌倉殿に対して寵を競っているのだと言う。
そう言われれば、大姫もあまり話した事が無い叔父である義経には、そんな節があったかもと思える。
義経は奥州から、血を分けた兄である頼朝と一緒に戦うためだけに、軍勢も連れずに僅かな数で参じたのだと聞く。
それだけ聞けば、麗しい兄弟の絆と聞こえるだろう。
しかしそれは大姫から見れば欺瞞でしかなく、大姫が気づいている以上に鎌倉殿である頼朝は気づいている。
本来であれば奥州藤原氏を味方につけ、大軍勢を率い、堂々たる参陣をしたほうが、お互いのためだった。頼朝は一兵でも多く武士を味方にしたかったし、何より血縁のある将軍候補がほしかったのだ。
そんな頼朝の期待に気づく事無く、義経は一刻でも早く兄に会いたいが為、鎌倉の背後の脅威である、奥州藤原氏を味方にしての参陣ではなく、身一つ軍勢も連れずに参陣したため、現在の様な微妙な立場となってしまっている。
これも、利で考えるのではなく、女御の恋慕にも似た気持ちと思えばなんとなく腑に落ちるのだ。
利で物事を考え、じわじわと考えた通りに物事を運ぶ頼朝と、思いのままに振舞う義経。
これで義経が愚弟で、なんの才能も無ければまだ救いがあるが、義経は軍事の天才で常勝無敗の将軍なのだ。
「困ったお人だこと」
恋慕を忘れて良い訳ではないと、大姫も思う
しかし、あの父に利ではなく情のみで対したらどうなるか?ましてや常勝将軍の立場で接したら・・・。答えは明白である。
翻って自分はどうなのか?
実際、自分は未だに木曽義高、清水冠者と呼ばれた我が夫を思慕しているし、片時も忘れてはいない。
父である頼朝から義高の死を聞いたときは、即座に命を絶とうとしたが、その為の守り刀を義高に預けてあった故、すぐには自害できなかった。
そのうちに、義高とされる死体が埋葬されたそうだが、何処からも守り刀の話が出てこない。
まさか討ったと主張する者が、守り刀をこっそり懐に入れるとも思えない。あれは源氏嫡流のみが許される装飾が入っているからだ。
もしそんな物を他に見せびらかそうとしたら、即座に通報され、鎌倉殿から掠め取ったと噂されるだろう。
そんな事から考えても、大姫は義高は生存していると信じている。
しかし、それを他に漏らしはしない。
今は、義高の死に悲しみ、満足にも動けない弱い姫である方が都合がよいのだ。
近頃の大姫は、義高が身代わりとして残して行った海野幸氏から、信濃秘伝の薬を処方され、弱かった体は快方に向かっている。
大姫が得ている情報は、頼朝が準備した諸国と鎌倉との情報網を利用して、白江ら侍女衆を使い集めている。彼女等は書簡の管理を任されている武士の下で働いている事もあり、情報は筒抜けだったからだ。
まさかお父様も実はお父様に次いで、私が情報通である事は知らない筈。
布団に入りながら諸国の情報を集め、大姫は正確な現在の源平合戦の状況を、頭の中だけで描いている。
「白江はいる?」
「はい、御前に」
音も無く、大姫の前で両膝をついて出てくる白江。
元は出雲地方の武士の娘となっている白江だが、その、実彼女は出雲大社を守る偲びの一族の出だった。それを知るのは大姫だけで、雇い主であった政子も知らない。
白江が、それだけ大姫に心服している証だ。
「使いをお願い」
「はい大姫様、どちらまで?」
「う~んそうね、本当なら義高殿と言いたい所だけれど、それは難しいわね、いいわ、叔父様、この度判官になられた九朗叔父様に繋ぎをつけて頂戴」
「九朗様ですか?あの京にいる?」
白江が無表情ながら、僅かだけ首を傾げた。そうするとまるで十も若返った様に見える。
大姫はそうだからこそ白江が気に入り、自らの腹心として手元に置いている。
この顔で彼女は武士を誑かして命を奪い、出雲の神器を守ってきたのよねぇ
大姫は飽きるまでそんな白江の顔を観察すると、再度言った。
「ええそうよ、九朗義経叔父様に大姫からの特別の使者として、もちろんわかっていることだけれど、お母様にも、鎌倉殿にも、白江の本当の雇い主である大社と御実家にも内緒よ、出来る?」
「・・・・・・はっ」
大社の名前が出た時に一瞬白江は息が止まりそうになった。彼女の本当の出自は自らがばらしたのだが、未だに繋がりがあり、山陰にあって源家の情報を集めている生家を知られていたとは。
確かに大姫には、情報を集め、分析し、結論を出す能力に非凡な物があると思っていたが、ここまでとは白江は思っていなかった。
まさに、一天万乗の能力と言えるかもしれない。もし世に男女の別が無ければ、原野でも馬上でも大海の上でもなく、布団の上で天下を制するのは我が姫かもしれない。
そんな事を感じる白江だった。
「ふふっこれで、少しは義高殿のためになるかしらん」
頬が紅潮してきた大姫は、顔を半分布団に隠して笑った。
10
あなたにおすすめの小説

戦国終わらず ~家康、夏の陣で討死~
川野遥
歴史・時代
長きに渡る戦国時代も大坂・夏の陣をもって終わりを告げる
…はずだった。
まさかの大逆転、豊臣勢が真田の活躍もありまさかの逆襲で徳川家康と秀忠を討ち果たし、大坂の陣の勝者に。果たして彼らは新たな秩序を作ることができるのか?
敗北した徳川勢も何とか巻き返しを図ろうとするが、徳川に臣従したはずの大名達が新たな野心を抱き始める。
文治系藩主は頼りなし?
暴れん坊藩主がまさかの活躍?
参考情報一切なし、全てゼロから切り開く戦国ifストーリーが始まる。
更新は週5~6予定です。
※ノベルアップ+とカクヨムにも掲載しています。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?
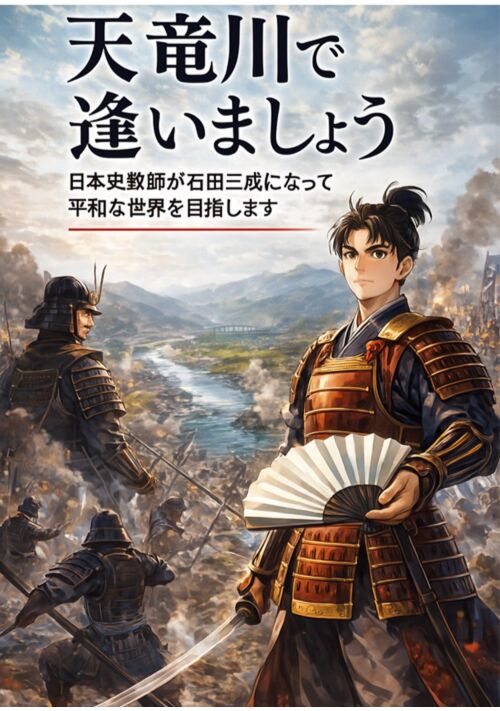
天竜川で逢いましょう 〜日本史教師が石田三成とか無理なので平和な世界を目指します〜
岩 大志
歴史・時代
ごくありふれた高校教師津久見裕太は、ひょんなことから頭を打ち、気を失う。
けたたましい轟音に気付き目を覚ますと多数の軍旗。
髭もじゃの男に「いよいよですな。」と、言われ混乱する津久見。
戦国時代の大きな分かれ道のド真ん中に転生した津久見はどうするのか!!???
そもそも現代人が生首とか無理なので、平和な世の中を目指そうと思います。
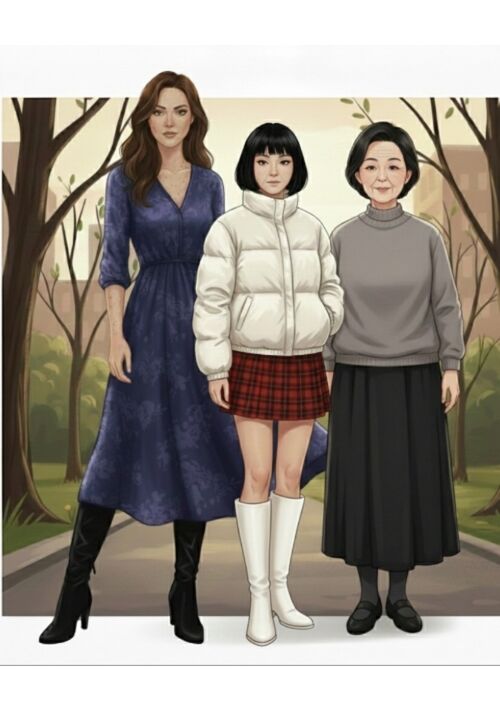
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

織田信長IF… 天下統一再び!!
華瑠羅
歴史・時代
日本の歴史上最も有名な『本能寺の変』の当日から物語は足早に流れて行く展開です。
この作品は「もし」という概念で物語が進行していきます。
主人公【織田信長】が死んで、若返って蘇り再び活躍するという作品です。
※この物語はフィクションです。

織田信長 -尾州払暁-
藪から犬
歴史・時代
織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。
守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。
織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。
そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。
毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。
スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
(2022.04.04)
※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。
※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















