4 / 12
第三章 とりさんのおはなし 参
とりさんのおはなし 参
しおりを挟む
第三章「とりさんのおはなし 参」
すっと桟敷に立つ雷鳴丸。日の光を浴びて翼が美しくひかり、頭にのる鶏冠は周囲一帯を睥睨する風格を持っている。
瞳は鋭く、しかしどこか優しさも持って、前にいる同属を睨み付けている。
雷鳴丸は勇者だ。
弱きを助け、強きもの達から守り、それを生きがいとし、今はしがない人と言う家来の為にその身を率先して戦いに投じている。安穏とした生を守り、自らに希望を託す人と言う家来の為に戦う。
雷鳴丸は勇者だった。
と、思っていそうだなぁ、絶対に人は餌を運ぶ家臣くらいにしか思っていないだろうな、と正嗣は雷鳴丸の勇姿を見つめていた。
ことすれば自分よりも頼りがいの有りそうな後姿だ。渡会の家長はもしかしたら雷鳴丸かもしれぬな。
「渡会様、大丈夫ですよね、とりさんは」
両の手を胸の前で握り締め、強く鋭い眼差しで雷鳴丸を見つめるふたみ。相手の奇岩丸は大きさで雷鳴丸の半分と少ししかない。貫禄で言えば完全に雷鳴丸の勝ちだ。
「大丈夫、雷鳴丸が負ける姿など想像がつかぬ」
あの鶏は名づけられる前から人に対しても、他の動物に対しても尊大で、それ以上に強かった。仲間を襲いに来た狸を返り討にした事もあれば、烏や鳶などが縄張りに入ってきたのを一撃で撃退した事もある。
闘鶏は初めてだが、戦いが初めてというわけではない。
「そっそうですね、わたしもです、あのとりさんは負けません」
「うん、どちらかと言えば心配は相手の方だ、怪我などさせぬと良いがな」
闘鶏で戦えば必ず傷が付く。酷い傷を受ければ、その鶏は明日には食膳に昇る事になってしまう。それを避けたいが為にふたみの商いに乗ったのだ。目的の為なら、少ない犠牲を許容できる男ならば、今こうなってはいない。
「始まるの」
鷹司が、珍しく真剣な目をしている。真剣勝負を見守るには真剣でないと
、という事か。
黒っぽい色を持つ奇岩丸が雷鳴丸を警戒しながら、ゆっくりと近づいていく、対して雷鳴丸はそんな奇岩丸の動きをくいっと見るだけで動かない。勇気があるならかかってこいとでも言いたげな自信に満ち溢れていて、とても闘鶏が初めての鶏には見えない。
素早く不規則な歩調で奇岩丸が雷鳴丸の周囲を飛び回る。隙を探っているのか不規則な動きなので、正嗣が戦っても読みが外れそうな秀逸な動きだ。忍び者ならこのような動きをするかもしれない。
ばさっと羽を広げ奇岩丸が大地を蹴り、爪を雷鳴丸に突き刺そうと上から襲い掛かろうとする。しかしそれは雷鳴丸の大きさを見誤る動きだった。奇岩丸の跳躍は童よりも大きな雷鳴丸の頭上を取ることは出来ず、羽の一振りで叩き落されてしまう。
素早く姿勢を戻した奇岩丸は再度、雷鳴丸の隙を狙うように周囲を跳ね回るが、正嗣の目から見ても、その動きは先ほどよりも鈍い。
それでも果敢に挑みかかる奇岩丸。
もう止めた方が良いのではないかと正嗣が思ったときに奇岩丸が動いた。今度は跳躍の前に地面の砂を雷鳴丸の顔に目掛けて飛ばしてから大地を蹴った。
その砂粒を目くらましに攻撃を仕掛ける奇岩丸。延ばした爪の先には、しかし雷鳴丸の姿はなかった。
その場でくるりと回転して砂粒を避けた雷鳴丸が、空中にいる奇岩丸の横に居た。
そして、場を圧する雷鳴が轟いた。
周囲で見ていた博徒たちから、驚きのうめき声が上がる。
「勝負ありじゃの」
雷鳴にどよめいて動かない博徒たちを見て、観戦していた鷹司が前に出る。雷鳴丸の足元には泡を吹いて倒れている奇岩丸がぐったりしている。切り傷等の外傷はないだろうが、鶏の耳の構造は判らないが正之助の様になっていては困る。
鷹司に続いて正嗣も前に出て、闘鶏場の奇岩丸の様子を伺う。
「血は出ていないな、それ以外に外傷はなし、体も温かいから死んではいないだろうが、むっ」
正嗣が奇岩丸の口元に手を添えると、呼吸の気配がない。
瞬間、正嗣の脳裏には剣道場で呼吸できなくなった少年を助けた師範の姿が浮かんだ。
あの時は、胸に強烈な一撃を入れられた少年に即座に近づいた師範が落ち着いて顔を持ち上げていた。
「こうか・・・」
即座に奇岩丸の顔を上げて、気道を確保。それでも呼吸は回復しない。たしか呼吸が長く回復しないと、命は助かっても考える力みたいなのが失われるらしい。
呼吸が回復しないのを見た正嗣はそこで、奇岩丸のくちばしをしっかり固定すると、水からの口で空気を送り込んだ。
背後からふたみの悲鳴の様な声や、博徒たちのどよめきが聞こえるが、今はそれどころじゃない。こっちは命がかかっているんだ。
生臭いくちばしの匂いに閉口しそうになるが、ぐっと耐えて、さらに空気を送り込む。同時に胸の周りを押して空気を吐き出すように促す。
最初はどよめいていた博徒たちも、その正嗣の姿を見て次第に静かになっていく。
「だめかっ」
十回ほど空気を送り込み、押し出させて、それでも奇岩丸の呼吸は戻らない。このままでは助からない。
絶望しかけた時、ふたみと、彼女を守るように雷鳴丸が正嗣のそばに来た。
無言で息を送り込みながら、視線が雷鳴丸と繋がる。ちょっと離れろと言っているような気がした。
その時の自分の感覚はうまく説明できないが、とにかく正嗣は奇岩丸を雷鳴丸の足も元に置いて二歩離れた。
雷鳴丸が大きく胸を膨らませ、体中に空気を溜め込む。いつもの雷鳴の様な泣き声を発する時よりも大きな動きだ。
もう空気はこれ以上はいらないだろうと思った刹那、特大の雷鳴が響き渡る。近くにいたふたみの服がまくれ上がる位の圧力だ。
「どうだっ」
何を期待していたのだろう。まさか鶏が鶏を救うと自分は思ったのであろうか。いささかの自嘲と僅かな希望をもって奇岩丸を見る。動いていない。手をくちばしに添える。生温かい風。
生きている。呼吸をしている。
先ほどまでの機敏な動きは出来ていないが、それでも奇岩丸はゆっくり起き上がる。首を左右に振り、人間ならまるで寝起きで前後不覚の状態の様に見えた。
「もう、大丈夫であろう」
もうすこし時間がたたないと何かの障害が出るか分からないが、とにかく命は助かった。雷鳴丸が命を奪うところを見たくなかった正嗣である。
「お前さんの勝ちだ、うちの奇岩丸はこれでも前西大関だったんだぜ、今回横綱が出れなかったら奇岩丸が東の横綱と戦うしかないと考えていた、しかしこのざまじゃ、それもできねぇ、いいさ、お武家さんの雷鳴丸には西の横綱として出てもらおう、いや、是非にも出て頂きたい、こんな雄姿見せられたら、日本一の鶏と言っても過言じゃない」
親分は下手褒めだった。先ほどまでの威圧的な迫力は也を潜め、純粋に雷鳴丸に対して尊敬の様な物を滲ませている。
それだけこの親分は闘鶏に対して真摯なのだろう。
「そちらの鶏が無事で良かった、すぐに全快とはいかないだろうが、それでも良かった」
「渡会様・・・・・・」
いつの間にかふたみが、土で汚れていた手を布で拭いてくれていた。よく見れば膝も土で黒くなっている。
無我夢中で飛び出して、闘鶏場の真ん中で救命作業をした代償だったが
正嗣はむしろ誇らしい気分だった。
動物狂いで、動物を守ると公言している正嗣だったが、自らの手でひとつの命を救ったの初めてだったのだ。
「ああすまぬな、ふたみ、汚れてしまうぞ」
両手を拭き、さらに膝まで拭こうとするふたみ。彼女の鋭い両の目には涙が浮かんでいた。手ぬぐいよりやや厚めの布が、どんどん黒くなっていく。
「いいんです、私、なんか、すごい、何かしなきゃいけないような気持ちで一杯で、本当はとりさんにも一杯感謝しなきゃいけないんですけど、なんか避けられそうで」
雷鳴丸ならそうだろう。
正嗣以外の人間が触れば、怪我の一つも覚悟しなければならない。
ふたみが名付け親だと気づけば、そのような事もないかもしれないが、いかんせん鶏にそれを期待しても仕方がない。
「勝って良かった、誰も何も死ななくて良かった、だけど、ここはまだ序の口だ、これから明日の勝負に向けて、ふたみにはやる事があるじゃないか」
そう明日の東の横綱との対戦は本題ではない、本題は勝つ事と、勝った時の条件を交渉することだ。
正嗣にはそれは出来ない。
ふたみがいて、しっかりと交渉出来てこそ助け舟が出せるのだ。
「わかっています、とりさんも渡会様もがんばって頂きました、ここからは商い人として私がしっかりと交渉しなければなりません、ありがとうございます」
「よしっ頑張れ、某もついているし、たぶん鷹司も協力くらいはするだろう、思う存分ぶつかっていけ「
ふたみのおかげで綺麗になった手。その手で彼女の頭を撫でる
瞬間嬉しそうに頬に笑みを浮かべたふたみは、すぐに鋭い目を取り戻して親分へと向き直る。
「私は伊勢の国、久居藩御用の伊勢屋藤兵衛が次女のふたみです、謹んで親分さんにお願いの儀があります、どうかお聞き届けくださいますよ、お願い申し上げます」
声に震えや怯えなど一切見せない、しっかりとした挨拶だった。最初に親分の前に出た時は正嗣の裾を掴み、おどおどしながらだったのが嘘のようだ。
「これはご丁寧に、ならばこちらもしっかりと挨拶させてもらいましょう、生国と申せば河内の山奥、かつては大楠公が開いた赤坂に産湯をつかり、長じて熊野三山の端でしがない一家を預からせて貰っております、性は板野、名は文吉、ただただ賭け事に生を賭ける博徒でございます」
幼少の、齢九つのふたみに対して、おそらく理解できるようにと言葉をだいぶ崩して挨拶する板野親分。
ではっと言って、ふたみを案内する。籠に入った雷鳴丸を背負い、正嗣とふたみは三内去れるまま、板野親分についていく。
鷹司はと言えば、なにやら博徒に混じって楽しそうに話しているし、伊増の姿は見えない。どちらも交渉はふたみに任せている、と言うことなのだろう。
闘鶏場から少し進むと、先ほどの簡易的な小屋とは違い、しっかりとした社殿が見えてきた。八幡様の社殿ではないので、これは熊野の社殿を輸送して組み立てた物だろう。五十人が入っても問題なさそうな広さだ。
朱にぬられた柱を横目に一歩足を中に踏み入れれば、白地に極彩色で描かれたさま尼名紙の姿が描かれている。
知識の乏しい正嗣だったが、天照大御神や須佐の神、八股烏の存在し分かった。
これを、今回の神事の為に運ばせる事が出来る板野親分の力の大きさに震えそうになる。
だがな、ふたみが震えていないのに、某だけが震えるわけにはいかぬ。
と、気合を入れる正嗣である。
対してふたみも、壁や天井に描かれている神代の世界を見つめてはいるが、正嗣のように圧倒されたりはしていない。
父から受けた商いの知識から、唐物の極彩色には慣れているし、神代の話も文として読んだ事もある。
「よっと、ここで話をするがいいかね」
なにやら大きな床机の様な物。それをはさむ様に平板に足が四つついている物の前で板野親分は此方を誘った。
「ええ、もちろん構いません」
木を組んだ床几の様な物をどのように扱えばいいのか正嗣は分からなかったが、ふたみは親分の誘いに乗って、木組の床几を引くと、身軽に座った。
背の高い床几なので、ふたみの両足は地から離れてぷらぷらとしている。
なにやら落ち着かない座具であるな。
ふたみの真似をして座る正嗣。床几よりだいぶ背が高く、尻の下には動物の皮をなめした物が使われているが、とにかく硬い。
床几は座る部分が布で、その張りを自ら調節できるので、柔らかさは好みで変えられる。
「腰や足が悪くなると、この様な唐物の床几が楽で良くてな、簡易ながら運ばせている、お武家さんには珍しくもあろうが、まあくつろいでいただけませんか」
「某は今は付き添いだ、気にせんでくれ」
「承知しております、さて、ではふたみ殿、話を承ろうか」
「は、はい、焦点を絞らせてもらいます、とりさんが西の横綱として闘鶏に参加するにあたり、まず参加条件は勝ち負けに関わらず、雷鳴丸、渡会様、私には一切手出し無用に願います、負けた場合の条件も同じで、それだけです」
板野親分は、目を閉じ、腕を組んで黙って聞いている。ふたみの言葉にかすかにうなづくだけだ。鷹司の名前が出てこないのは、あの公家様ならなんでも飄々となんとかしてしてしまうからだろう。
「それで、勝った場合はどうするね」
「は、はい、とりさんが勝った場合は、今後久居での神事ではない闘鶏の中止と、今回の横綱戦で得る物の半分を頂戴します、またこの一戦以降とりさんは闘鶏には絶対に参加しません、以上です」
東西の大親分達が一同に会する闘鶏大会だ。鷹司に聞いたが近畿でこれほどの規模で闘鶏が行われるのは稀で、実際に目にした者はいず、書に書かれているばかだという。
もちろん掛かりも莫大だろうが、賭かっている額も莫大だろう。
それの目玉対戦である。半分とはいえ、正嗣が五人位いても一生遊んで暮らせると予測でき。
「半分たぁ、大きく出たねふたみ殿、こちらも馬鹿じゃない、今後の闘鶏については承知しよう、闘鶏は派手で私ら博徒の好みだが、いかんせん準備に時間と銭を失いすぎる、神事でやるならもっとこじんまりでもいいし、お上への聞こえも良い、だからこの板野のい目が届く範囲では闘鶏を賭け事にしないことは約束しよう、だがね、勝利で得られる物の半分はいきすぎだ、半分の半分位がいところだろう」
半分の半分でも、正嗣と雷鳴丸とふたみには十分過ぎる額だ。そもそもふたみの目的は父親に闘鶏という賭け事を止めさせる事だから、もう目的は果たした様なものだ。
「いえ、だめです、半分は頂きます、この線は譲りません」
鋭い目、額に汗が浮かんでいるし、唇も僅かに震えている。だけどふたみは生来の鋭い目に意思の力を乗せて言い放った。
「そりゃなんでだい」
「わたしたちと親分さんは対等です、対等じゃなければこの交渉は成立しません、例えば親分さんが多く得るものが多い立場になれば、私たちはきっと将来、またとりさんにお願いしなければならない形に追い詰められます、それは望んでいないんです」
「対等かい、ここで俺らが一気にふたみ殿を人質にして、お武家さんにいう事を聞かせ、雷鳴丸を戦わせる事が可能だって考えないのかい」
口調は柔らかく、孫にでも語り聞かせる様に聞こえるが、板野親分が一声かければ、それはすぐに現実になる事だ。
いっぱしの武士のつもりの正嗣だが、誰かを守りながら複数の相手と斬りあうのには制限がある。
「そ、そうですね、もし板野親分がその気になれば、結果はそうなるかもしれません、渡会様はお優しいお方ですから、でも親分さんはそんなことをしません、その気なら先ほどのとりさんとの試しが終わった時に、そうしているはずで交渉の席には応じないはずです、人気のない場所に誘ったと言うこともできますが、私は渡会様と雷鳴丸と一緒で、だから、親分さんは明日の闘鶏に全力で挑ませる為にそんなことはしません」
「ふうむ」
「そ、それと、得られる物の半分の選択は親分さんに任せます」
それはつまり、半分と板野親分が決めた物で構わないという事だ。実質が半分かどうかではなく、あくまで板野親分と自分たちは対等な関係で闘鶏に参加したという名目が必要と言うことを伝えたのだ。
「ほぉ、ふたみ殿はその歳で俺の男を量るってのかい、これはおもしろいねぇ、長生きも長旅もするもんだ、熊野の山奥から出てきたがこんな娘さんに会えるとは思わなかった、わかった、交渉はそっちの言うとおりで構わないぜ、ただ勝利が絶対だ、それ以外の結果がまぁ約束できねぇな、すべての話は勝った時の事、負ければ何も、命も無い、それが博徒との賭けってもんだぜふたみ殿、覚えておいてくれよ」
「えっあっはい、そ、そうですね、ちょっと、でも、いえ、判りました」
色々な事を考えながらなのか、つっかえつっかえの答えだったが、板野親分が差し出した手をふたみが握った事で交渉は終わりとなった。
八幡神社からの帰り、もちろん伊増はついてこない。鷹司は闘鶏神事を勤める熊野権現の神官に聞きたいこ事があると、残った。
行きは四人だったが、帰りはふたみと二人っきりだ。だいぶさびしくなった。少し前まえ人間よりも動物のことばかりを気にかけていた正嗣だったが、数日で人の仲間が増えてきたもんだ。
ふたみと鷹司、この二人に、ついでに言えば伊増と出会わなければ、今頃自分は動物と共に路頭に迷っていたことだろう。藩には捨てられたが、今は明日が楽しみな正嗣であった。
二
「申し訳ありませんでした」
屋敷に戻ると、すぐにふたみが小さな頭を深々と下げて謝って来た。何か謝られることがあっただろうかと首をかしげる正嗣。
「何かあっただろうか?」
そして、その疑問をそのまま口に出してしまうという所が、正嗣と言う男の良さだ。
「も、申し訳ありません、渡会様と雷鳴丸には出来るだけ迷惑かけないように交渉しなければならないのに、命の危険まで・・・」
「なにを言うふたみ、おぬしは十分な交渉をしたではないか、あのような交渉、それがしには出来ぬ、ふたみだからこそ親分も応じたのであろう、どこに謝られることがある」
「で、でも、巻けたらすべての条件は無しだって・・・」
「確かに、それについては某も博徒と言う男たちを軽く考えていたかも知れぬ、それでも良いではないか、勝てば約束を守るという手形のような物よ、さっきも言ったが、ふたみは、あの、雷鳴丸が負ける姿が想像できるか?」
「いえ、まったく想像できません、とりさんは絶対に勝ちます」
「そういうことだ、安心せい」
頭を下げ続けているふたみの両肩の下に手を入れ、ぐっと持ち上げる。軽いふたみのからだが楽々と浮き上がり、正嗣と同じ高さで視線が交わる。
「ふたみと親分が対等なら、われ等も対等にならねばならぬな、二人であれば身分や年齢は無しに、某とふたみは対等になろう、それでよいか」
鋭い目が、それでも一杯に開かれ、そして閉じられる。
「はっ、はい、私でよろしければ、渡会様と対等に歩んでいければと・・・」
「これっ、対等な相手が渡会様などと呼ぶものか、某がふたみと呼ぶのだ、正嗣と呼べ良い」
「えっええ、それは少し言いにくいです、せめて正嗣様で許してください」
顔が紅潮し、必死に言うふたみに思わず、微笑が浮かんでしまう正嗣だった。
呼び方は、ふたみの好きにさせることにした。相手の嫌がることを強制する、そんなことは動物同士ではありえない。だから人間同士でも極力したくないと思うのも正嗣と言う男だった。
明日の雷鳴丸の出番は夕焼けが沈み始める頃だ。朝昼と闘鶏神事が行われ、普通の民に公開され、出店などもでるお祭りだ。
だが夜の帳と共に博徒たちが三々五々集まり、東西闘鶏対決が始まる。
雷鳴丸は西の横綱格なので、最後の対決になるが、他の親分にあまり雷鳴丸を見られたくないとの事で、早めに近くで待機する事を求められたのだ。それまでは出来るだけ雷鳴丸に負担をかけないようにと、他の親分に見られない為にも屋敷に篭る事となった。
「正嗣様、夕餉はどうしましょうか?」
「そうさな、と、いや待てふたみ、本日も家には帰らぬつもりか、あれ以上籐兵衛を心配させては後が大変になるのではないか」
昨日もふたみは泊まっている。二日連続で帰らないとなれば、藤兵衛の心労がいや増すであろう。十にもならない少女がやることではない。
「正嗣様、私たちは対等なんですよね、だからここは私にお任せください、私の父は私の父ですから」
落ち着いた声で応じるふたみ。とても九つの少女の言葉じゃなく大人びていたが、正嗣と対等の少女の言葉であれば受け入れる。
「そうか承知した、さて夕餉に出来るものがあったかな」
食材に関しては鷹司とふたみの手配で伊勢屋から伊増の手によって運ばれている。何があるかは見ていないが、なにかは調理できるだろう。時間はかかるが。
「正嗣様、ここは私に任せてください、実は考えているので」
「いや昨日もふたみに任せてしまった、また任せるのでは、それでは対等ではない、出来る事はなんでもするぞ」
「ふふっ、そんなに気負わなくても大丈夫ですよ正嗣様、実は親分さんから持っていけと色々持たされまして、さらに移すだけでお大名並みの夕餉になるんです、熊野の良いお酒もあります」
にこりとふたみ。何か答えようとしたが、その前に正嗣の腹が鳴った。
「あ、あらっ、並べるだけですから、すぐに用意しますね」
結局夕餉の支度はふたみがおこない、正嗣は使った皿や食後の白湯の準備をした。
二人だけの豪勢な食事を終えると、疲れが出たのかふたみはすぐに眠りについてしまった。正嗣は久しぶりに父が使っていた木刀を手に取ると素振りを始める。一振りに全力をこめる。
父の教えでは一振りの鋭さを、何回も何百回も維持する事が大事で技巧は必要ないとの事。最後の最後、死力を尽くした後でも全力で刀を振れなければ合戦では生き残れないと
の教えだ。
気配に気づいたのか、ミツキ達が周囲に座る。猫達はふたみと共に布団の中だ。
数十回も振ると、腕の筋肉が熱くなり、それに従い全身が刀を振る一つの生き物として自覚できる様になる。
この感覚が正嗣は嫌いではなかった。
何も考えずにただ木刀を振る。
真っ暗な闇も気にならず、吹き出る汗も気にしない。明日の事も、これからの事も気にしない。
ただただ、木刀を振るだけ。
そうして何刻がたっただろうか、不意に正嗣は、三日月が目の前に浮かんでいる事に気づいた。
そこから、自分の状態が判ってくる。
あまりにも無心で木刀を振っていたせいで、力尽きて倒れていたにも気づかなかったのだ。心配そうにミツキがすり寄ってくる。複数の犬たちが協力して水桶ごと持ってくる。良く出来た犬達だ。
水桶のぬるい水を飲む。この屋敷の良い所は共同の使用の井戸ではなく、独自に井戸がある事だ。水が欲しければ、隣近所を気にすることなく、いつでも好きな時に汲むことが出来るし、使い放題だ。風呂を自由に沸かす事が出来るのもそれが理由の一つである。
共同使用の井戸だと、水量を見ながら、隣近所の使用量まで考えながら使わないといけない。もし日照りの時に干上がってしまったら大変だ。川に水汲みに行くことも出来ない。
「ふぅ~」
適度な疲れが夜風に辺り、気持ち良い。
一時期は親の期待を背負って京の道場に通っていた。その時は毎日が新しい刺激と、体が起き上がれなくなるくらいの心地よい疲労に包まれ、悩む事は明日の道場で習う事ばかりで、まだ動物狂いの本領を発揮していなかった正嗣は、槍術は諦めていたが、刀術で身を立てることを夢見る少年剣士であった。
一年に満たない京での日々の中、父の京都大番役補佐の薬務が終り、同時に正嗣も久居に戻る事となった。気の合う友人もたくさん居た。別れは悲しく、辛い事であったが、お互いに一つの道を歩く同士。いつの日にかまたまみえる時もあらんと、お互いにさっぱりと別れたものだ。
その後で正嗣は動物に心魅かれ、同じ道を歩む同士ではなくなってしまったが。
そんな事をうつらうつらと考えつつ、ミツキ達に囲まれたまま、その場で眠りに落ちる正嗣であった。
三
自然と、ぱちりと目が覚めた。
寝起きの気怠さや、前日の疲れも残っていない万全の寝起きであった。しかし心のどこかで焦りを感じている。
初めての登城の際に寝過ごしてしまったかのような焦燥感が、粘ついた様に心のどこかに居る。
左右を見る。
自分の現在位置は屋敷の外、鶏小屋の近くで寝ている。脇には重い木刀。
雷鳴丸の姿は見えない。小屋から出ていないのだろうか。
しかし、十三匹もいる犬たちの一匹も見当たらない。ずっと近くに纏わりついて離れないというような甘え方をする犬達ではないが、いつも視界の隅に一匹くらいは居た。風景に溶け込むようにして、正嗣の邪魔にならず、静かに居た物だが、それが今日は居ない。
天を見上げれば、予想外にも陽は昼前を指している。
日没の時間には八幡神社に入らなければならないが、今から準備すれば焦る事は無い。
なんだろうか。
動物たちが見えない異常に、焦りはどんどん深くなる。
もしや夢ではないかと思い、頬をぴしゃりと叩くが、ちゃんと相応の痛みが走る。夢ではない。ならば動物たちは何処に行ったのだろうか。
木刀を握りしめて、屋敷に向かって動くものの気配が無いか探りながら歩く。
屋敷内にはふたみと猫が居た筈だ。この時間まで正嗣が外で寝ていたら、探しに来て起こしてくれているだろうが、それが無かった。つまりそれが出来ない状況にあるという事なのかもしれない。ぐっと木刀を握る手に力を籠める。
屋敷の入口は避け、縁側から中を覗き込む。
誰も居ない。
ふたみと猫が寝ていたであろう部屋の中には布団がそのままで、人の気配が無い。
昨日の板野親分の言葉が思い起こされる。ふたみを人質に取って言う事を聞かせるとの言葉だ。その後のふたみの交渉で、板野親分がそんな事をする訳はないと思ったのだが、相手は博徒。自分とは違う世界の常識で動いているのかもしれない。
裏をかかれたか…。
音を立てない様にゆっくりと部屋に入り、布団に手を当てる。返ってきた冷たい感触に、ふたみが布団から出てしばらくたっているのが判る。
それでも姿を見せない。これはもう確定だな。
正嗣は八幡神社まで走り出し、板野親分を逆に人質にとり、動物たちとふたみを助けようと考えるが、どこかでそれは短慮だと責める自分も居た。
たった一人で向っても相手の人数は判らないのだ。返り討ちに合えば、助けられる者はいなくなる。闘鶏が終った後ならば、普通に解放されるのではないか、とも考えたが確証は無い。こちらとは違う常識で動いているのだから、何が起こっても不思議ではない。
がたがたと言う音が奥から響いた。
場所は雪隠の方角だ。
音にだけは注意して、雪隠の扉を開ける。
中から出てきたのは、猿轡に両手両足を縛られ、血だらけになった伊増の姿だった。
すぐに近寄り、猿轡を外してやる正嗣。血がついてしまうが気にはしない。
「すまねぇ、ぐっ、あいつらがっ、お嬢ちゃんを・・・」
体中まんべんなく殴打されている様で、伊増は喋るのも辛そうだが、ふたみの行方を知っているとなれば聞き出さずにはいられない。両手両足の縄を解いてから襟元を掴み問いただす。
「痛いだろうが、これだけは話せ、ふたみと動物たちは何処に行った」
「すまねぇ、お嬢ちゃんは、忠助兄貴にやられた、兄貴は東とつるんでやがったんだ、おそらく今ごろは東の親分衆の所に一緒にいるだろう、だが雷鳴丸は先に俺が逃がしたから一緒じゃねぇ」
要約すると、伊増の兄貴分である忠助は、実は東の親分と繋がっており、今回の闘鶏で東が勝つように仕組んでいた。正之助を操り、正規の横綱鶏を襲わせたのも忠助の仕業であったとの事だ。東の親分はさらにこの久居の親分であり、伊勢屋との繋がりが深い地元の博徒らも結託しているという話だ。ふたみは伊勢屋の身代を貪り尽くす為の餌にもなるので、すぐに危害は加えられないだろうが、将来的に宿場町で飯炊き女にされる場合も考えられる。宿場町の飯炊き女とは、つまり給仕もする遊女の事だ。
「して、雷鳴丸は?」
「小屋から出したら、ちっさいのと一緒にあっという間に消えたぜ、勝てない勝負は挑まないすげえ鶏だ」
雷鳴丸は自らの縄張りを守るとき以外は基本温和な鶏だ。大事な物を守るために一時的に引いたということなのだろう。ならば探さねばならぬかと外に向かおうとするも、すぐに雷鳴丸は見つかった。
縁側に雷鳴丸、天丸、地丸の三羽で正嗣を待っていたのだ。しかも天丸と地丸に、先日自分が運ばれた籠を持ってこさせてもいる、
「すまぬ、遅くなった」
遅いと答える様に雷鳴丸が籠の中に入る。躊躇なくその籠を背負うと、這いずりながら出てきた伊増に対して
「すぐに動けば命にかかわるぞ、某が行くから、動けるようになったら板野親分に知らせて欲しい」
「ああ、ちょっとすぐは無理だが、知らせたら俺も行くからよ、忠助兄貴は殺さずにおいてくれよ、俺が殺すからさ」
「さあて、それはわからぬな、運があればそうする、ではな」
正嗣は袴を持ち上げ、全力疾走を始める。ここから八幡神社まで二里はある。歩くと一刻かかる距離だが、そんなに時間はかけていられぬと、正嗣は自分の足に四半刻で着くように走れと念じた。
田園風景を超えて久居の町に近づくと、闘鶏神事を中心にした祭りに浮かれる民が三々五々通りに繰り出して、普通に走れる状況じゃない。
その人ごみへ、速さを緩める事無く正嗣は突進する。気づいた大人は避けようとしてくれるが、手を引かれた子供や、犬や猫などの動物はそうはいかない。ぶつかりそうになった瞬間跳躍して飛び越したり、道場で鍛えた足裁きで避けつつ、走る速さを衰えさせない。
正嗣を見知っている者も中には居たが、普段の動物狂いしか知らぬので、正嗣本人であるかわからぬくらいの動きだ。気づく素振りは無い。
「おっ、お前は」
八幡神社が見えるころ、二匹の犬が併走している事に気づいた。渡会家の犬達の二匹だ。案内するように着いてくる。
「ふたみの場所が判るのか?」
いつもの犬達の行動から推測するに、そうだろう。信じて正嗣は二匹の犬にうなづくと着いていくことにした。
行き先は八幡神社の手前を右に曲がり、少し先にある粗末な民家だった。
その前に男たちが四人、見張りなのかぼんやりと立っているのが見える。多数と向き合う時の方法は二つ。一つ目は熟慮して隙を探し、相手の弱みを突く事。だが今は熟慮などしている時間はない。ふたみが傷つけられてでもいたら、伊勢屋藤兵衛に合わせる顔が無い。なので選択は二つ目。相手が体勢を整える前に、とにかくがむしゃらに突っ込むこと。しかし初撃で効果が無かった場合は、即座に引くべし。こちらの方法で行くしかない。
走っている勢いのまま跳躍し、走る速度と落ちる速度を合わせた左右双方の拳で一人ずつ殴り倒す。
何が起こったのか理解できないで居る残りの男達に足払いをしかけ、倒れる頭をこれも左右両手で掴み地面に叩きつける。
ここからは速さが勝負だ。
見張りを無力化した正嗣は、木刀を構えて中に入る。
広さは五間あるか無いか。土間に三人の男が背中を向けて酒を温めている。その奥の板の間に二人の男が居て、どちらも匕首を抜こうとしているのが見える。
届かぬ。
入り口から、奥の男達を殴り倒すのには距離が遠い。匕首を抜かれる前に倒したいが、それは無理だ。
とにかく届くところから倒すのを決めた正嗣は、背中を向けている三人のうち一人を蹴りつけ、勢いのままもう一人の肩に木刀を振り下ろす。
蹴られた男は、酒を温めていた火鉢に顔を突っ込み大火傷を負い
もう一人は、鎖骨を派手に折られて悶絶した。
のこりは三人、と構え直したところで援軍が到着。
一緒に走っていた犬が奥の匕首を構えていた男の手首にそれぞれ噛み付く。また近くにいた男も何処にいたのか、ミツキの爪で顔面を抉られ、元眼球があった場所から血を流していた。
「お前ら、死にたくなくばふたみをどうした!」
犬達が案内した以上、ふたみは近くに居るはず。この中には見えないが、必ず居る。
「こっこの野郎」
手首に噛み付いている犬を振りほどこうとした男に、ミツキの一撃が決まる。見た目は派手だが、そんなに深くない傷跡が首筋に走る。その血をみてもう一人の男が板戸を突き破って裏手に逃げ出そうとする。だが、その前に飛び掛った犬に取り押さえられる。
「そこかっ」
板戸のはずれた向こうにまた三人の男。二人は博徒の身形だが、残る一人は顔の半分を包帯で包んだ武士のいでたちだ。
こちらの騒動に気づき、刀を抜いている。
「やいやい、こっちを見やがれ」
包帯武士達とは離れた場所、松の根元に二人の男女が縛られ、その横で新たな男が長脇差を振りかぶっている。
「ふたみ、それと藤兵衛!」
二人ともぐったりとしていたが、呼びかけるとかすかに反応しているので、死んではいないようだ。
「それ以上暴れると二人の命はねぇぞ、お武家さん」
聞き覚えのある声だ。長脇差を構えているのが忠助だろう。最初会った時の様な迫力は微塵も感じさせない怯えた顔だ。
「やめておけ、二人を殺したらそれがしはもっと止まらぬぞ」
「うるせぃ、お前の相手は後ろのお武家さんがご所望だ、いいから黙って殺されろぃ」
まずい、忠助の長脇差がふたみと藤兵衛を狙っている。このまま動かずにいれば背後の武士に斬られる。動けばふたみと藤兵衛が死ぬことになり、動かなければ自分が斬られて死ぬ。
「くそう」
動けない。背後に斬撃の気配。冷たい刃の一寸が身を斬る感覚。じとりと血が背中を伝う。
なんだ、嬲って斬り殺すつもりか?
それでも正嗣は動けない。膾斬りにされるのを待つしかないのか。
ふたみの鋭い瞳が正嗣を見て、頷くように動かされる。
「なっ、待て、待つのだ、ふたみ」
正嗣の目の前で、ふたみが構えられている長脇差に向かって動き、首筋が刃に触れる。
その瞬間に忠助が長脇差を引いた。
「死んじまったら人質の意味がねぇだろうが、忠助のいらついた蹴りがふたみに向かうが、そこで藤兵衛が体を張って止める。ふくよかな体に蹴りがめり込む。
「じゃまだ、てめぇ」
再度足を振って、今度こそふたみを蹴り付けようとする忠助。だがそれは空から降って来た二匹の猫に阻止された。
回転しながら落ちてきた猫は、鋭い爪で忠助の目を正確に傷つけた。先ほどのミツキの爪撃とは違い、眼球破裂にはいたってないが、相手をひるませるには十分だ。
「はっ」
皮一枚斬られてはいるが、そんなのは関係ない。正嗣は一足飛びに忠助に近づくと、全力で横に薙いだ木刀で弾き飛ばした。手に残る感覚で骨の数本も折れた感触がある、起き上がることは無いだろう。そういえば、籠は?雷鳴丸はどうしたのだろう。
振り返った正嗣が見た物は真っ二つに割れた籠と、鶏のくせに大きく空中を舞う雷鳴丸の姿だった。
武士はうまく雷鳴丸の攻撃を避けたようだが、取り巻きとして一緒にいた二人の博徒はまともに食らい戦意喪失の状態だ。
「観念しろっ」
正面に正嗣、背後に雷鳴丸と囲まれた武士はそれでも刀を捨てない。
「おまえのせいだ、おまえのせいで我が家は屈辱に塗れた、お前さえいなければっ」
正之助の声だった。
雷鳴丸に手酷くやられた事が正之助の誇りを打ち砕いたのだろう。以前なら博徒と組んで、などとは考えない男だ。
「逆恨みも良いところだが、勝負するとしよう」
木刀を構える正嗣。対する正之助は起死回生の突きの構えを取る。
場に静けさが浸透し、意識のある誰もが息を飲む。
目を閉じる正嗣。
刹那、風を前方から感じて木刀を全力で振り下ろす。
正之助の切っ先が正嗣の顔に届く手前で、その刀自体を正嗣の木刀が叩き折り、その勢いのまま正之助の両手の骨まで折っていた。
「ぐあぁ」
痛みに膝をつく正之助。だが転がりまわることはせずに、その場で痛みに耐え動かない。
「勝負あったぞ正之助、これで終わりだ」
松の根元で、座り込んでいるふたみに手を貸して立たせる。
「まっ正嗣様、すみません、すみません、足手まといばかりで、本当に私は・・・」
「良いさ、ふたみはそれがしが守ると言った、皆も助けてくれたのだ、それで良い」
「あ、ありがとうみんな」
お礼を言われた猫二匹が、得意げににゃおんと鳴いた。
四
その後のこと。
東西闘鶏対決の結果は、当然の様に雷鳴丸が大勝した。
暴れ足りなかったのか、雷鳴丸は悔しさから次々と挑まれた東の鶏達を、鎧袖一触に破り去った。
また裏に回って忠助や正之助を操っていた東の親分はいつの間にか証拠を揃えた鷹司の告発により、東西闘鶏対決が終わる前に、東の親分衆がひっ捕らえ、きっちりとした処分をする事に決まったそうだ。
東西対決に水を差した詫びに、東の親分衆は熊野の板野親分に賭けられていた以上の支払う。具体的には係争地であった尾張の利権の全てと、四千両の小判を渡してきた。
当初は受け取れぬと突っぱねた板野親分だったが、東海道筋の治安と、京周辺での協力体制の樹立を条件に受け入れた。
近く太樹公、つまり江戸の将軍様が上洛し、それに伴い京周辺が騒がしくなる時の為だ。
上洛ともなれば数万の東側の人間が京に来ることになる。その際の治安維持は、西の親分衆だけでは手がたりないらしい。それらの話をふたみから聞いた正嗣は、そういうものかと思っただけだが。
伊勢屋藤兵衛は闘鶏で作った借金の全てを雷鳴丸に賭けたおかげで返済が叶い、再度ふたみとその義母との間に誓約書をかわしたらしい。
ふたみは板野親分から得た小判を使って、伊勢屋から分家し、ふたみ庵と言う小商家を立ち上げた。これには鷹司が一役買っており、ふたみ庵は藤原北家公認という看板の元に始まる事になる。藩も口出しできぬ立派な看板だ。
最後に某、渡会正嗣はと言えば、お家取り潰し自体は無かった事には出来ずに、久居藩士としての渡会家は無くなった。だが、役宅を鷹司が久居での定宿として指定したおかげで、そこで働く役夫として今のまま動物たちと暮らせる事になった。
宿の運営一切はふたみ庵が専属で行うので、特別に何かする必要はない。
「うまくいきすぎだな」
何もかもが落ち着き、猫は布団で丸くなり、犬達は一列縦隊で庭を走り、雷鳴丸は小屋を中心とした縄張りで落ち着いて散歩をしている。
激しい数日が過ぎて、また落ち着いた日々が渡会家に戻っていた。
たまに来る小さな少女や、気さくな公家、ふたみ庵で働くことになった元博徒の男だけが変化として残っただけで。
すっと桟敷に立つ雷鳴丸。日の光を浴びて翼が美しくひかり、頭にのる鶏冠は周囲一帯を睥睨する風格を持っている。
瞳は鋭く、しかしどこか優しさも持って、前にいる同属を睨み付けている。
雷鳴丸は勇者だ。
弱きを助け、強きもの達から守り、それを生きがいとし、今はしがない人と言う家来の為にその身を率先して戦いに投じている。安穏とした生を守り、自らに希望を託す人と言う家来の為に戦う。
雷鳴丸は勇者だった。
と、思っていそうだなぁ、絶対に人は餌を運ぶ家臣くらいにしか思っていないだろうな、と正嗣は雷鳴丸の勇姿を見つめていた。
ことすれば自分よりも頼りがいの有りそうな後姿だ。渡会の家長はもしかしたら雷鳴丸かもしれぬな。
「渡会様、大丈夫ですよね、とりさんは」
両の手を胸の前で握り締め、強く鋭い眼差しで雷鳴丸を見つめるふたみ。相手の奇岩丸は大きさで雷鳴丸の半分と少ししかない。貫禄で言えば完全に雷鳴丸の勝ちだ。
「大丈夫、雷鳴丸が負ける姿など想像がつかぬ」
あの鶏は名づけられる前から人に対しても、他の動物に対しても尊大で、それ以上に強かった。仲間を襲いに来た狸を返り討にした事もあれば、烏や鳶などが縄張りに入ってきたのを一撃で撃退した事もある。
闘鶏は初めてだが、戦いが初めてというわけではない。
「そっそうですね、わたしもです、あのとりさんは負けません」
「うん、どちらかと言えば心配は相手の方だ、怪我などさせぬと良いがな」
闘鶏で戦えば必ず傷が付く。酷い傷を受ければ、その鶏は明日には食膳に昇る事になってしまう。それを避けたいが為にふたみの商いに乗ったのだ。目的の為なら、少ない犠牲を許容できる男ならば、今こうなってはいない。
「始まるの」
鷹司が、珍しく真剣な目をしている。真剣勝負を見守るには真剣でないと
、という事か。
黒っぽい色を持つ奇岩丸が雷鳴丸を警戒しながら、ゆっくりと近づいていく、対して雷鳴丸はそんな奇岩丸の動きをくいっと見るだけで動かない。勇気があるならかかってこいとでも言いたげな自信に満ち溢れていて、とても闘鶏が初めての鶏には見えない。
素早く不規則な歩調で奇岩丸が雷鳴丸の周囲を飛び回る。隙を探っているのか不規則な動きなので、正嗣が戦っても読みが外れそうな秀逸な動きだ。忍び者ならこのような動きをするかもしれない。
ばさっと羽を広げ奇岩丸が大地を蹴り、爪を雷鳴丸に突き刺そうと上から襲い掛かろうとする。しかしそれは雷鳴丸の大きさを見誤る動きだった。奇岩丸の跳躍は童よりも大きな雷鳴丸の頭上を取ることは出来ず、羽の一振りで叩き落されてしまう。
素早く姿勢を戻した奇岩丸は再度、雷鳴丸の隙を狙うように周囲を跳ね回るが、正嗣の目から見ても、その動きは先ほどよりも鈍い。
それでも果敢に挑みかかる奇岩丸。
もう止めた方が良いのではないかと正嗣が思ったときに奇岩丸が動いた。今度は跳躍の前に地面の砂を雷鳴丸の顔に目掛けて飛ばしてから大地を蹴った。
その砂粒を目くらましに攻撃を仕掛ける奇岩丸。延ばした爪の先には、しかし雷鳴丸の姿はなかった。
その場でくるりと回転して砂粒を避けた雷鳴丸が、空中にいる奇岩丸の横に居た。
そして、場を圧する雷鳴が轟いた。
周囲で見ていた博徒たちから、驚きのうめき声が上がる。
「勝負ありじゃの」
雷鳴にどよめいて動かない博徒たちを見て、観戦していた鷹司が前に出る。雷鳴丸の足元には泡を吹いて倒れている奇岩丸がぐったりしている。切り傷等の外傷はないだろうが、鶏の耳の構造は判らないが正之助の様になっていては困る。
鷹司に続いて正嗣も前に出て、闘鶏場の奇岩丸の様子を伺う。
「血は出ていないな、それ以外に外傷はなし、体も温かいから死んではいないだろうが、むっ」
正嗣が奇岩丸の口元に手を添えると、呼吸の気配がない。
瞬間、正嗣の脳裏には剣道場で呼吸できなくなった少年を助けた師範の姿が浮かんだ。
あの時は、胸に強烈な一撃を入れられた少年に即座に近づいた師範が落ち着いて顔を持ち上げていた。
「こうか・・・」
即座に奇岩丸の顔を上げて、気道を確保。それでも呼吸は回復しない。たしか呼吸が長く回復しないと、命は助かっても考える力みたいなのが失われるらしい。
呼吸が回復しないのを見た正嗣はそこで、奇岩丸のくちばしをしっかり固定すると、水からの口で空気を送り込んだ。
背後からふたみの悲鳴の様な声や、博徒たちのどよめきが聞こえるが、今はそれどころじゃない。こっちは命がかかっているんだ。
生臭いくちばしの匂いに閉口しそうになるが、ぐっと耐えて、さらに空気を送り込む。同時に胸の周りを押して空気を吐き出すように促す。
最初はどよめいていた博徒たちも、その正嗣の姿を見て次第に静かになっていく。
「だめかっ」
十回ほど空気を送り込み、押し出させて、それでも奇岩丸の呼吸は戻らない。このままでは助からない。
絶望しかけた時、ふたみと、彼女を守るように雷鳴丸が正嗣のそばに来た。
無言で息を送り込みながら、視線が雷鳴丸と繋がる。ちょっと離れろと言っているような気がした。
その時の自分の感覚はうまく説明できないが、とにかく正嗣は奇岩丸を雷鳴丸の足も元に置いて二歩離れた。
雷鳴丸が大きく胸を膨らませ、体中に空気を溜め込む。いつもの雷鳴の様な泣き声を発する時よりも大きな動きだ。
もう空気はこれ以上はいらないだろうと思った刹那、特大の雷鳴が響き渡る。近くにいたふたみの服がまくれ上がる位の圧力だ。
「どうだっ」
何を期待していたのだろう。まさか鶏が鶏を救うと自分は思ったのであろうか。いささかの自嘲と僅かな希望をもって奇岩丸を見る。動いていない。手をくちばしに添える。生温かい風。
生きている。呼吸をしている。
先ほどまでの機敏な動きは出来ていないが、それでも奇岩丸はゆっくり起き上がる。首を左右に振り、人間ならまるで寝起きで前後不覚の状態の様に見えた。
「もう、大丈夫であろう」
もうすこし時間がたたないと何かの障害が出るか分からないが、とにかく命は助かった。雷鳴丸が命を奪うところを見たくなかった正嗣である。
「お前さんの勝ちだ、うちの奇岩丸はこれでも前西大関だったんだぜ、今回横綱が出れなかったら奇岩丸が東の横綱と戦うしかないと考えていた、しかしこのざまじゃ、それもできねぇ、いいさ、お武家さんの雷鳴丸には西の横綱として出てもらおう、いや、是非にも出て頂きたい、こんな雄姿見せられたら、日本一の鶏と言っても過言じゃない」
親分は下手褒めだった。先ほどまでの威圧的な迫力は也を潜め、純粋に雷鳴丸に対して尊敬の様な物を滲ませている。
それだけこの親分は闘鶏に対して真摯なのだろう。
「そちらの鶏が無事で良かった、すぐに全快とはいかないだろうが、それでも良かった」
「渡会様・・・・・・」
いつの間にかふたみが、土で汚れていた手を布で拭いてくれていた。よく見れば膝も土で黒くなっている。
無我夢中で飛び出して、闘鶏場の真ん中で救命作業をした代償だったが
正嗣はむしろ誇らしい気分だった。
動物狂いで、動物を守ると公言している正嗣だったが、自らの手でひとつの命を救ったの初めてだったのだ。
「ああすまぬな、ふたみ、汚れてしまうぞ」
両手を拭き、さらに膝まで拭こうとするふたみ。彼女の鋭い両の目には涙が浮かんでいた。手ぬぐいよりやや厚めの布が、どんどん黒くなっていく。
「いいんです、私、なんか、すごい、何かしなきゃいけないような気持ちで一杯で、本当はとりさんにも一杯感謝しなきゃいけないんですけど、なんか避けられそうで」
雷鳴丸ならそうだろう。
正嗣以外の人間が触れば、怪我の一つも覚悟しなければならない。
ふたみが名付け親だと気づけば、そのような事もないかもしれないが、いかんせん鶏にそれを期待しても仕方がない。
「勝って良かった、誰も何も死ななくて良かった、だけど、ここはまだ序の口だ、これから明日の勝負に向けて、ふたみにはやる事があるじゃないか」
そう明日の東の横綱との対戦は本題ではない、本題は勝つ事と、勝った時の条件を交渉することだ。
正嗣にはそれは出来ない。
ふたみがいて、しっかりと交渉出来てこそ助け舟が出せるのだ。
「わかっています、とりさんも渡会様もがんばって頂きました、ここからは商い人として私がしっかりと交渉しなければなりません、ありがとうございます」
「よしっ頑張れ、某もついているし、たぶん鷹司も協力くらいはするだろう、思う存分ぶつかっていけ「
ふたみのおかげで綺麗になった手。その手で彼女の頭を撫でる
瞬間嬉しそうに頬に笑みを浮かべたふたみは、すぐに鋭い目を取り戻して親分へと向き直る。
「私は伊勢の国、久居藩御用の伊勢屋藤兵衛が次女のふたみです、謹んで親分さんにお願いの儀があります、どうかお聞き届けくださいますよ、お願い申し上げます」
声に震えや怯えなど一切見せない、しっかりとした挨拶だった。最初に親分の前に出た時は正嗣の裾を掴み、おどおどしながらだったのが嘘のようだ。
「これはご丁寧に、ならばこちらもしっかりと挨拶させてもらいましょう、生国と申せば河内の山奥、かつては大楠公が開いた赤坂に産湯をつかり、長じて熊野三山の端でしがない一家を預からせて貰っております、性は板野、名は文吉、ただただ賭け事に生を賭ける博徒でございます」
幼少の、齢九つのふたみに対して、おそらく理解できるようにと言葉をだいぶ崩して挨拶する板野親分。
ではっと言って、ふたみを案内する。籠に入った雷鳴丸を背負い、正嗣とふたみは三内去れるまま、板野親分についていく。
鷹司はと言えば、なにやら博徒に混じって楽しそうに話しているし、伊増の姿は見えない。どちらも交渉はふたみに任せている、と言うことなのだろう。
闘鶏場から少し進むと、先ほどの簡易的な小屋とは違い、しっかりとした社殿が見えてきた。八幡様の社殿ではないので、これは熊野の社殿を輸送して組み立てた物だろう。五十人が入っても問題なさそうな広さだ。
朱にぬられた柱を横目に一歩足を中に踏み入れれば、白地に極彩色で描かれたさま尼名紙の姿が描かれている。
知識の乏しい正嗣だったが、天照大御神や須佐の神、八股烏の存在し分かった。
これを、今回の神事の為に運ばせる事が出来る板野親分の力の大きさに震えそうになる。
だがな、ふたみが震えていないのに、某だけが震えるわけにはいかぬ。
と、気合を入れる正嗣である。
対してふたみも、壁や天井に描かれている神代の世界を見つめてはいるが、正嗣のように圧倒されたりはしていない。
父から受けた商いの知識から、唐物の極彩色には慣れているし、神代の話も文として読んだ事もある。
「よっと、ここで話をするがいいかね」
なにやら大きな床机の様な物。それをはさむ様に平板に足が四つついている物の前で板野親分は此方を誘った。
「ええ、もちろん構いません」
木を組んだ床几の様な物をどのように扱えばいいのか正嗣は分からなかったが、ふたみは親分の誘いに乗って、木組の床几を引くと、身軽に座った。
背の高い床几なので、ふたみの両足は地から離れてぷらぷらとしている。
なにやら落ち着かない座具であるな。
ふたみの真似をして座る正嗣。床几よりだいぶ背が高く、尻の下には動物の皮をなめした物が使われているが、とにかく硬い。
床几は座る部分が布で、その張りを自ら調節できるので、柔らかさは好みで変えられる。
「腰や足が悪くなると、この様な唐物の床几が楽で良くてな、簡易ながら運ばせている、お武家さんには珍しくもあろうが、まあくつろいでいただけませんか」
「某は今は付き添いだ、気にせんでくれ」
「承知しております、さて、ではふたみ殿、話を承ろうか」
「は、はい、焦点を絞らせてもらいます、とりさんが西の横綱として闘鶏に参加するにあたり、まず参加条件は勝ち負けに関わらず、雷鳴丸、渡会様、私には一切手出し無用に願います、負けた場合の条件も同じで、それだけです」
板野親分は、目を閉じ、腕を組んで黙って聞いている。ふたみの言葉にかすかにうなづくだけだ。鷹司の名前が出てこないのは、あの公家様ならなんでも飄々となんとかしてしてしまうからだろう。
「それで、勝った場合はどうするね」
「は、はい、とりさんが勝った場合は、今後久居での神事ではない闘鶏の中止と、今回の横綱戦で得る物の半分を頂戴します、またこの一戦以降とりさんは闘鶏には絶対に参加しません、以上です」
東西の大親分達が一同に会する闘鶏大会だ。鷹司に聞いたが近畿でこれほどの規模で闘鶏が行われるのは稀で、実際に目にした者はいず、書に書かれているばかだという。
もちろん掛かりも莫大だろうが、賭かっている額も莫大だろう。
それの目玉対戦である。半分とはいえ、正嗣が五人位いても一生遊んで暮らせると予測でき。
「半分たぁ、大きく出たねふたみ殿、こちらも馬鹿じゃない、今後の闘鶏については承知しよう、闘鶏は派手で私ら博徒の好みだが、いかんせん準備に時間と銭を失いすぎる、神事でやるならもっとこじんまりでもいいし、お上への聞こえも良い、だからこの板野のい目が届く範囲では闘鶏を賭け事にしないことは約束しよう、だがね、勝利で得られる物の半分はいきすぎだ、半分の半分位がいところだろう」
半分の半分でも、正嗣と雷鳴丸とふたみには十分過ぎる額だ。そもそもふたみの目的は父親に闘鶏という賭け事を止めさせる事だから、もう目的は果たした様なものだ。
「いえ、だめです、半分は頂きます、この線は譲りません」
鋭い目、額に汗が浮かんでいるし、唇も僅かに震えている。だけどふたみは生来の鋭い目に意思の力を乗せて言い放った。
「そりゃなんでだい」
「わたしたちと親分さんは対等です、対等じゃなければこの交渉は成立しません、例えば親分さんが多く得るものが多い立場になれば、私たちはきっと将来、またとりさんにお願いしなければならない形に追い詰められます、それは望んでいないんです」
「対等かい、ここで俺らが一気にふたみ殿を人質にして、お武家さんにいう事を聞かせ、雷鳴丸を戦わせる事が可能だって考えないのかい」
口調は柔らかく、孫にでも語り聞かせる様に聞こえるが、板野親分が一声かければ、それはすぐに現実になる事だ。
いっぱしの武士のつもりの正嗣だが、誰かを守りながら複数の相手と斬りあうのには制限がある。
「そ、そうですね、もし板野親分がその気になれば、結果はそうなるかもしれません、渡会様はお優しいお方ですから、でも親分さんはそんなことをしません、その気なら先ほどのとりさんとの試しが終わった時に、そうしているはずで交渉の席には応じないはずです、人気のない場所に誘ったと言うこともできますが、私は渡会様と雷鳴丸と一緒で、だから、親分さんは明日の闘鶏に全力で挑ませる為にそんなことはしません」
「ふうむ」
「そ、それと、得られる物の半分の選択は親分さんに任せます」
それはつまり、半分と板野親分が決めた物で構わないという事だ。実質が半分かどうかではなく、あくまで板野親分と自分たちは対等な関係で闘鶏に参加したという名目が必要と言うことを伝えたのだ。
「ほぉ、ふたみ殿はその歳で俺の男を量るってのかい、これはおもしろいねぇ、長生きも長旅もするもんだ、熊野の山奥から出てきたがこんな娘さんに会えるとは思わなかった、わかった、交渉はそっちの言うとおりで構わないぜ、ただ勝利が絶対だ、それ以外の結果がまぁ約束できねぇな、すべての話は勝った時の事、負ければ何も、命も無い、それが博徒との賭けってもんだぜふたみ殿、覚えておいてくれよ」
「えっあっはい、そ、そうですね、ちょっと、でも、いえ、判りました」
色々な事を考えながらなのか、つっかえつっかえの答えだったが、板野親分が差し出した手をふたみが握った事で交渉は終わりとなった。
八幡神社からの帰り、もちろん伊増はついてこない。鷹司は闘鶏神事を勤める熊野権現の神官に聞きたいこ事があると、残った。
行きは四人だったが、帰りはふたみと二人っきりだ。だいぶさびしくなった。少し前まえ人間よりも動物のことばかりを気にかけていた正嗣だったが、数日で人の仲間が増えてきたもんだ。
ふたみと鷹司、この二人に、ついでに言えば伊増と出会わなければ、今頃自分は動物と共に路頭に迷っていたことだろう。藩には捨てられたが、今は明日が楽しみな正嗣であった。
二
「申し訳ありませんでした」
屋敷に戻ると、すぐにふたみが小さな頭を深々と下げて謝って来た。何か謝られることがあっただろうかと首をかしげる正嗣。
「何かあっただろうか?」
そして、その疑問をそのまま口に出してしまうという所が、正嗣と言う男の良さだ。
「も、申し訳ありません、渡会様と雷鳴丸には出来るだけ迷惑かけないように交渉しなければならないのに、命の危険まで・・・」
「なにを言うふたみ、おぬしは十分な交渉をしたではないか、あのような交渉、それがしには出来ぬ、ふたみだからこそ親分も応じたのであろう、どこに謝られることがある」
「で、でも、巻けたらすべての条件は無しだって・・・」
「確かに、それについては某も博徒と言う男たちを軽く考えていたかも知れぬ、それでも良いではないか、勝てば約束を守るという手形のような物よ、さっきも言ったが、ふたみは、あの、雷鳴丸が負ける姿が想像できるか?」
「いえ、まったく想像できません、とりさんは絶対に勝ちます」
「そういうことだ、安心せい」
頭を下げ続けているふたみの両肩の下に手を入れ、ぐっと持ち上げる。軽いふたみのからだが楽々と浮き上がり、正嗣と同じ高さで視線が交わる。
「ふたみと親分が対等なら、われ等も対等にならねばならぬな、二人であれば身分や年齢は無しに、某とふたみは対等になろう、それでよいか」
鋭い目が、それでも一杯に開かれ、そして閉じられる。
「はっ、はい、私でよろしければ、渡会様と対等に歩んでいければと・・・」
「これっ、対等な相手が渡会様などと呼ぶものか、某がふたみと呼ぶのだ、正嗣と呼べ良い」
「えっええ、それは少し言いにくいです、せめて正嗣様で許してください」
顔が紅潮し、必死に言うふたみに思わず、微笑が浮かんでしまう正嗣だった。
呼び方は、ふたみの好きにさせることにした。相手の嫌がることを強制する、そんなことは動物同士ではありえない。だから人間同士でも極力したくないと思うのも正嗣と言う男だった。
明日の雷鳴丸の出番は夕焼けが沈み始める頃だ。朝昼と闘鶏神事が行われ、普通の民に公開され、出店などもでるお祭りだ。
だが夜の帳と共に博徒たちが三々五々集まり、東西闘鶏対決が始まる。
雷鳴丸は西の横綱格なので、最後の対決になるが、他の親分にあまり雷鳴丸を見られたくないとの事で、早めに近くで待機する事を求められたのだ。それまでは出来るだけ雷鳴丸に負担をかけないようにと、他の親分に見られない為にも屋敷に篭る事となった。
「正嗣様、夕餉はどうしましょうか?」
「そうさな、と、いや待てふたみ、本日も家には帰らぬつもりか、あれ以上籐兵衛を心配させては後が大変になるのではないか」
昨日もふたみは泊まっている。二日連続で帰らないとなれば、藤兵衛の心労がいや増すであろう。十にもならない少女がやることではない。
「正嗣様、私たちは対等なんですよね、だからここは私にお任せください、私の父は私の父ですから」
落ち着いた声で応じるふたみ。とても九つの少女の言葉じゃなく大人びていたが、正嗣と対等の少女の言葉であれば受け入れる。
「そうか承知した、さて夕餉に出来るものがあったかな」
食材に関しては鷹司とふたみの手配で伊勢屋から伊増の手によって運ばれている。何があるかは見ていないが、なにかは調理できるだろう。時間はかかるが。
「正嗣様、ここは私に任せてください、実は考えているので」
「いや昨日もふたみに任せてしまった、また任せるのでは、それでは対等ではない、出来る事はなんでもするぞ」
「ふふっ、そんなに気負わなくても大丈夫ですよ正嗣様、実は親分さんから持っていけと色々持たされまして、さらに移すだけでお大名並みの夕餉になるんです、熊野の良いお酒もあります」
にこりとふたみ。何か答えようとしたが、その前に正嗣の腹が鳴った。
「あ、あらっ、並べるだけですから、すぐに用意しますね」
結局夕餉の支度はふたみがおこない、正嗣は使った皿や食後の白湯の準備をした。
二人だけの豪勢な食事を終えると、疲れが出たのかふたみはすぐに眠りについてしまった。正嗣は久しぶりに父が使っていた木刀を手に取ると素振りを始める。一振りに全力をこめる。
父の教えでは一振りの鋭さを、何回も何百回も維持する事が大事で技巧は必要ないとの事。最後の最後、死力を尽くした後でも全力で刀を振れなければ合戦では生き残れないと
の教えだ。
気配に気づいたのか、ミツキ達が周囲に座る。猫達はふたみと共に布団の中だ。
数十回も振ると、腕の筋肉が熱くなり、それに従い全身が刀を振る一つの生き物として自覚できる様になる。
この感覚が正嗣は嫌いではなかった。
何も考えずにただ木刀を振る。
真っ暗な闇も気にならず、吹き出る汗も気にしない。明日の事も、これからの事も気にしない。
ただただ、木刀を振るだけ。
そうして何刻がたっただろうか、不意に正嗣は、三日月が目の前に浮かんでいる事に気づいた。
そこから、自分の状態が判ってくる。
あまりにも無心で木刀を振っていたせいで、力尽きて倒れていたにも気づかなかったのだ。心配そうにミツキがすり寄ってくる。複数の犬たちが協力して水桶ごと持ってくる。良く出来た犬達だ。
水桶のぬるい水を飲む。この屋敷の良い所は共同の使用の井戸ではなく、独自に井戸がある事だ。水が欲しければ、隣近所を気にすることなく、いつでも好きな時に汲むことが出来るし、使い放題だ。風呂を自由に沸かす事が出来るのもそれが理由の一つである。
共同使用の井戸だと、水量を見ながら、隣近所の使用量まで考えながら使わないといけない。もし日照りの時に干上がってしまったら大変だ。川に水汲みに行くことも出来ない。
「ふぅ~」
適度な疲れが夜風に辺り、気持ち良い。
一時期は親の期待を背負って京の道場に通っていた。その時は毎日が新しい刺激と、体が起き上がれなくなるくらいの心地よい疲労に包まれ、悩む事は明日の道場で習う事ばかりで、まだ動物狂いの本領を発揮していなかった正嗣は、槍術は諦めていたが、刀術で身を立てることを夢見る少年剣士であった。
一年に満たない京での日々の中、父の京都大番役補佐の薬務が終り、同時に正嗣も久居に戻る事となった。気の合う友人もたくさん居た。別れは悲しく、辛い事であったが、お互いに一つの道を歩く同士。いつの日にかまたまみえる時もあらんと、お互いにさっぱりと別れたものだ。
その後で正嗣は動物に心魅かれ、同じ道を歩む同士ではなくなってしまったが。
そんな事をうつらうつらと考えつつ、ミツキ達に囲まれたまま、その場で眠りに落ちる正嗣であった。
三
自然と、ぱちりと目が覚めた。
寝起きの気怠さや、前日の疲れも残っていない万全の寝起きであった。しかし心のどこかで焦りを感じている。
初めての登城の際に寝過ごしてしまったかのような焦燥感が、粘ついた様に心のどこかに居る。
左右を見る。
自分の現在位置は屋敷の外、鶏小屋の近くで寝ている。脇には重い木刀。
雷鳴丸の姿は見えない。小屋から出ていないのだろうか。
しかし、十三匹もいる犬たちの一匹も見当たらない。ずっと近くに纏わりついて離れないというような甘え方をする犬達ではないが、いつも視界の隅に一匹くらいは居た。風景に溶け込むようにして、正嗣の邪魔にならず、静かに居た物だが、それが今日は居ない。
天を見上げれば、予想外にも陽は昼前を指している。
日没の時間には八幡神社に入らなければならないが、今から準備すれば焦る事は無い。
なんだろうか。
動物たちが見えない異常に、焦りはどんどん深くなる。
もしや夢ではないかと思い、頬をぴしゃりと叩くが、ちゃんと相応の痛みが走る。夢ではない。ならば動物たちは何処に行ったのだろうか。
木刀を握りしめて、屋敷に向かって動くものの気配が無いか探りながら歩く。
屋敷内にはふたみと猫が居た筈だ。この時間まで正嗣が外で寝ていたら、探しに来て起こしてくれているだろうが、それが無かった。つまりそれが出来ない状況にあるという事なのかもしれない。ぐっと木刀を握る手に力を籠める。
屋敷の入口は避け、縁側から中を覗き込む。
誰も居ない。
ふたみと猫が寝ていたであろう部屋の中には布団がそのままで、人の気配が無い。
昨日の板野親分の言葉が思い起こされる。ふたみを人質に取って言う事を聞かせるとの言葉だ。その後のふたみの交渉で、板野親分がそんな事をする訳はないと思ったのだが、相手は博徒。自分とは違う世界の常識で動いているのかもしれない。
裏をかかれたか…。
音を立てない様にゆっくりと部屋に入り、布団に手を当てる。返ってきた冷たい感触に、ふたみが布団から出てしばらくたっているのが判る。
それでも姿を見せない。これはもう確定だな。
正嗣は八幡神社まで走り出し、板野親分を逆に人質にとり、動物たちとふたみを助けようと考えるが、どこかでそれは短慮だと責める自分も居た。
たった一人で向っても相手の人数は判らないのだ。返り討ちに合えば、助けられる者はいなくなる。闘鶏が終った後ならば、普通に解放されるのではないか、とも考えたが確証は無い。こちらとは違う常識で動いているのだから、何が起こっても不思議ではない。
がたがたと言う音が奥から響いた。
場所は雪隠の方角だ。
音にだけは注意して、雪隠の扉を開ける。
中から出てきたのは、猿轡に両手両足を縛られ、血だらけになった伊増の姿だった。
すぐに近寄り、猿轡を外してやる正嗣。血がついてしまうが気にはしない。
「すまねぇ、ぐっ、あいつらがっ、お嬢ちゃんを・・・」
体中まんべんなく殴打されている様で、伊増は喋るのも辛そうだが、ふたみの行方を知っているとなれば聞き出さずにはいられない。両手両足の縄を解いてから襟元を掴み問いただす。
「痛いだろうが、これだけは話せ、ふたみと動物たちは何処に行った」
「すまねぇ、お嬢ちゃんは、忠助兄貴にやられた、兄貴は東とつるんでやがったんだ、おそらく今ごろは東の親分衆の所に一緒にいるだろう、だが雷鳴丸は先に俺が逃がしたから一緒じゃねぇ」
要約すると、伊増の兄貴分である忠助は、実は東の親分と繋がっており、今回の闘鶏で東が勝つように仕組んでいた。正之助を操り、正規の横綱鶏を襲わせたのも忠助の仕業であったとの事だ。東の親分はさらにこの久居の親分であり、伊勢屋との繋がりが深い地元の博徒らも結託しているという話だ。ふたみは伊勢屋の身代を貪り尽くす為の餌にもなるので、すぐに危害は加えられないだろうが、将来的に宿場町で飯炊き女にされる場合も考えられる。宿場町の飯炊き女とは、つまり給仕もする遊女の事だ。
「して、雷鳴丸は?」
「小屋から出したら、ちっさいのと一緒にあっという間に消えたぜ、勝てない勝負は挑まないすげえ鶏だ」
雷鳴丸は自らの縄張りを守るとき以外は基本温和な鶏だ。大事な物を守るために一時的に引いたということなのだろう。ならば探さねばならぬかと外に向かおうとするも、すぐに雷鳴丸は見つかった。
縁側に雷鳴丸、天丸、地丸の三羽で正嗣を待っていたのだ。しかも天丸と地丸に、先日自分が運ばれた籠を持ってこさせてもいる、
「すまぬ、遅くなった」
遅いと答える様に雷鳴丸が籠の中に入る。躊躇なくその籠を背負うと、這いずりながら出てきた伊増に対して
「すぐに動けば命にかかわるぞ、某が行くから、動けるようになったら板野親分に知らせて欲しい」
「ああ、ちょっとすぐは無理だが、知らせたら俺も行くからよ、忠助兄貴は殺さずにおいてくれよ、俺が殺すからさ」
「さあて、それはわからぬな、運があればそうする、ではな」
正嗣は袴を持ち上げ、全力疾走を始める。ここから八幡神社まで二里はある。歩くと一刻かかる距離だが、そんなに時間はかけていられぬと、正嗣は自分の足に四半刻で着くように走れと念じた。
田園風景を超えて久居の町に近づくと、闘鶏神事を中心にした祭りに浮かれる民が三々五々通りに繰り出して、普通に走れる状況じゃない。
その人ごみへ、速さを緩める事無く正嗣は突進する。気づいた大人は避けようとしてくれるが、手を引かれた子供や、犬や猫などの動物はそうはいかない。ぶつかりそうになった瞬間跳躍して飛び越したり、道場で鍛えた足裁きで避けつつ、走る速さを衰えさせない。
正嗣を見知っている者も中には居たが、普段の動物狂いしか知らぬので、正嗣本人であるかわからぬくらいの動きだ。気づく素振りは無い。
「おっ、お前は」
八幡神社が見えるころ、二匹の犬が併走している事に気づいた。渡会家の犬達の二匹だ。案内するように着いてくる。
「ふたみの場所が判るのか?」
いつもの犬達の行動から推測するに、そうだろう。信じて正嗣は二匹の犬にうなづくと着いていくことにした。
行き先は八幡神社の手前を右に曲がり、少し先にある粗末な民家だった。
その前に男たちが四人、見張りなのかぼんやりと立っているのが見える。多数と向き合う時の方法は二つ。一つ目は熟慮して隙を探し、相手の弱みを突く事。だが今は熟慮などしている時間はない。ふたみが傷つけられてでもいたら、伊勢屋藤兵衛に合わせる顔が無い。なので選択は二つ目。相手が体勢を整える前に、とにかくがむしゃらに突っ込むこと。しかし初撃で効果が無かった場合は、即座に引くべし。こちらの方法で行くしかない。
走っている勢いのまま跳躍し、走る速度と落ちる速度を合わせた左右双方の拳で一人ずつ殴り倒す。
何が起こったのか理解できないで居る残りの男達に足払いをしかけ、倒れる頭をこれも左右両手で掴み地面に叩きつける。
ここからは速さが勝負だ。
見張りを無力化した正嗣は、木刀を構えて中に入る。
広さは五間あるか無いか。土間に三人の男が背中を向けて酒を温めている。その奥の板の間に二人の男が居て、どちらも匕首を抜こうとしているのが見える。
届かぬ。
入り口から、奥の男達を殴り倒すのには距離が遠い。匕首を抜かれる前に倒したいが、それは無理だ。
とにかく届くところから倒すのを決めた正嗣は、背中を向けている三人のうち一人を蹴りつけ、勢いのままもう一人の肩に木刀を振り下ろす。
蹴られた男は、酒を温めていた火鉢に顔を突っ込み大火傷を負い
もう一人は、鎖骨を派手に折られて悶絶した。
のこりは三人、と構え直したところで援軍が到着。
一緒に走っていた犬が奥の匕首を構えていた男の手首にそれぞれ噛み付く。また近くにいた男も何処にいたのか、ミツキの爪で顔面を抉られ、元眼球があった場所から血を流していた。
「お前ら、死にたくなくばふたみをどうした!」
犬達が案内した以上、ふたみは近くに居るはず。この中には見えないが、必ず居る。
「こっこの野郎」
手首に噛み付いている犬を振りほどこうとした男に、ミツキの一撃が決まる。見た目は派手だが、そんなに深くない傷跡が首筋に走る。その血をみてもう一人の男が板戸を突き破って裏手に逃げ出そうとする。だが、その前に飛び掛った犬に取り押さえられる。
「そこかっ」
板戸のはずれた向こうにまた三人の男。二人は博徒の身形だが、残る一人は顔の半分を包帯で包んだ武士のいでたちだ。
こちらの騒動に気づき、刀を抜いている。
「やいやい、こっちを見やがれ」
包帯武士達とは離れた場所、松の根元に二人の男女が縛られ、その横で新たな男が長脇差を振りかぶっている。
「ふたみ、それと藤兵衛!」
二人ともぐったりとしていたが、呼びかけるとかすかに反応しているので、死んではいないようだ。
「それ以上暴れると二人の命はねぇぞ、お武家さん」
聞き覚えのある声だ。長脇差を構えているのが忠助だろう。最初会った時の様な迫力は微塵も感じさせない怯えた顔だ。
「やめておけ、二人を殺したらそれがしはもっと止まらぬぞ」
「うるせぃ、お前の相手は後ろのお武家さんがご所望だ、いいから黙って殺されろぃ」
まずい、忠助の長脇差がふたみと藤兵衛を狙っている。このまま動かずにいれば背後の武士に斬られる。動けばふたみと藤兵衛が死ぬことになり、動かなければ自分が斬られて死ぬ。
「くそう」
動けない。背後に斬撃の気配。冷たい刃の一寸が身を斬る感覚。じとりと血が背中を伝う。
なんだ、嬲って斬り殺すつもりか?
それでも正嗣は動けない。膾斬りにされるのを待つしかないのか。
ふたみの鋭い瞳が正嗣を見て、頷くように動かされる。
「なっ、待て、待つのだ、ふたみ」
正嗣の目の前で、ふたみが構えられている長脇差に向かって動き、首筋が刃に触れる。
その瞬間に忠助が長脇差を引いた。
「死んじまったら人質の意味がねぇだろうが、忠助のいらついた蹴りがふたみに向かうが、そこで藤兵衛が体を張って止める。ふくよかな体に蹴りがめり込む。
「じゃまだ、てめぇ」
再度足を振って、今度こそふたみを蹴り付けようとする忠助。だがそれは空から降って来た二匹の猫に阻止された。
回転しながら落ちてきた猫は、鋭い爪で忠助の目を正確に傷つけた。先ほどのミツキの爪撃とは違い、眼球破裂にはいたってないが、相手をひるませるには十分だ。
「はっ」
皮一枚斬られてはいるが、そんなのは関係ない。正嗣は一足飛びに忠助に近づくと、全力で横に薙いだ木刀で弾き飛ばした。手に残る感覚で骨の数本も折れた感触がある、起き上がることは無いだろう。そういえば、籠は?雷鳴丸はどうしたのだろう。
振り返った正嗣が見た物は真っ二つに割れた籠と、鶏のくせに大きく空中を舞う雷鳴丸の姿だった。
武士はうまく雷鳴丸の攻撃を避けたようだが、取り巻きとして一緒にいた二人の博徒はまともに食らい戦意喪失の状態だ。
「観念しろっ」
正面に正嗣、背後に雷鳴丸と囲まれた武士はそれでも刀を捨てない。
「おまえのせいだ、おまえのせいで我が家は屈辱に塗れた、お前さえいなければっ」
正之助の声だった。
雷鳴丸に手酷くやられた事が正之助の誇りを打ち砕いたのだろう。以前なら博徒と組んで、などとは考えない男だ。
「逆恨みも良いところだが、勝負するとしよう」
木刀を構える正嗣。対する正之助は起死回生の突きの構えを取る。
場に静けさが浸透し、意識のある誰もが息を飲む。
目を閉じる正嗣。
刹那、風を前方から感じて木刀を全力で振り下ろす。
正之助の切っ先が正嗣の顔に届く手前で、その刀自体を正嗣の木刀が叩き折り、その勢いのまま正之助の両手の骨まで折っていた。
「ぐあぁ」
痛みに膝をつく正之助。だが転がりまわることはせずに、その場で痛みに耐え動かない。
「勝負あったぞ正之助、これで終わりだ」
松の根元で、座り込んでいるふたみに手を貸して立たせる。
「まっ正嗣様、すみません、すみません、足手まといばかりで、本当に私は・・・」
「良いさ、ふたみはそれがしが守ると言った、皆も助けてくれたのだ、それで良い」
「あ、ありがとうみんな」
お礼を言われた猫二匹が、得意げににゃおんと鳴いた。
四
その後のこと。
東西闘鶏対決の結果は、当然の様に雷鳴丸が大勝した。
暴れ足りなかったのか、雷鳴丸は悔しさから次々と挑まれた東の鶏達を、鎧袖一触に破り去った。
また裏に回って忠助や正之助を操っていた東の親分はいつの間にか証拠を揃えた鷹司の告発により、東西闘鶏対決が終わる前に、東の親分衆がひっ捕らえ、きっちりとした処分をする事に決まったそうだ。
東西対決に水を差した詫びに、東の親分衆は熊野の板野親分に賭けられていた以上の支払う。具体的には係争地であった尾張の利権の全てと、四千両の小判を渡してきた。
当初は受け取れぬと突っぱねた板野親分だったが、東海道筋の治安と、京周辺での協力体制の樹立を条件に受け入れた。
近く太樹公、つまり江戸の将軍様が上洛し、それに伴い京周辺が騒がしくなる時の為だ。
上洛ともなれば数万の東側の人間が京に来ることになる。その際の治安維持は、西の親分衆だけでは手がたりないらしい。それらの話をふたみから聞いた正嗣は、そういうものかと思っただけだが。
伊勢屋藤兵衛は闘鶏で作った借金の全てを雷鳴丸に賭けたおかげで返済が叶い、再度ふたみとその義母との間に誓約書をかわしたらしい。
ふたみは板野親分から得た小判を使って、伊勢屋から分家し、ふたみ庵と言う小商家を立ち上げた。これには鷹司が一役買っており、ふたみ庵は藤原北家公認という看板の元に始まる事になる。藩も口出しできぬ立派な看板だ。
最後に某、渡会正嗣はと言えば、お家取り潰し自体は無かった事には出来ずに、久居藩士としての渡会家は無くなった。だが、役宅を鷹司が久居での定宿として指定したおかげで、そこで働く役夫として今のまま動物たちと暮らせる事になった。
宿の運営一切はふたみ庵が専属で行うので、特別に何かする必要はない。
「うまくいきすぎだな」
何もかもが落ち着き、猫は布団で丸くなり、犬達は一列縦隊で庭を走り、雷鳴丸は小屋を中心とした縄張りで落ち着いて散歩をしている。
激しい数日が過ぎて、また落ち着いた日々が渡会家に戻っていた。
たまに来る小さな少女や、気さくな公家、ふたみ庵で働くことになった元博徒の男だけが変化として残っただけで。
0
お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

晩夏の蝉
紫乃森統子
歴史・時代
当たり前の日々が崩れた、その日があった──。
まだほんの14歳の少年たちの日常を変えたのは、戊辰の戦火であった。
後に二本松少年隊と呼ばれた二本松藩の幼年兵、堀良輔と成田才次郎、木村丈太郎の三人の終着点。
※本作品は昭和16年発行の「二本松少年隊秘話」を主な参考にした史実ベースの創作作品です。

仏の顔
akira
歴史・時代
江戸時代
宿場町の廓で売れっ子芸者だったある女のお話
唄よし三味よし踊りよし、オマケに器量もよしと人気は当然だったが、ある旦那に身受けされ店を出る
幸せに暮らしていたが数年ももたず親ほど年の離れた亭主は他界、忽然と姿を消していたその女はある日ふらっと帰ってくる……

真田源三郎の休日
神光寺かをり
歴史・時代
信濃の小さな国衆(豪族)に過ぎない真田家は、甲斐の一大勢力・武田家の庇護のもと、どうにかこうにか生きていた。
……のだが、頼りの武田家が滅亡した!
家名存続のため、真田家当主・昌幸が選んだのは、なんと武田家を滅ぼした織田信長への従属!
ところがところが、速攻で本能寺の変が発生、織田信長は死亡してしまう。
こちらの選択によっては、真田家は――そして信州・甲州・上州の諸家は――あっという間に滅亡しかねない。
そして信之自身、最近出来たばかりの親友と槍を合わせることになる可能性が出てきた。
16歳の少年はこの連続ピンチを無事に乗り越えられるのか?
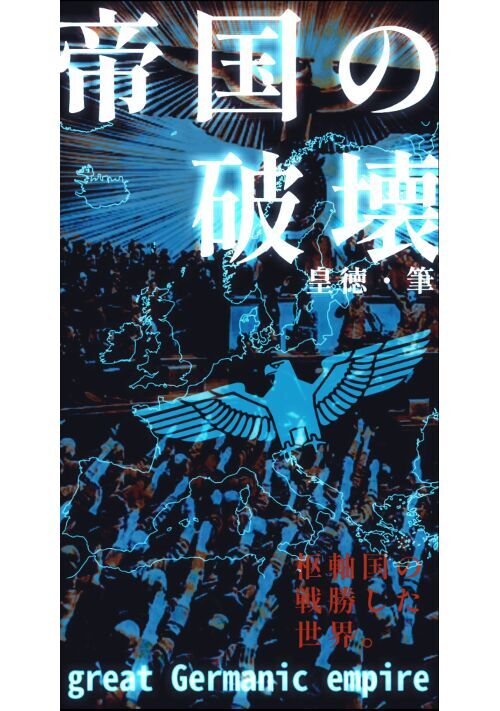
『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−
皇徳❀twitter
歴史・時代
この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。
二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

思い出乞ひわずらい
水城真以
歴史・時代
――これは、天下人の名を継ぐはずだった者の物語――
ある日、信長の嫡男、奇妙丸と知り合った勝蔵。奇妙丸の努力家な一面に惹かれる。
一方奇妙丸も、媚びへつらわない勝蔵に特別な感情を覚える。
同じく奇妙丸のもとを出入りする勝九朗や於泉と交流し、友情をはぐくんでいくが、ある日を境にその絆が破綻してしまって――。
織田信長の嫡男・信忠と仲間たちの幼少期のお話です。以前公開していた作品が長くなってしまったので、章ごとに区切って加筆修正しながら更新していきたいと思います。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め
七瀬京
歴史・時代
近藤勇の『首』が消えた……。
新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。
しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。
近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。
首はどこにあるのか。
そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。
※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

旧式戦艦はつせ
古井論理
歴史・時代
真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

江戸の夕映え
大麦 ふみ
歴史・時代
江戸時代にはたくさんの随筆が書かれました。
「のどやかな気分が漲っていて、読んでいると、己れもその時代に生きているような気持ちになる」(森 銑三)
そういったものを選んで、小説としてお届けしたく思います。
同じ江戸時代を生きていても、その暮らしぶり、境遇、ライフコース、そして考え方には、たいへんな幅、違いがあったことでしょう。
しかし、夕焼けがみなにひとしく差し込んでくるような、そんな目線であの時代の人々を描ければと存じます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















