91 / 217
執着旦那と愛の子作り&子育て編
え・・・叱られたい人?(困惑)④
しおりを挟む
血相を変えてレオンが屋敷にあらわれたのは、あれからさほど時間がかからなかった。
どうやら、レオンの屋敷で待ち合わせてくることになっていたのだが、それを破りシャーリーはこの屋敷に直行したことを知り慌てて出てきたようだ。
シャーリーはレオンのあまりにも早い到着に驚き顔をあげたが、自分の顔を見るなり無表情になるレオンに息を飲んで体をびくつかせた。
レオンはすぐに表情を柔らかくし、シャリオンに部屋の手配を頼むとシャーリーを連れて行った。
その後には領地からついてきたゾルの両親がつづいていく。
シャーリーを護送してきたのは、彼等のようだ。
シャリオンを心配し泣きじゃくっていたが、それ以外にも様子がおかしかったように見える。
そんな彼等の後ろ姿を見届けながらシャリオンは呟いた。
「大丈夫だろうか」
「シャーリー様が何をされても許す方なので、勝手にこちらに来訪したことを怒っているわけではありません。
しかし、大変お心が狭い方なので、自分がいないところでシャーリー様が涙し、それを見た人物が居ることを面白く思ってないのでしょう」
「・・・そういうことか」
あの2人がいつまでたっても仲が良いのは、シャリオンも良く知っている。
ガリウスの言葉に納得していると、シャリオンの手が握られて視線をあげると、ガリウスは真剣な眼差しをしている。
「それはあくまで、私もそうだからですが」
「・・・ガリウス?」
「・・・、はぁ」
様子が可笑しいガリウスに訝し気にしたのだが、小さくため息をつかれる。
「シャリオン。後で大切なお話があります」
「え?」
「貴方には認識を改めていただく必要があります」
「・・・?・・・どういうこと?」
「それは今夜お話しましょう。ずっと約束していた例の件もしようと思っていたことですし、丁度良いです」
そう言うガリウスには少し怒りを帯びている感じがした。
何故だ?と、自分の行動を反芻して思い当たることがった。
「ち、違うんだ。ガリィ」
「いい訳は今夜お伺いいたしますよ」
「っ」
ちらりと流し目で視線をやられて息を飲んだ。
その様子を見るにかなり怒りを感じているように見えた。
焦って弁明をしようとしたのだが、そこへレオンとゾルの父が戻ってきた。
一緒について行ったはずのゾルの母は、シャーリーについている様だ。
彼女はウルフ家の人間でありながら、シャーリーに対して敬愛を示している珍しい人物でもあり、シャーリーは特に彼女を信頼しているからだろう。
眉間に皺を寄せたレオンだったが、2人の様子が可笑しいことに訝し気にした。
その視線はあからさまにガリウスを批難している。
「待たせた。・・・?・・・何をした」
「いいえ。何も」
「ふん。その顔で言われても信ぴょう性がないわ。
・・・もしや、お前がシャーリーを責めた訳ではあるまいな」
ギロリと凍てつく目で睨むレオン。
「その様なことを仰りたいなら、お2人で帰られたらどうです?
今日はシャリオンに謝りに来たと聞きましたが」
「!」
ガリウスの言葉に弾かれたようにレオンは視線を逸らすと、シャリオンの元へと駆け寄ってくる。
そして愛おしそうに頬を撫で、そっと抱き寄せた。
「・・・もう起き上がって大丈夫なのか?」
「えぇ」
起きた時も体には痛いところはなかった。
細かい傷などはシャリオンが眠らされている間にとっくにガリウスが治させていた。
だから今はすっかり調子がいい状態である。
「・・・。すまぬ。私の力が及ばないばかりに」
「父上も、父様もご自分を責めないでください」
そう言うと、レオンはピクリと体を動かした後、引き寄せた体をほどいた。
そしてシャリオンを覗き込んだ。
「シャーリーが・・・そう言ったのか?」
「はい。・・・父様は何故ご自分を責めていらっしゃるのですか?」
こう言っては何だが、まだレオンにならわかる。
次期公爵である自分が他に恨みを買うのもわかる。
だが、なぜシャーリーが自分を責めたのかはわからなかった。
シャーリーの家は有力な伯爵家であることは聞いているが、それが関係があるのだろうか。
そんな風に勘繰ってしまう。
すると、レオンは小さくため息をつくと、ガリウスの据わっていない方のシャリオンの隣に腰かけた。
「・・・。シャーリーは・・・私と結婚する前多方面からそう言う目で見られていた」
「そう言う目?」
「フッ・・・お前は瓜二つだからな。
それに私が目を光らせていたから気づかないかもしれないが。
シャーリーはその美しさと天使のような慈悲を持った心に皆虜だった」
「・・・、」
真顔で何を言い出すかと思えば。
とんだのろけで、シャリオンは苦笑を浮かべた。
「嘘ではない。
誰も彼もシャーリーに惚れた。
どんなにお堅い人物も、気難しい貴族も、皆を引き寄せる。
義兄が居なければきっと攫われていた。
・・・いや、実際私に会う前は何度か攫われたことがあると聞いている」
「そう・・・なのですか」
「つかまった犯人は皆口をそろえてこういうのだ。
『シャーリーの美しさに惑わされた』と」
「・・・。まって下さい。父様はそれで私が攫われたのをご自分の所為だと思ってらっしゃるのですか?」
話の流れで言おうとしていることが分かって、そう尋ねればレオンは難しい表情をしてコクリと頷いた。
「父様の所為ではありません!」
「あぁそうだ」
「そして、父上やガリウスの所為でもありません」
「・・・シャリオン」
「どんな理由であれ、それは実行した犯人が悪いのです」
そう言うとレオンはくしゃりと顔を歪ませ、首を横に振る。
「しかし、私を恨めなど言われたことはあるだろう」
「それが何だというのですか」
確かにレオンの仕事の事や、シャーリーの美しさに下衆な感情を頂いている人間もいた。
だが、それで自分達の責めてほしくはない。
シャリオンはレオンから視線を逸らさなかった。
「・・・シャリオン」
「悪いのは何時だってそれをした犯人が悪いのです」
その意見をシャリオンは変える気は無い。
犯人以外に誰が悪いだとか、そんなことは意味がない話だ。
シャーリーにも後でそれを伝えなければならないと思いつつ、話を切り替える。
「この話は終わりです。私はその話をしたいわけではないのです。
・・・父上は私に隠していることがありますね」
「・・・、誰に何を聞いた」
それは肯定されたようなもので、シャリオンは眉を顰める。
「私はそんなに頼りないですか」
「・・・そういうことでは」
「ですが、ガリウスには話しているのでしょう?」
「それは・・・っ」
すると隣から呆れたようにガリウスがため息をつく。
それはほんの少しだけシャリオンの心をささくれさせた。
僕・・・そんなに可笑しなこと聞いている?
落ち着こうと思いたいのに、それが見失いそうだ。
高ぶりそうになったとき、ガリウスがシャリオンの手に手を重ねた。
「レオン様。シャリオンを悲しませたら許しませんよ」
「っ・・・貴様はどちらの味方なのだ」
「言ったでしょう?私はシャリオンの味方です。
・・・シャリオン。勘違いしないでください。
私も答えないので無理やりおど・・・ではなく、何度も尋ねて聞き出したのですよ」
さらりと不穏な言葉を言いながらニコリとほほ笑むガリウス。
公爵で上司でもあるレオンに本当に遠慮がないガリウス。
肝が据わっている。
思わずちらりとレオンを見ると不満げに声が漏れた。
「私を信じていただけないのですか?」
「っ・・・そういう、わけじゃ」
「ディディ殿にサーベル国の人間に『「狼と宝石を連れて来い」と言われた』と聞いたら、理由を知っているのはレオン様です。だったら本人に問いただしたほうが早いでしょう?」
ウルフ家の家紋は確かに狼をあしらっている。
それだけでウルフ家だと瞬時に思えたガリウスに感心する。
シャリオンはあの男、・・・ルシエルに『珍しい狼と宝石を探して冒険している』と言われた時、あの男を心の底から信用は出来なかったが、その言葉の意味にたどり着けなかった。
ゾルに武器を向け、そう言われて漸く気づいたくらいだ。
「そう、・・・だけど。
ルシエルの言っていた『1人捕まえれば全部捕まる』とは、どういう意味なの?」
「それは・・・。
・・・私が答えてしまって宜しいのですか?」
ガリウスはチラリとレオンを見る。
しかし、レオンは言いずらそうに言葉を飲んだ。
なんだか、その姿を見ると少し・・・胸に針で刺されるような痛みが走る。
そして、急に先ほど興奮した感情が引いていく。
悲しいけれど、・・・仕方がない。
シャリオンは苦笑を浮かべた後に、頭を下げた。
「・・・。父上。申し訳ありません。聞き分けの無いことを」
「!」
「父上が仰られないという事は不要だと言う事。差し出がましいことをしました」
「シャリオンっ違うのだっ」
「いいえ。・・・必要になったらガリウスが手を貸してくれるでしょう。だよね?」
そっとガリウスを見上げると、シャリオンの心情を見透かすようにジッとみられる。
きっとすべてを感じ取っているはずだ。
「・・・その聞き分けの良い所は心配になってしまいますね。
勿論。貴方が困っていてもいなくても全力で力になります。
・・・けれど、あなたは次期公爵なのですから、もっとわがままに知りたがって良いのです。
貴方には正しく導くことの出来る素質は持っています。
大丈夫。自信を持ってください」
「でも、」
「私はどちらでも良いです。
ですが、ずっと見てきた私から言わせていただきますと、
シャリオンはレオン様から聞き出すべきです」
「・・・、」
その言葉に視線を逸らしながら、そっとレオンを見ると、心配で苦慮した眼差しでシャリオンを見てきた。
「貴方が領地の主となり、ウルフ家も統べるのですから遠慮する必要はありません。
・・・ただ一つ。
レオン様の弁解をさせていただくと、・・・決してシャリオンが信用できないからではないです」
「・・・、」
「親が子を心配するのは当然です。
・・・危険な場所から我が子だけでも逃がした貴方になら、よくわかるのではないですか?」
「すまない、・・・シャリオン。
私は・・・頭では分かっているつもりなのだが。
・・・どうしてもお前の障害になりそうな面倒事を、退けてしまいたくなるのだ」
「・・・父上」
「それは・・・今ガリウスの言った通り、お前を領主として公爵として信頼していないわけじゃないのだ」
すると手を握ってくれているガリウスが、きゅっと手を強く握る。
それに一度視線を向けると、彼はコクリと頷いた。
・・・ちょっと、僕も拗ねてしまったかな
そんな風に思いながら苦笑を浮かべた。
「では、教えていただけますか?」
「わかった。我がハイシア家とウルフ家。コンドル家の話を話そう。
・・・、ウルフ家がサーベル国の人間であることは知っているな」
「はい」
あまりにも身近にいすぎて気づくのが遅くなってしまったが、今では理解している。
ゾイドス家の血筋を見ても違和感がなかったのはその為だ。
「ウルフ家がアルアディアに来る以前、コンドル家の分家と言う立ち位置でサーベル国で貴族であった。
まるで機械の様に宗家の指示に従い、戦闘に優れた一族。
戦争に出せば負け知らずで、騎士の家でもないのに戦いで右に出る者はなかった。
コンドル家は勿論、ウルフ家の強さは謎のベールで包まれており誰も真実を知らない。
言葉を発さないのに、統制の取れた隙の無い動き。
当時、ハイシア家の当主が外交の為に訪れた時も、その謎に触れようとしてみたが、王家に聞いてもわからないと言われるほどだった。
当時の当主はそれを内密にされていると一度は勘繰ったが、実際に知らなかったのだろうと手記には残っている」
「王家・・・その様なことを尋ねたのですか」
他国のことを随分と明け透けに聞きすぎなのではないだろうかと驚いてしまう。
「当時の公爵はあまり策を練るのは好きなほうではなかったようで、ストレートに尋ねたようだ。
しかし、ある時護衛にとコンドル家に依頼をすると送られてきたのはウルフ家の者だった。
辛うじて肌は貴族と思える肌の色だったが、眼光は鋭く戦いの中で生きる戦士に当主は少々呆気にとられたそうだ。
迎えに来たのは王都にある貴族街であり来賓客が泊る館だ。
そんな所に、これから戦場にでも向かうような顔つきの者が来たからだ。
おまけにその人間には術が掛けられている。
それは・・・つまり、『隷属の魔法』であったのだが、当主はそれを解いてしまった」
「・・・それは簡単に解けるものなのですか?」
「いや。通常の術者では解けない。
しかし、当時の当主は近年稀にみるほど魔力の高い魔術師で、特に精神系に強い人物であった」
「・・・ウルフ家の隷属の魔法を」
「少し話はずれるが、ゾル達が意識を共有しているのを知っているな」
「はい」
「その状態は、意識だけでなく五感も共有できる。そして、繋がっている人間はすべて同じ状態になる。
それはマインド系の魔法も同じだ」
「・・・、まさか」
「そうだ。つまりそう言うことだ。
1人隷属を掛ければ全員隷属状態になる。
・・・その昔、ウルフ家は一族全体を思考共有して繋がっていた。
1人の1人の視界は皆の視界。隙などもなく誰もウルフ家に勝てる者はいなかった。
しかし、それを良いように使ったのがコンドル家。
ウルフ家の1人を強力な隷属魔法をかけ全体を思うがままにしたのだ」
「・・・」
「ウルフ家を絶やさないために全てを管理し、コンドル家は無敵な状態だった。
しかし、ある時・・・当時の公爵がその呪われた楔を打ち切ると、ウルフ家はハイシア家に恩恵を感じこの国にまで来てくれた。
・・・もとより恨みを買いすぎた彼等にはサーベル国に居場所がなかったのもあるらしいが、一族ごとアルアディアにやってきた」
「・・・。・・・コンドル家は未だにウルフ家を欲しているのですね」
「その様だ。・・・確かに彼等の戦闘力は素晴らしい」
「・・・もしや、戦争を起こすつもりだったのでしょうか」
「そこまでは分からぬ。
しかし、内戦や国家転覆くらいは考えていたかもしれないな」
「・・・、」
「そして、我がハイシア家も滅亡させられていただろう」
有力な駒を奪ったハイシア家を恨んでいるのは当然だろう。
その話を聞きながら考えていると、レオンが続ける。
「ウルフ家の過去をお前に聞かせたくないわけじゃなく、・・・踏み込みコンドル家の家業に触れて欲しくはなかったのだ」
レオンがこちらを見てくるその視線は心配だと言っていた。
「・・・暗殺家業だそうですね」
「聞いたのか?・・・あぁ。
自らお前が突っ込んでいくことは無いだろうが、危険なことは遠ざけたかった。
暗殺家業を主とした貴族など穏やかではないだろう?
・・・、私の父上の代も先代もウルフ家の真相に触れる事柄はずっと起きなかった。
よって私はこの話をないものとし葬ろうとした」
「・・・、」
「それが・・・私の代でまさか降って湧くとは思わなかった」
悔やまれるように顔を歪ませるレオン。
「・・・。ゾル達の思考共有の秘術が禁術なのはその為ですか?」
「あぁ。ウルフ家を守るのもそうだが、似たような術はアルアディアにもあった。
だからコンドル家のような悪質な事件を起こさせないためにもこの国では禁止にしたのだ」
「そうだったのですね。・・・わかりました」
「・・・その」
「父上。ありがとうございます」
「シャリオン・・・」
「少しずつ教えてってください」
そうほほ笑むと、少し驚いたようにしたがレオンは苦笑を浮かべながらも頷くのだった。
一歩ずつ進めればいい。
例え迷っても、シャリオンには心強い味方がいる。
そう思いながら、そっとその手を握り締めるのだった。
どうやら、レオンの屋敷で待ち合わせてくることになっていたのだが、それを破りシャーリーはこの屋敷に直行したことを知り慌てて出てきたようだ。
シャーリーはレオンのあまりにも早い到着に驚き顔をあげたが、自分の顔を見るなり無表情になるレオンに息を飲んで体をびくつかせた。
レオンはすぐに表情を柔らかくし、シャリオンに部屋の手配を頼むとシャーリーを連れて行った。
その後には領地からついてきたゾルの両親がつづいていく。
シャーリーを護送してきたのは、彼等のようだ。
シャリオンを心配し泣きじゃくっていたが、それ以外にも様子がおかしかったように見える。
そんな彼等の後ろ姿を見届けながらシャリオンは呟いた。
「大丈夫だろうか」
「シャーリー様が何をされても許す方なので、勝手にこちらに来訪したことを怒っているわけではありません。
しかし、大変お心が狭い方なので、自分がいないところでシャーリー様が涙し、それを見た人物が居ることを面白く思ってないのでしょう」
「・・・そういうことか」
あの2人がいつまでたっても仲が良いのは、シャリオンも良く知っている。
ガリウスの言葉に納得していると、シャリオンの手が握られて視線をあげると、ガリウスは真剣な眼差しをしている。
「それはあくまで、私もそうだからですが」
「・・・ガリウス?」
「・・・、はぁ」
様子が可笑しいガリウスに訝し気にしたのだが、小さくため息をつかれる。
「シャリオン。後で大切なお話があります」
「え?」
「貴方には認識を改めていただく必要があります」
「・・・?・・・どういうこと?」
「それは今夜お話しましょう。ずっと約束していた例の件もしようと思っていたことですし、丁度良いです」
そう言うガリウスには少し怒りを帯びている感じがした。
何故だ?と、自分の行動を反芻して思い当たることがった。
「ち、違うんだ。ガリィ」
「いい訳は今夜お伺いいたしますよ」
「っ」
ちらりと流し目で視線をやられて息を飲んだ。
その様子を見るにかなり怒りを感じているように見えた。
焦って弁明をしようとしたのだが、そこへレオンとゾルの父が戻ってきた。
一緒について行ったはずのゾルの母は、シャーリーについている様だ。
彼女はウルフ家の人間でありながら、シャーリーに対して敬愛を示している珍しい人物でもあり、シャーリーは特に彼女を信頼しているからだろう。
眉間に皺を寄せたレオンだったが、2人の様子が可笑しいことに訝し気にした。
その視線はあからさまにガリウスを批難している。
「待たせた。・・・?・・・何をした」
「いいえ。何も」
「ふん。その顔で言われても信ぴょう性がないわ。
・・・もしや、お前がシャーリーを責めた訳ではあるまいな」
ギロリと凍てつく目で睨むレオン。
「その様なことを仰りたいなら、お2人で帰られたらどうです?
今日はシャリオンに謝りに来たと聞きましたが」
「!」
ガリウスの言葉に弾かれたようにレオンは視線を逸らすと、シャリオンの元へと駆け寄ってくる。
そして愛おしそうに頬を撫で、そっと抱き寄せた。
「・・・もう起き上がって大丈夫なのか?」
「えぇ」
起きた時も体には痛いところはなかった。
細かい傷などはシャリオンが眠らされている間にとっくにガリウスが治させていた。
だから今はすっかり調子がいい状態である。
「・・・。すまぬ。私の力が及ばないばかりに」
「父上も、父様もご自分を責めないでください」
そう言うと、レオンはピクリと体を動かした後、引き寄せた体をほどいた。
そしてシャリオンを覗き込んだ。
「シャーリーが・・・そう言ったのか?」
「はい。・・・父様は何故ご自分を責めていらっしゃるのですか?」
こう言っては何だが、まだレオンにならわかる。
次期公爵である自分が他に恨みを買うのもわかる。
だが、なぜシャーリーが自分を責めたのかはわからなかった。
シャーリーの家は有力な伯爵家であることは聞いているが、それが関係があるのだろうか。
そんな風に勘繰ってしまう。
すると、レオンは小さくため息をつくと、ガリウスの据わっていない方のシャリオンの隣に腰かけた。
「・・・。シャーリーは・・・私と結婚する前多方面からそう言う目で見られていた」
「そう言う目?」
「フッ・・・お前は瓜二つだからな。
それに私が目を光らせていたから気づかないかもしれないが。
シャーリーはその美しさと天使のような慈悲を持った心に皆虜だった」
「・・・、」
真顔で何を言い出すかと思えば。
とんだのろけで、シャリオンは苦笑を浮かべた。
「嘘ではない。
誰も彼もシャーリーに惚れた。
どんなにお堅い人物も、気難しい貴族も、皆を引き寄せる。
義兄が居なければきっと攫われていた。
・・・いや、実際私に会う前は何度か攫われたことがあると聞いている」
「そう・・・なのですか」
「つかまった犯人は皆口をそろえてこういうのだ。
『シャーリーの美しさに惑わされた』と」
「・・・。まって下さい。父様はそれで私が攫われたのをご自分の所為だと思ってらっしゃるのですか?」
話の流れで言おうとしていることが分かって、そう尋ねればレオンは難しい表情をしてコクリと頷いた。
「父様の所為ではありません!」
「あぁそうだ」
「そして、父上やガリウスの所為でもありません」
「・・・シャリオン」
「どんな理由であれ、それは実行した犯人が悪いのです」
そう言うとレオンはくしゃりと顔を歪ませ、首を横に振る。
「しかし、私を恨めなど言われたことはあるだろう」
「それが何だというのですか」
確かにレオンの仕事の事や、シャーリーの美しさに下衆な感情を頂いている人間もいた。
だが、それで自分達の責めてほしくはない。
シャリオンはレオンから視線を逸らさなかった。
「・・・シャリオン」
「悪いのは何時だってそれをした犯人が悪いのです」
その意見をシャリオンは変える気は無い。
犯人以外に誰が悪いだとか、そんなことは意味がない話だ。
シャーリーにも後でそれを伝えなければならないと思いつつ、話を切り替える。
「この話は終わりです。私はその話をしたいわけではないのです。
・・・父上は私に隠していることがありますね」
「・・・、誰に何を聞いた」
それは肯定されたようなもので、シャリオンは眉を顰める。
「私はそんなに頼りないですか」
「・・・そういうことでは」
「ですが、ガリウスには話しているのでしょう?」
「それは・・・っ」
すると隣から呆れたようにガリウスがため息をつく。
それはほんの少しだけシャリオンの心をささくれさせた。
僕・・・そんなに可笑しなこと聞いている?
落ち着こうと思いたいのに、それが見失いそうだ。
高ぶりそうになったとき、ガリウスがシャリオンの手に手を重ねた。
「レオン様。シャリオンを悲しませたら許しませんよ」
「っ・・・貴様はどちらの味方なのだ」
「言ったでしょう?私はシャリオンの味方です。
・・・シャリオン。勘違いしないでください。
私も答えないので無理やりおど・・・ではなく、何度も尋ねて聞き出したのですよ」
さらりと不穏な言葉を言いながらニコリとほほ笑むガリウス。
公爵で上司でもあるレオンに本当に遠慮がないガリウス。
肝が据わっている。
思わずちらりとレオンを見ると不満げに声が漏れた。
「私を信じていただけないのですか?」
「っ・・・そういう、わけじゃ」
「ディディ殿にサーベル国の人間に『「狼と宝石を連れて来い」と言われた』と聞いたら、理由を知っているのはレオン様です。だったら本人に問いただしたほうが早いでしょう?」
ウルフ家の家紋は確かに狼をあしらっている。
それだけでウルフ家だと瞬時に思えたガリウスに感心する。
シャリオンはあの男、・・・ルシエルに『珍しい狼と宝石を探して冒険している』と言われた時、あの男を心の底から信用は出来なかったが、その言葉の意味にたどり着けなかった。
ゾルに武器を向け、そう言われて漸く気づいたくらいだ。
「そう、・・・だけど。
ルシエルの言っていた『1人捕まえれば全部捕まる』とは、どういう意味なの?」
「それは・・・。
・・・私が答えてしまって宜しいのですか?」
ガリウスはチラリとレオンを見る。
しかし、レオンは言いずらそうに言葉を飲んだ。
なんだか、その姿を見ると少し・・・胸に針で刺されるような痛みが走る。
そして、急に先ほど興奮した感情が引いていく。
悲しいけれど、・・・仕方がない。
シャリオンは苦笑を浮かべた後に、頭を下げた。
「・・・。父上。申し訳ありません。聞き分けの無いことを」
「!」
「父上が仰られないという事は不要だと言う事。差し出がましいことをしました」
「シャリオンっ違うのだっ」
「いいえ。・・・必要になったらガリウスが手を貸してくれるでしょう。だよね?」
そっとガリウスを見上げると、シャリオンの心情を見透かすようにジッとみられる。
きっとすべてを感じ取っているはずだ。
「・・・その聞き分けの良い所は心配になってしまいますね。
勿論。貴方が困っていてもいなくても全力で力になります。
・・・けれど、あなたは次期公爵なのですから、もっとわがままに知りたがって良いのです。
貴方には正しく導くことの出来る素質は持っています。
大丈夫。自信を持ってください」
「でも、」
「私はどちらでも良いです。
ですが、ずっと見てきた私から言わせていただきますと、
シャリオンはレオン様から聞き出すべきです」
「・・・、」
その言葉に視線を逸らしながら、そっとレオンを見ると、心配で苦慮した眼差しでシャリオンを見てきた。
「貴方が領地の主となり、ウルフ家も統べるのですから遠慮する必要はありません。
・・・ただ一つ。
レオン様の弁解をさせていただくと、・・・決してシャリオンが信用できないからではないです」
「・・・、」
「親が子を心配するのは当然です。
・・・危険な場所から我が子だけでも逃がした貴方になら、よくわかるのではないですか?」
「すまない、・・・シャリオン。
私は・・・頭では分かっているつもりなのだが。
・・・どうしてもお前の障害になりそうな面倒事を、退けてしまいたくなるのだ」
「・・・父上」
「それは・・・今ガリウスの言った通り、お前を領主として公爵として信頼していないわけじゃないのだ」
すると手を握ってくれているガリウスが、きゅっと手を強く握る。
それに一度視線を向けると、彼はコクリと頷いた。
・・・ちょっと、僕も拗ねてしまったかな
そんな風に思いながら苦笑を浮かべた。
「では、教えていただけますか?」
「わかった。我がハイシア家とウルフ家。コンドル家の話を話そう。
・・・、ウルフ家がサーベル国の人間であることは知っているな」
「はい」
あまりにも身近にいすぎて気づくのが遅くなってしまったが、今では理解している。
ゾイドス家の血筋を見ても違和感がなかったのはその為だ。
「ウルフ家がアルアディアに来る以前、コンドル家の分家と言う立ち位置でサーベル国で貴族であった。
まるで機械の様に宗家の指示に従い、戦闘に優れた一族。
戦争に出せば負け知らずで、騎士の家でもないのに戦いで右に出る者はなかった。
コンドル家は勿論、ウルフ家の強さは謎のベールで包まれており誰も真実を知らない。
言葉を発さないのに、統制の取れた隙の無い動き。
当時、ハイシア家の当主が外交の為に訪れた時も、その謎に触れようとしてみたが、王家に聞いてもわからないと言われるほどだった。
当時の当主はそれを内密にされていると一度は勘繰ったが、実際に知らなかったのだろうと手記には残っている」
「王家・・・その様なことを尋ねたのですか」
他国のことを随分と明け透けに聞きすぎなのではないだろうかと驚いてしまう。
「当時の公爵はあまり策を練るのは好きなほうではなかったようで、ストレートに尋ねたようだ。
しかし、ある時護衛にとコンドル家に依頼をすると送られてきたのはウルフ家の者だった。
辛うじて肌は貴族と思える肌の色だったが、眼光は鋭く戦いの中で生きる戦士に当主は少々呆気にとられたそうだ。
迎えに来たのは王都にある貴族街であり来賓客が泊る館だ。
そんな所に、これから戦場にでも向かうような顔つきの者が来たからだ。
おまけにその人間には術が掛けられている。
それは・・・つまり、『隷属の魔法』であったのだが、当主はそれを解いてしまった」
「・・・それは簡単に解けるものなのですか?」
「いや。通常の術者では解けない。
しかし、当時の当主は近年稀にみるほど魔力の高い魔術師で、特に精神系に強い人物であった」
「・・・ウルフ家の隷属の魔法を」
「少し話はずれるが、ゾル達が意識を共有しているのを知っているな」
「はい」
「その状態は、意識だけでなく五感も共有できる。そして、繋がっている人間はすべて同じ状態になる。
それはマインド系の魔法も同じだ」
「・・・、まさか」
「そうだ。つまりそう言うことだ。
1人隷属を掛ければ全員隷属状態になる。
・・・その昔、ウルフ家は一族全体を思考共有して繋がっていた。
1人の1人の視界は皆の視界。隙などもなく誰もウルフ家に勝てる者はいなかった。
しかし、それを良いように使ったのがコンドル家。
ウルフ家の1人を強力な隷属魔法をかけ全体を思うがままにしたのだ」
「・・・」
「ウルフ家を絶やさないために全てを管理し、コンドル家は無敵な状態だった。
しかし、ある時・・・当時の公爵がその呪われた楔を打ち切ると、ウルフ家はハイシア家に恩恵を感じこの国にまで来てくれた。
・・・もとより恨みを買いすぎた彼等にはサーベル国に居場所がなかったのもあるらしいが、一族ごとアルアディアにやってきた」
「・・・。・・・コンドル家は未だにウルフ家を欲しているのですね」
「その様だ。・・・確かに彼等の戦闘力は素晴らしい」
「・・・もしや、戦争を起こすつもりだったのでしょうか」
「そこまでは分からぬ。
しかし、内戦や国家転覆くらいは考えていたかもしれないな」
「・・・、」
「そして、我がハイシア家も滅亡させられていただろう」
有力な駒を奪ったハイシア家を恨んでいるのは当然だろう。
その話を聞きながら考えていると、レオンが続ける。
「ウルフ家の過去をお前に聞かせたくないわけじゃなく、・・・踏み込みコンドル家の家業に触れて欲しくはなかったのだ」
レオンがこちらを見てくるその視線は心配だと言っていた。
「・・・暗殺家業だそうですね」
「聞いたのか?・・・あぁ。
自らお前が突っ込んでいくことは無いだろうが、危険なことは遠ざけたかった。
暗殺家業を主とした貴族など穏やかではないだろう?
・・・、私の父上の代も先代もウルフ家の真相に触れる事柄はずっと起きなかった。
よって私はこの話をないものとし葬ろうとした」
「・・・、」
「それが・・・私の代でまさか降って湧くとは思わなかった」
悔やまれるように顔を歪ませるレオン。
「・・・。ゾル達の思考共有の秘術が禁術なのはその為ですか?」
「あぁ。ウルフ家を守るのもそうだが、似たような術はアルアディアにもあった。
だからコンドル家のような悪質な事件を起こさせないためにもこの国では禁止にしたのだ」
「そうだったのですね。・・・わかりました」
「・・・その」
「父上。ありがとうございます」
「シャリオン・・・」
「少しずつ教えてってください」
そうほほ笑むと、少し驚いたようにしたがレオンは苦笑を浮かべながらも頷くのだった。
一歩ずつ進めればいい。
例え迷っても、シャリオンには心強い味方がいる。
そう思いながら、そっとその手を握り締めるのだった。
0
お気に入りに追加
1,131
あなたにおすすめの小説

王道学園の冷徹生徒会長、裏の顔がバレて総受けルート突入しちゃいました!え?逃げ場無しですか?
名無しのナナ氏
BL
王道学園に入学して1ヶ月でトップに君臨した冷徹生徒会長、有栖川 誠(ありすがわ まこと)。常に冷静で無表情、そして無言の誠を生徒達からは尊敬の眼差しで見られていた。
そんな彼のもう1つの姿は… どの企業にも属さないにも関わらず、VTuber界で人気を博した個人VTuber〈〈 アイリス 〉〉!? 本性は寂しがり屋の泣き虫。色々あって周りから誤解されまくってしまった結果アイリスとして素を出していた。そんなある日、生徒会の仕事を1人で黙々とやっている内に疲れてしまい__________
※
・非王道気味
・固定カプ予定は無い
・悲しい過去🐜
・不定期
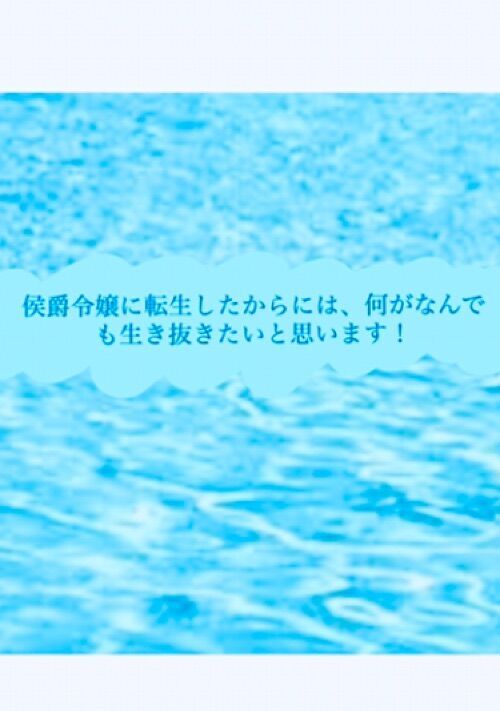
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

王女の中身は元自衛官だったので、継母に追放されたけど思い通りになりません
きぬがやあきら
恋愛
「妻はお妃様一人とお約束されたそうですが、今でもまだ同じことが言えますか?」
「正直なところ、不安を感じている」
久方ぶりに招かれた故郷、セレンティア城の月光満ちる庭園で、アシュレイは信じ難い光景を目撃するーー
激闘の末、王座に就いたアルダシールと結ばれた、元セレンティア王国の王女アシュレイ。
アラウァリア国では、新政権を勝ち取ったアシュレイを国母と崇めてくれる国民も多い。だが、結婚から2年、未だ後継ぎに恵まれないアルダシールに側室を推す声も上がり始める。そんな頃、弟シュナイゼルから結婚式の招待が舞い込んだ。
第2幕、連載開始しました!
お気に入り登録してくださった皆様、ありがとうございます! 心より御礼申し上げます。
以下、1章のあらすじです。
アシュレイは前世の記憶を持つ、セレンティア王国の皇女だった。後ろ盾もなく、継母である王妃に体よく追い出されてしまう。
表向きは外交の駒として、アラウァリア王国へ嫁ぐ形だが、国王は御年50歳で既に18人もの妃を持っている。
常に不遇の扱いを受けて、我慢の限界だったアシュレイは、大胆な計画を企てた。
それは輿入れの道中を、自ら雇った盗賊に襲撃させるもの。
サバイバルの知識もあるし、宝飾品を処分して生き抜けば、残りの人生を自由に謳歌できると踏んでいた。
しかし、輿入れ当日アシュレイを攫い出したのは、アラウァリアの第一王子・アルダシール。
盗賊団と共謀し、晴れて自由の身を望んでいたのに、アルダシールはアシュレイを手放してはくれず……。
アシュレイは自由と幸福を手に入れられるのか?

男女比がおかしい世界の貴族に転生してしまった件
美鈴
ファンタジー
転生したのは男性が少ない世界!?貴族に生まれたのはいいけど、どういう風に生きていこう…?
最新章の第五章も夕方18時に更新予定です!
☆の話は苦手な人は飛ばしても問題無い様に物語を紡いでおります。
※ホットランキング1位、ファンタジーランキング3位ありがとうございます!
※カクヨム様にも投稿しております。内容が大幅に異なり改稿しております。
※各種ランキング1位を頂いた事がある作品です!

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。

いつかコントローラーを投げ出して
せんぷう
BL
オメガバース。世界で男女以外に、アルファ・ベータ・オメガと性別が枝分かれした世界で新たにもう一つの性が発見された。
世界的にはレアなオメガ、アルファ以上の神に選別されたと言われる特異種。
バランサー。
アルファ、ベータ、オメガになるかを自らの意思で選択でき、バランサーの状態ならどのようなフェロモンですら影響を受けない、むしろ自身のフェロモンにより周囲を調伏できる最強の性別。
これは、バランサーであることを隠した少年の少し不運で不思議な出会いの物語。
裏社会のトップにして最強のアルファ攻め
×
最強種バランサーであることをそれとなく隠して生活する兄弟想いな受け
※オメガバース特殊設定、追加性別有り
.

【完結】極貧イケメン学生は体を売らない。【番外編あります】
紫紺
BL
貧乏学生をスパダリが救済!?代償は『恋人のフリ』だった。
相模原涼(さがみはらりょう)は法学部の大学2年生。
超がつく貧乏学生なのに、突然居酒屋のバイトをクビになってしまった。
失意に沈む涼の前に現れたのは、ブランドスーツに身を包んだイケメン、大手法律事務所の副所長 城南晄矢(じょうなんみつや)。
彼は涼にバイトしないかと誘うのだが……。
※番外編を公開しました(10/21)
生活に追われて恋とは無縁の極貧イケメンの涼と、何もかもに恵まれた晄矢のラブコメBL。二人の気持ちはどっちに向いていくのか。
※本作品中の公判、判例、事件等は全て架空のものです。完全なフィクションであり、参考にした事件等もございません。拙い表現や現実との乖離はどうぞご容赦ください。
※4月18日、完結しました。ありがとうございました。

【完結】魔王様、溺愛しすぎです!
綾雅(要らない悪役令嬢1巻重版)
ファンタジー
「パパと結婚する!」
8万年近い長きにわたり、最強の名を冠する魔王。勇者を退け続ける彼の居城である『魔王城』の城門に、人族と思われる赤子が捨てられた。その子を拾った魔王は自ら育てると言い出し!? しかも溺愛しすぎて、周囲が大混乱!
拾われた子は幼女となり、やがて育て親を喜ばせる最強の一言を放った。魔王は素直にその言葉を受け止め、嫁にすると宣言する。
シリアスなようでコメディな軽いドタバタ喜劇(?)です。
【同時掲載】アルファポリス、カクヨム、エブリスタ、小説家になろう
【表紙イラスト】しょうが様(https://www.pixiv.net/users/291264)
挿絵★あり
【完結】2021/12/02
※2022/08/16 第3回HJ小説大賞前期「小説家になろう」部門 一次審査通過
※2021/12/16 第1回 一二三書房WEB小説大賞、一次審査通過
※2021/12/03 「小説家になろう」ハイファンタジー日間94位
※2021/08/16、「HJ小説大賞2021前期『小説家になろう』部門」一次選考通過作品
※2020年8月「エブリスタ」ファンタジーカテゴリー1位(8/20〜24)
※2019年11月「ツギクル」第4回ツギクル大賞、最終選考作品
※2019年10月「ノベルアップ+」第1回小説大賞、一次選考通過作品
※2019年9月「マグネット」ヤンデレ特集掲載作品
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















