お気に入りに追加
40
あなたにおすすめの小説


攫われた転生王子は下町でスローライフを満喫中!?
伽羅
ファンタジー
転生したのに、どうやら捨てられたらしい。しかも気がついたら籠に入れられ川に流されている。
このままじゃ死んじゃう!っと思ったら運良く拾われて下町でスローライフを満喫中。
自分が王子と知らないまま、色々ともの作りをしながら新しい人生を楽しく生きている…。
そんな主人公や王宮を取り巻く不穏な空気とは…。
このまま下町でスローライフを送れるのか?
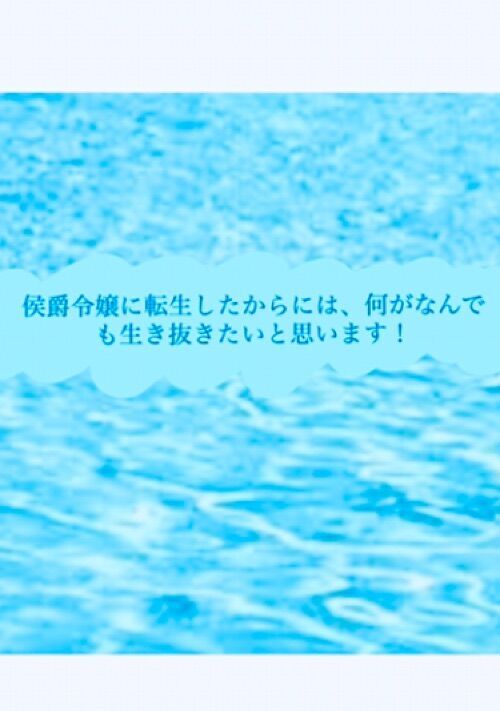
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

異世界でお取り寄せ生活
マーチ・メイ
ファンタジー
異世界の魔力不足を補うため、年に数人が魔法を貰い渡り人として渡っていく、そんな世界である日、日本で普通に働いていた橋沼桜が選ばれた。
突然のことに驚く桜だったが、魔法を貰えると知りすぐさま快諾。
貰った魔法は、昔食べて美味しかったチョコレートをまた食べたいがためのお取り寄せ魔法。
意気揚々と異世界へ旅立ち、そして桜の異世界生活が始まる。
貰った魔法を満喫しつつ、異世界で知り合った人達と緩く、のんびりと異世界生活を楽しんでいたら、取り寄せ魔法でとんでもないことが起こり……!?
そんな感じの話です。
のんびり緩い話が好きな人向け、恋愛要素は皆無です。
※小説家になろう、カクヨムでも同時掲載しております。

最遅で最強のレベルアップ~経験値1000分の1の大器晩成型探索者は勤続10年目10度目のレベルアップで覚醒しました!~
ある中管理職
ファンタジー
勤続10年目10度目のレベルアップ。
人よりも貰える経験値が極端に少なく、年に1回程度しかレベルアップしない32歳の主人公宮下要は10年掛かりようやくレベル10に到達した。
すると、ハズレスキル【大器晩成】が覚醒。
なんと1回のレベルアップのステータス上昇が通常の1000倍に。
チートスキル【ステータス上昇1000】を得た宮下はこれをきっかけに、今まで出会う事すら想像してこなかったモンスターを討伐。
探索者としての知名度や地位を一気に上げ、勤めていた店は討伐したレアモンスターの肉と素材の販売で大繁盛。
万年Fランクの【永遠の新米おじさん】と言われた宮下の成り上がり劇が今幕を開ける。

異世界に来ちゃったよ!?
いがむり
ファンタジー
235番……それが彼女の名前。記憶喪失の17歳で沢山の子どもたちと共にファクトリーと呼ばれるところで楽しく暮らしていた。
しかし、現在森の中。
「とにきゃく、こころこぉ?」
から始まる異世界ストーリー 。
主人公は可愛いです!
もふもふだってあります!!
語彙力は………………無いかもしれない…。
とにかく、異世界ファンタジー開幕です!
※不定期投稿です…本当に。
※誤字・脱字があればお知らせ下さい
(※印は鬱表現ありです)

人生初めての旅先が異世界でした!? ~ 元の世界へ帰る方法探して異世界めぐり、家に帰るまでが旅行です。~(仮)
葵セナ
ファンタジー
主人公 39歳フリーターが、初めての旅行に行こうと家を出たら何故か森の中?
管理神(神様)のミスで、異世界転移し見知らぬ森の中に…
不思議と持っていた一枚の紙を読み、元の世界に帰る方法を探して、異世界での冒険の始まり。
曖昧で、都合の良い魔法とスキルでを使い、異世界での冒険旅行? いったいどうなる!
ありがちな異世界物語と思いますが、暖かい目で見てやってください。
初めての作品なので誤字 脱字などおかしな所が出て来るかと思いますが、御容赦ください。(気が付けば修正していきます。)
ステータスも何処かで見たことあるような、似たり寄ったりの表示になっているかと思いますがどうか御容赦ください。よろしくお願いします。

吉原遊郭一の花魁は恋をした
佐武ろく
ライト文芸
飽くなき欲望により煌々と輝く吉原遊郭。その吉原において最高位とされる遊女である夕顔はある日、八助という男と出会った。吉原遊郭内にある料理屋『三好』で働く八助と吉原遊郭の最高位遊女の夕顔。決して交わる事の無い二人の運命はその出会いを機に徐々に変化していった。そしていつしか夕顔の胸の中で芽生えた恋心。だが大きく惹かれながらも遊女という立場に邪魔をされ思い通りにはいかない。二人の恋の行方はどうなってしまうのか。
※この物語はフィクションです。実在の団体や人物と一切関係はありません。また吉原遊郭の構造や制度等に独自のアイディアを織り交ぜていますので歴史に実在したものとは異なる部分があります。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















