お気に入りに追加
40
あなたにおすすめの小説


罪人として生まれた私が女侯爵となる日
迷い人
ファンタジー
守護の民と呼ばれる一族に私は生まれた。
母は、浄化の聖女と呼ばれ、魔物と戦う屈強な戦士達を癒していた。
魔物からとれる魔石は莫大な富を生む、それでも守護の民は人々のために戦い旅をする。
私達の心は、王族よりも気高い。
そう生まれ育った私は罪人の子だった。
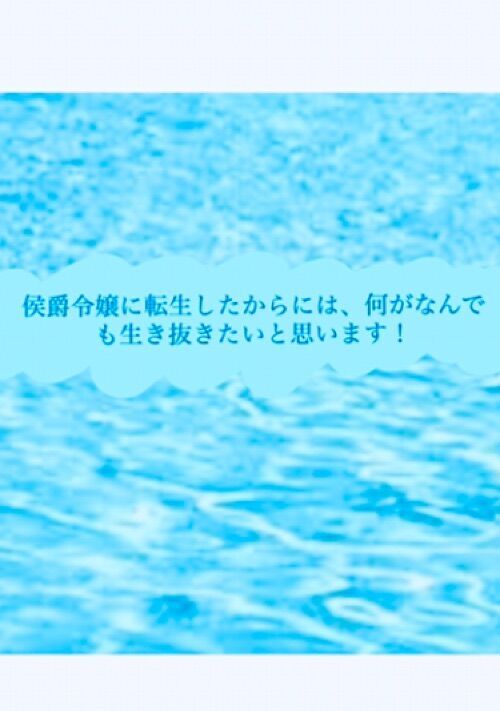
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

称号チートで異世界ハッピーライフ!~お願いしたスキルよりも女神様からもらった称号がチートすぎて無双状態です~
しらかめこう
ファンタジー
「これ、スキルよりも称号の方がチートじゃね?」
病により急死した主人公、突然現れた女神によって異世界へと転生することに?!
女神から様々なスキルを授かったが、それよりも想像以上の効果があったチート称号によって超ハイスピードで強くなっていく。
そして気づいた時にはすでに世界最強になっていた!?
そんな主人公の新しい人生が平穏であるはずもなく、行く先々で様々な面倒ごとに巻き込まれてしまう...?!
しかし、この世界で出会った友や愛するヒロインたちとの幸せで平穏な生活を手に入れるためにどんな無理難題がやってこようと最強の力で無双する!主人公たちが平穏なハッピーエンドに辿り着くまでの壮大な物語。
異世界転生の王道を行く最強無双劇!!!
ときにのんびり!そしてシリアス。楽しい異世界ライフのスタートだ!!
小説家になろう、カクヨム等、各種投稿サイトにて連載中。毎週金・土・日の18時ごろに最新話を投稿予定!!

婚約者に嫌われているようなので離れてみたら、なぜか抗議されました
花々
恋愛
メリアム侯爵家の令嬢クラリッサは、婚約者である公爵家のライアンから蔑まれている。
クラリッサは「お前の目は醜い」というライアンの言葉を鵜呑みにし、いつも前髪で顔を隠しながら過ごしていた。
そんなある日、クラリッサは王家主催のパーティーに参加する。
いつも通りクラリッサをほったらかしてほかの参加者と談笑しているライアンから離れて廊下に出たところ、見知らぬ青年がうずくまっているのを見つける。クラリッサが心配して介抱すると、青年からいたく感謝される。
数日後、クラリッサの元になぜか王家からの使者がやってきて……。
✴︎感想誠にありがとうございます❗️
✴︎(承認不要の方)ご指摘ありがとうございます。第一王子のミスでした💦
✴︎ヒロインの実家は侯爵家です。誤字失礼しました😵

異世界に召喚されたが勇者ではなかったために放り出された夫婦は拾った赤ちゃんを守り育てる。そして3人の孤児を弟子にする。
お小遣い月3万
ファンタジー
異世界に召喚された夫婦。だけど2人は勇者の資質を持っていなかった。ステータス画面を出現させることはできなかったのだ。ステータス画面が出現できない2人はレベルが上がらなかった。
夫の淳は初級魔法は使えるけど、それ以上の魔法は使えなかった。
妻の美子は魔法すら使えなかった。だけど、のちにユニークスキルを持っていることがわかる。彼女が作った料理を食べるとHPが回復するというユニークスキルである。
勇者になれなかった夫婦は城から放り出され、見知らぬ土地である異世界で暮らし始めた。
ある日、妻は川に洗濯に、夫はゴブリンの討伐に森に出かけた。
夫は竹のような植物が光っているのを見つける。光の正体を確認するために植物を切ると、そこに現れたのは赤ちゃんだった。
夫婦は赤ちゃんを育てることになった。赤ちゃんは女の子だった。
その子を大切に育てる。
女の子が5歳の時に、彼女がステータス画面を発現させることができるのに気づいてしまう。
2人は王様に子どもが奪われないようにステータス画面が発現することを隠した。
だけど子どもはどんどんと強くなって行く。
大切な我が子が魔王討伐に向かうまでの物語。世界で一番大切なモノを守るために夫婦は奮闘する。世界で一番愛しているモノの幸せのために夫婦は奮闘する。

冤罪で山に追放された令嬢ですが、逞しく生きてます
里見知美
ファンタジー
王太子に呪いをかけたと断罪され、神の山と恐れられるセントポリオンに追放された公爵令嬢エリザベス。その姿は老婆のように皺だらけで、魔女のように醜い顔をしているという。
だが実は、誰にも言えない理由があり…。
※もともとなろう様でも投稿していた作品ですが、手を加えちょっと長めの話になりました。作者としては抑えた内容になってるつもりですが、流血ありなので、ちょっとエグいかも。恋愛かファンタジーか迷ったんですがひとまず、ファンタジーにしてあります。
全28話で完結。

吉原遊郭一の花魁は恋をした
佐武ろく
ライト文芸
飽くなき欲望により煌々と輝く吉原遊郭。その吉原において最高位とされる遊女である夕顔はある日、八助という男と出会った。吉原遊郭内にある料理屋『三好』で働く八助と吉原遊郭の最高位遊女の夕顔。決して交わる事の無い二人の運命はその出会いを機に徐々に変化していった。そしていつしか夕顔の胸の中で芽生えた恋心。だが大きく惹かれながらも遊女という立場に邪魔をされ思い通りにはいかない。二人の恋の行方はどうなってしまうのか。
※この物語はフィクションです。実在の団体や人物と一切関係はありません。また吉原遊郭の構造や制度等に独自のアイディアを織り交ぜていますので歴史に実在したものとは異なる部分があります。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















