9 / 18
第9話 クジラ討伐2
しおりを挟む
ガリガリッ
辺りから聞こえてくる音。そして僕の体の中からも。
「ぐぅぅぅ」
膝辺りから皮膚を食い破って飛び出た『軍隊草』を僕は殴り潰す。
体の至る所が力が入らない、僕はそのまま体制を崩して倒れる。
ちらりとあたりを見る。飛びかかってくる『軍隊草』が数十体。様々な種類の木が割り込んできて僕らを守る。しかし、すでにいくつも穴が開いて。
防戦一方になっている。
グラシアの体は血と木くずで汚れて、そして足元から這い上がろうとする『生命の樹』。
そんな時、目の前を横切った『軍隊草』
それを殴り潰そうとした時、初めはやけに腕が重い気がして、一気に軽くなった。
視界に入ったものはひじの手前ほどしかない僕の腕。その先はと見ると、集まり絡み合って腕の形をした『生命の樹』が動き出しみるみる内に崩れていっていた。そして、グラシアのもとへ向かう。
そう言えば体の至る所の感覚がなくなっていて……。
僕は消えれるんだ。今までどこかふわふわとした感覚だったものが、いま形を持ち、重さを持った。
その時に渦巻いた様々な感情。こんな状況なのに僕はその感情について吟味し始めていた。抗うつもりもない。僕は目を瞑った。
ごめんグラシア。僕がいなくなれば、僕に気を裂く必要もない。それで僕はグラシアの一部に慣れて。……ユズキは……博……士はどう思うだ…ろうな。結局……このために生きて……きたのか……。満たされてる……筈なの……にな。
「やめてよ」
薄れ行く意識の中やけにはっきりと聞こえたグラシアの声。その時の僕はもう諦めていて、まだ聴覚が残っているんだなんて他人事感覚で。
もう手足は感覚がない。まるで落ちているような浮遊感。どこに力が入って、どこに力が入ってないのか分からない。
視界には僕の体からグラシアのもとへ向かう『生命の樹』が群れを成している。見える範囲だけで僕の体の四分一くらいの量があるんじゃないか。
臓器がひんやりとしたものを感じて。
同時に安らかな気分だった。場違いなのは分かる。どこも凄惨な状況で、でもグラシアの一部になれる。
絶対的存在なんだ。
「だからやめてよ」
ゾクゾク
痺れるような快感。その痺れがどんどんと強くなっていく。
なんだこれ……。
グラシアから発せられる大地エネルギーが強くなっていく。そして、地面がうねった。目の前や様々な地面の至る所がどんどん競りあがっていて、
ぐしゃぁ
赤い液体で目の前が埋め尽くされた。その液体は地面の至る所から噴き出した。その赤い液体から姿を現したのは枝。血で塗れた枝はその太さを増していく。
『暴食の樹』だ。数秒して気づいた。成長を止めた『暴食の樹』がまたグラシアのエネルギーを受け取って成長した。そして、クジラの体を貫いた。
僕やグラシアの周りを数十の枝が地面からクジラの体を貫いて現れる。僕らの周りに盾のように囲う。
どがぁぁぁん
至る所から爆発音が聞こえてきて、隙間から届く強い光と熱。
この辺りから意識がかすれ始めて、
目の前が時折ノイズが走ったように黒くなる。そしていつしか取れない黒いしみがついて、そのシミが大きくなっていく。
「……ィ、ル……、……ティ!」
すぐ近くでグラシアの声が聞こえる。なのに、まるで遠くのように聞こえなくなって。
痛いような、気持ちいような、何もなかったような。
そして何も感じなくなった。
かすかに残った意識の中で、僕なんて気にしないでくれ。こんな僕なんてと祈った。そして、もう目を覚まさないでくれと祈った。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ルティ!」
体中に広がる強い快感。僕は目を覚ます。
「ルティ」
そうして両側から感じる温かい感触。
「グラシア……ユズキ……」
僕はぽつりと言った。そして僕が生き残ったことにも気づいた。
体の感覚は手足の感覚はない。でも、死ぬことはないだろうと気づく。
博士の表情を見る。唇はキュッと結んで、でも口角を上げて、笑い損ねている。
生き残った事実がより現実味を帯びて、僕の心に重くのしかかる。
自分の体を考えなくて済んだおかげで別のところに意識を回せる。そこで気づいた。
傷一つないグラシアと、両腕がないユズキ。
「大丈夫だ。研究室に戻ればまだ『生命の樹』が大量にある」
博士はそう言った。
そこまでして僕を生き残そうとするのか。
どういう風に言えばいいのだろう。満足感? 一度間近に来たことでもう一度同じ盛り上がりを覚えれないのか、それともグラシアヘの申し訳なさが強くなったか。それとも、ユズキへの申し訳なさか。
前ほどに強くグラシアの一部になりたいと願えなくなっていた。
それと反比例して、強くなる息苦しさ。
急激に世界が狭く感じる。世界から自分が切り離された気分になる。僕はここにいるのにここにいない気がして。自分以外物が全部おもちゃのように見えて。
圧倒的な孤独感。
どう生きればいいんだろう。どう消えればいいんだろう。僕は一体どうすればいいんだ。
僕は逃げ場を求めるように辺りを見た。
まだクジラの背中にいるのだろう。辺りは凄惨な状況だった。
あたりの木々は吹き飛び、粉々に砕け、根元から折れている木も。その木肌は焦げていたり、何か木の残骸のようなものが突き刺さっていた李、木肌がめくれて中身が見えていたり。
微かに痙攣するものはあるだけで、動くものは確認できなかった。
これを全てグラシアの思いだけで行った。
……これが進化した先か。
何のために生きてるんだよ。
僕は逃げ場の絶望感を覚えた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「死者、重軽傷者、合わせて千人か……」
エツィオが資料をめくる。
「意外と被害が少なかったですね」
シーナがぽつりと言う。
「あのなぁ……」
エツィオがそう不服そうに口を開いたが、言葉を止め、更に不服そうに口を閉じる。
分かっていたことだが最も被害が出たのは軍隊でもなく、研究機関でもなく一般人だった。取り逃した『軍隊草』が居住区に向かい、大きな被害をもたらした。
エツィオは空を見た、キノコのような傘を開いている『暴食の樹』の頂上。
エツィオとシーナは人の住む『暴食の樹』の枝に立っていた。その眼下にいるクジラ。そのクジラに向かって多くの研究員が行きかっている。当たり前だ。ほとんどの種は絶滅していると言われている植物ばかりだ。
研究価値はどれほどのものか。
「トニー博士の供述を見たか? クジラにはいまだ莫大なエネルギーを蓄えており、それが地上に落下すると、その地上にエネルギーを与えることになる。それを止めるために被害はやむなしと考えた」
また地上で暮らすこと。これが人の願いだ。
そのためには、大地エネルギーを利用する種の絶滅が必要だ。目に着けば殺し、栄養を極力与えない。それが大事だ。そして、太陽エネルギーを利用する世界を作ることがゴールだ。
その観点で考えれば確かにうなずける。
しかし……。エツィオは首をひねった。エツィオは口を開こうとしたが、一度躊躇した。その後また口を開いた。
「他にも方法があっただろ。海に落とすとかさ……」
紙を持つ手に力が入る。くしゃと音を立てる紙。
「なぁ、これ思うんだけどさ。一番この作戦でのメリットてさ、簡単にクジラの背中に生えている植物を研究できることだろ。……トニー博士お前に作戦を伝えるときに……何か言ってたか?」
ところどころ躊躇うところがあったが、エツィオは頭に浮かんだことおをありのまま尋ねた。
二人の間に無言の時間が流れる。
強い風が二人を襲う。シーナの長い髪をはためかせる。
「……何か言ってたと思います」
シーナはぽつりと言った。
「なんだよそれ」
エツィオは声を荒げかけたが、シ―ナの表情があまりに当然のようで興味がなさそうな様子を見て、何を言っても無駄だとすぐに悟った。
向かう先のない感情を押し込めるために唇を強く噛みしめた。
辺りから聞こえてくる音。そして僕の体の中からも。
「ぐぅぅぅ」
膝辺りから皮膚を食い破って飛び出た『軍隊草』を僕は殴り潰す。
体の至る所が力が入らない、僕はそのまま体制を崩して倒れる。
ちらりとあたりを見る。飛びかかってくる『軍隊草』が数十体。様々な種類の木が割り込んできて僕らを守る。しかし、すでにいくつも穴が開いて。
防戦一方になっている。
グラシアの体は血と木くずで汚れて、そして足元から這い上がろうとする『生命の樹』。
そんな時、目の前を横切った『軍隊草』
それを殴り潰そうとした時、初めはやけに腕が重い気がして、一気に軽くなった。
視界に入ったものはひじの手前ほどしかない僕の腕。その先はと見ると、集まり絡み合って腕の形をした『生命の樹』が動き出しみるみる内に崩れていっていた。そして、グラシアのもとへ向かう。
そう言えば体の至る所の感覚がなくなっていて……。
僕は消えれるんだ。今までどこかふわふわとした感覚だったものが、いま形を持ち、重さを持った。
その時に渦巻いた様々な感情。こんな状況なのに僕はその感情について吟味し始めていた。抗うつもりもない。僕は目を瞑った。
ごめんグラシア。僕がいなくなれば、僕に気を裂く必要もない。それで僕はグラシアの一部に慣れて。……ユズキは……博……士はどう思うだ…ろうな。結局……このために生きて……きたのか……。満たされてる……筈なの……にな。
「やめてよ」
薄れ行く意識の中やけにはっきりと聞こえたグラシアの声。その時の僕はもう諦めていて、まだ聴覚が残っているんだなんて他人事感覚で。
もう手足は感覚がない。まるで落ちているような浮遊感。どこに力が入って、どこに力が入ってないのか分からない。
視界には僕の体からグラシアのもとへ向かう『生命の樹』が群れを成している。見える範囲だけで僕の体の四分一くらいの量があるんじゃないか。
臓器がひんやりとしたものを感じて。
同時に安らかな気分だった。場違いなのは分かる。どこも凄惨な状況で、でもグラシアの一部になれる。
絶対的存在なんだ。
「だからやめてよ」
ゾクゾク
痺れるような快感。その痺れがどんどんと強くなっていく。
なんだこれ……。
グラシアから発せられる大地エネルギーが強くなっていく。そして、地面がうねった。目の前や様々な地面の至る所がどんどん競りあがっていて、
ぐしゃぁ
赤い液体で目の前が埋め尽くされた。その液体は地面の至る所から噴き出した。その赤い液体から姿を現したのは枝。血で塗れた枝はその太さを増していく。
『暴食の樹』だ。数秒して気づいた。成長を止めた『暴食の樹』がまたグラシアのエネルギーを受け取って成長した。そして、クジラの体を貫いた。
僕やグラシアの周りを数十の枝が地面からクジラの体を貫いて現れる。僕らの周りに盾のように囲う。
どがぁぁぁん
至る所から爆発音が聞こえてきて、隙間から届く強い光と熱。
この辺りから意識がかすれ始めて、
目の前が時折ノイズが走ったように黒くなる。そしていつしか取れない黒いしみがついて、そのシミが大きくなっていく。
「……ィ、ル……、……ティ!」
すぐ近くでグラシアの声が聞こえる。なのに、まるで遠くのように聞こえなくなって。
痛いような、気持ちいような、何もなかったような。
そして何も感じなくなった。
かすかに残った意識の中で、僕なんて気にしないでくれ。こんな僕なんてと祈った。そして、もう目を覚まさないでくれと祈った。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ルティ!」
体中に広がる強い快感。僕は目を覚ます。
「ルティ」
そうして両側から感じる温かい感触。
「グラシア……ユズキ……」
僕はぽつりと言った。そして僕が生き残ったことにも気づいた。
体の感覚は手足の感覚はない。でも、死ぬことはないだろうと気づく。
博士の表情を見る。唇はキュッと結んで、でも口角を上げて、笑い損ねている。
生き残った事実がより現実味を帯びて、僕の心に重くのしかかる。
自分の体を考えなくて済んだおかげで別のところに意識を回せる。そこで気づいた。
傷一つないグラシアと、両腕がないユズキ。
「大丈夫だ。研究室に戻ればまだ『生命の樹』が大量にある」
博士はそう言った。
そこまでして僕を生き残そうとするのか。
どういう風に言えばいいのだろう。満足感? 一度間近に来たことでもう一度同じ盛り上がりを覚えれないのか、それともグラシアヘの申し訳なさが強くなったか。それとも、ユズキへの申し訳なさか。
前ほどに強くグラシアの一部になりたいと願えなくなっていた。
それと反比例して、強くなる息苦しさ。
急激に世界が狭く感じる。世界から自分が切り離された気分になる。僕はここにいるのにここにいない気がして。自分以外物が全部おもちゃのように見えて。
圧倒的な孤独感。
どう生きればいいんだろう。どう消えればいいんだろう。僕は一体どうすればいいんだ。
僕は逃げ場を求めるように辺りを見た。
まだクジラの背中にいるのだろう。辺りは凄惨な状況だった。
あたりの木々は吹き飛び、粉々に砕け、根元から折れている木も。その木肌は焦げていたり、何か木の残骸のようなものが突き刺さっていた李、木肌がめくれて中身が見えていたり。
微かに痙攣するものはあるだけで、動くものは確認できなかった。
これを全てグラシアの思いだけで行った。
……これが進化した先か。
何のために生きてるんだよ。
僕は逃げ場の絶望感を覚えた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「死者、重軽傷者、合わせて千人か……」
エツィオが資料をめくる。
「意外と被害が少なかったですね」
シーナがぽつりと言う。
「あのなぁ……」
エツィオがそう不服そうに口を開いたが、言葉を止め、更に不服そうに口を閉じる。
分かっていたことだが最も被害が出たのは軍隊でもなく、研究機関でもなく一般人だった。取り逃した『軍隊草』が居住区に向かい、大きな被害をもたらした。
エツィオは空を見た、キノコのような傘を開いている『暴食の樹』の頂上。
エツィオとシーナは人の住む『暴食の樹』の枝に立っていた。その眼下にいるクジラ。そのクジラに向かって多くの研究員が行きかっている。当たり前だ。ほとんどの種は絶滅していると言われている植物ばかりだ。
研究価値はどれほどのものか。
「トニー博士の供述を見たか? クジラにはいまだ莫大なエネルギーを蓄えており、それが地上に落下すると、その地上にエネルギーを与えることになる。それを止めるために被害はやむなしと考えた」
また地上で暮らすこと。これが人の願いだ。
そのためには、大地エネルギーを利用する種の絶滅が必要だ。目に着けば殺し、栄養を極力与えない。それが大事だ。そして、太陽エネルギーを利用する世界を作ることがゴールだ。
その観点で考えれば確かにうなずける。
しかし……。エツィオは首をひねった。エツィオは口を開こうとしたが、一度躊躇した。その後また口を開いた。
「他にも方法があっただろ。海に落とすとかさ……」
紙を持つ手に力が入る。くしゃと音を立てる紙。
「なぁ、これ思うんだけどさ。一番この作戦でのメリットてさ、簡単にクジラの背中に生えている植物を研究できることだろ。……トニー博士お前に作戦を伝えるときに……何か言ってたか?」
ところどころ躊躇うところがあったが、エツィオは頭に浮かんだことおをありのまま尋ねた。
二人の間に無言の時間が流れる。
強い風が二人を襲う。シーナの長い髪をはためかせる。
「……何か言ってたと思います」
シーナはぽつりと言った。
「なんだよそれ」
エツィオは声を荒げかけたが、シ―ナの表情があまりに当然のようで興味がなさそうな様子を見て、何を言っても無駄だとすぐに悟った。
向かう先のない感情を押し込めるために唇を強く噛みしめた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

化想操術師の日常
茶野森かのこ
キャラ文芸
たった一つの線で、世界が変わる。
化想操術師という仕事がある。
一般的には知られていないが、化想は誰にでも起きる可能性のある現象で、悲しみや苦しみが心に抱えきれなくなった時、人は無意識の内に化想と呼ばれるものを体の外に生み出してしまう。それは、空間や物や生き物と、その人の心を占めるものである為、様々だ。
化想操術師とは、頭の中に思い描いたものを、その指先を通して、現実に生み出す事が出来る力を持つ人達の事。本来なら無意識でしか出せない化想を、意識的に操る事が出来た。
クズミ化想社は、そんな化想に苦しむ人々に寄り添い、救う仕事をしている。
社長である九頭見志乃歩は、自身も化想を扱いながら、化想患者限定でカウンセラーをしている。
社員は自身を含めて四名。
九頭見野雪という少年は、化想を生み出す能力に長けていた。志乃歩の養子に入っている。
常に無表情であるが、それは感情を失わせるような過去があったからだ。それでも、志乃歩との出会いによって、その心はいつも誰かに寄り添おうとしている、優しい少年だ。
他に、志乃歩の秘書でもある黒兎、口は悪いが料理の腕前はピカイチの姫子、野雪が生み出した巨大な犬の化想のシロ。彼らは、山の中にある洋館で、賑やかに共同生活を送っていた。
その洋館に、新たな住人が加わった。
記憶を失った少女、たま子。化想が扱える彼女は、記憶が戻るまでの間、野雪達と共に過ごす事となった。
だが、記憶を失くしたたま子には、ある目的があった。
たま子はクズミ化想社の一人として、志乃歩や野雪と共に、化想を出してしまった人々の様々な思いに触れていく。
壊れた友情で海に閉じこもる少年、自分への後悔に復讐に走る女性、絵を描く度に化想を出してしまう少年。
化想操術の古い歴史を持つ、阿木之亥という家の人々、重ねた野雪の過去、初めて出来た好きなもの、焦がれた自由、犠牲にしても守らなきゃいけないもの。
野雪とたま子、化想を取り巻く彼らのお話です。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?
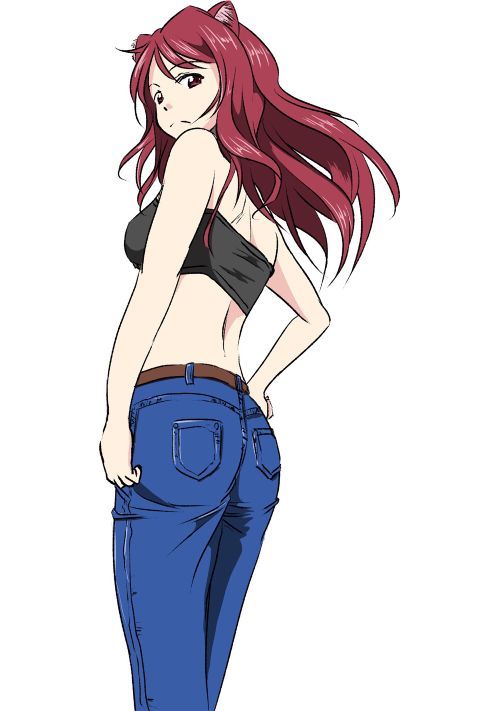
遥か
カリフォルニアデスロールの野良兎
キャラ文芸
鶴木援(ツルギタスケ)は、疲労状態で仕事から帰宅する。何も無い日常にトラウマを抱えた過去、何も起きなかったであろう未来を抱えたまま、何故か誤って監獄街に迷い込む。
生きることを問いかける薄暗いロー・ファンタジー。
表紙 @kafui_k_h


恵麗奈お嬢様のあやかし退治
刻芦葉
キャラ文芸
一般的な生活を送る美憂と、世界でも有名な鳳凰院グループのお嬢様である恵麗奈。
普通なら交わることのなかった二人は、人ならざる者から人を守る『退魔衆』で、命を預け合うパートナーとなった。
二人にある共通点は一つだけ。その身に大きな呪いを受けていること。
黒を煮詰めたような闇に呪われた美憂と、真夜中に浮かぶ太陽に呪われた恵麗奈は、命がけで妖怪との戦いを繰り広げていく。
第6回キャラ文芸大賞に参加してます。よろしくお願いします。

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。

ニンジャマスター・ダイヤ
竹井ゴールド
キャラ文芸
沖縄県の手塚島で育った母子家庭の手塚大也は実母の死によって、東京の遠縁の大鳥家に引き取られる事となった。
大鳥家は大鳥コンツェルンの創業一族で、裏では日本を陰から守る政府機関・大鳥忍軍を率いる忍者一族だった。
沖縄県の手塚島で忍者の修行をして育った大也は東京に出て、忍者の争いに否応なく巻き込まれるのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















