24 / 76
24. 黒の噂話
しおりを挟む「じゃあ茉里ちゃん、行ってらっしゃい!」
こうやって皓人さんが顔いっぱいの笑顔で私を仕事に送り出してくれるのは、これで何回目だろうか? 手を振りながら、会社の建屋に向かってせかせかと足を動かす。
皓人さんの家に泊まった翌日は、行き先が私の家だろうと会社だろうと、いつも皓人さんが車で送ってくれる。「毎回じゃ申し訳ないから」と断ろうとしたこともあったけれども、「おれ、ドライブ好きなんだよね」の一言で、それ以上は何も言えなくなってしまった。
さすがに会社の目の前まで送ってもらうのは、周囲の目もあるから遠慮してもらって。社屋の裏の目立たないところにいつも停めてくれているけれど、なんだかまだ慣れない。
そしていまだに、私と皓人さんの関係を彼が明言してくれたことも、彼の気持ちを言葉にしてくれたことも、一度だってないのだ。
言葉にこだわる必要もないし、気長に待とう、と思っているけれど、気にしないようにするのも、待つのも、地味に体力とメンタルを消耗する。
「中谷、昨日作ってもらった資料、悪いんだけど修正して欲しい箇所があって」
不意打ちな菊地さんの声に、私はあわてて資料のファイルを開いた。
「3つ目のグラフのスライド出せる? その元データの数字が間違ってたみたいで、あ、そう、そこ」
私に後ろから覆い被さるような格好で、菊地さんは画面を指差した。思いの外、近い距離に思わず息をのんでしまう。
「ここのデータを、正しい数字に修正して欲しいんだ」
「分かりました」
涼しい顔を作ってそう答えながらも、内心は心臓の音が聞こえてしまうんじゃないかと、ドギマギしていた。
「正しいデータのファイルはさっきメールしたから、それ使って」
「はい」
頷いてから、ちらり、菊地さんの顔を見上げると、至近距離でがっつりと瞳がかち合ってしまった。バチリ、と音がしそうなほどで、思わず逸らすことができず、じっと見つめてしまう。
この角度からだと伏し目がちになるからか、いつもよりも睫毛が長く見えるな。そんな場違いなことを考えている時だった。
「ちょっと菊地、セクハラ!」
いつもよりも強めな仁科さんの声に、ハッとしたように菊地さんは私の身体から距離をとった。
「中谷、ごめん」
そう言いながら小さく頭を下げる菊地さんに、状況が飲み込めないままの私は、蚊の鳴くような声で「大丈夫です」とだけ答えた。
仁科さんに軽く叩かれている菊地さんを見つめながら、段々と彼女の言葉の意味が飲み込めてきた。菊地さんと私の身体的距離が近すぎると感じた仁科さんが、それを指摘して菊地さんに注意してくれた、ということか。
つまり、セクハラの被害者は私ってことか。
内心驚きながら、菊地さんからのメールを開いた。菊地さんとはもう少し距離が近いこともあったし、不思議と不快に思ったことはなかったから気に留めていなかったけれども、確かに、あの距離感は端から見ていると不適切に思われるかもしれない。驚きの方が勝るものの、なんとなく納得できる。
昼休みになると、珍しく仁科さんからお誘いがあり、他の女性社員数人と共に食堂へと向かう。隅の方で定食をつつきながら、みなさんが花を咲かせる話を、なんとなく耳が拾う。
「中谷さん」
他の人々の会話を遮ることなく、さりげなく仁科さんは私だけに声をかけた。
「午前の件の続きになっちゃうんだけど、もし、男性社員の言動が不適切で不快に思ったら、いつでも私に相談してね。特に菊地と私は同期だから、小さなことでも私がきつく言い聞かせるし」
表情から仁科さんの真剣さが伝わってくる。こんな風に言ってもらえるのはとてまありがたいし、心強い。
「ありがとうございます」
笑顔で答えれば、仁科さんも力強く頷き返してくれる。
「でもさ、正直なところ菊地くんならありだなって思っちゃったりしない?」
テーブル内から不意に発せられた言葉に、ギクリ、と心臓が大きく跳ねた。心の内を見透かされたような、気まずさが私の全身へと静かに広まっていく。
「分かる。課長は無理だけど、菊地さんなら平気っていうか、むしろラッキー、みたいな?」
「イケメン無罪ってやつ? 別にすっごいイケメンって程じゃないけどさ」
「整ってるようには見えるけど、パーツはそこまでじゃないと思うときあるよね」
女子社員の好き放題な話し方に、心の奥がズクリ、と痛む。
人の口に戸は立てられぬ、と言うけれども、こうやって好き勝手言われるのは、その内容がプラスであろうがマイナスであろうが、良い気分にはならない。北野さんと脇田さんの件でさんざん噂話の種にされた身としては、より痛みが身に染みる部分がある。
けれども、それ以上に痛いのは、彼女たちの言葉は案外、私の心の声に近しいという現実だ。
「菊地くんって付き合ってる人いるのかな?」
誰かの何気ない一言に、つい耳を澄ませてしまう自分が、嫌だ。
「この間訊いたら、彼女はいないって言ってましたよ」
その言葉が聞こえて、なぜか安心したように胸を撫で下ろす私がいた。私には、関係がない話のはずなのに。
「そうなの? じゃあ、チャンスじゃん!」
「でも、なんでいないんだろう? 理想が高すぎるとか?」
「好みのタイプがめちゃくちゃうるさいなかな?」
盛り上がるテーブル内で、数人の視線が私に突き刺さったのは気のせいだろうか。結局、いまだに私は女子社員たちからは目をつけられているんだ。心のなかでため息を漏らす。
「仁科さん、同期なら菊地くんの好みとか知ってるんじゃない?」
自分の望まない話題で唐突に矛先を向けられた仁科さんは、曖昧な笑みを浮かべる。
「同期っていっても、そういう話はしないんで」
仁科さんはそう言って切り抜けようとするも、それを許してくれる空気ではなかった。
「じゃあさ、菊地くんの元カノは? どんな人だったか、とか、聞いたことないの?」
先輩社員に鋭い視線で射貫かれて、仁科さんは困ったように笑いながら、思案顔になる。気まずい空気のなか、おずおずと仁科さんは口を開いた。
「聞いたことはないんですけど、昔、街中で恋人っぽい人と手を繋いで歩いているのを1回だけ見かけたことがあります」
仁科さんの言葉に、私は二重の意味で落胆した。ここで菊地さんのプライベートを暴露してしまう仁科さんと、菊地さんの元カノの話で気分が落ち込んだ私に対して。
「どんな人だった?」
テーブルのみなさんは前のめりになって仁科さんの言葉を待つ。
「えっと、背が高い人だったと思います」
遠慮がちに、仁科さんは言った。
「他には?」
「他には……うーん、言葉にするのがちょっと難しいですね」
そう言ってはぐらかそうとする仁科さんを、彼女たちは逃さなかった。
「じゃあ、このテーブルの中で、誰が一番雰囲気似てた?」
いくつかの敵意のある視線が一瞬、私を捉えたのを感じて、思わず俯いてしまう。
「うーん、この中にはいませんね。皆さん、タイプからちょっと外れてる気がします」
あっけらかん、と仁科さんが言い放つと、先程までテーブルを支配していた緊張感のある空気が一瞬にして緩んだ。
「なーんだ。まあ、現実ってそんなもんだよね」
そんな一言と共に、話題はすぐに別のものへと移っていった。私はフーッと、誰にもばれないように息を吐き出す。一体いつから、息を詰めていたのだろうか。
ほんの少し。ほんの少しだけ、仁科さんが私の名前を挙げてくれることを期待した自分を、ぶん殴りたい気分だ。噂話を嫌っているはずの自分が、この人たちの話に思いっきり耳を傾けてしまった自分を呪い倒したい。
私はなんてちっぽけな人間なんだろう。
自己嫌悪に陥りながら、私はテーブルの女子社員に声をかけて一足先にオフィスフロアへと戻った。
「中谷が食堂なんて珍しいよな」
執務室に入ろうとしたところで、後ろから声をかけられる。その声が耳に届いたとたん、身体が一気に熱くなった。先程までこの人の噂話に荷担してしまっていた、羞恥心からだろうか。
「ちょっと、仁科さんに誘われて」
そう答えている間に、菊地さんはそっとドアを開けると、そのまま押さえた状態で私へ先に入るよう促す。いつもながら、スマート過ぎるその動作に心臓は否応なしに軽やかなリズムを刻んでしまう。
「お姉さまがたの空気に圧倒されちゃったんじゃないか?」
心配そうな表情を向けられて、無意識に下唇を噛み締めてしまう。
「あー、もう、あんまり唇噛み締めるなって」
無造作に菊地さんの手が私の顔に伸びてきたかと思うと、私に触れる前にピタリと止まり、そのまま彼の頭の後ろへと進路を変えた。
「ごめん。こういうの、普通に気持ち悪いし、セクハラだよな」
悪い、悪い、と謝る菊地さんを、私は不思議な表情で見上げる。
客観的に見れば、セクハラかもしれない。
けれども、気持ち悪いとか嫌だとかいう感情は微塵も浮かばなくて。
ただ、ドキドキした。
なんて言ってしまったら、問題なのだろうか。
「仁科にも注意されたんだよ。中谷への距離感、バグってないか、って」
本来なら有り難いはずの仁科さんの気遣いが、なぜだか私の中に暗い影を落とす。
そんなこと、言わなくていいのに。
そんな余計なこと、言わなくていいのに。
なんて、不埒な言葉が頭の回りをグルグルと回る。珍しいことがあったからだろうか。今日の私は、どこかおかしい。
「仁科さんと、仲良いですよね」
いつもより強ばった声が想わず口をついて出た。
「仲良い、のか? まあ、同じ部署で唯一の同期だから、気心知れてるってのはあると思うけど、特段仲が良いって程じゃない、はず」
本心でそう言ってるんだろうことは容易に分かっているのに、菊地さんの言葉が妙に私の胸に引っかかった。
「何? 羨ましいの?」
ちょっと強気な声に、自然と菊地さんの瞳を見上げてしまう。挑むような力強い視線と満足げに上がった口角が、私の心を大きく惑わせる。気付かないふりをするのが難しいほど、ドクン、と心臓が跳ねる。
このままだと、飲み込まれてしまいそうだ。
そう感じて咄嗟に足元へ視線を逸らす。視界に入る靴が、私に皓人さんの存在を思い出させた。少し前までならすぐに感じたであろう強い罪悪感が、なぜか今日は鈍くしか込み上げてこなかった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
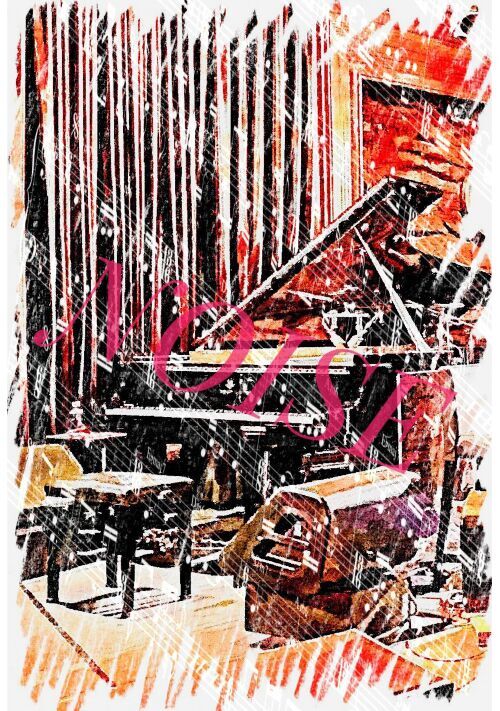
NOISE
セラム
青春
ある1つのライブに魅せられた結城光。
そのライブは幼い彼女の心に深く刻み込まれ、ピアニストになることを決意する。
そして彼女と共に育った幼馴染みのベース弾き・明里。
唯一無二の"音"を求めて光と明里はピアノとベース、そして音楽に向き合う。
奏でられた音はただの模倣か、それとも新たな世界か––––。
女子高生2人を中心に音を紡ぐ本格音楽小説!

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

CODE:HEXA
青出 風太
キャラ文芸
舞台は近未来の日本。
AI技術の発展によってAIを搭載したロボットの社会進出が進む中、発展の陰に隠された事故は多くの孤児を生んでいた。
孤児である主人公の吹雪六花はAIの暴走を阻止する組織の一員として暗躍する。
※「小説家になろう」「カクヨム」の方にも投稿しています。
※毎週金曜日の投稿を予定しています。変更の可能性があります。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















