20 / 76
20. 黒とのささやかな休憩
しおりを挟む「え、なんのこと?」
皓人さんからの想像もしていなかった追求に、私は思わず姿勢を正した。ただの音声通話なのだから、姿は見えないというのに。
「だから、最近おれに何か言わせようとしてない? って」
声音から、彼の苛立ちが伝わってくる。
「そ、そんなことないよ」
何がいけなかったんだろう? なんて今から考えてももう遅い。起きてしまったことを、無かったことにはできない。後の祭りだ。
「本当に?」
そう問いかける彼の口調は、私の言葉などちっとも信じていなさそうで。
いつものあの、甘くて優しい声と同じ声のはずなのに、全く違って聞こえる声に、思わず泣きたくなった。
私が何も言えないでいると、電話の向こうから深いため息が聞こえてくる。
どうすれば良かったんだろう。
どうすれば良いんだろう
声も出せず、私はただその場で固まってしまう。
「あのさ、」
そう話し始めた彼の声は、先程よりかは少しばかり優しい声音だった。
「好きってさ、無理矢理言わされるもんじゃなくて、自然と言っちゃうもんだと思うんだよね」
彼の口調は、いつもの優しい口調に戻っていた。けれども、甘い響きは、どこにも感じられない。
「そう、だよね。なんか、ごめんね」
気がつけば、私はそんなことを口走っていた。
どうして私が謝っているんだろう? という疑問が頭のなかにふわりと浮かぶ。
彼に無理矢理その言葉を言わせようとするなんて、そんなこと思ってもいなかった。ただ自然と、好きだという言葉が出てきただけなのに。それって、そんなに悪いことなの?
その言葉を言わないってことは、皓人さんは私のこと、好きじゃないってこと? じゃあ、今まで過ごしてきた時間は一体なんだったの?
グルグルと嫌な考えばかりが頭を巡る。
「ごめん、時差ボケで疲れてるのか、ちょっと今日は頭回らないわ。また明日、改めて話そう?」
「……分かった」
私の答えを聞くなり、通話はすぐに終了された。
スマートフォンに表示された「通話終了」の文字を見て、私は静かに膝を抱えて涙を流した。
*************************
ふー、と一気に息を吐き出す。
結局昨晩は、あのあとすぐに眠ってしまった。なんだか、心がひどく疲れていた。
朝起きて、目があまり腫れていないのを鏡で確認し、あのまま泣き暮らさなくて良かった、と安心した。泣き腫らした目で会社なんて行くもんじゃない。
とはいえ、心が疲れていることには変わりがないわけで。気を緩ませると泣いてしまいそうなので、神経を張り詰めさせる。PC画面で資料を見つめながら、私は下唇をぎゅっと噛みしめた。
「歯に口紅つくぞ」
頭上から落ちてきた声に、私ははっと顔を上げる。ニヤリ、と口の端を上げて笑う菊地さんに、カアッと自分の顔に熱が集まるのを感じた。
「今日さ、食堂にアイスクリーム屋のワゴンが来てるんだけど、男一人で行くのは、ちょっと恥ずかしいんだよなー」
世間話でもするかのように、菊地さんは話す。
「だから、中谷を拉致りに来た」
突然少年のように笑顔で菊地さんは言う。殺伐としていた私の神経が、ほんの少し緩まったような気がした。
「分かりました。拉致られます」
私は財布と口紅を手に取って、菊地さんの後に続くように立ち上がった。
後ろを歩きながら、ふと、菊地さんの背中って広いな、なんて考えが頭に浮かんだ。この背中に寄りかかって泣けたら、どれだけ楽だろうか。そんな考えが頭をもたげたのに気付き、私は必死でそれを追い払った。
「昨日のアドバイス、失敗だったんだろ?」
思いの外長蛇になっているアイスクリームワゴンの列に並びながら、菊地さんは問いかけた。
「え?」
「目、少し腫れてる」
目元を指差され、私は申し訳なさそうに小さく頷いた。
「ごめんな、俺のせいで」
「いえ、そんな、菊地さんが謝ることじゃ」
言いながら、昨日の皓人さんの言葉を思い出して、また胸が痛む。
「私と、彼の問題なんで」
話しながら、頭のなかでは皓人さんの言葉が何度もリピートされている。
あの冷たい声が、私の心をキュウッと締め付ける。心が酸欠になりそうだ。
「好きって、無理矢理言わせるもんじゃないですもんね。こっちにはそんなつもりがなくても、向こうがプレッシャーを感じたなら、しょうがないですよね」
関係がないはずの菊地さんにこんな話して、私ってばどういうつもりなんだろう?
自分が情けなくて、菊地さんと視線を合わせたくなくて、私は俯いた。
「俺もさ、昔、恋人に似たようなこと言われたことあるからさ、気持ちは分かる」
静かに、菊地さんは言った。
「こっちがそう思ったから言っただけなのに、向こうがそれにプレッシャー感じて。こっちも、無理矢理言わせようとは思ってないけど。でも、やっぱり同じ言葉を返して欲しかった気持ちも否定できないからさ、あんまり強く言えなくて」
ちらり、と視線だけ上げれば、菊地さんはどこか遠くを見つめていて。その恋人のことを考えているのだろうか、と思うと、胸が切ない音を立てた。
「だけどさ、本当に欲しいものを言ったときにそれを否定する恋人と一緒にいる意味って、どんぐらいあるんだろう?」
そう言って、菊地さんは私の方を真っ直ぐに見つめているのが、気配で分かった。彼の視線に合わせるように、私も顔を上げる。
「中谷にとっては辛い決断かもしれないけど、もしも相手が中谷の欲しいものをくれないなら、そんな相手とは関係を続ける必要はないんじゃないかなって、俺は思う」
じっと見つめられ、思わずゴクリ、と唾を飲み込んだ。彼の切れ長の瞳は真剣そのもので。その言葉が心からのものだというのが、伝わってくる。
「じゃあさ、欲しいものを欲しいって言う、練習な」
真剣な表情のまま、菊地さんは続ける。
「バニラと、チョコレート、どっちがいい?」
「へ?」
予想していたのとは全く違った問いかけに、私は思わずすっとんきょうな声を上げてしまった。
「どっちの味が欲しい? バニラか、チョコレートか」
菊地さんは、だんだんと近づいてきたワゴンの看板を指差した。
バニラか、チョコレートか。
看板に描かれた、バニラ味の白いソフトクリームのイラストは、なぜだか皓人さんを想起させた。甘くて、ふんわりとしていて、優しげで、そして、冷たい。
バニラ、と言おうとした口は、自然と固まってしまう。私は迷いの感情から、看板から視線をそらした。その視線が、菊地さんの瞳とかち合った。
ちょうどビルの窓から入ってくる光が菊地さんの瞳に入り込んで、いつもより少しだけ瞳の色が薄くなって見えた。
黒髪の前髪の隙間からのぞく、焦げ茶色の瞳。
それを単純に、綺麗だと思った。
あまりにも綺麗で、目が離せなくなった。
「中谷?」
「……チョコレート、にします」
まるで魔法か何かにかけられたみたいに、私の口は自然と動いた。
「いいのか? さっき、バニラって言おうとしてなかった?」
「良いんです。今日は、チョコレートの気分なので」
ニコリ、と笑えば、菊地さんはなんだか誇らしそうな笑みを返してくれた。
「ほら、チョコレート」
そう言って菊地さんが差し出してくれたチョコレート味のソフトクリームは、心なしか堂々と輝いているように見えて。私はお礼を言いながら、それを受け取った。
誰かに決めてもらったんじゃなく、運に任せたわけでもなく、自分で選んだ味。小さなことかもしれないけれども、私のなかでは、これは大きな出来事だ。
誇らしい気分で菊地さんの手元に握られたソフトクリームを見る。白と黒の渦巻きだ。
「……え? それ、」
「これ? ミックス」
当たり前のことのように、菊地さんは言った。
「バニラかチョコレートか、どっちかしかなかったんじゃないんですか?」
私の問いに菊地さんは、ほれ、とスプーンで看板を指す。確かにそこには、バニラとチョコレートだけでなく、ミックスの文字が存在した。
「え、なんか……ズルい」
私の言葉に笑いながら、菊地さんはは無造作に舌を出してソフトクリームを舐め上げた。
「どっちも食べられるならさ、両方味わいたいじゃん?」
そんな菊地さんの答えよりも、私の視線は彼の舌に釘付けだった。大胆且つ確実に、白と黒の柔らかいソフトクリームを赤い舌が捕える様は、直視してはいけない光景のような背徳感があって……。
「欲しい?」
冷たいアイスに冷やされたせいか、いつもよりも少しだしづらそうな声に、無性に身体の中心が熱くなる。
「え?」
「いや、物欲しそうに見てるからさ。やっぱり少しでもバニラ食いたい?」
「あ、いや」
ただあなたに見惚れていただけです、とは言えなくて。私はもごもごと適当な言い訳を舌に乗せて、自身のアイスに集中することにした。このまま放っておいたら、私の思考はどんどんと危ない方向へと突き進んでいってしまいそうだ。
私はとにかく、自分のソフトクリームに専念することにした。自分でチョコレートを選べたんだ。それをまずは誇らしく思おうじゃないか。食べ進めながら、自然と笑顔が溢れる。
「中谷、」
不意に名前を呼ばれ、菊地さんを見上げた。
「口の横、ついてる」
彼は自身の親指で、自分の唇の端を指し示す。
「え?」
あたふたしながら、私はすぐに教えてもらった箇所へと指を伸ばした。
「いや、ちょっと下過ぎ。もうちょっと上、で左、って、あ、行き過ぎ」
菊地さんの指示に従いながらも、私はなかなか該当の箇所にたどり着けない。しびれを切らしたらしい菊地さんは、諦めたような声を出すと、無遠慮に私の頬に手を添えた。
一瞬、時が止まったかと思った。
驚きで目を丸くして、私は菊地さんを見上げた。
そのまま、スローモーションのようなゆっくりさで、菊地さんは自身の親指の腹で私の唇を拭い去っていく。本当は普通のスピードだったのかもしれない。けれども、私にはとてもゆっくりに思えた。
「悪い、口紅もっと剥げたかも」
そう言いながら、彼は当たり前のように自分の親指を口に含む。私の唇を拭ったばかりの、その親指を。
カーッと頬が熱くなる。
この熱を収める方法を、私は知らない。
「あの、私、お手洗いに寄ってから戻りますね。あ、ご馳走さまでした」
私は慌ててそう告げると、バクリ、と残っていたアイスをコーンごと口に突っ込み、その場から逃げるようにしてトイレに駆け込んだ。
個室のドアを閉めて、胸の前に手を当てる。心臓がドクン、ドクン、と大きな音を立てているのが、掌に伝わった。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
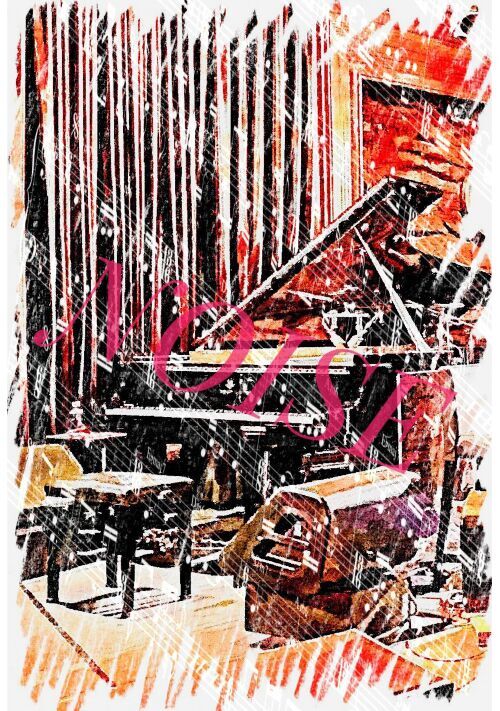
NOISE
セラム
青春
ある1つのライブに魅せられた結城光。
そのライブは幼い彼女の心に深く刻み込まれ、ピアニストになることを決意する。
そして彼女と共に育った幼馴染みのベース弾き・明里。
唯一無二の"音"を求めて光と明里はピアノとベース、そして音楽に向き合う。
奏でられた音はただの模倣か、それとも新たな世界か––––。
女子高生2人を中心に音を紡ぐ本格音楽小説!

CODE:HEXA
青出 風太
キャラ文芸
舞台は近未来の日本。
AI技術の発展によってAIを搭載したロボットの社会進出が進む中、発展の陰に隠された事故は多くの孤児を生んでいた。
孤児である主人公の吹雪六花はAIの暴走を阻止する組織の一員として暗躍する。
※「小説家になろう」「カクヨム」の方にも投稿しています。
※毎週金曜日の投稿を予定しています。変更の可能性があります。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















