5 / 15
#05 北風の鎮魂歌
しおりを挟む
──春を待てずに。
初冬の夜に大雪が降った。最近は積もる事も少なくなったから、珍しいと思ったが、子供のように喜ぶ事は出来なかった。歩けば靴の中に雪が入り込んで来るし、払い落せなかった雪は部屋の中で溶ける。さっさと終わらせて暖めた部屋に戻ろう。仕事も粗方片付いているから、久しぶりに朝から酒でも呑んでしまおう。そう思ってアパートの階段を下りると、妙な事に気が付いた。まだ朝早い所為か、階段から続く駐車場も道路もほとんど真っ平らな雪原になっている。その中に一列、道の真ん中から隣の空き地へ続く足跡が伸びていた。それは空き地の隅にある大きな木の太い枝の下まで続いていた。足跡はそこで途切れている。そこに何がある訳でもなく、戻ったような跡も無い。一体何が何をしたのだろう。俺は考えるのを止めてゴミ捨て場へ急いだ。
(了・足跡の先)
正常な足取りではない。それ位は自覚できる程度に酔っていた。珍しく旧友に誘われて呑んで、その帰りだ。それなりに年を食ったせいか呑み屋が全て閉まるまで、なんて呑み方はできなくなっていた。午後十一時。師走の呑み屋街はこれから騒がしくなって行くのだろうが、もうそれに付き合う気にもならなかった。コートを探って財布とスマホ、部屋の鍵のありかを確認する。それだけあれば問題無いし、それぐらいの思考はできる程度の酔い具合だった。後は部屋に戻ってシャワーでも浴びて、少し呑み直せば明日の朝だ。そんな事を考えながら慣れた道を歩く。呑み屋街の音と光が少しずつ遠くなると街灯がやけに眩しく見えた。新しいものに変えたのだろうか、少し前に通った時は切れかかっていたはずだ。まぁ、悪い事じゃないか。少し歩くと雪がちらついて来た。強い光に近付いて、目が慣れ始めると、その真下に真っ赤な何かが見えた。どうやら赤いコートを着た誰かが立っているらしい。待ち合わせだろうか。強い光の中を舞う雪がそいつの長い黒髪に落ちるが、払うような素振りどころか、身動き一つしない。人の事だ。気にする事でも無い。そのまま通り過ぎようとしたその時、そいつは小さな声で、それでもはっきりと分かる言葉を口にした。俺は聞こえていないフリをして歩いた。部屋に戻ってシャワーを浴びて、髪が乾くまで軽く呑み直してベッドに入った。
夢を見た。翌朝、朝食を終えて、昼が近付いてもその夢が頭を離れなかった。仕方なく近所の花屋へ向かい、赤い花を買った。その足であの街灯の下へ向かった。先客が居たらしい。赤い花が一本供えられていた。俺は買ったばかりの花をその隣に添えて手を合わせた。昨晩の夢の中、あの赤いコートの女は、この街灯の下でこう言った。
「私、ここで死んだのよ。」
女の目的も先客が誰なのかも知らないが、これでもう夢には出ない欲しいと願うばかりだった。
(了・赤い花)
クリスマスだ年末だと言って誰もがおいしい重いができる訳ではない。つがいの居ない男三人が安アパートの一室に集まって、寂しく鍋を囲みアルコールを喉に流し込む事だってある。幸いな事に食材も酒も、暖房の類も充実している。いや、この状況と大雪の予報を見て買い込んだ。外は吹雪に近い有様だったがこれなら要らない苦労をする事はない。不安があるとすれば、風当たりが良過ぎてガタガタ鳴っているガラス戸ぐらいか。
「割れやしないだろうな。」
「さぁね、何か飛んで来れば割れるだろうが。」
三人で笑った。
「そりゃどこも一緒だろ。」
そんな事でも言って笑っていなければ虚しくて潰れてしまいそうだった。
一しきり鍋を食べ終え、簡単な片付けをした。どうせ炬燵で寝るのだろうから、ガスコンロ毎ひっくり返したら大変な事になる。簡単な肴と酒だけを残して炬燵に戻った時、大きな音がした。この部屋は沿線の隣にあるから、汽車が通る度に大きな音が通り過ぎ、小さな地震が起こるし、時折どこかの部屋の戸の閉まる音が響いて来る事もある。
「おい、今の何だ?」
慣れていた俺は気にならなかったが、友人は気になったようだった。
「ああ、いつものこったよ。」
「ホントに何か飛んで来たんじゃないか?」
冗談半分だろう、もう一人の友人がカーテンを開けた。そこには吹き込んだ雪が貼り付いたガラス戸と、赤い手形が付いていた。それは雪が溶けるように透明に変わりながら流れ落ちて行った。
「何が飛んで来たんだ?」
「知るかよ。」
慌てた様子でカーテンを閉める友人に、俺はそれしか言えなかった。
(了・手形)
風の強い夕方だった。身を縮めて歩く歩道に等間隔で生える街路樹はすっかり葉を落としていて、強い風に枝を揺さぶられるだけだった。早く帰って熱い風呂にでも浸かりたかったが、交差点の信号に止められた。無視してしまおうかとも思ったが、まだ車通りがある。足を止めて恨めしい思いで空を見上げる。雲が広がっていた。すぐに暗くなって、雪が降り出しそうだ。視線を地上に戻す瞬間一際強い風が吹いた。一層大きく街路樹の枝が揺れるが、その中に揺れずにいるものがあった。他が風よけになっているのか、偶然そこだけ風が入らなかったのか、どうでも良かった。早く帰ろう。
翌朝、地方紙に交通事故の記事が載った。俺が足止めを食らった交差点で横断歩道を渡っていた女性が轢かれて重体らしい。時刻は丁度俺が家に辿り着いた頃になっていた。運転手の証言として「青信号だったし、直前まで見えなかった。」と書かれていた。あの枝の隙間で揺れずにいた何かと関係あるのだろうか。何れ俺には確認のしようもない。
(了・北風と悪魔)
炬燵に首まで入ってテレビを見ていると姉に悪戯をされる事がある。足をくすぐられたり、引っ張られたり。今日はやたら力が強かった。
「ちょっと、痛いってば。」
振り払うように炬燵から体を半分出した。
「どったの?」
リビングに入って来た風呂上りらしい姉が歯ブラシをくわえたまま言う。母は台所で洗い物をしている。父はまだ帰って来ていないし、他には家族もペットも家にはいない。慌てて炬燵からはい出た。覗き込んで見る勇気は、今のところ無い。
(了・誰?)
我が家には幽霊が居る。はっきりと姿を見た事は無いが、恐らく女性だろうと思う。珈琲を淹れようと思えば勝手に瓶が開く。風呂に入ろうとすると勝手に扉が開いて、タオルも用意される。朝になれば米が炊かれていて、目玉焼きも出来あがっている。一つ困る事があるとすれば、酒瓶が開かない事だ。
「呑み過ぎですよ。」
耳元で囁く声が聴こえる。それはそうだろうが、少しぐらい許容して貰いたいものだ。
(了・貴方好み)
少女、だろう。日本人形のような和服だが、袷が逆で色も白い。安アパートの誰かも知らない人の部屋の玄関口に立ち、ふっとこっちをみて、微笑む。可愛らしい、と思うべきだろう。そんな容貌だった。翌日、少女が微笑んでいた部屋の人間が死んだ。自殺なんてそれ程驚く事じゃない。悩みや投げ出したい事なんか幾らでもある。不思議と気になったのはそんな時に必ずその少女が居る事だ。今も。俺の部屋の前に居る少女に、俺は何を言えば良いのだろう?
(了・次の獲物)
玄関先に小さな雪だるまがあった。はてと思う。確かに悪戯好きな従姉が来る予定はあったが、未だ少し先の筈だ。空を見上げる。滔々と雪が落ちる。そういえば、産まれる事のなかった兄か姉が居たな。苦笑して鍵を回す。今更、何でもない話か。
(了・雪だるま)
少しばかり山間に入った辺りにある家に婿入りした。俺は次男だし、実家には何となく馴染めなかった。冬に入ると平地でも雪が降る地方だ、こんな場所なら早くから雪が降り積もり、氷柱を垂らす。始めての迎える冬のその寒さに俺はやや閉口していたが、
「なぁ。」
「なぁに?」
嫁に問い掛けた。納屋の隅、垂れ下がった氷柱が赤黒く染まっている。
「ああ、あれ? 納屋は古いままだからねー、サビとかペンキじゃない?」
そんなものだろうか。
「ま、ひい爺ちゃんが死んだトコでもあるけど。」
平然と言ってのける嫁と、全く気にする様子の無い家族を見て、どうもここにも馴染めないかも知れないな、と思った。
(了・赤)
其れは純白の花だった。真っ白な少女が俺に向かって差し出して居る。頭の先から足の先まで白いのに、その眼だけは蒼かった。
「いつまで?」
高い、玲瓏な声で問い掛けて来る。意図は全く解らなかった。
「すっかり寒くなったねぇ。」
恋人にはこの少女が見えていないようだった。
「今年もマフラー編んであげるね。」
去年の秋の終わり。編み物が得意な彼女は、俺の好み通り青い色の毛糸でマフラーを編んで呉れた。
「うん。そうしよう。去年のは、捨てよう。毎日巻いてくれたからすっかり解れちゃったもんね。」
彼女が其れで良いのなら、其れで良いだろう。
「それでお別れ、ってのは、多分無理だけど。」
零れる涙を拭えない。俺にはもう彼女に触れる手が無い。
「いつまで、認めないつもり?」
白い花が冷たい風に揺れた。
「それじゃ、また来るね。」
彼女は涙を拭いながらふらふらと立ち上がった。線香の匂いがする。
「貴方が認めれば、後はその花が導いてくれる。」
雪が降り始めた。花と同じ、真っ白な雪。何時も違うのは、まるで道のように雪が降らない場所がある事だった。白い花を見詰める。俺ももう、次の場所へ行くべきなのだろうか。
(了・北風の鎮魂歌)
初冬の夜に大雪が降った。最近は積もる事も少なくなったから、珍しいと思ったが、子供のように喜ぶ事は出来なかった。歩けば靴の中に雪が入り込んで来るし、払い落せなかった雪は部屋の中で溶ける。さっさと終わらせて暖めた部屋に戻ろう。仕事も粗方片付いているから、久しぶりに朝から酒でも呑んでしまおう。そう思ってアパートの階段を下りると、妙な事に気が付いた。まだ朝早い所為か、階段から続く駐車場も道路もほとんど真っ平らな雪原になっている。その中に一列、道の真ん中から隣の空き地へ続く足跡が伸びていた。それは空き地の隅にある大きな木の太い枝の下まで続いていた。足跡はそこで途切れている。そこに何がある訳でもなく、戻ったような跡も無い。一体何が何をしたのだろう。俺は考えるのを止めてゴミ捨て場へ急いだ。
(了・足跡の先)
正常な足取りではない。それ位は自覚できる程度に酔っていた。珍しく旧友に誘われて呑んで、その帰りだ。それなりに年を食ったせいか呑み屋が全て閉まるまで、なんて呑み方はできなくなっていた。午後十一時。師走の呑み屋街はこれから騒がしくなって行くのだろうが、もうそれに付き合う気にもならなかった。コートを探って財布とスマホ、部屋の鍵のありかを確認する。それだけあれば問題無いし、それぐらいの思考はできる程度の酔い具合だった。後は部屋に戻ってシャワーでも浴びて、少し呑み直せば明日の朝だ。そんな事を考えながら慣れた道を歩く。呑み屋街の音と光が少しずつ遠くなると街灯がやけに眩しく見えた。新しいものに変えたのだろうか、少し前に通った時は切れかかっていたはずだ。まぁ、悪い事じゃないか。少し歩くと雪がちらついて来た。強い光に近付いて、目が慣れ始めると、その真下に真っ赤な何かが見えた。どうやら赤いコートを着た誰かが立っているらしい。待ち合わせだろうか。強い光の中を舞う雪がそいつの長い黒髪に落ちるが、払うような素振りどころか、身動き一つしない。人の事だ。気にする事でも無い。そのまま通り過ぎようとしたその時、そいつは小さな声で、それでもはっきりと分かる言葉を口にした。俺は聞こえていないフリをして歩いた。部屋に戻ってシャワーを浴びて、髪が乾くまで軽く呑み直してベッドに入った。
夢を見た。翌朝、朝食を終えて、昼が近付いてもその夢が頭を離れなかった。仕方なく近所の花屋へ向かい、赤い花を買った。その足であの街灯の下へ向かった。先客が居たらしい。赤い花が一本供えられていた。俺は買ったばかりの花をその隣に添えて手を合わせた。昨晩の夢の中、あの赤いコートの女は、この街灯の下でこう言った。
「私、ここで死んだのよ。」
女の目的も先客が誰なのかも知らないが、これでもう夢には出ない欲しいと願うばかりだった。
(了・赤い花)
クリスマスだ年末だと言って誰もがおいしい重いができる訳ではない。つがいの居ない男三人が安アパートの一室に集まって、寂しく鍋を囲みアルコールを喉に流し込む事だってある。幸いな事に食材も酒も、暖房の類も充実している。いや、この状況と大雪の予報を見て買い込んだ。外は吹雪に近い有様だったがこれなら要らない苦労をする事はない。不安があるとすれば、風当たりが良過ぎてガタガタ鳴っているガラス戸ぐらいか。
「割れやしないだろうな。」
「さぁね、何か飛んで来れば割れるだろうが。」
三人で笑った。
「そりゃどこも一緒だろ。」
そんな事でも言って笑っていなければ虚しくて潰れてしまいそうだった。
一しきり鍋を食べ終え、簡単な片付けをした。どうせ炬燵で寝るのだろうから、ガスコンロ毎ひっくり返したら大変な事になる。簡単な肴と酒だけを残して炬燵に戻った時、大きな音がした。この部屋は沿線の隣にあるから、汽車が通る度に大きな音が通り過ぎ、小さな地震が起こるし、時折どこかの部屋の戸の閉まる音が響いて来る事もある。
「おい、今の何だ?」
慣れていた俺は気にならなかったが、友人は気になったようだった。
「ああ、いつものこったよ。」
「ホントに何か飛んで来たんじゃないか?」
冗談半分だろう、もう一人の友人がカーテンを開けた。そこには吹き込んだ雪が貼り付いたガラス戸と、赤い手形が付いていた。それは雪が溶けるように透明に変わりながら流れ落ちて行った。
「何が飛んで来たんだ?」
「知るかよ。」
慌てた様子でカーテンを閉める友人に、俺はそれしか言えなかった。
(了・手形)
風の強い夕方だった。身を縮めて歩く歩道に等間隔で生える街路樹はすっかり葉を落としていて、強い風に枝を揺さぶられるだけだった。早く帰って熱い風呂にでも浸かりたかったが、交差点の信号に止められた。無視してしまおうかとも思ったが、まだ車通りがある。足を止めて恨めしい思いで空を見上げる。雲が広がっていた。すぐに暗くなって、雪が降り出しそうだ。視線を地上に戻す瞬間一際強い風が吹いた。一層大きく街路樹の枝が揺れるが、その中に揺れずにいるものがあった。他が風よけになっているのか、偶然そこだけ風が入らなかったのか、どうでも良かった。早く帰ろう。
翌朝、地方紙に交通事故の記事が載った。俺が足止めを食らった交差点で横断歩道を渡っていた女性が轢かれて重体らしい。時刻は丁度俺が家に辿り着いた頃になっていた。運転手の証言として「青信号だったし、直前まで見えなかった。」と書かれていた。あの枝の隙間で揺れずにいた何かと関係あるのだろうか。何れ俺には確認のしようもない。
(了・北風と悪魔)
炬燵に首まで入ってテレビを見ていると姉に悪戯をされる事がある。足をくすぐられたり、引っ張られたり。今日はやたら力が強かった。
「ちょっと、痛いってば。」
振り払うように炬燵から体を半分出した。
「どったの?」
リビングに入って来た風呂上りらしい姉が歯ブラシをくわえたまま言う。母は台所で洗い物をしている。父はまだ帰って来ていないし、他には家族もペットも家にはいない。慌てて炬燵からはい出た。覗き込んで見る勇気は、今のところ無い。
(了・誰?)
我が家には幽霊が居る。はっきりと姿を見た事は無いが、恐らく女性だろうと思う。珈琲を淹れようと思えば勝手に瓶が開く。風呂に入ろうとすると勝手に扉が開いて、タオルも用意される。朝になれば米が炊かれていて、目玉焼きも出来あがっている。一つ困る事があるとすれば、酒瓶が開かない事だ。
「呑み過ぎですよ。」
耳元で囁く声が聴こえる。それはそうだろうが、少しぐらい許容して貰いたいものだ。
(了・貴方好み)
少女、だろう。日本人形のような和服だが、袷が逆で色も白い。安アパートの誰かも知らない人の部屋の玄関口に立ち、ふっとこっちをみて、微笑む。可愛らしい、と思うべきだろう。そんな容貌だった。翌日、少女が微笑んでいた部屋の人間が死んだ。自殺なんてそれ程驚く事じゃない。悩みや投げ出したい事なんか幾らでもある。不思議と気になったのはそんな時に必ずその少女が居る事だ。今も。俺の部屋の前に居る少女に、俺は何を言えば良いのだろう?
(了・次の獲物)
玄関先に小さな雪だるまがあった。はてと思う。確かに悪戯好きな従姉が来る予定はあったが、未だ少し先の筈だ。空を見上げる。滔々と雪が落ちる。そういえば、産まれる事のなかった兄か姉が居たな。苦笑して鍵を回す。今更、何でもない話か。
(了・雪だるま)
少しばかり山間に入った辺りにある家に婿入りした。俺は次男だし、実家には何となく馴染めなかった。冬に入ると平地でも雪が降る地方だ、こんな場所なら早くから雪が降り積もり、氷柱を垂らす。始めての迎える冬のその寒さに俺はやや閉口していたが、
「なぁ。」
「なぁに?」
嫁に問い掛けた。納屋の隅、垂れ下がった氷柱が赤黒く染まっている。
「ああ、あれ? 納屋は古いままだからねー、サビとかペンキじゃない?」
そんなものだろうか。
「ま、ひい爺ちゃんが死んだトコでもあるけど。」
平然と言ってのける嫁と、全く気にする様子の無い家族を見て、どうもここにも馴染めないかも知れないな、と思った。
(了・赤)
其れは純白の花だった。真っ白な少女が俺に向かって差し出して居る。頭の先から足の先まで白いのに、その眼だけは蒼かった。
「いつまで?」
高い、玲瓏な声で問い掛けて来る。意図は全く解らなかった。
「すっかり寒くなったねぇ。」
恋人にはこの少女が見えていないようだった。
「今年もマフラー編んであげるね。」
去年の秋の終わり。編み物が得意な彼女は、俺の好み通り青い色の毛糸でマフラーを編んで呉れた。
「うん。そうしよう。去年のは、捨てよう。毎日巻いてくれたからすっかり解れちゃったもんね。」
彼女が其れで良いのなら、其れで良いだろう。
「それでお別れ、ってのは、多分無理だけど。」
零れる涙を拭えない。俺にはもう彼女に触れる手が無い。
「いつまで、認めないつもり?」
白い花が冷たい風に揺れた。
「それじゃ、また来るね。」
彼女は涙を拭いながらふらふらと立ち上がった。線香の匂いがする。
「貴方が認めれば、後はその花が導いてくれる。」
雪が降り始めた。花と同じ、真っ白な雪。何時も違うのは、まるで道のように雪が降らない場所がある事だった。白い花を見詰める。俺ももう、次の場所へ行くべきなのだろうか。
(了・北風の鎮魂歌)
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


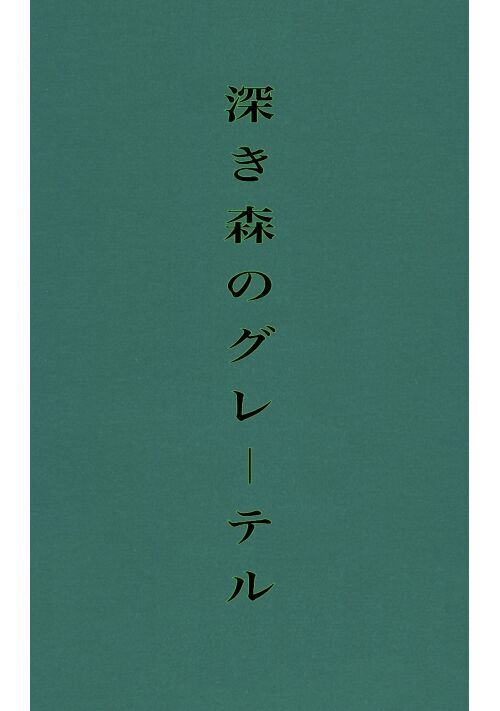
深き森のグレーテル
週刊 なかのや
ホラー
新米刑事の朝羽 花菜は、殺人鬼の岬 浩二を追っていた。
現場周辺が包囲されている中、追われた殺人鬼は濃霧に包まれた樹海に入り朝羽達も追った。
視界が晴れない状況で先輩刑事と共に捜索していると、一瞬の隙を突かれ朝羽は岬に人質として捕まったが……


ダルマさんが消えた
猫町氷柱
ホラー
ダルマさんが転んだの裏側には隠された都市伝説があった。都市伝説実践配信者の頬月 唯は実際に検証しその日を境に姿をくらましてしまう。一体彼女の身に何が起きたのだろうか。



ランダムチャット
ぷるぷぺ
ホラー
彼女いない歴=年齢の俺が(高校生2年生)出会いを求めてランダムチャットをする。
とても気が合う女の子と仲良くなりリアルで出会う事になった、その女の子はアニメに出てくるヒロインなみに可愛くすぐさま告白し付き合う事になったのだか、、、この時の俺は彼女がどれほど恐ろしいのか知る由もなかった。
恋愛×サイコホラー×エロの内容を入れた作品です!!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















