お気に入りに追加
4
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

淫らな蜜に狂わされ
歌龍吟伶
恋愛
普段と変わらない日々は思わぬ形で終わりを迎える…突然の出会い、そして体も心も開かれた少女の人生録。
全体的に性的表現・性行為あり。
他所で知人限定公開していましたが、こちらに移しました。
全3話完結済みです。

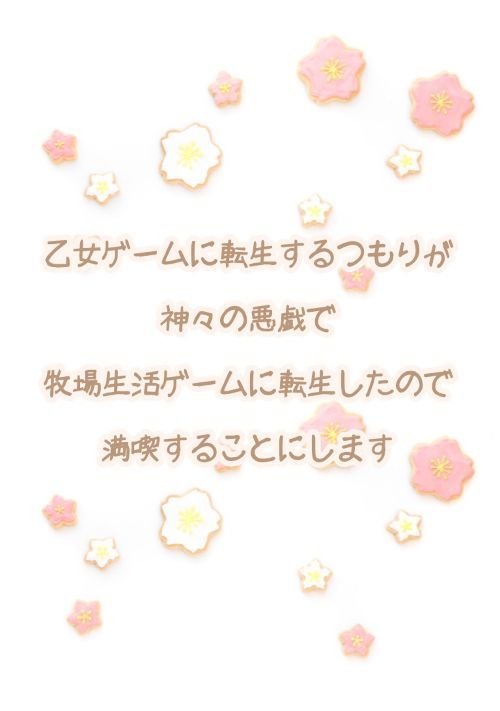
乙女ゲームに転生するつもりが神々の悪戯で牧場生活ゲームに転生したので満喫することにします
森 湖春
恋愛
長年の夢である世界旅行に出掛けた叔父から、寂れた牧場を譲り受けた少女、イーヴィン。
彼女は畑を耕す最中、うっかり破壊途中の岩に頭を打って倒れた。
そして、彼女は気付くーーここが、『ハーモニーハーベスト』という牧場生活シミュレーションゲームの世界だということを。自分が、転生者だということも。
どうやら、神々の悪戯で転生を失敗したらしい。最近流行りの乙女ゲームの悪役令嬢に転生出来なかったのは残念だけれど、これはこれで悪くない。
近くの村には婿候補がいるし、乙女ゲームと言えなくもない。ならば、楽しもうじゃないか。
婿候補は獣医、大工、異国の王子様。
うっかりしてたら男主人公の嫁候補と婿候補が結婚してしまうのに、女神と妖精のフォローで微妙チートな少女は牧場ライフ満喫中!
同居中の過保護な妖精の目を掻い潜り、果たして彼女は誰を婿にするのか⁈
神々の悪戯から始まる、まったり牧場恋愛物語。
※この作品は『小説家になろう』様にも掲載しています。

今夜は帰さない~憧れの騎士団長と濃厚な一夜を
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
ラウニは騎士団で働く事務官である。
そんな彼女が仕事で第五騎士団団長であるオリベルの執務室を訪ねると、彼の姿はなかった。
だが隣の部屋からは、彼が苦しそうに呻いている声が聞こえてきた。
そんな彼を助けようと隣室へと続く扉を開けたラウニが目にしたのは――。

お母様が国王陛下に見染められて再婚することになったら、美麗だけど残念な義兄の王太子殿下に婚姻を迫られました!
奏音 美都
恋愛
まだ夜の冷気が残る早朝、焼かれたパンを店に並べていると、いつもは慌ただしく動き回っている母さんが、私の後ろに立っていた。
「エリー、実は……国王陛下に見染められて、婚姻を交わすことになったんだけど、貴女も王宮に入ってくれるかしら?」
国王陛下に見染められて……って。国王陛下が母さんを好きになって、求婚したってこと!? え、で……私も王宮にって、王室の一員になれってこと!?
国王陛下に挨拶に伺うと、そこには美しい顔立ちの王太子殿下がいた。
「エリー、どうか僕と結婚してくれ! 君こそ、僕の妻に相応しい!」
え……私、貴方の妹になるんですけど?
どこから突っ込んでいいのか分かんない。

外では氷の騎士なんて呼ばれてる旦那様に今日も溺愛されてます
刻芦葉
恋愛
王国に仕える近衛騎士ユリウスは一切笑顔を見せないことから氷の騎士と呼ばれていた。ただそんな氷の騎士様だけど私の前だけは優しい笑顔を見せてくれる。今日も私は不器用だけど格好いい旦那様に溺愛されています。

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?
gacchi
恋愛
13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。
そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて
「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」
もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?
3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。
4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。
1章が書籍になりました。

【完結】何んでそうなるの、側妃ですか?
西野歌夏
恋愛
頭空っぽにして読んでいただく感じです。
テーマはやりたい放題…だと思います。
エリザベス・ディッシュ侯爵令嬢、通称リジーは18歳。16歳の時にノーザント子爵家のクリフと婚約した。ところが、太めだという理由で一方的に婚約破棄されてしまう。やってられないと街に繰り出したリジーはある若者と意気投合して…。
とにかく性的表現多めですので、ご注意いただければと思います。※印のものは性的表現があります。
BL要素は匂わせるにとどめました。
また今度となりますでしょうか。
思いもかけないキャラクターが登場してしまい、無計画にも程がある作者としても悩みました。笑って読んでいただければ幸いです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















