34 / 56
第3章 秋
第7話 大雨
しおりを挟む
その日の椎谷の里は朝から大雨だった。地面に当たる雨音が屋敷の中まで響き渡っていた。それはまるで葵姫を里に留めようとしているかのようだった。今日は葵姫の迎えの者が来ることになっていた。だがいつまで待ってもその者たちは現れなかった。
「この雨では迎えの方は来られないかもしれぬ。いや、こちらに向かわれて途中で道に迷っておられるかもしれぬ。」
百雲斎はつぶやいた。その一行を迎えるため、葵姫や紅之介は母屋に来ていた。迎えの者が来るというのに葵姫は華やかな着物姿ではなく、馬に乗る時の袴姿だった。一人で馬に乗って里への未練を捨てて、そのまますぐに麻山城に帰ろうというつもりか、それとも・・・。
紅之介と葵姫は一夜を共に過ごした。あれから朝になり、誰にも見られぬように葵姫は自分の寝所に戻った。そして今、2人が母屋で顔を合わせた時、お互いに恥ずかしそうに微笑んだ。それは愛を交したという2人だけの秘密を持ったからだった。よく見れば2人の様子はいつもと違う・・・だが周りの者はそれに気づかなかった。
葵姫と紅之介は何気なく横に並んで座っていた。じっと外の雨を眺めているふりをしながら、誰にも見られぬようにそっと手を重ねていた。互いに声をかけることはなかったが、たまに顔を見合わせて微笑んでいた。2人はお互いの心の中がわかり、愛を確かめたことで心に落ち着きがあった。たとえ別れることになったとしても、この愛の心だけは持ち続けていけると信じていた。
外では雨がひどくなっていた。ごうごうと風が鳴り、落ちてくる雨粒も激しくなった。これでは外を歩くのさえ難儀である。たとえ迎えの者が来ても葵姫を送り出すことはできない。葵姫が城へ帰るのは延期しなければならないだろう。
「今日は無理かもしれぬ。いやこの雨ではしばらくお帰りが伸びるかも・・・」
空を見て百雲斎が独言した。彼は天気のことを外したことがない。長くこの地にいて経験的にわかっているのだ。その言葉を聞いて、葵姫と紅之介は別れの日が延びたことに少し安堵していた。
「しかしひどい雨じゃ。山道で迷っておられぬとよいが・・・」
百雲斎はいつまでも到着せぬ一行のことが心配になっていた。雨で道がわからなくなって、そこから逸れてしまったら山奥をさまようことになる。百雲斎は紅之介に命じた。
「すまぬが紅之介。見て来てくれぬか。迎えの方々が途中で難儀しているかもしれぬ。」
「はっ。では行ってまいります。」
紅之介はそう答えるとそのまま出て行った。その後ろ姿を葵姫は優しい目でじっと見ていた。それは昨日までの葵姫の様子と違っていた。愛する者を見送るしぐさであった。また紅之介も戸を開ける時、そっと葵姫に目線を合わせた。
百雲斎はそれに気づくどころではなかった。どうにもならぬ事態にため息をついて葵姫に言った。
「姫様。申し訳ありませぬ。少し延びるかもしれませんが、必ず城には戻れますぞ。ご安心ください。」
「ええ、いえ。気にしておりません。」
葵姫は微笑みながら答えた。その心の中では
(このまま迎えが来なければいいのに。このままずっと・・・)
と思っていた。
大雨の中を紅之介は山道に馬を走らせた。その道は水につかったり崩れたりしており、その途中にある川は増水し、橋は所々流されていた。こんな雨が降るのは数年ぶりか・・・いやこれほどまで激しい雨を経験したことがないのかもしれない。何とか今は道を通れぬことはないが、これ以上激しくなれば椎谷の里に通じる道はすべて潰れ、孤立してしまうかもしれない。紅之介は向こうの山の雲の状態を見た。
(この分では明日まで降り続く。当分、止むことはない・・・)
それは紅之介にもわかった。とにかくこの分では迎えの一行は引き返しているかもしれない。
(これではお迎えの方々はしばらく来られぬ。それなら・・・いやいや、そうではない!)
紅之介は気を引き締めて、もう少し辺りを見て回ろうとした。急に何か嫌な予感を覚えたのだ。しばらく馬を走らせてみた。すると何かの音が遠くから聞こえてきた。馬を止めてふと耳をすませば、雨の音に交じって人の叫び声、怒鳴り声、悲鳴が入り混じって聞こえてきた。
(この近くで戦? 一体、誰が戦っているのだ?)
紅之介はその声がする方に馬を進めた。
紅之介がさらに馬を進めて山嶽を越えていくと、行く先々で鎧を着た兵の屍が転がっていた。この辺りまで戦が広がったらしい。紅之介は馬から降りて、その近くに打ち捨ててある旗印を拾った。
(これは東堂家の旗印!)
紅之介は目を見開いて驚いた。信じたくはないがこの様子から見ると、万代の兵に御屋形様の軍勢がさんざんに打ち破られていたように思われた。幸いそこには万代の兵は姿を現さなかったが、すでに近く来ていることは確かだ。もしかすると万代勢がその勢いに乗じて椎谷の里にも押し寄せるかもしれかった。
「一刻も早く頭領様にお知らせしなければ・・・」
紅之介は急いで馬に飛び乗ると、椎谷の里に走らせた。
「この雨では迎えの方は来られないかもしれぬ。いや、こちらに向かわれて途中で道に迷っておられるかもしれぬ。」
百雲斎はつぶやいた。その一行を迎えるため、葵姫や紅之介は母屋に来ていた。迎えの者が来るというのに葵姫は華やかな着物姿ではなく、馬に乗る時の袴姿だった。一人で馬に乗って里への未練を捨てて、そのまますぐに麻山城に帰ろうというつもりか、それとも・・・。
紅之介と葵姫は一夜を共に過ごした。あれから朝になり、誰にも見られぬように葵姫は自分の寝所に戻った。そして今、2人が母屋で顔を合わせた時、お互いに恥ずかしそうに微笑んだ。それは愛を交したという2人だけの秘密を持ったからだった。よく見れば2人の様子はいつもと違う・・・だが周りの者はそれに気づかなかった。
葵姫と紅之介は何気なく横に並んで座っていた。じっと外の雨を眺めているふりをしながら、誰にも見られぬようにそっと手を重ねていた。互いに声をかけることはなかったが、たまに顔を見合わせて微笑んでいた。2人はお互いの心の中がわかり、愛を確かめたことで心に落ち着きがあった。たとえ別れることになったとしても、この愛の心だけは持ち続けていけると信じていた。
外では雨がひどくなっていた。ごうごうと風が鳴り、落ちてくる雨粒も激しくなった。これでは外を歩くのさえ難儀である。たとえ迎えの者が来ても葵姫を送り出すことはできない。葵姫が城へ帰るのは延期しなければならないだろう。
「今日は無理かもしれぬ。いやこの雨ではしばらくお帰りが伸びるかも・・・」
空を見て百雲斎が独言した。彼は天気のことを外したことがない。長くこの地にいて経験的にわかっているのだ。その言葉を聞いて、葵姫と紅之介は別れの日が延びたことに少し安堵していた。
「しかしひどい雨じゃ。山道で迷っておられぬとよいが・・・」
百雲斎はいつまでも到着せぬ一行のことが心配になっていた。雨で道がわからなくなって、そこから逸れてしまったら山奥をさまようことになる。百雲斎は紅之介に命じた。
「すまぬが紅之介。見て来てくれぬか。迎えの方々が途中で難儀しているかもしれぬ。」
「はっ。では行ってまいります。」
紅之介はそう答えるとそのまま出て行った。その後ろ姿を葵姫は優しい目でじっと見ていた。それは昨日までの葵姫の様子と違っていた。愛する者を見送るしぐさであった。また紅之介も戸を開ける時、そっと葵姫に目線を合わせた。
百雲斎はそれに気づくどころではなかった。どうにもならぬ事態にため息をついて葵姫に言った。
「姫様。申し訳ありませぬ。少し延びるかもしれませんが、必ず城には戻れますぞ。ご安心ください。」
「ええ、いえ。気にしておりません。」
葵姫は微笑みながら答えた。その心の中では
(このまま迎えが来なければいいのに。このままずっと・・・)
と思っていた。
大雨の中を紅之介は山道に馬を走らせた。その道は水につかったり崩れたりしており、その途中にある川は増水し、橋は所々流されていた。こんな雨が降るのは数年ぶりか・・・いやこれほどまで激しい雨を経験したことがないのかもしれない。何とか今は道を通れぬことはないが、これ以上激しくなれば椎谷の里に通じる道はすべて潰れ、孤立してしまうかもしれない。紅之介は向こうの山の雲の状態を見た。
(この分では明日まで降り続く。当分、止むことはない・・・)
それは紅之介にもわかった。とにかくこの分では迎えの一行は引き返しているかもしれない。
(これではお迎えの方々はしばらく来られぬ。それなら・・・いやいや、そうではない!)
紅之介は気を引き締めて、もう少し辺りを見て回ろうとした。急に何か嫌な予感を覚えたのだ。しばらく馬を走らせてみた。すると何かの音が遠くから聞こえてきた。馬を止めてふと耳をすませば、雨の音に交じって人の叫び声、怒鳴り声、悲鳴が入り混じって聞こえてきた。
(この近くで戦? 一体、誰が戦っているのだ?)
紅之介はその声がする方に馬を進めた。
紅之介がさらに馬を進めて山嶽を越えていくと、行く先々で鎧を着た兵の屍が転がっていた。この辺りまで戦が広がったらしい。紅之介は馬から降りて、その近くに打ち捨ててある旗印を拾った。
(これは東堂家の旗印!)
紅之介は目を見開いて驚いた。信じたくはないがこの様子から見ると、万代の兵に御屋形様の軍勢がさんざんに打ち破られていたように思われた。幸いそこには万代の兵は姿を現さなかったが、すでに近く来ていることは確かだ。もしかすると万代勢がその勢いに乗じて椎谷の里にも押し寄せるかもしれかった。
「一刻も早く頭領様にお知らせしなければ・・・」
紅之介は急いで馬に飛び乗ると、椎谷の里に走らせた。
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

肩越の逢瀬 韋駄天お吟結髪手控
紅侘助(くれない わびすけ)
歴史・時代
江戸吉原は揚屋町の長屋に住む女髪結師のお吟。
日々の修練から神速の手業を身につけ韋駄天の異名を取るお吟は、ふとしたことから角町の妓楼・揚羽屋の花魁・露菊の髪を結うように頼まれる。
お吟は露菊に辛く悲しいを別れをせねばならなかった思い人の気配を感じ動揺する。
自ら望んで吉原の遊女となった露菊と辛い過去を持つお吟は次第に惹かれ合うようになる。
その二人の逢瀬の背後で、露菊の身請け話が進行していた――
イラストレーター猫月ユキ企画「花魁はなくらべ その弐」参加作。

抜け忍料理屋ねこまんま
JUN
歴史・時代
里を抜けた忍者は、抜け忍として追われる事になる。久磨川衆から逃げ出した忍者、疾風、八雲、狭霧。彼らは遠く離れた地で新しい生活を始めるが、周囲では色々と問題が持ち上がる。目立ってはいけないと、影から解決を図って平穏な毎日を送る兄弟だが、このまま無事に暮らしていけるのだろうか……?


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

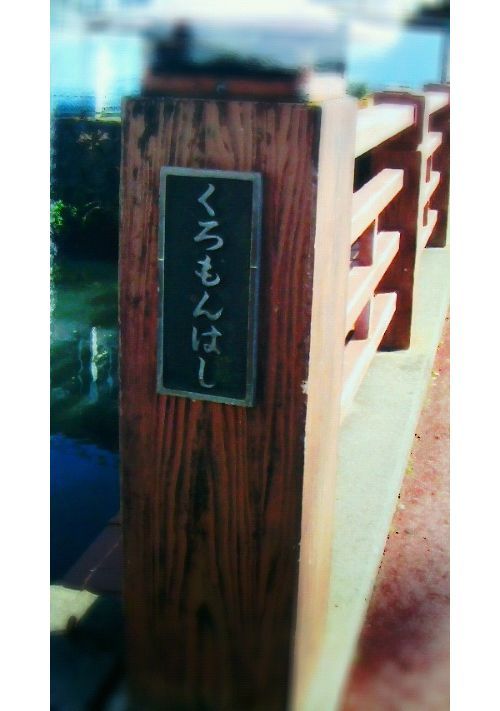
肥後の春を待ち望む
尾方佐羽
歴史・時代
秀吉の天下統一が目前になった天正の頃、肥後(熊本)の国主になった佐々成政に対して国人たちが次から次へと反旗を翻した。それを先導した国人の筆頭格が隈部親永(くまべちかなが)である。彼はなぜ、島津も退くほどの強大な敵に立ち向かったのか。国人たちはどのように戦ったのか。そして、九州人ながら秀吉に従い国人衆とあいまみえることになった若き立花統虎(宗茂)の胸中は……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















