お気に入りに追加
24
あなたにおすすめの小説

日本一のイケメン俳優に惚れられてしまったんですが
五右衛門
BL
月井晴彦は過去のトラウマから自信を失い、人と距離を置きながら高校生活を送っていた。ある日、帰り道で少女が複数の男子からナンパされている場面に遭遇する。普段は関わりを避ける晴彦だが、僅かばかりの勇気を出して、手が震えながらも必死に少女を助けた。
しかし、その少女は実は美男子俳優の白銀玲央だった。彼は日本一有名な高校生俳優で、高い演技力と美しすぎる美貌も相まって多くの賞を受賞している天才である。玲央は何かお礼がしたいと言うも、晴彦は動揺してしまい逃げるように立ち去る。しかし数日後、体育館に集まった全校生徒の前で現れたのは、あの時の青年だった──
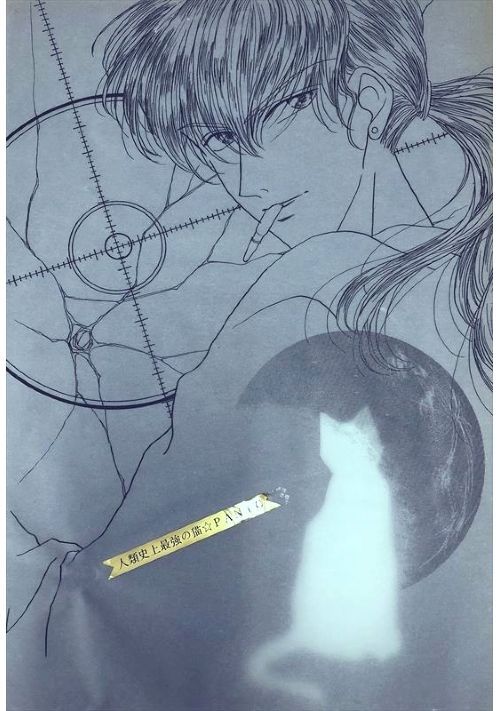
【完結】帝王様は、表でも裏でも有名な飼い猫を溺愛する
綾雅(要らない悪役令嬢1/7発売)
BL
離地暦201年――人類は地球を離れ、宇宙で新たな生活を始め200年近くが経過した。貧困の差が広がる地球を捨て、裕福な人々は宇宙へ進出していく。
狙撃手として裏で名を馳せたルーイは、地球での狙撃の帰りに公安に拘束された。逃走経路を疎かにした結果だ。表では一流モデルとして有名な青年が裏路地で保護される、滅多にない事態に公安は彼を疑うが……。
表も裏もひっくるめてルーイの『飼い主』である権力者リューアは公安からの問い合わせに対し、彼の保護と称した強制連行を指示する。
権力者一族の争いに巻き込まれるルーイと、ひたすらに彼に甘いリューアの愛の行方は?
【重複投稿】エブリスタ、アルファポリス、小説家になろう
【注意】※印は性的表現有ります

家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!
灯璃
BL
家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。
何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。
仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。
思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。
みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。
※完結しました!ありがとうございました!

【完結】運命さんこんにちは、さようなら
ハリネズミ
BL
Ωである神楽 咲(かぐら さき)は『運命』と出会ったが、知らない間に番になっていたのは別の人物、影山 燐(かげやま りん)だった。
とある誤解から思うように優しくできない燐と、番=家族だと考え、家族が欲しかったことから簡単に受け入れてしまったマイペースな咲とのちぐはぐでピュアなラブストーリー。
==========
完結しました。ありがとうございました。

黄色い水仙を君に贈る
えんがわ
BL
──────────
「ねぇ、別れよっか……俺たち……。」
「ああ、そうだな」
「っ……ばいばい……」
俺は……ただっ……
「うわああああああああ!」
君に愛して欲しかっただけなのに……

幼馴染は僕を選ばない。
佳乃
BL
ずっと続くと思っていた〈腐れ縁〉は〈腐った縁〉だった。
僕は好きだったのに、ずっと一緒にいられると思っていたのに。
僕がいた場所は僕じゃ無い誰かの場所となり、繋がっていると思っていた縁は腐り果てて切れてしまった。
好きだった。
好きだった。
好きだった。
離れることで断ち切った縁。
気付いた時に断ち切られていた縁。
辛いのは、苦しいのは彼なのか、僕なのか…。

【完結・BL】DT騎士団員は、騎士団長様に告白したい!【騎士団員×騎士団長】
彩華
BL
とある平和な国。「ある日」を境に、この国を守る騎士団へ入団することを夢見ていたトーマは、無事にその夢を叶えた。それもこれも、あの日の初恋。騎士団長・アランに一目惚れしたため。年若いトーマの恋心は、日々募っていくばかり。自身の気持ちを、アランに伝えるべきか? そんな悶々とする騎士団員の話。
「好きだって言えるなら、言いたい。いや、でもやっぱ、言わなくても良いな……。ああ゛―!でも、アラン様が好きだって言いてぇよー!!」

【第1章完結】悪役令息に転生して絶望していたら王国至宝のエルフ様にヨシヨシしてもらえるので、頑張って生きたいと思います!
梻メギ
BL
「あ…もう、駄目だ」プツリと糸が切れるように限界を迎え死に至ったブラック企業に勤める主人公は、目覚めると悪役令息になっていた。どのルートを辿っても断罪確定な悪役令息に生まれ変わったことに絶望した主人公は、頑張る意欲そして生きる気力を失い床に伏してしまう。そんな、人生の何もかもに絶望した主人公の元へ王国お抱えのエルフ様がやってきて───!?
【王国至宝のエルフ様×元社畜のお疲れ悪役令息】
▼第2章2025年1月18日より投稿予定
▼この作品と出会ってくださり、ありがとうございます!初投稿になります、どうか温かい目で見守っていただけますと幸いです。
▼こちらの作品はムーンライトノベルズ様にも投稿しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















