10 / 44
第一幕 事件
10 園枝家主催の夜会にて2
しおりを挟むトワが去って、しばらくの間、桜子は一人で腰掛けに座っていた。腰掛け、と言っても、洋風庭園に合うような、瀟洒なデザイン。
桜子の位置からは、植栽のちょうど向こう側に、盛り上がる会場が見えていた。
園枝有朋は、主催者らしく、あちらこちらと会場内を縦横無尽に動き回り、色々な人たちと挨拶を交わしている。
しかも、その合間に、男たちから、「娘の相手を」と託され、ダンスを踊っている。
有朋が、一度、女性の手を取り踊りだすと、華やかさに会場中の視線を独占する。
桜子の父は、中心からやや離れた場所で、誰かと話していた。
あれは……
(……樹兄さん?)
どうやら、相手は東堂樹らしい。いつも和服の樹が、珍しく燕尾服。一瞬、見間違えたのかと思った。
「樹兄さまも、いらしていたのね……。」
呟いた瞬間。
「桜子さん?」
背後から、名を呼ばれ振り向く。
「藤高……少尉。」
藤高貢が、植栽の向こう、木の陰から現れた。
「こちらにいたんですね。探しました。」
「探していた? 私を……ですか?」
「えぇ。いらしているはずなのに、見当たらなかったので。」
貢は、長身を持て余すように、頭上の枝を掴んで、足元の花壇をヒョイッと乗り越えた。
「なぜ私を探していたのか、お聞きしても?」
「勿論、踊るためですよ。」
貢は、桜子の質問が愚問だとでも言いたげに、即答した。
「藤高少尉が、私と踊るのですか?」
「そりゃあ、そうしたほうがいいでしょう?」
「なぜでしょう?」
さっきから聞いてばかりいる。この人との会話は、根本的に噛み合わない気がする。
「皆の前で踊ったほうが、私が貴女の有力な婚約者候補だと、周囲に認知させることができるでしょう?」
あぁ、やっぱり。聞くんじゃなかった。
馬鹿にされてる?
ううん、違う。
馬鹿にするほど、桜子への関心はない。
藤高貢にとっては、湖城家の令嬢との婚約が大事なのであって、桜子個人は、どうでもいいのだ。
桜子は、震えそうになる手を、ギュッと掴んだ。
こんなことで動揺してはダメ。
この人がこういう考えだってことは、先日お会いして、分かっていたじゃない。
「しかし、こんなところに一人でいるなんて。貴女は、狙われている自覚がないのか? あの男は、どうしているんだ。」
貢は、ブツブツ呟きながら、桜子のほうと歩み寄る。と、いきなり桜子の腕を取った。
「ひッ!」
思わず叫び声が、小さく漏れる。
「い……いきなり女性の腕を掴むなんて、ぶ……無礼です……!」
貢は、全く気にしている様子もなく、
「戻りましょう。まぁ、あの男がいなくとも、私が側にいれば問題ない。」
「あの……は……ッ!!」
ーーー離してッ!
叫びそうになった瞬間、
「僕なら、ちゃんといますよ。」
桜子の腕を掴む貢の、その腕を、新伍が掴んでいた。いつもの四方八方に散らばる散切り頭ではなく、きちんと整髪されている。
「五島さん……!」
「ちょっと遅くなりました。」
新伍が、桜子に向かって、微笑んだ。その顔で、ホッと心が緩んだ。
新伍は、貢のほうを向いて、
「さて、桜子さんは足を痛めているようです。少し休憩が必要でしょう。休んでから、僕が中へお送りしますよ。」
「足を?」
「慣れない靴のせいです。僕が代えの靴を預かってきましたので、会場で少しお待ちいただけますか?」
桜子を掴む貢の手が緩んだ。
「わかりました。ダンスは、会場で、もう一度、申し込みましょう。そのときは、受けてくれますね?」
踵を返し、会場の方へと消えていった。
貢がいなくなると、新伍が、
「さて、大丈夫ですか?」
外套の内側から、靴を取り出した。外套の下は、皆と同じ燕尾服。
「靴!? 本当にお持ちくださったんですね。」
「座ってください。」
「えっ?! 五島さん……が、履かせてくれる…のですか?」
戸惑いと恥じらいで、顔が熱くなったが、
「いえ、イツさんが一緒に来ていますよ。」
どこからともなく、イツが「お嬢さまッ!!」と、現れ、駆け寄る。
「足は、大丈夫ですか?」
桜子が座ると、傍らに屈んで、靴を脱がせた。出掛けに、どの靴にするのかで、イツと意見が相反したことを思い出し、
「あなたの言う通り、慣れている靴にすれば良かったわ。」
「新しい靴は、また今度にしましょう。何回か履いて練習すれば、馴染みます。………あら? 足の指、痛めてしまいましたね。手当されました?」
「えぇ。さっき、園枝家の女中さんがしてくれたのよ。」
「痛くありませんか? お薬をお持ちしましょうか?」
「大丈夫よ。」
そんなことを話しているうちに、あっという間に、靴は替え終わった。
「それでは、私はこちらを持って帰りますので。」
時津が送ってくれたのだという。
「分かったわ。よろしくね。」
イツがいなくなると、新伍と二人になった。夜会の喧騒が庭木の向こうから聞こえている。
「足は、まだ痛みますか?」
「平気です。もう、ダンスだって踊れますよ。」
履き慣れた靴は、さっきよりも踵が低く、足に馴染んでいて、柔らかい。新伍に向けて、足をトントンと鳴らしてみせた。
「試しに踊ってみますか?」
どうせ、会場に戻ったら貢に誘われるのだ。皆の前で申し込まれたら、断ることは出来ない。それなら、ここで、一旦、練習しておくのもいいかなと思ったのだが、
「結構です。」
新伍が珍しく逃げ腰に後ずさった。
「五島さん?」
「私は、踊れませんので……。」
「えっ!そうなんですか?」
意外だ。
初対面から、いつも余裕の表情ばかり見せてきた新伍にも、苦手なことがあるなんて。
「簡単ですよ。ホラ、手を取って、」
「い……いいですよ、僕は!!」
桜子は嫌がる新伍の前に立つと、構わず、右手を新伍の右上に重ね、左手を新伍の肩に乗せる。
「手は腰へ。」
新伍の手を取って、自分の腰に回した。
「それで、こう……踊るんです。」
まっすぐ伸ばした右手を波のようにユラ、ユラ、ユラ。今度は反対に左手を伸ばして、ユラ、ユラ、ユラ。
「足は適当に動かしてください。私の足を踏まないように。」
新伍は、最初のうちは、「うわっ!」「うをっ!」と、ぎこち無く動いていたが、すぐに、慣れて、桜子の足を踏まないようにトントンと跳ねるように踊った。多分、器用な質なのだ。
正しいダンスとは程遠いけれど、結構楽しい。
「あの……これ、合っていますか?」
「全然、合ってないです。」
「………。」
「………ふふふふふ。」
可笑しい。自然と笑いが込み上げてきた。
二人は、ガス灯の柔らかな明かりに包まれていた。
しばらく踊ったところで、どちらからともなく踊るのをやめる。
「………もう、戻りますね。」
「そうですね。藤高少尉がお待ちでしょうし。」
(藤高少尉……)
心の底に燻っている不安を解消するために、念を押した。
「あのっ!! 藤高……少尉は、本当に、あの恋文の人ではないんですよね?」
「違いますね。」
新伍がきっぱりと否定した。
「字を見たでしょう? 筆跡が全く違う。今、桜子さんの周りにいる方の筆跡は、時津さんやイツさんもを始めとする使用人の方も含め、一通り確認しましたが、該当する人はいませんでした。」
「………分かりました。」
「そんなに構えなくても、大丈夫ですよ。僕も、会場の隅から見ていますから。」
新伍がそういうなら、大丈夫だろう。大丈夫だ、と思える。
会場に戻って、藤高貢踊る。
それが、夜会にでた湖城の娘としての役目。
会場に戻ると、早速、貢が寄ってきた。
「湖城桜子さん、一曲、お相手よろしいですか?」
慇懃な申し込み。桜子も令嬢として応じた。手を取られ、会場の中央へ。
貢は、なんの情感もない、正確無比なダンスを踊った。
いきなり手首を掴まれたときは、背筋が粟立ったが、こうして、儀礼的に相対すれば、そこまでの嫌悪感はなかった。
新伍のおかげ……なのかもしれない。
貢が終わると、今度は園枝有朋が待ち構えていた。
「ようやく、皆さんとの挨拶が終わりまして。」
洗練された仕草で、恭しく腰を折った。
「桜子さん、私とも一曲、お相手願えますか?」
貢と踊った以上、同じ婚約者候補の有朋の誘いを断るわけには、いかない。
足はーーー靴を代えたおかげで、大丈夫そうだ。
「はい。お願いいたします。」
有朋のダンスは、上手かった。
桜子を巧みに導いて、踊りやすい。それでいて、見目華やかなので、彼が踊りだすと、皆が注目する。
桜子は、こんなにも人に見られながら踊るのは、初めてだった。
「桜子さんは、上手ですよ。だから、皆が見てるんです。」
有朋が、パチリと片目を瞑る。と、グイッと腰を引き寄せて、小声で、
「見せつけてやりましょう。」
大人の男性の艶と華。
慣れていない桜子は、色気を当てられて、ドキマギしてしまう。この人が、女性に人気があるのが、わかる気がする。
父の側に戻ってくると、今度は、東堂樹に声をかけられた。
「桜子ちゃん、お疲れさま。」
「樹兄さん!」
やはり、こういう場所でも、見慣れた樹の顔を見るとホッとする。
「足も痛いだろう? 僕とのダンスは、今日はお預けかな。」
流石に樹は気づいていたらしい。
正直、樹の提案は有り難く、桜子も、できたら、そうしたい。だけど……貢や有朋同様、樹も桜子の婚約者候補だ。
あの二人だけと踊ることで、事実上、樹は選外なのだ、とは思って欲しくなかった。
「大丈夫です。少しだけなら。」
桜子は、樹の腕を取った。ダメダメと首を振って、逃げようとする樹に、
「行きましょう!」
「で……でも……」
「ほら、早く。」
樹は優しいけれど、断ることが苦手だ。強気に押し切られたら、駄目だと言えない、その性格を熟知している桜子は、強引に腕を引っ張った。
樹は、小さい時から、桜子の練習相手。上手いとか、下手だとか、そういう次元の関係性ではない。勝手知ったる樹との踊りは、他の二人よりもずっと、楽だった。
「さすが、桜子ちゃん。上手だね。」
「樹お兄さまこそ。」
樹との踊り方は、身体が覚えている。変な力が入っていないせいか、足の痛みも全く気にならない。
桜子の身体に馴染んだ相手。
でも、一番楽しかったのはーーー
踊りながら、視線の先には、ガス灯に照らされた庭。そして、壁際にもたれ、会場内に隈なく視線を巡らす、真っ黒い髪の………。
桜子は、慌てて、頭を振った。
(何を考えているのっ?!)
私の婚約者候補は、この三人なのに………。
私が何を思おうと、三人の中の誰かと、私は、遠からず、婚約を結ぶのに。
0
お気に入りに追加
111
あなたにおすすめの小説

紙の本のカバーをめくりたい話
みぅら
ミステリー
紙の本のカバーをめくろうとしたら、見ず知らずの人に「その本、カバーをめくらない方がいいですよ」と制止されて、モヤモヤしながら本を読む話。
男性向けでも女性向けでもありません。
カテゴリにその他がなかったのでミステリーにしていますが、全然ミステリーではありません。


若月骨董店若旦那の事件簿~水晶盤の宵~
七瀬京
ミステリー
秋。若月骨董店に、骨董鑑定の仕事が舞い込んできた。持ち込まれた品を見て、骨董屋の息子である春宵(しゅんゆう)は驚愕する。
依頼人はその依頼の品を『鬼の剥製』だという。
依頼人は高浜祥子。そして持ち主は、高浜祥子の遠縁に当たるという橿原京香(かしはらみやこ)という女だった。
橿原家は、水産業を営みそれなりの財産もあるという家だった。しかし、水産業で繁盛していると言うだけではなく、橿原京香が嫁いできてから、ろくな事がおきた事が無いという事でも、有名な家だった。
そして、春宵は、『鬼の剥製』を一目見たときから、ある事実に気が付いていた。この『鬼の剥製』が、本物の人間を使っているという事実だった………。
秋を舞台にした『鬼の剥製』と一人の女の物語。
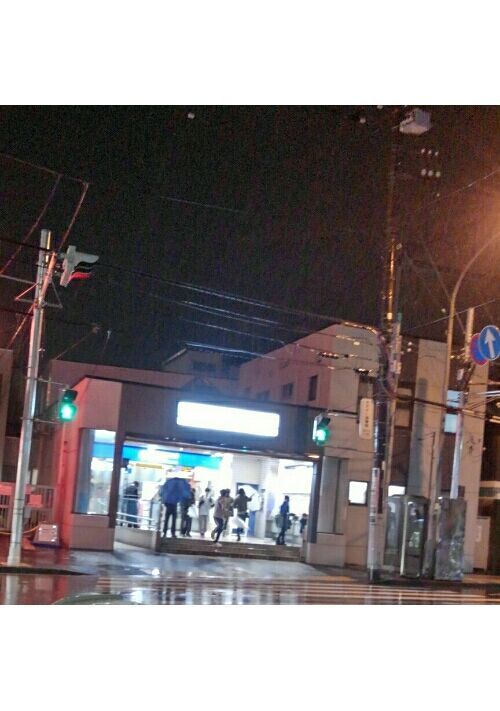

【R15】アリア・ルージュの妄信
皐月うしこ
ミステリー
その日、白濁の中で少女は死んだ。
異質な匂いに包まれて、全身を粘着質な白い液体に覆われて、乱れた着衣が物語る悲惨な光景を何と表現すればいいのだろう。世界は日常に溢れている。何気ない会話、変わらない秒針、規則正しく進む人波。それでもここに、雲が形を変えるように、ガラスが粉々に砕けるように、一輪の花が小さな種を産んだ。

マクデブルクの半球
ナコイトオル
ミステリー
ある夜、電話がかかってきた。ただそれだけの、はずだった。
高校時代、自分と折り合いの付かなかった優等生からの唐突な電話。それが全てのはじまりだった。
電話をかけたのとほぼ同時刻、何者かに突き落とされ意識不明となった青年コウと、そんな彼と昔折り合いを付けることが出来なかった、容疑者となった女、ユキ。どうしてこうなったのかを調べていく内に、コウを突き落とした容疑者はどんどんと増えてきてしまう───
「犯人を探そう。出来れば、彼が目を覚ますまでに」
自他共に認める在宅ストーカーを相棒に、誰かのために進む、犯人探し。

この満ち足りた匣庭の中で 二章―Moon of miniature garden―
至堂文斗
ミステリー
それこそが、赤い満月へと至るのだろうか――
『満ち足りた暮らし』をコンセプトとして発展を遂げてきたニュータウン、満生台。
更なる発展を掲げ、電波塔計画が進められ……そして二〇一二年の八月、地図から消えた街。
鬼の伝承に浸食されていく混沌の街で、再び二週間の物語は幕を開ける。
古くより伝えられてきた、赤い満月が昇るその夜まで。
オートマティスム、鬼封じの池、『八〇二』の数字。
ムーンスパロー、周波数帯、デリンジャー現象。
ブラッドムーン、潮汐力、盈虧院……。
ほら、また頭の中に響いてくる鬼の声。
逃れられない惨劇へ向けて、私たちはただ日々を重ねていく――。
出題篇PV:https://www.youtube.com/watch?v=1mjjf9TY6Io

獣人の里の仕置き小屋
真木
恋愛
ある狼獣人の里には、仕置き小屋というところがある。
獣人は愛情深く、その執着ゆえに伴侶が逃げ出すとき、獣人の夫が伴侶に仕置きをするところだ。
今夜もまた一人、里から出ようとして仕置き小屋に連れられてきた少女がいた。
仕置き小屋にあるものを見て、彼女は……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















