2 / 2
これでも青春だ、知らんけど ~後編~
しおりを挟む
前編からのつづき。
「これでも青春だ、知らんけど ~後編~」
学食のテーブルに三人の男が座っていた。草野校長と森教頭と年配の白髪の男性である。時間は十三時二十分。昼休みは十二時四十分から十三時三十分までのため、あと十分ほどで昼休みは終わる。そのため、生徒たちはすでに食べ終えて、教室に戻っていた。
しかし、たった一人だけ、食堂の隅でうどんをすすっている男子生徒がいた。特別にバイトの許可をもらって、昼休みに学食で皿洗いのアルバイトをしている宮井である。家が貧しい宮井は、月曜日から金曜日までこの学食で皿洗いをし、賃金として千円をもらい、まかないとして、うどんかそばを一杯もらっているのである。今日のまかないはネギがたっぷり乗ったキツネうどんであった。学食の大森店長が気を使って大盛にしてくれている。
うどんを食べ終えた宮井が、器を返却して、三人の元へやって来た。
「教頭先生、ご無沙汰してます」頭を下げる。
「おお、宮井くんか。最近会ってなかったね。元気にやってるかい?」教頭はうれしそうに顔を向ける。
「はい。せっかく教頭先生にお世話してもらったバイトですから、休まずに働いてます」
「ほう、がんばってるね。お母さんの具合はどうかね?」母の体調を気遣ってくれる。
「はい。元気にパートを掛け持ちして働いてます」
「六人の弟くん達も元気かい?」
「はい、みんな元気です。僕と違って、よく勉強する優秀な弟たちです」
「ほう、そうかね。君が社会人になって、家にたくさんお金を入れられるようになったら、少しは楽ができるねえ」
「はい。僕たち兄弟はみんな年子ですから、毎年、一人ずつ、どんどん社会人になって、どんどん家にお金を入れて、どんどん裕福になって、ついには豪邸を建てる予定です。これが僕たち宮井家の夢です」
「ほう、すごいね。夢が叶うといいね。また何か困ったことがあったら、いつでも相談に来なさいよ。これからもがんばってね」
「はい、ありがとうございます」
宮井は教頭に深々と頭を下げて、教室に帰って行った。学食には三人が残った。自分に頭を下げてくれなかった校長はブスッとして、恥ずかしさを誤魔化すように、自慢のヒゲに手をやっている。白髪の男性は事情がよく分からず、困惑した表情を浮かべていた。ただ、校長と教頭は仲が悪そうだと感じた。
ときどき、校長と教頭は学校の食堂で昼食を食べる。いつも出前のウマイ寿司を食べているわけではない。学食を利用するのは、生徒とのコミュニケーションを取りたいらしいのだが、当然、誰も近寄って来ない。生徒に人気のある教頭にだけ、数人が挨拶をして通り過ぎて行くだけだ。校長なんて眼中にない。学校における校長と教頭の存在なんてそんなものだ。
今日は学食で食事をした後に、一人の男性と話をすることになっていた。目の前に座っている年配の男性がそうである。
今年から竜巻高校は社会人入学を受け入れることになっていた。彼がその第一号である。名前を大久保田といい、年齢は六十六歳である。背は高く、スリムで、髪は豊かだが、真っ白になっている。落ち着いた柔和な表情を浮かべている。
三人でカレーライスのウェルカムランチを終えた。ウェルカムと言っても、三人はそれぞれ自分でお金を出して、食券を買ったのである。校長と教頭のどっちが新入生に奢るかで、大いに揉めたからで、結局、自腹を切ってもらったらいいという結論になり、名ばかりのウェルカムランチになったのである。校長も教頭も自分のためならお金は払う。ましてや、お互いに相手を出し抜くためなら、金に糸目は付けない。しかし、他人のためにはケチに徹する。そもそも新入生といっても、自分たちよりも年上なのである。なぜ、年上の人にご馳走をしなければならないのか。このことで二人は三十分も議論を重ねたのである。
だが、三人は無事にカレーライスを食べ終えた。そこへ学食の店長がやって来た。
「食器をお下げいたします」
学食はセルフサービスになっていて、食べ終えた器は各自が片付けるのだが、校長と教頭に気を使って、下げに来たのである。
「ああ、これは大森店長。さっき、バイトの宮井君に会いましたよ。がんばってるようですね」教頭が声をかける。
「はい。真面目に働いてもらってます。さすが、教頭先生が推薦された生徒ですね。こちらから何も言わなくても、自分からテキパキと動いてくれます」
「大森店長がまかないを大盛にしてくれてるそうですね」
「いや、大したことはありませんよ。ネギを多めに入れるとか、天かすを山盛りにする程度です。育ち盛りなのに宮井君は痩せてますからね。たくさん食べてもらわないと」
「いつもありがとうございます」教頭は頭を下げるが、校長は店長から自分に挨拶がないため、またブスッとして、自慢のヒゲに手をやっている。
育ち盛りだから、たくさん食べてもらいたいと言いながら、サービスしてるのはネギと天かすか? どれだけセコいんだと、校長は自分のセコさを棚に上げて、頭の中で批判している。
「では、失礼します」大森店長は食べ終えた三つのカレー皿を持って行った。
だが、すぐに戻って来た。
「食後のコーヒーでございます」マグカップを三つ並べ始める。
「いや、悪いねえ」校長がお礼を言うが、
「一杯、二百円でございます」
「なに! 金を取るのかね!?」校長の声が裏返る。
「はい。もちろんでございます。こちらも商売ですから」大森店長は平然と答える。
自販機の缶コーヒーは百二十円だぞ。子供向けのキャラクターが描かれたマグカップに入ったインスタントコーヒーが二百円かね。どれだけセコいんだと、またもや自分のことを棚に上げて、校長は頭の中でブツクサ文句を言う。
三人はそれぞれ二百円ずつ払い、マグカップコーヒーをズルズルと飲み始めた。
「カップはここに置いておいてください。後ほど取りに来ますから」
大森店長は六百円を握り締めて、厨房に戻って行った。
校長は六十六歳の新入生に話し掛けた。簡単な挨拶はすでに済ませてある。
「ご苗字は大久保田さんと言うのですか。変わってますね」
新しく高校一年生になるといっても、校長よりも年上であり、用務員の岡戸と同い年である。よって、敬語を使っている。
「大久保さんという苗字はありますし、久保田さんという苗字もよく聞きますが、二つ合わせたような大久保田さんという方には初めて会いましたよ」
大久保田は説明を始める。
「もともと、先祖は大久保姓でした。大久保姓ばかりの人たちが村を作って住んでいたそうです。隣には久保田姓の人たちの村がありました。あるとき、村の境界線のことで争いが起こり、大久保村が久保田村を襲撃したそうです。村に火を放ち、焼き尽くし、村人を次々に襲い、皆殺しにし、半日で全滅させたそうです。それで、大久保村が久保田村を吸収合併して、大久保田村になったそうです」
「そんな歴史がありましたか。それは驚きました」校長が目を丸くする。「村人を皆殺しとは恐ろしいですね」
「子どもからお年寄りまで、殴ったり、刺したり、斬りつけたりして、村人全員を殺した後は、首を全部切り離して、村の広場に並べ、勝利の証とし、最後は火をつけて燃やしたそうです。胴体はそのまま埋めたのですが、焼却後に残った頭蓋骨は大久保田村の入口に山積みにして、村のランドマークのようにしていたそうです」
「そんな気味の悪いことを、やさしそうな顔でよく語れますね」
「苗字の由来はよく訊かれますからね。そのたびにこの皆殺しの話をしてますよ。その村はもう消滅したそうですが、困った先祖ですよ。ははは」
「子孫のあなたに祟りはありませんか」
「そんなものはありません。ときどき寝ているときに首が締め付けられるように苦しくなって、夜中にハッと目が覚めますよ。ははは」
「それは祟りじゃないですか。供養した方がいいのではないですか。私がいいお寺を紹介しますよ。私の紹介でしたら、格安で引き受けてくれますよ」
「大久保田さん」隣で聞いていた教頭が強引に割り込んだ。
校長が紹介しようとしているのは、諏訪一大寺の星輝和尚だと察知したからだ。あんな生臭坊主に供養されたら、祟りが倍増して、大久保田さんは夜中にポックリ死んでしまうに違いない。私が適当にナンマイダとお経を上げた方が余程効果があるだろう。
「失礼ながら、お年は六十六歳ですね」教頭が質問する。
大久保田は、テレビでよく見る人気芸人と同い年だとうれしそうに言ったが、その芸人よりもかなり老けて見える。頭髪は白いし、シワも多く、腰も曲がっている。
「社会人入学ですが、我々は二十代前半くらいの人を想定していたのですよ。何かの事情で高校に行けなかった人を支援しようということです」教頭が困惑気味に言う。
「私は経済的理由で進学を諦めたのですが、この年になって、学びたいとう意欲がふつふつと沸いて来まして、応募させていただきました次第です」大久保田はハキハキ話す。
「ほう。そう事情があったのですか。大久保田さんの入学は、うちの生徒への刺激にもなると思います。ぜひ、がんばってください」
「私の年齢からすると、彼らは子供というより、孫のようですが、学問以外にも、今の流行りとか、若者言葉とか、いろいろなことを学びたいと思います」
「いろいろとクラブ活動がありますよ」教頭だけが話を続ける。
校長に話をさせたら何を言い出すか分からないからだ。
「私は手芸部に入りたいと思ってます」
「手芸部ですか!? 確かにうちの高校にありますが」
「私は編み物が趣味でして、セーターでもマフラーでも手袋でも編むことができますよ。ときどきフリマに出品して、ちょっぴり売れてます」
「手芸部は三人の女子が所属してますので、話しておきます。大久保田さんは手芸部唯一の男子生徒になりますね」
「はい。がんばって編みますよ」
竜巻高校には一年に一回、登山研修という行事がある。登山というと、マラソン大会、ぎょう虫検査、練誠会に続いて嫌われている行事のように思われるがそうではない。登る山が低く、ほとんど丘のようであり、登山というよりもピクニックだからである。生徒と付き添いの先生たちは午前中を使ってブラブラと頂上を目指し、午後の時間を使ってブラブラと戻ってくるという楽チンな行事である。しかも、その小さな山は学校のすぐ裏にあり、わざわざバスに揺られて行く距離ではなく、これまたブラブラ歩いて行って、ブラブラ帰って来れるからである。一日、丘で遊んで授業をサボるようなものである。
しかし、こんな楽しそうな行事を欠席する生徒たちもいた。スコット山田をリーダー、チャーリーをサブリーダーとする竜巻高校の七人のヤンキー集団である。理由はヤンキーには自然も汗も似合わないからだという。今頃は七台のバイクで市内を走り回っていることだろう。
天気は快晴で言うことなし。といっても、この山登りが苦痛に思える人物がいた。ラッパー安藤である。授業中にラップを歌っていて、英語の酒井先生に半殺しにされた安藤だったが、性懲りもなく、また授業中に踊ってしまったのだ。
前回は東北の三つの祭――盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、青森ねぶた祭りを踊って怒られたのだが、今回は先生のご機嫌を取ろうと、仙台・青葉まつりの中で踊られる“仙台すずめ踊り”を、持参した手作りウチワを持って、ソレソレと踊ったのだ。しかし、これも先生にとって逆効果のようだった。またもや、バカにされたと解釈されてしまったのだ。
「すずめを舐めるんじゃねえ!」
ふたたびキレた酒井先生が、容赦なく教卓に蹴りを入れた結果、前回と同じように安藤は滑って来た教卓と窓ガラスに挟まれて、瀕死のすずめのようになり、また足の骨にヒビが入ってしまっていたのだ。
「安藤君、今度の登山研修はどうするのかな?」数日前、酒井先生が優しく訊いた。
「足がこの通りですから、欠席します」足にギプスをはめている。
「たかが骨のヒビくらいで学校の大事な行事を休むのかな?」
酒井がニコニコしながら安藤の目を見つめる。
「レントゲン撮ったら、三本のヒビが入ってまして……」
「……」酒井は決して視線を外さない。
「痛みがあって、昨日も寝れなくて……」
「……」笑っているだけに、返って恐ろしい。
「痛み止めの薬も効かなくて……」
「……」酒井の目の奥は笑ってない。
「お母さんにも休むように言われたし……」
「……」目の奥にあるのが本性だ。
「お医者さんも安静にしておくようにと……」
「……」黙って安藤の返事を待つ。
「たった今、痛みが消えました!」
「そうでしょう。病は気からよ」
よって、安藤は松葉杖をついての参加である。
しかし、酒井先生も鬼ではない。安藤の介添えとして、ラグビー部の玉本と足立を付き添いにしてあげたのだ。歩けなくなったら、持参した担架で運んであげろということである。歩けなくなるまで歩けということでもあるのだが、担架を持参しての登山研修は全国でも珍しい試みだろう。二度もキレてしまった酒井先生はまだ元に戻りそうにない。
先頭を歩くのは草野校長であり、そのすぐ後ろを森教頭が追いかけている。こんなところでも、二人は張り合っているのである。ついさっきまでは森教頭が先頭だったのだが、ほどけた靴のヒモを結んでいる間、校長に追い抜かれたのである。そして今、教頭は抜き返そうと必死の形相で歩いている。
特に険しい道というわけでもなく、高低差がほとんどない平坦な山道なのだが、二人のお年寄りにはちょっとしんどい。
校長はこの日のために、登山用の杖=トレッキングポールを新調してきた。二本セットになったアルミ製の三段伸縮の銀色のステッキである。このステッキを校長・教頭室のパソコンからネット注文をしているのを、教頭は目ざとく見つけ、校長がいなくなったときに、注文履歴からこの商品を特定し、どうしても負けたくない教頭は、カーボンファイバー製の五段伸縮の金色の防水仕様の収納袋も付いた一番いいやつを買い求めたのである。
そして、二つの商品は同日同時刻の宅配便で校長・教頭室に届いた。箱を開封してお互いのトレッキングポールを比較した瞬間、教頭が勝ち誇ったような顔をしたのを、校長は見逃さなかった。
トレッキングポールは左右の手に一本ずつ持って使う。二本を同時に使って歩いた方がバランスを取りやすいからである。
「校長、トレッキングポールの調子はいかがですか?」後ろから教頭が訊いてくる。
「ああ、調子はいい。膝にかかる負担も軽減されとるからな」
「私のトレッキングポールも調子がいいですよ。何といってもカーボン製ですからね。まあ、軽い、軽い。おまけに丈夫とくれば、カーボン製しかないでしょうなあ。――校長のポールは何でできてましたか?」知っているのに、わざと訊いてくる。
「これはアルミ製だが」校長は悔しがるが、「いくらいい道具を持っておっても、使う人がヘナチョコなら何の意味もなかろう」果敢に言い返す。
ヘナチョコ呼ばわりされた教頭はいきなりスピードを上げて、校長を追い抜きにかかる。
校長も抜かれてたまるかとばかりに、スピードを上げる。教頭の長い足に負けじと、校長は短い足をフル稼働させて、トップの座を譲らない。二人の脇でトレッキングポールが前後にビュンビュン揺れている。
まだまだ若い者には負けんと校長は心の中で叫ぶ。こんな年寄りには負けんと教頭は心の中で叫ぶ。年齢は一歳しか違わないというのに。
校長と教頭の歩いた跡にはたくさんの足跡と、たくさんのポールが刺さった跡が点々と続き、砂煙と落ち葉が舞っている。
二人のゼエゼエという死にそうな息切れに驚いたリスが一目散に逃げて行く。お互い相手を打ち負かそうとして、周りは見えていない。前から来る登山客があわてて道を譲り、今のオヤジたちは何だと振り返る。二人はたちまち他の生徒たちを引き離し、やがて、豆粒のように小さくなっていった。
「相変わらず、あの二人はバカだ」「あんな大人になりたくないな」
生徒たちは冷静である。反面教師とはこのことであった。そんな中、生き物係の二人、犬井と鳥谷は多忙を極めていた。登山の途中で見かける昆虫や咲いている花の名前を教えろと、生徒たちがうるさいのだ。
「お前らは生き物係だろう。こいつの名前くらい知っておけよ」と、木に止まっている見たこともないヘンテコリンな茶色い昆虫を指差して言う。
生き物係といっても、十二匹の鯉と一匹の犬しか飼育してない。迷い犬ポチは犬井の足元に座っている。犬井はポチの飼育主任である。ポチも登山研修に連れて来たのである。
女子からも声がかかる。
「この花は何という名前なの?」
「僕たちは生き物係だから」分かるわけない。
「お花だって生き物だよ」知ってて当然でしょ。
「それはそうだけど」花に詳しい男なんて珍しい。植物園の職員か植物学者くらいだろう。
「おい、鳥谷。あれは何という鳥だ?」
別の男子生徒が木に止まってる黒色と灰色が混ざった変な鳥を指差して、訊いてくる。
「分からないなあ」
「お前、鳥谷という苗字だろう。鳥に詳しくなくてどうするんだ」
「名前は関係ないだろ」鳥谷が言い返す。「お前なんて、デブのくせに苗字は細井じゃないか」
「そんなことを言うと、チビなのに高井君がかわいそうじゃないか」
「頭が悪いのに金田一君もかわいそうだよ」
「貧乏なのに金山君の立場もないぞ」
「美人なのに姫宮さんはどうなんだ?」
「それは合ってる」「確かに」
生徒が入り乱れているうちに、犬井はスマホの画像検索機能を使って、昆虫や花や鳥を撮影し、名前を調べ上げる。
「おお、さすが犬井君!」
みんなが犬井を取り囲む。一方、バカにされて腹の虫がおさまらない鳥谷は、見つけた五十センチほどのヘビを持って、生徒を追いかけ始めた。
そして、先ほど文句を言って来たデブの細井が追い付かれた。
「さっきはよくもバカにしやがったな!」
「おう、やれるもんならやってみろ!」
鳥谷が蛇を持って細井に近づいて行く。細井が木の幹に足を取られて尻もちをついた。鳥谷はすかさず目の前に蛇を持っていく。
「これはヒバカリという蛇だ。噛まれたら、その日ばかりの命。略してヒバカリと言うんだ」
「待ってくれ! ボクが悪かった。鳥に詳しくない鳥谷さんなんて全国に一万人くらいいるから、蛇をどけてくれ。まだ死にたくない。家には食べ残した食材がたくさんあるんだ」
やって来た犬井が鳥谷の横でニヤニヤして立っている。以前、ヒバカリは毒蛇だと思われていたのだが、今では毒のない蛇だと知られていて、大人しく、めったに噛み付くこともないことを知っているからだ。さすが生き物係だ。
鳥谷はヒバカリをそっと地面に置いた。ポチが驚いて逃げようとするが、ヒバカリは何事もなかったかのように、草むらの中へと入って行った。
「ああ、怖かったよう」デブの細井がのそっと立ち上がった。
生徒たちの喧騒を尻目に傍らの岩に座って、おにぎりを食べている男がいる。
やっぱり、山で自然に囲まれて食べるおにぎりは最高だ。普通に食べるよりも三倍はうまい。具は、梅干、昆布、おかか、鮭に明太子。なんでもうまい。いっそのこと、具がなくても塩だけでもうまい。登山で疲れた体には塩が合う。海苔もいらない。米だけでうまい。ああ、日本人に生まれて来てよかったなあ。明日、地球が滅びるとして、最後の晩餐はおにぎりにしたいね。おふくろの味だ。ソウルフードだ。シンプルイズベストだ。
男は水筒からお茶をラッパ飲みする。
――プハッ。ああ、お茶が合う。
やっぱり、おにぎりには日本茶だ。おふくろのお茶だ。ソウルドリンクだ。
山で食べる幸せに浸っていると、後ろから声をかけられた。
「まだ昼食の時間じゃないですよ、星輝和尚さん」
振り向くと、男子生徒が立っていた。
「おお、君は生徒会長の平井一郎君じゃないか。どうだい、君もおにぎりを食べるかい」
「いいえ、まだ十時ですから」
「そうだったかな?」
和尚さんは作務衣の袖を引っ張って、金色の高級腕時計を見る。
「おお、平井君の言う通り、わしのロレックスも午前十時だ。腹が減ったもんで、てっきり十二時半くらいだと思っておったのだよ。どうやら、私の腹時計は故障しているようだなあ」
「お昼ご飯は十二時からと決まってます。ちゃん規則を守ってください」
「さすがに生徒会長殿はルールに厳しいのう。だが、心配無用じゃ。まだおにぎりは五個残っておるし、お茶も半分残っとるわ」
水筒をブンブン振る和尚を残して、平井は仲間の元へ戻る。この和尚には何を言っても無駄だと思ったからだ。
なんで、こんな全身が煩悩のような人がお坊さんをやってるんだ? この人の辞書には戒律という文字はないのか?
それにしても、なぜ和尚さんが高校生の登山研修に来ているのか? まさか、生徒が滑落死したとき、すぐにお経があげられるようにか? 残念ながら、この山は滑落して命を落とすような険しい箇所はない。ならば、町内の慰安旅行と勘違いしてるのか?
平井の優秀な頭脳で考えても分からなかった。
川べりにたたずんでいる坊主頭は生徒会副会長の金森である。手を洗って、水を飲んでいる。話している相手は岡戸さんのようだ。手に虫取り網と虫かごを持っている。和尚さんもそうだけど、いったい用務員さんが、何のためにこの登山研修に参加しているのか? 二人を見下ろす平井は不思議がる。
「結局、二宮金次郎像には二度、追いかけられたよ」岡戸が恐ろし気な顔をして言う。
「本当に出たのですか?」金森は驚く。
「出たよ。この目で見た。たまたまそこにいたスコット山田君も一緒に見ているから、見間違いではないよ」
「えっ、スコット山田君がいたのですか?」
「彼は晴れて、我がゴーストバスターズの一員になったのだよ」
「あのヤンキーがそんな面倒な役をよく引き受けましたね」
「いい子だよ、彼は」金で雇ったとは言わない。
「それで、二宮金次郎はその虫取り網で捕獲できたのですか?」
「いいや。捕獲できておったら、私は今ごろマスコミに取り囲まれて、ヒーローになっておる。残念ながら素通りして行きおった。だが、二宮金次郎像を撤去する話はなくなったから、これからは彼も安心して走るだろうよ」
「やはり走るのですか?」
「そうだ。長生きするには足腰を鍛えないとダメだぞ、金森君。毎夜、走って足腰を鍛えておる二宮君は江戸時代からずっと生きておる。――おっ、蝶だ!」
岡戸は虫取り網を持って駆け出した。
「岡戸さん、もしかして、その蝶もゴーストですか!?」金森も後を追いかけて行く。
「いや、これは現実の蝶だ。昆虫を採集して、生き物係に売りつけるんだ。――ほら、見てみなさい」
岡戸は虫かごを示す。トンボとカナブンが入っている。
「ここに蝶を加えた昆虫三点セットで売りつけようと、私は企んでおるんだ。待て、蝶! 人間に逆らうんじゃない。こりゃ、すばしっこいのう。それっ!――よしっ、捕まえた!」
「その昆虫三点セットはいくらで売れるんですか?」
「せいぜい、虫かご込みで八百円だろう。だが、心配には及ばん。ここまでは準備運動だ。狙いはこんな昆虫ではなく、鳥だ。――いたぞ! オオルリだ。これはキレイだ」岡戸が見上げる。
青色と白色の小さな鳥が木の枝に止まっている。見た目が美しく、青い鳥御三家の一つであり、鳴き声も美しく、日本三鳴鳥の一つでもある。
「つまり、彼女は鳥業界で二冠を達成しておる」
「野鳥を捕獲してもいいんですか?」
「オオルリはダメさ。密漁に決まっているだろう」
どこまで本気なのか分からない。
「だがな、オオルリは一羽七千円で売れるんだ」
岡戸が振り回す虫取り網で捕まるドジな野鳥はいないだろう。せいぜい、弱った昆虫だ。それに、オオルリを捕まえたところで、生き物係の二人は買い取ってくれるのか? 学校で飼育してもいいのか? ダメだろうな。生き物については素人の僕にでも分かる。岡戸さんは逮捕されて、新聞に載るだろうし、学校も強制捜査されるだろう。
草野校長と森教頭はお互いに負けじと張り合って歩いているうちに疲れ果て、たどり着いた広い場所の真ん中にある石の上に座り込んでいた。歩き出してすぐ、痛みが膝に来て、腰に来て、背中に来て、両腕に来て、頭に来て、二人して歩く気力が奪われてしまったのである。
「教頭先生、なかなかやるじゃないか」
「校長先生こそ、お達者ですな」
ゼエゼエ言いながら、お互いを褒めたたえる。仲がいいのか悪いのか分からない。昨日の敵は今日の友だ。強敵と書いて友と読むようなものだ。二人仲良く、水筒の水をゴクゴク飲む。そのとき、前方からお揃いの黄色いジャージを着た集団がやって来た。
「ほう、雷電高校の生徒たちですなあ」教頭が首を伸ばして確認する。
校長も立ち上がる気力はなく、首だけを伸ばして、確認する。
「おお、そうだな。彼らも今日登っておったのか」
雷電高校は竜巻高校のライバル校である。
眺めているうちに、竜巻高校の生徒たちも後ろから追い付いて来た。両校の生徒と先生たち約三百人ずつ、合計六百人が山の中腹にある広場で対峙する。
ちょうど真ん中に竜巻高校の校長と教頭がいる。普段から仲の悪い両校の一触即発の状態を仲裁するため、自ら中央に進み出たのではなく、たまたまここで疲れて休んでいたら、挟まれただけである。まだのんびりと水筒を片手に座っている。
好き勝手に私服を着て来た竜巻高校と違って、黄色いジャージで統一した雷電高校の生徒の集団が、モーゼが割った海のように割れて、真ん中に道ができた。その道に十人ほどの生徒にかつがれた御神輿のような物が出現した。二本の大きな木に渡された神輿の部分に豪勢な椅子が設置されている。その椅子に座っていたのは、雷電高校の花桐理事長であった。神輿の横には西見校長が従っている。
「やあ、草野校長と森教頭じゃないか!」下々を見下ろしている理事長がデカい声で叫ぶ。「そんなところで、なぜ油を売っておるのかね?」
雷電高校の生徒は、どうだうちの理事長はすげえだろうという顔を向けて来る。竜巻高校の生徒は、なんだこの神輿ジジイは、モーロクしたのかという顔を向けてやる。
仕方なく、二人は立ち上がる。
「理事長」草野校長が見上げる。「それは一体何ですか?」
「見ての通り、人間神輿じゃわい。この年になると、小さな山とはいえ、登るのはしんどくてな。さすがのロールスロイスもここまでは登って来れん。かと言って、生徒たちとの触れ合いは大切にしたいんじゃ。というわけで、このように屈強な生徒諸君に神輿をかついでもらってるわけだ。――おお、中村先生じゃないか!」
竜巻高校の集団の中から中村を見つけたようだ。この理事長と気が合わなかったため、中村は雷電高校から竜巻高校へと左遷された。その恨みは今も忘れないでいる。
「これは理事長、ご無沙汰しております」
それでも、挨拶はちゃんと交わして、頭を下げる。
「少し小耳に挟んだのだが、君は竜巻高校にサッカー部を作ろうとしておるらしいのう」
「はい」中村は御神輿に近寄り、理事長を見上げる。「いずれ、そちらのサッカー部とも対戦する機会がやって来ると思います。そのときはお手柔らかにお願いします」
お手柔らかにと言ったが、心の中では叩きつぶしてやると思っている。
「ほう。この中途半端な時期によく部員が集まったな」
「いえ。まだ十一人は揃っておりません」
それを聞いた雷電高校の生徒は笑い転げる。
「十一人いないんじゃ、九人で野球をやればいい」「九人もいないんじゃないのか」「六人だったら、スリーエックススリーのバスケができるじゃん」「六人も集まってないんじゃない」「じゃあ、一人で相撲部でも始めればいい」
それを聞いた竜巻高校の生徒は悔しがる。中村先生がサッカー部員を集めていることは知っているが、集まってないことも知っているからだ。
「中村先生。わしが乗っている人間神輿をかついでいる生徒を見なさい」
見覚えのある生徒たちだ。
「分かったかね。全員サッカー部なのだよ。その中でも精鋭の十一人なのだよ。この神輿は彼らの足腰の鍛錬も兼ねているというわけだ。これで登山研修をすると、けっこうキツイぞ。だが、彼らにとっては大したことでない」
確かに理事長をかついでいる生徒の足は丈夫そうで、みんな精悍な顔つきをしている。
「最低の人数十一人が揃ったら連絡をくれたまえ。サッカー部設立記念試合を開催してあげよう。どうしても揃わないようなら、女子も加えればどうかね。男女混合チームで戦えばよろしい」
ふたたび雷電高校の生徒は笑い転げる。中村は歯ぎしりをして悔しがる。
「さて、行くとするか!」理事長が右手をあげて、神輿の横にいる西見校長に指示を出す。「その山道を右折してくれるかね」
ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ。
人間神輿は雷電高校の生徒集団を引き連れて、広場の道をカチカチと音を立てて、右に曲がって行く。
理事長を乗せた神輿には、なぜか方向指示器が付いていた。
中村は悔しそうに神輿を見送った。
一方、竜巻高校はこの広場で昼食だった。
集まった生徒たちは雷電高校の悪口を言っている。
「言いたいことを言われて悔しいよな」
「黄色いジャージ集団なんて、ブルースリーオタクかよ」
「なんだ、あの神輿は。神様気取りかよ」
「あのタヌキ理事長の奴、男女混合サッカーだって、ひどいよな」
「サッカー部は中村先生が何とかしてくれるんじゃない。俺は園芸部だから無理だけど」
「俺も天文部だから無理だけど、早く部員が集まってほしいよな」
「それで雷電高校サッカー部を撃破すると」
「でも、あの名門に勝つなんて、草野球チームがプロ野球チームに勝つようなものだよな」
「小学生横綱が照ノ富士に勝つようなものだからなあ」
「AKBが乃木坂に勝つようなものだからなあ」
「微妙だな」
「まあ、長い人生には大逆転があるさ」
「そうだな。俺たちが歩んで来た人生はまだ短いからな」
「あんな変な連中は放っておいて、メシにしよう。――おお、みんな並んでるじゃん!」
広場の隅でお弁当が配られていて、すでに長い行列ができている。もちろん、午前中に早弁をしていた星輝和尚もちゃっかり並んでいるし、岡戸もトンボとカナブンと蝶が入った昆虫三点セットが入った虫かごを持って並んでいる。
「はい、お弁当ですよー。みんな並んでくださいよー」白い割烹着を着た年配の男性がお弁当を渡している。「お弁当を受け取ったら、隣でお茶も受け取ってくださいよー」
「はい、お茶はこちらですよー」同じく割烹着を着た年配の女性がペットボトル入りのお茶を手渡している。
「お茶はこちらにもありますよ」もう一人の黒と白の服を着た若い女性もペットボトルを手渡している。「はい、どうぞ」
生徒会長の平井と副会長の金森が木製ベンチに並んで座った。お弁当の包みをほどく。
「おお、ちらし寿司だ!」平井が思わず声をあげる。
「すげえ。トロにウニにイクラ……。こんな豪華なちらし寿司は初めて見た」金森も驚く。
「とりあえず、水分補給といきますか」平井はペットボトルを開けて、お茶を口にする。「でもな、なんでウマイ寿司の大将と女将がここまで出張って来て、ちらし寿司を配ってるんだ?」
「分からないね」金森はトロを口にして、つぶやいた。「お店の宣伝かもね。あるいは校長あたりが格安で準備させたんじゃないか」
「これ、三千円はするな」
「それを、あの校長が二千円くらいに値切りやがったんだよ」
「とんでもない校長だな。そんな学校の生徒会長が僕だもんなあ」平井がボヤく。
「副会長が僕だもんなあ」金森も同調する。
「おかしなことがもう一つある。女将の隣でお茶を配ってた若い女性は教会のシスターだったぞ」
「黒と白の修道服で登山している人を始めて見たわ。通販で買ったコスプレかと思ったが、あれは本物のシスターさんだな」
「娘にしちゃ、キレイだったな」
「あの二人の娘じゃないな。全然似てない。トンビがタカを生んだとは思えん。どういう関係か知らないが、慈善事業もシスターの活動の一つだからね」
「お茶を配るのも慈善事業というわけか」
「星輝和尚に用務員の岡戸さんにウマイ寿司の大将と女将に教会のシスターまで参加しているとは、変な登山研修だよな」平井もトロに齧り付く。「研修の趣旨がよく分からん」
「ちらし寿司がおいしいからいいことにしようや。ムシャムシャ」
「そうだな、ムシャムシャ」
午後はスマホの自撮り合戦になった。お腹も一杯になり、後は山を下りるだけなので、生徒たちも気楽で、先生たちも大目に見ている。被写体で人気があるのは、もちろん学校のマドンナだった。つまり、小久保“マドンナ”先生と、姫宮“マドンナ”生徒のダブルマドンナである。
「小久保先生、一緒に写真を撮ってください!」
「生き物係の犬井君ね。いいよ。ここに並んで」小久保は自分の隣を指差す。
「鳥谷、悪いけど、シャッターを押してくれ」犬井は自分のスマホを渡す。
「あら、犬井君、手に何を持ってるの?」
「ああこれですか。用務員の岡戸さんに買わされたトンボとカナブンと蝶の昆虫三点セットです」
「いくらで買ったの?」
「虫かご込みで八百円です」
「しょうがないオジサンだよね」
「生き物係ですから、大事に育てます。――鳥谷、シャッターを頼む」
「おお、まかせておけ!」
鳥谷は、犬井が小久保先生に気があることを知っている。
「お二人さん、もっと近づいて。いや、もっともっと。ピッタリと。ベッタリと。はい、犬井、ここで先生の肩に手を回して!」
「できるか!」
――カシャ!
犬井が顔を赤らめて叫んだ顔がバッチリ撮れた。
「鳥谷、殺すぞ、お前!」犬井が迫って来る。
「待て待て。生き物係として、命は大切にしよう」鳥谷がなだめる。
「ああ、そうだな。次は僕が撮ってあげるよ。マドンナ姫宮の所へ行こうや」犬井が誘う。
鳥谷は姫宮に気があるのだが、姫宮の前にはツーショット撮影の順番待ちの行列ができている。男子ばかりではなく、女子も並んでいる。姫宮は女子にも人気があるのだ。
「おいおい、ライバルが多いぞ。大丈夫か、我らの鳥谷君」犬井が茶化す。
「生き物が好きな人に悪い人はいないからね。その辺をアピールしてくるよ」
「昆虫三点セットを貸そうか?」犬井は虫かごを掲げる。
「いらない」鳥谷は即座に断る。「それを見ると岡戸さんの顔がチラつく」
「それは致命的だな」
小久保“マドンナ”先生に次いで美しい酒井“準マドンナ”先生の存在も忘れてはいけない。酒井先生は二度に渡って、ラッパー安藤をボコボコにしたが、クラス内で口止めがされていて、他のクラスの生徒たちは、相変わらず、酒井が青森県出身の大人しくて、真面目で、純朴な先生だと思い込んでいる。男子と女子、両方の生徒に人気があり、こちらも行列ができていた。しかし、担任をしているクラスの生徒は一人も近寄らなかった。酒井の正体を知っているだけに、恐ろしくて近寄れないのだが、あのクラスの子たちは、普段から会ってるから、今さら一緒に写真なんか撮らないのだろうとみんなは思い違いをしていた。
二人のマドンナと準マドンナに続いて人気があったのはシスターのマリー・アマーチェだった。白と黒の修道服は、山のてっぺんでは浮いてしまっているが、集まった生徒たちが人垣を作っていた。
普段、教会なんかに行かない生徒たちはシスターに会ったり、話をしたりしない。おまけに美人となると、興味津々なのだろう。
「シスター、僕と写真を撮ってください!」
「待て。俺が先だ!」
「何だと、シスターは俺が先に見つけたんだ」
「絶滅寸前の希少動物みたいに言うなよ」
「右の頬を打たれたら、左の頬を差し出せよ!」
「お前こそ、汝の敵を愛せよ!」
男子が揉めているうちに、女子がシスターを取り巻いた。
唖然とする男子。
「おいおい、女子は要領がいいよなあ」男子がボヤく。
「あんたたちがトロいだけでしょ」女子は余裕だ。
女子がシスターを囲んで集合写真を撮っている。大学を出たばかりの女性新任教師と生徒たちのように見える。各自のスマホを順番に受け取ってシャッターを切っているのは教頭であった。そんなことは生徒か、他の教師にやらせればいいのにと誰もが思うのだが、教頭も楽しそうなので任せることにした。こんな森教頭も生徒たちの人気者だった。
ここが嫌われ者の校長と違う所なのだよと、生徒に囲まれた教頭も満足げだ。ただ、シャッターを押すだけなのだが。
「はい。皆さん、写しますよー。笑って、笑って。シスターも笑ってくださーい!」
中央に立っていたシスターがVサインをして、叫んだ。
「イエーイ!」
――カシャ!
シスターもイエーイなんて言うのか!?
イエス様に許しを請うているのか?
一瞬、山の上は騒然としたが、また笑い声が戻った。
「平井君!」
呼ばれて振り返ると星輝和尚が立っていた。
「君が生徒会長だと見込んで頼みがある。御仏からのお願いだと思って聞いてほしい」
「はい、何でしょうか?」嫌な予感しかしない。
「わしもキレイな娘さんと写真が撮りたいんじゃ」
予感は当たった。嫌な予感は当たるものである。何とかの法則だ。それでも、平井は愕然とする。この和尚さんの体は煩悩でできているのか? 食欲の次は性欲か? 練誠会という行事も、金に目がくらんで引き受けたらしいから、金銭欲も旺盛だ。食欲、性欲、金銭欲。――三大欲望の揃い踏みだ。
だが、ニコニコ笑うタヌキ顔を見ていると、かわいそうにも思えてくる。
「では、僕が話を付けてきます」生徒会長として責任を果たしてあげよう。「見てみると、二人のマドンナとシスターに人気が集まっているようですが、どなたと撮りたいですか?」
「三人全員に決まっておろう。差別はいかん。御仏の下では、みな平等じゃ」
都合よく、仏を持ち出す。いつかバチが当たるだろう。
人のいい平井はタヌキ和尚のために、三人に声をかけて、撮影をセッティングしてあげた。
和尚は三人の美女に囲まれて、ヨダレがこぼれそうだ。
「はい、和尚さん。チーズ!」平井はシャッターを押してあげた。
和尚はこの世のモノとは思えないほどの眩しい笑顔をレンズに向けた。紺色の作務衣を着た和尚と、白と黒の修道服を着たシスターが同じ写真に入っている。シュールな光景だ。
「いやあ、三人のお嬢さん方、お忙しいところをどうも。三人に御仏のご加護のあらんことを。ナンマイダ~」
星輝和尚は手を合わせたが、三人のうちの一人はシスターであった。ナンマイダ~と言われたシスターは、どう返していいのか分からず、とりあえず胸の前で十字を切っていた。
アーメン。和尚さんにも神のご加護を。
和尚がニコニコ顔で平井の元にやって来た。
「ありがとう。これで何の迷いもなく、成仏できるよ」
平井は「それはよかったです」と答えたが、心の中では、そんな迷いだらけで、煩悩のかたまりのような人が成仏できるわけないでしょうと、たくさんの罵声を浴びせていた。
「平井君、実はもう一つ、頼みがあるんだが」
また嫌な予感がする。
「あのお二人も、三人のお嬢さんと写真が撮りたいと言っておるのだよ」
平井が振り向くと、定年間近の美術の野呂先生と社会人入学の大久保田が肩を組んで、ニコニコ笑いながら立っていた。
また嫌な予感は当たった。
二人は仲が良くて肩を組んでいるのではなく、疲れ切って、お互いを支え合っていたのだ。“人”という字がお互いを支え合っているようなものだ。低い山を登るといっても、五十九歳と六十六歳には大変だったようだ。
しかし、三人の美女と写真を撮るために、最後の力を振り絞って、ガクガクの膝で立っていたのである。煩悩のなせるワザであった。
両マドンナとシスターと違って、男子生徒が見向きもしなかったのが、保健室の主、アラフィフの美魔女佐藤恵子先生だった。
今日は登山のため、いつものボディコン白衣ではなく、深紅のボディコンジャージを着ての参加である。気合十分である。この広場にたどり着くまで、救急セットを持って、ケガ人はいないか、具合の悪くなった人はいないかと、登ってる学校関係者に訊いて回っていた。傍から見ると、保健室の先生が甲斐甲斐しく仕事をしているように見えたのだが、訊いて回る相手はすべて男子生徒と男性教師で、下心が丸分かりだったので、女子たちには白い目で見られていた。
「恵子先生はいい人なんだけどねえ」
「私たちの悩みも聞いてくれるのにねえ」
「保健師としての腕も確かなんだけどねえ」
「男に目がないのよねえ」
「男にだらしないのよねえ」
女子生徒の評判はさんざんである。あとは山を下りるだけなのだが、恵子先生は深紅のボディコンジャージ姿で、腰をくねらせながら、しつこく男子生徒と男性教師を追いかけ回して、顰蹙を買っていた。
「足は大丈夫かしら? 冷却スプレーを吹きかけてあげるわよ。サービスで、私の吐息も吹きかけてあげるわよ」
「熱中症には気を付けてね。具合が悪くなったら、木陰で休んでね。私の膝を枕の代わりに貸してあげるわよ。寂しいのなら、添い寝してあげるわよ」
「腰は痛くない? 湿布があるわよ。先生が心を込めて、貼って、あ・げ・る」
「すごい汗ね。普段から汗っかきだから大丈夫? ダメよ。私が汗を拭いて、あ・げ・る」
そんな恵子先生を見て、男性教師はいつものことだと思いながらも、私は大丈夫ですよ、どこも痛くありませんからと、うまくあしらっている。一方、男子生徒はというと、そんな社会人のような気の利いた芸当ができるわけもなく、ワーワー言いながら、本能で逃げ回っている。
気が付けば、恵子先生の周りに男子はいなくなっていた。
「おかしいわ。大き目のジャージを体の線がくっきり出るように加工して、深紅のボディコンジャージに仕上げて来たというのに、なぜ世の男性は私の魅力に気づいてくれないのかしら。男子高校生と言えば、性欲のかたまりのような存在よ。そんな子も逃げて行くって、どういうこと? それに、年上の女性に憧れる年頃のはずよ。あの子たちの母親よりも、ちょっぴり年上なだけじゃないの」
もう誰もいなくなった山の上に救急セットを持って、たった一人で呆然とたたずむ恵子先生。
「一学年は三百人、その半分の百五十人が男子生徒として、私は百五十人の男子プラス五人の男性教員から同時にフラれたことになる。ギネス級だ。――すごいじゃん、私!」
だが、こんなことで挫けるようなアラフィフの美魔女ではなかった。
手鏡を取り出して、顔を映してみる。
「あら、かわいい! 美しすぎる保健師だわ」
吹いて来る風が少しだけ、頬にやさしい。
「大丈夫。まだまだ地球上にはたくさんのオスがいるわ!――ヤッホー!」力いっぱい叫んでみる。
こだまは返って来なかった。
周りには声が反響する山がなかったからだ。
「こだまのバカヤロー!」
ちょうど真下を黄色いジャージを着た雷電高校の生徒たちが下山していた。奇妙な声を聞いて見上げる生徒に、恵子先生はいくつもの投げキッスを飛ばした。
「わっ、やまんばが出たぞ!」「昭和の妖怪だ!」「UMAだ!」
生徒は大騒ぎする。
そのうち生徒たちは石を投げだした。あわてて避難する恵子先生。神輿に乗った花桐理事長も何事かと、丘を見上げたが、美魔女の恵子先生が好みのタイプではなかったようで、嫌な物を見たような顔をして、すぐに目を逸らした。神輿は方向指示器をカチカチ点滅させながら、北の林の中へと消えて行った。
各自が山を下りて行く。登山研修はこれで終わりだった。結局、松葉杖をついていたラッパー安藤は、途中で足が痛くなって、歩けなくなり、ラグビー部の玉本と足立が持参していた担架に乗せられて、下山することになった。
当然だろう。足の骨に三本のヒビが入っていたのだから。
「あらかじめ担架を持って登山をするっておかしくないか?」玉本が言う。
「だって、酒井先生の命令だから」足立は諦めている。
「もう、あの先生には逆らえないな」
「正体があれだもんな」
「みちのくの妖怪」
「酒井先生の前では、ハイハイとイエスマンに徹することが身を守ることになるな」
「さもないと、こいつみたいに」足立は安藤を見下ろす。「半殺しにされる」
安藤は気持ちがよくなったのか、目を閉じたまま運ばれている。
「爆睡とは、いい気なもんだな。こんなことじゃ、棺桶を持ってくればよかったよな」と足立。
「おい、棺桶はないだろ!」安藤が目を開く。
「なんだ、起きてるのか?」
「ずっと起きてるわ!」
「ウソつけ。今、目が覚めたのだろうよ。――えいっ! これでも喰らえ!」
「待て! 揺らさないでくれ!」
玉本と足立が息を合わせて担架を揺らす。
「俺はケガ人なんだぞ!」
「何だ、偉そうに!」玉本が怒鳴る。
「いや、すまん。偉そうにしたお詫びと、担架で運んでくれているお礼に、俺の即興ラップを聞かせてやろう」
「聞いてくださいだろっ!」足立も怒鳴る。
「お二人さん、お聞きくださいませ。今から歌のスタンバイをさせていただきます」
安藤はしばらく目を閉じて、精神統一らしきものをした後、おもむろに歌い出した。
♪山を担架で下って行く~。山の中に担架があったんか~。僕はこんな担架に乗ったんか~。ラグビー部の二人がおったんか~。二人で担架を持ったんか~。お昼ご飯は喰ったんか~。この担架、どこで買ったんか~。
♪山を担架で下って行く~。僕の心は砕け散り~。お腹も痛くて下りそう~。だけど、くだらないケガ~。
上半身を動かせる安藤はリズムに合わせて、腕を振っているが、そのリズムはバラバラだ。担架で運んでいる玉本と足立には揺れて、うるさいだけだ。
♪行き着く先は天国か~。なんで下に天国がある~。上にあっても登れない~。だったら下ろう、どこまでも~。俺たち三人離れずに~。三人は運命共同体~。二人はラグビー部のスターだぜ~。YOYO!
あまりにもヘタで下らない歌のため、玉本と足立は担架を地面に放置して、脱兎のごとく、駆け出した。
安藤はむくりと上半身を起こす。
「おぉーい!」置き去りにされた叫びが、空しく山道に響く。「待てー、薄情者! お前ら、それでも健全たるアスリートかー!?」
「おーい、安藤。早く下りないと、夕暮れ時はクマが出るぞー!」振り返って玉本が叫ぶ。
もちろん、こんな丘にクマはいない。
野性の動物が出たとしても、せいぜいウサギかリスだ。
だが、「マジかよー!」と安藤はマジで信じる。
「クマは時速六十キロで走るぞー!」足立も叫ぶ。
「それは速い方なのかー!?」安藤も大声で尋ねる。
「ウサイン・ボルトは時速四十五キロだー!」
「クマ、速いじゃん! デブなのに速いじゃん! 四足だから速いじゃん! 足をケガしてなくても、追いつかれるじゃん! 僕の武器は松葉杖しかないじゃん! ラップを歌ってヒマはないじゃん!」
その後、どうやって安藤が下山したかは、誰にも分からなかったが、翌日はちゃんと学校に来ていたし、担架もラグビー部の部室に戻されていた。ただ、足の骨のヒビが三本から四本に増えたというウワサだった。
竜巻高校のヤンキー七人がバイクで街を疾走していた。先頭はハーフヤンキーのスコット山田で、二番手は留学生ヤンキーのチャーリーだ。その後を五台のバイクが続く。
この七人の集団には名前がない。暴走族のようにカッコイイ漢字の名前を付けようという案もあったのだが、リーダーのスコットもサブリーダーのチャーリーも揃って漢字が苦手だったのでやめたのである。では、カタカナの名前はどうか、となったのだが、地方都市の売れないビジュアル系バンド名のようだというので諦めたのである。
「みんなー!」スコット山田が振り向いて、大声で叫ぶ。「スピードを落とせ!」
これから警察署の前を通り過ぎるため、速度を落とすように指示したのだ。
「OK!」国際免許でぶっ飛ばすイギリス人チャーリーが返事をして、さらに後ろに伝言する。「レディースアンドジェントルマン、スピードダウン!」
「レディースなんか、いないだろ!」三番手を走っていた井川が叫ぶ。
署の玄関には、立ち番をしている新人警官が二人いる。署の前なんかで見つかって、スピード違反で捕まったら、ヤンキーの名折れだ。
七人はスピードを落とすと、背筋と両腕をしゃんと伸ばして、健全なツーリング集団のフリをして通り過ぎる。
そして、署の前を通り過ぎると、またぶっ飛ばす!
「チャーリー!」スコット山田が呼ぶ。「そろそろ登山研修も終わった頃だろうな」
「ああ、そうだな。あんな丘には登りたくないよ。こうして飛ばしてるのが最高だ」
「俺たちに、あんなボーイスカウトみたいなことが似合うわけない。コンクリートジャングルの間をぶっ飛ばして、すり抜けるのお似合いだぜ!」
「そうだぜ!」
七人は信号を守るものの、ジグザグ走行を繰り返し、クラクションを鳴らして、暴走を続ける。あわてて道を空ける車や、横断歩道を早足で渡る人々を見て、喜んでいる。
街で最も大きな道路に出たとき、最後方の男が叫んだ。
「みんな、道を開けるんだ!」
「何だと!」スコット山田は叫ぶ。「俺たちがなんで、道を譲らなきゃならないんだ!」
文句を一つ吐いて、後ろを振り返ると、黒くてデカい車が猛スピードで走って来る。
だが、デカい割にはエンジン音がしない。――なんだ、こいつは!?
チャーリーが叫んだ。
「スコット、道を譲れ! こいつはロールスロイスファントムだ! 六千万くらいする最高級車だから、ぶつけたらヤバいぞ。すげえ金を巻き上げられるぞ」
「なんだ、詳しいな」
「ボクの国の車だからね」
「ああ、イギリスの車か。メシは不味いが、車はすげえな。だが、やけにエンジンが静かだな」
「だから、ファントム=幽霊と言うんだ。ロールスロイスとネッシーはイギリスの二大自慢なんだ」
七台のバイクは仕方なく、脇に避けて、ロールスロイスのファントム様に道を譲った。
少しの傷がついても、俺たちのお小遣いでは払えないだろう。宮井の学食のバイトを代わってもらうしかない。それでも足らないだろうが。
一体どんなセレブが乗ってるのかと、スコットはすれ違いざまに、車の中を覗いた。
ロールスのデカい後部座席に、雷電高校のデカい花桐理事長が、踏ん反り返って座っていた。
「あの野郎か!」スコットはギシギシと歯ぎしりをする。
ロールスロイスファントムには同じく黒塗りの後続車がいた。大きな国産車だったが、こいつが七人に幅寄せをしてきた。道の端をゆっくりと並んで走っているというのに、嫌がらせをするかのように、ギリギリの所を追い抜いて行ったのだ。中を覗くと、デカい後部座席に、ちっこい西見校長が座っていた。さらにその後ろから、荷物を乗せた大型トラックが走って来た。
「あの校長もいやがるのか!」スコットはギシギシギシと歯ぎしりをする。
三台の車は連なって、そのまま猛スピードで去って行った。二台の車には登山研修帰りの雷電高校の理事長と校長が乗っていて、三台目の大型トラックには方向指示器付きの神輿が積んであったのだが、登山研修に参加してなかったスコットたちは知る由もなかった。
おそらく、やつらに俺たち七人の顔は見えていない。ヘルメットをかぶっていたため、竜巻高校の生徒だとは気づかなかったはずだ。竜巻高校への嫌がらせではないにしろ、道を譲らされて、さらに幅寄せをされたとなれば、無性に腹が立つ。ヤンキーの面目が丸つぶれだ。
三台の車の後をつけて、雷電高校に入って行くことを確認すると、七台のバイクはスコットの合図で、作戦会議をするため、近くのコンビニの駐車場に入った。
「今のは雷電高校のお偉いさんだ。だが、相手がお偉いさんであろうと、ファントムであろうと、やられたらやり返す。それが俺たちヤンキーの宿命だ」
「おう!」五人がヘルメット越しに叫んで、片手を突き上げた。
しかし、チャーリーだけは黙ったままだ。
「宿命って、どういう意味だっけ?」日本語は難しい。
「英語でデスティニーだ」スコットが教える。
「なんだ、デスティニーか。なんだか、ロマンチックだな」チャーリーは笑う。
「ああ、歌の歌詞によく出てくるからな。だが、俺たちが奴らに思い知らせて、デスティニーを悪い意味に変えてやればいい。デスティニーという単語を聞くたびに、吐き気を催させればいい。俺たちは言葉さえ支配するヤンキーだ!」
スコット山田が叫んだが、他の六人は意味が分からなかった。チャーリーはもう一度意味を訊こうかと思ったが、気を使ってやめることにした。チャーリーは優しい英国紳士だ。
なぜ、紳士がヤンキーをやっているのか分からないが、その優しさが、後でややこしいことを引き受けることになる。
その後、七人はホームセンターに行き、バールとカナヅチなどを購入して、花桐理事長と西見校長、そして雷電高校への復讐の準備を進めた。
「善は急げだ! 今夜、決行する! たとえそれが悪であっても、俺たちにとっては善だ。俺たちにとっては聖戦だ! 負けられない戦いだ!」スコット山田がデカい声で吠えた。
しかし、他の六人は思った。
何もホームセンターの中で叫ばなくてもいいだろ。
みんなは他人のフリをしようと、近くにある商品を手に取って、品定めをしているフリをした。
チャーリーはたまたま緑色の便座カバーを手に取ってしまい、途方に暮れていた。
「What? 何これ?」
そして、夜の八時半。もっと遅い時間に決行したかったのだが、ヤンキー七人のうち、二人の家の門限が夜の九時だったから、この時間になったのだ。
俺たちはチームワークを大切にする。連帯責任も大切にする。そして、家族も大切にする。
二手に分かれて、雷電高校の周りを一周して、校門の前で落ち合う。
「チャーリー、どうだった?」スコットが訊く。
「俺たち以外に怪しい奴は歩いてない」
「こっちもだ」
外から見る限り、学校内のどの校舎も真っ暗で、もう誰も残ってないようだ。スコットたちは七台のバイクを学校から少し離れた空き地に止めて、歩いて校門に向かった。
どうすれば雷電高校に一矢報いることができるのか? 俺たち七人は無い知恵を絞って考えた。学校の窓ガラスを割ったり、放火したり、爆破することは大きなダメージを与える。しかし、俺たちはただの高校生ヤンキーだ。そんな極悪人のようなことはできない。まるで高校球児のような、爽やかで清々しい復讐が似合っている。
「俺たちにとって、もっとも頭に来て、もっとも痛手を受けることは何だ?」スコット山田が問う。
「名を汚されることじゃないか?」チャーリーが答える。
「俺たちヤンキー集団には名が無い。たとえば、名前がある暴走族にとって、それは何だ?」
「暴走族が掲げている旗を奪われることじゃないか?」
「それだ!」スコットがひらめいた。
七人は“雷電高等学校”という学校名が記された看板=学校銘板を盗み出すことにした。それは校門にあるコンクリートの壁に埋め込まれている、横120センチ×縦20センチ×厚さ15センチの金属製の銘板であった。四人を見張りとして学校の周りに配置し、三人でバールとカナヅチを使って、銘板を外すという作戦だ。
あらためて集合した校門付近には誰も歩いてない。
「よしっ、決行だ!」スコットが小さく叫ぶ。
チャーリーは首の周りに緑色の何かを巻き付けていた。
「何だ、それは?」スコットが訊く。
「さっきのホームセンターで買ったマフラーだよ」
「それは便座カバーだろ!」
「暖かくていいよ」
「便器に座ったとき、お尻が冷てぇ! とならないように暖かいんだよ。なんで、そんなものを買うんだよ」
「手に取った物は買った方がいいかなと思って」
「ヤンキーにそんな律儀さは不要だ。律儀もカバーもここに捨てておけよ」
スコットとチャーリーと井川が仕事に取り掛かる。
銘板の上の部分のコンクリートに三人で穴を開けて行く。左右と真ん中の三か所だ。
「意外に大きな音がするな」チャーリーが不安げに言う。
夜の街にカナヅチでコンコンと叩く音が響くのだ。
「心配するな、四人が見張ってくれている」スコットがなだめる。
十五分ほどが過ぎた頃、見張りの一人が電話をかけてきた。学校の前を誰かが通るようだ。
三人は作業を止めて、校門でウンコ座りをする。こんなこともあろうかと、全員学生服を着て来ている。チャーリーは急いで帽子をかぶり、金髪を隠した。
やがて、スーツ姿の中年男性が通りかかった。一度、こちらをチラッと見たが、ヤンキーが校門でタムロしていると勘違いして、目を合わさないよう、足早に通り過ぎて行った。
「よしっ、再開しよう」スコットが立ち上がる。
さらに二十分が経過し、銘板の上部に三か所の穴が開いた。その穴にスコットとチャーリーと井川が手をかける。
「いいか、せーので引っ張るぞ。――せーの!」
――バキバキッ!
“雷電高等学校”と書かれた学校銘板が見事に外れた。
「やったぜ!」
翌朝、雷電高校に出勤してきた教師が校門の壁に埋め込まれているはずの学校銘板が外されていることに気づいた。そして、なぜかそこには緑色の便座カバーが落ちていた。
理事長も校長も訳が分からず、首をひねる。
「校門=肛門、だから便器→便座カバーというシャレじゃないのかね?」
「ややこしいシャレですな」
「ところで、校長。うちの高校の銘板なんか盗んでどうするんだ?」理事長が疑問を呈する。
「銅なんかの金属は高く売れますからね」
「高校名が入っていたら、盗んだことがバレるだろう」
「買い取り業者に何者かが銘板を売りに来たら、すぐに通報してもらえるように、警察から通達を流してもらいましょう。先ほど110番させましたから、もうすぐ到着すると思います」
「しかし、学校銘板なんか売るかね。他に使い道といったら何だね?」
「受験のお守りにするとか」
「あんな大きな物をお守りにするかね?」
「もっとも、うちの高校は銘板をお守りにされるほど、偏差値は高くありませんがね」
「校長のアンタがそんなことを言うかね。まあ、確かにその通りだがな」
理事長の財力をもってしても、雷電高校に優秀な生徒は集まって来てないのだ。
昼食を食べ終えた頃、スコット山田とチャーリーが放送で呼び出された。校長・教頭室まで来いという。この二人が呼び出されるのは珍しくないので、誰も気にしていない
スコットとチャーリーは連れ立って歩き出すが、なぜ校長に呼ばれたのか、その理由が多すぎて分からない。チャーリーが心当たりのある理由をスコットに確認する。
「音楽の沢村先生の車に十円玉で引っかいて傷付けたことかな?」
「あの野郎が女子の肩に手をやったりしてセクハラをしていたから懲らしめてやったんだ」
「校内に飛んで来たハトに石を投げたことかな?」
「あちこちにフンを落として、用務員の岡戸さんも困っていたから、懲らしめたんだ」
「体育館に転がっていたバランスボールの空気を全部抜いて回ったことかな?」
「使ったきり片付けないから、整理整頓するように忠告をしてやったんだ」
二人は渡り廊下を歩いて行く。
「なあ、チャーリー。俺たちがやってることは正義だよな」
「弱きを助け、強きを挫く。これが真のヤンキーだよ。だから僕はヤンキーになったんだよ」
「俺に大和魂が宿っているように、チャーリーには騎士道精神が宿ってるというわけだ。俺たちはカッコイイよなあ」
スコット山田は、登山研修をさぼり、バイクでぶっ飛ばしながら、横断歩道を渡ってる人を蹴散らしていることなんかすっかり忘れて、自分の言葉に酔いながらも、ふと窓の外を見た。
「チャーリー、俺たちは昨日の件で呼ばれたらしい」
職員用の駐車スペースにロールスロイスファントムが、ケツをはみ出させて停まっていた。傍らに運転手らしき男が立っている。
「あれじゃ、十円玉で引っかけないね」チャーリーが言う。
スコットはどこかに電話をかけていた。
「――そうだ。十五分後に頼む。お礼はカヌレ? なんだそれは?」
校長・教頭室に入ると、草野校長と森教頭が応接セットに座って待っていた。向かいには雷電高校の花桐理事長と西見校長が座っている。
草野校長が声をかけた。
「スコット山田君とチャーリー何とか君。そこに座りなさい」
空いてるソファを指差す。チャーリーの本名はいまだにややこしくて覚えられないようだ。
「さっそくだが、昨日の夜、君たちはどこにいたかね?」
花桐理事長と西見校長が鋭い視線を向けて来る。
スコット山田は考えた。俺たちが呼ばれたということは、バイク七台で走っているところを、誰かに見られたか、どこかの防犯カメラに映っていたのだろう。ここでウソを吐くと墓穴を掘る。
「仲間とバイクで健全なツーリングにいそしんでおりました」
「仲間というのは、うちの生徒かね?」
「はい。ここにいるチャーリー君も含めた七人の気のいい奴らです」
「実はね」花桐理事長が割り込んで来る。「うちの銘板が盗まれたのだよ。君たちは知らんかね?」
「メーバンって何ですか?」チャーリーが訊く。
「銘板も知らんのか?」
「僕はイギリス人なもので知りません」
「俺はオカンがイギリス人のハーフなもんで、食べたことありません」
「食べ物ではない」理事長はムッとする。
「バームクーヘンのようなものじゃないのですか?」
「あんなもん、堅くて喰えん」
スコット山田もチャーリーも昨晩校門から盗んだ物を銘板と呼ぶことを知らなかった。つまり、とぼけているのではなく、本当に知らないのだ。
「学校名が書いてある看板みたいなものだ」理事長が説明する。「それがなくなったのだよ」
「はっきり言うと」今度は草野校長が口を挟む。「君たち七人が雷電高校の前をバイクで通るところを見ていた人がいたんだ。それで、君たちが犯人じゃないかと疑っておるのだよ」とはっきり言う。
あの看板が銘板と言うものだと分かったスコット山田がとぼけて訊く。
「その銘板というのはどのくらいの大きさなんですか?」
「だいたい、長さは一メートルちょっとだな」西見校長が答える。
「そんなデカい物を抱えてバイクに乗っていたら、おまわりに止められますよ。それとも、銘板を抱えてバイクで走る俺たちの姿を見た人がいるのですか?」
「いや、それはないんだが」理事長の歯切れが悪くなる。
「じゃあ、物的証拠が揃ったら、また声をかけてください」
スコットがズバッと言い切ったとき、理事長の電話が鳴った。
「なに。銘板が見つかった!? ――ああ、うん、そうか。分かった」
電話を切った理事長はみんなの方を向いて言った。
「たった今、見つかったようだ。校門の塀と花壇の隙間に落ちていたらしい。どうやら犯人は銘板を外した後、塀から校内に投げ込んだようで、園芸部の女子生徒が花壇に水をやりに行って見つけたようだ」
その女子生徒は雷電高校生なのだが、スコットの女友達で、さっき電話をかけた相手だ。
校門近くに学校名の書かれた看板が落ちているはずだから、今から十五分後に、なくなっている看板を見つけましたと、誰でもいいから先生に報告するようにお願いをしておいたのだ。その先生から、計画通り、このタイミングで理事長に電話が入ったというわけだ。
お礼に、スコット山田はカヌレという名前のスイーツを、その女子生徒に奢ることになっていた。
最近やっとマリトッツォという名前を覚えたというのに、今度はカヌレかよ。カヌレなんてスイーツはうまいのか? 日本人なら豆大福だろうよ。
外した銘板は意外に重くて大きかった。こんな物は持って帰れないし、持って帰っても扱いに困るということで、塀の向こうに放り投げていたのだ。スコットが強気だったのも、手元に証拠品である銘板を持ってなかったからである。
犯人不明のまま、スコットとチャーリーは釈放された。うちの教頭からは時間を取らせて済まなかったねと言われたが、向こうの理事長からは一言の謝罪もなかった。
だが、そんなことは想定内であった。あいつはそんな奴だ。一時的にせよ、雷電高校のお偉いさん方をアタフタさせて、少しは気が晴れた二人であった。
校長・教頭室から出て来たスコットとチャーリーは伸びをして、定番のセリフを言った。
「ああ、娑婆の空気はうまいぜ!」
建物から外に出てみると、昨日一緒に銘板を外した井川が立っていた。二人を心配して、ここまで迎えに来てくれていたのだ。
そして、彼も頭を深々と下げて、定番のセリフを口にした。
「お勤めご苦労さんです!」
ロールスロイスファントムの脇に立っていた運転手にジロリと見られた。
「ノープロブレム!」
チャーリーが片手をあげて、見事な発音で叫んだ。
ああ、キングズ・イングリッシュは美しい。
学校に対して理不尽なクレームや要求を繰り返す、モンスターペアレントが近年、話題になっているが、モンスターは何も親だけではない。たとえば、今、草野校長の前に座っている老人がそうだ。学校の近所に六十年以上、住んでいるらしいが、学校が出す騒音がうるさいと文句を言いに来たのである。かれこれ、三時間ほど居座っていて、まだまだ終わりそうにないので、草野校長の仕事を森教頭が代行している始末である。
「子供たちが騒ぐと言いましても、わざと騒いでいるわけではありませんし、声が聞こえますのは、休み時間と体育の時間と放課後くらいじゃないでしょうか」校長が同じ説明を繰り返す。
「いや、わしはそれがうるさいと言っておるんだ」
子供たちの声は元気でいいし、何も気にならないと言う人もいれば、あんなものは騒音であり、日々の生活に支障をきたすという人もいる。このじいさんは後者だ。年齢はおそらく八十代だろう。だが、背筋はしゃんと伸びている。白髪交じりの短髪であり、口はへの字に曲げており、三時間、一度も柔和な表情になったり、笑ったりしない。意志の強さがうかがわれる。
こんな頑固なじいさんは、毎日何を楽しみに生きておるんだと校長は思う。
「校内放送はなるべく控えます。チャイムの音や下校時の音楽のボリュームも下げます。教職員の車も、この近くではゆっくりと走り、クラクションはなるべく鳴らさないようにします」
校長はいくつかの提案をしているが、老人は聞く耳を持たず、騒音がうるさい、何とかしろの繰り返しである。では、具体的にどうしてほしいのかと訊いても、それはそちらで考えろの一点張りである。老人に出すお茶のおかわりは十回近くになっている。校長は二度、トイレに行くために席をはずしたが、じいさんはドカッと座ったままである。
この騒音ジジイの膀胱はどうなってるんだ? ジジイの性格のように、ずうずうしく肥大しておるのか?
校長のイライラも限界に近づいている。
電話のベルが鳴り、教頭がやって来た。
「校長、父兄から電話です。急用ということです」
「急用? では、ちょっと、失礼します」
校長が応接セットから校長机に向かい、受話器を取った。
「お待たせいたしました。校長の草野です」
受話器の向こうはツーツー音である。教頭が気を利かせて、ニセの電話をかけてくれたのだろう。おそらく自分のスマホからこの固定電話にかけ、自分で受話器を取り、スマホを切り、校長を呼びに行ったのだろう。
校長は教頭に感謝しつつ、何も言わない受話器に向かって、芝居を続ける。
「ほう、それは大変ですね。一刻を争いますな。学校としても、早急に対応を検討させていただきます」わざと老人の方に目をやる。老人もこちらを見ていて、目が合う。「はい、その件につきましては、ここに教頭もおりますので、今から話し合って、ご連絡を差し上げます。いえ、お待ちいただければ、至急に連絡いたしますので。はいはい。では、失礼いたします」
校長は急いで、爺さんの前に戻った。
「どうやら急用のようだな」
「いいえ、大丈夫です。先ほどの続きですが……」
「いや、また来る」
老人は残っていたお茶を飲み干すと、席を立ち、さっさと出て行った。
「いやあ、教頭先生、助かったよ」
「大変でしたね」
いつもは仲が悪い二人だが、この時ばかりは校長に同情していた。とっさの連係プレーはうまくいった。
「教頭先生、悪いけど、あの騒音ジジイの住所と名前を聞いたから、あの老人は普段どういう暮らしをしているのか、何をやっているのか、近所に探りを入れて来てくれんかね」
「敵情視察というわけですな。やってみましょう。何か弱みが見つかるといいですな」
教頭は、これで校長に一つ貸しができると考え、引き受けることにした。貸しができなければ、こんな面倒なことを引き受けるわけない。
翌日、教頭は帽子をかぶり、マスクをして、騒音ジジイの家の周りを歩き回り、じいさんは十年ほど前に妻を亡くし、今は一人暮らしをしており、酒が大好きで、よく昼間から飲んでいるということを聞き出した。さらに、以前は高校の数学の教師だったことも判明した。――まさか同業者だったとは。
さらに近所を歩き、一軒の酒屋を見つけた。店主にそれとなくじいさんのことを聞いてみると、ここでよく酒を買っているという。しかも、安い酒しか買わないということだった。教頭は校長と電話で相談した上、この店で一番高い、大吟醸菊理媛を五万円で購入した。代金は裏金である。ミニ四駆のプレイ代として、花桐理事長が毎回置いて行ってくれる一万円を積み立てたものである。つまり、校長と教頭の腹は痛まない。
その夜、校長はアポなしで騒音ジジイの家に行き、大吟醸菊理媛を渡して、大した話もせずに、帰って来た。
それ以来、じいさんは学校にはピタリと来なくなった。
昼休みの時間。学校犬ポチが校庭を走り回って、サッカーボールで遊んでいる。それを、近くで生き物係の犬井と鳥谷が見守っている。二人はポチと一緒に遊ぼうと近づこうとするが、サッカーボールの方が楽しいらしく、こちらを見向きもしない。
「ポチの前世はサッカー選手だろうな」犬井が言う。
「犬界では一番のドリブラーだね」鳥谷も感心する。
そんな二人と一匹を窓から見下ろしているのは、姫宮“マドンナ”生徒である。周りに三人の女子が集まっている。結菜と芽衣と葵だ。
先日、校庭にポチを見つけて、真っ先に教室を脱出した、くノ一三人組である。
「ホントに心当たりはないの?」結菜がマドンナ姫宮にまた同じことを訊く。
校内に奇妙なウワサが女子専用学校メールで流れていた。そのウワサとは、明日の午後六時、体育館で一人の男子が姫宮に公開ライブ告白するというもので、その見届け人として、女子限定で集まってほしいという内容であった。そして、このメールは決して男子に見せてはいけないと書かれていた。
当然、見届け人は強制参加ではなく、希望者のみだ。だが、こんな面白そうなイベントをスルーする女子は少数だと思われた。
結菜が姫宮に訊いていたのは、その告白してくる男子の名前だった。
「心当たりなんか無いよ」姫宮はそっけなく言う。
「そう言うと思ったよ」結菜は芽衣と葵に目配せする。二人はニヤニヤしている。「正確には“無い”のではなく、有り過ぎて、いったい誰だか分からないのでしょ」
芽衣が引き継いでしゃべる。
「今まで告白して来た男子は数知れないし、女子にも告白されているから、その人数は覚えてないのだろうね。いいよなあ」
葵も続く。
「まだ告白して来ない男子に加えて、断られたけど、もう一度チャレンジしようと企んでいる男子もいるだろうから、多すぎて、誰だか分からないよねえ。うらやましいなあ」
女子の嫉妬は怖い。容赦のない皮肉が飛び交う。だが、姫宮はどこ吹く風で、ニコニコしながら、三人の話をフンフンと聞いてあげている。嫉妬や皮肉なんていつものことだと意に介しない。この余裕がマドンナと呼ばれる所以だと三人は思った。
結菜がみんなに言う。
「日時と場所を指定してくるなんて、宝石を盗もうとしているルパン三世みたいじゃん」
すかさず、芽衣が銭形警部のモノマネをする。
「奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です」
「キャー!」言った本人も含めて、三人が叫ぶ。「ヤバいよねー」「ベタだよねー」「昭和だよねー」
叫んだ後、三人はあわてて声をひそめた。このイベントを男子に
知られてはいけないからだ。女子専用学校メールには、この内容を
男子に教えるとタタリがあると記されていた。朝起きてみると体が
牛になっているというタタリだそうだ。今までの人生から牛生に変
わりたくない女子は、決して男子に言わないように、口のチャック
を閉じた。
しかし、男子専用学校メールでも、似たようなイベント案内が流れていることを女子は知らない。男子のメールにも、それを女子に漏らすと、朝起きたら体が毛ガニになっているというタタリがあると書かれていた。今までの人生から蟹生に変わりたくない男子は、決して、女子に言わないように、口のチャックを閉じた。
翌日の午後五時四十五分。体育館の西入口から女子が続々と入って行く。入口で靴を脱いで、靴下のまま、足音を立てずに中央付近へと歩いて行く。誰もが無言だ。吐く息もわずかで、気配さえ微かなものになっている。時間を厳守して、そのように振る舞えとメールで指示をされていたのである。破ったら牛のタタリだ。
体育館は電気が消え、窓も黒いカーテンで塞がれて、真っ暗になっている。中央付近にはなぜか黒い幕が下されている。前方にある舞台の幕を持って来たようだ。この幕によって、体育館は二つに区切られていた。この幕の向こうに、告白する男子が待っているのだろうと、誰もが考え、興奮し、暗闇の中で、無言のまま、雰囲気は盛り上がっていた。
中央付近には公開告白をされる姫宮がいるはずなのだが、暗くて分からない。おそらく、幕のすぐそばに一人で立っているのだろうと誰もが思っていた。
やがて、約束の午後六時が近づいて来た。
みんなは声を出さずに、心の中でカウントダウンを始める。
“ファイブ、フォー、スリー、ツー、ワン、ゼロ!”
――午後六時ジャスト!
中央に下がっていた黒い幕が、いきなり落ちて、照明が灯された。
姫宮の姿はなかった。
幕の向こうには約五十人の男子生徒が群がっていた。男子専用学校メールには、午後五時三十分に東入口から体育館に入るように指示されていた。女子と同じく、靴を脱いで、静かに時が来るのを待つように、騒げばタタリがあると記されていた。毛ガニのタタリだ。
体育館の中は黒い幕で仕切られていて、男子は六時になるのを、無言で待ち、今、幕が下された。
女子の集団と男子の集団が見合った形になった。
女子はたくさんの男子に驚き、姫宮を探している。
男子もたくさんの女子に驚き、姫宮を探している。
「ちょっと、どういうこと?」一人の女子が男子に詰め寄る。
「いや、分かんねえって!」男子が後ずさりしながら答える。
無言を貫いていた男女が一斉に話し出し、体育館の中は騒然となる。
結菜が芽衣と葵に言った。
「わたしたち、ルパンにやられたよね」
すかさず、芽衣がまたモノマネをする。
「奴はとんでもないものを盗んで行きました」
「昨日、聞いたわ!」葵が文句を言う。「心を盗まれたというよりも、まんまと騙されて、むかついてるんですけど!」
女子と男子が情報を交換したことで、この企みの全貌が見えてきた。
女子のメールには、体育館で一人の男子が姫宮に告白をするから、見届けるように書いてあった。一方、男子のメールには、体育館で姫宮が待っているので、希望者は告白するように書かれていた。
中央付近に群れていた約五十人の男子は告白者であった。実に約百五十人の男子の三分の一の男子が姫宮に告白をしようと、集まっていたのである。五十人の男子の中には、熱き思いを伝えようと、手紙やプレゼントの箱を持つ者がいて、大きな花束を抱えている者まで来ていた。
告白男子の群れの先頭に立っていたのは、今年、社会人入学をした大久保田であった。
「大久保田さん、こんな所で何をやってるんですか!?」
男子たちは驚くととも大笑いをする。
「いやあ、年齢の数だけ、バラの花を買ってきたのだがねえ。ははは」
「六十六本っすか?」
「そうそう。六千六百円もかかってしまいましたよ。しかし、まさか、当人が来てないとはねえ。想定外ですよ。ねえ、野呂先生」
「ええっ!?」全員が驚いて、振り返った。
隅の方から定年間近の野呂先生が腰を曲げて、トボトボ歩いて来た。
いつものグレーのスーツを着て、やはり、バラの花束を抱えている。
「いやあ、私は五十九歳ですから、五千九百円かかりましたわ。それに、手紙も書いて来ました」
スーツの胸ポケットから取り出して見せる。ネコのイラストが描かれたかわいい封筒だ。
「わしも書きましたぞ」大久保田は学生服の胸ポケットから手紙を出す。汚い茶封筒だった。
ネコ封筒VS茶封筒。
女子はこの光景を呆れて見ていた。
「あの二人、うちのお父さんより年上だよ」
「ヘタすれば、おじいちゃんだよ」
「なんで、自分の年齢の数のバラを買うかね」
「普通、相手の年の数でしょ。うちら十七歳だから、十七本でいいんだよ」
「あの二人、絶対、一緒にお花屋さんへ買いに行ったよね」
「あのう、バラの花をプレゼントしたいので、六十六本包んでくれるかね」
「わしは五十九本じゃ」モノマネをする女子まで現れる。
「お二人合わせて、一万二千五百円になります」花屋のモノマネ。
「あのう、お会計は別にしてくれるかのう」「領収書も別々で頼みますぞ」
容赦なくからかう女子。
そして、女子たちは、男の人って、いくつになってもバカだよねと結論付けた。
「でもさ。このイベントは誰が仕掛けたの?」
「姫宮の姿が見えないのだから、あの子が仕掛け人だよ」
「目的が分からないよね。まさか、うちらをからかった?」
「もしかして、みんながコミュニケーションを取れるように計画してくれたんじゃない?」
体育館に集まった男子と女子は騙されたことも忘れて、あちこちで楽しそうに談笑している。もともと、普段から男子と女子の間ではあまり会話がなく、両者に大きな壁があるような高校だったため、この光景は珍しい。
「――だとしたら、大成功だね!」
いまだに呆然と立ち尽くす大久保田と野呂先生以外は、時間が経つのも忘れて、男女で会話を楽しんでいる。男子も女子もまんまと騙された。だが、騙された者同志に連帯感が生まれたのだろう。
突然体育館の照明が消えた。
そして、中二階にあるギャラリーと呼ばれている部分に三人の人影が現れた。なぜか、ライトアップされる。ちょうど光が当たるように照明器具がタイマーでセッティングされていたようだ。
三人はそれぞれ赤と青と紫のレオタードを着ていて、それぞれが赤と黄と青の腰ヒモでウェストマークしていた。
「キャッツ・アイだ……」誰かがつぶやく。
その三人とは、小久保“マドンナ”先生と、姫宮“マドンナ”生徒と、シスターのマリー・アマーチェだった。
生徒はギャラリーを見上げた。そして、理解した。
黒幕は小久保先生だったのだと。
「みなさん!」小久保先生が口を開いた。「今夜のパーティーはいかがでしたか?」
全員がいっせいに拍手をして、歓声をあげた。男子と女子が仲良くなれるように、仕掛けられたのだと分かったからだ。
そして、それは成功している。体育館内の雰囲気がそれを示している。
「これからも、みんな仲良く……」
小久保先生の話が途切れた。みんながスマホを持って駆け寄り、写真を撮り始めたからだ。
マドンナ先生とマドンナ生徒のレオタード姿など、お目にかかれる機会など滅多にない。さらにシスターだ。いつもは白と黒の地味な修道服を着ているシスターが、なんと紫色のレオタードだ。こんな機会は一生に一度あるかないかだ。――ないに決まっている。
こんな光景をイエス様が見たら腰を抜かすだろう。しかし、たくさんの生徒に喜んでいただき、幸せになっていただくというのは博愛である。キリスト教の博愛精神である。あの世から叱られはしないだろう。
体育館の中は“竜巻高校キャッツ・アイ”に向けて、次々に焚かれるフラッシュで眩しい。しかし、なぜ、シスターがここにいるのか、誰にも分からない。神出鬼没のシスターである。
写真を撮ろうと群がっているのは男子生徒だけではない。女子も全員ギャラリーの下に集まっている。三人は普段から女子にも人気があるからだ。
呆然と立っていた大久保田と野呂先生も、再びスイッチが入ったかのように、活発に動き出し、シャッターをパシャパシャ切っている。普段からは考えられない、すばやい動きだ。
「いやあ、大久保田さん、いい夜になりましたなあ」
「野呂先生、私はこの学校に入学して良かったですわ」
「こりゃ、青春ですな」
「生きてて良かった~」
「ははははは」
「いひひひひ」
高齢者の高笑いが体育館に響いた。
用務員岡戸は刺股を手に体育館に近づいていた。さっきまで生徒たちが体育館で何かのイベントをやっていたようだが、もう帰ってしまって、誰もいないはずだ。だが、何か物音と声が聞こえる。その正体を確かめようと、近づいているのである。刺股は必需品だ。
なんといっても、二宮金次郎に二度も追いかけられて、木娘に笑いかけられたのだから、第三のお化けが出ないとも限らない。二度出ることは三度出ると言うではないか。
岡戸はそっと扉を開けた。中は真っ暗だ。だが、窓を塞いでいた黒いカーテンは外されているので、月の光が入り込んでいて、まったく見えないわけではない。右手で刺股を抱えたまま、手探りで壁の電気のスイッチをパチパチと押した。
中央に第三のお化けが立っていた。
「あら、岡戸ちゃん!」保健室の主、アラフィフの美魔女恵子先生だった。
「なんだ、恵子先生か……」全身の力が抜けた。
「なんだとは、冷たいわねえ。岡戸ちゃんと私の仲よ」腰をくねらせて言う。
「いや、アンタとは用務員と保健師の関係でしかない」きっぱり返す。勘違いされては困る。
先ほどから岡戸は遠くを見ながら話している。恵子先生が真っ白のレオタード姿だったから、直視できないのだ。しかも、既製のレオタードを得意の裁縫で加工し、体の線がよりくっきりと見えるように詰めて、さらに必要以上に布が股間に食い込むようにしてある、超ハイレグレオタードだったのである。
体操のコマネチもここまで喰い込んどらんかったぞ。
しかも、若いコマネチと違って、アラフィフである。第三の白いお化けから視線を外したくなるのも無理はない。
「恵子先生はここで何をしとるんだ? エアロビの練習かね?」天井を見上げて訊く。
「違うのよう。ここで今夜、公開告白大会があると聞いて参加したのよ」また腰をくねらす。「私の作るチャーハンが気に入って、保健室に食べに来てくれるシスターからの情報よ」
ときどき保健室には悩みを持った生徒がやって来るのだが、保健師だけでは解決が難しい悩みを、近所の教会のシスターのマリー・アマーチェさんへ下請けに出していたのである。そして、いつしか、マリー・アマーチェと恵子先生はチャーハン仲間となったのである。
「もしかして、恵子先生は誰かに告白しようと思っておったのかね?」床を見ながら訊く。
「そうよぉ。この際、若けりゃ誰でもいいのよ。でも、来てみたら誰もいなかったというわけ。午後六時開始のはずだったのに、おかしいわねえ」
「先生、今は七時だよ」腕時計を見ながら言う。
「えっ、そうなの!? 一時間、間違えた。アチャー!」
恵子先生は手のひらで額をペシッと叩いて、昭和の悔しがり方をした。
「そうと分かったら帰りましょ!」恵子先生は切り替えが早い。「ところで、岡戸ちゃんは何で刺股を持ってるわけ?」
アンタのような白いレオタード喰い込みお化けが出たときのためとは言えない。
「体育館から物音と声が聞こえたから、怪しいと持って、一応持って来たんだよ」
「きっと、それは私の声よ。誰もいなかったから悔しがって、独り言を言っていただけ。年を取ったら独り言が増えると言うけど、年を取らなくても、独り言は出ちゃうのよね」
いやいや、十分、あんたは年を取ってるよとは言えない。
「ところで、岡戸ちゃんは刺股なんか使えるの?」
「ああ、悪者が現れたらこれで戦うのさ」
岡戸は刺股をビュンと振り回す。
「あら素敵!」アラフィフの美魔女レオタードが手を叩いて喜ぶ。
「こう見えても、刺股三段の国家資格を持っておる」いい加減なことを言う。
「だと思ったわ」いい加減な答えが返って来る。
岡戸は電気のスイッチを消して、今日一日で、いろいろな思いが詰まった体育館の扉を閉めた。残念ながら、岡戸はキャッツ・アイを見ることができなかったのだが。
「いい夢を見させてくれてありがとね」
美魔女が体育館に向けて、投げキッスをした。
「ところで岡戸ちゃん、この使用済みハイレグレオタードを三千円で買わない?」
「買わない」
「刺股と交換しない?」
「しない」
「好きな人にはそうして冷たくするのよねえ」勝手に決めつける。
「わしは用務員室に戻るから」岡戸は相手をするのをやめて、刺股をかつぎながら、早足で去って行く。
公開告白大会に参加しそびれた美魔女の恵子保健師は着替えるために、トボトボと保健室へ戻った。
すると、なんと、入口に大きなバラの花束が置いてあるではないか!
「あら! 誰かしら、私への告白かしら!?」
恵子先生は花束の中をくまなく探したが、手紙は入ってなかった。
「差出人が分からないわ。きっと照れくさくて、書けなかったのよね。分かるわ、その気持ち。シャイな誰かが、どこかで私のことを見つめてくれている。――あら、素敵じゃない」
苦労して数えてみると、バラの数は百二十五本あった。
「なんで、百二十五本なのかしら?」
恵子先生はいくら考えても分からない。
使い道がなくなった大久保田の六十六本と、野呂先生の五十九本を合わせた、百二十五本のバラを、二人がそっと保健室の入口に置いてあげたことを、美魔女は知らなかった。
「私って、まだまだ捨てたものじゃないわね!」
美魔女の全身には、さらなる自信がみなぎって来た。
「よっしゃー!」
その自信で、白色喰い込みレオタードがはち切れそうになった。
今夜の月の光はいつもよりやさしく感じた。
竜巻高校の校長・教頭室では五人の人物がテーブルを囲んで座っていた。校長と教頭が並んで座り、向かい側にウマイ寿司の大将と女将が座り、横には新任の体育教師中村が座っている。
「こちらです」中村が一枚の紙をテーブルの上に置いた。
それは、新しく作るサッカー部の部員名簿だったのだが、同時に試合のメンバー表になっていた。まだ試合も何も決まってないのだが、気の早い中村が仕上げてきたのだ。
----------------------------------------------------------------------
「竜巻高校サッカー部」
*部長:中村正敏(28)→新任の体育教師。
*監督:馬居徳之助(59)→ウマイ寿司の大将。
*コーチ:馬居清子(52)→ウマイ寿司の女将。
~先発メンバー~
・GK:
チャーリー(17)→ヤンキー留学生。
・DF:
犬井太(17)→生き物係。
鳥谷海斗(17)→生き物係。
平井一郎(17)→生徒会長。
金森太陽(17)→生徒会副会長。
・MF:
宮井健太(17)→学食でバイト。
中島優斗(17)→松寿司がニックネーム。
安藤陸(17)→自称ラッパー。
・FW:
玉本和男(17)→ラグビー部と兼任。
足立壮四郎(17)→ラグビー部と兼任。
遠藤朝陽(15)→スポーツ飛び級。走る遠藤豆。
*控えメンバー
大久保田作太郎(66)→社会人入学。手芸部と兼任。
*チームドクター
佐藤恵子(推定50前後)→保健室の先生。自称美魔女。
*マネージャー
小久保百合(28)→英語教師。マドンナ先生。
姫宮瑠伽(17)→マドンナ生徒。
*用具係
岡戸恭四郎(66)→用務員。
---------------------------------------------------------------------
草野校長が部員名簿を手に取った。
「うーん」自慢の口髭に手をやりながら唸っている。「部員数は控えを入れて、十二人か。ギリギリ試合はできるな」
「どうでしょうか?」中村が不安げに訊く。
みんなの視線も校長に集まる。
「素晴らしい!」校長が叫んだ。「短期間でよくここまで仕上げてくれた!」
「ご理解いただいて、安心しました」中村はホッとしたようだ。
これだけのメンバーを揃えるのには苦労した。生徒たちは既にどこかのクラブに所属しているか、帰宅部だったため、なかなかウンと言ってくれない。持ち前の情熱を全開にして語っても、分かってくれない生徒ばかりだった。
そこで、試合のときだけでも来てくれるようにお願いをした。試合を重ねるごとに、その活躍を見て、部員が増えるのではないかと期待したからだ。
チャーリーは優しい英国紳士だった。その優しさに付け込んで、強引に話を進めたら、観念して、引き受けてくれた。だが、ヤンキーリーダーのスコット山田はどうしても首を縦に振らなかった。ヤンキーとしての矜持を保ちたいらしい。確かにスポーツで汗を流すヤンキーはいないだろう。
生き物係の犬井と鳥谷には学校犬ポチの世話を頼んだ。その際、エサ代などの経費を校長と交渉して、必要以上に獲得してやった。その恩を利用して入部させたのである。彼らに運動の経験はない。当然、人数合わせの入部である。
平井生徒会長と金森生徒会副会長には、今後の竜巻高校の発展のために一肌脱いでくれ、竜巻高校史にお前たちの名前が残るぞと、いい加減なことを言って口説き落とした。
学食でバイト中の宮井にも声をかけた。
「僕はこの通り、痩せてますし、体力はありませんよ」
「学食のバイトはいくらもらってるんだ?」
「五十分で千円です」
「一試合九十分で三千円出そう」
「入ります!」
簡単に落とせた。
松寿司がニックネームの中島には、サッカー部の監督がウマイ寿司の大将だとこっそり教えたところ、いつもお世話になってますからと、気持ち良く引き受けてくれた。
自称ラッパーの安藤は、酒井先生に入部の依頼をしてもらった。英語の授業が終わって、一言二言話しただけで承諾を得たらしい。どう言って納得させたのか分からない。魔法でも使ったのか?
「安藤君、中村先生がサッカー部員を集めてるのだけど」酒井先生がじっと見つめる。
「僕は足の骨に四本のヒビが入ってまして」安藤はうつむく。
「あら、そうなの」先生の飛び蹴りでヒビが入ったのだが知らんフリである。「サッカー部が活動を始める頃には、治ってるでしょう」
「でも、スポーツは苦手ですし」
「今すぐ、ヒビの本数が五本に増えてもいいの?」
「入ります!」
簡単に落とせた。
ラグビー部の玉本と足立は、サッカーの試合はせいぜい週二だからと、兼任で入部してくれた。部室で苦労して説得した甲斐があった。
スポーツ飛び級の遠藤もサッカーをやったことがないと断って来たが、ボールに触らなくてもいい、ワーワーキャーキャー言いながら走り回ってくれればいい。君は走るのが好きだろうと言って納得してもらった。
社会人入学の大久保田さんは控えだ。全校生徒に声をかけたのだが、次々に断られて、もはや残っていたのは大久保田さんしかいなかったのだ。ケガ人が出たときのために勧誘したのだが、若い人と触れ合いたいということで、二つ返事でサッカー部に来てくれた。普段はベンチを温めるための要員だが、ベンチ内で編み物をしてくれていてもかまわないと言ってある。残り物には福があるというから、何かの役には立ってくれるかもしれない。
チームドクターは恵子先生だ。男子のサッカー部だと言うと、こちらも二つ返事で引き受けてくれた。女子のサッカー部だと来てくれなかっただろう。老いてますます盛んだと思ったが、もちろん口に出して言わない。
二人のマネージャーにはダブルマドンナを配置した。もちろん、選手のモチベーションを上げるためである。男は美人の前では張り切るものである。女性教師がサッカー部のマネージャーというのはおかしいが、校長がいいと言ったので、いいことにする。他校からクレームが入ったら、校長のせいにすればいい。
最後に、用具係は用務員の岡戸さんだ。学校内のいろいろな用具のことに知悉しており、また顔に似合わず器用だから、何かと便利だろう。もちろん便利屋としてチームに加わってくださいとは言ってない。
部員名簿を見て、校長と仲が悪い教頭はイチャモンを付けてきた。特に要望はないのだが、さっき校長が素晴らしいと言って褒めたため、何でもいいから、逆らいたいのだ。
「この中でサッカー経験があるのはどの子ですか?」
「いや、いません」中村は痛いところを突かれたと思った。
「では、運動経験があるのはどの子ですか?」
「ラグビー部の玉本と足立だけですが、飛び級の遠藤は小柄ですけど、足が速く、走る遠藤豆と呼ばれて、先日、学校犬ポチに勝利して、学級新聞の号外に写真入りで載りました」
「確かに短期間で部員とスタッフを揃えたのは評価しましょう。しかし、はっきり言って、寄せ集めではないでしょうか?」教頭はホントにはっきり言う。「監督はどう思われますか?」
みんなの視線が大将に向かう。だが、いつもは大将と呼ばれていて、監督と呼ばれ慣れてないため、自分が訊かれていると気づかない。隣の女将から足を蹴飛ばされて、やっと覚醒した。
「――えっ、わしか? ああ、そうですね。中村先生はよくやってくれたと思いますよ。まあ、試合を重ねるごとに経験も積まれますから、強くなっていくのではないですか。強くなれば、有望な人材も入ってきますよ。監督としては、与えられた条件の下で全力を尽くすだけですよ」
「コーチはどうお考えですか?」教頭が女将さんに訊く。
「私もうちのダンナ、いえ、監督と同じ考えです。私のあらゆるサッカー知識を動員して、指導をしていく所存です」
詳しいのは韓流のサッカー選手の顔と体型だけだとは言えない。そもそもこの夫婦は強引に監督、コーチに任命されたのだ。いつも上等な寿司を頼んであげているじゃないかと言われて、断れなかったのである。
さらに先日は、登山研修用にと、三百人分のちらし寿司の注文をいただいた。校長にはかなり値切られたが、これでダメ押しをされた形だ。
しかし、この部員名簿を見て、首からお揃いの十字架をかけた寿司屋の夫婦は内心喜んだ。このメンバーでは他校に勝てない。素人が見ても分かる。
二人の考えは、三か月間だけ監督とコーチ引き受けよう。その間、いくつかの試合があるだろう。しかし、きっと成績は悪いだろう。だから、二人して解任されるだろう。よって、堂々と辞めていけるだろうというものだった。
だが、その間の監督、コーチ料は成績に関係なく、ガッポリといただいてやる。そして、今、このメンバーを見て、二人は確信した。――試合は全戦全敗だ。
思惑通りに事が運びそうで、笑いそうになる。たった三か月の辛抱だ。後はたんまりとギャラをもらう。そして、また日常の寿司屋の大将と女将の生活に戻る。
それでも、大将は名簿を見て、一つの疑問をぶつけた。何か言っておかないと、やる気がないことがバレるかもしれないと思ったからだ。そこで、中村に向かって訊いてみた。
「控えメンバーに書いてある、六十六歳の大久保田さんというのはどういう方ですか? 随分と年配の高校生のようですが」
「この方は今年から社会人入学された方で、年金で学費を払っておられます」
「サッカーの経験がおありですか?」
「いいえ。編み物がご趣味で、セーターでもマフラーでも手袋でも編むことができるという、素晴らしい人格者です。このたび、手芸部にも入部してくださいました。まだ男性部員は一人だけですが、晴れて大久保田さんが部長に選出されました」
大将はホッとした。ブラジルにサッカー留学の経験がある六十六歳だったら、大変だと思ったからだ。レジェンド釜本邦茂の優秀な直弟子であってもいけない。彼らは年齢に関係なく、すごいはずだ。そんな大物はいらない。間違っても、試合に勝ってはいけないのだ。
「ですので、大久保田さんは手芸部との兼任です」
「それはお忙しいところを申し訳ないですなあ」大将はわざとらしく言う。
隣に座ってる女将も大将の気持ちを察して、笑いが込み上げそうになった。長い間、夫婦をやっているため、何を考えているのか、だいたいは分かるのだ。
中村は部員名簿を校長に見せて、承諾を得られたので一安心だった。途中で教頭がゴチャゴチャ言ってきたが、何とか切り抜けることができた。これから部員たちをじっくり育てて、半年後くらいに、他校との練習試合ができればいいかと考えていた。そして、その後はしだいに力をつけて、ゆくゆくは日本一だ。最終的には、日本一を踏み台にして世界一を目指す!
相手は世界だ。そう焦ることもない。一歩ずつ前進することが大切だ。十二人の部員にもそう言って聞かせよう。
中村の体の中ではやる気が燃えたぎっていたが、大将と女将はまるでやる気がないことに気付いてなかった。
校舎から外に出ると、ちょうど職員用の駐車スペースに、ロールスロイスファントムが滑り込んで来た。雷電高校の理事長御一行様だ。おそらくミニ四駆のレースを楽しみに来たのだろう。ヒマな連中だ。花桐理事長と西見校長が揃って下りて来た。
「これは中村先生、お元気ですか?」
理事長が明るい声で挨拶をしてくる。
この人物はこのように外面だけはいいので、生徒や父兄にある程度の信用がある。
「はい。おかげ様で」明るい声で返してあげる。
「その後、サッカー部の創設の件はどうなっておるのかね?」
「はい。もう出来上がりました」
「ほう、そうかね」理事長の目がキラッと光った。中村の自信ありげな言い方が気に入らなかったようだ。「しかし、お宅の新設サッカー部が、我が雷電高校サッカー部に勝つには三十年早いでしょうな。残念ながら、わしはそんなに長生きができん。見たかったよ、うちの名門サッカー部が君の新設サッカー部に負けてしまうところをな」
皮肉たっぷりの言葉を受けて、中村の目もキラッと光った。
「見せてあげますよ。理事長がご存命中に、うちのサッカー部が勝つところをね」
「言ってくれたねえ」理事長は表情に出さないが、怒っている。「その試合は一年後かね、二年後かね、それとも十年後かね? それくらいならわしも生きておるぞ」
「ご冗談を。今月中ですよ」
「ほう。今月といえば、あと二週間しかないが、そんな大口を叩いていいのかね?」
「もちろんですよ」また自信ありげに答える。
理事長は竜巻高校にサッカーができる人材などいないことを知っている。指導できる教員もいないことを知っている。サッカー部を作ったといっても、寄せ集めだということも見抜いている。よって、自信があるように見せかけている中村の表情と違って、理事長は余裕の表情をしている。
我が雷電高校には、サッカーでもミニ四駆でも勝てるわけなかろう。
「ならば、記念すべき初戦のために、グランドは我が雷電高校が提供しようではないか。電光掲示板も稼働させよう。審判も準備しておこう。はっきりとした日時の交渉は西見校長とやってくれたまえ」
指示された西見が頷く。「後ほど打ち合わせの電話を入れます」
「中村先生、また会おうや」理事長は薄ら笑いを浮かべる。
運転手を残して、二人は校長・教頭室へ向かって行く。背中には余裕が感じられる。雷電が負けるわけないという自信の現れである。
中村は売り言葉に買い言葉で、ついカッとなり、後になって、大変なことになってしまったと後悔した。
半年後くらいに、他校との練習試合ができればいいと考えていたのに、わずか二週間後になってしまったからだ。
ああ、みんなにどう伝えればいいのか。
しかし、時間は待ってくれなかった。
そして二週間後。雷電高校と竜巻高校の初試合の当日。天候は晴れ。気温、湿度ともに絶好のサッカー日和となった。
雷電高校の観客席に、エッホ、エッホの掛け声とともに、理事長を乗せた神輿が到着した。かついでいるのは相撲部の面々である。サッカー部の精鋭たちは試合出場のため、今日は相撲部の精鋭たちに変更されていた。当然、サッカー部員より屈強である。よって、神輿の運行はサッカー部員がかつぐより揺れも少なく、安定していた。そのため理事長はご機嫌である。
やがて神輿は右折の方向指示器をカチカチ点滅させると、メインスタンドのホーム側にゆっくりと下ろされ、専用器具で固定された。理事長はこのまま神輿を下りることなく、一段高いところから観戦することができる。神輿のすぐ横には西見校長が控え、大きなウチワで理事長をあおいでいる。
雷電高校の観客席にはホームゲームということもあり、チアガールや吹奏楽部や応援団など、多数の生徒が学校カラーの黄色いTシャツを着て、集まっている。既にいくつもの旗が振られ、声援も飛び交い、活気に溢れている。
一方、メインスタンドのビジター側の席に座っていたのは、竜巻高校の草野校長と森教頭の二人だけだった。広い観客席には誰も来ていない。
一陣の風が空しく埃を巻き上げた。
「教頭、うちは我々二人だけかね?」校長が寂しい周辺を見渡して言う。
「はあ、何分にもアウェーなものですから」申し訳なさそうに言う。
雷電高校の吹奏楽部が演奏前の音出しを始めた。
「教頭、うちに鳴り物がないのは寂しいなあ」
「二人だけですから、手拍子くらいしかありませんよ」
「では、ちょっと叩いてみるか」
校長と教頭がパチパチと手を叩いてみる。
「やめよう」校長は諦めが早い。「余計にむなしい」
「今日の試合のことは、学校メールで全校生徒に伝えてありますから、ボチボチ来ると思いますよ」教頭は諦めない。
そのとき、反対側のバックスタンドに何か光るものを見つけた。
「校長、あれを見てください。テレビカメラですよ」
「何! なんでこんな高校生の練習試合がテレビで放映されるんだ!?」
「花桐理事長の仕業じゃないですかね」
「あのタヌキオヤジ、金に物を言わせてテレビ局を買収しやがったな。――教頭、この観客席を映されたらマズいよ。ポツンと二人だけだからな」
「校長、いいことを思い付きましたよ。生徒たちに、サッカーの応援に来ればテレビに映ると言えばいいのですよ。みんな、映りたくてやって来ますよ」
「おお、それは名案だな。さっそく頼むよ」
教頭は学校に残っている事務員に電話をかけて、もう一度学校メールを全校生徒に発信してくれるよう依頼した。テレビに映って、スターになれるという校長の緊急メッセージを添付して。
「校長はテレビに出たことがありますか?」
「昔、大雪が降ったとき、派手に転んで、それがたまたま風景を撮っていたカメラに映り込んで、全国ニュースで流れたことがあるよ。あのときは参ったな。今なら顔にモザイクがかかるだろうけど、昔は個人情報だの、プライバシーだの、厳しくなかったからな。会う人、会う人に、お宅、転んでましたなと言って笑われたなあ。わっはっは」
――ピーッ。
「何だ、今の笛は?」
「校長、試合が始まりました」
「何! わしはまだ君が代を歌っとらんぞ!」
「高校の練習試合では歌いませんよ」
「二人で歌おうじゃないか!」校長が立ち上がる。
「座ってください。テレビに映ってしまいますよ。二人だと、君が代をデュエットしてるみたいじゃないですか。国歌を侮辱してはいけませんよ」
雷電の西見校長が双眼鏡を片手にグランドを偵察している。
神輿の上に座っている理事長から声が掛かる。
「竜巻高校の選手はどうかね?」
「まず、使えそうなのはフォワードの二人ですね」
校長が指差す方向にいるのは玉本と足立である。ボールを追いかけて走っている。
「おそらく、どこかの運動部と兼任していると思われます。あのゴツイ体型からしてラグビー部じゃないでしょうか。それと同じくフォワードの小さい選手ですね」
「あれは遠藤だろう」理事長は知っていた。「さすがにスポーツ飛び級だけあって、足が速いな」
「走る遠藤豆と呼ばれてます。しかし、彼はさっきから、ワーワー叫びながら走ってるだけで、一度もボールに触れてません。サッカー経験はないでしょう。しかも、年齢からすると、まだ中学生ですから、そんなに体も出来上がってませんね。あとはゴールキーパーですね」
「おお、金髪の外国人選手だな。助っ人外国人か?」
「おそらく留学生でしょう。かなりの上背がありますが、まだシュートは飛んで来てませんので、その力は未知数です。――使えるのは以上ですね」
「部員たちは高さもないようだな」
「外国人キーパーを除くと、平均身長は百七十センチに満たないでしょうね」
「思った通りの寄せ集めだな。監督とコーチはどういう人物だ?」
校長は双眼鏡をベンチに向ける。
「ベンチには四人います。部長の中村先生と、ユニフォームを着た控えの選手と思われる生徒。あとは監督とコーチでしょうか。しかし理事長、なんだか変ですよ」
「どうした?」
「まず、控えの選手と思われる生徒は白髪で、どう見ても年配者です」
「いろいろと苦労して、老けとるんじゃないかね」
「それと、監督とコーチですけど、これも年配の男性と女性で、首から揃いの十字架を下げてます」
「神頼みで勝とうというのだろう」
「二人とも白い割烹着を来て、白い長靴を履いて、男性の方は頭にねじり鉢巻をしてます」
「なんだそれは? まるで寿司屋の大将と女将じゃないか」
「まさか、寿司屋の大将と女将が監督とコーチをやるとは思えせんが」
「当たり前だ。監督が寿司屋の大将を兼任してるサッカー部なんて聞いたことがないぞ。まあ、二人の素性は分からんが、それだけ人材不足ということなのだろう」
「こんなチームに我が雷電高校サッカー部が負けるはずがありません」
「そういうことだ。テレビ局にも来てもらって、全国放送してるんだ。あんな変なチームに負けたら日本中に恥をさらすことになる」
雷電高校の吹奏楽部が力強い音を奏でている。
一方、竜巻高校の応援席は静かなままだ。
「教頭、うちの吹奏楽部はどうしたんだ?」
「今日は全国大会の地方予選に参加していて不在です」
「雷電高校の吹奏楽部は演奏をしとるぞ」
「彼らは前年、好成績を収めたので、シード校として地方予選を免除されてます」
「そういうことか。向こうは何もかも優秀だな」
「しかし、校長。うちには吹奏楽部とは別の音楽系クラブがあります。――ほら、到着しましたよ」
和服姿の六人の男子生徒がこちらにやって来た。
「教頭先生。遅くなりました」六人が静かに頭を下げる。
「おお、待っていたよ。もう試合は始まっている。さっそく演奏を始めてくれるかね」
「向こうは今、鉄腕アトムを演奏しておるぞ」校長からも声がかかる。「アトムに負けないように頼むぞ」
男子はバックからそれぞれ楽器を取り出して、演奏を始めた。
まず、一人目の男子が小さな笛を吹き始める。
プゥ~。プゥ~。プゥ~。
「教頭、あれは何の楽器かね?」
「ひちりきです」
「小さい楽器なのに大きな音が出るな」
「あまりにも大きい音なので、清少納言はうるさくて聞きたくないとまで言ってます」
二人目の男子は細い竹を束ねたような楽器を吹き始めた。
プァ~。プァ~。プァ~。
「教頭、あれは何の楽器かね?」
「笙(しょう)です。あれは息を吸っても吐いても音が出るのですよ」
「なかなか神秘的な音がするな」
三人目の男子は一メートルほどの楽器を取り出した。
ポロロン。ポロロン。ポロロン。
「あれは何の楽器かね?」
「琵琶です」
「この子たちは何のクラブかね?」
「雅楽部です」
「この子たちの演奏を聞いていると、おごそかな気分になって、太古に思いを馳せたくなるのだが、ピッチを駆け回ってる選手を鼓舞するには至らないと思うが」
「では、残り三人の演奏を聞いていただけますか」
「何を演奏するのかね?」
「三人で尺八を吹きます」
ブォ~。ブォ~。ブォ~。
「おお、これはお正月の定番の曲、宮城道雄の“春の海”ですよ」教頭は名曲が聴けてうれしそうだ。
「教頭、確かに正月らしいゆったりとした気分になれるが、和楽器というのは、サッカーの応援に合っておるかね?」
「しかし校長、うちの音楽系クラブはもう一つあります。そちらは和楽器ではなく、洋楽器を奏でます。十分、期待が持てますよ。――あっ、ちょうど来ました」
「校長先生、教頭先生、遅くなりました」
場違いなピンクのドレスを着た女子生徒が、大きな楽器を抱えて立っていた。
「君は何を演奏してくれるのかね?」
「ハープです」
女子生徒はハープをセットすると、華麗に弾き始めた。
ポロン、ポロン、ポロン。
「校長、素敵な音色ですねえ。――校長?」
「ああ、すまん。寝てた。あまりにも安らいだもので」
雅楽部の和服の六人の男子と、ハープ部のピンクドレスの女子が並んで演奏している。
プゥ~。プゥ~。プゥ~。プァ~。プァ~。プァ~。ポロロン。ポロロン。ポロロン。ブォ~。ブォ~。ブォ~。ポロン、ポロン、ポロン。
和楽と洋楽のコラボである。シュールな光景である。
「教頭、我々がやってることは、おかしくないかね?」
「特に違和感はありませんが」
「なんだか、うちの応援はサッカー場に合わないと思うのだがなあ」
雷電高校が応援ソングの定番、宇宙戦艦ヤマトの演奏を始めた。
「あれっ、校長、大変ですよ!」
「どうした?」
「うちの高校が二対ゼロで負けてます」
神輿の上に座っている理事長から、ふもとで双眼鏡を覗く西見校長に声が掛かる。
「二点差なら、もう竜巻高校に勝つ見込みはないだろう」
「おっしゃる通りです。奴らは所詮、寄せ集め。最初から勝敗は見えておりました」
理事長が神輿から立ち上がって、声援を送る。
「我が雷電高校の選手諸君! 楽勝だぞ。もう手を抜いてもいいぞ!」
走っている雷電高校の選手たちから笑いが漏れる。
「ケガをしないようにボチボチやればいいぞ! あまり真剣にやると、弱い者いじめになるからな! 常に相手のことを考えてあげることが、人生には必要だぞ!」
またも、選手たちが笑い転げる。
「おい、相手の竜巻高校の選手たち! もっと真剣にやりなさい! うちの選手がヒマそうにしとるぞ! もっと攻め込んで行きなさい!」
理事長は相手の選手にヤジを飛ばし始めた。
雷電高校の強力フォワードが波状攻撃を仕掛けていた。竜巻高校のベンチからは、ウマイ寿司の大将こと馬居監督と、女将の馬居清子コーチの声が飛んでいるが、何かを指示しているわけではなく、ただ「がんばれー!」「しっかりー!」と叫んでいるだけだった。二人して、初めての采配なので緊張していて、具体的で的確な指示など出せないのである。
部長の中村はベンチ入りしても、なるべく馬居監督とコーチや選手には口出しをせず、裏方に徹しようと思っていた。二人の方がサッカーに詳しいようだったからだ。それに、この二人に決めたのは草野校長だったし、教頭の支持も得ている。つまり、校長と教頭のお墨付きだ。自分は部長として、サッカー部を創設することに全力を注ぎ、実務は二人に任せればいい。そういう思いでやって来た。そして、こうして試合ができるようにまで漕ぎ着けた。
竜巻高校にはサッカー部がないという七不思議の一つも、消し去ることに成功した。
後は大将と女将に任せよう。わずか三か月だけ指導くれる予定のようだが、今日、強豪の雷電高校に勝てば、その気持ちも変わって来るかもしれない。
中村部長はベンチに腰掛け、黙って戦況を見守っていた。
しかし、チームがピンチになると、そうも言っていられない。思わず立ち上がり、監督とコーチを押しのけて、最前線で選手に指示を出し始めた。
「そんなところで休むなー! もっと走れー! 走って、走って、走りまくれー! サッカーは走ってナンボだ! 動けなくなったときは死ぬときだぞー!」
「そんな大げさな~」選手たちはバテバテである。「僕たちはマグロかよ~」
「何を弱気なことを言ってるんだ! 九十分間、休みなく走るんだー! おい、チャーリー! お前はキーパーなんだから、みんなと一緒になって、ゴールの前を右に左へと、ウロウロ走るんじゃない! お前は唯一、動かないでドンと構えるポジションだ! こらっ、だからといって、そんな所でウンコ座りをするんじゃない! 日本に来て覚えたからといって、ここでお披露目しなくてもいい。スタンドアップだ。少なくとも、今は立っていてくれ!」
馬居監督とコーチは、中村部長が出しゃばって声援を送ることを快く思ってない。選手たちが、部長の声援を聞いて発奮し、間違って勝ってしまったら、困るからだ。次々と試合に負けて、三か月後に、二人揃ってクビになるという計画がダメになってしまう。
二人は苦虫を噛み潰したような顔をして、戦況を見つめていた。しかしその顔は点数がなかなか入らないことへの苛立ちだと、生徒からは見られていた。
そのうちに、雷電高校の強力フォワード選手がミッドフィルダーの学食バイト・宮井と松寿司・中島をあっと言う間に抜き去り、ディフェンスの生き物係の犬井と鳥谷のコンビをかわし、俊足を飛ばして駆けつけたフォワードの遠藤もかわし、ゴールキーパーのチャーリーと一対一になってしまった。
教頭の顔色が変わった。
「校長、大ピンチですよ。三点目を取られたら、サッカーでは逆転が難しいですよ」
「チャーリー君はサッカーをやっていたのかね?」
「イギリスではクリケットをやっていたそうです」
「馬に乗って、棒を振り回すやつかね?」
「それは貴族のスポーツのポロです」
「サッカー経験がないなら、マズいなあ」
チャーリーはゴールの中央に立ち、大きく両手を広げた。
「カモーン! 今こそ、ヤンキーの根性を見せてやる!」
誰もが三点目を覚悟した。勝敗は決まったと思った。
しかし、雷電高校のエースストライカーがシュートを放とうとしたとき、白くて丸い物体が猛スピードで走って来て、ボールとぶつかった。
ボールはコロコロ転がって行く。エースストライカーは空振りをして、スッテンコロリンと転んでしまった。競技場に笑い声が響く。
――ウソだろ。何だ、今のは?
ストライカーが白い物体を目で追ってみると犬だった。
「ポチ!」生き物係の犬井が駆け寄る。「よくやった!」
みんなに見えないように、頭をナデナデしてあげる。生き物係が学校犬ポチを散歩がてら、ここまで連れて来て、グランドの隅に繋いでいたのだが、いつの間にか抜け出して、大好きなサッカーボールを見つけ、突進して来たようだ。
「逃げ出したらダメだろ、ポチ!」
敵が見ている前では叱るフリをしておくが、目は笑っている。校庭でサッカーボールを使って遊ばせておいたことが、こんなときに役に立つなんて。
ポチの名付け親である中村部長を見てみると、ベンチ前で大喜びになって、はしゃぎ回り、監督とコーチ夫婦に後ろから羽交い絞めにされていた。こんなシーンを雷電高校に見られてはいけない。ポチが我々の回し者だとバレてしまうし、犬に助けられた情けないチームだと思われてしまう。
「中村先生、落ち着いて、落ち着いて」ねじり鉢巻きの馬居監督が止める。
「こんなときに落ち着いてられますか! 私が学校犬として引き取ったポチが一矢報いてくれたのですよ! 大将! 試合が終わったら、ポチへのご褒美として、マグロのトロの炙りを用意してくれませんか!」
「はいはい、分かりました。大トロでも中トロでも小トロでも、心を込めて炙りますから、とりあえず、ベンチに座っていてください」
雷電高校の監督が審判に抗議をしたが、犬はグランドに転がっている石と同じく不可抗力だとして、そのままスルーされた。
ゴール前に転がっていたボールを、チャーリーが思い切り蹴っ飛ばし、
「ゴーゴー! 行け行けー!」フォワードをはやし立てる。
「どうだ、みんな見たかー! これがヤンキーの根性だぜー! 雷電高校がナンボのもんじゃーい! おーっ!」
チャーリーはゴール前で、片手を天に向かって突き上げるが、ボールには指一本触れなかった。
ポチに助けられたことは忘れている。
すでに二点取られていることも忘れていた。
「校長、教頭、お待たせいたしました」
二人が振り返ると、定年間近の美術の野呂先生が立っていた。
いつものグレーのスーツである。
「野呂先生、来てくださいましたか!」教頭がうれしそうに出迎える。
「吹奏楽部が不在ということで、音楽のテープを流そうと、家からこれを持参いたしました」
かなり古い型のカセットテープレコーダーを掲げる。
「おお、それはいい。さっそく大音響で流してくれたまえ」校長もうれしそうだ。
しかし、野呂は先ほどから続いている雅楽部とハープ部の演奏に目をやる。
「彼らを気にすることはない」校長が言う。「彼らには彼らの独自の世界がある。先生は少し離れた場所で流してくれればいい」
「承知いたしました」
「派手なのを頼むよ」
野呂は演奏中の音楽系クラブの隣に移動し、ショルダーバッグからたくさんのカセットテープをガラガラと取り出した。野呂の個人的な昭和コレクションの一部である。
やがて、カセットテレコのスイッチが押され、大音響で曲が流れ出した。さっそく校長が耳を傾ける。
「教頭、これは何の曲かね?」
「美空ひばりの“愛燦燦”ですな」
観客席に座った野呂は目をつぶって曲に聞き入っている。
そして、曲が変わった。
「教頭、これは何の曲かね?」
「都はるみの“アンコ椿は恋の花”ですな」
野呂は体を左右にスイングしながら聞いている。
「教頭、やっぱりおかしくないかね?」
校長が疑問を呈するが、続いて流れて来た曲は、
「舟木一夫の“高校三年生”ですな」
「うーん、ちょっと近づいて来たか。だが、この場に合わんと思うのだがな」校長が野呂に叫ぶ。「野呂先生、ここはサッカー場ですよ! 昭和の歌謡ショーをやる場ではありませんよ! もう少し違う曲はないかね」
野呂はカセットテープの山を崩して、一本のテープを取り出した。
「では校長、これはどうでしょうか?」
元気が出そうなイントロが流れて来た。
「教頭、これはいいね。何の曲かね?」
「青い三角定規の“太陽がくれた季節”ですな。“飛び出せ!青春”の主題歌ですよ」
「いいじゃないか。これで行こう。選手諸君もやる気が出るだろう。――野呂先生、これでOKだ! こういう“青春もの”をどんどん流してくれ! 演歌は後で野呂先生が家に帰って、風呂の中で聞けばいい」
「校長。大変です!」教頭が叫んだ。
「どうした?」
「うちが一点入れて、二対一になってます」
「なんでだ!? ――おい、そこの君」校長はひちりきを吹いている男子に声をかける。「うちの一点はどうやって入ったのかね?」
ひちりき君は演奏を止めて説明する。
「パスを受けた遠藤君が、疾風のごとく走り出し、敵を置き去りにして、三十メートルくらい独走してから、見事にゴールを決めました」
「すごいじゃないか、遠藤豆君!」
ひちりき君は、なぜ校長先生がそんな貴重なシーンを見てなかったのか不思議に思いながらも、チームの勝利を願って、ひちりきの演奏を再開した。
プゥ~。プゥ~。プゥ~。
神輿の上に座っている理事長から、選手に檄が飛ぶ。
「雷電高校の君たち! 一点返されてどうする! あんな遠藤豆に、グランドを縦横無尽に走り回られるんじゃない! 手を抜いてもかまわんが、手を抜きすぎてもイカンぞ!」
理事長は興奮して神輿の上で立ち上がる。校長があわてて駆け寄る。
「理事長、気をつけてください! ここは落ち着いて!」
「落ち着いていられるか! あの寄せ集め集団に一点を入れられたんだぞ! こんな屈辱があるか!」
「まだ勝ってますし、一点くらい、すぐに取り返してくれますよ」
理事長はしぶしぶ座り込む。
「校長、教頭、ただ今、到着いたしました」
「おお、岡戸さん、遅かったじゃないですか」教頭がうれしそうに迎える。
「これを持って来ました」
用務員岡戸の脇に巨大な旗が寝かせてあった。
「敵の雷電高校にはたくさんの応援旗が揺れてますが、うちにはありません。ですので、作ってみました。アルミのポールは私が用意して、旗の部分は手芸部の部長の大久保田さんに頼みました。竜巻高校という校名から、竜巻をデザインに取り入れて、校章と組み合わせて、素晴らしい応援旗になってます」岡戸は自慢げに言う。
「ほう、これは大きい旗ですなあ」校長は感心する。「よく短期間で作ってくれましたなあ」
「私はサッカー部の用具係に任命されましたから、これくらいはやっておこうと思ってます。ですが、一つ問題がありまして、この旗は縦が五メートル、横は六メートルもあります。重すぎて、一人では上げられません。ここまでは引き摺って来ました。おそらく数人がかりでないと、立てられないと思います。そこまで考えてなかったのは、私の不徳と致すところです」
「この通り、うちの応援席には人がおらんから、私たちが手伝いましょう」
「いや、校長と教頭にそんな力仕事をさせるわけにはいきません。私が何とか立てましょう。私が作った応援旗ですから、責任を持って立てますよ」
岡戸は、演奏している皆さんの邪魔にならないようにと、端の方へ巨大な旗をズルズルと引き摺って行った。
「草野校長!」
呼ばれた校長が振り向いた。
一人の老人が立っていた。
「これは、騒音ジジイではなく、あのときの……。その節は失礼いたしました」
いつぞや、生徒の声がうるさいと文句を言いに来たじいさんじゃないか。
校長は老人の名前を忘れたので、ごまかして、挨拶だけする。教頭もあわてて頭を下げる。
ここまでしつこく因縁を付けに来たのかと不安になるが、
「新設されたサッカー部の初の対外試合が雷電高校であると聞きましてな。ここまでやって来たのですよ」
どうやら、騒音のクレームではなさそうだ。
「なぜ、そんな詳しいことをご存じなのですか?」
「わしの家まで校内放送が聞こえてくる」
やはり、クレームか?
「これは申し訳ないです。ボリュームは下げているのですが」校長はすかさず謝罪する。隣で教頭も頭を下げる。
「いや、かまわんよ」老人はあの時とは違って、柔和な表情をしている。
つまり、クレームではなく、この試合が気になって、やって来たということらしい。
やはり、いつも安酒を飲んでいる人に大吟醸菊理媛の付け届けは大きい。なんといっても五万円も注ぎ込んだのだ。花桐理事長からせしめた裏金だが。
そして、その後も老人は酒を要求してくるようなことはしなかった。教頭の聞き込みによると、じいさんは元教師らしい。元チンピラでなくてよかった。
じいさんは辺りを見渡して言う。
「雷電高校の応援に比べたら、竜巻高校の応援は規模が小さくて、しょぼいのう。ひとつ、わしが応援を買って出てやろう」
「それは、どういったことで?」教頭が尋ねる。
「これだよ」
騒音じいさんは茶色いジャケットのポケットから楽器を取り出した。
「ラッパですか!?」
「騎兵隊が吹くあれだ」
「あれと言いますと?」教頭には分からない。
「あんた、ジョン・ウェインの駅馬車を見とらんのか。あの映画の
中で、騎兵隊が吹いておっただろう。――あれだよ」
騒音じいさんは雅楽部とハープ部の間に立って、突撃ラッパを吹き始めた。
パッパラ、パッパ、パーッ!
学食バイト・宮井と松寿司・中島とラッパー安藤は、三人がかりで敵に襲いかかり、ボールを奪い取った。一対一では勝てないから、複数で向かって行くようにと、馬居監督から指示が出ていたのだ。その指示は監督とコーチと部長の三人が無い知恵を振り絞って考えたものだったのだが、生徒たちは何も知らない。うまく奪えたので、さすが馬居監督だと思っている。
そのボールを三人の間で大切に回している。点数は二対一で負けているが、一点差なら追い付いて逆転もできる。あの雷電高校に勝てるかもしれないのだ。
「あーあ、お腹が減ったなあ」宮井が敵陣に向けて、ボールを運びながら言う。
「今日みたいに学食のバイトが休みの時、昼飯はどうしてるんだ?」安藤が訊く。
「昼飯は抜きだよ」
「マジかよ」安藤はボールを受けながら言う。
この試合が終われば、中村先生から三千円もらえることは黙っておく。
「倒れるなよ、宮井」安藤からボールを受けた中島が心配してくれる。
「慣れてるから大丈夫だよ。それよりも、雷電に比べて、うちの応援はセコイなあ」
「今日は吹奏楽部が来てないからな」中島がボールをキープしたまま言う。
「それにしても、雅楽部とハープ部と野呂先生のカセット応援だよ。わびさびを感じるよ」
「さっきから、用務員の岡戸さんが応援旗を立てようとしてるんだけど、重くてあげられないみたいなんだ」中島から再びボールを受けた安藤が言う。
「あんなにデカいと、上がらないだろうよ」宮井が近づいて来て言う。
パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。
「何だ、この音は!?」ピッチに立つ、全選手が驚いた。
騒音じいさんが突撃ラッパを大音響で吹き始めたのだ。
そして、大声で叫ぶ。
「竜巻高校の諸君! がんばるのじゃ~。がんばるのじゃ~。がんばるのじゃ~」
パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。
パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。
草野校長は思った。騒音じいさん自身が騒音だ。
先ほど、応援席に英語の酒井先生がやって来た。そして、東北地方の三つの祭――盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、青森ねぶた祭りの踊りを、一人で次々と踊って、選手を激励している。周りにいる生徒たちはプレイする選手たちよりも、踊る酒井を見ながら、カメラを向けている。応援よりもこっちの方が大切だ。
東北地方から出て来たばかりで、野暮ったかった酒井だったが、最近は訛りも消えて、すっかり、あか抜けたと評判であった。元々、東北美人だったのだが、その美しさがさらに際立って来たと生徒たちはウワサをしていた。
その原因は、ラッパー志願の安藤を二度に渡って秒殺したことで自信を付けたところにある。安藤の足の骨のヒビの本数が、酒井先生の元気の源となっていたのだが、生徒たちはそこまで深く酒井の気持ちを読んではいない。
この東北地方の三つの祭の踊りは、ラッパー安藤が教室で踊っていたものである。あまりにもヘタクソで目も当てられなかったため、それを、本来のキレのある躍りで完全再現しているのである。できれば、ヘタクソだった安藤に見せてやりたいものだと思っていたところ、ちょうど目の前に安藤がボールを追って、やって来た。
「おい、安藤!」踊りを中断して、観客席から声をかける。
「あっ、これは酒井先生! なんと素晴らしい踊りでございましょう。僕の踊りとは月とスッポンくらい違います。きっと先生は将来立派なラッパーになれます。僕もうかうかと……」
「黙れ! うちは一点負けてるだろ。私の踊りなんか見てないで、さっさと点を取って来い!」
「はい、すいません!」
「すぐに走れ!」
「はっ、ただ今!」
ラッパー安藤は骨に四本のヒビが入った足で駆け出した。
「校長、あの方たちは!?」
黒と白の修道服を着たシスターが静々と観客席に入って来る。その人数は二十名。先頭を優雅に歩くのは教会のシスター、マリー・アマーチェである。
「校長先生、教頭先生。シスター全員で応援にやって参りました」
目の前に二十名のシスターが集結した。
「これはわざわざ申し訳ないです」
校長も教頭もあわてて立ち上がり、胸の前で十字を切る。
「楽器は持参しておりませんので、私たちは賛美歌で応援したいと思います」マリー・アマーチェが鈴を転がすような声で言う。
「はい、よろしくお願いいたします。アーメン」校長がお願いをする。
「一点ビハインドで負けてます。逆転できますように。アーメン」教頭もお願いする。
シスターたちは、カセットテレコで音楽を流している野呂先生の隣に整列した。
美しく、清々しい女性たちの集団を目の当たりにして、野呂先生の口はポカンと開いたままだ。できれば、彼女たちと写真を撮りたいものだと考えている。
「野呂先生! 曲が止まってますよ」校長から声が飛ぶ。
「ああ、すいません。すぐにカセットテープを入れ替えます。アーメン」
二十名のシスターによる賛美歌の合唱が始まった。
一曲目は“アメイジング・グレイス”だ。世界中で最も愛され、歌われている曲の一つである。美しく清らかな声が場内に響き始めた。
両校の応援団が静かになり、選手たちもプレーを忘れて、歌に聴き入る。ヤジを飛ばしていた花桐理事長さえも静かになる。竜巻高校の選手たちは、我を忘れて大喜びだ。
「見ろよ、僕たちの応援席にシスターが来てくれてるぞ!」
「マリー・アマーチェさんだ! 他にもキレイどころがいっぱいいる!」
「すげえ、リアル“天使にラブ・ソングを”だ」
次に歌われたのは“主よ 御許に近づかん”であった。またもや、澄み切った声がグランドまで流れてくる。今まで、雷電には勝てそうにないと思い込んでいた竜巻高校の選手だったが、これらの歌を聴くことにより、彼らのモチベーションは爆上げした。
「勝てるぞ、僕たち! アーメン」
「逆転するぞ、僕たち! アーメン」
歌の力は素晴らしい。人々に大きな力を与える。やる気を与える。希望を与える。
たとえ、“主よ 御許に近づかん”が、タイタニック号沈没のときに演奏されていた曲だとしても。
なぜ、この曲がチョイスされたのか分からないが、幸いなことに、この曲を知っている生徒はいないようだった。
「いやあ、校長先生、教頭先生。お待たせしました」
二人は同時に振り向いた。今日はよく後ろから呼ばれる。
「これは諏訪一大寺の星輝和尚じゃないですか!」
「サッカー部の試合があると聞きましたので、修行仲間を引き連れて、応援にやって来ましたぞ」
二十名の袈裟を着たお坊さんがずらっと並んでいた。
「これはわざわざ申し訳ないです」
校長も教頭もあわてて立ち上がり、胸の前で手を合わせる。
今日は胸の前で十字を切ったり、手を合わせたり、忙しい。
「よろしくお願いいたします。ナンマイダ」校長がお願いをする。
「一点ビハインドで負けてます。逆転できますように。ナンマイダ」教頭もお願いする。
アーメンと言ったり、ナンマイダと言ったり、忙しい。
二十名のお坊さんが、二十名のシスターの隣に並んだ。
ポク、ポク、ポク、ポク。
お坊さんが一人に一つずつ携帯している木魚が鳴らされた。
「まか はんにゃー、はーらー、みったー、しんぎょうー」
般若心経が朗々とグランドに響き渡る。またもや両校の応援団が静かになり、選手たちもプレーを忘れて、お経に聴き入る。またもやヤジを飛ばしていた花桐理事長も静かになる。ここでヤジでも飛ばしたら、仏様のバチが当たるんじゃないかと、一抹の不安を抱いたからだ。
「見ろよ、僕たちの応援にお坊さんが来てくれているぞ!」
「すげえ! 地味なお坊さんがいっぱいいる!」
竜巻高校の選手は少し喜んでいる。彼らのモチベーションはさらに少しだけ上がった。
「教頭先生、神と仏の応援があれば、鬼に金棒だな」校長はうれしそうだ。
「神なのか、仏なのか、鬼なのか、よく分かりませんな」
「それにしても、雷電高校のように、吹奏楽部が演奏して、チアガールが踊るのが普通の応援というものではないかね。うちの学校と来たら、ひちりきに、笙(しょう)に、琵琶に、三本の尺八に、ハープに、突撃ラッパに、賛美歌に、般若心経だ。和と洋とこの世とあの世の総動員だぞ。――こんな応援はおかしくないかね。それとも、ワシの方がおかしいのかね?」
賑やかになった応援席の中で、校長の頭の中は混乱する。
スコット山田はチャーリーがいないため、いつもより一台少ない、六台のバイクで街を疾走していた。
あれほど止めたのに、チャーリーはサッカー部に入ってしまった。新任の中村先生に、部員が集まらなくて困っているから助けてくれと口説かれて、人のいいチャーリーは騎士道精神を発揮したのかもしれない。といっても試合があるときだけの、助っ人外国人選手だという。
そして、今日が初の対外試合で、敵はライバル校の雷電高校らしい。
「俺たちには関係はない。いつものように、バイクをぶっ飛ばすだけだ」
今日も、法定速度を守ってノロノロと走ってる車を蹴散らし、追い抜いて来た車を六台で取り囲んで、罵声を浴びせて、さんざん脅した上で、一気に抜き返した。
――そして、赤信号で全台止まった。
信号待ちをしている間、スコット山田はふと横を見た。昔ながらの小さな電気屋があった。
近くに大型家電量販店があるのに、こんな場所でがんばってるのか。すげえな、街の電気屋さん。
小さなショーウィンドーにテレビが置かれて、ちょうど竜巻高校と雷電高校のサッカーの試合を放映していた。テレビ画面が通りに向けてあり、通行人が群がっている。――昭和でよく見かける風景だった。
たかが練習試合だぞ。なぜテレビでやってるんだ?
花桐理事長が裏で動いていることをスコット山田は知らない。
そこへ黄色いジャージ姿の学生四人が通りかかった。雷電高校の学生たちだ。
「おい、見てみなよ。うちの高校のサッカーやってるぞ。二対一で勝ってるじゃん」
「当たり前だろ。竜巻高校みたいなアホ学校に負けるかよ。あいつら新設サッカー部だぞ」
「だったら、一点はご祝儀だろ。本気でやったらゼロに抑えて完勝だな」
「見ろよ、キーパーは金髪の外国人だ。助っ人外国人かよ」
そのとき、雷電高校からシュートが放たれた。チャーリーは横っ飛びになって、それを防いだ。手の先に触れたボールは、ゴール前をコロコロ転がる。そのボールに向かって、チャーリーはさらに飛んで、体を使って押さえ込んだ。雷電高校のフォワードは勢い余ったフリをして、チャーリーにボコボコと蹴りを入れる。
「いいぞ! やれー!」テレビを囲んだ四人が歓声をあげる。「金髪をぶっ殺せー!」
審判が駆け寄り、チャーリーはふらつきながら、立ち上がった。イエローカードは出ない。
「イエローカードなんか出るかよ。ホームゲームだぞ」四人は笑う。
「助っ人外国人も大したことなかったな。デカいだけの見かけ倒しだ」
「竜巻高校が勝てるわけない。勝つにはあと二点入れなきゃならないんだぞ」
「無理だな。アホ学校だからな」
四人の会話はバイク音よりも大きく、竜巻高校の六人に丸聞こえだ。
スコット山田の表情が見る見る変わっていく。
「あれ見てみなよ。応援旗が上がらないんだ」
テレビには巨大な応援旗を一人で上げようと奮闘している岡戸の姿が映し出された。映ってることも知らずに、歯を食いしばっている。
「あのオッサン、何をやってるんだ。そんなデカい旗が上がるわけないだろ」
四人はテレビ画面を指差して、爆笑する。
「うちの理事長が言ってたわ。あいつらが雷電高校に勝つには三十年早いってな」
「行こうや。結果は見えてる。うち大差で楽勝だ。こんな汚い電気屋の軒下で見てるだけ時間の無駄だ」
四人は笑いながら行ってしまった。
信号が青になった。憤怒の形相をしたスコット山田が振り向いて、五人の仲間に言った。
「今から雷電高校に行くぞ!」
六台のバイクは一気にUターンした。先頭のスコット山田は歩道に乗り上げ、さっきの四人組に後ろから順に蹴りを入れていく。
ボコッ、ボコッ、ボコッ、ボコッ。
うずくまる四人をバックミラーで確認して、車道に戻ると、猛スピードで走り出した。
背中を足で蹴られた四人は息が詰まり、何が起きたのか分からないまま、歩道に座り込んでいた。
競技場では、野呂先生が流すカセットテレコから、ドラマ“われら青春!”の主題歌“帰らざる日のために”が聞こえて来た。透き通るような三人の女性のハーモニーが競技場に流れる。
真っ先に反応したのはベンチ前に立っている馬居監督だった。
「おお、この曲は!?」
いや、懐かしいなあ。あの頃、青春ドラマを必死に見ていたものなあ。思い出すだけで涙が出そうになるなあ。女将にも教えてやらないとなあ。
女将を見ると、ベンチの端に座っている。日焼けが気になるらしい。ベンチの屋根は透明なので、そんなところに座っていても陽が射すから、あまり変わらないと思うのだが。
「おい、今流れてる応援曲を聞いてみな。“帰らざる日のために”だぞ」
女将も同年代である。青春ドラマに涙した世代である。
曲を聴くために、女将はいやいやベンチから出て来て、しばらく耳をすます。
「えっ!? これを歌ってるのは“いずみたくシンガーズ”じゃないの?」
「これは“キャンディーズ”だよ」
「へえ、“キャンディーズ”がカバーしてるんだ。それは知らなかったわ」
曲はサビの部分に差しかかる。
「おお、ここだ。このサビを歌ってるのは我らがキャンディーズのスーちゃんだ!」
「この高音部はすごいねえ。心に染み渡るねえ。さすがスーちゃんだねえ」
気だるそうにしていた女将は、スーちゃんの歌声を聞いて元気になる。
馬居監督は、すぐ目の前を走っていたラッパー安藤を捕まえた。
「安藤君、みんなに伝言を頼むよ。スーちゃんも応援していると」
「スーちゃんですか?」
「そうだ、スーちゃんだ。頼んだよ!」
ラッパー安藤は、そばに走って来た学食バイトの宮井に声をかける。
「監督からの伝言だ。スーちゃんも応援している」
「――誰、その人?」
「いや、分からんが、みんなに伝言しろということだ」
宮井は駆け出し、前方を走っていた松寿司・中島に追い付く。
「監督からの伝言だ。スーちゃんも応援している」
「誰だって? どこの国の人?」
「それが分からないんだ」
「金森に訊いてみよう。あいつ韓流スターに詳しいから」
中島はいったん下がって、ディフェンスの生徒会副会長の金森の元に行く。
「監督からの伝言だ。スーちゃんという韓流スターが応援してくれている」
「韓流スターにスーちゃんなんていないよ。名前からして、中国の女優さんじゃない?」
「そうか。とにかく、みんなにこの伝言を回してくれということだ」
「分かった」金森は生徒会長の平井に近づく。
「金森! 監督からの伝言だ。スーちゃんという中国の女優さんが僕たちを応援してくれている」
「なんで?」
「それが分からない。でも、全員に伝えろということなので、生き物係の二人とチャーリーにも伝言を頼むよ」
「よく分からないが、分かった。伝えに走るよ」
ミッドフィルダーの松寿司・中島は、フォワードのラグビー部の玉本の元に駆け寄る。
「監督からの伝言だ。スーちゃんという中国の国際女優が僕たちを応援してくれている」
「意味がわからないけど」
「まあ、とにかく、足立君にも伝言を頼むよ」
玉本は同じラグビー部の足立のところに走る。
「監督からの伝言だ。スーちゃんというハリウッド映画にも出演経験がある中国の国際女優が僕たちを応援してくれているらしい」
「どういうこと?」
「よく分からないのだが、遠藤君にも伝えてくれ」
足立がやっとの思いで、俊足の遠藤に追い付く。
「遠藤君、監督からの伝言だ。スーちゃんというハリウッド映画にも出演経験があるアカデミー賞主演女優賞最有力候補の中国の国際女優が僕たちを応援してくれている」
「なんで中国の方が僕たちを?」
「たぶん、あれだ」玉本がバックバックスタンドを指差す。テレビカメラが見える。「あのカメラだ。衛星放送を使って、この試合を中国全土で放映してるんだ」
「十四億人の中国人が僕たちの試合を見ていて、その中のスーちゃんというものすごくキレイな国際女優さんが、応援してくれているということ?」
「そういうことじゃないかなあ」
「十四億の中国国民と、そんな美人に応援されたら、僕たち、がんばるしかないね!」
スーちゃんのお陰で、さらに彼らのモチベーションは上がった。
「ありがとう、スーちゃん!」
馬居監督は晴れ上がった空を見上げて、手を合わせた。
岡戸は必死になって、横倒しになっている巨大な応援旗を立てようと頑張っている。
なにしろ、これを作ったのは自分だ。自分のことは自分でしなくてはいけない。子供の頃からそう言われていた。しかし……。
「ああ、ダメか。設計ミスだ。ビクともせんわ。手は痛いし、腰も痛いし、足もダルいし、疲れで目は霞んでくるし。――もう体に力が入らん」
岡戸は恨めしそうに旗を見下ろす。いくらなんでも大きすぎるよなあ。新入生だから頑張ってみましたと言われても、手芸部の大久保田さん、張り切り過ぎなんだよなあ。まさか、こんな大きな旗が出来上がってくるとは思わなかったものなあ。寸法を指定しておけばよかったなあ。
「まあ、仕方がないか。さっきは断ってしまったけど、校長と教頭に助けを求めに行くか」二人の元へ行こうとすると、
「岡戸さん、そんな根性無しじゃ、女にモテませんよ」
岡戸が振り返った。
男子生徒が立っていた。
「スコット山田君!」
「俺に任せてください」
「いや、いくら力持ちのスコット山田君でも、これは持ち上がらんぞ」
「俺一人じゃ無理です。だが仲間で力を合わせれば、できないことはないですよ」
後ろから五人の仲間がやって来た。全員で六人になった。
「みんな、竜巻高校ヤンキー部の根性を全国に見せてやろうや!」
「おう!」井川がデカい声で答えてくれる。
「チャーリー、見ておけよ。これがヤンキーの心意気だぜ。さっきお前のことを、見かけ倒しだと言ってバカにした雷電の四人組を見返してやるからな!」
「よしっ、やるぜー!」六人の声が応援席に響いた。
岡戸はあっけに取られて、ゴツい六人を見上げた。
すでに試合は後半戦に入っている。しかし、あと一点が遠かった。雷電高校はこのまま余裕で逃げ切ろうと、適当に走っているだけだ。竜巻高校の寄せ集めサッカー部のために全力を尽くすなんて、力の無駄だと思い始めているからだ。
こんな奴らには勝って当たり前。練習にさえならないし、勝ったところで、誰にも褒められない。
雷電高校の選手全員がそう思いながら、プレーを続けている。
「みんな、あれを見ろ!」キーパーのチャーリーが大声を上げて、応援席を指差した。
竜巻高校の応援旗が今、立ち上がろうとしている。
「ウソだろ」雷電の選手も驚いて、足を止める。
「起き上がっていくぞ」他の選手も釣られて立ち止まる。
「あんなものが上がるのか」花桐理事長も驚いて、神輿の上に立ちあがった。
双方の応援団も手を止めて、固唾を飲んで見守る。審判さえも立ち止まり、競技場全体が静まり返る。
やがて、応援旗がスコット山田たちヤンキー部六人の手によって立てられた。
倒れないように六人が十二本の腕で支える。
そこへ、ゆったりとした風が吹いて来た。大きな旗が大きく揺れる。
「見えてるか、チャーリー! これが俺たち竜巻高校の旗だぞー!」
スコット山田がアルミのポールにしがみついたまま叫ぶ。
旗の真ん中には、竜をモチーフにした校章が描かれ、天に舞い上がる竜巻がデザインされている。手芸部の大久保田さんによる渾身の力作であった。
「僕たちの旗が立ったー!」「立ったぞー!」
竜巻高校サッカー部に歓喜の渦が巻き起こった。チャーリーは、巨大な応援旗が再び倒れないように、懸命に押さえるヤンキー仲間に向けて、こぶしを突き上げた。
「みんなー、しっかり見えてるぜー!」
ピー、ピー、ピー。
旗の周りに集まった男たちが笛を吹き始めた。
「教頭、あの人たちは何だね?」草野校長が不思議がる。
「どう見ても警官ですな」教頭も分からない。
旗の周りで十人の警官が笛を吹いて応援している。
「岡戸さんがうれしそうに話し掛けてるので、知り合いじゃないですかねえ」
深夜、二宮金次郎像を捕まえようとしている岡戸を不審者と間違えたときの警官が、小笠原警部補を筆頭にして、応援に来てくれているのだが、校長も教頭もその経緯を知らない。
ピー、ピー、ピー。
「あんなにたくさんの警官がなぜ競技場に来れるのかね?」
「非番じゃないですかね」
「一度に十人もの警官が非番になって、警察署はちゃんと機能するのかね」
「今日は小倉優子が一日署長を務める日ですよ」
「なるほど。ゆうこりんなら安心だな」
ピー、ピー、ピー。
笛を吹く十人の警官たち。中には警棒を振り回して、声援を送っている者もいる。
「教頭、やっぱりうちの応援は変じゃないかね?」
「いえ、何ら常識は外れてないと認識しておりますが」
一方の雷電高校は竜巻高校の旗が立ち上がったことに驚いていたが、
「あんな旗に構うな。自分たちのサッカーをやろう!」
「そうだよ。サッカーを楽しもう!」
気合を入れ直したが、どこからか数匹の虫が飛んで来て、選手の邪魔を始めた。目の前をビュンビュンと通り過ぎる。
「なんだ、こいつらは。あっちへ行け!」みんなは必死で追い払う。
この虫こそは、犬井が登山研修の時、用務員の岡戸さんに虫かご込みで、八百円で買わされたトンボとカナブンと蝶の昆虫三点セットであった。結局、あの日は昆虫セットを三つも買わされたのである。合計二千四百円である。
用務員さんが生徒相手に商売をするか?
お金への執着心さえなければ、いい人なんけどなあ。
しかし、生き物係としては、昆虫も大切に扱わなくてはいけない。
今日は天気も良かったので、ここまで連れて来て、虫かごから解放してあげることにした。すると、虫たちは長い間閉じ込められていた腹いせなのか、雷電の選手に襲いかかったのである。
見事に屹立した旗に見とれて止んでいた竜巻高校の応援の演奏が再開した。雅楽部、ハープ部、カセットテープ、突撃ラッパ、賛美歌、般若心経……。和洋折衷、バラバラの応援が奇跡的に一体化して、選手を鼓舞する。
「あれを見ろ!」またチャーリーが叫ぶ。「電光掲示板を見ろ!」
竜巻高校の選手が振り向いて、電光掲示板を見ると、二対二になっていた。
「あれ、僕たち、追い付いてる」平井生徒会長が呆然とする。
「なんでだ?」金森副会長も分からない。
「みんな、ゴール前を見ろよ!」松寿司・中島が指差す。
ゴール前では小さな遠藤がフライパンの上で豆が弾けるようにピョンピョンと跳ねていた。応援旗に見取れ、さらに九匹の昆虫の攻撃で敵がアタフタしている隙を突いたのである。
「飛び級の遠藤豆君だ! このドサクサに紛れて、シュートを決めてくれたんだ!」
「同点になったぞ! あの雷電相手に二点差を追い付いたぞ!」
「勝てる! マジで僕たち勝てるんじゃない」
「応援席のみなさん、ありがとー!」
「シスター、お坊さん、ありがとー!」
「中国の国際女優スーちゃん、ありがとー!」
「学校犬ポチ、ありがとー!」
「ヤンキー、ありがとー」
「応援旗をありがとー!」
「お巡りさん、ありがとー!」
「虫たち、ありがとー!」
竜巻高校イレブンは歓喜の声を上げた。
応援席では生徒たちが音楽に合わせて声を張り上げ、肩を組んで体を揺すり、一丸となって応援している。先日、小久保“マドンナ”先生が体育館で仕掛けた暗闇パーティのお陰で、男子生徒と女子生徒はすっかり仲良くなっていたのである。
だが、隙を見て、点を取ろうとしたのは、雷電高校も同じだった。同点になり、気が緩んでいた竜巻高校の選手を蹴散らし、またもや、エースストライカーが簡単にゴール前まで、ボールを持ち込んでしまった。
今度はチャーリーも油断していた。一瞬にして顔面が蒼白になった。あわてて身構えるが、敵はすでにシュートを放つ体勢になっている。
ダメだ。今度は間に合わない。三点目が入る。もうポチは来てくれない。――誰もがそう思った。
そのとき、黒くて大きな物体が猛スピードで走って来て、ボールを蹴飛ばした。ボールはコロコロ転がって行く。
エースストライカーは空振りをして、またもや、スッテンコロリンと転んでしまった。競技場にまたしても、笑い声が響いた。
ウソだろ。何だ、今のは? また犬か? 黒い犬か?
エースストライカーが周りを見渡すが、犬一匹いない。チャーリーもあたりをキョロキョロ見渡している。
審判も呆然としている。今度は何が起きたか誰にも分からない。
いや、たった一人だけ、その正体を見破った人物がいた。用務員の岡戸だった。岡戸は応援旗のそばに立っていた。そして、確かに見た。
二宮金次郎が猛スピードで走って行って、ボールを蹴飛ばしたところを。
「二宮君、来てくれたのか。昼間に化けて出て来てくれて、ありがとう!」
二宮金次郎像を撤去せず、残すことになったことへのお礼だと思った。岡戸は竜巻高校の二宮金次郎像の方角に向けて、頭を下げた。そして、思った。江戸時代にサッカーがあったのだろうか? 草履でボールを蹴飛ばして、痛くなかったのだろうか? ボールを蹴飛ばすときくらい、薪を下しておいた方がいいのではないか?
グランドには魔物が住んでいると言われる。何も知らない両校の生徒たちは、きっとこれは魔物のしわざだと思った。
魔物呼ばわりされているとも知らず、二宮金次郎像は竜巻高校に戻るため、薪をかついだまま、懸命に商店街の中を駆け抜けていた。
その顔には笑みが浮かんでいたことを誰も知らない。
この頃から、竜巻高校の応援席には続々と生徒たちが集まり出した。テレビに映って、スターになれるという校長のメッセージ付きの学校メールを読んで、駆け付けた生徒が多数いたからだ。
そして、竜巻高校のベンチを見て、ウマイ寿司の大将と女将が指揮を執っていることに生徒たちは目玉をひんむいて驚いた。
「監督はクリスティアーノ・ロナウドじゃないのかよ!」
「信じてたのは、お前だけだよ」
「マジかよ。せっかくサイン色紙を持って来たのによ」
「寿司屋のオヤジのサインをもらってどうするんだよ」
「普通は客の方からサインをして、店に飾るのものだろう。まったく、ふざけてるよな」
「お前、そんな顔をするなよ。あれ見てみな」
正面のバックバックスタンドからテレビカメラがこちらを狙っていた。
「ヤバいじゃん。映ってるじゃん。どうすればいいんだ?」
「こういう時は、スマイルに決まってるだろ。――みんな、テレビに映ってるぞー! 竜巻高校の生徒は、いつでもスマイルを忘れるなよー! とんでもないことが起きても忘れるなよー! すぐスマイルするべきだぞー! 俺たちは子供じゃないからなー!」
集まって来た生徒の中に、色付きの小さな四角いパネルを持った者たちが多数いた。男女混合の彼らは、木魚を叩いて、般若心経を唱えているお坊さん集団の隣に、次々と陣取った。
全校生徒が総動員され、その人数は八百人を越えていた。やがて、その席に大きく“がんばれ”の文字が現れた。そのパネルを頭の上に掲げて、文字を作っていたのだ。
「あれは昔、甲子園の高校野球大会でよく見られた人文字ではないか!」校長が驚く。
「PL学園の名物でしたなあ」教頭は懐かしがる。
続いて、人文字が作ったのは“ぜったい勝利”である。
「すごいな、教頭。勝利なんていう細かい文字を、よく人文字で作れるな」
「そうですなあ。あれは誰が主導しておるのでしょうかねえ。――あっ、君!」
このときになると、応援席にはたくさんの人が行き交っていた。教頭は目の前を歩いている一人に声をかけた。確か、三年生で学級委員長をやってる男子生徒だ。
「君、あの人文字はどこのクラブの生徒がやっているのかな?」
「所属しているクラブはバラバラですけど、漢字部の漢検一級を持ってる生徒が、みんなの指導をしているそうです」
「ほう、漢字部ですか。いや、ありがとう」
次に、人文字が作ったのは“七転八起”であった。
「今のうちのチームにピッタリの四字熟語だねえ」
校長は感心する。みんなもあまりの出来にどよめく。
次に、人文字が作ったのは“獅子奮迅”であった。
「校長、これもいいですなあ。うちにぴったりですなあ」
続いて、人文字が作ったのは“臥薪嘗胆”であった。
「しだいに難しくなってきたなあ」
続いて、人文字が作ったのは“駑馬十駕”であった。
「教頭、あれはどういう意味かね?」
「いや、分かりません」
さらに、人文字が作ったのは“珠聯璧合”であった。
「教頭、これは分からんね」
「私もさっぱり分かりません」
続けて、“虎嘯風生”“為虎傳翼”“鬱鬱勃勃”が作られた。
「ここまで来ると、意味どころか、読めもせんな」
「見たこともありませんな」
「さすが漢検一級だな」
「よくこんな複雑な文字が人文字で作れますなあ」
「うちの生徒がこんな優秀だったとはな。これで多少偏差値も上がるんじゃないかね」
ラッパー安藤が転んで起き上がれなくなった。酒井先生に飛び蹴りを喰らってできた足の骨のヒビが、走り回ったことで、四本から五本に増えていたのだ。
「すいません」
担架で運ばれて行く安藤は部長と監督とみんなに謝った。
「安藤、気にするな!」中村部長が熱く叫ぶ。「私たちは勝つぞ! あの雷電高校に勝つぞ! 安藤の代わりは、ほら、あそこにいらっしゃるから心配するな!」
ベンチの隅に座っていた社会人入学の大久保田が、手芸部の課題として膝の上で編んでいたセーターの編み物を横に置いて、ゆるりと立ち上がった。
ここで場内アナウンスが流れた。
「選手の交代をお知らせします。安藤君に代わりまして、大久保田君」
――17歳から66歳へ。
父親どころか、祖父への三代に渡る世代交代である。
応援席から大きな歓声と拍手が沸き起こる。大久保田は公開告白のときの六十六本のバラの花束で、すっかり人気者になっていたからだ。
「大久保田さん、頼みましたよ!」中村が声をかける。
「お任せください。まだまだ若い者には負けませんぞ。――痛ェ!」
馬居監督がお守りとしてベンチの隅に置いていた岡持ちに足をぶつけた。手にした物を落としそうになる。
「大久保田さん、それは置いていってください」また中村が声をかける。
「おお、忘れておったわい」
走り回るサッカーのために、大久保田は携帯用の酸素吸入器を持参していたのだ。用具係の岡戸が用意してくれたものだった。あやうく、手に持ったまま、ピッチに立つところだった。
酸素吸入器を編みかけのセーターの隣に置く。
「試合の途中で苦しくなったら、ここまで吸いに来るかのう」
雷電高校の選手が足を止め、ピッチに入って来る大久保田を見て驚いている。
頭は白髪で、腰が曲がっていて、動作が緩やかだからだ。
「おじいさんじゃん!」
「あの人のどこが高校生なんだよ」
「何年浪人して、留年すれば、ああなるんだよ」
「みんな、待てよ。お前ら、あの有名なドッキリを知らないのか。その道の達人がおじいさんに変装してプレーに加わるんだ」
「じゃあ、あれは特殊メイクでおじいさんになっているのか!?」
「日本の特殊メイク技術はすごいぞ。ノーベル賞ももらってるからな。あれはおじいさんじゃないぞ。最初はヨボヨボで、ヘタなフリをして、笑われるのだけど、途中でその能力を全開にして、逆に驚かせるというパターンだ」
「ということは、あのおじいさんは誰よ?」
「ヴィッセル神戸のイエニスタじゃね?」
「イエニスタは現役だろ。Jリーグと高校サッカーの掛け持ちはしないだろ」
「セルジオ越後さんじゃね?」
「セルジオ越後さんは七十歳を越えてるから、特殊メイクの必要はないだろ」
「ゴン中山じゃね?」
「そうだよ! 現役を引退してかなり経つけど、俺たちに中山雅史のシュートが止められるのか?」
「元日本代表だぞ」
「ハットトリックでギネス記録を持ってるぞ」
「やべえよ、マジで」
「俺たち負けるかもしれんよ」
「竜巻高校なんかに負けたら、理事長にぶっ殺されるぞ」
ビビってる雷電高校の選手が再び動き出す。
ちょうど、ボールが大久保田の方へ転がって行った。
大久保田は見事に空振りをして転んだ。
「ほら、見てみろよ。最初はわざとヘタなフリをしてるだろ」
学食バイト・宮井がボールを取りに来る。
「大久保田さん、大丈夫ですか?」
「ああ」本当に転んだ大久保田がのっそり立ち上がる。「大丈夫だ、おそらく」
「あまり無理しないでくださいよ」
大久保田は腰をさすっている。
「ああ、保険証を持ってくるのを忘れたなあ」
すでに病院へ行くつもりでいた。
雷電高校は応援ソングの定番キューティーハニーの演奏を始めた。
それに合わせて華やかなチアガールたちが踊り出す。
草野校長は自分たちの応援席を見渡した。向こうとはずいぶん違う。
「教頭、人文字は素晴らしいのだが、うちには雷電高校のような華やかさがないな。ハープを弾いてくれている彼女はピンクのドレスで華があるが、その他の面々は地味じゃないか。野呂先生はネズミ色のスーツだし、シスターは白と黒だし、お坊さんは茶色の袈裟だし、騒音じいさんも茶色のジャケットだし」
「そうですなあ。多数の応援はありがたいですが、うちには色も華も少ないですなあ」
教頭が困った顔をしたとき、金ぴかの衣装がやって来た。
「どうも、お世話様です!」PTAの桃の木会長だった。
本業はお笑いのピン芸人であり、普段は劇場でウクレレ漫談をしている。もちろん、この会場にも仕事用の派手な衣装を着て、ウクレレを持って来ていた。応援席が少しだけ華やかになった。
「一つ、あたしもこれで応援させていただきますよ」ウクレレをポロンと鳴らす。
桃の木会長は応援席に陣取り、ウクレレを弾き始めた。
「えー、みなさん。やる気、元気、驚き、桃の木です! ♪~ポロン。新しくできたサッカー部が~、強豪雷電高校に挑んで行くよ~。♪~ポロン。誰もが勝てるはずないと思っていたが~。♪~ポロン。今は二対二の同点だよ~。♪~ポロン。勝利は目前まで来ておるぞ~。♪~ポロン。名前負けせず~、気後れせず~、がんばるのだよ~。♪~ポロン。♪~ポロン。♪~ポロン」
お笑い好きの生徒たちから大きな拍手が起きた。
ウクレレ漫談が終わったとき、応援席が大きくどよめいた。みんなが視線を向ける先には、レオタードを着た女性たちが立っていた。
「教頭、あの子たちは何の格好をしておるのかね?」
「あれはキャッツ・アイですよ。漫画に出てくる三姉妹の女怪盗です」
その三姉妹とは体育館でも登場した、小久保“マドンナ”先生と、姫宮“マドンナ”生徒と、シスターのマリー・アマーチェだった。サッカー部を応援するために、あのときのキャッツ・アイが再びスタジアムに集結したのである。
シスターは賛美歌を歌っている仲間たちに事情を説明して、抜け出し、白と黒の修道服から紫色のレオタードに着替えて、サッカー部のマネージャーでもある二人のマドンナと合流したのである。
“竜巻高校キャッツ・アイ”参上!
「みんな、がんばってー!」「私たちがついてるよー!」「絶対勝ってねー!」
選手たちに黄色い声援を送ってから、赤と青と紫の三色レオタードが踊り出す。バックでは制服姿の三人の女子生徒たちも踊り出した。姫宮のクラスメートである結菜と芽衣と葵の、くノ一三人組も駆けつけたのである。彼女たちを見た、敵の応援席からも歓声が聞えて来る。
レオタードの赤色と青色と紫色。野呂先生のネズミ色。シスターの白色と黒色。お坊さんと騒音じいさんの茶色。桃の木会長の金色。
竜巻高校の応援席が色付き、満開の花壇のように、一気に華やいだ。
「教頭はさっき三姉妹の女怪盗と言ったが、レオタードの女性は四人おるぞ」校長が不思議がる。
「はあ?」教頭は立ち上がって確認した。
三人の陰に隠れて見えなかったのだが、確かにもう一人いる。
その女性と目が合った。
「教頭先生ー! あたしよー。あ・た・し」
保健室の主、アラフィフの美魔女恵子先生が白い超ハイレグレオタードで踊っていた。
赤と青と紫の三色に加え、ついに白色も加わった。
恵子先生は手に派手な扇子を持って、振り回している。ふわふわの羽根を付けたカラフルな扇子だ。伝説のディスコ「ジュリアナ東京」で使われていた「ジュリ扇」である。昭和の遺物である。この日のために手作りしてきたのである。恵子先生は、必要以上に腰をくねらせながら踊っている。三人の正式キャッツ・アイに負けてたまるかと、対抗意識を燃やしているのである。汗で透けてしまうとヤバい、白色喰い込みレオタードである。先日、誰かから百二十五本のバラの花束をプレゼントされて、気合が入っているのである。誰かがどこかで見ていてくれていると、本気で信じているのである。
たとえ、それが大久保田と野呂先生が置いた残り物のバラであっても。
それに、先日の登山研修で雷電高校の生徒たちから、やまんば呼ばわりされて、リベンジに燃えているのである。
「なにが昭和の妖怪よ!」
怒りで喰い込みレオタードがはち切れそうになる。
「それにしても、せっかくの手作りレオタードをまたこうして着る機会が訪れるなんて、岡戸ちゃんに三千円で売らなくてよかったわ。刺股と交換しなくてよかったわ。みんなー、勝ったら、私とデートしてあげるわよー! チュッ、チュッ、チュッ」
恵子先生は味方のチームに向かって投げキッスを連発する。
「ついでにこの場をお借りして、保健師からの業務連絡をしておくわね。みんなー! ぎょう虫検査のセロファン紙は月曜日に提出だよー。締め切り厳守でお願いねー!」
そして、敵の雷電の応援席に向けて叫んだ。
「ヤッホー!」
――ヤッホー!
今度はちゃんと、こだまとなって帰って来た。
「うふっ、こだまも私のはち切れんばかりの魅力に負けたようね」
この光景はピッチに立つ敵の雷電高校の選手にも見えていた。
「おい、あのキャッツ・アイ、三人ともキレイだぞ!」
「おお、ホントだ。すげえな。竜巻高校に転校したいよ」
「待てよ。あの横にいる人はなんだ?」
「どれ? わあ! おばちゃんが混じってる!」
「登山研修で遭遇した妖怪やまんばだ!」
「あれは、俺のオカンくらいの年だろ」
「俺のオカンがあんな格好をすると言い出したら、命がけで止めるぞ!」
「みんな、あっちを見るな!」
「呪われるぞ!」
「ゲームに集中しろ!」
「あの白色喰い込みレオタードおばちゃんを見せて、俺たちを精神的に動揺させるという竜巻高校の作戦だとしたら?」
「――大成功だな」
草野校長は活気に溢れた、自分たちの応援席を見渡した。
「教頭。うちにもやっと華やかさが出てきたな」
「そうですな。金ぴかのPTA会長に、赤と青と紫のキャッツ・アイ。おまけに恵子先生の白色喰い込みレオタードが参戦してくれましたからなあ」
「最後のは微妙だがな。サッカーの点数と同じく、華やかさでも雷電高校に追い付いたということだな。後は追加点を取って、勝利してくれるのを待つだけだ」
そのとき、遠くから声が聞こえてきた。
「いかがですかー。いかがですかー」
校長はそちらに目をやる。
「教頭、応援席に売り子が来ておるぞ。あの人は何を売っておるんだ?」
「さて、何でしょうか。私は聞いておりませんが」
男性が肩からクーラーボックスを担いで、生徒に次々と何かを売り歩いている。
校長の視線を感じたのか、その男性が振り向いた。
「これは校長先生。ああ、教頭先生もご一緒ですか」
男性は足早に階段を駆け上がって、二人の元にやって来た。
「おお、これは学食の大森店長じゃないか。ここで何を売っておるのかね?」校長が驚いて訊く。
「この通り」クーラーボックスをコンコンと叩く。「アイスを売ってます。生徒さんが集まるというので、出張販売にやって参りました」
相変わらずこの店長はセコいなと思いつつ、
「だいぶ、生徒も増えてきたからな。私もちょうど、応援の熱気で体が暑くなって来たところだよ。どれでもいいから、一つくれるかね」
「はい、どれでもと言われましたが」ボックスのフタを開ける。「この通り、全部ホームランバーです。ホームランで勢いをつけてほしいですからね。一応、バニラ味とチョコ味の二種類を持って来てます」
「では、バニラ味をもらおうかな」
「ありがとうございます。教頭先生はいかがいたしますか?」
「私はチョコ味をもらおうかな」
どんなことでも、校長には逆らいたい教頭である。
同じバニラ味を頼むなんてありえなかった。
「ホームランバーはいかがですかー」
大森店長は代金を受け取ると、声を張り上げながら、遠ざかって行く。
二人は並んでホームランバーを食べはじめた。
「校長、このアイスは子供の頃からありますね。いやあ、懐かしい味ですねえ」教頭は目を細めている。
校長は自慢の口髭にアイスを付けながら食べている。
「教頭、確かに懐かしいが、サッカーの試合をしているのに、ホームランはおかしくないかね?」
「ホームランバーは縁起物ですから、この場にピッタリじゃないでしょうか。――おっ、当たりですよ!」
教頭が校長に食べ終わった棒を見せる。そこには“ホームラン(大当たり)☆☆”と書いてあった。「これで新しいホームランバーと交換してもらえますよ」
すると校長も、「あっ、ワシも当たりだぞ!」
やはり、“ホームラン(大当たり)☆☆”と書いてあった。
「では、私が大森店長のところに行って、校長の分も一緒に交換して来ますよ」
「いや、かまわん。自分で行く」
「大丈夫ですよ。私が……」
「ワシは自分のことは自分でやる主義だからな」
校長は主義などと言い出したが、本当は交換したホームランバーを教頭に喰われるんじゃないかと心配したのである。
「では、一緒に行きましょうか」
二人は仲良く立ち上がった。
「大森店長、待ってくれー! ホームランバーが当たったんじゃー! 次はチョコ味を頼むぞー!」校長が叫びながら階段を駆け上がる。
何! 校長はチョコ味か。ならば……。
「店長、私も当たりましたー!」教頭も負けずに駆け上がる。「私はバニラ味です! バニラ味ですぞー!」決して同じものを頼まない。
生徒たちは目の前を通り過ぎて行く校長と教頭を見て、いい年した大人がまた不毛な争いをしていると、冷やかな目で見ている。
二人は片手に当たりの棒を振りかざしながら、競うように、大森店長の元へと走って行く。
まるで、登山研修のときの再現のようになっているが、すぐに二人はバテるだろう。そして、火照った体に、二本目の冷たいホームランバーは染み入ることだろう。
幸せな二人としか言いようがない。
竜巻高校のベンチからコーチを務める女将が出てきた。紫外線対策で屋根の下に避難していたのだが、そろそろ試合が終わりそうなので、よっこらせと出てきたのである。立っていた中村部長はまたベンチに戻っていた。馬居監督はずっと立ちっぱなしだ。
女将はこの状況をチャンスと見た。うるさい部長が後ろに引っ込んだからである。
「あんた」監督である大将を呼ぶ。「分かってるね。うちが勝ったらダメなんよ。この後も監督とコーチを続けるように言われるからね。三か月だけ引き受けて、さっさと退任するんだからね」
「ああ、分かってるよ」
「あんた、分かってたら、なんで、そんな最前線にいて、選手に檄を飛ばしてるのよ」
「隣で部長が張り切って応援してたもので、釣られてつい大声になって……」
「あんた! 五対0で惨敗する予定が、遠藤豆君が張り切って二点も入れちゃうから、今は二対二の同点でしょ。残り時間からして、あと一点取った方が勝ちよ。うちが確実に負けるように、オウンゴールのサインを出してよ」
「そんなサイン、あるわけないだろ」
「だったら点を取らないように、攻めてる選手を戻してよ」
うるさい女将コーチの要求を受けて、大将監督は選手に指示を出した。
「全員、自陣まで戻るんだー!」大きな声で叫んだ。
下がって行く竜巻高校選手を見て、雷電高校応援席の神輿の上にいる理事長は喜んだ。
「おいおい、ミッドフィルダーどころかフォワードまで下げたぞ」
「やはり、理事長がおっしゃってた通りの寄せ集めですな。何も分かっちゃいませんな」
双眼鏡を覗きながら、神輿の下で控える西見校長が薄ら笑いを浮かべる。
「あの寿司屋の大将と女将のような監督とコーチも大したことはないな。もう時間が残り少ないというのに守りを固めるとはな。ここは点を取りに行く場面だろ」
「引き分け狙いでしょうな」
「確かに、うちと引き分けるだけでも名誉と言えるだろうが、勝負は勝つか負けるかだ。それが選手のモチベーションを上げるんだ。素人の監督には分からんだろうがな。あと一点だ。全員の選手を下げても、うちのフォワード陣が総攻撃をかければ、いとも簡単なことだ」
残り時間は十五分+アディショナルタイム二分=十七分。
竜巻高校の選手は馬居監督の指示により、全員が自陣に戻った。しかし、誰も不平を唱える者はいなかった。サッカーの経験がないため、こんなものかと思っていたためである。
一方、女将コーチはうれしそうだ。
「これでうちが点数を取ることはないね。あとは雷電の選手にがんばってもらって、うちから点を取ってもらうことだね」
だが、全員で守る竜巻の前に、雷電はなかなか点が取れない。シュートの一本も打てないのだ。いくら素人集団とはいえ、十一人全員で守りを固めると、点数は簡単に入らない。
「ちょっと、雷電の子たちは何をやってるのよ! もっとがんばりなさいよ!」
女将コーチはイライラしている。原因は、点数が入らないことも
あるが、更年期障害である。ちょっとしたことでも、感情のコントロールができず、イラつくのである。
そのうち、攻めている雷電に疲れが出てきた。竜巻は転がって来たボールを蹴飛ばして、外に出しているだけである。敵のフォワードと一対一で戦おうなんて思っていない。複数人で対応している。よって、大して疲れてないのである。
双眼鏡で覗いていた西見校長が理事長を見上げて言った。
「うちの選手に疲れが見えて、動きが鈍って来てます」
「まさか。あいつらはこれが狙いだったのか。徹底して守りを固めているところを、わざと攻めさせて、疲れさせるという作戦だったのか。――あの寿司屋の大将のような監督は、相当のキャリアを持つ、名指導者なのかもしれんな。やはり、人を見かけで判断したらダメだ。わしとしたことが、油断をしてしまったようだな。見かけというと、あの老人のような大久保田選手はいつになったら特殊メイクを剥がして、その能力を全開するのかね?」
「また、わざと足をもつれさせて、転んでるフリをしてますね」
「だが、残り時間は少ない。そろそろ素顔を見せて、本領を発揮する頃だろう。元日本代表ゴン中山の御尊顔を拝もうではないか。その華麗なるシュートもな」
なんだか、大久保田という選手が怪しい。高校生にしては老けている。変装したゴン中山に違いないという情報が、すでに理事長の元へは届いていた。
そして、花桐理事長と同じ考えをしている人物がいた。ベンチに座って戦況を見つめている中村部長である。すべての選手を自陣に引き上げるという大胆な作戦が功を奏して、雷電の選手に疲れが生じて来たと信じていた。
素晴らしい! さすがサッカーに詳しい大将と女将だ。ここに来て、こんな一か八かの作戦を決行するとは思わなかった。その作戦はドンピシャで当たった。サッカーのことをよく知らない俺にはできないことだ。あの二人に任せてよかった。これで勝てる。あと一歩だ!
中村部長の夢はあくまでも世界だ。この試合に勝ち、連戦連勝を続け、やがて日本一になり、日本一を踏み台にして世界一を目指そうと思っている。本気で思っている。
まさか、大将監督と女将コーチが、わざと試合に負けようとしているとは、夢にも思ってない。
竜巻の選手は全員が自陣に戻っているが、雷電の選手は全員が攻撃に参加しているわけではない。当然、ディフェンス陣を始めとする選手が数人残って、ゴールを守りながら、戦況を見つめている。
女将はそれが気に喰わない。
「あんた、あの後ろの方で突っ立ってる雷電の子たちもこっちに来て、全員でうちのゴールにバンバンとシュートをするように言ってよ」
「監督が敵の選手に指示できるわけないだろ。聞いたこともないよ」
「前例がないならやってみろと偉い人が言ってたでしょ」
「ここで出す格言じゃないよ」
「とにかく、言ってみてよ」
またしつこいコーチに言われて、仕方なく、監督は敵の雷電に向かって大きな声で叫んだ。
「突っ立ってないで、全員上がれー! 一人残らず、上がれー! 一丸となって攻撃するんだー! シュートをバンバンと放つんだー!」
そのとき、ボールを奪った遠藤が走り出した。そのあとを、二人のラグビー部の玉本と足立が続く、さらにその後を竜巻の選手全員が駆け上がって行く。
馬居監督の、全員上がれの指示は当然、自分たちへの指示だと受け取った竜巻の選手が、いっせいに走り出したのである。まさか、監督が敵の選手に指示を出したとは誰も思ってない。
スポーツ飛び級の遠藤は速い。このピッチに立つ誰よりも速い。敵の選手も、さすがのラグビー部の二人も振り切られる。すぐに、敵陣のゴールの左側にたどり着いた。敵のデカいキーパーが迫って来る。遠藤の足は速いが非力だ。ドサクサに紛れて、ちょこっと打つシュート力はあっても、一対一でキーパーを弾くようなシュート力はない。
後ろから来た玉本にパスをする。玉本にサッカー経験はない。だが、ラグビーで培ったパワーは、サッカーにも通用するはずだ。ボールを受けた玉本は渾身の力で蹴飛ばした。敵のキーパーはボールを横っ飛びで弾く。あまりにも強烈なシュートだったため、キャッチできず、弾くのが精一杯だったのだ。弾かれたボールはゴールの右の方に転がって行った。
左からシュートを打つ、キーパーが弾いたボールは右に転がる。そのため、あらかじめ右に人を配置しておく。そんなことを素人の竜巻の選手が考えてるわけない。
右側には誰もいない。転々とボールは転がる。だが、誰もいないはずの右側に人影がフラッと現れた。学校犬ポチでも二宮金次郎でもない。チャーリーだった。
馬居監督の、一人残らず上がれの指示に、素直なチャーリーは、ゴールキーパーにもかかわらず、上がって来たのだ。ゴール前を見ると、みんなは左側に固まっている。
では、皆さんの邪魔にならないようにと、ヤンキーにしては謙虚なチャーリーは、ポッカリとスペースが空いていた右側に走り込んだのであった。
そして、走り込んでみたら、たまたま目の前にボールが転がって来たのである。
オーマイガーッ!
ここでシュートを決めれば勝てる。時間はすでにアディショナルタイムに入っている。シュートが入った瞬間、勝利も決定するだろう。
応援席では、雅楽部が、ハープ部が、突撃ラッパが、賛美歌が、般若心経が、カセットテープが、ウクレレが、四人のキャッツ・アイが、人文字が選手を応援してくれている。そして、巨大な応援旗は、スコット山田たち六人のヤンキー仲間によって、今も倒れることなく、支えられ、その勇姿を風になびかせている。
チャーリーは思った。あんなに僕たちのことを応援してくれている。ここで、みんなの期待に答えなくてはいけない。ヤンキー部サブリーダーの根性を見せてやる。
思い起こせば、イギリスに生まれた僕は日本へと留学し、スコット山田と出会い、ヤンキーという生き様に魅了された。ヤンキーという生き様は、日本の侍に通じるのかもしれない。その日本の侍は英国の騎士に通じると確信している僕は迷わず、ヤンキー道を進み始めた。それから僕は国際免許でバイクを乗り回し、ヤンキーの定番のウンコ座りをマスターして……。
「こらっ、チャーリー! いつまでブツブツと独り言を言ってるんだ。 早くシュートを打て!」
中村部長のデカい声でふと我に返ると、すぐ目の前に、起き上がって突進してくる敵ゴールキーパーの必死の形相が見えた。
「ヤバい。殺される!」
チャーリーはボールを蹴ろうと狙い所を探した。ゴールの左隅が見えた。あそこに入れるとシュートが決まる。
だが、僕が狙って入るとは思えない。
キーパーのみならず、他の選手たちも迫って来た。周りが全部敵
になった。海に囲まれたイギリスと日本みたいだ。
ああ、もう逃げられない。
だけど、どうせ狙っても入らないのなら……。
チャーリーは目をつぶった。
そして、長い足で思い切り蹴飛ばした。
「ヤンキー魂よ、このボールに宿ってくれ!」
やがて、球技場全体が静かになった。
みんな、なぜ黙っているのか? 僕が蹴ったボールはどうなったのだろう? うまく入ったのか? 大きく外れたのか? キーパーにキャッチされたのか?
ボールを蹴った感覚はある。だから、空振りはしてないはずだ。
チャーリーが勇気を出して、目を開けようとした瞬間、競技場に長い笛の音が響いた。
ゲームセットだった。
駆け寄って来た仲間に、チャーリーは地面に引き倒された。その上から選手が乗ってくる。やたらと重い。ラグビー部の玉本と足立だった。さらに、その上から、宮井も中島も犬井も鳥谷も平井も金森もみんな乗っかって来る。どさくさに紛れて、サッカー部設立の立役者、中村部長も交じっている。
すぐにそれは選手たちの山となった。
選手の山によじ登り、てっぺんでヨロヨロと立ち上がったのは、サッカーの才能なんか、これっぽっちも持ち合わせてない、ニセ者のゴン中山、社会人入学の大久保田だった。手には酸素吸入器を持っている。
「皆の者~、竜巻高校がやりましたぞ~。あの雷電高校に勝ちましたぞ~。――ああ、腰が痛いわい。首も痛い。先祖のタタリかのう。だが、勝ちましたぞ~!」
特殊メイクなんかしていない素の大久保田が雄叫びを上げた。
「ゼイ、ゼイ、ゼイ……」
息が切れたため、あわてて酸素吸入器を口に当てる。
大久保田に呼応して、中村部長も叫ぶ。
「みんなー! よくやってくれたー! あの雷電高校に勝てたなんて夢のようだ! がんばれば夢は叶うんだ! そのことを、あらためて教えてくれたみんな、ありがとー! よーし、次は世界一だぞ!」
雷電の理事長に一矢報いることができて、中村はうれしくて、興奮している。全身に鳥肌が立っている。選手に感謝し、大将と女将に感謝し、応援席に感謝し、ポチにも感謝している。日本一をすっ飛ばして、世界一を目指している。
悔しがる理事長の顔が目に浮かんでいることだろう。中村はこの選手の山の中にいるはずなのだが、いつもの大きな声は聞こえても、みんなに埋もれていて、その姿は見えない。選手たちは人間の山を形成しながら、まだ歓喜に沸いている。
一番下で押しつぶされて、ウンウン唸っているチャーリーには気の毒なことだった。
チャーリーは、誰かの手だか足だか分からない隙間から外を覗いた。さっき蹴飛ばしたボールが、雷電高校のゴールの中で転がっていた。
わおっ、本当にゴールしたんだ!
首を捻って、違う方向からも外を覗いてみた。ベンチの前で馬居監督のたたずんでいる姿が見えた。
思いもよらず勝ってしまったため、呆然自失の状態なのだが、チャーリーは監督が勝利の余韻に浸っていると勘違いした。
「最後はヤンキーのボクが決めましたよ! ありがとう、寿司マスター!」
竜巻高校応援席は勝利を目の当たりにして、大騒ぎをしていた。
草野校長は興奮して我を忘れ、森教頭と抱き合い、二人でピョンピョン跳ねて喜んだ。ふと、我に返ると、目の前に大嫌いな教頭の顔があったので、あわてて向こうに押しやった。森教頭も同じだったらしく、あわてて校長の顔を向こうに押しやった。しばらくの間、二人は無言となり、気まずい雰囲気となった。
雅楽部は持参していた太鼓を打ち鳴らし、ハープは激しく掻き鳴らされ、キャッツ・アイの三人は抱き合って喜び、くノ一の三人は涙し、祝いの突撃ラッパを大音響で吹く騒音じいさんに、なぜか、アラフィフの美魔女恵子先生が抱きついていた。――トンデモカップル誕生である。
「私という名の紙飛行機はまだ墜落しないわよ!」
やっと春が来た恵子先生はジュリ扇をバサバサ振り回して、喜びを爆発させている。マリー・アマーチェと星輝和尚は宗教の垣根を越えて、握手を交わし、中には木魚と十字架を交換している者も現れ、野呂先生はカセットテレコのボリュームを最大限に上げて“愛は勝つ”を流し、酒井先生は“仙台すずめ踊り”をソレソレと踊り、桃の木PTA会長はウクレレを振り回し、大森店長はホームランバーが完売して空になったクーラーボックスを頭上に掲げ、警官たちは喜びのあまり拳銃をぶっ放しそうになるのを我慢し、人文字では“倒載干戈”という四字熟語を作り上げていた。
“とうさいかんか”。――戦いが終わって平和になったという意味である。
グランドの隅に繋がれた学校犬ポチもうれしそうに吠え、おそらく、どこで見守ってくれている二宮金次郎も喜んで走り回ってくれていることだろう。
得点者チャーリーを下敷きにした選手の山に、ラッパー安藤も勝利者として、加わりたかったのだが、骨に五本のヒビが入った足が痛くて、行けなかった。
安藤はベンチの脇にしゃがんで、最近愛用していた二本の松葉杖を逆さまに立てた。そして、狙いを定めて、スイッチを押した。用具係の岡戸さんに頼んで仕込んであった二発の打ち上げ花火が、松葉杖の先から空へ向けて打ち上がった。
ヒュー、ヒュー。パーン、パーン。
大きな音がしたが、快晴の空をバックに広がった花火はあまり見えなかった。だが、大空に花火が上がったことは、竜巻高校の応援席でも、二発の大きな音で分かった。
昼間の見えない花火に向けて、大歓声が上がった。
そして、それは英語の酒井愛子先生も気づいた。
「やるじゃん、ラッパー安藤」
とてもうれしそうにつぶやいた。
一方、負けた雷電高校の応援席では……。
西見校長の手から双眼鏡がずり落ちた。
花桐理事長は御神輿の上に立ちあがって、呆然としている。
「校長、我々は竜巻高校に負けたのか?」見下ろして訊く。
「どうやら、そのようです」見上げて言う。「ゴールキーパーにシュートを決められました」
「まさか、キーパーまで攻撃に加わるような采配を行うとは、やはりあの寿司屋みたいな監督はタダ者ではなかったな。寄せ集めのチームだと思って、気を抜いていたのが敗因だ。生徒は素人でも、指導者が優秀なら負けることもあるわ。中村先生が高笑いする姿が目に浮かぶわい。だが、この恨みはいつかきっと晴らしてやる。――さあ、帰るぞ!」
理事長は御神輿の上の椅子に座り込んだ。そして、神輿が相撲部の手によって持ち上げられた。だが、一向に進まない。
「どうした!? 早く行かんか!」神輿の上から理事長が怒鳴る。
西見校長が神輿の後ろから叫んだ。
「方向指示器が作動しません!」
「方向指示器が作動せんのに、道を曲がったら、道路交通法違反だろ。金属部分の接触が悪いのではないのか。スイッチを何回か押してみろ」
カチ、カチ、カチ、カチ。
「理事長、バッテリーから煙が出てきました」
「バカ者、カチカチやりすぎなんだよ。――早く下ろせ!」
理事長が地面に足を付いたとき、足首がグネッと曲がって、階段を転がり落ちて行った。
「理事長!」西見があわてて追いかける。
ゴロゴロ、ゴロゴロ。――ドカッ。
理事長が止まった。
「理事長! 大丈夫ですか?」
「バカ者! 階段の上から下まで転がり落ちて、大丈夫なわけなかろう! 大丈夫ではない人間に、大丈夫ですかなんて訊くな!」
「おケガはどうですか?」
「バカ者、頭から血をタラタラ流してケガをしている人間に、おケガはどうですかなんて訊くな! それよりも、わしの大切な御神輿はどうなっておるんだ?」
「えーと、御神輿ですけど」西見が階段を見上げる。「ご覧の通り、炎に包まれております」
竜巻高校のベンチ前で大将監督と女将コーチが突っ立っている。
「あんた、大変だよ。あの雷電高校に勝ってしまったよ」
「まさか、勝っちゃうとはなあ。びっくりだよなあ」
「中村部長は子供たちの元へ駆けて行っちゃったね」
「よほど嬉しかったのだろうな」
「あんた、私があれほど言ったでしょうが、勝ってはダメだって」
「俺も勝てないように、お前から言われた通り、子供たちに指示したじゃないか」
「うちの子たちは素直なのか、バカなのか分からないねえ」
「サッカーの才能があったんじゃないのか」
「あんたがベンチに岡持ちなんか持ってくるから勝っちゃうんでしょ」
「お守りの代わりに持って来たんだよ」
「負けるように、上下逆さまに置くべきだったかねえ」
「今さら言われてもなあ」
「ところで、これはテレビに映ってるのかい?」
「ああ、あそこにカメラがあるな」
「あら、いやだ。ちゃんとお化粧しとけばよかったわ」
「俺たち二人の格好は、全国のたくさんの視聴者に見られてるんだな」
「だって、中村部長が普段着でいいと言うから」
「寿司屋の普段着はこの割烹着と長靴だからなあ」
「でも、こんな格好でも勝ってしまったのだからね。これじゃ、三か月で退任できないよ。あと三年くらいやってくれと言われるよ。どうするのよ」
「どうするって言われてもなあ。お前はどうしたい?」
「そんなの、ギャラしだいに決まってるでしょ!」
首から下げたお揃いの十字架がキラリと光った。
竜巻高校の応援席で披露された最後の人文字は“叢軽折軸”であった。
“そうけいせつじく”
小さな力でも、集まれば大きな力になるという意味だった。
(了)
「これでも青春だ、知らんけど ~後編~」
学食のテーブルに三人の男が座っていた。草野校長と森教頭と年配の白髪の男性である。時間は十三時二十分。昼休みは十二時四十分から十三時三十分までのため、あと十分ほどで昼休みは終わる。そのため、生徒たちはすでに食べ終えて、教室に戻っていた。
しかし、たった一人だけ、食堂の隅でうどんをすすっている男子生徒がいた。特別にバイトの許可をもらって、昼休みに学食で皿洗いのアルバイトをしている宮井である。家が貧しい宮井は、月曜日から金曜日までこの学食で皿洗いをし、賃金として千円をもらい、まかないとして、うどんかそばを一杯もらっているのである。今日のまかないはネギがたっぷり乗ったキツネうどんであった。学食の大森店長が気を使って大盛にしてくれている。
うどんを食べ終えた宮井が、器を返却して、三人の元へやって来た。
「教頭先生、ご無沙汰してます」頭を下げる。
「おお、宮井くんか。最近会ってなかったね。元気にやってるかい?」教頭はうれしそうに顔を向ける。
「はい。せっかく教頭先生にお世話してもらったバイトですから、休まずに働いてます」
「ほう、がんばってるね。お母さんの具合はどうかね?」母の体調を気遣ってくれる。
「はい。元気にパートを掛け持ちして働いてます」
「六人の弟くん達も元気かい?」
「はい、みんな元気です。僕と違って、よく勉強する優秀な弟たちです」
「ほう、そうかね。君が社会人になって、家にたくさんお金を入れられるようになったら、少しは楽ができるねえ」
「はい。僕たち兄弟はみんな年子ですから、毎年、一人ずつ、どんどん社会人になって、どんどん家にお金を入れて、どんどん裕福になって、ついには豪邸を建てる予定です。これが僕たち宮井家の夢です」
「ほう、すごいね。夢が叶うといいね。また何か困ったことがあったら、いつでも相談に来なさいよ。これからもがんばってね」
「はい、ありがとうございます」
宮井は教頭に深々と頭を下げて、教室に帰って行った。学食には三人が残った。自分に頭を下げてくれなかった校長はブスッとして、恥ずかしさを誤魔化すように、自慢のヒゲに手をやっている。白髪の男性は事情がよく分からず、困惑した表情を浮かべていた。ただ、校長と教頭は仲が悪そうだと感じた。
ときどき、校長と教頭は学校の食堂で昼食を食べる。いつも出前のウマイ寿司を食べているわけではない。学食を利用するのは、生徒とのコミュニケーションを取りたいらしいのだが、当然、誰も近寄って来ない。生徒に人気のある教頭にだけ、数人が挨拶をして通り過ぎて行くだけだ。校長なんて眼中にない。学校における校長と教頭の存在なんてそんなものだ。
今日は学食で食事をした後に、一人の男性と話をすることになっていた。目の前に座っている年配の男性がそうである。
今年から竜巻高校は社会人入学を受け入れることになっていた。彼がその第一号である。名前を大久保田といい、年齢は六十六歳である。背は高く、スリムで、髪は豊かだが、真っ白になっている。落ち着いた柔和な表情を浮かべている。
三人でカレーライスのウェルカムランチを終えた。ウェルカムと言っても、三人はそれぞれ自分でお金を出して、食券を買ったのである。校長と教頭のどっちが新入生に奢るかで、大いに揉めたからで、結局、自腹を切ってもらったらいいという結論になり、名ばかりのウェルカムランチになったのである。校長も教頭も自分のためならお金は払う。ましてや、お互いに相手を出し抜くためなら、金に糸目は付けない。しかし、他人のためにはケチに徹する。そもそも新入生といっても、自分たちよりも年上なのである。なぜ、年上の人にご馳走をしなければならないのか。このことで二人は三十分も議論を重ねたのである。
だが、三人は無事にカレーライスを食べ終えた。そこへ学食の店長がやって来た。
「食器をお下げいたします」
学食はセルフサービスになっていて、食べ終えた器は各自が片付けるのだが、校長と教頭に気を使って、下げに来たのである。
「ああ、これは大森店長。さっき、バイトの宮井君に会いましたよ。がんばってるようですね」教頭が声をかける。
「はい。真面目に働いてもらってます。さすが、教頭先生が推薦された生徒ですね。こちらから何も言わなくても、自分からテキパキと動いてくれます」
「大森店長がまかないを大盛にしてくれてるそうですね」
「いや、大したことはありませんよ。ネギを多めに入れるとか、天かすを山盛りにする程度です。育ち盛りなのに宮井君は痩せてますからね。たくさん食べてもらわないと」
「いつもありがとうございます」教頭は頭を下げるが、校長は店長から自分に挨拶がないため、またブスッとして、自慢のヒゲに手をやっている。
育ち盛りだから、たくさん食べてもらいたいと言いながら、サービスしてるのはネギと天かすか? どれだけセコいんだと、校長は自分のセコさを棚に上げて、頭の中で批判している。
「では、失礼します」大森店長は食べ終えた三つのカレー皿を持って行った。
だが、すぐに戻って来た。
「食後のコーヒーでございます」マグカップを三つ並べ始める。
「いや、悪いねえ」校長がお礼を言うが、
「一杯、二百円でございます」
「なに! 金を取るのかね!?」校長の声が裏返る。
「はい。もちろんでございます。こちらも商売ですから」大森店長は平然と答える。
自販機の缶コーヒーは百二十円だぞ。子供向けのキャラクターが描かれたマグカップに入ったインスタントコーヒーが二百円かね。どれだけセコいんだと、またもや自分のことを棚に上げて、校長は頭の中でブツクサ文句を言う。
三人はそれぞれ二百円ずつ払い、マグカップコーヒーをズルズルと飲み始めた。
「カップはここに置いておいてください。後ほど取りに来ますから」
大森店長は六百円を握り締めて、厨房に戻って行った。
校長は六十六歳の新入生に話し掛けた。簡単な挨拶はすでに済ませてある。
「ご苗字は大久保田さんと言うのですか。変わってますね」
新しく高校一年生になるといっても、校長よりも年上であり、用務員の岡戸と同い年である。よって、敬語を使っている。
「大久保さんという苗字はありますし、久保田さんという苗字もよく聞きますが、二つ合わせたような大久保田さんという方には初めて会いましたよ」
大久保田は説明を始める。
「もともと、先祖は大久保姓でした。大久保姓ばかりの人たちが村を作って住んでいたそうです。隣には久保田姓の人たちの村がありました。あるとき、村の境界線のことで争いが起こり、大久保村が久保田村を襲撃したそうです。村に火を放ち、焼き尽くし、村人を次々に襲い、皆殺しにし、半日で全滅させたそうです。それで、大久保村が久保田村を吸収合併して、大久保田村になったそうです」
「そんな歴史がありましたか。それは驚きました」校長が目を丸くする。「村人を皆殺しとは恐ろしいですね」
「子どもからお年寄りまで、殴ったり、刺したり、斬りつけたりして、村人全員を殺した後は、首を全部切り離して、村の広場に並べ、勝利の証とし、最後は火をつけて燃やしたそうです。胴体はそのまま埋めたのですが、焼却後に残った頭蓋骨は大久保田村の入口に山積みにして、村のランドマークのようにしていたそうです」
「そんな気味の悪いことを、やさしそうな顔でよく語れますね」
「苗字の由来はよく訊かれますからね。そのたびにこの皆殺しの話をしてますよ。その村はもう消滅したそうですが、困った先祖ですよ。ははは」
「子孫のあなたに祟りはありませんか」
「そんなものはありません。ときどき寝ているときに首が締め付けられるように苦しくなって、夜中にハッと目が覚めますよ。ははは」
「それは祟りじゃないですか。供養した方がいいのではないですか。私がいいお寺を紹介しますよ。私の紹介でしたら、格安で引き受けてくれますよ」
「大久保田さん」隣で聞いていた教頭が強引に割り込んだ。
校長が紹介しようとしているのは、諏訪一大寺の星輝和尚だと察知したからだ。あんな生臭坊主に供養されたら、祟りが倍増して、大久保田さんは夜中にポックリ死んでしまうに違いない。私が適当にナンマイダとお経を上げた方が余程効果があるだろう。
「失礼ながら、お年は六十六歳ですね」教頭が質問する。
大久保田は、テレビでよく見る人気芸人と同い年だとうれしそうに言ったが、その芸人よりもかなり老けて見える。頭髪は白いし、シワも多く、腰も曲がっている。
「社会人入学ですが、我々は二十代前半くらいの人を想定していたのですよ。何かの事情で高校に行けなかった人を支援しようということです」教頭が困惑気味に言う。
「私は経済的理由で進学を諦めたのですが、この年になって、学びたいとう意欲がふつふつと沸いて来まして、応募させていただきました次第です」大久保田はハキハキ話す。
「ほう。そう事情があったのですか。大久保田さんの入学は、うちの生徒への刺激にもなると思います。ぜひ、がんばってください」
「私の年齢からすると、彼らは子供というより、孫のようですが、学問以外にも、今の流行りとか、若者言葉とか、いろいろなことを学びたいと思います」
「いろいろとクラブ活動がありますよ」教頭だけが話を続ける。
校長に話をさせたら何を言い出すか分からないからだ。
「私は手芸部に入りたいと思ってます」
「手芸部ですか!? 確かにうちの高校にありますが」
「私は編み物が趣味でして、セーターでもマフラーでも手袋でも編むことができますよ。ときどきフリマに出品して、ちょっぴり売れてます」
「手芸部は三人の女子が所属してますので、話しておきます。大久保田さんは手芸部唯一の男子生徒になりますね」
「はい。がんばって編みますよ」
竜巻高校には一年に一回、登山研修という行事がある。登山というと、マラソン大会、ぎょう虫検査、練誠会に続いて嫌われている行事のように思われるがそうではない。登る山が低く、ほとんど丘のようであり、登山というよりもピクニックだからである。生徒と付き添いの先生たちは午前中を使ってブラブラと頂上を目指し、午後の時間を使ってブラブラと戻ってくるという楽チンな行事である。しかも、その小さな山は学校のすぐ裏にあり、わざわざバスに揺られて行く距離ではなく、これまたブラブラ歩いて行って、ブラブラ帰って来れるからである。一日、丘で遊んで授業をサボるようなものである。
しかし、こんな楽しそうな行事を欠席する生徒たちもいた。スコット山田をリーダー、チャーリーをサブリーダーとする竜巻高校の七人のヤンキー集団である。理由はヤンキーには自然も汗も似合わないからだという。今頃は七台のバイクで市内を走り回っていることだろう。
天気は快晴で言うことなし。といっても、この山登りが苦痛に思える人物がいた。ラッパー安藤である。授業中にラップを歌っていて、英語の酒井先生に半殺しにされた安藤だったが、性懲りもなく、また授業中に踊ってしまったのだ。
前回は東北の三つの祭――盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、青森ねぶた祭りを踊って怒られたのだが、今回は先生のご機嫌を取ろうと、仙台・青葉まつりの中で踊られる“仙台すずめ踊り”を、持参した手作りウチワを持って、ソレソレと踊ったのだ。しかし、これも先生にとって逆効果のようだった。またもや、バカにされたと解釈されてしまったのだ。
「すずめを舐めるんじゃねえ!」
ふたたびキレた酒井先生が、容赦なく教卓に蹴りを入れた結果、前回と同じように安藤は滑って来た教卓と窓ガラスに挟まれて、瀕死のすずめのようになり、また足の骨にヒビが入ってしまっていたのだ。
「安藤君、今度の登山研修はどうするのかな?」数日前、酒井先生が優しく訊いた。
「足がこの通りですから、欠席します」足にギプスをはめている。
「たかが骨のヒビくらいで学校の大事な行事を休むのかな?」
酒井がニコニコしながら安藤の目を見つめる。
「レントゲン撮ったら、三本のヒビが入ってまして……」
「……」酒井は決して視線を外さない。
「痛みがあって、昨日も寝れなくて……」
「……」笑っているだけに、返って恐ろしい。
「痛み止めの薬も効かなくて……」
「……」酒井の目の奥は笑ってない。
「お母さんにも休むように言われたし……」
「……」目の奥にあるのが本性だ。
「お医者さんも安静にしておくようにと……」
「……」黙って安藤の返事を待つ。
「たった今、痛みが消えました!」
「そうでしょう。病は気からよ」
よって、安藤は松葉杖をついての参加である。
しかし、酒井先生も鬼ではない。安藤の介添えとして、ラグビー部の玉本と足立を付き添いにしてあげたのだ。歩けなくなったら、持参した担架で運んであげろということである。歩けなくなるまで歩けということでもあるのだが、担架を持参しての登山研修は全国でも珍しい試みだろう。二度もキレてしまった酒井先生はまだ元に戻りそうにない。
先頭を歩くのは草野校長であり、そのすぐ後ろを森教頭が追いかけている。こんなところでも、二人は張り合っているのである。ついさっきまでは森教頭が先頭だったのだが、ほどけた靴のヒモを結んでいる間、校長に追い抜かれたのである。そして今、教頭は抜き返そうと必死の形相で歩いている。
特に険しい道というわけでもなく、高低差がほとんどない平坦な山道なのだが、二人のお年寄りにはちょっとしんどい。
校長はこの日のために、登山用の杖=トレッキングポールを新調してきた。二本セットになったアルミ製の三段伸縮の銀色のステッキである。このステッキを校長・教頭室のパソコンからネット注文をしているのを、教頭は目ざとく見つけ、校長がいなくなったときに、注文履歴からこの商品を特定し、どうしても負けたくない教頭は、カーボンファイバー製の五段伸縮の金色の防水仕様の収納袋も付いた一番いいやつを買い求めたのである。
そして、二つの商品は同日同時刻の宅配便で校長・教頭室に届いた。箱を開封してお互いのトレッキングポールを比較した瞬間、教頭が勝ち誇ったような顔をしたのを、校長は見逃さなかった。
トレッキングポールは左右の手に一本ずつ持って使う。二本を同時に使って歩いた方がバランスを取りやすいからである。
「校長、トレッキングポールの調子はいかがですか?」後ろから教頭が訊いてくる。
「ああ、調子はいい。膝にかかる負担も軽減されとるからな」
「私のトレッキングポールも調子がいいですよ。何といってもカーボン製ですからね。まあ、軽い、軽い。おまけに丈夫とくれば、カーボン製しかないでしょうなあ。――校長のポールは何でできてましたか?」知っているのに、わざと訊いてくる。
「これはアルミ製だが」校長は悔しがるが、「いくらいい道具を持っておっても、使う人がヘナチョコなら何の意味もなかろう」果敢に言い返す。
ヘナチョコ呼ばわりされた教頭はいきなりスピードを上げて、校長を追い抜きにかかる。
校長も抜かれてたまるかとばかりに、スピードを上げる。教頭の長い足に負けじと、校長は短い足をフル稼働させて、トップの座を譲らない。二人の脇でトレッキングポールが前後にビュンビュン揺れている。
まだまだ若い者には負けんと校長は心の中で叫ぶ。こんな年寄りには負けんと教頭は心の中で叫ぶ。年齢は一歳しか違わないというのに。
校長と教頭の歩いた跡にはたくさんの足跡と、たくさんのポールが刺さった跡が点々と続き、砂煙と落ち葉が舞っている。
二人のゼエゼエという死にそうな息切れに驚いたリスが一目散に逃げて行く。お互い相手を打ち負かそうとして、周りは見えていない。前から来る登山客があわてて道を譲り、今のオヤジたちは何だと振り返る。二人はたちまち他の生徒たちを引き離し、やがて、豆粒のように小さくなっていった。
「相変わらず、あの二人はバカだ」「あんな大人になりたくないな」
生徒たちは冷静である。反面教師とはこのことであった。そんな中、生き物係の二人、犬井と鳥谷は多忙を極めていた。登山の途中で見かける昆虫や咲いている花の名前を教えろと、生徒たちがうるさいのだ。
「お前らは生き物係だろう。こいつの名前くらい知っておけよ」と、木に止まっている見たこともないヘンテコリンな茶色い昆虫を指差して言う。
生き物係といっても、十二匹の鯉と一匹の犬しか飼育してない。迷い犬ポチは犬井の足元に座っている。犬井はポチの飼育主任である。ポチも登山研修に連れて来たのである。
女子からも声がかかる。
「この花は何という名前なの?」
「僕たちは生き物係だから」分かるわけない。
「お花だって生き物だよ」知ってて当然でしょ。
「それはそうだけど」花に詳しい男なんて珍しい。植物園の職員か植物学者くらいだろう。
「おい、鳥谷。あれは何という鳥だ?」
別の男子生徒が木に止まってる黒色と灰色が混ざった変な鳥を指差して、訊いてくる。
「分からないなあ」
「お前、鳥谷という苗字だろう。鳥に詳しくなくてどうするんだ」
「名前は関係ないだろ」鳥谷が言い返す。「お前なんて、デブのくせに苗字は細井じゃないか」
「そんなことを言うと、チビなのに高井君がかわいそうじゃないか」
「頭が悪いのに金田一君もかわいそうだよ」
「貧乏なのに金山君の立場もないぞ」
「美人なのに姫宮さんはどうなんだ?」
「それは合ってる」「確かに」
生徒が入り乱れているうちに、犬井はスマホの画像検索機能を使って、昆虫や花や鳥を撮影し、名前を調べ上げる。
「おお、さすが犬井君!」
みんなが犬井を取り囲む。一方、バカにされて腹の虫がおさまらない鳥谷は、見つけた五十センチほどのヘビを持って、生徒を追いかけ始めた。
そして、先ほど文句を言って来たデブの細井が追い付かれた。
「さっきはよくもバカにしやがったな!」
「おう、やれるもんならやってみろ!」
鳥谷が蛇を持って細井に近づいて行く。細井が木の幹に足を取られて尻もちをついた。鳥谷はすかさず目の前に蛇を持っていく。
「これはヒバカリという蛇だ。噛まれたら、その日ばかりの命。略してヒバカリと言うんだ」
「待ってくれ! ボクが悪かった。鳥に詳しくない鳥谷さんなんて全国に一万人くらいいるから、蛇をどけてくれ。まだ死にたくない。家には食べ残した食材がたくさんあるんだ」
やって来た犬井が鳥谷の横でニヤニヤして立っている。以前、ヒバカリは毒蛇だと思われていたのだが、今では毒のない蛇だと知られていて、大人しく、めったに噛み付くこともないことを知っているからだ。さすが生き物係だ。
鳥谷はヒバカリをそっと地面に置いた。ポチが驚いて逃げようとするが、ヒバカリは何事もなかったかのように、草むらの中へと入って行った。
「ああ、怖かったよう」デブの細井がのそっと立ち上がった。
生徒たちの喧騒を尻目に傍らの岩に座って、おにぎりを食べている男がいる。
やっぱり、山で自然に囲まれて食べるおにぎりは最高だ。普通に食べるよりも三倍はうまい。具は、梅干、昆布、おかか、鮭に明太子。なんでもうまい。いっそのこと、具がなくても塩だけでもうまい。登山で疲れた体には塩が合う。海苔もいらない。米だけでうまい。ああ、日本人に生まれて来てよかったなあ。明日、地球が滅びるとして、最後の晩餐はおにぎりにしたいね。おふくろの味だ。ソウルフードだ。シンプルイズベストだ。
男は水筒からお茶をラッパ飲みする。
――プハッ。ああ、お茶が合う。
やっぱり、おにぎりには日本茶だ。おふくろのお茶だ。ソウルドリンクだ。
山で食べる幸せに浸っていると、後ろから声をかけられた。
「まだ昼食の時間じゃないですよ、星輝和尚さん」
振り向くと、男子生徒が立っていた。
「おお、君は生徒会長の平井一郎君じゃないか。どうだい、君もおにぎりを食べるかい」
「いいえ、まだ十時ですから」
「そうだったかな?」
和尚さんは作務衣の袖を引っ張って、金色の高級腕時計を見る。
「おお、平井君の言う通り、わしのロレックスも午前十時だ。腹が減ったもんで、てっきり十二時半くらいだと思っておったのだよ。どうやら、私の腹時計は故障しているようだなあ」
「お昼ご飯は十二時からと決まってます。ちゃん規則を守ってください」
「さすがに生徒会長殿はルールに厳しいのう。だが、心配無用じゃ。まだおにぎりは五個残っておるし、お茶も半分残っとるわ」
水筒をブンブン振る和尚を残して、平井は仲間の元へ戻る。この和尚には何を言っても無駄だと思ったからだ。
なんで、こんな全身が煩悩のような人がお坊さんをやってるんだ? この人の辞書には戒律という文字はないのか?
それにしても、なぜ和尚さんが高校生の登山研修に来ているのか? まさか、生徒が滑落死したとき、すぐにお経があげられるようにか? 残念ながら、この山は滑落して命を落とすような険しい箇所はない。ならば、町内の慰安旅行と勘違いしてるのか?
平井の優秀な頭脳で考えても分からなかった。
川べりにたたずんでいる坊主頭は生徒会副会長の金森である。手を洗って、水を飲んでいる。話している相手は岡戸さんのようだ。手に虫取り網と虫かごを持っている。和尚さんもそうだけど、いったい用務員さんが、何のためにこの登山研修に参加しているのか? 二人を見下ろす平井は不思議がる。
「結局、二宮金次郎像には二度、追いかけられたよ」岡戸が恐ろし気な顔をして言う。
「本当に出たのですか?」金森は驚く。
「出たよ。この目で見た。たまたまそこにいたスコット山田君も一緒に見ているから、見間違いではないよ」
「えっ、スコット山田君がいたのですか?」
「彼は晴れて、我がゴーストバスターズの一員になったのだよ」
「あのヤンキーがそんな面倒な役をよく引き受けましたね」
「いい子だよ、彼は」金で雇ったとは言わない。
「それで、二宮金次郎はその虫取り網で捕獲できたのですか?」
「いいや。捕獲できておったら、私は今ごろマスコミに取り囲まれて、ヒーローになっておる。残念ながら素通りして行きおった。だが、二宮金次郎像を撤去する話はなくなったから、これからは彼も安心して走るだろうよ」
「やはり走るのですか?」
「そうだ。長生きするには足腰を鍛えないとダメだぞ、金森君。毎夜、走って足腰を鍛えておる二宮君は江戸時代からずっと生きておる。――おっ、蝶だ!」
岡戸は虫取り網を持って駆け出した。
「岡戸さん、もしかして、その蝶もゴーストですか!?」金森も後を追いかけて行く。
「いや、これは現実の蝶だ。昆虫を採集して、生き物係に売りつけるんだ。――ほら、見てみなさい」
岡戸は虫かごを示す。トンボとカナブンが入っている。
「ここに蝶を加えた昆虫三点セットで売りつけようと、私は企んでおるんだ。待て、蝶! 人間に逆らうんじゃない。こりゃ、すばしっこいのう。それっ!――よしっ、捕まえた!」
「その昆虫三点セットはいくらで売れるんですか?」
「せいぜい、虫かご込みで八百円だろう。だが、心配には及ばん。ここまでは準備運動だ。狙いはこんな昆虫ではなく、鳥だ。――いたぞ! オオルリだ。これはキレイだ」岡戸が見上げる。
青色と白色の小さな鳥が木の枝に止まっている。見た目が美しく、青い鳥御三家の一つであり、鳴き声も美しく、日本三鳴鳥の一つでもある。
「つまり、彼女は鳥業界で二冠を達成しておる」
「野鳥を捕獲してもいいんですか?」
「オオルリはダメさ。密漁に決まっているだろう」
どこまで本気なのか分からない。
「だがな、オオルリは一羽七千円で売れるんだ」
岡戸が振り回す虫取り網で捕まるドジな野鳥はいないだろう。せいぜい、弱った昆虫だ。それに、オオルリを捕まえたところで、生き物係の二人は買い取ってくれるのか? 学校で飼育してもいいのか? ダメだろうな。生き物については素人の僕にでも分かる。岡戸さんは逮捕されて、新聞に載るだろうし、学校も強制捜査されるだろう。
草野校長と森教頭はお互いに負けじと張り合って歩いているうちに疲れ果て、たどり着いた広い場所の真ん中にある石の上に座り込んでいた。歩き出してすぐ、痛みが膝に来て、腰に来て、背中に来て、両腕に来て、頭に来て、二人して歩く気力が奪われてしまったのである。
「教頭先生、なかなかやるじゃないか」
「校長先生こそ、お達者ですな」
ゼエゼエ言いながら、お互いを褒めたたえる。仲がいいのか悪いのか分からない。昨日の敵は今日の友だ。強敵と書いて友と読むようなものだ。二人仲良く、水筒の水をゴクゴク飲む。そのとき、前方からお揃いの黄色いジャージを着た集団がやって来た。
「ほう、雷電高校の生徒たちですなあ」教頭が首を伸ばして確認する。
校長も立ち上がる気力はなく、首だけを伸ばして、確認する。
「おお、そうだな。彼らも今日登っておったのか」
雷電高校は竜巻高校のライバル校である。
眺めているうちに、竜巻高校の生徒たちも後ろから追い付いて来た。両校の生徒と先生たち約三百人ずつ、合計六百人が山の中腹にある広場で対峙する。
ちょうど真ん中に竜巻高校の校長と教頭がいる。普段から仲の悪い両校の一触即発の状態を仲裁するため、自ら中央に進み出たのではなく、たまたまここで疲れて休んでいたら、挟まれただけである。まだのんびりと水筒を片手に座っている。
好き勝手に私服を着て来た竜巻高校と違って、黄色いジャージで統一した雷電高校の生徒の集団が、モーゼが割った海のように割れて、真ん中に道ができた。その道に十人ほどの生徒にかつがれた御神輿のような物が出現した。二本の大きな木に渡された神輿の部分に豪勢な椅子が設置されている。その椅子に座っていたのは、雷電高校の花桐理事長であった。神輿の横には西見校長が従っている。
「やあ、草野校長と森教頭じゃないか!」下々を見下ろしている理事長がデカい声で叫ぶ。「そんなところで、なぜ油を売っておるのかね?」
雷電高校の生徒は、どうだうちの理事長はすげえだろうという顔を向けて来る。竜巻高校の生徒は、なんだこの神輿ジジイは、モーロクしたのかという顔を向けてやる。
仕方なく、二人は立ち上がる。
「理事長」草野校長が見上げる。「それは一体何ですか?」
「見ての通り、人間神輿じゃわい。この年になると、小さな山とはいえ、登るのはしんどくてな。さすがのロールスロイスもここまでは登って来れん。かと言って、生徒たちとの触れ合いは大切にしたいんじゃ。というわけで、このように屈強な生徒諸君に神輿をかついでもらってるわけだ。――おお、中村先生じゃないか!」
竜巻高校の集団の中から中村を見つけたようだ。この理事長と気が合わなかったため、中村は雷電高校から竜巻高校へと左遷された。その恨みは今も忘れないでいる。
「これは理事長、ご無沙汰しております」
それでも、挨拶はちゃんと交わして、頭を下げる。
「少し小耳に挟んだのだが、君は竜巻高校にサッカー部を作ろうとしておるらしいのう」
「はい」中村は御神輿に近寄り、理事長を見上げる。「いずれ、そちらのサッカー部とも対戦する機会がやって来ると思います。そのときはお手柔らかにお願いします」
お手柔らかにと言ったが、心の中では叩きつぶしてやると思っている。
「ほう。この中途半端な時期によく部員が集まったな」
「いえ。まだ十一人は揃っておりません」
それを聞いた雷電高校の生徒は笑い転げる。
「十一人いないんじゃ、九人で野球をやればいい」「九人もいないんじゃないのか」「六人だったら、スリーエックススリーのバスケができるじゃん」「六人も集まってないんじゃない」「じゃあ、一人で相撲部でも始めればいい」
それを聞いた竜巻高校の生徒は悔しがる。中村先生がサッカー部員を集めていることは知っているが、集まってないことも知っているからだ。
「中村先生。わしが乗っている人間神輿をかついでいる生徒を見なさい」
見覚えのある生徒たちだ。
「分かったかね。全員サッカー部なのだよ。その中でも精鋭の十一人なのだよ。この神輿は彼らの足腰の鍛錬も兼ねているというわけだ。これで登山研修をすると、けっこうキツイぞ。だが、彼らにとっては大したことでない」
確かに理事長をかついでいる生徒の足は丈夫そうで、みんな精悍な顔つきをしている。
「最低の人数十一人が揃ったら連絡をくれたまえ。サッカー部設立記念試合を開催してあげよう。どうしても揃わないようなら、女子も加えればどうかね。男女混合チームで戦えばよろしい」
ふたたび雷電高校の生徒は笑い転げる。中村は歯ぎしりをして悔しがる。
「さて、行くとするか!」理事長が右手をあげて、神輿の横にいる西見校長に指示を出す。「その山道を右折してくれるかね」
ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ。
人間神輿は雷電高校の生徒集団を引き連れて、広場の道をカチカチと音を立てて、右に曲がって行く。
理事長を乗せた神輿には、なぜか方向指示器が付いていた。
中村は悔しそうに神輿を見送った。
一方、竜巻高校はこの広場で昼食だった。
集まった生徒たちは雷電高校の悪口を言っている。
「言いたいことを言われて悔しいよな」
「黄色いジャージ集団なんて、ブルースリーオタクかよ」
「なんだ、あの神輿は。神様気取りかよ」
「あのタヌキ理事長の奴、男女混合サッカーだって、ひどいよな」
「サッカー部は中村先生が何とかしてくれるんじゃない。俺は園芸部だから無理だけど」
「俺も天文部だから無理だけど、早く部員が集まってほしいよな」
「それで雷電高校サッカー部を撃破すると」
「でも、あの名門に勝つなんて、草野球チームがプロ野球チームに勝つようなものだよな」
「小学生横綱が照ノ富士に勝つようなものだからなあ」
「AKBが乃木坂に勝つようなものだからなあ」
「微妙だな」
「まあ、長い人生には大逆転があるさ」
「そうだな。俺たちが歩んで来た人生はまだ短いからな」
「あんな変な連中は放っておいて、メシにしよう。――おお、みんな並んでるじゃん!」
広場の隅でお弁当が配られていて、すでに長い行列ができている。もちろん、午前中に早弁をしていた星輝和尚もちゃっかり並んでいるし、岡戸もトンボとカナブンと蝶が入った昆虫三点セットが入った虫かごを持って並んでいる。
「はい、お弁当ですよー。みんな並んでくださいよー」白い割烹着を着た年配の男性がお弁当を渡している。「お弁当を受け取ったら、隣でお茶も受け取ってくださいよー」
「はい、お茶はこちらですよー」同じく割烹着を着た年配の女性がペットボトル入りのお茶を手渡している。
「お茶はこちらにもありますよ」もう一人の黒と白の服を着た若い女性もペットボトルを手渡している。「はい、どうぞ」
生徒会長の平井と副会長の金森が木製ベンチに並んで座った。お弁当の包みをほどく。
「おお、ちらし寿司だ!」平井が思わず声をあげる。
「すげえ。トロにウニにイクラ……。こんな豪華なちらし寿司は初めて見た」金森も驚く。
「とりあえず、水分補給といきますか」平井はペットボトルを開けて、お茶を口にする。「でもな、なんでウマイ寿司の大将と女将がここまで出張って来て、ちらし寿司を配ってるんだ?」
「分からないね」金森はトロを口にして、つぶやいた。「お店の宣伝かもね。あるいは校長あたりが格安で準備させたんじゃないか」
「これ、三千円はするな」
「それを、あの校長が二千円くらいに値切りやがったんだよ」
「とんでもない校長だな。そんな学校の生徒会長が僕だもんなあ」平井がボヤく。
「副会長が僕だもんなあ」金森も同調する。
「おかしなことがもう一つある。女将の隣でお茶を配ってた若い女性は教会のシスターだったぞ」
「黒と白の修道服で登山している人を始めて見たわ。通販で買ったコスプレかと思ったが、あれは本物のシスターさんだな」
「娘にしちゃ、キレイだったな」
「あの二人の娘じゃないな。全然似てない。トンビがタカを生んだとは思えん。どういう関係か知らないが、慈善事業もシスターの活動の一つだからね」
「お茶を配るのも慈善事業というわけか」
「星輝和尚に用務員の岡戸さんにウマイ寿司の大将と女将に教会のシスターまで参加しているとは、変な登山研修だよな」平井もトロに齧り付く。「研修の趣旨がよく分からん」
「ちらし寿司がおいしいからいいことにしようや。ムシャムシャ」
「そうだな、ムシャムシャ」
午後はスマホの自撮り合戦になった。お腹も一杯になり、後は山を下りるだけなので、生徒たちも気楽で、先生たちも大目に見ている。被写体で人気があるのは、もちろん学校のマドンナだった。つまり、小久保“マドンナ”先生と、姫宮“マドンナ”生徒のダブルマドンナである。
「小久保先生、一緒に写真を撮ってください!」
「生き物係の犬井君ね。いいよ。ここに並んで」小久保は自分の隣を指差す。
「鳥谷、悪いけど、シャッターを押してくれ」犬井は自分のスマホを渡す。
「あら、犬井君、手に何を持ってるの?」
「ああこれですか。用務員の岡戸さんに買わされたトンボとカナブンと蝶の昆虫三点セットです」
「いくらで買ったの?」
「虫かご込みで八百円です」
「しょうがないオジサンだよね」
「生き物係ですから、大事に育てます。――鳥谷、シャッターを頼む」
「おお、まかせておけ!」
鳥谷は、犬井が小久保先生に気があることを知っている。
「お二人さん、もっと近づいて。いや、もっともっと。ピッタリと。ベッタリと。はい、犬井、ここで先生の肩に手を回して!」
「できるか!」
――カシャ!
犬井が顔を赤らめて叫んだ顔がバッチリ撮れた。
「鳥谷、殺すぞ、お前!」犬井が迫って来る。
「待て待て。生き物係として、命は大切にしよう」鳥谷がなだめる。
「ああ、そうだな。次は僕が撮ってあげるよ。マドンナ姫宮の所へ行こうや」犬井が誘う。
鳥谷は姫宮に気があるのだが、姫宮の前にはツーショット撮影の順番待ちの行列ができている。男子ばかりではなく、女子も並んでいる。姫宮は女子にも人気があるのだ。
「おいおい、ライバルが多いぞ。大丈夫か、我らの鳥谷君」犬井が茶化す。
「生き物が好きな人に悪い人はいないからね。その辺をアピールしてくるよ」
「昆虫三点セットを貸そうか?」犬井は虫かごを掲げる。
「いらない」鳥谷は即座に断る。「それを見ると岡戸さんの顔がチラつく」
「それは致命的だな」
小久保“マドンナ”先生に次いで美しい酒井“準マドンナ”先生の存在も忘れてはいけない。酒井先生は二度に渡って、ラッパー安藤をボコボコにしたが、クラス内で口止めがされていて、他のクラスの生徒たちは、相変わらず、酒井が青森県出身の大人しくて、真面目で、純朴な先生だと思い込んでいる。男子と女子、両方の生徒に人気があり、こちらも行列ができていた。しかし、担任をしているクラスの生徒は一人も近寄らなかった。酒井の正体を知っているだけに、恐ろしくて近寄れないのだが、あのクラスの子たちは、普段から会ってるから、今さら一緒に写真なんか撮らないのだろうとみんなは思い違いをしていた。
二人のマドンナと準マドンナに続いて人気があったのはシスターのマリー・アマーチェだった。白と黒の修道服は、山のてっぺんでは浮いてしまっているが、集まった生徒たちが人垣を作っていた。
普段、教会なんかに行かない生徒たちはシスターに会ったり、話をしたりしない。おまけに美人となると、興味津々なのだろう。
「シスター、僕と写真を撮ってください!」
「待て。俺が先だ!」
「何だと、シスターは俺が先に見つけたんだ」
「絶滅寸前の希少動物みたいに言うなよ」
「右の頬を打たれたら、左の頬を差し出せよ!」
「お前こそ、汝の敵を愛せよ!」
男子が揉めているうちに、女子がシスターを取り巻いた。
唖然とする男子。
「おいおい、女子は要領がいいよなあ」男子がボヤく。
「あんたたちがトロいだけでしょ」女子は余裕だ。
女子がシスターを囲んで集合写真を撮っている。大学を出たばかりの女性新任教師と生徒たちのように見える。各自のスマホを順番に受け取ってシャッターを切っているのは教頭であった。そんなことは生徒か、他の教師にやらせればいいのにと誰もが思うのだが、教頭も楽しそうなので任せることにした。こんな森教頭も生徒たちの人気者だった。
ここが嫌われ者の校長と違う所なのだよと、生徒に囲まれた教頭も満足げだ。ただ、シャッターを押すだけなのだが。
「はい。皆さん、写しますよー。笑って、笑って。シスターも笑ってくださーい!」
中央に立っていたシスターがVサインをして、叫んだ。
「イエーイ!」
――カシャ!
シスターもイエーイなんて言うのか!?
イエス様に許しを請うているのか?
一瞬、山の上は騒然としたが、また笑い声が戻った。
「平井君!」
呼ばれて振り返ると星輝和尚が立っていた。
「君が生徒会長だと見込んで頼みがある。御仏からのお願いだと思って聞いてほしい」
「はい、何でしょうか?」嫌な予感しかしない。
「わしもキレイな娘さんと写真が撮りたいんじゃ」
予感は当たった。嫌な予感は当たるものである。何とかの法則だ。それでも、平井は愕然とする。この和尚さんの体は煩悩でできているのか? 食欲の次は性欲か? 練誠会という行事も、金に目がくらんで引き受けたらしいから、金銭欲も旺盛だ。食欲、性欲、金銭欲。――三大欲望の揃い踏みだ。
だが、ニコニコ笑うタヌキ顔を見ていると、かわいそうにも思えてくる。
「では、僕が話を付けてきます」生徒会長として責任を果たしてあげよう。「見てみると、二人のマドンナとシスターに人気が集まっているようですが、どなたと撮りたいですか?」
「三人全員に決まっておろう。差別はいかん。御仏の下では、みな平等じゃ」
都合よく、仏を持ち出す。いつかバチが当たるだろう。
人のいい平井はタヌキ和尚のために、三人に声をかけて、撮影をセッティングしてあげた。
和尚は三人の美女に囲まれて、ヨダレがこぼれそうだ。
「はい、和尚さん。チーズ!」平井はシャッターを押してあげた。
和尚はこの世のモノとは思えないほどの眩しい笑顔をレンズに向けた。紺色の作務衣を着た和尚と、白と黒の修道服を着たシスターが同じ写真に入っている。シュールな光景だ。
「いやあ、三人のお嬢さん方、お忙しいところをどうも。三人に御仏のご加護のあらんことを。ナンマイダ~」
星輝和尚は手を合わせたが、三人のうちの一人はシスターであった。ナンマイダ~と言われたシスターは、どう返していいのか分からず、とりあえず胸の前で十字を切っていた。
アーメン。和尚さんにも神のご加護を。
和尚がニコニコ顔で平井の元にやって来た。
「ありがとう。これで何の迷いもなく、成仏できるよ」
平井は「それはよかったです」と答えたが、心の中では、そんな迷いだらけで、煩悩のかたまりのような人が成仏できるわけないでしょうと、たくさんの罵声を浴びせていた。
「平井君、実はもう一つ、頼みがあるんだが」
また嫌な予感がする。
「あのお二人も、三人のお嬢さんと写真が撮りたいと言っておるのだよ」
平井が振り向くと、定年間近の美術の野呂先生と社会人入学の大久保田が肩を組んで、ニコニコ笑いながら立っていた。
また嫌な予感は当たった。
二人は仲が良くて肩を組んでいるのではなく、疲れ切って、お互いを支え合っていたのだ。“人”という字がお互いを支え合っているようなものだ。低い山を登るといっても、五十九歳と六十六歳には大変だったようだ。
しかし、三人の美女と写真を撮るために、最後の力を振り絞って、ガクガクの膝で立っていたのである。煩悩のなせるワザであった。
両マドンナとシスターと違って、男子生徒が見向きもしなかったのが、保健室の主、アラフィフの美魔女佐藤恵子先生だった。
今日は登山のため、いつものボディコン白衣ではなく、深紅のボディコンジャージを着ての参加である。気合十分である。この広場にたどり着くまで、救急セットを持って、ケガ人はいないか、具合の悪くなった人はいないかと、登ってる学校関係者に訊いて回っていた。傍から見ると、保健室の先生が甲斐甲斐しく仕事をしているように見えたのだが、訊いて回る相手はすべて男子生徒と男性教師で、下心が丸分かりだったので、女子たちには白い目で見られていた。
「恵子先生はいい人なんだけどねえ」
「私たちの悩みも聞いてくれるのにねえ」
「保健師としての腕も確かなんだけどねえ」
「男に目がないのよねえ」
「男にだらしないのよねえ」
女子生徒の評判はさんざんである。あとは山を下りるだけなのだが、恵子先生は深紅のボディコンジャージ姿で、腰をくねらせながら、しつこく男子生徒と男性教師を追いかけ回して、顰蹙を買っていた。
「足は大丈夫かしら? 冷却スプレーを吹きかけてあげるわよ。サービスで、私の吐息も吹きかけてあげるわよ」
「熱中症には気を付けてね。具合が悪くなったら、木陰で休んでね。私の膝を枕の代わりに貸してあげるわよ。寂しいのなら、添い寝してあげるわよ」
「腰は痛くない? 湿布があるわよ。先生が心を込めて、貼って、あ・げ・る」
「すごい汗ね。普段から汗っかきだから大丈夫? ダメよ。私が汗を拭いて、あ・げ・る」
そんな恵子先生を見て、男性教師はいつものことだと思いながらも、私は大丈夫ですよ、どこも痛くありませんからと、うまくあしらっている。一方、男子生徒はというと、そんな社会人のような気の利いた芸当ができるわけもなく、ワーワー言いながら、本能で逃げ回っている。
気が付けば、恵子先生の周りに男子はいなくなっていた。
「おかしいわ。大き目のジャージを体の線がくっきり出るように加工して、深紅のボディコンジャージに仕上げて来たというのに、なぜ世の男性は私の魅力に気づいてくれないのかしら。男子高校生と言えば、性欲のかたまりのような存在よ。そんな子も逃げて行くって、どういうこと? それに、年上の女性に憧れる年頃のはずよ。あの子たちの母親よりも、ちょっぴり年上なだけじゃないの」
もう誰もいなくなった山の上に救急セットを持って、たった一人で呆然とたたずむ恵子先生。
「一学年は三百人、その半分の百五十人が男子生徒として、私は百五十人の男子プラス五人の男性教員から同時にフラれたことになる。ギネス級だ。――すごいじゃん、私!」
だが、こんなことで挫けるようなアラフィフの美魔女ではなかった。
手鏡を取り出して、顔を映してみる。
「あら、かわいい! 美しすぎる保健師だわ」
吹いて来る風が少しだけ、頬にやさしい。
「大丈夫。まだまだ地球上にはたくさんのオスがいるわ!――ヤッホー!」力いっぱい叫んでみる。
こだまは返って来なかった。
周りには声が反響する山がなかったからだ。
「こだまのバカヤロー!」
ちょうど真下を黄色いジャージを着た雷電高校の生徒たちが下山していた。奇妙な声を聞いて見上げる生徒に、恵子先生はいくつもの投げキッスを飛ばした。
「わっ、やまんばが出たぞ!」「昭和の妖怪だ!」「UMAだ!」
生徒は大騒ぎする。
そのうち生徒たちは石を投げだした。あわてて避難する恵子先生。神輿に乗った花桐理事長も何事かと、丘を見上げたが、美魔女の恵子先生が好みのタイプではなかったようで、嫌な物を見たような顔をして、すぐに目を逸らした。神輿は方向指示器をカチカチ点滅させながら、北の林の中へと消えて行った。
各自が山を下りて行く。登山研修はこれで終わりだった。結局、松葉杖をついていたラッパー安藤は、途中で足が痛くなって、歩けなくなり、ラグビー部の玉本と足立が持参していた担架に乗せられて、下山することになった。
当然だろう。足の骨に三本のヒビが入っていたのだから。
「あらかじめ担架を持って登山をするっておかしくないか?」玉本が言う。
「だって、酒井先生の命令だから」足立は諦めている。
「もう、あの先生には逆らえないな」
「正体があれだもんな」
「みちのくの妖怪」
「酒井先生の前では、ハイハイとイエスマンに徹することが身を守ることになるな」
「さもないと、こいつみたいに」足立は安藤を見下ろす。「半殺しにされる」
安藤は気持ちがよくなったのか、目を閉じたまま運ばれている。
「爆睡とは、いい気なもんだな。こんなことじゃ、棺桶を持ってくればよかったよな」と足立。
「おい、棺桶はないだろ!」安藤が目を開く。
「なんだ、起きてるのか?」
「ずっと起きてるわ!」
「ウソつけ。今、目が覚めたのだろうよ。――えいっ! これでも喰らえ!」
「待て! 揺らさないでくれ!」
玉本と足立が息を合わせて担架を揺らす。
「俺はケガ人なんだぞ!」
「何だ、偉そうに!」玉本が怒鳴る。
「いや、すまん。偉そうにしたお詫びと、担架で運んでくれているお礼に、俺の即興ラップを聞かせてやろう」
「聞いてくださいだろっ!」足立も怒鳴る。
「お二人さん、お聞きくださいませ。今から歌のスタンバイをさせていただきます」
安藤はしばらく目を閉じて、精神統一らしきものをした後、おもむろに歌い出した。
♪山を担架で下って行く~。山の中に担架があったんか~。僕はこんな担架に乗ったんか~。ラグビー部の二人がおったんか~。二人で担架を持ったんか~。お昼ご飯は喰ったんか~。この担架、どこで買ったんか~。
♪山を担架で下って行く~。僕の心は砕け散り~。お腹も痛くて下りそう~。だけど、くだらないケガ~。
上半身を動かせる安藤はリズムに合わせて、腕を振っているが、そのリズムはバラバラだ。担架で運んでいる玉本と足立には揺れて、うるさいだけだ。
♪行き着く先は天国か~。なんで下に天国がある~。上にあっても登れない~。だったら下ろう、どこまでも~。俺たち三人離れずに~。三人は運命共同体~。二人はラグビー部のスターだぜ~。YOYO!
あまりにもヘタで下らない歌のため、玉本と足立は担架を地面に放置して、脱兎のごとく、駆け出した。
安藤はむくりと上半身を起こす。
「おぉーい!」置き去りにされた叫びが、空しく山道に響く。「待てー、薄情者! お前ら、それでも健全たるアスリートかー!?」
「おーい、安藤。早く下りないと、夕暮れ時はクマが出るぞー!」振り返って玉本が叫ぶ。
もちろん、こんな丘にクマはいない。
野性の動物が出たとしても、せいぜいウサギかリスだ。
だが、「マジかよー!」と安藤はマジで信じる。
「クマは時速六十キロで走るぞー!」足立も叫ぶ。
「それは速い方なのかー!?」安藤も大声で尋ねる。
「ウサイン・ボルトは時速四十五キロだー!」
「クマ、速いじゃん! デブなのに速いじゃん! 四足だから速いじゃん! 足をケガしてなくても、追いつかれるじゃん! 僕の武器は松葉杖しかないじゃん! ラップを歌ってヒマはないじゃん!」
その後、どうやって安藤が下山したかは、誰にも分からなかったが、翌日はちゃんと学校に来ていたし、担架もラグビー部の部室に戻されていた。ただ、足の骨のヒビが三本から四本に増えたというウワサだった。
竜巻高校のヤンキー七人がバイクで街を疾走していた。先頭はハーフヤンキーのスコット山田で、二番手は留学生ヤンキーのチャーリーだ。その後を五台のバイクが続く。
この七人の集団には名前がない。暴走族のようにカッコイイ漢字の名前を付けようという案もあったのだが、リーダーのスコットもサブリーダーのチャーリーも揃って漢字が苦手だったのでやめたのである。では、カタカナの名前はどうか、となったのだが、地方都市の売れないビジュアル系バンド名のようだというので諦めたのである。
「みんなー!」スコット山田が振り向いて、大声で叫ぶ。「スピードを落とせ!」
これから警察署の前を通り過ぎるため、速度を落とすように指示したのだ。
「OK!」国際免許でぶっ飛ばすイギリス人チャーリーが返事をして、さらに後ろに伝言する。「レディースアンドジェントルマン、スピードダウン!」
「レディースなんか、いないだろ!」三番手を走っていた井川が叫ぶ。
署の玄関には、立ち番をしている新人警官が二人いる。署の前なんかで見つかって、スピード違反で捕まったら、ヤンキーの名折れだ。
七人はスピードを落とすと、背筋と両腕をしゃんと伸ばして、健全なツーリング集団のフリをして通り過ぎる。
そして、署の前を通り過ぎると、またぶっ飛ばす!
「チャーリー!」スコット山田が呼ぶ。「そろそろ登山研修も終わった頃だろうな」
「ああ、そうだな。あんな丘には登りたくないよ。こうして飛ばしてるのが最高だ」
「俺たちに、あんなボーイスカウトみたいなことが似合うわけない。コンクリートジャングルの間をぶっ飛ばして、すり抜けるのお似合いだぜ!」
「そうだぜ!」
七人は信号を守るものの、ジグザグ走行を繰り返し、クラクションを鳴らして、暴走を続ける。あわてて道を空ける車や、横断歩道を早足で渡る人々を見て、喜んでいる。
街で最も大きな道路に出たとき、最後方の男が叫んだ。
「みんな、道を開けるんだ!」
「何だと!」スコット山田は叫ぶ。「俺たちがなんで、道を譲らなきゃならないんだ!」
文句を一つ吐いて、後ろを振り返ると、黒くてデカい車が猛スピードで走って来る。
だが、デカい割にはエンジン音がしない。――なんだ、こいつは!?
チャーリーが叫んだ。
「スコット、道を譲れ! こいつはロールスロイスファントムだ! 六千万くらいする最高級車だから、ぶつけたらヤバいぞ。すげえ金を巻き上げられるぞ」
「なんだ、詳しいな」
「ボクの国の車だからね」
「ああ、イギリスの車か。メシは不味いが、車はすげえな。だが、やけにエンジンが静かだな」
「だから、ファントム=幽霊と言うんだ。ロールスロイスとネッシーはイギリスの二大自慢なんだ」
七台のバイクは仕方なく、脇に避けて、ロールスロイスのファントム様に道を譲った。
少しの傷がついても、俺たちのお小遣いでは払えないだろう。宮井の学食のバイトを代わってもらうしかない。それでも足らないだろうが。
一体どんなセレブが乗ってるのかと、スコットはすれ違いざまに、車の中を覗いた。
ロールスのデカい後部座席に、雷電高校のデカい花桐理事長が、踏ん反り返って座っていた。
「あの野郎か!」スコットはギシギシと歯ぎしりをする。
ロールスロイスファントムには同じく黒塗りの後続車がいた。大きな国産車だったが、こいつが七人に幅寄せをしてきた。道の端をゆっくりと並んで走っているというのに、嫌がらせをするかのように、ギリギリの所を追い抜いて行ったのだ。中を覗くと、デカい後部座席に、ちっこい西見校長が座っていた。さらにその後ろから、荷物を乗せた大型トラックが走って来た。
「あの校長もいやがるのか!」スコットはギシギシギシと歯ぎしりをする。
三台の車は連なって、そのまま猛スピードで去って行った。二台の車には登山研修帰りの雷電高校の理事長と校長が乗っていて、三台目の大型トラックには方向指示器付きの神輿が積んであったのだが、登山研修に参加してなかったスコットたちは知る由もなかった。
おそらく、やつらに俺たち七人の顔は見えていない。ヘルメットをかぶっていたため、竜巻高校の生徒だとは気づかなかったはずだ。竜巻高校への嫌がらせではないにしろ、道を譲らされて、さらに幅寄せをされたとなれば、無性に腹が立つ。ヤンキーの面目が丸つぶれだ。
三台の車の後をつけて、雷電高校に入って行くことを確認すると、七台のバイクはスコットの合図で、作戦会議をするため、近くのコンビニの駐車場に入った。
「今のは雷電高校のお偉いさんだ。だが、相手がお偉いさんであろうと、ファントムであろうと、やられたらやり返す。それが俺たちヤンキーの宿命だ」
「おう!」五人がヘルメット越しに叫んで、片手を突き上げた。
しかし、チャーリーだけは黙ったままだ。
「宿命って、どういう意味だっけ?」日本語は難しい。
「英語でデスティニーだ」スコットが教える。
「なんだ、デスティニーか。なんだか、ロマンチックだな」チャーリーは笑う。
「ああ、歌の歌詞によく出てくるからな。だが、俺たちが奴らに思い知らせて、デスティニーを悪い意味に変えてやればいい。デスティニーという単語を聞くたびに、吐き気を催させればいい。俺たちは言葉さえ支配するヤンキーだ!」
スコット山田が叫んだが、他の六人は意味が分からなかった。チャーリーはもう一度意味を訊こうかと思ったが、気を使ってやめることにした。チャーリーは優しい英国紳士だ。
なぜ、紳士がヤンキーをやっているのか分からないが、その優しさが、後でややこしいことを引き受けることになる。
その後、七人はホームセンターに行き、バールとカナヅチなどを購入して、花桐理事長と西見校長、そして雷電高校への復讐の準備を進めた。
「善は急げだ! 今夜、決行する! たとえそれが悪であっても、俺たちにとっては善だ。俺たちにとっては聖戦だ! 負けられない戦いだ!」スコット山田がデカい声で吠えた。
しかし、他の六人は思った。
何もホームセンターの中で叫ばなくてもいいだろ。
みんなは他人のフリをしようと、近くにある商品を手に取って、品定めをしているフリをした。
チャーリーはたまたま緑色の便座カバーを手に取ってしまい、途方に暮れていた。
「What? 何これ?」
そして、夜の八時半。もっと遅い時間に決行したかったのだが、ヤンキー七人のうち、二人の家の門限が夜の九時だったから、この時間になったのだ。
俺たちはチームワークを大切にする。連帯責任も大切にする。そして、家族も大切にする。
二手に分かれて、雷電高校の周りを一周して、校門の前で落ち合う。
「チャーリー、どうだった?」スコットが訊く。
「俺たち以外に怪しい奴は歩いてない」
「こっちもだ」
外から見る限り、学校内のどの校舎も真っ暗で、もう誰も残ってないようだ。スコットたちは七台のバイクを学校から少し離れた空き地に止めて、歩いて校門に向かった。
どうすれば雷電高校に一矢報いることができるのか? 俺たち七人は無い知恵を絞って考えた。学校の窓ガラスを割ったり、放火したり、爆破することは大きなダメージを与える。しかし、俺たちはただの高校生ヤンキーだ。そんな極悪人のようなことはできない。まるで高校球児のような、爽やかで清々しい復讐が似合っている。
「俺たちにとって、もっとも頭に来て、もっとも痛手を受けることは何だ?」スコット山田が問う。
「名を汚されることじゃないか?」チャーリーが答える。
「俺たちヤンキー集団には名が無い。たとえば、名前がある暴走族にとって、それは何だ?」
「暴走族が掲げている旗を奪われることじゃないか?」
「それだ!」スコットがひらめいた。
七人は“雷電高等学校”という学校名が記された看板=学校銘板を盗み出すことにした。それは校門にあるコンクリートの壁に埋め込まれている、横120センチ×縦20センチ×厚さ15センチの金属製の銘板であった。四人を見張りとして学校の周りに配置し、三人でバールとカナヅチを使って、銘板を外すという作戦だ。
あらためて集合した校門付近には誰も歩いてない。
「よしっ、決行だ!」スコットが小さく叫ぶ。
チャーリーは首の周りに緑色の何かを巻き付けていた。
「何だ、それは?」スコットが訊く。
「さっきのホームセンターで買ったマフラーだよ」
「それは便座カバーだろ!」
「暖かくていいよ」
「便器に座ったとき、お尻が冷てぇ! とならないように暖かいんだよ。なんで、そんなものを買うんだよ」
「手に取った物は買った方がいいかなと思って」
「ヤンキーにそんな律儀さは不要だ。律儀もカバーもここに捨てておけよ」
スコットとチャーリーと井川が仕事に取り掛かる。
銘板の上の部分のコンクリートに三人で穴を開けて行く。左右と真ん中の三か所だ。
「意外に大きな音がするな」チャーリーが不安げに言う。
夜の街にカナヅチでコンコンと叩く音が響くのだ。
「心配するな、四人が見張ってくれている」スコットがなだめる。
十五分ほどが過ぎた頃、見張りの一人が電話をかけてきた。学校の前を誰かが通るようだ。
三人は作業を止めて、校門でウンコ座りをする。こんなこともあろうかと、全員学生服を着て来ている。チャーリーは急いで帽子をかぶり、金髪を隠した。
やがて、スーツ姿の中年男性が通りかかった。一度、こちらをチラッと見たが、ヤンキーが校門でタムロしていると勘違いして、目を合わさないよう、足早に通り過ぎて行った。
「よしっ、再開しよう」スコットが立ち上がる。
さらに二十分が経過し、銘板の上部に三か所の穴が開いた。その穴にスコットとチャーリーと井川が手をかける。
「いいか、せーので引っ張るぞ。――せーの!」
――バキバキッ!
“雷電高等学校”と書かれた学校銘板が見事に外れた。
「やったぜ!」
翌朝、雷電高校に出勤してきた教師が校門の壁に埋め込まれているはずの学校銘板が外されていることに気づいた。そして、なぜかそこには緑色の便座カバーが落ちていた。
理事長も校長も訳が分からず、首をひねる。
「校門=肛門、だから便器→便座カバーというシャレじゃないのかね?」
「ややこしいシャレですな」
「ところで、校長。うちの高校の銘板なんか盗んでどうするんだ?」理事長が疑問を呈する。
「銅なんかの金属は高く売れますからね」
「高校名が入っていたら、盗んだことがバレるだろう」
「買い取り業者に何者かが銘板を売りに来たら、すぐに通報してもらえるように、警察から通達を流してもらいましょう。先ほど110番させましたから、もうすぐ到着すると思います」
「しかし、学校銘板なんか売るかね。他に使い道といったら何だね?」
「受験のお守りにするとか」
「あんな大きな物をお守りにするかね?」
「もっとも、うちの高校は銘板をお守りにされるほど、偏差値は高くありませんがね」
「校長のアンタがそんなことを言うかね。まあ、確かにその通りだがな」
理事長の財力をもってしても、雷電高校に優秀な生徒は集まって来てないのだ。
昼食を食べ終えた頃、スコット山田とチャーリーが放送で呼び出された。校長・教頭室まで来いという。この二人が呼び出されるのは珍しくないので、誰も気にしていない
スコットとチャーリーは連れ立って歩き出すが、なぜ校長に呼ばれたのか、その理由が多すぎて分からない。チャーリーが心当たりのある理由をスコットに確認する。
「音楽の沢村先生の車に十円玉で引っかいて傷付けたことかな?」
「あの野郎が女子の肩に手をやったりしてセクハラをしていたから懲らしめてやったんだ」
「校内に飛んで来たハトに石を投げたことかな?」
「あちこちにフンを落として、用務員の岡戸さんも困っていたから、懲らしめたんだ」
「体育館に転がっていたバランスボールの空気を全部抜いて回ったことかな?」
「使ったきり片付けないから、整理整頓するように忠告をしてやったんだ」
二人は渡り廊下を歩いて行く。
「なあ、チャーリー。俺たちがやってることは正義だよな」
「弱きを助け、強きを挫く。これが真のヤンキーだよ。だから僕はヤンキーになったんだよ」
「俺に大和魂が宿っているように、チャーリーには騎士道精神が宿ってるというわけだ。俺たちはカッコイイよなあ」
スコット山田は、登山研修をさぼり、バイクでぶっ飛ばしながら、横断歩道を渡ってる人を蹴散らしていることなんかすっかり忘れて、自分の言葉に酔いながらも、ふと窓の外を見た。
「チャーリー、俺たちは昨日の件で呼ばれたらしい」
職員用の駐車スペースにロールスロイスファントムが、ケツをはみ出させて停まっていた。傍らに運転手らしき男が立っている。
「あれじゃ、十円玉で引っかけないね」チャーリーが言う。
スコットはどこかに電話をかけていた。
「――そうだ。十五分後に頼む。お礼はカヌレ? なんだそれは?」
校長・教頭室に入ると、草野校長と森教頭が応接セットに座って待っていた。向かいには雷電高校の花桐理事長と西見校長が座っている。
草野校長が声をかけた。
「スコット山田君とチャーリー何とか君。そこに座りなさい」
空いてるソファを指差す。チャーリーの本名はいまだにややこしくて覚えられないようだ。
「さっそくだが、昨日の夜、君たちはどこにいたかね?」
花桐理事長と西見校長が鋭い視線を向けて来る。
スコット山田は考えた。俺たちが呼ばれたということは、バイク七台で走っているところを、誰かに見られたか、どこかの防犯カメラに映っていたのだろう。ここでウソを吐くと墓穴を掘る。
「仲間とバイクで健全なツーリングにいそしんでおりました」
「仲間というのは、うちの生徒かね?」
「はい。ここにいるチャーリー君も含めた七人の気のいい奴らです」
「実はね」花桐理事長が割り込んで来る。「うちの銘板が盗まれたのだよ。君たちは知らんかね?」
「メーバンって何ですか?」チャーリーが訊く。
「銘板も知らんのか?」
「僕はイギリス人なもので知りません」
「俺はオカンがイギリス人のハーフなもんで、食べたことありません」
「食べ物ではない」理事長はムッとする。
「バームクーヘンのようなものじゃないのですか?」
「あんなもん、堅くて喰えん」
スコット山田もチャーリーも昨晩校門から盗んだ物を銘板と呼ぶことを知らなかった。つまり、とぼけているのではなく、本当に知らないのだ。
「学校名が書いてある看板みたいなものだ」理事長が説明する。「それがなくなったのだよ」
「はっきり言うと」今度は草野校長が口を挟む。「君たち七人が雷電高校の前をバイクで通るところを見ていた人がいたんだ。それで、君たちが犯人じゃないかと疑っておるのだよ」とはっきり言う。
あの看板が銘板と言うものだと分かったスコット山田がとぼけて訊く。
「その銘板というのはどのくらいの大きさなんですか?」
「だいたい、長さは一メートルちょっとだな」西見校長が答える。
「そんなデカい物を抱えてバイクに乗っていたら、おまわりに止められますよ。それとも、銘板を抱えてバイクで走る俺たちの姿を見た人がいるのですか?」
「いや、それはないんだが」理事長の歯切れが悪くなる。
「じゃあ、物的証拠が揃ったら、また声をかけてください」
スコットがズバッと言い切ったとき、理事長の電話が鳴った。
「なに。銘板が見つかった!? ――ああ、うん、そうか。分かった」
電話を切った理事長はみんなの方を向いて言った。
「たった今、見つかったようだ。校門の塀と花壇の隙間に落ちていたらしい。どうやら犯人は銘板を外した後、塀から校内に投げ込んだようで、園芸部の女子生徒が花壇に水をやりに行って見つけたようだ」
その女子生徒は雷電高校生なのだが、スコットの女友達で、さっき電話をかけた相手だ。
校門近くに学校名の書かれた看板が落ちているはずだから、今から十五分後に、なくなっている看板を見つけましたと、誰でもいいから先生に報告するようにお願いをしておいたのだ。その先生から、計画通り、このタイミングで理事長に電話が入ったというわけだ。
お礼に、スコット山田はカヌレという名前のスイーツを、その女子生徒に奢ることになっていた。
最近やっとマリトッツォという名前を覚えたというのに、今度はカヌレかよ。カヌレなんてスイーツはうまいのか? 日本人なら豆大福だろうよ。
外した銘板は意外に重くて大きかった。こんな物は持って帰れないし、持って帰っても扱いに困るということで、塀の向こうに放り投げていたのだ。スコットが強気だったのも、手元に証拠品である銘板を持ってなかったからである。
犯人不明のまま、スコットとチャーリーは釈放された。うちの教頭からは時間を取らせて済まなかったねと言われたが、向こうの理事長からは一言の謝罪もなかった。
だが、そんなことは想定内であった。あいつはそんな奴だ。一時的にせよ、雷電高校のお偉いさん方をアタフタさせて、少しは気が晴れた二人であった。
校長・教頭室から出て来たスコットとチャーリーは伸びをして、定番のセリフを言った。
「ああ、娑婆の空気はうまいぜ!」
建物から外に出てみると、昨日一緒に銘板を外した井川が立っていた。二人を心配して、ここまで迎えに来てくれていたのだ。
そして、彼も頭を深々と下げて、定番のセリフを口にした。
「お勤めご苦労さんです!」
ロールスロイスファントムの脇に立っていた運転手にジロリと見られた。
「ノープロブレム!」
チャーリーが片手をあげて、見事な発音で叫んだ。
ああ、キングズ・イングリッシュは美しい。
学校に対して理不尽なクレームや要求を繰り返す、モンスターペアレントが近年、話題になっているが、モンスターは何も親だけではない。たとえば、今、草野校長の前に座っている老人がそうだ。学校の近所に六十年以上、住んでいるらしいが、学校が出す騒音がうるさいと文句を言いに来たのである。かれこれ、三時間ほど居座っていて、まだまだ終わりそうにないので、草野校長の仕事を森教頭が代行している始末である。
「子供たちが騒ぐと言いましても、わざと騒いでいるわけではありませんし、声が聞こえますのは、休み時間と体育の時間と放課後くらいじゃないでしょうか」校長が同じ説明を繰り返す。
「いや、わしはそれがうるさいと言っておるんだ」
子供たちの声は元気でいいし、何も気にならないと言う人もいれば、あんなものは騒音であり、日々の生活に支障をきたすという人もいる。このじいさんは後者だ。年齢はおそらく八十代だろう。だが、背筋はしゃんと伸びている。白髪交じりの短髪であり、口はへの字に曲げており、三時間、一度も柔和な表情になったり、笑ったりしない。意志の強さがうかがわれる。
こんな頑固なじいさんは、毎日何を楽しみに生きておるんだと校長は思う。
「校内放送はなるべく控えます。チャイムの音や下校時の音楽のボリュームも下げます。教職員の車も、この近くではゆっくりと走り、クラクションはなるべく鳴らさないようにします」
校長はいくつかの提案をしているが、老人は聞く耳を持たず、騒音がうるさい、何とかしろの繰り返しである。では、具体的にどうしてほしいのかと訊いても、それはそちらで考えろの一点張りである。老人に出すお茶のおかわりは十回近くになっている。校長は二度、トイレに行くために席をはずしたが、じいさんはドカッと座ったままである。
この騒音ジジイの膀胱はどうなってるんだ? ジジイの性格のように、ずうずうしく肥大しておるのか?
校長のイライラも限界に近づいている。
電話のベルが鳴り、教頭がやって来た。
「校長、父兄から電話です。急用ということです」
「急用? では、ちょっと、失礼します」
校長が応接セットから校長机に向かい、受話器を取った。
「お待たせいたしました。校長の草野です」
受話器の向こうはツーツー音である。教頭が気を利かせて、ニセの電話をかけてくれたのだろう。おそらく自分のスマホからこの固定電話にかけ、自分で受話器を取り、スマホを切り、校長を呼びに行ったのだろう。
校長は教頭に感謝しつつ、何も言わない受話器に向かって、芝居を続ける。
「ほう、それは大変ですね。一刻を争いますな。学校としても、早急に対応を検討させていただきます」わざと老人の方に目をやる。老人もこちらを見ていて、目が合う。「はい、その件につきましては、ここに教頭もおりますので、今から話し合って、ご連絡を差し上げます。いえ、お待ちいただければ、至急に連絡いたしますので。はいはい。では、失礼いたします」
校長は急いで、爺さんの前に戻った。
「どうやら急用のようだな」
「いいえ、大丈夫です。先ほどの続きですが……」
「いや、また来る」
老人は残っていたお茶を飲み干すと、席を立ち、さっさと出て行った。
「いやあ、教頭先生、助かったよ」
「大変でしたね」
いつもは仲が悪い二人だが、この時ばかりは校長に同情していた。とっさの連係プレーはうまくいった。
「教頭先生、悪いけど、あの騒音ジジイの住所と名前を聞いたから、あの老人は普段どういう暮らしをしているのか、何をやっているのか、近所に探りを入れて来てくれんかね」
「敵情視察というわけですな。やってみましょう。何か弱みが見つかるといいですな」
教頭は、これで校長に一つ貸しができると考え、引き受けることにした。貸しができなければ、こんな面倒なことを引き受けるわけない。
翌日、教頭は帽子をかぶり、マスクをして、騒音ジジイの家の周りを歩き回り、じいさんは十年ほど前に妻を亡くし、今は一人暮らしをしており、酒が大好きで、よく昼間から飲んでいるということを聞き出した。さらに、以前は高校の数学の教師だったことも判明した。――まさか同業者だったとは。
さらに近所を歩き、一軒の酒屋を見つけた。店主にそれとなくじいさんのことを聞いてみると、ここでよく酒を買っているという。しかも、安い酒しか買わないということだった。教頭は校長と電話で相談した上、この店で一番高い、大吟醸菊理媛を五万円で購入した。代金は裏金である。ミニ四駆のプレイ代として、花桐理事長が毎回置いて行ってくれる一万円を積み立てたものである。つまり、校長と教頭の腹は痛まない。
その夜、校長はアポなしで騒音ジジイの家に行き、大吟醸菊理媛を渡して、大した話もせずに、帰って来た。
それ以来、じいさんは学校にはピタリと来なくなった。
昼休みの時間。学校犬ポチが校庭を走り回って、サッカーボールで遊んでいる。それを、近くで生き物係の犬井と鳥谷が見守っている。二人はポチと一緒に遊ぼうと近づこうとするが、サッカーボールの方が楽しいらしく、こちらを見向きもしない。
「ポチの前世はサッカー選手だろうな」犬井が言う。
「犬界では一番のドリブラーだね」鳥谷も感心する。
そんな二人と一匹を窓から見下ろしているのは、姫宮“マドンナ”生徒である。周りに三人の女子が集まっている。結菜と芽衣と葵だ。
先日、校庭にポチを見つけて、真っ先に教室を脱出した、くノ一三人組である。
「ホントに心当たりはないの?」結菜がマドンナ姫宮にまた同じことを訊く。
校内に奇妙なウワサが女子専用学校メールで流れていた。そのウワサとは、明日の午後六時、体育館で一人の男子が姫宮に公開ライブ告白するというもので、その見届け人として、女子限定で集まってほしいという内容であった。そして、このメールは決して男子に見せてはいけないと書かれていた。
当然、見届け人は強制参加ではなく、希望者のみだ。だが、こんな面白そうなイベントをスルーする女子は少数だと思われた。
結菜が姫宮に訊いていたのは、その告白してくる男子の名前だった。
「心当たりなんか無いよ」姫宮はそっけなく言う。
「そう言うと思ったよ」結菜は芽衣と葵に目配せする。二人はニヤニヤしている。「正確には“無い”のではなく、有り過ぎて、いったい誰だか分からないのでしょ」
芽衣が引き継いでしゃべる。
「今まで告白して来た男子は数知れないし、女子にも告白されているから、その人数は覚えてないのだろうね。いいよなあ」
葵も続く。
「まだ告白して来ない男子に加えて、断られたけど、もう一度チャレンジしようと企んでいる男子もいるだろうから、多すぎて、誰だか分からないよねえ。うらやましいなあ」
女子の嫉妬は怖い。容赦のない皮肉が飛び交う。だが、姫宮はどこ吹く風で、ニコニコしながら、三人の話をフンフンと聞いてあげている。嫉妬や皮肉なんていつものことだと意に介しない。この余裕がマドンナと呼ばれる所以だと三人は思った。
結菜がみんなに言う。
「日時と場所を指定してくるなんて、宝石を盗もうとしているルパン三世みたいじゃん」
すかさず、芽衣が銭形警部のモノマネをする。
「奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です」
「キャー!」言った本人も含めて、三人が叫ぶ。「ヤバいよねー」「ベタだよねー」「昭和だよねー」
叫んだ後、三人はあわてて声をひそめた。このイベントを男子に
知られてはいけないからだ。女子専用学校メールには、この内容を
男子に教えるとタタリがあると記されていた。朝起きてみると体が
牛になっているというタタリだそうだ。今までの人生から牛生に変
わりたくない女子は、決して男子に言わないように、口のチャック
を閉じた。
しかし、男子専用学校メールでも、似たようなイベント案内が流れていることを女子は知らない。男子のメールにも、それを女子に漏らすと、朝起きたら体が毛ガニになっているというタタリがあると書かれていた。今までの人生から蟹生に変わりたくない男子は、決して、女子に言わないように、口のチャックを閉じた。
翌日の午後五時四十五分。体育館の西入口から女子が続々と入って行く。入口で靴を脱いで、靴下のまま、足音を立てずに中央付近へと歩いて行く。誰もが無言だ。吐く息もわずかで、気配さえ微かなものになっている。時間を厳守して、そのように振る舞えとメールで指示をされていたのである。破ったら牛のタタリだ。
体育館は電気が消え、窓も黒いカーテンで塞がれて、真っ暗になっている。中央付近にはなぜか黒い幕が下されている。前方にある舞台の幕を持って来たようだ。この幕によって、体育館は二つに区切られていた。この幕の向こうに、告白する男子が待っているのだろうと、誰もが考え、興奮し、暗闇の中で、無言のまま、雰囲気は盛り上がっていた。
中央付近には公開告白をされる姫宮がいるはずなのだが、暗くて分からない。おそらく、幕のすぐそばに一人で立っているのだろうと誰もが思っていた。
やがて、約束の午後六時が近づいて来た。
みんなは声を出さずに、心の中でカウントダウンを始める。
“ファイブ、フォー、スリー、ツー、ワン、ゼロ!”
――午後六時ジャスト!
中央に下がっていた黒い幕が、いきなり落ちて、照明が灯された。
姫宮の姿はなかった。
幕の向こうには約五十人の男子生徒が群がっていた。男子専用学校メールには、午後五時三十分に東入口から体育館に入るように指示されていた。女子と同じく、靴を脱いで、静かに時が来るのを待つように、騒げばタタリがあると記されていた。毛ガニのタタリだ。
体育館の中は黒い幕で仕切られていて、男子は六時になるのを、無言で待ち、今、幕が下された。
女子の集団と男子の集団が見合った形になった。
女子はたくさんの男子に驚き、姫宮を探している。
男子もたくさんの女子に驚き、姫宮を探している。
「ちょっと、どういうこと?」一人の女子が男子に詰め寄る。
「いや、分かんねえって!」男子が後ずさりしながら答える。
無言を貫いていた男女が一斉に話し出し、体育館の中は騒然となる。
結菜が芽衣と葵に言った。
「わたしたち、ルパンにやられたよね」
すかさず、芽衣がまたモノマネをする。
「奴はとんでもないものを盗んで行きました」
「昨日、聞いたわ!」葵が文句を言う。「心を盗まれたというよりも、まんまと騙されて、むかついてるんですけど!」
女子と男子が情報を交換したことで、この企みの全貌が見えてきた。
女子のメールには、体育館で一人の男子が姫宮に告白をするから、見届けるように書いてあった。一方、男子のメールには、体育館で姫宮が待っているので、希望者は告白するように書かれていた。
中央付近に群れていた約五十人の男子は告白者であった。実に約百五十人の男子の三分の一の男子が姫宮に告白をしようと、集まっていたのである。五十人の男子の中には、熱き思いを伝えようと、手紙やプレゼントの箱を持つ者がいて、大きな花束を抱えている者まで来ていた。
告白男子の群れの先頭に立っていたのは、今年、社会人入学をした大久保田であった。
「大久保田さん、こんな所で何をやってるんですか!?」
男子たちは驚くととも大笑いをする。
「いやあ、年齢の数だけ、バラの花を買ってきたのだがねえ。ははは」
「六十六本っすか?」
「そうそう。六千六百円もかかってしまいましたよ。しかし、まさか、当人が来てないとはねえ。想定外ですよ。ねえ、野呂先生」
「ええっ!?」全員が驚いて、振り返った。
隅の方から定年間近の野呂先生が腰を曲げて、トボトボ歩いて来た。
いつものグレーのスーツを着て、やはり、バラの花束を抱えている。
「いやあ、私は五十九歳ですから、五千九百円かかりましたわ。それに、手紙も書いて来ました」
スーツの胸ポケットから取り出して見せる。ネコのイラストが描かれたかわいい封筒だ。
「わしも書きましたぞ」大久保田は学生服の胸ポケットから手紙を出す。汚い茶封筒だった。
ネコ封筒VS茶封筒。
女子はこの光景を呆れて見ていた。
「あの二人、うちのお父さんより年上だよ」
「ヘタすれば、おじいちゃんだよ」
「なんで、自分の年齢の数のバラを買うかね」
「普通、相手の年の数でしょ。うちら十七歳だから、十七本でいいんだよ」
「あの二人、絶対、一緒にお花屋さんへ買いに行ったよね」
「あのう、バラの花をプレゼントしたいので、六十六本包んでくれるかね」
「わしは五十九本じゃ」モノマネをする女子まで現れる。
「お二人合わせて、一万二千五百円になります」花屋のモノマネ。
「あのう、お会計は別にしてくれるかのう」「領収書も別々で頼みますぞ」
容赦なくからかう女子。
そして、女子たちは、男の人って、いくつになってもバカだよねと結論付けた。
「でもさ。このイベントは誰が仕掛けたの?」
「姫宮の姿が見えないのだから、あの子が仕掛け人だよ」
「目的が分からないよね。まさか、うちらをからかった?」
「もしかして、みんながコミュニケーションを取れるように計画してくれたんじゃない?」
体育館に集まった男子と女子は騙されたことも忘れて、あちこちで楽しそうに談笑している。もともと、普段から男子と女子の間ではあまり会話がなく、両者に大きな壁があるような高校だったため、この光景は珍しい。
「――だとしたら、大成功だね!」
いまだに呆然と立ち尽くす大久保田と野呂先生以外は、時間が経つのも忘れて、男女で会話を楽しんでいる。男子も女子もまんまと騙された。だが、騙された者同志に連帯感が生まれたのだろう。
突然体育館の照明が消えた。
そして、中二階にあるギャラリーと呼ばれている部分に三人の人影が現れた。なぜか、ライトアップされる。ちょうど光が当たるように照明器具がタイマーでセッティングされていたようだ。
三人はそれぞれ赤と青と紫のレオタードを着ていて、それぞれが赤と黄と青の腰ヒモでウェストマークしていた。
「キャッツ・アイだ……」誰かがつぶやく。
その三人とは、小久保“マドンナ”先生と、姫宮“マドンナ”生徒と、シスターのマリー・アマーチェだった。
生徒はギャラリーを見上げた。そして、理解した。
黒幕は小久保先生だったのだと。
「みなさん!」小久保先生が口を開いた。「今夜のパーティーはいかがでしたか?」
全員がいっせいに拍手をして、歓声をあげた。男子と女子が仲良くなれるように、仕掛けられたのだと分かったからだ。
そして、それは成功している。体育館内の雰囲気がそれを示している。
「これからも、みんな仲良く……」
小久保先生の話が途切れた。みんながスマホを持って駆け寄り、写真を撮り始めたからだ。
マドンナ先生とマドンナ生徒のレオタード姿など、お目にかかれる機会など滅多にない。さらにシスターだ。いつもは白と黒の地味な修道服を着ているシスターが、なんと紫色のレオタードだ。こんな機会は一生に一度あるかないかだ。――ないに決まっている。
こんな光景をイエス様が見たら腰を抜かすだろう。しかし、たくさんの生徒に喜んでいただき、幸せになっていただくというのは博愛である。キリスト教の博愛精神である。あの世から叱られはしないだろう。
体育館の中は“竜巻高校キャッツ・アイ”に向けて、次々に焚かれるフラッシュで眩しい。しかし、なぜ、シスターがここにいるのか、誰にも分からない。神出鬼没のシスターである。
写真を撮ろうと群がっているのは男子生徒だけではない。女子も全員ギャラリーの下に集まっている。三人は普段から女子にも人気があるからだ。
呆然と立っていた大久保田と野呂先生も、再びスイッチが入ったかのように、活発に動き出し、シャッターをパシャパシャ切っている。普段からは考えられない、すばやい動きだ。
「いやあ、大久保田さん、いい夜になりましたなあ」
「野呂先生、私はこの学校に入学して良かったですわ」
「こりゃ、青春ですな」
「生きてて良かった~」
「ははははは」
「いひひひひ」
高齢者の高笑いが体育館に響いた。
用務員岡戸は刺股を手に体育館に近づいていた。さっきまで生徒たちが体育館で何かのイベントをやっていたようだが、もう帰ってしまって、誰もいないはずだ。だが、何か物音と声が聞こえる。その正体を確かめようと、近づいているのである。刺股は必需品だ。
なんといっても、二宮金次郎に二度も追いかけられて、木娘に笑いかけられたのだから、第三のお化けが出ないとも限らない。二度出ることは三度出ると言うではないか。
岡戸はそっと扉を開けた。中は真っ暗だ。だが、窓を塞いでいた黒いカーテンは外されているので、月の光が入り込んでいて、まったく見えないわけではない。右手で刺股を抱えたまま、手探りで壁の電気のスイッチをパチパチと押した。
中央に第三のお化けが立っていた。
「あら、岡戸ちゃん!」保健室の主、アラフィフの美魔女恵子先生だった。
「なんだ、恵子先生か……」全身の力が抜けた。
「なんだとは、冷たいわねえ。岡戸ちゃんと私の仲よ」腰をくねらせて言う。
「いや、アンタとは用務員と保健師の関係でしかない」きっぱり返す。勘違いされては困る。
先ほどから岡戸は遠くを見ながら話している。恵子先生が真っ白のレオタード姿だったから、直視できないのだ。しかも、既製のレオタードを得意の裁縫で加工し、体の線がよりくっきりと見えるように詰めて、さらに必要以上に布が股間に食い込むようにしてある、超ハイレグレオタードだったのである。
体操のコマネチもここまで喰い込んどらんかったぞ。
しかも、若いコマネチと違って、アラフィフである。第三の白いお化けから視線を外したくなるのも無理はない。
「恵子先生はここで何をしとるんだ? エアロビの練習かね?」天井を見上げて訊く。
「違うのよう。ここで今夜、公開告白大会があると聞いて参加したのよ」また腰をくねらす。「私の作るチャーハンが気に入って、保健室に食べに来てくれるシスターからの情報よ」
ときどき保健室には悩みを持った生徒がやって来るのだが、保健師だけでは解決が難しい悩みを、近所の教会のシスターのマリー・アマーチェさんへ下請けに出していたのである。そして、いつしか、マリー・アマーチェと恵子先生はチャーハン仲間となったのである。
「もしかして、恵子先生は誰かに告白しようと思っておったのかね?」床を見ながら訊く。
「そうよぉ。この際、若けりゃ誰でもいいのよ。でも、来てみたら誰もいなかったというわけ。午後六時開始のはずだったのに、おかしいわねえ」
「先生、今は七時だよ」腕時計を見ながら言う。
「えっ、そうなの!? 一時間、間違えた。アチャー!」
恵子先生は手のひらで額をペシッと叩いて、昭和の悔しがり方をした。
「そうと分かったら帰りましょ!」恵子先生は切り替えが早い。「ところで、岡戸ちゃんは何で刺股を持ってるわけ?」
アンタのような白いレオタード喰い込みお化けが出たときのためとは言えない。
「体育館から物音と声が聞こえたから、怪しいと持って、一応持って来たんだよ」
「きっと、それは私の声よ。誰もいなかったから悔しがって、独り言を言っていただけ。年を取ったら独り言が増えると言うけど、年を取らなくても、独り言は出ちゃうのよね」
いやいや、十分、あんたは年を取ってるよとは言えない。
「ところで、岡戸ちゃんは刺股なんか使えるの?」
「ああ、悪者が現れたらこれで戦うのさ」
岡戸は刺股をビュンと振り回す。
「あら素敵!」アラフィフの美魔女レオタードが手を叩いて喜ぶ。
「こう見えても、刺股三段の国家資格を持っておる」いい加減なことを言う。
「だと思ったわ」いい加減な答えが返って来る。
岡戸は電気のスイッチを消して、今日一日で、いろいろな思いが詰まった体育館の扉を閉めた。残念ながら、岡戸はキャッツ・アイを見ることができなかったのだが。
「いい夢を見させてくれてありがとね」
美魔女が体育館に向けて、投げキッスをした。
「ところで岡戸ちゃん、この使用済みハイレグレオタードを三千円で買わない?」
「買わない」
「刺股と交換しない?」
「しない」
「好きな人にはそうして冷たくするのよねえ」勝手に決めつける。
「わしは用務員室に戻るから」岡戸は相手をするのをやめて、刺股をかつぎながら、早足で去って行く。
公開告白大会に参加しそびれた美魔女の恵子保健師は着替えるために、トボトボと保健室へ戻った。
すると、なんと、入口に大きなバラの花束が置いてあるではないか!
「あら! 誰かしら、私への告白かしら!?」
恵子先生は花束の中をくまなく探したが、手紙は入ってなかった。
「差出人が分からないわ。きっと照れくさくて、書けなかったのよね。分かるわ、その気持ち。シャイな誰かが、どこかで私のことを見つめてくれている。――あら、素敵じゃない」
苦労して数えてみると、バラの数は百二十五本あった。
「なんで、百二十五本なのかしら?」
恵子先生はいくら考えても分からない。
使い道がなくなった大久保田の六十六本と、野呂先生の五十九本を合わせた、百二十五本のバラを、二人がそっと保健室の入口に置いてあげたことを、美魔女は知らなかった。
「私って、まだまだ捨てたものじゃないわね!」
美魔女の全身には、さらなる自信がみなぎって来た。
「よっしゃー!」
その自信で、白色喰い込みレオタードがはち切れそうになった。
今夜の月の光はいつもよりやさしく感じた。
竜巻高校の校長・教頭室では五人の人物がテーブルを囲んで座っていた。校長と教頭が並んで座り、向かい側にウマイ寿司の大将と女将が座り、横には新任の体育教師中村が座っている。
「こちらです」中村が一枚の紙をテーブルの上に置いた。
それは、新しく作るサッカー部の部員名簿だったのだが、同時に試合のメンバー表になっていた。まだ試合も何も決まってないのだが、気の早い中村が仕上げてきたのだ。
----------------------------------------------------------------------
「竜巻高校サッカー部」
*部長:中村正敏(28)→新任の体育教師。
*監督:馬居徳之助(59)→ウマイ寿司の大将。
*コーチ:馬居清子(52)→ウマイ寿司の女将。
~先発メンバー~
・GK:
チャーリー(17)→ヤンキー留学生。
・DF:
犬井太(17)→生き物係。
鳥谷海斗(17)→生き物係。
平井一郎(17)→生徒会長。
金森太陽(17)→生徒会副会長。
・MF:
宮井健太(17)→学食でバイト。
中島優斗(17)→松寿司がニックネーム。
安藤陸(17)→自称ラッパー。
・FW:
玉本和男(17)→ラグビー部と兼任。
足立壮四郎(17)→ラグビー部と兼任。
遠藤朝陽(15)→スポーツ飛び級。走る遠藤豆。
*控えメンバー
大久保田作太郎(66)→社会人入学。手芸部と兼任。
*チームドクター
佐藤恵子(推定50前後)→保健室の先生。自称美魔女。
*マネージャー
小久保百合(28)→英語教師。マドンナ先生。
姫宮瑠伽(17)→マドンナ生徒。
*用具係
岡戸恭四郎(66)→用務員。
---------------------------------------------------------------------
草野校長が部員名簿を手に取った。
「うーん」自慢の口髭に手をやりながら唸っている。「部員数は控えを入れて、十二人か。ギリギリ試合はできるな」
「どうでしょうか?」中村が不安げに訊く。
みんなの視線も校長に集まる。
「素晴らしい!」校長が叫んだ。「短期間でよくここまで仕上げてくれた!」
「ご理解いただいて、安心しました」中村はホッとしたようだ。
これだけのメンバーを揃えるのには苦労した。生徒たちは既にどこかのクラブに所属しているか、帰宅部だったため、なかなかウンと言ってくれない。持ち前の情熱を全開にして語っても、分かってくれない生徒ばかりだった。
そこで、試合のときだけでも来てくれるようにお願いをした。試合を重ねるごとに、その活躍を見て、部員が増えるのではないかと期待したからだ。
チャーリーは優しい英国紳士だった。その優しさに付け込んで、強引に話を進めたら、観念して、引き受けてくれた。だが、ヤンキーリーダーのスコット山田はどうしても首を縦に振らなかった。ヤンキーとしての矜持を保ちたいらしい。確かにスポーツで汗を流すヤンキーはいないだろう。
生き物係の犬井と鳥谷には学校犬ポチの世話を頼んだ。その際、エサ代などの経費を校長と交渉して、必要以上に獲得してやった。その恩を利用して入部させたのである。彼らに運動の経験はない。当然、人数合わせの入部である。
平井生徒会長と金森生徒会副会長には、今後の竜巻高校の発展のために一肌脱いでくれ、竜巻高校史にお前たちの名前が残るぞと、いい加減なことを言って口説き落とした。
学食でバイト中の宮井にも声をかけた。
「僕はこの通り、痩せてますし、体力はありませんよ」
「学食のバイトはいくらもらってるんだ?」
「五十分で千円です」
「一試合九十分で三千円出そう」
「入ります!」
簡単に落とせた。
松寿司がニックネームの中島には、サッカー部の監督がウマイ寿司の大将だとこっそり教えたところ、いつもお世話になってますからと、気持ち良く引き受けてくれた。
自称ラッパーの安藤は、酒井先生に入部の依頼をしてもらった。英語の授業が終わって、一言二言話しただけで承諾を得たらしい。どう言って納得させたのか分からない。魔法でも使ったのか?
「安藤君、中村先生がサッカー部員を集めてるのだけど」酒井先生がじっと見つめる。
「僕は足の骨に四本のヒビが入ってまして」安藤はうつむく。
「あら、そうなの」先生の飛び蹴りでヒビが入ったのだが知らんフリである。「サッカー部が活動を始める頃には、治ってるでしょう」
「でも、スポーツは苦手ですし」
「今すぐ、ヒビの本数が五本に増えてもいいの?」
「入ります!」
簡単に落とせた。
ラグビー部の玉本と足立は、サッカーの試合はせいぜい週二だからと、兼任で入部してくれた。部室で苦労して説得した甲斐があった。
スポーツ飛び級の遠藤もサッカーをやったことがないと断って来たが、ボールに触らなくてもいい、ワーワーキャーキャー言いながら走り回ってくれればいい。君は走るのが好きだろうと言って納得してもらった。
社会人入学の大久保田さんは控えだ。全校生徒に声をかけたのだが、次々に断られて、もはや残っていたのは大久保田さんしかいなかったのだ。ケガ人が出たときのために勧誘したのだが、若い人と触れ合いたいということで、二つ返事でサッカー部に来てくれた。普段はベンチを温めるための要員だが、ベンチ内で編み物をしてくれていてもかまわないと言ってある。残り物には福があるというから、何かの役には立ってくれるかもしれない。
チームドクターは恵子先生だ。男子のサッカー部だと言うと、こちらも二つ返事で引き受けてくれた。女子のサッカー部だと来てくれなかっただろう。老いてますます盛んだと思ったが、もちろん口に出して言わない。
二人のマネージャーにはダブルマドンナを配置した。もちろん、選手のモチベーションを上げるためである。男は美人の前では張り切るものである。女性教師がサッカー部のマネージャーというのはおかしいが、校長がいいと言ったので、いいことにする。他校からクレームが入ったら、校長のせいにすればいい。
最後に、用具係は用務員の岡戸さんだ。学校内のいろいろな用具のことに知悉しており、また顔に似合わず器用だから、何かと便利だろう。もちろん便利屋としてチームに加わってくださいとは言ってない。
部員名簿を見て、校長と仲が悪い教頭はイチャモンを付けてきた。特に要望はないのだが、さっき校長が素晴らしいと言って褒めたため、何でもいいから、逆らいたいのだ。
「この中でサッカー経験があるのはどの子ですか?」
「いや、いません」中村は痛いところを突かれたと思った。
「では、運動経験があるのはどの子ですか?」
「ラグビー部の玉本と足立だけですが、飛び級の遠藤は小柄ですけど、足が速く、走る遠藤豆と呼ばれて、先日、学校犬ポチに勝利して、学級新聞の号外に写真入りで載りました」
「確かに短期間で部員とスタッフを揃えたのは評価しましょう。しかし、はっきり言って、寄せ集めではないでしょうか?」教頭はホントにはっきり言う。「監督はどう思われますか?」
みんなの視線が大将に向かう。だが、いつもは大将と呼ばれていて、監督と呼ばれ慣れてないため、自分が訊かれていると気づかない。隣の女将から足を蹴飛ばされて、やっと覚醒した。
「――えっ、わしか? ああ、そうですね。中村先生はよくやってくれたと思いますよ。まあ、試合を重ねるごとに経験も積まれますから、強くなっていくのではないですか。強くなれば、有望な人材も入ってきますよ。監督としては、与えられた条件の下で全力を尽くすだけですよ」
「コーチはどうお考えですか?」教頭が女将さんに訊く。
「私もうちのダンナ、いえ、監督と同じ考えです。私のあらゆるサッカー知識を動員して、指導をしていく所存です」
詳しいのは韓流のサッカー選手の顔と体型だけだとは言えない。そもそもこの夫婦は強引に監督、コーチに任命されたのだ。いつも上等な寿司を頼んであげているじゃないかと言われて、断れなかったのである。
さらに先日は、登山研修用にと、三百人分のちらし寿司の注文をいただいた。校長にはかなり値切られたが、これでダメ押しをされた形だ。
しかし、この部員名簿を見て、首からお揃いの十字架をかけた寿司屋の夫婦は内心喜んだ。このメンバーでは他校に勝てない。素人が見ても分かる。
二人の考えは、三か月間だけ監督とコーチ引き受けよう。その間、いくつかの試合があるだろう。しかし、きっと成績は悪いだろう。だから、二人して解任されるだろう。よって、堂々と辞めていけるだろうというものだった。
だが、その間の監督、コーチ料は成績に関係なく、ガッポリといただいてやる。そして、今、このメンバーを見て、二人は確信した。――試合は全戦全敗だ。
思惑通りに事が運びそうで、笑いそうになる。たった三か月の辛抱だ。後はたんまりとギャラをもらう。そして、また日常の寿司屋の大将と女将の生活に戻る。
それでも、大将は名簿を見て、一つの疑問をぶつけた。何か言っておかないと、やる気がないことがバレるかもしれないと思ったからだ。そこで、中村に向かって訊いてみた。
「控えメンバーに書いてある、六十六歳の大久保田さんというのはどういう方ですか? 随分と年配の高校生のようですが」
「この方は今年から社会人入学された方で、年金で学費を払っておられます」
「サッカーの経験がおありですか?」
「いいえ。編み物がご趣味で、セーターでもマフラーでも手袋でも編むことができるという、素晴らしい人格者です。このたび、手芸部にも入部してくださいました。まだ男性部員は一人だけですが、晴れて大久保田さんが部長に選出されました」
大将はホッとした。ブラジルにサッカー留学の経験がある六十六歳だったら、大変だと思ったからだ。レジェンド釜本邦茂の優秀な直弟子であってもいけない。彼らは年齢に関係なく、すごいはずだ。そんな大物はいらない。間違っても、試合に勝ってはいけないのだ。
「ですので、大久保田さんは手芸部との兼任です」
「それはお忙しいところを申し訳ないですなあ」大将はわざとらしく言う。
隣に座ってる女将も大将の気持ちを察して、笑いが込み上げそうになった。長い間、夫婦をやっているため、何を考えているのか、だいたいは分かるのだ。
中村は部員名簿を校長に見せて、承諾を得られたので一安心だった。途中で教頭がゴチャゴチャ言ってきたが、何とか切り抜けることができた。これから部員たちをじっくり育てて、半年後くらいに、他校との練習試合ができればいいかと考えていた。そして、その後はしだいに力をつけて、ゆくゆくは日本一だ。最終的には、日本一を踏み台にして世界一を目指す!
相手は世界だ。そう焦ることもない。一歩ずつ前進することが大切だ。十二人の部員にもそう言って聞かせよう。
中村の体の中ではやる気が燃えたぎっていたが、大将と女将はまるでやる気がないことに気付いてなかった。
校舎から外に出ると、ちょうど職員用の駐車スペースに、ロールスロイスファントムが滑り込んで来た。雷電高校の理事長御一行様だ。おそらくミニ四駆のレースを楽しみに来たのだろう。ヒマな連中だ。花桐理事長と西見校長が揃って下りて来た。
「これは中村先生、お元気ですか?」
理事長が明るい声で挨拶をしてくる。
この人物はこのように外面だけはいいので、生徒や父兄にある程度の信用がある。
「はい。おかげ様で」明るい声で返してあげる。
「その後、サッカー部の創設の件はどうなっておるのかね?」
「はい。もう出来上がりました」
「ほう、そうかね」理事長の目がキラッと光った。中村の自信ありげな言い方が気に入らなかったようだ。「しかし、お宅の新設サッカー部が、我が雷電高校サッカー部に勝つには三十年早いでしょうな。残念ながら、わしはそんなに長生きができん。見たかったよ、うちの名門サッカー部が君の新設サッカー部に負けてしまうところをな」
皮肉たっぷりの言葉を受けて、中村の目もキラッと光った。
「見せてあげますよ。理事長がご存命中に、うちのサッカー部が勝つところをね」
「言ってくれたねえ」理事長は表情に出さないが、怒っている。「その試合は一年後かね、二年後かね、それとも十年後かね? それくらいならわしも生きておるぞ」
「ご冗談を。今月中ですよ」
「ほう。今月といえば、あと二週間しかないが、そんな大口を叩いていいのかね?」
「もちろんですよ」また自信ありげに答える。
理事長は竜巻高校にサッカーができる人材などいないことを知っている。指導できる教員もいないことを知っている。サッカー部を作ったといっても、寄せ集めだということも見抜いている。よって、自信があるように見せかけている中村の表情と違って、理事長は余裕の表情をしている。
我が雷電高校には、サッカーでもミニ四駆でも勝てるわけなかろう。
「ならば、記念すべき初戦のために、グランドは我が雷電高校が提供しようではないか。電光掲示板も稼働させよう。審判も準備しておこう。はっきりとした日時の交渉は西見校長とやってくれたまえ」
指示された西見が頷く。「後ほど打ち合わせの電話を入れます」
「中村先生、また会おうや」理事長は薄ら笑いを浮かべる。
運転手を残して、二人は校長・教頭室へ向かって行く。背中には余裕が感じられる。雷電が負けるわけないという自信の現れである。
中村は売り言葉に買い言葉で、ついカッとなり、後になって、大変なことになってしまったと後悔した。
半年後くらいに、他校との練習試合ができればいいと考えていたのに、わずか二週間後になってしまったからだ。
ああ、みんなにどう伝えればいいのか。
しかし、時間は待ってくれなかった。
そして二週間後。雷電高校と竜巻高校の初試合の当日。天候は晴れ。気温、湿度ともに絶好のサッカー日和となった。
雷電高校の観客席に、エッホ、エッホの掛け声とともに、理事長を乗せた神輿が到着した。かついでいるのは相撲部の面々である。サッカー部の精鋭たちは試合出場のため、今日は相撲部の精鋭たちに変更されていた。当然、サッカー部員より屈強である。よって、神輿の運行はサッカー部員がかつぐより揺れも少なく、安定していた。そのため理事長はご機嫌である。
やがて神輿は右折の方向指示器をカチカチ点滅させると、メインスタンドのホーム側にゆっくりと下ろされ、専用器具で固定された。理事長はこのまま神輿を下りることなく、一段高いところから観戦することができる。神輿のすぐ横には西見校長が控え、大きなウチワで理事長をあおいでいる。
雷電高校の観客席にはホームゲームということもあり、チアガールや吹奏楽部や応援団など、多数の生徒が学校カラーの黄色いTシャツを着て、集まっている。既にいくつもの旗が振られ、声援も飛び交い、活気に溢れている。
一方、メインスタンドのビジター側の席に座っていたのは、竜巻高校の草野校長と森教頭の二人だけだった。広い観客席には誰も来ていない。
一陣の風が空しく埃を巻き上げた。
「教頭、うちは我々二人だけかね?」校長が寂しい周辺を見渡して言う。
「はあ、何分にもアウェーなものですから」申し訳なさそうに言う。
雷電高校の吹奏楽部が演奏前の音出しを始めた。
「教頭、うちに鳴り物がないのは寂しいなあ」
「二人だけですから、手拍子くらいしかありませんよ」
「では、ちょっと叩いてみるか」
校長と教頭がパチパチと手を叩いてみる。
「やめよう」校長は諦めが早い。「余計にむなしい」
「今日の試合のことは、学校メールで全校生徒に伝えてありますから、ボチボチ来ると思いますよ」教頭は諦めない。
そのとき、反対側のバックスタンドに何か光るものを見つけた。
「校長、あれを見てください。テレビカメラですよ」
「何! なんでこんな高校生の練習試合がテレビで放映されるんだ!?」
「花桐理事長の仕業じゃないですかね」
「あのタヌキオヤジ、金に物を言わせてテレビ局を買収しやがったな。――教頭、この観客席を映されたらマズいよ。ポツンと二人だけだからな」
「校長、いいことを思い付きましたよ。生徒たちに、サッカーの応援に来ればテレビに映ると言えばいいのですよ。みんな、映りたくてやって来ますよ」
「おお、それは名案だな。さっそく頼むよ」
教頭は学校に残っている事務員に電話をかけて、もう一度学校メールを全校生徒に発信してくれるよう依頼した。テレビに映って、スターになれるという校長の緊急メッセージを添付して。
「校長はテレビに出たことがありますか?」
「昔、大雪が降ったとき、派手に転んで、それがたまたま風景を撮っていたカメラに映り込んで、全国ニュースで流れたことがあるよ。あのときは参ったな。今なら顔にモザイクがかかるだろうけど、昔は個人情報だの、プライバシーだの、厳しくなかったからな。会う人、会う人に、お宅、転んでましたなと言って笑われたなあ。わっはっは」
――ピーッ。
「何だ、今の笛は?」
「校長、試合が始まりました」
「何! わしはまだ君が代を歌っとらんぞ!」
「高校の練習試合では歌いませんよ」
「二人で歌おうじゃないか!」校長が立ち上がる。
「座ってください。テレビに映ってしまいますよ。二人だと、君が代をデュエットしてるみたいじゃないですか。国歌を侮辱してはいけませんよ」
雷電の西見校長が双眼鏡を片手にグランドを偵察している。
神輿の上に座っている理事長から声が掛かる。
「竜巻高校の選手はどうかね?」
「まず、使えそうなのはフォワードの二人ですね」
校長が指差す方向にいるのは玉本と足立である。ボールを追いかけて走っている。
「おそらく、どこかの運動部と兼任していると思われます。あのゴツイ体型からしてラグビー部じゃないでしょうか。それと同じくフォワードの小さい選手ですね」
「あれは遠藤だろう」理事長は知っていた。「さすがにスポーツ飛び級だけあって、足が速いな」
「走る遠藤豆と呼ばれてます。しかし、彼はさっきから、ワーワー叫びながら走ってるだけで、一度もボールに触れてません。サッカー経験はないでしょう。しかも、年齢からすると、まだ中学生ですから、そんなに体も出来上がってませんね。あとはゴールキーパーですね」
「おお、金髪の外国人選手だな。助っ人外国人か?」
「おそらく留学生でしょう。かなりの上背がありますが、まだシュートは飛んで来てませんので、その力は未知数です。――使えるのは以上ですね」
「部員たちは高さもないようだな」
「外国人キーパーを除くと、平均身長は百七十センチに満たないでしょうね」
「思った通りの寄せ集めだな。監督とコーチはどういう人物だ?」
校長は双眼鏡をベンチに向ける。
「ベンチには四人います。部長の中村先生と、ユニフォームを着た控えの選手と思われる生徒。あとは監督とコーチでしょうか。しかし理事長、なんだか変ですよ」
「どうした?」
「まず、控えの選手と思われる生徒は白髪で、どう見ても年配者です」
「いろいろと苦労して、老けとるんじゃないかね」
「それと、監督とコーチですけど、これも年配の男性と女性で、首から揃いの十字架を下げてます」
「神頼みで勝とうというのだろう」
「二人とも白い割烹着を来て、白い長靴を履いて、男性の方は頭にねじり鉢巻をしてます」
「なんだそれは? まるで寿司屋の大将と女将じゃないか」
「まさか、寿司屋の大将と女将が監督とコーチをやるとは思えせんが」
「当たり前だ。監督が寿司屋の大将を兼任してるサッカー部なんて聞いたことがないぞ。まあ、二人の素性は分からんが、それだけ人材不足ということなのだろう」
「こんなチームに我が雷電高校サッカー部が負けるはずがありません」
「そういうことだ。テレビ局にも来てもらって、全国放送してるんだ。あんな変なチームに負けたら日本中に恥をさらすことになる」
雷電高校の吹奏楽部が力強い音を奏でている。
一方、竜巻高校の応援席は静かなままだ。
「教頭、うちの吹奏楽部はどうしたんだ?」
「今日は全国大会の地方予選に参加していて不在です」
「雷電高校の吹奏楽部は演奏をしとるぞ」
「彼らは前年、好成績を収めたので、シード校として地方予選を免除されてます」
「そういうことか。向こうは何もかも優秀だな」
「しかし、校長。うちには吹奏楽部とは別の音楽系クラブがあります。――ほら、到着しましたよ」
和服姿の六人の男子生徒がこちらにやって来た。
「教頭先生。遅くなりました」六人が静かに頭を下げる。
「おお、待っていたよ。もう試合は始まっている。さっそく演奏を始めてくれるかね」
「向こうは今、鉄腕アトムを演奏しておるぞ」校長からも声がかかる。「アトムに負けないように頼むぞ」
男子はバックからそれぞれ楽器を取り出して、演奏を始めた。
まず、一人目の男子が小さな笛を吹き始める。
プゥ~。プゥ~。プゥ~。
「教頭、あれは何の楽器かね?」
「ひちりきです」
「小さい楽器なのに大きな音が出るな」
「あまりにも大きい音なので、清少納言はうるさくて聞きたくないとまで言ってます」
二人目の男子は細い竹を束ねたような楽器を吹き始めた。
プァ~。プァ~。プァ~。
「教頭、あれは何の楽器かね?」
「笙(しょう)です。あれは息を吸っても吐いても音が出るのですよ」
「なかなか神秘的な音がするな」
三人目の男子は一メートルほどの楽器を取り出した。
ポロロン。ポロロン。ポロロン。
「あれは何の楽器かね?」
「琵琶です」
「この子たちは何のクラブかね?」
「雅楽部です」
「この子たちの演奏を聞いていると、おごそかな気分になって、太古に思いを馳せたくなるのだが、ピッチを駆け回ってる選手を鼓舞するには至らないと思うが」
「では、残り三人の演奏を聞いていただけますか」
「何を演奏するのかね?」
「三人で尺八を吹きます」
ブォ~。ブォ~。ブォ~。
「おお、これはお正月の定番の曲、宮城道雄の“春の海”ですよ」教頭は名曲が聴けてうれしそうだ。
「教頭、確かに正月らしいゆったりとした気分になれるが、和楽器というのは、サッカーの応援に合っておるかね?」
「しかし校長、うちの音楽系クラブはもう一つあります。そちらは和楽器ではなく、洋楽器を奏でます。十分、期待が持てますよ。――あっ、ちょうど来ました」
「校長先生、教頭先生、遅くなりました」
場違いなピンクのドレスを着た女子生徒が、大きな楽器を抱えて立っていた。
「君は何を演奏してくれるのかね?」
「ハープです」
女子生徒はハープをセットすると、華麗に弾き始めた。
ポロン、ポロン、ポロン。
「校長、素敵な音色ですねえ。――校長?」
「ああ、すまん。寝てた。あまりにも安らいだもので」
雅楽部の和服の六人の男子と、ハープ部のピンクドレスの女子が並んで演奏している。
プゥ~。プゥ~。プゥ~。プァ~。プァ~。プァ~。ポロロン。ポロロン。ポロロン。ブォ~。ブォ~。ブォ~。ポロン、ポロン、ポロン。
和楽と洋楽のコラボである。シュールな光景である。
「教頭、我々がやってることは、おかしくないかね?」
「特に違和感はありませんが」
「なんだか、うちの応援はサッカー場に合わないと思うのだがなあ」
雷電高校が応援ソングの定番、宇宙戦艦ヤマトの演奏を始めた。
「あれっ、校長、大変ですよ!」
「どうした?」
「うちの高校が二対ゼロで負けてます」
神輿の上に座っている理事長から、ふもとで双眼鏡を覗く西見校長に声が掛かる。
「二点差なら、もう竜巻高校に勝つ見込みはないだろう」
「おっしゃる通りです。奴らは所詮、寄せ集め。最初から勝敗は見えておりました」
理事長が神輿から立ち上がって、声援を送る。
「我が雷電高校の選手諸君! 楽勝だぞ。もう手を抜いてもいいぞ!」
走っている雷電高校の選手たちから笑いが漏れる。
「ケガをしないようにボチボチやればいいぞ! あまり真剣にやると、弱い者いじめになるからな! 常に相手のことを考えてあげることが、人生には必要だぞ!」
またも、選手たちが笑い転げる。
「おい、相手の竜巻高校の選手たち! もっと真剣にやりなさい! うちの選手がヒマそうにしとるぞ! もっと攻め込んで行きなさい!」
理事長は相手の選手にヤジを飛ばし始めた。
雷電高校の強力フォワードが波状攻撃を仕掛けていた。竜巻高校のベンチからは、ウマイ寿司の大将こと馬居監督と、女将の馬居清子コーチの声が飛んでいるが、何かを指示しているわけではなく、ただ「がんばれー!」「しっかりー!」と叫んでいるだけだった。二人して、初めての采配なので緊張していて、具体的で的確な指示など出せないのである。
部長の中村はベンチ入りしても、なるべく馬居監督とコーチや選手には口出しをせず、裏方に徹しようと思っていた。二人の方がサッカーに詳しいようだったからだ。それに、この二人に決めたのは草野校長だったし、教頭の支持も得ている。つまり、校長と教頭のお墨付きだ。自分は部長として、サッカー部を創設することに全力を注ぎ、実務は二人に任せればいい。そういう思いでやって来た。そして、こうして試合ができるようにまで漕ぎ着けた。
竜巻高校にはサッカー部がないという七不思議の一つも、消し去ることに成功した。
後は大将と女将に任せよう。わずか三か月だけ指導くれる予定のようだが、今日、強豪の雷電高校に勝てば、その気持ちも変わって来るかもしれない。
中村部長はベンチに腰掛け、黙って戦況を見守っていた。
しかし、チームがピンチになると、そうも言っていられない。思わず立ち上がり、監督とコーチを押しのけて、最前線で選手に指示を出し始めた。
「そんなところで休むなー! もっと走れー! 走って、走って、走りまくれー! サッカーは走ってナンボだ! 動けなくなったときは死ぬときだぞー!」
「そんな大げさな~」選手たちはバテバテである。「僕たちはマグロかよ~」
「何を弱気なことを言ってるんだ! 九十分間、休みなく走るんだー! おい、チャーリー! お前はキーパーなんだから、みんなと一緒になって、ゴールの前を右に左へと、ウロウロ走るんじゃない! お前は唯一、動かないでドンと構えるポジションだ! こらっ、だからといって、そんな所でウンコ座りをするんじゃない! 日本に来て覚えたからといって、ここでお披露目しなくてもいい。スタンドアップだ。少なくとも、今は立っていてくれ!」
馬居監督とコーチは、中村部長が出しゃばって声援を送ることを快く思ってない。選手たちが、部長の声援を聞いて発奮し、間違って勝ってしまったら、困るからだ。次々と試合に負けて、三か月後に、二人揃ってクビになるという計画がダメになってしまう。
二人は苦虫を噛み潰したような顔をして、戦況を見つめていた。しかしその顔は点数がなかなか入らないことへの苛立ちだと、生徒からは見られていた。
そのうちに、雷電高校の強力フォワード選手がミッドフィルダーの学食バイト・宮井と松寿司・中島をあっと言う間に抜き去り、ディフェンスの生き物係の犬井と鳥谷のコンビをかわし、俊足を飛ばして駆けつけたフォワードの遠藤もかわし、ゴールキーパーのチャーリーと一対一になってしまった。
教頭の顔色が変わった。
「校長、大ピンチですよ。三点目を取られたら、サッカーでは逆転が難しいですよ」
「チャーリー君はサッカーをやっていたのかね?」
「イギリスではクリケットをやっていたそうです」
「馬に乗って、棒を振り回すやつかね?」
「それは貴族のスポーツのポロです」
「サッカー経験がないなら、マズいなあ」
チャーリーはゴールの中央に立ち、大きく両手を広げた。
「カモーン! 今こそ、ヤンキーの根性を見せてやる!」
誰もが三点目を覚悟した。勝敗は決まったと思った。
しかし、雷電高校のエースストライカーがシュートを放とうとしたとき、白くて丸い物体が猛スピードで走って来て、ボールとぶつかった。
ボールはコロコロ転がって行く。エースストライカーは空振りをして、スッテンコロリンと転んでしまった。競技場に笑い声が響く。
――ウソだろ。何だ、今のは?
ストライカーが白い物体を目で追ってみると犬だった。
「ポチ!」生き物係の犬井が駆け寄る。「よくやった!」
みんなに見えないように、頭をナデナデしてあげる。生き物係が学校犬ポチを散歩がてら、ここまで連れて来て、グランドの隅に繋いでいたのだが、いつの間にか抜け出して、大好きなサッカーボールを見つけ、突進して来たようだ。
「逃げ出したらダメだろ、ポチ!」
敵が見ている前では叱るフリをしておくが、目は笑っている。校庭でサッカーボールを使って遊ばせておいたことが、こんなときに役に立つなんて。
ポチの名付け親である中村部長を見てみると、ベンチ前で大喜びになって、はしゃぎ回り、監督とコーチ夫婦に後ろから羽交い絞めにされていた。こんなシーンを雷電高校に見られてはいけない。ポチが我々の回し者だとバレてしまうし、犬に助けられた情けないチームだと思われてしまう。
「中村先生、落ち着いて、落ち着いて」ねじり鉢巻きの馬居監督が止める。
「こんなときに落ち着いてられますか! 私が学校犬として引き取ったポチが一矢報いてくれたのですよ! 大将! 試合が終わったら、ポチへのご褒美として、マグロのトロの炙りを用意してくれませんか!」
「はいはい、分かりました。大トロでも中トロでも小トロでも、心を込めて炙りますから、とりあえず、ベンチに座っていてください」
雷電高校の監督が審判に抗議をしたが、犬はグランドに転がっている石と同じく不可抗力だとして、そのままスルーされた。
ゴール前に転がっていたボールを、チャーリーが思い切り蹴っ飛ばし、
「ゴーゴー! 行け行けー!」フォワードをはやし立てる。
「どうだ、みんな見たかー! これがヤンキーの根性だぜー! 雷電高校がナンボのもんじゃーい! おーっ!」
チャーリーはゴール前で、片手を天に向かって突き上げるが、ボールには指一本触れなかった。
ポチに助けられたことは忘れている。
すでに二点取られていることも忘れていた。
「校長、教頭、お待たせいたしました」
二人が振り返ると、定年間近の美術の野呂先生が立っていた。
いつものグレーのスーツである。
「野呂先生、来てくださいましたか!」教頭がうれしそうに出迎える。
「吹奏楽部が不在ということで、音楽のテープを流そうと、家からこれを持参いたしました」
かなり古い型のカセットテープレコーダーを掲げる。
「おお、それはいい。さっそく大音響で流してくれたまえ」校長もうれしそうだ。
しかし、野呂は先ほどから続いている雅楽部とハープ部の演奏に目をやる。
「彼らを気にすることはない」校長が言う。「彼らには彼らの独自の世界がある。先生は少し離れた場所で流してくれればいい」
「承知いたしました」
「派手なのを頼むよ」
野呂は演奏中の音楽系クラブの隣に移動し、ショルダーバッグからたくさんのカセットテープをガラガラと取り出した。野呂の個人的な昭和コレクションの一部である。
やがて、カセットテレコのスイッチが押され、大音響で曲が流れ出した。さっそく校長が耳を傾ける。
「教頭、これは何の曲かね?」
「美空ひばりの“愛燦燦”ですな」
観客席に座った野呂は目をつぶって曲に聞き入っている。
そして、曲が変わった。
「教頭、これは何の曲かね?」
「都はるみの“アンコ椿は恋の花”ですな」
野呂は体を左右にスイングしながら聞いている。
「教頭、やっぱりおかしくないかね?」
校長が疑問を呈するが、続いて流れて来た曲は、
「舟木一夫の“高校三年生”ですな」
「うーん、ちょっと近づいて来たか。だが、この場に合わんと思うのだがな」校長が野呂に叫ぶ。「野呂先生、ここはサッカー場ですよ! 昭和の歌謡ショーをやる場ではありませんよ! もう少し違う曲はないかね」
野呂はカセットテープの山を崩して、一本のテープを取り出した。
「では校長、これはどうでしょうか?」
元気が出そうなイントロが流れて来た。
「教頭、これはいいね。何の曲かね?」
「青い三角定規の“太陽がくれた季節”ですな。“飛び出せ!青春”の主題歌ですよ」
「いいじゃないか。これで行こう。選手諸君もやる気が出るだろう。――野呂先生、これでOKだ! こういう“青春もの”をどんどん流してくれ! 演歌は後で野呂先生が家に帰って、風呂の中で聞けばいい」
「校長。大変です!」教頭が叫んだ。
「どうした?」
「うちが一点入れて、二対一になってます」
「なんでだ!? ――おい、そこの君」校長はひちりきを吹いている男子に声をかける。「うちの一点はどうやって入ったのかね?」
ひちりき君は演奏を止めて説明する。
「パスを受けた遠藤君が、疾風のごとく走り出し、敵を置き去りにして、三十メートルくらい独走してから、見事にゴールを決めました」
「すごいじゃないか、遠藤豆君!」
ひちりき君は、なぜ校長先生がそんな貴重なシーンを見てなかったのか不思議に思いながらも、チームの勝利を願って、ひちりきの演奏を再開した。
プゥ~。プゥ~。プゥ~。
神輿の上に座っている理事長から、選手に檄が飛ぶ。
「雷電高校の君たち! 一点返されてどうする! あんな遠藤豆に、グランドを縦横無尽に走り回られるんじゃない! 手を抜いてもかまわんが、手を抜きすぎてもイカンぞ!」
理事長は興奮して神輿の上で立ち上がる。校長があわてて駆け寄る。
「理事長、気をつけてください! ここは落ち着いて!」
「落ち着いていられるか! あの寄せ集め集団に一点を入れられたんだぞ! こんな屈辱があるか!」
「まだ勝ってますし、一点くらい、すぐに取り返してくれますよ」
理事長はしぶしぶ座り込む。
「校長、教頭、ただ今、到着いたしました」
「おお、岡戸さん、遅かったじゃないですか」教頭がうれしそうに迎える。
「これを持って来ました」
用務員岡戸の脇に巨大な旗が寝かせてあった。
「敵の雷電高校にはたくさんの応援旗が揺れてますが、うちにはありません。ですので、作ってみました。アルミのポールは私が用意して、旗の部分は手芸部の部長の大久保田さんに頼みました。竜巻高校という校名から、竜巻をデザインに取り入れて、校章と組み合わせて、素晴らしい応援旗になってます」岡戸は自慢げに言う。
「ほう、これは大きい旗ですなあ」校長は感心する。「よく短期間で作ってくれましたなあ」
「私はサッカー部の用具係に任命されましたから、これくらいはやっておこうと思ってます。ですが、一つ問題がありまして、この旗は縦が五メートル、横は六メートルもあります。重すぎて、一人では上げられません。ここまでは引き摺って来ました。おそらく数人がかりでないと、立てられないと思います。そこまで考えてなかったのは、私の不徳と致すところです」
「この通り、うちの応援席には人がおらんから、私たちが手伝いましょう」
「いや、校長と教頭にそんな力仕事をさせるわけにはいきません。私が何とか立てましょう。私が作った応援旗ですから、責任を持って立てますよ」
岡戸は、演奏している皆さんの邪魔にならないようにと、端の方へ巨大な旗をズルズルと引き摺って行った。
「草野校長!」
呼ばれた校長が振り向いた。
一人の老人が立っていた。
「これは、騒音ジジイではなく、あのときの……。その節は失礼いたしました」
いつぞや、生徒の声がうるさいと文句を言いに来たじいさんじゃないか。
校長は老人の名前を忘れたので、ごまかして、挨拶だけする。教頭もあわてて頭を下げる。
ここまでしつこく因縁を付けに来たのかと不安になるが、
「新設されたサッカー部の初の対外試合が雷電高校であると聞きましてな。ここまでやって来たのですよ」
どうやら、騒音のクレームではなさそうだ。
「なぜ、そんな詳しいことをご存じなのですか?」
「わしの家まで校内放送が聞こえてくる」
やはり、クレームか?
「これは申し訳ないです。ボリュームは下げているのですが」校長はすかさず謝罪する。隣で教頭も頭を下げる。
「いや、かまわんよ」老人はあの時とは違って、柔和な表情をしている。
つまり、クレームではなく、この試合が気になって、やって来たということらしい。
やはり、いつも安酒を飲んでいる人に大吟醸菊理媛の付け届けは大きい。なんといっても五万円も注ぎ込んだのだ。花桐理事長からせしめた裏金だが。
そして、その後も老人は酒を要求してくるようなことはしなかった。教頭の聞き込みによると、じいさんは元教師らしい。元チンピラでなくてよかった。
じいさんは辺りを見渡して言う。
「雷電高校の応援に比べたら、竜巻高校の応援は規模が小さくて、しょぼいのう。ひとつ、わしが応援を買って出てやろう」
「それは、どういったことで?」教頭が尋ねる。
「これだよ」
騒音じいさんは茶色いジャケットのポケットから楽器を取り出した。
「ラッパですか!?」
「騎兵隊が吹くあれだ」
「あれと言いますと?」教頭には分からない。
「あんた、ジョン・ウェインの駅馬車を見とらんのか。あの映画の
中で、騎兵隊が吹いておっただろう。――あれだよ」
騒音じいさんは雅楽部とハープ部の間に立って、突撃ラッパを吹き始めた。
パッパラ、パッパ、パーッ!
学食バイト・宮井と松寿司・中島とラッパー安藤は、三人がかりで敵に襲いかかり、ボールを奪い取った。一対一では勝てないから、複数で向かって行くようにと、馬居監督から指示が出ていたのだ。その指示は監督とコーチと部長の三人が無い知恵を振り絞って考えたものだったのだが、生徒たちは何も知らない。うまく奪えたので、さすが馬居監督だと思っている。
そのボールを三人の間で大切に回している。点数は二対一で負けているが、一点差なら追い付いて逆転もできる。あの雷電高校に勝てるかもしれないのだ。
「あーあ、お腹が減ったなあ」宮井が敵陣に向けて、ボールを運びながら言う。
「今日みたいに学食のバイトが休みの時、昼飯はどうしてるんだ?」安藤が訊く。
「昼飯は抜きだよ」
「マジかよ」安藤はボールを受けながら言う。
この試合が終われば、中村先生から三千円もらえることは黙っておく。
「倒れるなよ、宮井」安藤からボールを受けた中島が心配してくれる。
「慣れてるから大丈夫だよ。それよりも、雷電に比べて、うちの応援はセコイなあ」
「今日は吹奏楽部が来てないからな」中島がボールをキープしたまま言う。
「それにしても、雅楽部とハープ部と野呂先生のカセット応援だよ。わびさびを感じるよ」
「さっきから、用務員の岡戸さんが応援旗を立てようとしてるんだけど、重くてあげられないみたいなんだ」中島から再びボールを受けた安藤が言う。
「あんなにデカいと、上がらないだろうよ」宮井が近づいて来て言う。
パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。
「何だ、この音は!?」ピッチに立つ、全選手が驚いた。
騒音じいさんが突撃ラッパを大音響で吹き始めたのだ。
そして、大声で叫ぶ。
「竜巻高校の諸君! がんばるのじゃ~。がんばるのじゃ~。がんばるのじゃ~」
パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。
パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。パッパラ、パッパパー。
草野校長は思った。騒音じいさん自身が騒音だ。
先ほど、応援席に英語の酒井先生がやって来た。そして、東北地方の三つの祭――盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、青森ねぶた祭りの踊りを、一人で次々と踊って、選手を激励している。周りにいる生徒たちはプレイする選手たちよりも、踊る酒井を見ながら、カメラを向けている。応援よりもこっちの方が大切だ。
東北地方から出て来たばかりで、野暮ったかった酒井だったが、最近は訛りも消えて、すっかり、あか抜けたと評判であった。元々、東北美人だったのだが、その美しさがさらに際立って来たと生徒たちはウワサをしていた。
その原因は、ラッパー志願の安藤を二度に渡って秒殺したことで自信を付けたところにある。安藤の足の骨のヒビの本数が、酒井先生の元気の源となっていたのだが、生徒たちはそこまで深く酒井の気持ちを読んではいない。
この東北地方の三つの祭の踊りは、ラッパー安藤が教室で踊っていたものである。あまりにもヘタクソで目も当てられなかったため、それを、本来のキレのある躍りで完全再現しているのである。できれば、ヘタクソだった安藤に見せてやりたいものだと思っていたところ、ちょうど目の前に安藤がボールを追って、やって来た。
「おい、安藤!」踊りを中断して、観客席から声をかける。
「あっ、これは酒井先生! なんと素晴らしい踊りでございましょう。僕の踊りとは月とスッポンくらい違います。きっと先生は将来立派なラッパーになれます。僕もうかうかと……」
「黙れ! うちは一点負けてるだろ。私の踊りなんか見てないで、さっさと点を取って来い!」
「はい、すいません!」
「すぐに走れ!」
「はっ、ただ今!」
ラッパー安藤は骨に四本のヒビが入った足で駆け出した。
「校長、あの方たちは!?」
黒と白の修道服を着たシスターが静々と観客席に入って来る。その人数は二十名。先頭を優雅に歩くのは教会のシスター、マリー・アマーチェである。
「校長先生、教頭先生。シスター全員で応援にやって参りました」
目の前に二十名のシスターが集結した。
「これはわざわざ申し訳ないです」
校長も教頭もあわてて立ち上がり、胸の前で十字を切る。
「楽器は持参しておりませんので、私たちは賛美歌で応援したいと思います」マリー・アマーチェが鈴を転がすような声で言う。
「はい、よろしくお願いいたします。アーメン」校長がお願いをする。
「一点ビハインドで負けてます。逆転できますように。アーメン」教頭もお願いする。
シスターたちは、カセットテレコで音楽を流している野呂先生の隣に整列した。
美しく、清々しい女性たちの集団を目の当たりにして、野呂先生の口はポカンと開いたままだ。できれば、彼女たちと写真を撮りたいものだと考えている。
「野呂先生! 曲が止まってますよ」校長から声が飛ぶ。
「ああ、すいません。すぐにカセットテープを入れ替えます。アーメン」
二十名のシスターによる賛美歌の合唱が始まった。
一曲目は“アメイジング・グレイス”だ。世界中で最も愛され、歌われている曲の一つである。美しく清らかな声が場内に響き始めた。
両校の応援団が静かになり、選手たちもプレーを忘れて、歌に聴き入る。ヤジを飛ばしていた花桐理事長さえも静かになる。竜巻高校の選手たちは、我を忘れて大喜びだ。
「見ろよ、僕たちの応援席にシスターが来てくれてるぞ!」
「マリー・アマーチェさんだ! 他にもキレイどころがいっぱいいる!」
「すげえ、リアル“天使にラブ・ソングを”だ」
次に歌われたのは“主よ 御許に近づかん”であった。またもや、澄み切った声がグランドまで流れてくる。今まで、雷電には勝てそうにないと思い込んでいた竜巻高校の選手だったが、これらの歌を聴くことにより、彼らのモチベーションは爆上げした。
「勝てるぞ、僕たち! アーメン」
「逆転するぞ、僕たち! アーメン」
歌の力は素晴らしい。人々に大きな力を与える。やる気を与える。希望を与える。
たとえ、“主よ 御許に近づかん”が、タイタニック号沈没のときに演奏されていた曲だとしても。
なぜ、この曲がチョイスされたのか分からないが、幸いなことに、この曲を知っている生徒はいないようだった。
「いやあ、校長先生、教頭先生。お待たせしました」
二人は同時に振り向いた。今日はよく後ろから呼ばれる。
「これは諏訪一大寺の星輝和尚じゃないですか!」
「サッカー部の試合があると聞きましたので、修行仲間を引き連れて、応援にやって来ましたぞ」
二十名の袈裟を着たお坊さんがずらっと並んでいた。
「これはわざわざ申し訳ないです」
校長も教頭もあわてて立ち上がり、胸の前で手を合わせる。
今日は胸の前で十字を切ったり、手を合わせたり、忙しい。
「よろしくお願いいたします。ナンマイダ」校長がお願いをする。
「一点ビハインドで負けてます。逆転できますように。ナンマイダ」教頭もお願いする。
アーメンと言ったり、ナンマイダと言ったり、忙しい。
二十名のお坊さんが、二十名のシスターの隣に並んだ。
ポク、ポク、ポク、ポク。
お坊さんが一人に一つずつ携帯している木魚が鳴らされた。
「まか はんにゃー、はーらー、みったー、しんぎょうー」
般若心経が朗々とグランドに響き渡る。またもや両校の応援団が静かになり、選手たちもプレーを忘れて、お経に聴き入る。またもやヤジを飛ばしていた花桐理事長も静かになる。ここでヤジでも飛ばしたら、仏様のバチが当たるんじゃないかと、一抹の不安を抱いたからだ。
「見ろよ、僕たちの応援にお坊さんが来てくれているぞ!」
「すげえ! 地味なお坊さんがいっぱいいる!」
竜巻高校の選手は少し喜んでいる。彼らのモチベーションはさらに少しだけ上がった。
「教頭先生、神と仏の応援があれば、鬼に金棒だな」校長はうれしそうだ。
「神なのか、仏なのか、鬼なのか、よく分かりませんな」
「それにしても、雷電高校のように、吹奏楽部が演奏して、チアガールが踊るのが普通の応援というものではないかね。うちの学校と来たら、ひちりきに、笙(しょう)に、琵琶に、三本の尺八に、ハープに、突撃ラッパに、賛美歌に、般若心経だ。和と洋とこの世とあの世の総動員だぞ。――こんな応援はおかしくないかね。それとも、ワシの方がおかしいのかね?」
賑やかになった応援席の中で、校長の頭の中は混乱する。
スコット山田はチャーリーがいないため、いつもより一台少ない、六台のバイクで街を疾走していた。
あれほど止めたのに、チャーリーはサッカー部に入ってしまった。新任の中村先生に、部員が集まらなくて困っているから助けてくれと口説かれて、人のいいチャーリーは騎士道精神を発揮したのかもしれない。といっても試合があるときだけの、助っ人外国人選手だという。
そして、今日が初の対外試合で、敵はライバル校の雷電高校らしい。
「俺たちには関係はない。いつものように、バイクをぶっ飛ばすだけだ」
今日も、法定速度を守ってノロノロと走ってる車を蹴散らし、追い抜いて来た車を六台で取り囲んで、罵声を浴びせて、さんざん脅した上で、一気に抜き返した。
――そして、赤信号で全台止まった。
信号待ちをしている間、スコット山田はふと横を見た。昔ながらの小さな電気屋があった。
近くに大型家電量販店があるのに、こんな場所でがんばってるのか。すげえな、街の電気屋さん。
小さなショーウィンドーにテレビが置かれて、ちょうど竜巻高校と雷電高校のサッカーの試合を放映していた。テレビ画面が通りに向けてあり、通行人が群がっている。――昭和でよく見かける風景だった。
たかが練習試合だぞ。なぜテレビでやってるんだ?
花桐理事長が裏で動いていることをスコット山田は知らない。
そこへ黄色いジャージ姿の学生四人が通りかかった。雷電高校の学生たちだ。
「おい、見てみなよ。うちの高校のサッカーやってるぞ。二対一で勝ってるじゃん」
「当たり前だろ。竜巻高校みたいなアホ学校に負けるかよ。あいつら新設サッカー部だぞ」
「だったら、一点はご祝儀だろ。本気でやったらゼロに抑えて完勝だな」
「見ろよ、キーパーは金髪の外国人だ。助っ人外国人かよ」
そのとき、雷電高校からシュートが放たれた。チャーリーは横っ飛びになって、それを防いだ。手の先に触れたボールは、ゴール前をコロコロ転がる。そのボールに向かって、チャーリーはさらに飛んで、体を使って押さえ込んだ。雷電高校のフォワードは勢い余ったフリをして、チャーリーにボコボコと蹴りを入れる。
「いいぞ! やれー!」テレビを囲んだ四人が歓声をあげる。「金髪をぶっ殺せー!」
審判が駆け寄り、チャーリーはふらつきながら、立ち上がった。イエローカードは出ない。
「イエローカードなんか出るかよ。ホームゲームだぞ」四人は笑う。
「助っ人外国人も大したことなかったな。デカいだけの見かけ倒しだ」
「竜巻高校が勝てるわけない。勝つにはあと二点入れなきゃならないんだぞ」
「無理だな。アホ学校だからな」
四人の会話はバイク音よりも大きく、竜巻高校の六人に丸聞こえだ。
スコット山田の表情が見る見る変わっていく。
「あれ見てみなよ。応援旗が上がらないんだ」
テレビには巨大な応援旗を一人で上げようと奮闘している岡戸の姿が映し出された。映ってることも知らずに、歯を食いしばっている。
「あのオッサン、何をやってるんだ。そんなデカい旗が上がるわけないだろ」
四人はテレビ画面を指差して、爆笑する。
「うちの理事長が言ってたわ。あいつらが雷電高校に勝つには三十年早いってな」
「行こうや。結果は見えてる。うち大差で楽勝だ。こんな汚い電気屋の軒下で見てるだけ時間の無駄だ」
四人は笑いながら行ってしまった。
信号が青になった。憤怒の形相をしたスコット山田が振り向いて、五人の仲間に言った。
「今から雷電高校に行くぞ!」
六台のバイクは一気にUターンした。先頭のスコット山田は歩道に乗り上げ、さっきの四人組に後ろから順に蹴りを入れていく。
ボコッ、ボコッ、ボコッ、ボコッ。
うずくまる四人をバックミラーで確認して、車道に戻ると、猛スピードで走り出した。
背中を足で蹴られた四人は息が詰まり、何が起きたのか分からないまま、歩道に座り込んでいた。
競技場では、野呂先生が流すカセットテレコから、ドラマ“われら青春!”の主題歌“帰らざる日のために”が聞こえて来た。透き通るような三人の女性のハーモニーが競技場に流れる。
真っ先に反応したのはベンチ前に立っている馬居監督だった。
「おお、この曲は!?」
いや、懐かしいなあ。あの頃、青春ドラマを必死に見ていたものなあ。思い出すだけで涙が出そうになるなあ。女将にも教えてやらないとなあ。
女将を見ると、ベンチの端に座っている。日焼けが気になるらしい。ベンチの屋根は透明なので、そんなところに座っていても陽が射すから、あまり変わらないと思うのだが。
「おい、今流れてる応援曲を聞いてみな。“帰らざる日のために”だぞ」
女将も同年代である。青春ドラマに涙した世代である。
曲を聴くために、女将はいやいやベンチから出て来て、しばらく耳をすます。
「えっ!? これを歌ってるのは“いずみたくシンガーズ”じゃないの?」
「これは“キャンディーズ”だよ」
「へえ、“キャンディーズ”がカバーしてるんだ。それは知らなかったわ」
曲はサビの部分に差しかかる。
「おお、ここだ。このサビを歌ってるのは我らがキャンディーズのスーちゃんだ!」
「この高音部はすごいねえ。心に染み渡るねえ。さすがスーちゃんだねえ」
気だるそうにしていた女将は、スーちゃんの歌声を聞いて元気になる。
馬居監督は、すぐ目の前を走っていたラッパー安藤を捕まえた。
「安藤君、みんなに伝言を頼むよ。スーちゃんも応援していると」
「スーちゃんですか?」
「そうだ、スーちゃんだ。頼んだよ!」
ラッパー安藤は、そばに走って来た学食バイトの宮井に声をかける。
「監督からの伝言だ。スーちゃんも応援している」
「――誰、その人?」
「いや、分からんが、みんなに伝言しろということだ」
宮井は駆け出し、前方を走っていた松寿司・中島に追い付く。
「監督からの伝言だ。スーちゃんも応援している」
「誰だって? どこの国の人?」
「それが分からないんだ」
「金森に訊いてみよう。あいつ韓流スターに詳しいから」
中島はいったん下がって、ディフェンスの生徒会副会長の金森の元に行く。
「監督からの伝言だ。スーちゃんという韓流スターが応援してくれている」
「韓流スターにスーちゃんなんていないよ。名前からして、中国の女優さんじゃない?」
「そうか。とにかく、みんなにこの伝言を回してくれということだ」
「分かった」金森は生徒会長の平井に近づく。
「金森! 監督からの伝言だ。スーちゃんという中国の女優さんが僕たちを応援してくれている」
「なんで?」
「それが分からない。でも、全員に伝えろということなので、生き物係の二人とチャーリーにも伝言を頼むよ」
「よく分からないが、分かった。伝えに走るよ」
ミッドフィルダーの松寿司・中島は、フォワードのラグビー部の玉本の元に駆け寄る。
「監督からの伝言だ。スーちゃんという中国の国際女優が僕たちを応援してくれている」
「意味がわからないけど」
「まあ、とにかく、足立君にも伝言を頼むよ」
玉本は同じラグビー部の足立のところに走る。
「監督からの伝言だ。スーちゃんというハリウッド映画にも出演経験がある中国の国際女優が僕たちを応援してくれているらしい」
「どういうこと?」
「よく分からないのだが、遠藤君にも伝えてくれ」
足立がやっとの思いで、俊足の遠藤に追い付く。
「遠藤君、監督からの伝言だ。スーちゃんというハリウッド映画にも出演経験があるアカデミー賞主演女優賞最有力候補の中国の国際女優が僕たちを応援してくれている」
「なんで中国の方が僕たちを?」
「たぶん、あれだ」玉本がバックバックスタンドを指差す。テレビカメラが見える。「あのカメラだ。衛星放送を使って、この試合を中国全土で放映してるんだ」
「十四億人の中国人が僕たちの試合を見ていて、その中のスーちゃんというものすごくキレイな国際女優さんが、応援してくれているということ?」
「そういうことじゃないかなあ」
「十四億の中国国民と、そんな美人に応援されたら、僕たち、がんばるしかないね!」
スーちゃんのお陰で、さらに彼らのモチベーションは上がった。
「ありがとう、スーちゃん!」
馬居監督は晴れ上がった空を見上げて、手を合わせた。
岡戸は必死になって、横倒しになっている巨大な応援旗を立てようと頑張っている。
なにしろ、これを作ったのは自分だ。自分のことは自分でしなくてはいけない。子供の頃からそう言われていた。しかし……。
「ああ、ダメか。設計ミスだ。ビクともせんわ。手は痛いし、腰も痛いし、足もダルいし、疲れで目は霞んでくるし。――もう体に力が入らん」
岡戸は恨めしそうに旗を見下ろす。いくらなんでも大きすぎるよなあ。新入生だから頑張ってみましたと言われても、手芸部の大久保田さん、張り切り過ぎなんだよなあ。まさか、こんな大きな旗が出来上がってくるとは思わなかったものなあ。寸法を指定しておけばよかったなあ。
「まあ、仕方がないか。さっきは断ってしまったけど、校長と教頭に助けを求めに行くか」二人の元へ行こうとすると、
「岡戸さん、そんな根性無しじゃ、女にモテませんよ」
岡戸が振り返った。
男子生徒が立っていた。
「スコット山田君!」
「俺に任せてください」
「いや、いくら力持ちのスコット山田君でも、これは持ち上がらんぞ」
「俺一人じゃ無理です。だが仲間で力を合わせれば、できないことはないですよ」
後ろから五人の仲間がやって来た。全員で六人になった。
「みんな、竜巻高校ヤンキー部の根性を全国に見せてやろうや!」
「おう!」井川がデカい声で答えてくれる。
「チャーリー、見ておけよ。これがヤンキーの心意気だぜ。さっきお前のことを、見かけ倒しだと言ってバカにした雷電の四人組を見返してやるからな!」
「よしっ、やるぜー!」六人の声が応援席に響いた。
岡戸はあっけに取られて、ゴツい六人を見上げた。
すでに試合は後半戦に入っている。しかし、あと一点が遠かった。雷電高校はこのまま余裕で逃げ切ろうと、適当に走っているだけだ。竜巻高校の寄せ集めサッカー部のために全力を尽くすなんて、力の無駄だと思い始めているからだ。
こんな奴らには勝って当たり前。練習にさえならないし、勝ったところで、誰にも褒められない。
雷電高校の選手全員がそう思いながら、プレーを続けている。
「みんな、あれを見ろ!」キーパーのチャーリーが大声を上げて、応援席を指差した。
竜巻高校の応援旗が今、立ち上がろうとしている。
「ウソだろ」雷電の選手も驚いて、足を止める。
「起き上がっていくぞ」他の選手も釣られて立ち止まる。
「あんなものが上がるのか」花桐理事長も驚いて、神輿の上に立ちあがった。
双方の応援団も手を止めて、固唾を飲んで見守る。審判さえも立ち止まり、競技場全体が静まり返る。
やがて、応援旗がスコット山田たちヤンキー部六人の手によって立てられた。
倒れないように六人が十二本の腕で支える。
そこへ、ゆったりとした風が吹いて来た。大きな旗が大きく揺れる。
「見えてるか、チャーリー! これが俺たち竜巻高校の旗だぞー!」
スコット山田がアルミのポールにしがみついたまま叫ぶ。
旗の真ん中には、竜をモチーフにした校章が描かれ、天に舞い上がる竜巻がデザインされている。手芸部の大久保田さんによる渾身の力作であった。
「僕たちの旗が立ったー!」「立ったぞー!」
竜巻高校サッカー部に歓喜の渦が巻き起こった。チャーリーは、巨大な応援旗が再び倒れないように、懸命に押さえるヤンキー仲間に向けて、こぶしを突き上げた。
「みんなー、しっかり見えてるぜー!」
ピー、ピー、ピー。
旗の周りに集まった男たちが笛を吹き始めた。
「教頭、あの人たちは何だね?」草野校長が不思議がる。
「どう見ても警官ですな」教頭も分からない。
旗の周りで十人の警官が笛を吹いて応援している。
「岡戸さんがうれしそうに話し掛けてるので、知り合いじゃないですかねえ」
深夜、二宮金次郎像を捕まえようとしている岡戸を不審者と間違えたときの警官が、小笠原警部補を筆頭にして、応援に来てくれているのだが、校長も教頭もその経緯を知らない。
ピー、ピー、ピー。
「あんなにたくさんの警官がなぜ競技場に来れるのかね?」
「非番じゃないですかね」
「一度に十人もの警官が非番になって、警察署はちゃんと機能するのかね」
「今日は小倉優子が一日署長を務める日ですよ」
「なるほど。ゆうこりんなら安心だな」
ピー、ピー、ピー。
笛を吹く十人の警官たち。中には警棒を振り回して、声援を送っている者もいる。
「教頭、やっぱりうちの応援は変じゃないかね?」
「いえ、何ら常識は外れてないと認識しておりますが」
一方の雷電高校は竜巻高校の旗が立ち上がったことに驚いていたが、
「あんな旗に構うな。自分たちのサッカーをやろう!」
「そうだよ。サッカーを楽しもう!」
気合を入れ直したが、どこからか数匹の虫が飛んで来て、選手の邪魔を始めた。目の前をビュンビュンと通り過ぎる。
「なんだ、こいつらは。あっちへ行け!」みんなは必死で追い払う。
この虫こそは、犬井が登山研修の時、用務員の岡戸さんに虫かご込みで、八百円で買わされたトンボとカナブンと蝶の昆虫三点セットであった。結局、あの日は昆虫セットを三つも買わされたのである。合計二千四百円である。
用務員さんが生徒相手に商売をするか?
お金への執着心さえなければ、いい人なんけどなあ。
しかし、生き物係としては、昆虫も大切に扱わなくてはいけない。
今日は天気も良かったので、ここまで連れて来て、虫かごから解放してあげることにした。すると、虫たちは長い間閉じ込められていた腹いせなのか、雷電の選手に襲いかかったのである。
見事に屹立した旗に見とれて止んでいた竜巻高校の応援の演奏が再開した。雅楽部、ハープ部、カセットテープ、突撃ラッパ、賛美歌、般若心経……。和洋折衷、バラバラの応援が奇跡的に一体化して、選手を鼓舞する。
「あれを見ろ!」またチャーリーが叫ぶ。「電光掲示板を見ろ!」
竜巻高校の選手が振り向いて、電光掲示板を見ると、二対二になっていた。
「あれ、僕たち、追い付いてる」平井生徒会長が呆然とする。
「なんでだ?」金森副会長も分からない。
「みんな、ゴール前を見ろよ!」松寿司・中島が指差す。
ゴール前では小さな遠藤がフライパンの上で豆が弾けるようにピョンピョンと跳ねていた。応援旗に見取れ、さらに九匹の昆虫の攻撃で敵がアタフタしている隙を突いたのである。
「飛び級の遠藤豆君だ! このドサクサに紛れて、シュートを決めてくれたんだ!」
「同点になったぞ! あの雷電相手に二点差を追い付いたぞ!」
「勝てる! マジで僕たち勝てるんじゃない」
「応援席のみなさん、ありがとー!」
「シスター、お坊さん、ありがとー!」
「中国の国際女優スーちゃん、ありがとー!」
「学校犬ポチ、ありがとー!」
「ヤンキー、ありがとー」
「応援旗をありがとー!」
「お巡りさん、ありがとー!」
「虫たち、ありがとー!」
竜巻高校イレブンは歓喜の声を上げた。
応援席では生徒たちが音楽に合わせて声を張り上げ、肩を組んで体を揺すり、一丸となって応援している。先日、小久保“マドンナ”先生が体育館で仕掛けた暗闇パーティのお陰で、男子生徒と女子生徒はすっかり仲良くなっていたのである。
だが、隙を見て、点を取ろうとしたのは、雷電高校も同じだった。同点になり、気が緩んでいた竜巻高校の選手を蹴散らし、またもや、エースストライカーが簡単にゴール前まで、ボールを持ち込んでしまった。
今度はチャーリーも油断していた。一瞬にして顔面が蒼白になった。あわてて身構えるが、敵はすでにシュートを放つ体勢になっている。
ダメだ。今度は間に合わない。三点目が入る。もうポチは来てくれない。――誰もがそう思った。
そのとき、黒くて大きな物体が猛スピードで走って来て、ボールを蹴飛ばした。ボールはコロコロ転がって行く。
エースストライカーは空振りをして、またもや、スッテンコロリンと転んでしまった。競技場にまたしても、笑い声が響いた。
ウソだろ。何だ、今のは? また犬か? 黒い犬か?
エースストライカーが周りを見渡すが、犬一匹いない。チャーリーもあたりをキョロキョロ見渡している。
審判も呆然としている。今度は何が起きたか誰にも分からない。
いや、たった一人だけ、その正体を見破った人物がいた。用務員の岡戸だった。岡戸は応援旗のそばに立っていた。そして、確かに見た。
二宮金次郎が猛スピードで走って行って、ボールを蹴飛ばしたところを。
「二宮君、来てくれたのか。昼間に化けて出て来てくれて、ありがとう!」
二宮金次郎像を撤去せず、残すことになったことへのお礼だと思った。岡戸は竜巻高校の二宮金次郎像の方角に向けて、頭を下げた。そして、思った。江戸時代にサッカーがあったのだろうか? 草履でボールを蹴飛ばして、痛くなかったのだろうか? ボールを蹴飛ばすときくらい、薪を下しておいた方がいいのではないか?
グランドには魔物が住んでいると言われる。何も知らない両校の生徒たちは、きっとこれは魔物のしわざだと思った。
魔物呼ばわりされているとも知らず、二宮金次郎像は竜巻高校に戻るため、薪をかついだまま、懸命に商店街の中を駆け抜けていた。
その顔には笑みが浮かんでいたことを誰も知らない。
この頃から、竜巻高校の応援席には続々と生徒たちが集まり出した。テレビに映って、スターになれるという校長のメッセージ付きの学校メールを読んで、駆け付けた生徒が多数いたからだ。
そして、竜巻高校のベンチを見て、ウマイ寿司の大将と女将が指揮を執っていることに生徒たちは目玉をひんむいて驚いた。
「監督はクリスティアーノ・ロナウドじゃないのかよ!」
「信じてたのは、お前だけだよ」
「マジかよ。せっかくサイン色紙を持って来たのによ」
「寿司屋のオヤジのサインをもらってどうするんだよ」
「普通は客の方からサインをして、店に飾るのものだろう。まったく、ふざけてるよな」
「お前、そんな顔をするなよ。あれ見てみな」
正面のバックバックスタンドからテレビカメラがこちらを狙っていた。
「ヤバいじゃん。映ってるじゃん。どうすればいいんだ?」
「こういう時は、スマイルに決まってるだろ。――みんな、テレビに映ってるぞー! 竜巻高校の生徒は、いつでもスマイルを忘れるなよー! とんでもないことが起きても忘れるなよー! すぐスマイルするべきだぞー! 俺たちは子供じゃないからなー!」
集まって来た生徒の中に、色付きの小さな四角いパネルを持った者たちが多数いた。男女混合の彼らは、木魚を叩いて、般若心経を唱えているお坊さん集団の隣に、次々と陣取った。
全校生徒が総動員され、その人数は八百人を越えていた。やがて、その席に大きく“がんばれ”の文字が現れた。そのパネルを頭の上に掲げて、文字を作っていたのだ。
「あれは昔、甲子園の高校野球大会でよく見られた人文字ではないか!」校長が驚く。
「PL学園の名物でしたなあ」教頭は懐かしがる。
続いて、人文字が作ったのは“ぜったい勝利”である。
「すごいな、教頭。勝利なんていう細かい文字を、よく人文字で作れるな」
「そうですなあ。あれは誰が主導しておるのでしょうかねえ。――あっ、君!」
このときになると、応援席にはたくさんの人が行き交っていた。教頭は目の前を歩いている一人に声をかけた。確か、三年生で学級委員長をやってる男子生徒だ。
「君、あの人文字はどこのクラブの生徒がやっているのかな?」
「所属しているクラブはバラバラですけど、漢字部の漢検一級を持ってる生徒が、みんなの指導をしているそうです」
「ほう、漢字部ですか。いや、ありがとう」
次に、人文字が作ったのは“七転八起”であった。
「今のうちのチームにピッタリの四字熟語だねえ」
校長は感心する。みんなもあまりの出来にどよめく。
次に、人文字が作ったのは“獅子奮迅”であった。
「校長、これもいいですなあ。うちにぴったりですなあ」
続いて、人文字が作ったのは“臥薪嘗胆”であった。
「しだいに難しくなってきたなあ」
続いて、人文字が作ったのは“駑馬十駕”であった。
「教頭、あれはどういう意味かね?」
「いや、分かりません」
さらに、人文字が作ったのは“珠聯璧合”であった。
「教頭、これは分からんね」
「私もさっぱり分かりません」
続けて、“虎嘯風生”“為虎傳翼”“鬱鬱勃勃”が作られた。
「ここまで来ると、意味どころか、読めもせんな」
「見たこともありませんな」
「さすが漢検一級だな」
「よくこんな複雑な文字が人文字で作れますなあ」
「うちの生徒がこんな優秀だったとはな。これで多少偏差値も上がるんじゃないかね」
ラッパー安藤が転んで起き上がれなくなった。酒井先生に飛び蹴りを喰らってできた足の骨のヒビが、走り回ったことで、四本から五本に増えていたのだ。
「すいません」
担架で運ばれて行く安藤は部長と監督とみんなに謝った。
「安藤、気にするな!」中村部長が熱く叫ぶ。「私たちは勝つぞ! あの雷電高校に勝つぞ! 安藤の代わりは、ほら、あそこにいらっしゃるから心配するな!」
ベンチの隅に座っていた社会人入学の大久保田が、手芸部の課題として膝の上で編んでいたセーターの編み物を横に置いて、ゆるりと立ち上がった。
ここで場内アナウンスが流れた。
「選手の交代をお知らせします。安藤君に代わりまして、大久保田君」
――17歳から66歳へ。
父親どころか、祖父への三代に渡る世代交代である。
応援席から大きな歓声と拍手が沸き起こる。大久保田は公開告白のときの六十六本のバラの花束で、すっかり人気者になっていたからだ。
「大久保田さん、頼みましたよ!」中村が声をかける。
「お任せください。まだまだ若い者には負けませんぞ。――痛ェ!」
馬居監督がお守りとしてベンチの隅に置いていた岡持ちに足をぶつけた。手にした物を落としそうになる。
「大久保田さん、それは置いていってください」また中村が声をかける。
「おお、忘れておったわい」
走り回るサッカーのために、大久保田は携帯用の酸素吸入器を持参していたのだ。用具係の岡戸が用意してくれたものだった。あやうく、手に持ったまま、ピッチに立つところだった。
酸素吸入器を編みかけのセーターの隣に置く。
「試合の途中で苦しくなったら、ここまで吸いに来るかのう」
雷電高校の選手が足を止め、ピッチに入って来る大久保田を見て驚いている。
頭は白髪で、腰が曲がっていて、動作が緩やかだからだ。
「おじいさんじゃん!」
「あの人のどこが高校生なんだよ」
「何年浪人して、留年すれば、ああなるんだよ」
「みんな、待てよ。お前ら、あの有名なドッキリを知らないのか。その道の達人がおじいさんに変装してプレーに加わるんだ」
「じゃあ、あれは特殊メイクでおじいさんになっているのか!?」
「日本の特殊メイク技術はすごいぞ。ノーベル賞ももらってるからな。あれはおじいさんじゃないぞ。最初はヨボヨボで、ヘタなフリをして、笑われるのだけど、途中でその能力を全開にして、逆に驚かせるというパターンだ」
「ということは、あのおじいさんは誰よ?」
「ヴィッセル神戸のイエニスタじゃね?」
「イエニスタは現役だろ。Jリーグと高校サッカーの掛け持ちはしないだろ」
「セルジオ越後さんじゃね?」
「セルジオ越後さんは七十歳を越えてるから、特殊メイクの必要はないだろ」
「ゴン中山じゃね?」
「そうだよ! 現役を引退してかなり経つけど、俺たちに中山雅史のシュートが止められるのか?」
「元日本代表だぞ」
「ハットトリックでギネス記録を持ってるぞ」
「やべえよ、マジで」
「俺たち負けるかもしれんよ」
「竜巻高校なんかに負けたら、理事長にぶっ殺されるぞ」
ビビってる雷電高校の選手が再び動き出す。
ちょうど、ボールが大久保田の方へ転がって行った。
大久保田は見事に空振りをして転んだ。
「ほら、見てみろよ。最初はわざとヘタなフリをしてるだろ」
学食バイト・宮井がボールを取りに来る。
「大久保田さん、大丈夫ですか?」
「ああ」本当に転んだ大久保田がのっそり立ち上がる。「大丈夫だ、おそらく」
「あまり無理しないでくださいよ」
大久保田は腰をさすっている。
「ああ、保険証を持ってくるのを忘れたなあ」
すでに病院へ行くつもりでいた。
雷電高校は応援ソングの定番キューティーハニーの演奏を始めた。
それに合わせて華やかなチアガールたちが踊り出す。
草野校長は自分たちの応援席を見渡した。向こうとはずいぶん違う。
「教頭、人文字は素晴らしいのだが、うちには雷電高校のような華やかさがないな。ハープを弾いてくれている彼女はピンクのドレスで華があるが、その他の面々は地味じゃないか。野呂先生はネズミ色のスーツだし、シスターは白と黒だし、お坊さんは茶色の袈裟だし、騒音じいさんも茶色のジャケットだし」
「そうですなあ。多数の応援はありがたいですが、うちには色も華も少ないですなあ」
教頭が困った顔をしたとき、金ぴかの衣装がやって来た。
「どうも、お世話様です!」PTAの桃の木会長だった。
本業はお笑いのピン芸人であり、普段は劇場でウクレレ漫談をしている。もちろん、この会場にも仕事用の派手な衣装を着て、ウクレレを持って来ていた。応援席が少しだけ華やかになった。
「一つ、あたしもこれで応援させていただきますよ」ウクレレをポロンと鳴らす。
桃の木会長は応援席に陣取り、ウクレレを弾き始めた。
「えー、みなさん。やる気、元気、驚き、桃の木です! ♪~ポロン。新しくできたサッカー部が~、強豪雷電高校に挑んで行くよ~。♪~ポロン。誰もが勝てるはずないと思っていたが~。♪~ポロン。今は二対二の同点だよ~。♪~ポロン。勝利は目前まで来ておるぞ~。♪~ポロン。名前負けせず~、気後れせず~、がんばるのだよ~。♪~ポロン。♪~ポロン。♪~ポロン」
お笑い好きの生徒たちから大きな拍手が起きた。
ウクレレ漫談が終わったとき、応援席が大きくどよめいた。みんなが視線を向ける先には、レオタードを着た女性たちが立っていた。
「教頭、あの子たちは何の格好をしておるのかね?」
「あれはキャッツ・アイですよ。漫画に出てくる三姉妹の女怪盗です」
その三姉妹とは体育館でも登場した、小久保“マドンナ”先生と、姫宮“マドンナ”生徒と、シスターのマリー・アマーチェだった。サッカー部を応援するために、あのときのキャッツ・アイが再びスタジアムに集結したのである。
シスターは賛美歌を歌っている仲間たちに事情を説明して、抜け出し、白と黒の修道服から紫色のレオタードに着替えて、サッカー部のマネージャーでもある二人のマドンナと合流したのである。
“竜巻高校キャッツ・アイ”参上!
「みんな、がんばってー!」「私たちがついてるよー!」「絶対勝ってねー!」
選手たちに黄色い声援を送ってから、赤と青と紫の三色レオタードが踊り出す。バックでは制服姿の三人の女子生徒たちも踊り出した。姫宮のクラスメートである結菜と芽衣と葵の、くノ一三人組も駆けつけたのである。彼女たちを見た、敵の応援席からも歓声が聞えて来る。
レオタードの赤色と青色と紫色。野呂先生のネズミ色。シスターの白色と黒色。お坊さんと騒音じいさんの茶色。桃の木会長の金色。
竜巻高校の応援席が色付き、満開の花壇のように、一気に華やいだ。
「教頭はさっき三姉妹の女怪盗と言ったが、レオタードの女性は四人おるぞ」校長が不思議がる。
「はあ?」教頭は立ち上がって確認した。
三人の陰に隠れて見えなかったのだが、確かにもう一人いる。
その女性と目が合った。
「教頭先生ー! あたしよー。あ・た・し」
保健室の主、アラフィフの美魔女恵子先生が白い超ハイレグレオタードで踊っていた。
赤と青と紫の三色に加え、ついに白色も加わった。
恵子先生は手に派手な扇子を持って、振り回している。ふわふわの羽根を付けたカラフルな扇子だ。伝説のディスコ「ジュリアナ東京」で使われていた「ジュリ扇」である。昭和の遺物である。この日のために手作りしてきたのである。恵子先生は、必要以上に腰をくねらせながら踊っている。三人の正式キャッツ・アイに負けてたまるかと、対抗意識を燃やしているのである。汗で透けてしまうとヤバい、白色喰い込みレオタードである。先日、誰かから百二十五本のバラの花束をプレゼントされて、気合が入っているのである。誰かがどこかで見ていてくれていると、本気で信じているのである。
たとえ、それが大久保田と野呂先生が置いた残り物のバラであっても。
それに、先日の登山研修で雷電高校の生徒たちから、やまんば呼ばわりされて、リベンジに燃えているのである。
「なにが昭和の妖怪よ!」
怒りで喰い込みレオタードがはち切れそうになる。
「それにしても、せっかくの手作りレオタードをまたこうして着る機会が訪れるなんて、岡戸ちゃんに三千円で売らなくてよかったわ。刺股と交換しなくてよかったわ。みんなー、勝ったら、私とデートしてあげるわよー! チュッ、チュッ、チュッ」
恵子先生は味方のチームに向かって投げキッスを連発する。
「ついでにこの場をお借りして、保健師からの業務連絡をしておくわね。みんなー! ぎょう虫検査のセロファン紙は月曜日に提出だよー。締め切り厳守でお願いねー!」
そして、敵の雷電の応援席に向けて叫んだ。
「ヤッホー!」
――ヤッホー!
今度はちゃんと、こだまとなって帰って来た。
「うふっ、こだまも私のはち切れんばかりの魅力に負けたようね」
この光景はピッチに立つ敵の雷電高校の選手にも見えていた。
「おい、あのキャッツ・アイ、三人ともキレイだぞ!」
「おお、ホントだ。すげえな。竜巻高校に転校したいよ」
「待てよ。あの横にいる人はなんだ?」
「どれ? わあ! おばちゃんが混じってる!」
「登山研修で遭遇した妖怪やまんばだ!」
「あれは、俺のオカンくらいの年だろ」
「俺のオカンがあんな格好をすると言い出したら、命がけで止めるぞ!」
「みんな、あっちを見るな!」
「呪われるぞ!」
「ゲームに集中しろ!」
「あの白色喰い込みレオタードおばちゃんを見せて、俺たちを精神的に動揺させるという竜巻高校の作戦だとしたら?」
「――大成功だな」
草野校長は活気に溢れた、自分たちの応援席を見渡した。
「教頭。うちにもやっと華やかさが出てきたな」
「そうですな。金ぴかのPTA会長に、赤と青と紫のキャッツ・アイ。おまけに恵子先生の白色喰い込みレオタードが参戦してくれましたからなあ」
「最後のは微妙だがな。サッカーの点数と同じく、華やかさでも雷電高校に追い付いたということだな。後は追加点を取って、勝利してくれるのを待つだけだ」
そのとき、遠くから声が聞こえてきた。
「いかがですかー。いかがですかー」
校長はそちらに目をやる。
「教頭、応援席に売り子が来ておるぞ。あの人は何を売っておるんだ?」
「さて、何でしょうか。私は聞いておりませんが」
男性が肩からクーラーボックスを担いで、生徒に次々と何かを売り歩いている。
校長の視線を感じたのか、その男性が振り向いた。
「これは校長先生。ああ、教頭先生もご一緒ですか」
男性は足早に階段を駆け上がって、二人の元にやって来た。
「おお、これは学食の大森店長じゃないか。ここで何を売っておるのかね?」校長が驚いて訊く。
「この通り」クーラーボックスをコンコンと叩く。「アイスを売ってます。生徒さんが集まるというので、出張販売にやって参りました」
相変わらずこの店長はセコいなと思いつつ、
「だいぶ、生徒も増えてきたからな。私もちょうど、応援の熱気で体が暑くなって来たところだよ。どれでもいいから、一つくれるかね」
「はい、どれでもと言われましたが」ボックスのフタを開ける。「この通り、全部ホームランバーです。ホームランで勢いをつけてほしいですからね。一応、バニラ味とチョコ味の二種類を持って来てます」
「では、バニラ味をもらおうかな」
「ありがとうございます。教頭先生はいかがいたしますか?」
「私はチョコ味をもらおうかな」
どんなことでも、校長には逆らいたい教頭である。
同じバニラ味を頼むなんてありえなかった。
「ホームランバーはいかがですかー」
大森店長は代金を受け取ると、声を張り上げながら、遠ざかって行く。
二人は並んでホームランバーを食べはじめた。
「校長、このアイスは子供の頃からありますね。いやあ、懐かしい味ですねえ」教頭は目を細めている。
校長は自慢の口髭にアイスを付けながら食べている。
「教頭、確かに懐かしいが、サッカーの試合をしているのに、ホームランはおかしくないかね?」
「ホームランバーは縁起物ですから、この場にピッタリじゃないでしょうか。――おっ、当たりですよ!」
教頭が校長に食べ終わった棒を見せる。そこには“ホームラン(大当たり)☆☆”と書いてあった。「これで新しいホームランバーと交換してもらえますよ」
すると校長も、「あっ、ワシも当たりだぞ!」
やはり、“ホームラン(大当たり)☆☆”と書いてあった。
「では、私が大森店長のところに行って、校長の分も一緒に交換して来ますよ」
「いや、かまわん。自分で行く」
「大丈夫ですよ。私が……」
「ワシは自分のことは自分でやる主義だからな」
校長は主義などと言い出したが、本当は交換したホームランバーを教頭に喰われるんじゃないかと心配したのである。
「では、一緒に行きましょうか」
二人は仲良く立ち上がった。
「大森店長、待ってくれー! ホームランバーが当たったんじゃー! 次はチョコ味を頼むぞー!」校長が叫びながら階段を駆け上がる。
何! 校長はチョコ味か。ならば……。
「店長、私も当たりましたー!」教頭も負けずに駆け上がる。「私はバニラ味です! バニラ味ですぞー!」決して同じものを頼まない。
生徒たちは目の前を通り過ぎて行く校長と教頭を見て、いい年した大人がまた不毛な争いをしていると、冷やかな目で見ている。
二人は片手に当たりの棒を振りかざしながら、競うように、大森店長の元へと走って行く。
まるで、登山研修のときの再現のようになっているが、すぐに二人はバテるだろう。そして、火照った体に、二本目の冷たいホームランバーは染み入ることだろう。
幸せな二人としか言いようがない。
竜巻高校のベンチからコーチを務める女将が出てきた。紫外線対策で屋根の下に避難していたのだが、そろそろ試合が終わりそうなので、よっこらせと出てきたのである。立っていた中村部長はまたベンチに戻っていた。馬居監督はずっと立ちっぱなしだ。
女将はこの状況をチャンスと見た。うるさい部長が後ろに引っ込んだからである。
「あんた」監督である大将を呼ぶ。「分かってるね。うちが勝ったらダメなんよ。この後も監督とコーチを続けるように言われるからね。三か月だけ引き受けて、さっさと退任するんだからね」
「ああ、分かってるよ」
「あんた、分かってたら、なんで、そんな最前線にいて、選手に檄を飛ばしてるのよ」
「隣で部長が張り切って応援してたもので、釣られてつい大声になって……」
「あんた! 五対0で惨敗する予定が、遠藤豆君が張り切って二点も入れちゃうから、今は二対二の同点でしょ。残り時間からして、あと一点取った方が勝ちよ。うちが確実に負けるように、オウンゴールのサインを出してよ」
「そんなサイン、あるわけないだろ」
「だったら点を取らないように、攻めてる選手を戻してよ」
うるさい女将コーチの要求を受けて、大将監督は選手に指示を出した。
「全員、自陣まで戻るんだー!」大きな声で叫んだ。
下がって行く竜巻高校選手を見て、雷電高校応援席の神輿の上にいる理事長は喜んだ。
「おいおい、ミッドフィルダーどころかフォワードまで下げたぞ」
「やはり、理事長がおっしゃってた通りの寄せ集めですな。何も分かっちゃいませんな」
双眼鏡を覗きながら、神輿の下で控える西見校長が薄ら笑いを浮かべる。
「あの寿司屋の大将と女将のような監督とコーチも大したことはないな。もう時間が残り少ないというのに守りを固めるとはな。ここは点を取りに行く場面だろ」
「引き分け狙いでしょうな」
「確かに、うちと引き分けるだけでも名誉と言えるだろうが、勝負は勝つか負けるかだ。それが選手のモチベーションを上げるんだ。素人の監督には分からんだろうがな。あと一点だ。全員の選手を下げても、うちのフォワード陣が総攻撃をかければ、いとも簡単なことだ」
残り時間は十五分+アディショナルタイム二分=十七分。
竜巻高校の選手は馬居監督の指示により、全員が自陣に戻った。しかし、誰も不平を唱える者はいなかった。サッカーの経験がないため、こんなものかと思っていたためである。
一方、女将コーチはうれしそうだ。
「これでうちが点数を取ることはないね。あとは雷電の選手にがんばってもらって、うちから点を取ってもらうことだね」
だが、全員で守る竜巻の前に、雷電はなかなか点が取れない。シュートの一本も打てないのだ。いくら素人集団とはいえ、十一人全員で守りを固めると、点数は簡単に入らない。
「ちょっと、雷電の子たちは何をやってるのよ! もっとがんばりなさいよ!」
女将コーチはイライラしている。原因は、点数が入らないことも
あるが、更年期障害である。ちょっとしたことでも、感情のコントロールができず、イラつくのである。
そのうち、攻めている雷電に疲れが出てきた。竜巻は転がって来たボールを蹴飛ばして、外に出しているだけである。敵のフォワードと一対一で戦おうなんて思っていない。複数人で対応している。よって、大して疲れてないのである。
双眼鏡で覗いていた西見校長が理事長を見上げて言った。
「うちの選手に疲れが見えて、動きが鈍って来てます」
「まさか。あいつらはこれが狙いだったのか。徹底して守りを固めているところを、わざと攻めさせて、疲れさせるという作戦だったのか。――あの寿司屋の大将のような監督は、相当のキャリアを持つ、名指導者なのかもしれんな。やはり、人を見かけで判断したらダメだ。わしとしたことが、油断をしてしまったようだな。見かけというと、あの老人のような大久保田選手はいつになったら特殊メイクを剥がして、その能力を全開するのかね?」
「また、わざと足をもつれさせて、転んでるフリをしてますね」
「だが、残り時間は少ない。そろそろ素顔を見せて、本領を発揮する頃だろう。元日本代表ゴン中山の御尊顔を拝もうではないか。その華麗なるシュートもな」
なんだか、大久保田という選手が怪しい。高校生にしては老けている。変装したゴン中山に違いないという情報が、すでに理事長の元へは届いていた。
そして、花桐理事長と同じ考えをしている人物がいた。ベンチに座って戦況を見つめている中村部長である。すべての選手を自陣に引き上げるという大胆な作戦が功を奏して、雷電の選手に疲れが生じて来たと信じていた。
素晴らしい! さすがサッカーに詳しい大将と女将だ。ここに来て、こんな一か八かの作戦を決行するとは思わなかった。その作戦はドンピシャで当たった。サッカーのことをよく知らない俺にはできないことだ。あの二人に任せてよかった。これで勝てる。あと一歩だ!
中村部長の夢はあくまでも世界だ。この試合に勝ち、連戦連勝を続け、やがて日本一になり、日本一を踏み台にして世界一を目指そうと思っている。本気で思っている。
まさか、大将監督と女将コーチが、わざと試合に負けようとしているとは、夢にも思ってない。
竜巻の選手は全員が自陣に戻っているが、雷電の選手は全員が攻撃に参加しているわけではない。当然、ディフェンス陣を始めとする選手が数人残って、ゴールを守りながら、戦況を見つめている。
女将はそれが気に喰わない。
「あんた、あの後ろの方で突っ立ってる雷電の子たちもこっちに来て、全員でうちのゴールにバンバンとシュートをするように言ってよ」
「監督が敵の選手に指示できるわけないだろ。聞いたこともないよ」
「前例がないならやってみろと偉い人が言ってたでしょ」
「ここで出す格言じゃないよ」
「とにかく、言ってみてよ」
またしつこいコーチに言われて、仕方なく、監督は敵の雷電に向かって大きな声で叫んだ。
「突っ立ってないで、全員上がれー! 一人残らず、上がれー! 一丸となって攻撃するんだー! シュートをバンバンと放つんだー!」
そのとき、ボールを奪った遠藤が走り出した。そのあとを、二人のラグビー部の玉本と足立が続く、さらにその後を竜巻の選手全員が駆け上がって行く。
馬居監督の、全員上がれの指示は当然、自分たちへの指示だと受け取った竜巻の選手が、いっせいに走り出したのである。まさか、監督が敵の選手に指示を出したとは誰も思ってない。
スポーツ飛び級の遠藤は速い。このピッチに立つ誰よりも速い。敵の選手も、さすがのラグビー部の二人も振り切られる。すぐに、敵陣のゴールの左側にたどり着いた。敵のデカいキーパーが迫って来る。遠藤の足は速いが非力だ。ドサクサに紛れて、ちょこっと打つシュート力はあっても、一対一でキーパーを弾くようなシュート力はない。
後ろから来た玉本にパスをする。玉本にサッカー経験はない。だが、ラグビーで培ったパワーは、サッカーにも通用するはずだ。ボールを受けた玉本は渾身の力で蹴飛ばした。敵のキーパーはボールを横っ飛びで弾く。あまりにも強烈なシュートだったため、キャッチできず、弾くのが精一杯だったのだ。弾かれたボールはゴールの右の方に転がって行った。
左からシュートを打つ、キーパーが弾いたボールは右に転がる。そのため、あらかじめ右に人を配置しておく。そんなことを素人の竜巻の選手が考えてるわけない。
右側には誰もいない。転々とボールは転がる。だが、誰もいないはずの右側に人影がフラッと現れた。学校犬ポチでも二宮金次郎でもない。チャーリーだった。
馬居監督の、一人残らず上がれの指示に、素直なチャーリーは、ゴールキーパーにもかかわらず、上がって来たのだ。ゴール前を見ると、みんなは左側に固まっている。
では、皆さんの邪魔にならないようにと、ヤンキーにしては謙虚なチャーリーは、ポッカリとスペースが空いていた右側に走り込んだのであった。
そして、走り込んでみたら、たまたま目の前にボールが転がって来たのである。
オーマイガーッ!
ここでシュートを決めれば勝てる。時間はすでにアディショナルタイムに入っている。シュートが入った瞬間、勝利も決定するだろう。
応援席では、雅楽部が、ハープ部が、突撃ラッパが、賛美歌が、般若心経が、カセットテープが、ウクレレが、四人のキャッツ・アイが、人文字が選手を応援してくれている。そして、巨大な応援旗は、スコット山田たち六人のヤンキー仲間によって、今も倒れることなく、支えられ、その勇姿を風になびかせている。
チャーリーは思った。あんなに僕たちのことを応援してくれている。ここで、みんなの期待に答えなくてはいけない。ヤンキー部サブリーダーの根性を見せてやる。
思い起こせば、イギリスに生まれた僕は日本へと留学し、スコット山田と出会い、ヤンキーという生き様に魅了された。ヤンキーという生き様は、日本の侍に通じるのかもしれない。その日本の侍は英国の騎士に通じると確信している僕は迷わず、ヤンキー道を進み始めた。それから僕は国際免許でバイクを乗り回し、ヤンキーの定番のウンコ座りをマスターして……。
「こらっ、チャーリー! いつまでブツブツと独り言を言ってるんだ。 早くシュートを打て!」
中村部長のデカい声でふと我に返ると、すぐ目の前に、起き上がって突進してくる敵ゴールキーパーの必死の形相が見えた。
「ヤバい。殺される!」
チャーリーはボールを蹴ろうと狙い所を探した。ゴールの左隅が見えた。あそこに入れるとシュートが決まる。
だが、僕が狙って入るとは思えない。
キーパーのみならず、他の選手たちも迫って来た。周りが全部敵
になった。海に囲まれたイギリスと日本みたいだ。
ああ、もう逃げられない。
だけど、どうせ狙っても入らないのなら……。
チャーリーは目をつぶった。
そして、長い足で思い切り蹴飛ばした。
「ヤンキー魂よ、このボールに宿ってくれ!」
やがて、球技場全体が静かになった。
みんな、なぜ黙っているのか? 僕が蹴ったボールはどうなったのだろう? うまく入ったのか? 大きく外れたのか? キーパーにキャッチされたのか?
ボールを蹴った感覚はある。だから、空振りはしてないはずだ。
チャーリーが勇気を出して、目を開けようとした瞬間、競技場に長い笛の音が響いた。
ゲームセットだった。
駆け寄って来た仲間に、チャーリーは地面に引き倒された。その上から選手が乗ってくる。やたらと重い。ラグビー部の玉本と足立だった。さらに、その上から、宮井も中島も犬井も鳥谷も平井も金森もみんな乗っかって来る。どさくさに紛れて、サッカー部設立の立役者、中村部長も交じっている。
すぐにそれは選手たちの山となった。
選手の山によじ登り、てっぺんでヨロヨロと立ち上がったのは、サッカーの才能なんか、これっぽっちも持ち合わせてない、ニセ者のゴン中山、社会人入学の大久保田だった。手には酸素吸入器を持っている。
「皆の者~、竜巻高校がやりましたぞ~。あの雷電高校に勝ちましたぞ~。――ああ、腰が痛いわい。首も痛い。先祖のタタリかのう。だが、勝ちましたぞ~!」
特殊メイクなんかしていない素の大久保田が雄叫びを上げた。
「ゼイ、ゼイ、ゼイ……」
息が切れたため、あわてて酸素吸入器を口に当てる。
大久保田に呼応して、中村部長も叫ぶ。
「みんなー! よくやってくれたー! あの雷電高校に勝てたなんて夢のようだ! がんばれば夢は叶うんだ! そのことを、あらためて教えてくれたみんな、ありがとー! よーし、次は世界一だぞ!」
雷電の理事長に一矢報いることができて、中村はうれしくて、興奮している。全身に鳥肌が立っている。選手に感謝し、大将と女将に感謝し、応援席に感謝し、ポチにも感謝している。日本一をすっ飛ばして、世界一を目指している。
悔しがる理事長の顔が目に浮かんでいることだろう。中村はこの選手の山の中にいるはずなのだが、いつもの大きな声は聞こえても、みんなに埋もれていて、その姿は見えない。選手たちは人間の山を形成しながら、まだ歓喜に沸いている。
一番下で押しつぶされて、ウンウン唸っているチャーリーには気の毒なことだった。
チャーリーは、誰かの手だか足だか分からない隙間から外を覗いた。さっき蹴飛ばしたボールが、雷電高校のゴールの中で転がっていた。
わおっ、本当にゴールしたんだ!
首を捻って、違う方向からも外を覗いてみた。ベンチの前で馬居監督のたたずんでいる姿が見えた。
思いもよらず勝ってしまったため、呆然自失の状態なのだが、チャーリーは監督が勝利の余韻に浸っていると勘違いした。
「最後はヤンキーのボクが決めましたよ! ありがとう、寿司マスター!」
竜巻高校応援席は勝利を目の当たりにして、大騒ぎをしていた。
草野校長は興奮して我を忘れ、森教頭と抱き合い、二人でピョンピョン跳ねて喜んだ。ふと、我に返ると、目の前に大嫌いな教頭の顔があったので、あわてて向こうに押しやった。森教頭も同じだったらしく、あわてて校長の顔を向こうに押しやった。しばらくの間、二人は無言となり、気まずい雰囲気となった。
雅楽部は持参していた太鼓を打ち鳴らし、ハープは激しく掻き鳴らされ、キャッツ・アイの三人は抱き合って喜び、くノ一の三人は涙し、祝いの突撃ラッパを大音響で吹く騒音じいさんに、なぜか、アラフィフの美魔女恵子先生が抱きついていた。――トンデモカップル誕生である。
「私という名の紙飛行機はまだ墜落しないわよ!」
やっと春が来た恵子先生はジュリ扇をバサバサ振り回して、喜びを爆発させている。マリー・アマーチェと星輝和尚は宗教の垣根を越えて、握手を交わし、中には木魚と十字架を交換している者も現れ、野呂先生はカセットテレコのボリュームを最大限に上げて“愛は勝つ”を流し、酒井先生は“仙台すずめ踊り”をソレソレと踊り、桃の木PTA会長はウクレレを振り回し、大森店長はホームランバーが完売して空になったクーラーボックスを頭上に掲げ、警官たちは喜びのあまり拳銃をぶっ放しそうになるのを我慢し、人文字では“倒載干戈”という四字熟語を作り上げていた。
“とうさいかんか”。――戦いが終わって平和になったという意味である。
グランドの隅に繋がれた学校犬ポチもうれしそうに吠え、おそらく、どこで見守ってくれている二宮金次郎も喜んで走り回ってくれていることだろう。
得点者チャーリーを下敷きにした選手の山に、ラッパー安藤も勝利者として、加わりたかったのだが、骨に五本のヒビが入った足が痛くて、行けなかった。
安藤はベンチの脇にしゃがんで、最近愛用していた二本の松葉杖を逆さまに立てた。そして、狙いを定めて、スイッチを押した。用具係の岡戸さんに頼んで仕込んであった二発の打ち上げ花火が、松葉杖の先から空へ向けて打ち上がった。
ヒュー、ヒュー。パーン、パーン。
大きな音がしたが、快晴の空をバックに広がった花火はあまり見えなかった。だが、大空に花火が上がったことは、竜巻高校の応援席でも、二発の大きな音で分かった。
昼間の見えない花火に向けて、大歓声が上がった。
そして、それは英語の酒井愛子先生も気づいた。
「やるじゃん、ラッパー安藤」
とてもうれしそうにつぶやいた。
一方、負けた雷電高校の応援席では……。
西見校長の手から双眼鏡がずり落ちた。
花桐理事長は御神輿の上に立ちあがって、呆然としている。
「校長、我々は竜巻高校に負けたのか?」見下ろして訊く。
「どうやら、そのようです」見上げて言う。「ゴールキーパーにシュートを決められました」
「まさか、キーパーまで攻撃に加わるような采配を行うとは、やはりあの寿司屋みたいな監督はタダ者ではなかったな。寄せ集めのチームだと思って、気を抜いていたのが敗因だ。生徒は素人でも、指導者が優秀なら負けることもあるわ。中村先生が高笑いする姿が目に浮かぶわい。だが、この恨みはいつかきっと晴らしてやる。――さあ、帰るぞ!」
理事長は御神輿の上の椅子に座り込んだ。そして、神輿が相撲部の手によって持ち上げられた。だが、一向に進まない。
「どうした!? 早く行かんか!」神輿の上から理事長が怒鳴る。
西見校長が神輿の後ろから叫んだ。
「方向指示器が作動しません!」
「方向指示器が作動せんのに、道を曲がったら、道路交通法違反だろ。金属部分の接触が悪いのではないのか。スイッチを何回か押してみろ」
カチ、カチ、カチ、カチ。
「理事長、バッテリーから煙が出てきました」
「バカ者、カチカチやりすぎなんだよ。――早く下ろせ!」
理事長が地面に足を付いたとき、足首がグネッと曲がって、階段を転がり落ちて行った。
「理事長!」西見があわてて追いかける。
ゴロゴロ、ゴロゴロ。――ドカッ。
理事長が止まった。
「理事長! 大丈夫ですか?」
「バカ者! 階段の上から下まで転がり落ちて、大丈夫なわけなかろう! 大丈夫ではない人間に、大丈夫ですかなんて訊くな!」
「おケガはどうですか?」
「バカ者、頭から血をタラタラ流してケガをしている人間に、おケガはどうですかなんて訊くな! それよりも、わしの大切な御神輿はどうなっておるんだ?」
「えーと、御神輿ですけど」西見が階段を見上げる。「ご覧の通り、炎に包まれております」
竜巻高校のベンチ前で大将監督と女将コーチが突っ立っている。
「あんた、大変だよ。あの雷電高校に勝ってしまったよ」
「まさか、勝っちゃうとはなあ。びっくりだよなあ」
「中村部長は子供たちの元へ駆けて行っちゃったね」
「よほど嬉しかったのだろうな」
「あんた、私があれほど言ったでしょうが、勝ってはダメだって」
「俺も勝てないように、お前から言われた通り、子供たちに指示したじゃないか」
「うちの子たちは素直なのか、バカなのか分からないねえ」
「サッカーの才能があったんじゃないのか」
「あんたがベンチに岡持ちなんか持ってくるから勝っちゃうんでしょ」
「お守りの代わりに持って来たんだよ」
「負けるように、上下逆さまに置くべきだったかねえ」
「今さら言われてもなあ」
「ところで、これはテレビに映ってるのかい?」
「ああ、あそこにカメラがあるな」
「あら、いやだ。ちゃんとお化粧しとけばよかったわ」
「俺たち二人の格好は、全国のたくさんの視聴者に見られてるんだな」
「だって、中村部長が普段着でいいと言うから」
「寿司屋の普段着はこの割烹着と長靴だからなあ」
「でも、こんな格好でも勝ってしまったのだからね。これじゃ、三か月で退任できないよ。あと三年くらいやってくれと言われるよ。どうするのよ」
「どうするって言われてもなあ。お前はどうしたい?」
「そんなの、ギャラしだいに決まってるでしょ!」
首から下げたお揃いの十字架がキラリと光った。
竜巻高校の応援席で披露された最後の人文字は“叢軽折軸”であった。
“そうけいせつじく”
小さな力でも、集まれば大きな力になるという意味だった。
(了)
0
お気に入りに追加
2
この作品は感想を受け付けておりません。
あなたにおすすめの小説


三限目の国語
理科準備室
BL
昭和の4年生の男の子の「ぼく」は学校で授業中にうんこしたくなります。学校の授業中にこれまで入学以来これまで無事に家までガマンできたのですが、今回ばかりはまだ4限目の国語の授業で、給食もあるのでもう家までガマンできそうもなく、「ぼく」は授業をこっそり抜け出して初めての学校のトイレでうんこすることを決意します。でも初めての学校でのうんこは不安がいっぱい・・・それを一つ一つ乗り越えていてうんこするまでの姿を描いていきます。「けしごむ」さんからいただいたイラスト入り。


リストカット伝染圧
クナリ
青春
高校一年生の真名月リツは、二学期から東京の高校に転校してきた。
そこで出会ったのは、「その生徒に触れた人は、必ず手首を切ってしまう」と噂される同級生、鈍村鉄子だった。
鉄子は左手首に何本もの傷を持つ自殺念慮の持ち主で、彼女に触れると、その衝動が伝染してリストカットをさせてしまうという。
リツの両親は春に離婚しており、妹は不登校となって、なにかと不安定な状態だったが、不愛想な鉄子と少しずつ打ち解けあい、鉄子に触れないように気をつけながらも関係を深めていく。
表面上は鉄面皮であっても、内面はリツ以上に不安定で苦しみ続けている鉄子のために、内向的過ぎる状態からだんだんと変わっていくリツだったが、ある日とうとう鉄子と接触してしまう。


ゆめまち日記
三ツ木 紘
青春
人それぞれ隠したいこと、知られたくないことがある。
一般的にそれを――秘密という――
ごく普通の一般高校生・時枝翔は少し変わった秘密を持つ彼女らと出会う。
二つの名前に縛られる者。
過去に後悔した者
とある噂の真相を待ち続ける者。
秘密がゆえに苦労しながらも高校生活を楽しむ彼ら彼女らの青春ストーリー。
『日記』シリーズ第一作!

義姉妹百合恋愛
沢谷 暖日
青春
姫川瑞樹はある日、母親を交通事故でなくした。
「再婚するから」
そう言った父親が1ヶ月後連れてきたのは、新しい母親と、美人で可愛らしい義理の妹、楓だった。
次の日から、唐突に楓が急に積極的になる。
それもそのはず、楓にとっての瑞樹は幼稚園の頃の初恋相手だったのだ。
※他サイトにも掲載しております
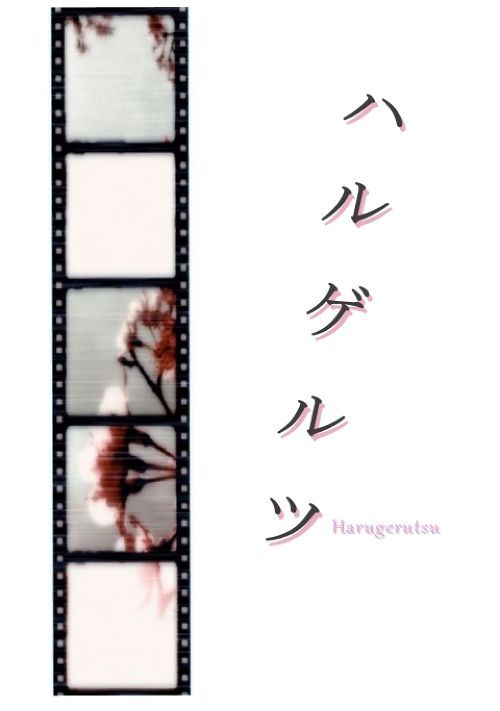
ハルゲルツ
ささゆき細雪
青春
中学の同級生、彰子(あきこ)と春継(はるつぐ)。
セバスチャン騒動によってはじまってしまったと言っても過言ではないふたりの関係は、卒業して半年たった今も恋人同士と呼ぶには淡く、脆い。
「なんで俺たちつきあってんだろ?」
ある秋の朝。春継が口にした言葉から、微妙なすれ違いが始まった。
折しも見た目だけは美少女である彰子は、他の男子に言い寄られてしまい?
美少女だけど残念な性格のヒロインをめぐって、男子たちが翻弄される? ちょっと風変わりな青春小説。メクるでも公開中です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















