お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

8分間のパピリオ
横田コネクタ
SF
人間の血管内に寄生する謎の有機構造体”ソレウス構造体”により、人類はその尊厳を脅かされていた。
蒲生里大学「ソレウス・キラー操縦研究会」のメンバーは、20マイクロメートルのマイクロマシーンを操りソレウス構造体を倒すことに青春を捧げるーー。
というSFです。


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

博士のロボット
おみくじ
SF
18世紀半ば、イギリスでの産業革命以降、機械技術は世界各国で大きく発展した。人間のように労働する機械を、人々はロボットと呼ぶようになり、20世紀後半はロボット総労働力時代の全盛期であった。
しかしそんな時代に、イギリスのとある若き天才ロボット工学博士が、世界を驚愕させるものを発明する。
それは人間を教育するロボット。
このロボットは学生の成績向上に大きく貢献し、実用化まであと一歩のところまでせまった。しかし大きな壁にぶち当たってしまう。それは、幼稚園に通う子ども達の教育であった。
『木の枝は魔法の杖』『綺麗なガラス玉は人魚の涙』と無茶苦茶なことを言う子ども達。
博士の教育ロボットはオーバーヒートして壊されてしまう。一体どうすれば上手くいくのか。
頭を悩ます博士は、苦難しながらも、遂に答えを見つける。

GROUND ZERO
K
SF
「崩壊世界(ゼロ)から始まる―」
何故そうなったの覚えている者は誰一人として存在しない
全てが一度崩壊し人々がこれまでに築き上げてきた文化や技術、法や良識は瓦礫の海に呑み込まれた
堆積した世界の砕片に埋もれた筈の太古の記憶が時折無作法に寝返りを打つ
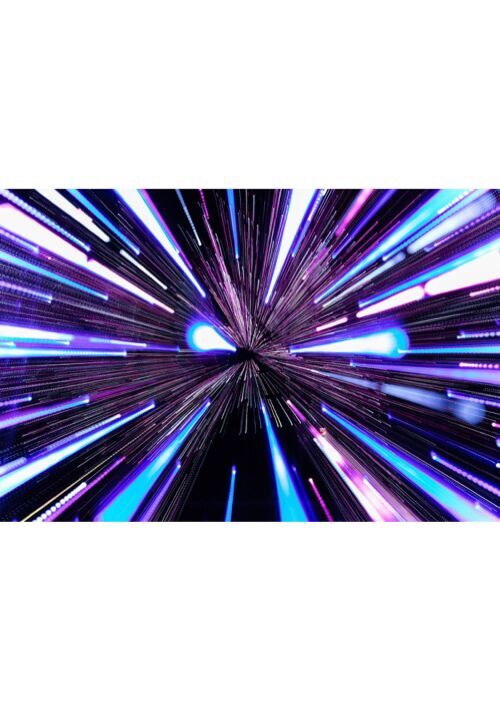
【総集編】未来予測短編集
Grisly
SF
❤️⭐️お願いします。未来はこうなる!
当たったら恐ろしい、未来予測達。
SF短編小説。ショートショート集。
これだけ出せば
1つは当たるかも知れません笑

「メジャー・インフラトン」序章2/7(僕のグランドゼロ〜マズルカの調べに乗って。少年兵の季節FIRE!FIRE!FIRE! No1. )
あおっち
SF
敵の帝国、AXISがいよいよ日本へ攻めて来たのだ。その島嶼攻撃、すなわち敵の第1次目標は対馬だった。
この序章2/7は主人公、椎葉きよしの少年時代の物語です。女子高校の修学旅行中にAXIS兵士に襲われる女子高生達。かろうじて逃げ出した少女が1人。そこで出会った少年、椎葉きよしと布村愛子、そして少女達との出会い。
パンダ隊長と少女達に名付けられたきよしの活躍はいかに!少女達の運命は!
ジャンプ血清保持者(ゼロ・スターター)椎葉きよしを助ける人々。そして、初めての恋人ジェシカ。札幌、定山渓温泉に集まった対馬島嶼防衛戦で関係を持った家族との絆のストーリー。
彼らに関連する人々の生き様を、笑いと涙で送る物語。疲れたあなたに贈る微妙なSF物語です。是非、ご覧あれ。
※加筆や修正が予告なしにあります。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















