お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

遥かなるマインド・ウォー
弓チョコ
SF
西暦201X年。
遥かな宇宙から、ふたつの来訪者がやってきた。
ひとつは侵略者。人間のような知的生命体を主食とする怪人。
もうひとつは、侵略者から人間を守ろうと力を授ける守護者。
戦争が始まる。
※この物語はフィクションです。実在する、この世のあらゆる全てと一切の関係がありません。物語の展開やキャラクターの主張なども、何かを現実へ影響させるような意図のあるものではありません。

願いを叶えるだけの僕と人形
十四年生
SF
人がいいだけのお人よしの僕が、どういうわけか神様に言われて、人形を背中に背負いながら、滅びたという世界で、自分以外の願いを叶えて歩くことになったそんなお話。

鋼殻牙龍ドラグリヲ
南蛮蜥蜴
ファンタジー
歪なる怪物「害獣」の侵攻によって緩やかに滅びゆく世界にて、「アーマメントビースト」と呼ばれる兵器を操り、相棒のアンドロイド「カルマ」と共に戦いに明け暮れる主人公「真継雪兎」
ある日、彼はとある任務中に害獣に寄生され、身体を根本から造り替えられてしまう。 乗っ取られる危険を意識しつつも生きることを選んだ雪兎だったが、それが苦難の道のりの始まりだった。
次々と出現する凶悪な害獣達相手に、無双の機械龍「ドラグリヲ」が咆哮と共に牙を剥く。
延々と繰り返される殺戮と喪失の果てに、勇敢で臆病な青年を待ち受けるのは絶対的な破滅か、それともささやかな希望か。
※小説になろう、カクヨム、ノベプラでも掲載中です。
※挿絵は雨川真優(アメカワマユ)様@zgmf_x11dより頂きました。利用許可済です。

❤️レムールアーナ人の遺産❤️
apusuking
SF
アランは、神代記の伝説〈宇宙が誕生してから40億年後に始めての知性体が誕生し、更に20億年の時を経てから知性体は宇宙に進出を始める。
神々の申し子で有るレムルアーナ人は、数億年を掛けて宇宙の至る所にレムルアーナ人の文明を築き上げて宇宙は人々で溢れ平和で共存共栄で発展を続ける。
時を経てレムルアーナ文明は予知せぬ謎の種族の襲来を受け、宇宙を二分する戦いとなる。戦争終焉頃にはレムルアーナ人は誕生星系を除いて衰退し滅亡するが、レムルアーナ人は後世の為に科学的資産と数々の奇跡的な遺産を残した。
レムールアーナ人に代わり3大種族が台頭して、やがてレムルアーナ人は伝説となり宇宙に蔓延する。
宇宙の彼方の隠蔽された星系に、レムルアーナ文明の輝かしい遺産が眠る。其の遺産を手にした者は宇宙を征するで有ろ。但し、辿り付くには3つの鍵と7つの試練を乗り越えねばならない。
3つの鍵は心の中に眠り、開けるには心の目を開いて真実を見よ。心の鍵は3つ有り、3つの鍵を開けて真実の鍵が開く〉を知り、其の神代記時代のレムールアーナ人が残した遺産を残した場所が暗示されていると悟るが、闇の勢力の陰謀に巻き込まれゴーストリアンが破壊さ

惑星保護区
ラムダムランプ
SF
この物語について
旧人類と別宇宙から来た種族との出来事にまつわる話です。
概要
かつて地球に住んでいた旧人類と別宇宙から来た種族がトラブルを引き起こし、その事が発端となり、地球が宇宙の中で【保護区】(地球で言う自然保護区)に制定され
制定後は、他の星の種族は勿論、あらゆる別宇宙の種族は地球や現人類に対し、安易に接触、交流、知能や技術供与する事を固く禁じられた。
現人類に対して、未だ地球以外の種族が接触して来ないのは、この為である。
初めて書きますので読みにくいと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

逆転のレヴラデウス
弓チョコ
ファンタジー
1000年の間、人間に虐げられてきた魔物達は魔王を誕生させ、逆襲を始める。
1000年の間、魔物に虐げられてきた人間達は、救世主の誕生を願う。
人間と魔物の、戦争の物語。
それを終結させた、王と英雄の物語。
逆転の物語。
※この物語は「起・承・転・結」の全4話構成です。

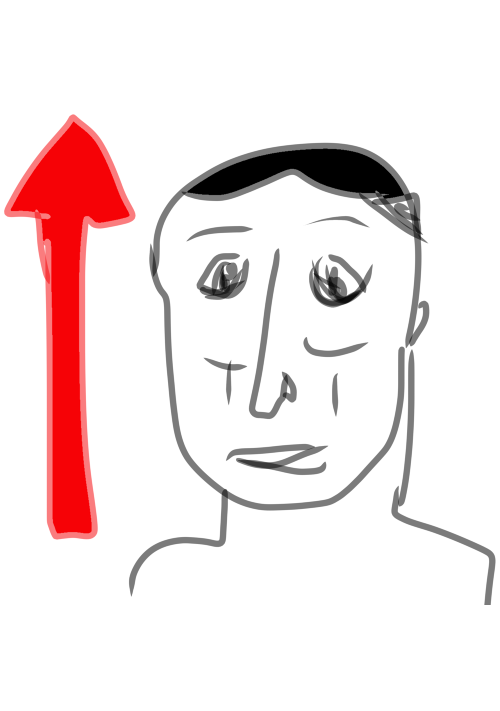
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















