27 / 65
第一章 どうして僕が彼女を『放』っておけなかったのか
第26話 今宵は素敵な『夜』になりそうだ
しおりを挟む
「そうだね。どうも僕はそうじゃないらしい。別に構わない。君を止められるなら!」
我ながら本当に何を言っているのか。今度こそ命を奪われるかもしれないというのに。その本人と向かい合おうなんて真面じゃない。
いったいいつから? 今ここでアルナと対峙したときから? いや、あの雨の日。最初に彼女と出会った時から、とっくに普通じゃなくなっている。
「わからない……わからないよ……でも、どうしても邪魔をするというのなら……」
アルナはスカートを少し託し上げると、するりと薄刃が中へと吸い込まれ消失した。
「私が貴方を殺す」
放たれた殺気で、屋敷の空気が張り詰めていく。
だけど、もう臆さない。多分今日が最後の機会。
また引き下がってしまったら、きっと二度と彼女とは会えなくなる。
これは意地だ! 端から覚悟は出来ている。
アルナの足元に白い火花が散った刹那、ふっと姿が消えた。来るっ!
腰を落とし、身を屈めると、後頭部をアルナの手刀が掠め、猛烈な風切り音を響かせる。
真面に貰ったら、頭と胴が切り離されかねない一撃。後ろ髪が少し持って行かれたけど。
身体を翻し、アルナを捕えようとしたが――既にいない。
多分初撃と同じ縮地功で躱したんだ。縮地功は基礎的な象気による高速歩法術。
眼には見えないけど、攪乱し隙をつこうと空間を立体的に、縦横無尽に駆け巡っているのは分かる。
同等の速さで動かなきゃ視界に入れることさえ敵わないか。なら!
象気を足に集中させ床を蹴る。滅血拳の縮地功【群光迅】――。
捉えた! 彼女の纏う象気……何て綺麗なんだ。まるで青白い花火のよう。
「まさかミナト!? 貴方も象術をっ!? 私の【絶鬼道】にそっくりなんて!」
光と雷の残光が絡み合い、夜露を含んだ庭園内を走り抜ける。
海のように広い芝生へと出るとほぼ同時、僕等は再び跳躍した。
交差する技と技。衝突する気と気。アルナの攻撃は全部急所ばかりを狙ってくる。確実に殺すつもりきている。
だけど、ハウアさんじゃあるまいし女性を殴るなんて真似、死んでも出来ない。
互いの腕が激突する。なんて力だ。
一度気を緩めようものなら簡単に吹っ飛ばされそう。
それになんて形相。こんなアルナ初めてだ。
歯を食いしばって睨みつけて、とても女の子がする顔じゃない。
「ミナトっ! 貴方は一体っ!?」
「決まっているじゃないか! 僕は君の友達だっ!」
アルナの表情に迷いが見えた。
怒りじゃない。苦しんでいるんだ。
いったい誰が彼女を? 半分は自分に間違いない。残りは多分一族の掟。
「過ち犯そうとしている友達を放っておけるわけないじゃないか!?」
捕まえようと手を伸ばすも半身を捩って躱された。
翻り様、蛇に似たうねりをする何かを、視界の端に捉える。
咄嗟に防いだ腕に、極太の鞭で殴られたような衝撃が走る。ビリビリといつまでも後を引きずる痛み。
なるほど、初めてアルナに殺されかけ、欄干に叩付けられたのはこれだったんだ。
アルナの白くて細い脚が撓って、立て続けに死角から飛んでくる。
どうなってるんだこの軌道!? まさか関節でも外れているのか!?
まるで無数の蛇に襲われているみたいだ。段々変な趣味が目覚め――じゃなくて!
マズイ! 防御が間に合わない! だけど急所に食らえば一溜まりも無い。
不意にアルナの手の中で何かが煌き、反射的に手甲の鋼の部分で弾いた。
こ、これは【麗月】の暗器、柳葉飛刀――。
「しまったっ!」
視線を落とした僅かな隙をつかれ、右脇腹にアルナの強烈な蹴りが突き刺さる。
衝撃波と鈍い音が体内に響き渡る。
間違いなく肋骨6番と7番に罅が入った。
肝臓周辺は筋肉が少なく鍛えにくい。
激痛のあまり危うく蹲りそうなったところに空かさず畳みかけられる。
辛うじて防ぐも、内臓の位置が変わるぐらいの重い衝撃に、軽々と身体が吹っ飛ばされた。
「ぐっ!」
夜露の滴る芝生の上に叩きつけられ、肺から空気が抜けた。
直ぐに身を起こしたのも束の間、馬乗りでアルナに地面へと押し付けられる。
眼前に飛刀を突きつけられ、殺意が揺らめく刃先を目にしても、僕は――冷静だった。
「ハァ……ハァ……どうしたん、だい……殺さないの?」
お互い肩で息をしながら、雨露にまみれた僕達。
濡れた長い髪が月の光で煌く。
不謹慎とは分かっていたけど、アルナの姿が、なんというか、とても色っぽかった。
「何で……」
声を絞るように、そんな寂しげな言葉がアルナの震える唇から零れてくる。
やがて彼女から堰を切ったように嗚咽が漏れ始めた。
「どうして……思い出のままで……いてくれなかったの……どうして……綺麗な思い出のまま……」
ふと額に温かい露が滴って、流れ落ちていく。
悪いことをした。
一歩間違えれば最後の別れが殺し合いという一番強烈な記憶を刻みつけてしまうところだった。
自分にとっての故郷がそうであるように。
彼女の頬にそっと触れ、微笑んで見せた。
我ながら本当に何を言っているのか。今度こそ命を奪われるかもしれないというのに。その本人と向かい合おうなんて真面じゃない。
いったいいつから? 今ここでアルナと対峙したときから? いや、あの雨の日。最初に彼女と出会った時から、とっくに普通じゃなくなっている。
「わからない……わからないよ……でも、どうしても邪魔をするというのなら……」
アルナはスカートを少し託し上げると、するりと薄刃が中へと吸い込まれ消失した。
「私が貴方を殺す」
放たれた殺気で、屋敷の空気が張り詰めていく。
だけど、もう臆さない。多分今日が最後の機会。
また引き下がってしまったら、きっと二度と彼女とは会えなくなる。
これは意地だ! 端から覚悟は出来ている。
アルナの足元に白い火花が散った刹那、ふっと姿が消えた。来るっ!
腰を落とし、身を屈めると、後頭部をアルナの手刀が掠め、猛烈な風切り音を響かせる。
真面に貰ったら、頭と胴が切り離されかねない一撃。後ろ髪が少し持って行かれたけど。
身体を翻し、アルナを捕えようとしたが――既にいない。
多分初撃と同じ縮地功で躱したんだ。縮地功は基礎的な象気による高速歩法術。
眼には見えないけど、攪乱し隙をつこうと空間を立体的に、縦横無尽に駆け巡っているのは分かる。
同等の速さで動かなきゃ視界に入れることさえ敵わないか。なら!
象気を足に集中させ床を蹴る。滅血拳の縮地功【群光迅】――。
捉えた! 彼女の纏う象気……何て綺麗なんだ。まるで青白い花火のよう。
「まさかミナト!? 貴方も象術をっ!? 私の【絶鬼道】にそっくりなんて!」
光と雷の残光が絡み合い、夜露を含んだ庭園内を走り抜ける。
海のように広い芝生へと出るとほぼ同時、僕等は再び跳躍した。
交差する技と技。衝突する気と気。アルナの攻撃は全部急所ばかりを狙ってくる。確実に殺すつもりきている。
だけど、ハウアさんじゃあるまいし女性を殴るなんて真似、死んでも出来ない。
互いの腕が激突する。なんて力だ。
一度気を緩めようものなら簡単に吹っ飛ばされそう。
それになんて形相。こんなアルナ初めてだ。
歯を食いしばって睨みつけて、とても女の子がする顔じゃない。
「ミナトっ! 貴方は一体っ!?」
「決まっているじゃないか! 僕は君の友達だっ!」
アルナの表情に迷いが見えた。
怒りじゃない。苦しんでいるんだ。
いったい誰が彼女を? 半分は自分に間違いない。残りは多分一族の掟。
「過ち犯そうとしている友達を放っておけるわけないじゃないか!?」
捕まえようと手を伸ばすも半身を捩って躱された。
翻り様、蛇に似たうねりをする何かを、視界の端に捉える。
咄嗟に防いだ腕に、極太の鞭で殴られたような衝撃が走る。ビリビリといつまでも後を引きずる痛み。
なるほど、初めてアルナに殺されかけ、欄干に叩付けられたのはこれだったんだ。
アルナの白くて細い脚が撓って、立て続けに死角から飛んでくる。
どうなってるんだこの軌道!? まさか関節でも外れているのか!?
まるで無数の蛇に襲われているみたいだ。段々変な趣味が目覚め――じゃなくて!
マズイ! 防御が間に合わない! だけど急所に食らえば一溜まりも無い。
不意にアルナの手の中で何かが煌き、反射的に手甲の鋼の部分で弾いた。
こ、これは【麗月】の暗器、柳葉飛刀――。
「しまったっ!」
視線を落とした僅かな隙をつかれ、右脇腹にアルナの強烈な蹴りが突き刺さる。
衝撃波と鈍い音が体内に響き渡る。
間違いなく肋骨6番と7番に罅が入った。
肝臓周辺は筋肉が少なく鍛えにくい。
激痛のあまり危うく蹲りそうなったところに空かさず畳みかけられる。
辛うじて防ぐも、内臓の位置が変わるぐらいの重い衝撃に、軽々と身体が吹っ飛ばされた。
「ぐっ!」
夜露の滴る芝生の上に叩きつけられ、肺から空気が抜けた。
直ぐに身を起こしたのも束の間、馬乗りでアルナに地面へと押し付けられる。
眼前に飛刀を突きつけられ、殺意が揺らめく刃先を目にしても、僕は――冷静だった。
「ハァ……ハァ……どうしたん、だい……殺さないの?」
お互い肩で息をしながら、雨露にまみれた僕達。
濡れた長い髪が月の光で煌く。
不謹慎とは分かっていたけど、アルナの姿が、なんというか、とても色っぽかった。
「何で……」
声を絞るように、そんな寂しげな言葉がアルナの震える唇から零れてくる。
やがて彼女から堰を切ったように嗚咽が漏れ始めた。
「どうして……思い出のままで……いてくれなかったの……どうして……綺麗な思い出のまま……」
ふと額に温かい露が滴って、流れ落ちていく。
悪いことをした。
一歩間違えれば最後の別れが殺し合いという一番強烈な記憶を刻みつけてしまうところだった。
自分にとっての故郷がそうであるように。
彼女の頬にそっと触れ、微笑んで見せた。
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
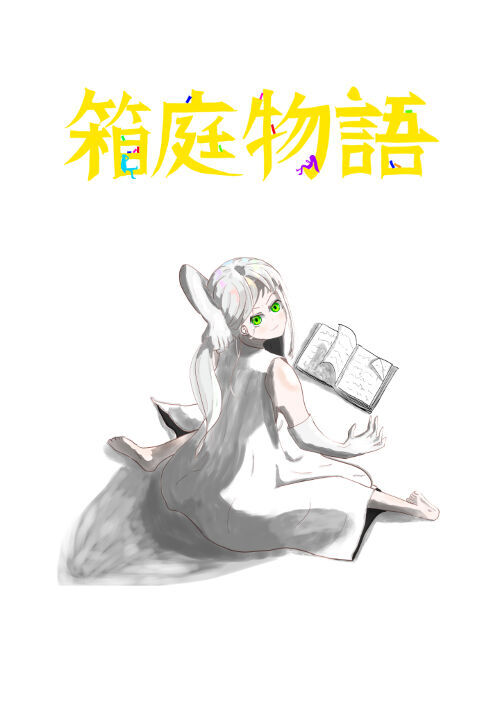
箱庭物語
晴羽照尊
ファンタジー
※本作は他の小説投稿サイト様でも公開しております。
※エンディングまでだいたいのストーリーは出来上がっておりますので、問題なく更新していけるはずです。予定では400話弱、150万文字程度で完結となります。(参考までに)
※この物語には実在の地名や人名、建造物などが登場しますが、一部現実にそぐわない場合がございます。それらは作者の創作であり、実在のそれらとは関わりありません。
※2020年3月21日、カクヨム様にて連載開始。
あらすじ
2020年。世界には776冊の『異本』と呼ばれる特別な本があった。それは、読む者に作用し、在る場所に異変をもたらし、世界を揺るがすほどのものさえ存在した。
その『異本』を全て集めることを目的とする男がいた。男はその蒐集の途中、一人の少女と出会う。少女が『異本』の一冊を持っていたからだ。
だが、突然の襲撃で少女の持つ『異本』は焼失してしまう。
男は集めるべき『異本』の消失に落胆するが、失われた『異本』は少女の中に遺っていると知る。
こうして男と少女は出会い、ともに旅をすることになった。
これは、世界中を旅して、『異本』を集め、誰かへ捧げる物語だ。

『希望の実』拾い食いから始まる逆転ダンジョン生活!(改訂版)
IXA
ファンタジー
凡そ三十年前、この世界は一変した。
世界各地に次々と現れた天を突く蒼の塔、それとほぼ同時期に発見されたのが、『ダンジョン』と呼ばれる奇妙な空間だ。
不気味で異質、しかしながらダンジョン内で手に入る資源は欲望を刺激し、ダンジョン内で戦い続ける『探索者』と呼ばれる職業すら生まれた。そしていつしか人類は拒否感を拭いきれずも、ダンジョンに依存する生活へ移行していく。
そんなある日、ちっぽけな少女が探索者協会の扉を叩いた。
諸事情により金欠な彼女が探索者となった時、世界の流れは大きく変わっていくこととなる……
人との出会い、無数に折り重なる悪意、そして隠された真実と絶望。
夢見る少女の戦いの果て、ちっぽけな彼女は一体何を選ぶ?
絶望に、立ち向かえ。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

月(ルナ)は笑う――幻想怪奇蒐集譚
浦出卓郎
ファンタジー
戦後――
人種根絶を目指した独裁政党スワスティカが崩壊、三つの国へと分かれた。
オルランド公国、ヒルデガルト共和国、カザック自治領。
ある者は敗戦で苦汁をなめ、ある者は戦勝気分で沸き立つ世間を、綺譚蒐集者《アンソロジスト》ルナ・ペルッツは、メイド兼従者兼馭者の吸血鬼ズデンカと時代遅れの馬車に乗って今日も征く。
綺譚――
面白い話、奇妙な話を彼女に提供した者は願いが一つ叶う、という噂があった。
カクヨム、なろうでも連載中!

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ロマン・エイジ
葉桜藍
ファンタジー
鉄と石炭、煤煙と蒸気が漂い、列強国が睨み合うユースティア大陸。
グラーセン王国の若者、クラウス・フォン・シャルンストはマールに留学していた。彼はある夜、不思議な少女に出会う。彼女はクラウスに、自分の夢に協力してほしいという。
彼女の夢。それはかつて大陸に存在していた、『クロイツ帝国』を復活させるというものだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















