2 / 65
序章 こうして僕は『殺』されかけました
第1話 『2年前』まで田舎のクソガキでした
しおりを挟む
時は聖王歴1888年、世紀末を迎えようとしている今日。
僕ことミナト=ルトラは2年前晴れて憧れの【守護契約士】になり、充実した日々を送っている。
守護契約士の仕事は、政府や市民からの依頼を受け、地域社会の治安や秩序を守ること。
専ら内容といえば、迷い猫の捜索から、危険な野生動物の対処。要人警護やら軍事教育まで幅広い。
僕は現在、【アナティシア連合王国】の【ボースワドゥム市】の守護契約士協会に配属されている。伝統来な煉瓦造りの建物が立ち並ぶ甘美な町だ。
「グディーラさん。こんな感じでいいですかね?」
「う~ん、少し右に傾いてない?」
本日は協会の支部長であるグディーラさんと一緒に、防犯を促す張り紙貼り。一番の下っ端に出来るのはこれくらいなもの。
最初から花のある護衛やらなんやらを任されるとは思っていなかったよ。勿論それは覚悟の上。でも、ほんのちょぉっとぐらいは期待していたけど……。
「こうですか?」
「そうそう! ありがとう。助かったわ」
振り返ると豊満な初夏の風が吹き抜け、グディーラさんの金髪の髪が靡いた。
目元は仮面で隠していて、いまいち表情が読みにくい。話によれば以前彼女も守護契約士だったらしく、怪我で前線を退いたのだという。
眉間あたりにその傷が残っているんだとか。
……それに本名、教えて貰ったことないんだよなぁ。捨てたとか言われて。
「いいえ、これも大事な仕事ですから」
「そうね。今は特にね」
最近は特に物騒ということもあって連日先輩三人は出払っている。
「二人ともご苦労様。はい、これ差し入れだよ」
「あ、ありがとうございます! もしかして焼きたてですか?」
なんと、張り紙を貼らせて貰ったパン屋の主人から焼きたてのパンを頂いてしまった。気遣いが胸に染みる。
「おう! みんなで食べてくれ!」
主人とは先日僕が迷子になった娘さんを家まで送り届けたことがあった。その縁で店先に張り紙を貼らせて貰っている。
「そんな悪いですよ、ご主人……」
申し訳なさそうにするグディーラさん。
「なーに、この前うちの娘の面倒見てくれただろ。そん時の、せめてもの感謝のつもりだよ。受けっとってくれ」
「ありがとうございます。じゃあ、有難く頂戴いたしますね」
不意に鐘の音がして、時計塔が【ボースワドゥム】の町に正午を知らせる。
「あぁ~お昼になっちゃいましたね。ランチにしましょう?」
「もうそんな時間? そっか……どうする? 一緒に食事する?」
グディーラさんは口元を綻ばせて、これは揶揄っているなぁ……。彼女のそんな蠱惑的な一面が正直苦手だ。
大人の女性に不敵な笑みで誘われたら、誰だってドキっとする。
自分で言うのもなんだけど僕みたいな健全な青少年なら尚更。だけど今日は残念ながら――先約がある。
「すいません。僕も予定が……」
「もしかしてあの子と? いいわねぇ~青春っていうのは」
「そんなんじゃないですよ。彼女とは友達です。でもそうです。はい。食事をする約束をしていまして……」
「ふ~ん、友達ね。いつかの大雨の日に初めて連れてきた時はびっくりしたけど。いつの間にかお昼に逢引するような関係になっているなんてね?」
「やめてくださいよ。まだそんなんじゃないですっ!」
「まだ、ね? そうだ……ついでというのもなんだけど、ミナトにお使いを頼みたいの。いいかしら?」
グディーラさんが手渡してきたのは数枚の硬貨。ざっくりと5千アウラある。
「【ルミナイタ通り】に新しく菓子店が出来たのを知っている? あそこに【ロガージュ】ってお菓子を一度でいいから食べてみたいの」
一番安いので構わないから買ってきてくれないかしら? と――。
別にそのくらいならいいけど。
彼女の言う菓子店とは1ヶ月ほど前に開店した《パティスリー・デ・アダス》という店だ。
開業当初から【ロガージュ】という丸太の形をしたケーキが連日列を成す程大人気。
ひと月たった今でこそ売切れになることはなくなったものの、毎日盛況で大評判。
「分かりました。でも5千アウラは多いですよ?」
中流層向けの品なら2、3千で手に入る。ただ、噂では何でも2、3万のものがあるとか。
評判を聞き付けた見栄っ張りな上流階級は、挙って後者の高級品を購入していくとか。
「お釣りはあげる。花でも贈ってあげたらどう?」
「やめてくださいって、そんなんじゃないですよ。もう……」
しつこく揶揄ってくるグディーラさんに正直煩わしく思いながら、その場を後にした。
10分ほど並ぶだけ買えたのは運が良かった。少し遅れたけど幸い2ホール獲得できたので、彼女も機嫌を直してくれるに違いない。
「あら? ミナトさん? 今朝ぶりですね」
待ち合わせの公園に向かう途中で一人の修道女、セイネさんと鉢合わせした。
真昼に会うなんて珍しい。今頃って、食事の準備で忙しい時間だよね?
「あ、セイネさん。今日はお出かけですか? 奇遇ですね? どうしたんですかその荷物」
セイネさんは腕に何冊も本を抱えていた。
修道服の袖からは手首から肘に掛けて生える【有羽種】特有の煌びやかな羽が見え隠れする。
色は頭巾の隙間から覗かせる髪と同じ、新緑に似た鮮やかな緑をしていた。
「えぇ、午後から新しく出来た初等学校で聖書の授業なんです」
なんだか楽しそう。セイネさん、子供好きだもんな。
「でもまだ読み書きが難しい子達もいるので、分かりやすいものをいくつか見繕ったんです。ミナトさんはお昼ですか?」
「はい。今から公園に向かうところでして」
僕ことミナト=ルトラは2年前晴れて憧れの【守護契約士】になり、充実した日々を送っている。
守護契約士の仕事は、政府や市民からの依頼を受け、地域社会の治安や秩序を守ること。
専ら内容といえば、迷い猫の捜索から、危険な野生動物の対処。要人警護やら軍事教育まで幅広い。
僕は現在、【アナティシア連合王国】の【ボースワドゥム市】の守護契約士協会に配属されている。伝統来な煉瓦造りの建物が立ち並ぶ甘美な町だ。
「グディーラさん。こんな感じでいいですかね?」
「う~ん、少し右に傾いてない?」
本日は協会の支部長であるグディーラさんと一緒に、防犯を促す張り紙貼り。一番の下っ端に出来るのはこれくらいなもの。
最初から花のある護衛やらなんやらを任されるとは思っていなかったよ。勿論それは覚悟の上。でも、ほんのちょぉっとぐらいは期待していたけど……。
「こうですか?」
「そうそう! ありがとう。助かったわ」
振り返ると豊満な初夏の風が吹き抜け、グディーラさんの金髪の髪が靡いた。
目元は仮面で隠していて、いまいち表情が読みにくい。話によれば以前彼女も守護契約士だったらしく、怪我で前線を退いたのだという。
眉間あたりにその傷が残っているんだとか。
……それに本名、教えて貰ったことないんだよなぁ。捨てたとか言われて。
「いいえ、これも大事な仕事ですから」
「そうね。今は特にね」
最近は特に物騒ということもあって連日先輩三人は出払っている。
「二人ともご苦労様。はい、これ差し入れだよ」
「あ、ありがとうございます! もしかして焼きたてですか?」
なんと、張り紙を貼らせて貰ったパン屋の主人から焼きたてのパンを頂いてしまった。気遣いが胸に染みる。
「おう! みんなで食べてくれ!」
主人とは先日僕が迷子になった娘さんを家まで送り届けたことがあった。その縁で店先に張り紙を貼らせて貰っている。
「そんな悪いですよ、ご主人……」
申し訳なさそうにするグディーラさん。
「なーに、この前うちの娘の面倒見てくれただろ。そん時の、せめてもの感謝のつもりだよ。受けっとってくれ」
「ありがとうございます。じゃあ、有難く頂戴いたしますね」
不意に鐘の音がして、時計塔が【ボースワドゥム】の町に正午を知らせる。
「あぁ~お昼になっちゃいましたね。ランチにしましょう?」
「もうそんな時間? そっか……どうする? 一緒に食事する?」
グディーラさんは口元を綻ばせて、これは揶揄っているなぁ……。彼女のそんな蠱惑的な一面が正直苦手だ。
大人の女性に不敵な笑みで誘われたら、誰だってドキっとする。
自分で言うのもなんだけど僕みたいな健全な青少年なら尚更。だけど今日は残念ながら――先約がある。
「すいません。僕も予定が……」
「もしかしてあの子と? いいわねぇ~青春っていうのは」
「そんなんじゃないですよ。彼女とは友達です。でもそうです。はい。食事をする約束をしていまして……」
「ふ~ん、友達ね。いつかの大雨の日に初めて連れてきた時はびっくりしたけど。いつの間にかお昼に逢引するような関係になっているなんてね?」
「やめてくださいよ。まだそんなんじゃないですっ!」
「まだ、ね? そうだ……ついでというのもなんだけど、ミナトにお使いを頼みたいの。いいかしら?」
グディーラさんが手渡してきたのは数枚の硬貨。ざっくりと5千アウラある。
「【ルミナイタ通り】に新しく菓子店が出来たのを知っている? あそこに【ロガージュ】ってお菓子を一度でいいから食べてみたいの」
一番安いので構わないから買ってきてくれないかしら? と――。
別にそのくらいならいいけど。
彼女の言う菓子店とは1ヶ月ほど前に開店した《パティスリー・デ・アダス》という店だ。
開業当初から【ロガージュ】という丸太の形をしたケーキが連日列を成す程大人気。
ひと月たった今でこそ売切れになることはなくなったものの、毎日盛況で大評判。
「分かりました。でも5千アウラは多いですよ?」
中流層向けの品なら2、3千で手に入る。ただ、噂では何でも2、3万のものがあるとか。
評判を聞き付けた見栄っ張りな上流階級は、挙って後者の高級品を購入していくとか。
「お釣りはあげる。花でも贈ってあげたらどう?」
「やめてくださいって、そんなんじゃないですよ。もう……」
しつこく揶揄ってくるグディーラさんに正直煩わしく思いながら、その場を後にした。
10分ほど並ぶだけ買えたのは運が良かった。少し遅れたけど幸い2ホール獲得できたので、彼女も機嫌を直してくれるに違いない。
「あら? ミナトさん? 今朝ぶりですね」
待ち合わせの公園に向かう途中で一人の修道女、セイネさんと鉢合わせした。
真昼に会うなんて珍しい。今頃って、食事の準備で忙しい時間だよね?
「あ、セイネさん。今日はお出かけですか? 奇遇ですね? どうしたんですかその荷物」
セイネさんは腕に何冊も本を抱えていた。
修道服の袖からは手首から肘に掛けて生える【有羽種】特有の煌びやかな羽が見え隠れする。
色は頭巾の隙間から覗かせる髪と同じ、新緑に似た鮮やかな緑をしていた。
「えぇ、午後から新しく出来た初等学校で聖書の授業なんです」
なんだか楽しそう。セイネさん、子供好きだもんな。
「でもまだ読み書きが難しい子達もいるので、分かりやすいものをいくつか見繕ったんです。ミナトさんはお昼ですか?」
「はい。今から公園に向かうところでして」
0
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

一般トレジャーハンターの俺が最強の魔王を仲間に入れたら世界が敵になったんだけど……どうしよ?
大好き丸
ファンタジー
天上魔界「イイルクオン」
世界は大きく分けて二つの勢力が存在する。
”人類”と”魔族”
生存圏を争って日夜争いを続けている。
しかしそんな中、戦争に背を向け、ただひたすらに宝を追い求める男がいた。
トレジャーハンターその名はラルフ。
夢とロマンを求め、日夜、洞窟や遺跡に潜る。
そこで出会った未知との遭遇はラルフの人生の大きな転換期となり世界が動く
欺瞞、裏切り、秩序の崩壊、
世界の均衡が崩れた時、終焉を迎える。
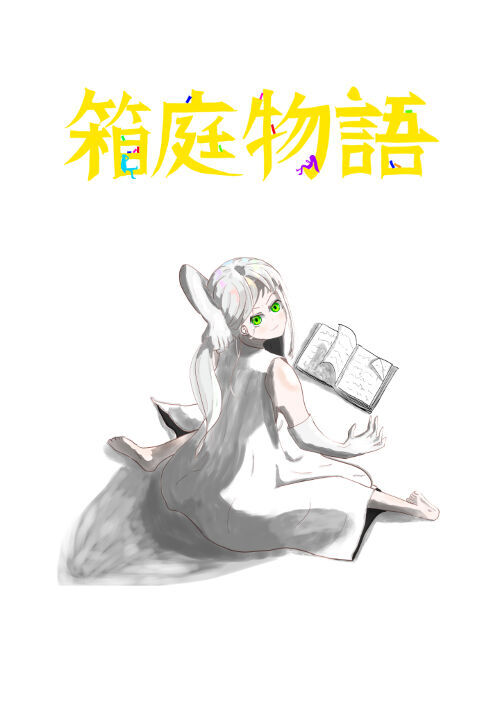
箱庭物語
晴羽照尊
ファンタジー
※本作は他の小説投稿サイト様でも公開しております。
※エンディングまでだいたいのストーリーは出来上がっておりますので、問題なく更新していけるはずです。予定では400話弱、150万文字程度で完結となります。(参考までに)
※この物語には実在の地名や人名、建造物などが登場しますが、一部現実にそぐわない場合がございます。それらは作者の創作であり、実在のそれらとは関わりありません。
※2020年3月21日、カクヨム様にて連載開始。
あらすじ
2020年。世界には776冊の『異本』と呼ばれる特別な本があった。それは、読む者に作用し、在る場所に異変をもたらし、世界を揺るがすほどのものさえ存在した。
その『異本』を全て集めることを目的とする男がいた。男はその蒐集の途中、一人の少女と出会う。少女が『異本』の一冊を持っていたからだ。
だが、突然の襲撃で少女の持つ『異本』は焼失してしまう。
男は集めるべき『異本』の消失に落胆するが、失われた『異本』は少女の中に遺っていると知る。
こうして男と少女は出会い、ともに旅をすることになった。
これは、世界中を旅して、『異本』を集め、誰かへ捧げる物語だ。

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

双子獣人と不思議な魔導書
夜色シアン
ファンタジー
〈注:現在は小説家になろう、マグネット!にて連載中です〉
著:狼狐
表紙:暗黒魔界大帝国王リク@UNKnown_P
ユグドラシルーーそこは貴重な魔導書が存在する大陸。しかし貴重が故に謎が多い魔導書の使用、そして一部の魔法が一部地域で禁忌とされている。
また人々から恐れ、疎まれ、憎まれと人からは嫌われている種族、人狼ーーその人狼として生まれ育ったハティとスコルの双子は、他界した母親が所持していた魔導書『零の魔導書』を完成させるため、人狼と人の仲を和解すべく、旅立つのだがーー
「ハティ〜ハティ養分が不足してるよ〜」
「私の養分ってなんですか!スコルさん!?」
登場人物全員が一癖二癖ある双子達の旅路が、今始まる!
ーー第二幕「牙を穿て」開幕!ーー

異世界行ったら人外と友達になった
小梅カリカリ
ファンタジー
気が付いたら異世界に来ていた瑠璃
優しい骸骨夫婦や頼りになるエルフ
彼女の人柄に惹かれ集まる素敵な仲間達
竜に頭丸呑みされても、誘拐されそうになっても、異世界から帰れなくても
立ち直り前に進む瑠璃
そしてこの世界で暮らしていく事を決意する

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















