お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

転生貴族のハーレムチート生活 【400万ポイント突破】
ゼクト
ファンタジー
ファンタジー大賞に応募中です。 ぜひ投票お願いします
ある日、神崎優斗は川でおぼれているおばあちゃんを助けようとして川の中にある岩にあたりおばあちゃんは助けられたが死んでしまったそれをたまたま地球を見ていた創造神が転生をさせてくれることになりいろいろな神の加護をもらい今貴族の子として転生するのであった
【不定期になると思います まだはじめたばかりなのでアドバイスなどどんどんコメントしてください。ノベルバ、小説家になろう、カクヨムにも同じ作品を投稿しているので、気が向いたら、そちらもお願いします。
累計400万ポイント突破しました。
応援ありがとうございます。】
ツイッター始めました→ゼクト @VEUu26CiB0OpjtL

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2月26日から29日現在まで4日間、アルファポリスのファンタジー部門1位達成!感謝です!
小説家になろうでも10位獲得しました!
そして、カクヨムでもランクイン中です!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
スキルを強奪する為に異世界召喚を実行した欲望まみれの権力者から逃げるおっさん。
いつものように電車通勤をしていたわけだが、気が付けばまさかの異世界召喚に巻き込まれる。
欲望者から逃げ切って反撃をするか、隠れて地味に暮らすか・・・・
●●●●●●●●●●●●●●●
小説家になろうで執筆中の作品です。
アルファポリス、、カクヨムでも公開中です。
現在見直し作業中です。
変換ミス、打ちミス等が多い作品です。申し訳ありません。
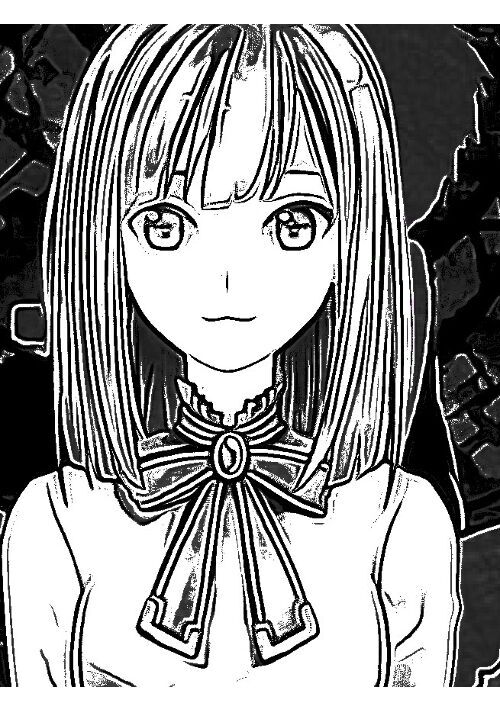

鑑定能力で恩を返す
KBT
ファンタジー
どこにでもいる普通のサラリーマンの蔵田悟。
彼ははある日、上司の悪態を吐きながら深酒をし、目が覚めると見知らぬ世界にいた。
そこは剣と魔法、人間、獣人、亜人、魔物が跋扈する異世界フォートルードだった。
この世界には稀に異世界から《迷い人》が転移しており、悟もその1人だった。
帰る方法もなく、途方に暮れていた悟だったが、通りすがりの商人ロンメルに命を救われる。
そして稀少な能力である鑑定能力が自身にある事がわかり、ブロディア王国の公都ハメルンの裏通りにあるロンメルの店で働かせてもらう事になった。
そして、ロンメルから店の番頭を任された悟は《サト》と名前を変え、命の恩人であるロンメルへの恩返しのため、商店を大きくしようと鑑定能力を駆使して、海千山千の商人達や荒くれ者の冒険者達を相手に日夜奮闘するのだった。

スライム10,000体討伐から始まるハーレム生活
昼寝部
ファンタジー
この世界は12歳になったら神からスキルを授かることができ、俺も12歳になった時にスキルを授かった。
しかし、俺のスキルは【@&¥#%】と正しく表記されず、役に立たないスキルということが判明した。
そんな中、両親を亡くした俺は妹に不自由のない生活を送ってもらうため、冒険者として活動を始める。
しかし、【@&¥#%】というスキルでは強いモンスターを討伐することができず、3年間冒険者をしてもスライムしか倒せなかった。
そんなある日、俺がスライムを10,000体討伐した瞬間、スキル【@&¥#%】がチートスキルへと変化して……。
これは、ある日突然、最強の冒険者となった主人公が、今まで『スライムしか倒せないゴミ』とバカにしてきた奴らに“ざまぁ”し、美少女たちと幸せな日々を過ごす物語。

パーティーを追放された装備製作者、実は世界最強 〜ソロになったので、自分で作った最強装備で無双する〜
Tamaki Yoshigae
ファンタジー
ロイルはSランク冒険者パーティーの一員で、付与術師としてメンバーの武器の調整を担当していた。
だがある日、彼は「お前の付与などなくても俺たちは最強だ」と言われ、パーティーをクビになる。
仕方なく彼は、辺境で人生を再スタートすることにした。
素人が扱っても規格外の威力が出る武器を作れる彼は、今まで戦闘経験ゼロながらも瞬く間に成り上がる。
一方、自分たちの実力を過信するあまりチートな付与術師を失ったパーティーは、かつての猛威を振るえなくなっていた。

ハズレスキル【収納】のせいで実家を追放されたが、全てを収納できるチートスキルでした。今更土下座してももう遅い
平山和人
ファンタジー
侯爵家の三男であるカイトが成人の儀で授けられたスキルは【収納】であった。アイテムボックスの下位互換だと、家族からも見放され、カイトは家を追放されることになった。
ダンジョンをさまよい、魔物に襲われ死ぬと思われた時、カイトは【収納】の真の力に気づく。【収納】は魔物や魔法を吸収し、さらには異世界の飲食物を取り寄せることができるチートスキルであったのだ。
かくして自由になったカイトは世界中を自由気ままに旅することになった。一方、カイトの家族は彼の活躍を耳にしてカイトに戻ってくるように土下座してくるがもう遅い。

悪役貴族の四男に転生した俺は、怠惰で自由な生活がしたいので、自由気ままな冒険者生活(スローライフ)を始めたかった。
SOU 5月17日10作同時連載開始❗❗
ファンタジー
俺は何もしてないのに兄達のせいで悪役貴族扱いされているんだが……
アーノルドは名門貴族クローリー家の四男に転生した。家の掲げる独立独行の家訓のため、剣技に魔術果ては鍛冶師の技術を身に着けた。
そして15歳となった現在。アーノルドは、魔剣士を育成する教育機関に入学するのだが、親戚や上の兄達のせいで悪役扱いをされ、付いた渾名は【悪役公子】。
実家ではやりたくもない【付与魔術】をやらされ、学園に通っていても心の無い言葉を投げかけられる日々に嫌気がさした俺は、自由を求めて冒険者になる事にした。
剣術ではなく刀を打ち刀を使う彼は、憧れの自由と、美味いメシとスローライフを求めて、時に戦い。時にメシを食らい、時に剣を打つ。
アーノルドの第二の人生が幕を開ける。しかし、同級生で仲の悪いメイザース家の娘ミナに学園での態度が演技だと知られてしまい。アーノルドの理想の生活は、ハチャメチャなものになって行く。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















