28 / 133
第4章
24 クエマドロからのお誘い
しおりを挟む
心安い一日はあっと言う間に過ぎ去り、朝が来た。
「そうだ、今日なんだけど――」
簡単な朝食を終え、清涼飲料のペットボトルを開けながらヴィネが言った。
「デンたん、午後からちょこっと付き合ってもらえるかな」
「はい。何でしょう」
私が問うと彼女は続けた。
「クエマドロって覚えてるよね。デンたんのこと気に入っちゃったみたいでさ。何かもう一度会いたいんだって。3時頃って言ってたから、多分お茶か夕ご飯のお誘いかも。て言っても、デンたんは一応処刑人だし、怪我してるんだから無理そうなら断ってくれてもいいんだけど」
ヴィネは上目遣いに私を見た。
「明日にはりょおちんも帰ってくるわけだし、お出迎えの準備もしなくちゃ、かな?」
「それはないです」
私は即答した。彼女はクスリと笑う。
「そっか。うん。ま、ヴィネもついてくから大丈夫だね」
私は軽くうなずいた。クエマドロは気安い雰囲気の持ち主だったし、以前会った時に「嫌なことは強制したりしない」と言っていた。拒否権を行使できる人間が相手なら、たとえ殺人現場に居合わせることになったとしても行動を共にする自分を少しは許せるような気がした。
ヴィネの部屋でお菓子を摘みながら二人でゲームに興ずるうち、あっと言う間に午後になった。不摂生きわまりないがやたらと楽しく、危うく時間を忘れるところだった。生まれて初めて10代らしいことをした気がする。
気付けば待ち合わせ時刻が迫っており、大急ぎで部屋を出る。ヴィネは「少し遅れそうって連絡しといたから大丈夫だよ」と言い、マイペースに車を走らせるが、助手席の私は落ち着かなかった。
到着したのは大型ディスカウントストアの駐車場だった。大幅に遅刻したこともあり、気が重い。車外に出て周りを見渡すが、それらしい姿は見えない。
「確かここだったんだけど……マドロン、先にお店入ってるかも。連絡入れるね」
ヴィネが携帯端末を繰りながら言った。
少しして、
「待ってたよー、二人とも」
背後から声が聞こえた。振り向けば、見覚えのある男がこちらに歩いて来ている。整った顔、無造作に見えて計画的に作り込まれた髪、都会的なジャケット姿の彼は紛れもなくクエマドロだ。
「よく来てくれたね、温泉ちゃん。今日はよろしく。あれっ、眼鏡変えた? いいじゃん」
私は「どうも」と頭を下げ、ヴィネは「もしも~し、ヴィネもいるんですけど」と軽口を叩いた。
クエマドロが失くしたと言っていた携帯端末を手にしていたので、「見つかったんですね」と訊いてみると、彼はおかげさまで落とし物センターに届いていた、騒がせて悪かったと労ってくれた。
とすると、あの像の中で鳴っていた音はまったく別の何かだったのだろうか。もしかすると周牢が仕込んだ罠だったかも知れない。発信機付きピアスの件からして十分あり得る。彼は単細胞に見えてなかなか厄介な手合いのようだ。
「そんなことより、今日は一体何の用なの? マドロン」
割り込むように問うヴィネに、クエマドロは「ああ、そうそう」と呼び出しの理由を明かした。
「温泉ちゃん、ヴィネちゃん、二人にはこれからおれの軽作業と資材集めのアシスタントをお願いします」
「え~?」
ヴィネが不満げな声を上げた。
「ヴィネはともかく、なんでわざわざデンたんに依頼するの? マドロンの“仕事”に必要な材料ってけっこう運ぶのに力要るものばっかじゃん。いつも本部の専門スタッフが準備する手はずになってるのに、今日だけ呼び出すなんて意味わかんないし。それもこんな手負いのか弱いオンナノコに重労働ムチャブリとか、ナイわ~」
「ちょ、違うって。て言うか何、温泉ちゃんどっか怪我してるの?」
「そうだよ。肋骨折れちゃって大変だったんだから」
それを聞くや、クエマドロは表情を曇らせる。
「え……どういうこと?」
私が、夜会の日に会場を離れようとしたら出入り口付近でちょっとした事故に巻き込まれたこと、骨折はしたが軽傷なので心配無用であることを伝えたところ、ようやく彼の顔に安堵が浮かんだ。
「そうだったんだ。温泉ちゃん途中でいなくなっちゃったし、メッセージ送っても既読付かないから嫌われたかと思ってたんだけど、そんな大変なことになってたんだね。凌遅くんは何やってたの?」
「一応、そばにはいたんですけど……」
私が事のあらましを説明すると、クエマドロは眉根を寄せて嘆息した。
「あー、おれが一緒だったら絶対怪我なんかさせないのになあ……やっぱり“違う星のヒト”に温泉ちゃんの教育係はハードル高いんだよ。ねえ、温泉ちゃん、本気でおれに乗り換える気ない?」
「はいはい、ここぞとばかりに売り込まないの!」
困惑する私を見兼ねて、ヴィネが助け舟を出してくれた。
「デンたん、ほんとは今日だって湿布貼って安静にしてなきゃいけないんだよ。一緒に怪我して入院してたりょおちんも明日には帰ってくるし、あんまり長い時間拘束させられないからね」
するとクエマドロは心外そうな顔で切り返した。
「ヴィネちゃん、そういうことは事前に教えといてよ。知ってたら呼び出したりしなかったのに……」
「あれぇ? そんなこと言って、カワイイ後輩に会いたいばかりに適当な用事をでっち上げたんじゃないのかな。それってセクハラでパワハラだよ?」
なおも悪戯っぽく非難するヴィネに苦笑しながらクエマドロは続けた。
「温泉ちゃんがカワイイのは事実だし、用事があるのも本当だから」
そう言うと彼は私の側へ寄り、窺うように目線を合わせた。
「無理させちゃってごめんね。でも力仕事とかじゃないから安心して。先日おれの窯、新しくしたのね。そしたら予想以上に地味なんだわ。だから、ここで何か飾りになりそうなもの選んで、デコるの手伝ってくれないかなあと思って」
何だ、その程度のことなら造作もない。私は胸を撫で下ろし、快諾した。
「よかったね、マドロン。デンたんが優しくて」
「ほんと温泉ちゃん天使だわ。ヴィネちゃんとは大違い」
冗談を言い合う彼らに挟まれる形で、私は建物へと歩を進める。
店内は外から見るよりずっと広かった。いろいろなテイストのありとあらゆる品が並んでいる。
考えてみれば、一口に飾りと言われても、窯そのものがどんな容相か知らないのだから何とも困る。第一、私には芸術の素養がないので、限りなく地味且つ無難なチョイスになるのは間違いない。
とりあえず店内を見て回り、造花やウォールステッカー、マスキングテープなど飾りになりそうなものをいくつか見繕った。ヴィネもカラースプレーを次々とかごへ入れていく。
彼女に引っ張られる形で雑貨コーナーなども覗いてしまい、予想以上に時間を食った。
その際、ヴィネが猫の耳を象ったリングを二つ購入し、片方を私にくれた。
「えへへ。カワイイから買っちゃった。一個デンたんにあげる! ヴィネとおそろだよ」
恐縮したが、実は店内を回っていた時に見かけて惹かれていたものだったので、素直にお礼を言って受け取った。
ヴィネにはいつも気遣ってもらってばかりだ。そのうち何らかの形でお返しをしよう。
彼女が「せっかくだし、リング一緒に付けない?」と言うので、付き合うことにした。
ヴィネは大喜びで私の手を取り、クエマドロの元へ駆け寄ると「マドロン、見て見て! カワイイでしょ~」と盛大にアピールした。
「お! なにそれ。小型のメリケンサック?」
シュールながら言い得て妙なたとえをするクエマドロに、ヴィネは「は? 違うし! どう見てもニャンコじゃん。てゆーか、どういう感性してんのー……」とキツめの突っ込みを忘れなかった。
「え? 違うの? 戦闘力上げてくれそうなフォルムだよね」
クエマドロがどこまで本気かわからない見解を示すと、ヴィネは心底呆れた様子で嘆息する。
「も~、マドロンにファンシーグッズの感想求めたヴィネがバカだった……デンたん、この人のコメントはガン無視の方向で! 普通の人にはニャンコのお耳にしか見えないから大丈夫だよっ!」
「は、はぁ……」
正直な話、これ以降、可愛らしい猫耳リングがメリケンサックにしか見えなくなってしまったのだが、ヴィネには絶対に悟られまいと心に誓った。
「いいねえ。これだけあれば十分じゃないかな」
一通り集まったところでクエマドロが満足げにうなずいた。彼は両手に何かの袋を提げている。材料の一部だろうか。
私の視線に気付いたのか、クエマドロはひょいと袋を掲げて言った。
「ああ、これ? 後で新しい窯の完成を祝して一杯やろうと思ってさ。温泉ちゃんにジュースとお菓子も買ってあるから、一緒に楽しもうね」
「ねえねえ、ヴィネには?」
不服そうな随伴者の口出しに、クエマドロは「忘れてないって」と言って小さな紙袋を彼女に渡した。ヴィネの興奮具合が尋常ではないので、おそらくそのチョイスは正解なのだろう。
「あれ、もうこんな時間だ。荷物積んだらご飯行きますか。お店予約してあるんだ」
クエマドロが言った。すると店名を聞いたヴィネが、すぐさま携帯端末で検索をかけた。
「この近くじゃん。評判の創作料理店だって。楽しみ!」
「期待してくれていいよ。おれの行きつけの創作フレンチなんだけど、すごく美味しいから」
久し振りの“娑婆の飯”に期待が高まる。
父と二人になってから外食などほとんどした記憶がない。母が健在だった頃は、祖母の介護の合間に、誕生日だクリスマスだ、テストで満点を取ったお祝いだと言って事あるごとに連れ出してくれたものだが、そちらの方が奇特なことだったのかも知れない。
私達はクエマドロの車に同乗させてもらい、目的地へ向かうことになった。誘導された先に停まっていたのは、車に疎い私でも知っている高級自動車メーカーのSUVモデルだった。
夜会の時、クエマドロはフリーランサーだと話していたが、一体どんな仕事をすればこの年でこんな車を持てるのだろう。そう言えば彼の身に着けている品はいずれも富裕層向けの海外ブランドだ。LR×Dの恐ろしく高額な報酬が一助となっているのは想像に難くない。
それにしてもあまりに通常からかけ離れたスペックだ。観察しているだけで感覚がおかしくなってくる。
動揺と期待で軽く惑乱しながら、5分ほどでお目当ての場所へ到着した。件の店は入り口からすでに洗練された佇まいで、私のような庶民はこんなことでもなければ永遠に訪れることはないであろう場所だった。
見るからに上等な内装や客層に気圧され、緊張しながら歩を進める。
席へ通されてからも座り心地の悪さを感じ、連れの二人に合わせてどぎまぎと料理を選んだ。
「温泉ちゃんは仔牛の煮込みかあ。肉、好きなんだっけ?」
クエマドロが問う。肯定すると、彼は「やっぱ肉好き女子ってカワイイコ多いんだよねえ」とソースの怪しい見解を挟んだ。
「えー、何でも食べる子はもっとカワイイんだよ。例えばヴィネみたいな」
「温泉ちゃん、後でおれのランプ肉も分けてあげるね」
ヴィネのコメントは当然のごとくスルーされる。
「オッサン、無視すんな」
「こらこら、ヴィネちゃん。おれはまだギリ“お兄サン”の領域だから」
「アラサーは立派なオッサンでしょ」
「ヤメロ、小娘。それ以上言ったらデザート没収だからな」
「ちょっとマドロン、冗談通じないのは頭固くなってきた証拠だよ?」
同伴者達がじゃれ合う。そのうち私を巻き込んでの歓談が続く。
彼らは仇敵の一味だというのに私は不覚にも愉快になっていた。
少しして皿が運ばれてきた。創作料理は外れるときついのでやや気がかりだったが、新鮮な魚介類と野菜の食べ合わせも仔牛の煮込みも、どれもこれもが信じられないほどおいしかった。
しかし料理を口に運ぶ度、「ああ、凌遅はこれを食べられないのだな」などとついくだらないことに意識が向いてしまうのには閉口した。彼の偏食は単なる好みの問題だ。気の毒でもなければ気にかける意味すらない。
あの男に監視されずに済む貴重な自由時間だというのに、わざわざ思い出すなんて馬鹿げている。もうじき嫌でも一対一で向き合わねばならないのだから。
私はポケットの中に忍ばせていた筆記具に触れ、そっと決意を新たにした。
「そうだ、今日なんだけど――」
簡単な朝食を終え、清涼飲料のペットボトルを開けながらヴィネが言った。
「デンたん、午後からちょこっと付き合ってもらえるかな」
「はい。何でしょう」
私が問うと彼女は続けた。
「クエマドロって覚えてるよね。デンたんのこと気に入っちゃったみたいでさ。何かもう一度会いたいんだって。3時頃って言ってたから、多分お茶か夕ご飯のお誘いかも。て言っても、デンたんは一応処刑人だし、怪我してるんだから無理そうなら断ってくれてもいいんだけど」
ヴィネは上目遣いに私を見た。
「明日にはりょおちんも帰ってくるわけだし、お出迎えの準備もしなくちゃ、かな?」
「それはないです」
私は即答した。彼女はクスリと笑う。
「そっか。うん。ま、ヴィネもついてくから大丈夫だね」
私は軽くうなずいた。クエマドロは気安い雰囲気の持ち主だったし、以前会った時に「嫌なことは強制したりしない」と言っていた。拒否権を行使できる人間が相手なら、たとえ殺人現場に居合わせることになったとしても行動を共にする自分を少しは許せるような気がした。
ヴィネの部屋でお菓子を摘みながら二人でゲームに興ずるうち、あっと言う間に午後になった。不摂生きわまりないがやたらと楽しく、危うく時間を忘れるところだった。生まれて初めて10代らしいことをした気がする。
気付けば待ち合わせ時刻が迫っており、大急ぎで部屋を出る。ヴィネは「少し遅れそうって連絡しといたから大丈夫だよ」と言い、マイペースに車を走らせるが、助手席の私は落ち着かなかった。
到着したのは大型ディスカウントストアの駐車場だった。大幅に遅刻したこともあり、気が重い。車外に出て周りを見渡すが、それらしい姿は見えない。
「確かここだったんだけど……マドロン、先にお店入ってるかも。連絡入れるね」
ヴィネが携帯端末を繰りながら言った。
少しして、
「待ってたよー、二人とも」
背後から声が聞こえた。振り向けば、見覚えのある男がこちらに歩いて来ている。整った顔、無造作に見えて計画的に作り込まれた髪、都会的なジャケット姿の彼は紛れもなくクエマドロだ。
「よく来てくれたね、温泉ちゃん。今日はよろしく。あれっ、眼鏡変えた? いいじゃん」
私は「どうも」と頭を下げ、ヴィネは「もしも~し、ヴィネもいるんですけど」と軽口を叩いた。
クエマドロが失くしたと言っていた携帯端末を手にしていたので、「見つかったんですね」と訊いてみると、彼はおかげさまで落とし物センターに届いていた、騒がせて悪かったと労ってくれた。
とすると、あの像の中で鳴っていた音はまったく別の何かだったのだろうか。もしかすると周牢が仕込んだ罠だったかも知れない。発信機付きピアスの件からして十分あり得る。彼は単細胞に見えてなかなか厄介な手合いのようだ。
「そんなことより、今日は一体何の用なの? マドロン」
割り込むように問うヴィネに、クエマドロは「ああ、そうそう」と呼び出しの理由を明かした。
「温泉ちゃん、ヴィネちゃん、二人にはこれからおれの軽作業と資材集めのアシスタントをお願いします」
「え~?」
ヴィネが不満げな声を上げた。
「ヴィネはともかく、なんでわざわざデンたんに依頼するの? マドロンの“仕事”に必要な材料ってけっこう運ぶのに力要るものばっかじゃん。いつも本部の専門スタッフが準備する手はずになってるのに、今日だけ呼び出すなんて意味わかんないし。それもこんな手負いのか弱いオンナノコに重労働ムチャブリとか、ナイわ~」
「ちょ、違うって。て言うか何、温泉ちゃんどっか怪我してるの?」
「そうだよ。肋骨折れちゃって大変だったんだから」
それを聞くや、クエマドロは表情を曇らせる。
「え……どういうこと?」
私が、夜会の日に会場を離れようとしたら出入り口付近でちょっとした事故に巻き込まれたこと、骨折はしたが軽傷なので心配無用であることを伝えたところ、ようやく彼の顔に安堵が浮かんだ。
「そうだったんだ。温泉ちゃん途中でいなくなっちゃったし、メッセージ送っても既読付かないから嫌われたかと思ってたんだけど、そんな大変なことになってたんだね。凌遅くんは何やってたの?」
「一応、そばにはいたんですけど……」
私が事のあらましを説明すると、クエマドロは眉根を寄せて嘆息した。
「あー、おれが一緒だったら絶対怪我なんかさせないのになあ……やっぱり“違う星のヒト”に温泉ちゃんの教育係はハードル高いんだよ。ねえ、温泉ちゃん、本気でおれに乗り換える気ない?」
「はいはい、ここぞとばかりに売り込まないの!」
困惑する私を見兼ねて、ヴィネが助け舟を出してくれた。
「デンたん、ほんとは今日だって湿布貼って安静にしてなきゃいけないんだよ。一緒に怪我して入院してたりょおちんも明日には帰ってくるし、あんまり長い時間拘束させられないからね」
するとクエマドロは心外そうな顔で切り返した。
「ヴィネちゃん、そういうことは事前に教えといてよ。知ってたら呼び出したりしなかったのに……」
「あれぇ? そんなこと言って、カワイイ後輩に会いたいばかりに適当な用事をでっち上げたんじゃないのかな。それってセクハラでパワハラだよ?」
なおも悪戯っぽく非難するヴィネに苦笑しながらクエマドロは続けた。
「温泉ちゃんがカワイイのは事実だし、用事があるのも本当だから」
そう言うと彼は私の側へ寄り、窺うように目線を合わせた。
「無理させちゃってごめんね。でも力仕事とかじゃないから安心して。先日おれの窯、新しくしたのね。そしたら予想以上に地味なんだわ。だから、ここで何か飾りになりそうなもの選んで、デコるの手伝ってくれないかなあと思って」
何だ、その程度のことなら造作もない。私は胸を撫で下ろし、快諾した。
「よかったね、マドロン。デンたんが優しくて」
「ほんと温泉ちゃん天使だわ。ヴィネちゃんとは大違い」
冗談を言い合う彼らに挟まれる形で、私は建物へと歩を進める。
店内は外から見るよりずっと広かった。いろいろなテイストのありとあらゆる品が並んでいる。
考えてみれば、一口に飾りと言われても、窯そのものがどんな容相か知らないのだから何とも困る。第一、私には芸術の素養がないので、限りなく地味且つ無難なチョイスになるのは間違いない。
とりあえず店内を見て回り、造花やウォールステッカー、マスキングテープなど飾りになりそうなものをいくつか見繕った。ヴィネもカラースプレーを次々とかごへ入れていく。
彼女に引っ張られる形で雑貨コーナーなども覗いてしまい、予想以上に時間を食った。
その際、ヴィネが猫の耳を象ったリングを二つ購入し、片方を私にくれた。
「えへへ。カワイイから買っちゃった。一個デンたんにあげる! ヴィネとおそろだよ」
恐縮したが、実は店内を回っていた時に見かけて惹かれていたものだったので、素直にお礼を言って受け取った。
ヴィネにはいつも気遣ってもらってばかりだ。そのうち何らかの形でお返しをしよう。
彼女が「せっかくだし、リング一緒に付けない?」と言うので、付き合うことにした。
ヴィネは大喜びで私の手を取り、クエマドロの元へ駆け寄ると「マドロン、見て見て! カワイイでしょ~」と盛大にアピールした。
「お! なにそれ。小型のメリケンサック?」
シュールながら言い得て妙なたとえをするクエマドロに、ヴィネは「は? 違うし! どう見てもニャンコじゃん。てゆーか、どういう感性してんのー……」とキツめの突っ込みを忘れなかった。
「え? 違うの? 戦闘力上げてくれそうなフォルムだよね」
クエマドロがどこまで本気かわからない見解を示すと、ヴィネは心底呆れた様子で嘆息する。
「も~、マドロンにファンシーグッズの感想求めたヴィネがバカだった……デンたん、この人のコメントはガン無視の方向で! 普通の人にはニャンコのお耳にしか見えないから大丈夫だよっ!」
「は、はぁ……」
正直な話、これ以降、可愛らしい猫耳リングがメリケンサックにしか見えなくなってしまったのだが、ヴィネには絶対に悟られまいと心に誓った。
「いいねえ。これだけあれば十分じゃないかな」
一通り集まったところでクエマドロが満足げにうなずいた。彼は両手に何かの袋を提げている。材料の一部だろうか。
私の視線に気付いたのか、クエマドロはひょいと袋を掲げて言った。
「ああ、これ? 後で新しい窯の完成を祝して一杯やろうと思ってさ。温泉ちゃんにジュースとお菓子も買ってあるから、一緒に楽しもうね」
「ねえねえ、ヴィネには?」
不服そうな随伴者の口出しに、クエマドロは「忘れてないって」と言って小さな紙袋を彼女に渡した。ヴィネの興奮具合が尋常ではないので、おそらくそのチョイスは正解なのだろう。
「あれ、もうこんな時間だ。荷物積んだらご飯行きますか。お店予約してあるんだ」
クエマドロが言った。すると店名を聞いたヴィネが、すぐさま携帯端末で検索をかけた。
「この近くじゃん。評判の創作料理店だって。楽しみ!」
「期待してくれていいよ。おれの行きつけの創作フレンチなんだけど、すごく美味しいから」
久し振りの“娑婆の飯”に期待が高まる。
父と二人になってから外食などほとんどした記憶がない。母が健在だった頃は、祖母の介護の合間に、誕生日だクリスマスだ、テストで満点を取ったお祝いだと言って事あるごとに連れ出してくれたものだが、そちらの方が奇特なことだったのかも知れない。
私達はクエマドロの車に同乗させてもらい、目的地へ向かうことになった。誘導された先に停まっていたのは、車に疎い私でも知っている高級自動車メーカーのSUVモデルだった。
夜会の時、クエマドロはフリーランサーだと話していたが、一体どんな仕事をすればこの年でこんな車を持てるのだろう。そう言えば彼の身に着けている品はいずれも富裕層向けの海外ブランドだ。LR×Dの恐ろしく高額な報酬が一助となっているのは想像に難くない。
それにしてもあまりに通常からかけ離れたスペックだ。観察しているだけで感覚がおかしくなってくる。
動揺と期待で軽く惑乱しながら、5分ほどでお目当ての場所へ到着した。件の店は入り口からすでに洗練された佇まいで、私のような庶民はこんなことでもなければ永遠に訪れることはないであろう場所だった。
見るからに上等な内装や客層に気圧され、緊張しながら歩を進める。
席へ通されてからも座り心地の悪さを感じ、連れの二人に合わせてどぎまぎと料理を選んだ。
「温泉ちゃんは仔牛の煮込みかあ。肉、好きなんだっけ?」
クエマドロが問う。肯定すると、彼は「やっぱ肉好き女子ってカワイイコ多いんだよねえ」とソースの怪しい見解を挟んだ。
「えー、何でも食べる子はもっとカワイイんだよ。例えばヴィネみたいな」
「温泉ちゃん、後でおれのランプ肉も分けてあげるね」
ヴィネのコメントは当然のごとくスルーされる。
「オッサン、無視すんな」
「こらこら、ヴィネちゃん。おれはまだギリ“お兄サン”の領域だから」
「アラサーは立派なオッサンでしょ」
「ヤメロ、小娘。それ以上言ったらデザート没収だからな」
「ちょっとマドロン、冗談通じないのは頭固くなってきた証拠だよ?」
同伴者達がじゃれ合う。そのうち私を巻き込んでの歓談が続く。
彼らは仇敵の一味だというのに私は不覚にも愉快になっていた。
少しして皿が運ばれてきた。創作料理は外れるときついのでやや気がかりだったが、新鮮な魚介類と野菜の食べ合わせも仔牛の煮込みも、どれもこれもが信じられないほどおいしかった。
しかし料理を口に運ぶ度、「ああ、凌遅はこれを食べられないのだな」などとついくだらないことに意識が向いてしまうのには閉口した。彼の偏食は単なる好みの問題だ。気の毒でもなければ気にかける意味すらない。
あの男に監視されずに済む貴重な自由時間だというのに、わざわざ思い出すなんて馬鹿げている。もうじき嫌でも一対一で向き合わねばならないのだから。
私はポケットの中に忍ばせていた筆記具に触れ、そっと決意を新たにした。
2
お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子
ちひろ
恋愛
マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子の話。
Fantiaでは他にもえっちなお話を書いてます。よかったら遊びに来てね。

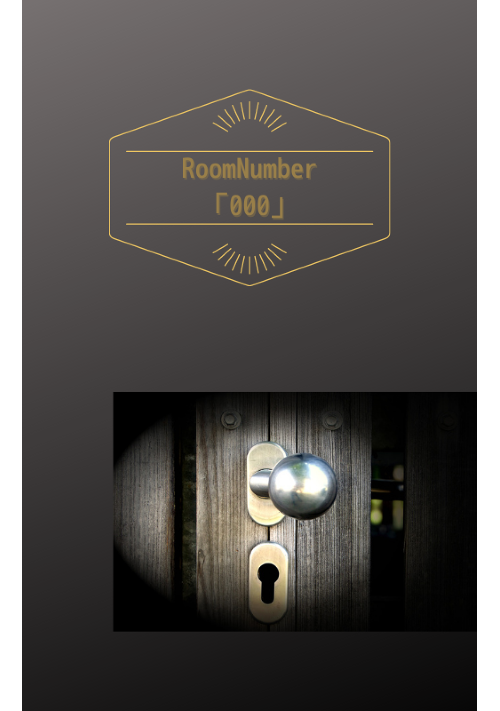
RoomNunmber「000」
誠奈
ミステリー
ある日突然届いた一通のメール。
そこには、報酬を与える代わりに、ある人物を誘拐するよう書かれていて……
丁度金に困っていた翔真は、訝しみつつも依頼を受け入れ、幼馴染の智樹を誘い、実行に移す……が、そこである事件に巻き込まれてしまう。
二人は密室となった部屋から出ることは出来るのだろうか?
※この作品は、以前別サイトにて公開していた物を、作者名及び、登場人物の名称等加筆修正を加えた上で公開しております。
※BL要素かなり薄いですが、匂わせ程度にはありますのでご注意を。


隣の席の女の子がエッチだったのでおっぱい揉んでみたら発情されました
ねんごろ
恋愛
隣の女の子がエッチすぎて、思わず授業中に胸を揉んでしまったら……
という、とんでもないお話を書きました。
ぜひ読んでください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















