お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

女嫌いな騎士団長が味わう、苦くて甘い恋の上書き
待鳥園子
恋愛
「では、言い出したお前が犠牲になれ」
「嫌ですぅ!」
惚れ薬の効果上書きで、女嫌いな騎士団長が一時的に好きになる対象になる事になったローラ。
薬の効果が切れるまで一ヶ月だし、すぐだろうと思っていたけれど、久しぶりに会ったルドルフ団長の様子がどうやらおかしいようで!?
※来栖もよりーぬ先生に「30ぐらいの女性苦手なヒーロー」と誕生日プレゼントリクエストされたので書きました。

恋とキスは背伸びして
葉月 まい
恋愛
結城 美怜(24歳)…身長160㎝、平社員
成瀬 隼斗(33歳)…身長182㎝、本部長
年齢差 9歳
身長差 22㎝
役職 雲泥の差
この違い、恋愛には大きな壁?
そして同期の卓の存在
異性の親友は成立する?
数々の壁を乗り越え、結ばれるまでの
二人の恋の物語

身代わり婚~暴君と呼ばれる辺境伯に拒絶された仮初の花嫁
結城芙由奈@12/27電子書籍配信
恋愛
【決してご迷惑はお掛けしません。どうか私をここに置いて頂けませんか?】
妾腹の娘として厄介者扱いを受けていたアリアドネは姉の身代わりとして暴君として名高い辺境伯に嫁がされる。結婚すれば幸せになれるかもしれないと淡い期待を抱いていたのも束の間。望まぬ花嫁を押し付けられたとして夫となるべく辺境伯に初対面で冷たい言葉を投げつけらた。さらに城から追い出されそうになるものの、ある人物に救われて下働きとして置いてもらえる事になるのだった―。

虐げられた令嬢は、姉の代わりに王子へ嫁ぐ――たとえお飾りの妃だとしても
千堂みくま
恋愛
「この卑しい娘め、おまえはただの身代わりだろうが!」 ケルホーン伯爵家に生まれたシーナは、ある理由から義理の家族に虐げられていた。シーナは姉のルターナと瓜二つの顔を持ち、背格好もよく似ている。姉は病弱なため、義父はシーナに「ルターナの代わりに、婚約者のレクオン王子と面会しろ」と強要してきた。二人はなんとか支えあって生きてきたが、とうとうある冬の日にルターナは帰らぬ人となってしまう。「このお金を持って、逃げて――」ルターナは最後の力で屋敷から妹を逃がし、シーナは名前を捨てて別人として暮らしはじめたが、レクオン王子が迎えにやってきて……。○第15回恋愛小説大賞に参加しています。もしよろしければ応援お願いいたします。

彼女にも愛する人がいた
まるまる⭐️
恋愛
既に冷たくなった王妃を見つけたのは、彼女に食事を運んで来た侍女だった。
「宮廷医の見立てでは、王妃様の死因は餓死。然も彼が言うには、王妃様は亡くなってから既に2、3日は経過しているだろうとの事でした」
そう宰相から報告を受けた俺は、自分の耳を疑った。
餓死だと? この王宮で?
彼女は俺の従兄妹で隣国ジルハイムの王女だ。
俺の背中を嫌な汗が流れた。
では、亡くなってから今日まで、彼女がいない事に誰も気付きもしなかったと言うのか…?
そんな馬鹿な…。信じられなかった。
だがそんな俺を他所に宰相は更に告げる。
「亡くなった王妃様は陛下の子を懐妊されておりました」と…。
彼女がこの国へ嫁いで来て2年。漸く子が出来た事をこんな形で知るなんて…。
俺はその報告に愕然とした。

溺愛されていると信じておりました──が。もう、どうでもいいです。
ふまさ
恋愛
いつものように屋敷まで迎えにきてくれた、幼馴染みであり、婚約者でもある伯爵令息──ミックに、フィオナが微笑む。
「おはよう、ミック。毎朝迎えに来なくても、学園ですぐに会えるのに」
「駄目だよ。もし学園に向かう途中できみに何かあったら、ぼくは悔やんでも悔やみきれない。傍にいれば、いつでも守ってあげられるからね」
ミックがフィオナを抱き締める。それはそれは、愛おしそうに。その様子に、フィオナの両親が見守るように穏やかに笑う。
──対して。
傍に控える使用人たちに、笑顔はなかった。
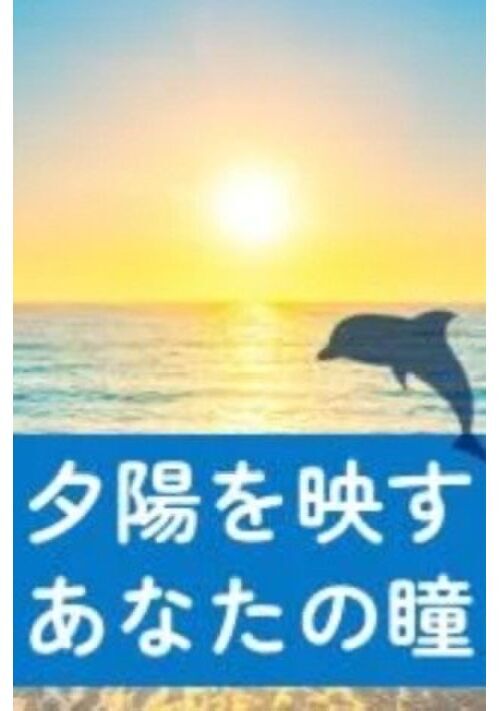
夕陽を映すあなたの瞳
葉月 まい
恋愛
恋愛に興味のないサバサバ女の 心
バリバリの商社マンで優等生タイプの 昴
そんな二人が、
高校の同窓会の幹事をすることに…
意思疎通は上手くいくのか?
ちゃんと幹事は出来るのか?
まさか、恋に発展なんて…
しないですよね?…あれ?
思わぬ二人の恋の行方は??
*✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻
高校の同窓会の幹事をすることになった
心と昴。
8年ぶりに再会し、準備を進めるうちに
いつしか二人は距離を縮めていく…。
高校時代は
決して交わることのなかった二人。
ぎこちなく、でも少しずつ
お互いを想い始め…
☆*:.。. 登場人物 .。.:*☆
久住 心 (26歳)… 水族館の飼育員
Kuzumi Kokoro
伊吹 昴 (26歳)… 海外を飛び回る商社マン
Ibuki Subaru

愛されない花嫁は初夜を一人で過ごす
リオール
恋愛
「俺はお前を妻と思わないし愛する事もない」
夫となったバジルはそう言って部屋を出て行った。妻となったアルビナは、初夜を一人で過ごすこととなる。
後に夫から聞かされた衝撃の事実。
アルビナは夫への復讐に、静かに心を燃やすのだった。
※シリアスです。
※ざまあが行き過ぎ・過剰だといったご意見を頂戴しております。年齢制限は設定しておりませんが、お読みになる場合は自己責任でお願い致します。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















