お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

【完結】婿入り予定の婚約者は恋人と結婚したいらしい 〜そのひと爵位継げなくなるけどそんなに欲しいなら譲ります〜
早奈恵
恋愛
【完結】ざまぁ展開あります⚫︎幼なじみで婚約者のデニスが恋人を作り、破談となってしまう。困ったステファニーは急遽婿探しをする事になる。⚫︎新しい相手と婚約発表直前『やっぱりステファニーと結婚する』とデニスが言い出した。⚫︎辺境伯になるにはステファニーと結婚が必要と気が付いたデニスと辺境伯夫人になりたかった恋人ブリトニーを前に、ステファニーは新しい婚約者ブラッドリーと共に対抗する。⚫︎デニスの恋人ブリトニーが不公平だと言い、デニスにもチャンスをくれと縋り出す。⚫︎そしてデニスとブラッドが言い合いになり、決闘することに……。

虐げられた令嬢は、姉の代わりに王子へ嫁ぐ――たとえお飾りの妃だとしても
千堂みくま
恋愛
「この卑しい娘め、おまえはただの身代わりだろうが!」 ケルホーン伯爵家に生まれたシーナは、ある理由から義理の家族に虐げられていた。シーナは姉のルターナと瓜二つの顔を持ち、背格好もよく似ている。姉は病弱なため、義父はシーナに「ルターナの代わりに、婚約者のレクオン王子と面会しろ」と強要してきた。二人はなんとか支えあって生きてきたが、とうとうある冬の日にルターナは帰らぬ人となってしまう。「このお金を持って、逃げて――」ルターナは最後の力で屋敷から妹を逃がし、シーナは名前を捨てて別人として暮らしはじめたが、レクオン王子が迎えにやってきて……。○第15回恋愛小説大賞に参加しています。もしよろしければ応援お願いいたします。


彼女にも愛する人がいた
まるまる⭐️
恋愛
既に冷たくなった王妃を見つけたのは、彼女に食事を運んで来た侍女だった。
「宮廷医の見立てでは、王妃様の死因は餓死。然も彼が言うには、王妃様は亡くなってから既に2、3日は経過しているだろうとの事でした」
そう宰相から報告を受けた俺は、自分の耳を疑った。
餓死だと? この王宮で?
彼女は俺の従兄妹で隣国ジルハイムの王女だ。
俺の背中を嫌な汗が流れた。
では、亡くなってから今日まで、彼女がいない事に誰も気付きもしなかったと言うのか…?
そんな馬鹿な…。信じられなかった。
だがそんな俺を他所に宰相は更に告げる。
「亡くなった王妃様は陛下の子を懐妊されておりました」と…。
彼女がこの国へ嫁いで来て2年。漸く子が出来た事をこんな形で知るなんて…。
俺はその報告に愕然とした。
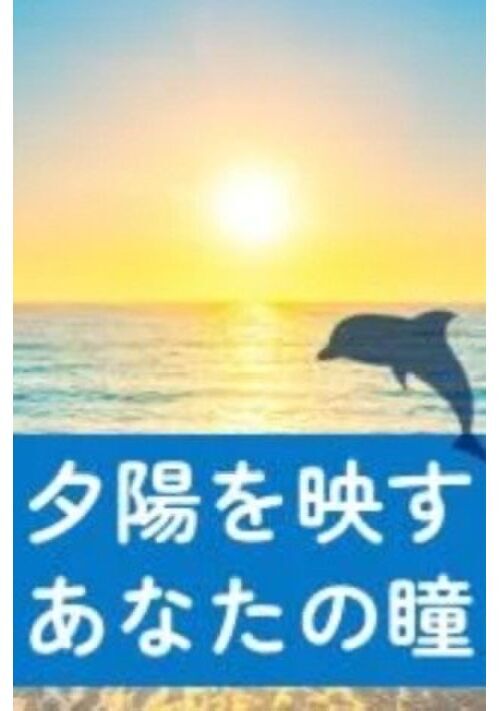
夕陽を映すあなたの瞳
葉月 まい
恋愛
恋愛に興味のないサバサバ女の 心
バリバリの商社マンで優等生タイプの 昴
そんな二人が、
高校の同窓会の幹事をすることに…
意思疎通は上手くいくのか?
ちゃんと幹事は出来るのか?
まさか、恋に発展なんて…
しないですよね?…あれ?
思わぬ二人の恋の行方は??
*✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻
高校の同窓会の幹事をすることになった
心と昴。
8年ぶりに再会し、準備を進めるうちに
いつしか二人は距離を縮めていく…。
高校時代は
決して交わることのなかった二人。
ぎこちなく、でも少しずつ
お互いを想い始め…
☆*:.。. 登場人物 .。.:*☆
久住 心 (26歳)… 水族館の飼育員
Kuzumi Kokoro
伊吹 昴 (26歳)… 海外を飛び回る商社マン
Ibuki Subaru

家族から見放されましたが、王家が救ってくれました!
マルローネ
恋愛
「お前は私に相応しくない。婚約を破棄する」
花嫁修業中の伯爵令嬢のユリアは突然、相応しくないとして婚約者の侯爵令息であるレイモンドに捨てられた。それを聞いた彼女の父親も家族もユリアを必要なしとして捨て去る。
途方に暮れたユリアだったが彼女にはとても大きな味方がおり……。

異世界に召喚されたけど、従姉妹に嵌められて即森に捨てられました。
バナナマヨネーズ
恋愛
香澄静弥は、幼馴染で従姉妹の千歌子に嵌められて、異世界召喚されてすぐに魔の森に捨てられてしまった。しかし、静弥は森に捨てられたことを逆に人生をやり直すチャンスだと考え直した。誰も自分を知らない場所で気ままに生きると決めた静弥は、異世界召喚の際に与えられた力をフル活用して異世界生活を楽しみだした。そんなある日のことだ、魔の森に来訪者がやってきた。それから、静弥の異世界ライフはちょっとだけ騒がしくて、楽しいものへと変わっていくのだった。
全123話
※小説家になろう様にも掲載しています。

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















