お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

恋とキスは背伸びして
葉月 まい
恋愛
結城 美怜(24歳)…身長160㎝、平社員
成瀬 隼斗(33歳)…身長182㎝、本部長
年齢差 9歳
身長差 22㎝
役職 雲泥の差
この違い、恋愛には大きな壁?
そして同期の卓の存在
異性の親友は成立する?
数々の壁を乗り越え、結ばれるまでの
二人の恋の物語

公爵子息に気に入られて貴族令嬢になったけど姑の嫌がらせで婚約破棄されました。傷心の私を癒してくれるのは幼馴染だけです
エルトリア
恋愛
「アルフレッド・リヒテンブルグと、リーリエ・バンクシーとの婚約は、只今をもって破棄致します」
塗装看板屋バンクシー・ペイントサービスを営むリーリエは、人命救助をきっかけに出会った公爵子息アルフレッドから求婚される。
平民と貴族という身分差に戸惑いながらも、アルフレッドに惹かれていくリーリエ。
だが、それを快く思わない公爵夫人は、リーリエに対して冷酷な態度を取る。さらには、許嫁を名乗る娘が現れて――。
お披露目を兼ねた舞踏会で、婚約破棄を言い渡されたリーリエが、失意から再び立ち上がる物語。
著者:藤本透
原案:エルトリア

裏切られた令嬢は死を選んだ。そして……
希猫 ゆうみ
恋愛
スチュアート伯爵家の令嬢レーラは裏切られた。
幼馴染に婚約者を奪われたのだ。
レーラの17才の誕生日に、二人はキスをして、そして言った。
「一度きりの人生だから、本当に愛せる人と結婚するよ」
「ごめんねレーラ。ロバートを愛してるの」
誕生日に婚約破棄されたレーラは絶望し、生きる事を諦めてしまう。
けれど死にきれず、再び目覚めた時、新しい人生が幕を開けた。
レーラに許しを請い、縋る裏切り者たち。
心を鎖し生きて行かざるを得ないレーラの前に、一人の求婚者が現れる。
強く気高く冷酷に。
裏切り者たちが落ちぶれていく様を眺めながら、レーラは愛と幸せを手に入れていく。
☆完結しました。ありがとうございました!☆
(ホットランキング8位ありがとうございます!(9/10、19:30現在))
(ホットランキング1位~9位~2位ありがとうございます!(9/6~9))
(ホットランキング1位!?ありがとうございます!!(9/5、13:20現在))
(ホットランキング9位ありがとうございます!(9/4、18:30現在))

[完結]貴方なんか、要りません
シマ
恋愛
私、ロゼッタ・チャールストン15歳には婚約者がいる。
バカで女にだらしなくて、ギャンブル好きのクズだ。公爵家当主に土下座する勢いで頼まれた婚約だったから断われなかった。
だから、条件を付けて学園を卒業するまでに、全てクリアする事を約束した筈なのに……
一つもクリア出来ない貴方なんか要りません。絶対に婚約破棄します。

彼女にも愛する人がいた
まるまる⭐️
恋愛
既に冷たくなった王妃を見つけたのは、彼女に食事を運んで来た侍女だった。
「宮廷医の見立てでは、王妃様の死因は餓死。然も彼が言うには、王妃様は亡くなってから既に2、3日は経過しているだろうとの事でした」
そう宰相から報告を受けた俺は、自分の耳を疑った。
餓死だと? この王宮で?
彼女は俺の従兄妹で隣国ジルハイムの王女だ。
俺の背中を嫌な汗が流れた。
では、亡くなってから今日まで、彼女がいない事に誰も気付きもしなかったと言うのか…?
そんな馬鹿な…。信じられなかった。
だがそんな俺を他所に宰相は更に告げる。
「亡くなった王妃様は陛下の子を懐妊されておりました」と…。
彼女がこの国へ嫁いで来て2年。漸く子が出来た事をこんな形で知るなんて…。
俺はその報告に愕然とした。

【本編完結】独りよがりの初恋でした
須木 水夏
恋愛
好きだった人。ずっと好きだった人。その人のそばに居たくて、そばに居るために頑張ってた。
それが全く意味の無いことだなんて、知らなかったから。
アンティーヌは図書館の本棚の影で聞いてしまう。大好きな人が他の人に囁く愛の言葉を。
#ほろ苦い初恋
#それぞれにハッピーエンド
特にざまぁなどはありません。
小さく淡い恋の、始まりと終わりを描きました。完結いたします。
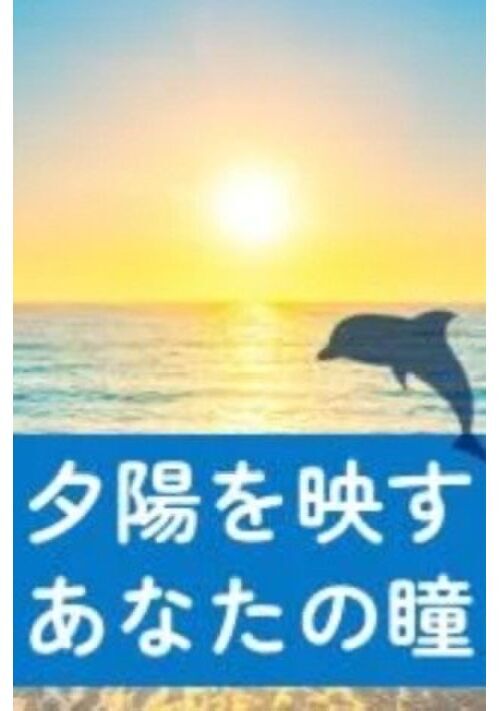
夕陽を映すあなたの瞳
葉月 まい
恋愛
恋愛に興味のないサバサバ女の 心
バリバリの商社マンで優等生タイプの 昴
そんな二人が、
高校の同窓会の幹事をすることに…
意思疎通は上手くいくのか?
ちゃんと幹事は出来るのか?
まさか、恋に発展なんて…
しないですよね?…あれ?
思わぬ二人の恋の行方は??
*✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻
高校の同窓会の幹事をすることになった
心と昴。
8年ぶりに再会し、準備を進めるうちに
いつしか二人は距離を縮めていく…。
高校時代は
決して交わることのなかった二人。
ぎこちなく、でも少しずつ
お互いを想い始め…
☆*:.。. 登場人物 .。.:*☆
久住 心 (26歳)… 水族館の飼育員
Kuzumi Kokoro
伊吹 昴 (26歳)… 海外を飛び回る商社マン
Ibuki Subaru

「あなたの好きなひとを盗るつもりなんてなかった。どうか許して」と親友に謝られたけど、その男性は私の好きなひとではありません。まあいっか。
石河 翠
恋愛
真面目が取り柄のハリエットには、同い年の従姉妹エミリーがいる。母親同士の仲が悪く、二人は何かにつけ比較されてきた。
ある日招待されたお茶会にて、ハリエットは突然エミリーから謝られる。なんとエミリーは、ハリエットの好きなひとを盗ってしまったのだという。エミリーの母親は、ハリエットを出し抜けてご機嫌の様子。
ところが、紹介された男性はハリエットの好きなひととは全くの別人。しかもエミリーは勘違いしているわけではないらしい。そこでハリエットは伯母の誤解を解かないまま、エミリーの結婚式への出席を希望し……。
母親の束縛から逃れて初恋を叶えるしたたかなヒロインと恋人を溺愛する腹黒ヒーローの恋物語。ハッピーエンドです。
この作品は他サイトにも投稿しております。
扉絵は写真ACよりチョコラテさまの作品(写真ID:23852097)をお借りしております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















