お気に入りに追加
7
あなたにおすすめの小説

【完結】偽りの婚約のつもりが愛されていました
ユユ
恋愛
可憐な妹に何度も婚約者を奪われて生きてきた。
だけど私は子爵家の跡継ぎ。
騒ぎ立てることはしなかった。
子爵家の仕事を手伝い、婚約者を持つ令嬢として
慎ましく振る舞ってきた。
五人目の婚約者と妹は体を重ねた。
妹は身籠った。
父は跡継ぎと婚約相手を妹に変えて
私を今更嫁に出すと言った。
全てを奪われた私はもう我慢を止めた。
* 作り話です。
* 短めの話にするつもりです
* 暇つぶしにどうぞ

自国から去りたかったので、怪しい求婚だけど受けました。
しゃーりん
恋愛
侯爵令嬢アミディアは婚約者と別れるように言われていたところを隣国から来た客人オルビスに助けられた。
アミディアが自国に嫌気がさしているのを察したオルビスは、自分と結婚すればこの国から出られると求婚する。
隣国には何度も訪れたことはあるし親戚もいる。
学園を卒業した今が逃げる時だと思い、アミディアはオルビスの怪しい求婚を受けることにした。
訳アリの結婚になるのだろうと思い込んで隣国で暮らすことになったけど溺愛されるというお話です。

もつれた心、ほどいてあげる~カリスマ美容師御曹司の甘美な溺愛レッスン~
泉南佳那
恋愛
イケメンカリスマ美容師と内気で地味な書店員との、甘々溺愛ストーリーです!
どうぞお楽しみいただけますように。
〈あらすじ〉
加藤優紀は、現在、25歳の書店員。
東京の中心部ながら、昭和味たっぷりの裏町に位置する「高木書店」という名の本屋を、祖母とふたりで切り盛りしている。
彼女が高木書店で働きはじめたのは、3年ほど前から。
短大卒業後、不動産会社で営業事務をしていたが、同期の、親会社の重役令嬢からいじめに近い嫌がらせを受け、逃げるように会社を辞めた過去があった。
そのことは優紀の心に小さいながらも深い傷をつけた。
人付き合いを恐れるようになった優紀は、それ以来、つぶれかけの本屋で人の目につかない質素な生活に安んじていた。
一方、高木書店の目と鼻の先に、優紀の兄の幼なじみで、大企業の社長令息にしてカリスマ美容師の香坂玲伊が〈リインカネーション〉という総合ビューティーサロンを経営していた。
玲伊は優紀より4歳年上の29歳。
優紀も、兄とともに玲伊と一緒に遊んだ幼なじみであった。
店が近いこともあり、玲伊はしょっちゅう、優紀の本屋に顔を出していた。
子供のころから、かっこよくて優しかった玲伊は、優紀の初恋の人。
その気持ちは今もまったく変わっていなかったが、しがない書店員の自分が、カリスマ美容師にして御曹司の彼に釣り合うはずがないと、その恋心に蓋をしていた。
そんなある日、優紀は玲伊に「自分の店に来て」言われる。
優紀が〈リインカネーション〉を訪れると、人気のファッション誌『KALEN』の編集者が待っていた。
そして「シンデレラ・プロジェクト」のモデルをしてほしいと依頼される。
「シンデレラ・プロジェクト」とは、玲伊の店の1周年記念の企画で、〈リインカネーション〉のすべての施設を使い、2~3カ月でモデルの女性を美しく変身させ、それを雑誌の連載記事として掲載するというもの。
優紀は固辞したが、玲伊の熱心な誘いに負け、最終的に引き受けることとなる。
はじめての経験に戸惑いながらも、超一流の施術に心が満たされていく優紀。
そして、玲伊への恋心はいっそう募ってゆく。
玲伊はとても優しいが、それは親友の妹だから。
そんな切ない気持ちを抱えていた。
プロジェクトがはじまり、ひと月が過ぎた。
書店の仕事と〈リインカネーション〉の施術という二重生活に慣れてきた矢先、大問題が発生する。
突然、編集部に上層部から横やりが入り、優紀は「シンデレラ・プロジェクト」のモデルを下ろされることになった。
残念に思いながらも、やはり夢でしかなかったのだとあきらめる優紀だったが、そんなとき、玲伊から呼び出しを受けて……

【完結】あなたが妹を選んだのです…後悔しても遅いですよ?
なか
恋愛
「ローザ!!お前との結婚は取り消しさせてもらう!!」
結婚式の前日に彼は大きな声でそう言った
「なぜでしょうか?ライアン様」
尋ねる私に彼は勝ち誇ったような笑みを浮かべ
私の妹マリアの名前を呼んだ
「ごめんなさいお姉様~」
「俺は真実の愛を見つけたのだ!」
真実の愛?
妹の大きな胸を見ながら言うあなたに説得力の欠片も
理性も感じられません
怒りで拳を握る
明日に控える結婚式がキャンセルとなればどれだけの方々に迷惑がかかるか
けど息を吐いて冷静さを取り戻す
落ち着いて
これでいい……ようやく終わるのだ
「本当によろしいのですね?」
私の問いかけに彼は頷く
では離縁いたしまししょう
後悔しても遅いですよ?
これは全てあなたが選んだ選択なのですから

【本編完結】独りよがりの初恋でした
須木 水夏
恋愛
好きだった人。ずっと好きだった人。その人のそばに居たくて、そばに居るために頑張ってた。
それが全く意味の無いことだなんて、知らなかったから。
アンティーヌは図書館の本棚の影で聞いてしまう。大好きな人が他の人に囁く愛の言葉を。
#ほろ苦い初恋
#それぞれにハッピーエンド
特にざまぁなどはありません。
小さく淡い恋の、始まりと終わりを描きました。完結いたします。
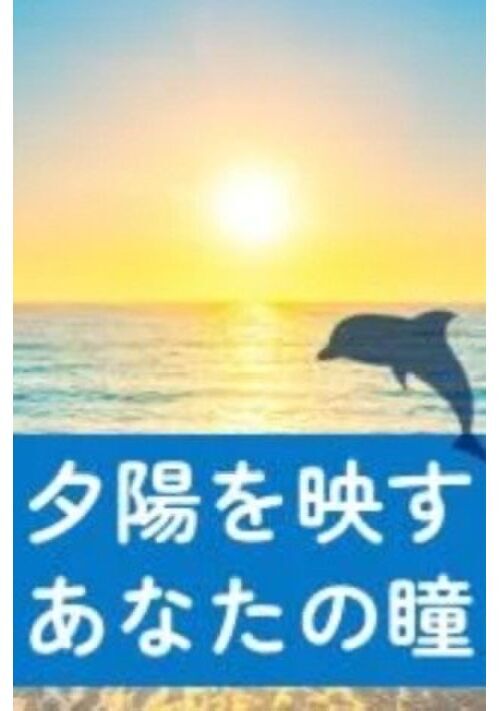
夕陽を映すあなたの瞳
葉月 まい
恋愛
恋愛に興味のないサバサバ女の 心
バリバリの商社マンで優等生タイプの 昴
そんな二人が、
高校の同窓会の幹事をすることに…
意思疎通は上手くいくのか?
ちゃんと幹事は出来るのか?
まさか、恋に発展なんて…
しないですよね?…あれ?
思わぬ二人の恋の行方は??
*✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻* *✻:::✻*✻:::✻
高校の同窓会の幹事をすることになった
心と昴。
8年ぶりに再会し、準備を進めるうちに
いつしか二人は距離を縮めていく…。
高校時代は
決して交わることのなかった二人。
ぎこちなく、でも少しずつ
お互いを想い始め…
☆*:.。. 登場人物 .。.:*☆
久住 心 (26歳)… 水族館の飼育員
Kuzumi Kokoro
伊吹 昴 (26歳)… 海外を飛び回る商社マン
Ibuki Subaru

彼女にも愛する人がいた
まるまる⭐️
恋愛
既に冷たくなった王妃を見つけたのは、彼女に食事を運んで来た侍女だった。
「宮廷医の見立てでは、王妃様の死因は餓死。然も彼が言うには、王妃様は亡くなってから既に2、3日は経過しているだろうとの事でした」
そう宰相から報告を受けた俺は、自分の耳を疑った。
餓死だと? この王宮で?
彼女は俺の従兄妹で隣国ジルハイムの王女だ。
俺の背中を嫌な汗が流れた。
では、亡くなってから今日まで、彼女がいない事に誰も気付きもしなかったと言うのか…?
そんな馬鹿な…。信じられなかった。
だがそんな俺を他所に宰相は更に告げる。
「亡くなった王妃様は陛下の子を懐妊されておりました」と…。
彼女がこの国へ嫁いで来て2年。漸く子が出来た事をこんな形で知るなんて…。
俺はその報告に愕然とした。

【完結】乙女ゲーム開始前に消える病弱モブ令嬢に転生しました
佐倉穂波
恋愛
転生したルイシャは、自分が若くして死んでしまう乙女ゲームのモブ令嬢で事を知る。
確かに、まともに起き上がることすら困難なこの体は、いつ死んでもおかしくない状態だった。
(そんな……死にたくないっ!)
乙女ゲームの記憶が正しければ、あと数年で死んでしまうルイシャは、「生きる」ために努力することにした。
2023.9.3 投稿分の改稿終了。
2023.9.4 表紙を作ってみました。
2023.9.15 完結。
2023.9.23 後日談を投稿しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















