44 / 533
二夜 蜃(シェン)の楼(たかどの)
二夜 蜃の楼 10
しおりを挟む紀元前二三〇年、韓を滅ぼしたのを皮切りに、趙、魏、楚、燕を次々に攻め滅ぼし、紀元前二二一年、最後に残った斎を滅ぼして戦国の六国を全て併合、天下統一を遂げた秦の始皇帝、秦王政は、次々と夥しい数の宮殿を築き、紀元前二二〇年、《地上空間》と《天上世界》を対応させるという構想の下に、『極廟』を建築した。
極――すなわち、天の中心にきらめく北極星のことである。
さらに八年後の紀元前二一二年には、天帝の棲む紫微宮に対応する阿房宮を造り、自らの本拠もそこに移した。
彼は地上界を支配するだけでなく、天上世界をも含めた全宇宙、さらには彼(あ)の世たる冥界をも支配することを欲したのだ。
阿房宮と閣道によって繋がる驪山の始皇陵(驪山陵)こそが、その冥界と呼応するものである。
「……つまり、ここは本当に実在する世界なのか?」
デューイの話を聞いて、舜は訊いた。
「正しくは、本当に存在していた世界だ。まだこの国が秦と呼ばれていた頃に――。秦王朝は、紀元前二〇七年に滅亡している。――中国人のくせに、自分の国の歴史も知らないのか?」
その言葉には、舜もかなり、ムッ、とした。
「オレは、昔のことなんか興味がないんだよっ」
と、ぶっきらぼうに、吐き捨てる。
なんとなく今、黄帝がデューイと共に行け、と言った意味が解ったような気が、した。
そして、黄帝が今頃、舜が帰って来た時の厭味を考えているような気も……しないではない。――いや、きっと考えているだろう。
「あのクソおやじ。知っててオレに教えなかったな」
本当は、舜が面倒臭くて聞かなかっただけなのだが、そんなことなど、当人はすっかり忘れている。
黄帝はあの日、こう言ったのだ。
『あのですね、舜くん。物事を知るには、たとえ遠回りに思えても、一から順番に聞いた方が早いこともあるのですよ。たとえ偶然、一もなしに十を見つけることが出来たとしても、一を理解していない君には、その十の意味さえ解らないのですから……』
と――。
その前には確か、秦王政の名前も出ていたような気が、する。
つまり、悪いのは舜、という訳である。
「秦の始皇帝は、人間としての限界――つまり、『死』を超越するために、不老長生のための仙薬や仙人を探し求めていたんだ。自らを天帝や冥界の王に準えて、不滅の生を願ったように」
「ハッ。馬鹿な奴だな。長く生きたって、黄帝みたいな変人になるだけだってのに」
舜は肩を竦めて、天を仰いだ。
人間は、死ぬことが出来る寿命があって、幸せなのだ。元来、愚かな生き物なのだから、長く生きていてもロクなことにはならない。
「だけど……。まさか、本当に死を超越して、之罘山に阿房宮や驪山陵を存在させていたなんて……」
デューイは感心するように、不滅願望の産物を見渡した。
だが、本当に、人間の妄執だけで、こんな世界が築ける、というのだろうか。
「人間にこんな力はないさ。あるとすれば、そいつはもう、人間じゃない」
別のものになってまで長生きをしたい、と思うものなのだろうか、人間とは。
デューイのように、自分の意志とは関係なく、別のものに変えられてしまった者はともかくとして――。
「あれが阿房宮だろう」
デューイの視線の先には、壮麗を極める建造物があった。
「楽しそうだな」
やたらと〃にこにこ〃しているデューイを見て、舜は皮肉な視線を投げ付けた。
体の苦痛がここへ来てなくなっていることもあって、デューイは本来の性格以上に、人の良さそうな顔をしているのだ。
「そりゃ、秦の始皇帝に逢える機会なんて、死ぬまでないと思っていたからね」
どうやら彼には、今の状況よりも、歴史上の人物に逢えることの方が、楽しみらしい。
「……オレ、こいつと黄帝とこのまま一緒に暮らしてたら、精神に異常を来すかも知んない」
舜の新たな苦悩の始まりの一日であった……。
0
お気に入りに追加
32
あなたにおすすめの小説

転生先の異世界で温泉ブームを巻き起こせ!
カエデネコ
ファンタジー
日本のとある旅館の跡継ぎ娘として育てられた前世を活かして転生先でも作りたい最高の温泉地!
恋に仕事に事件に忙しい!
カクヨムの方でも「カエデネコ」でメイン活動してます。カクヨムの方が更新が早いです。よろしければそちらもお願いしますm(_ _)m

チャラ孫子―もし孫武さんがちょっとだけチャラ男だったら―
神光寺かをり
歴史・時代
チャラいインテリか。
陽キャのミリオタか。
中国・春秋時代。
歴史にその名を遺す偉大な兵法家・孫子こと孫武さんが、自らの兵法を軽ーくレクチャー!
風林火山って結局なんなの?
呉越同舟ってどういう意味?
ちょっとだけ……ほんのちょっとだけ「チャラ男」な孫武さんによる、
軽薄な現代語訳「孫子の兵法」です。
※直訳ではなく、意訳な雰囲気でお送りいたしております。
※この作品は、ノベルデイズ、pixiv小説で公開中の同名作に、修正加筆を施した物です。
※この作品は、ノベルアップ+、小説家になろうでも公開しています。
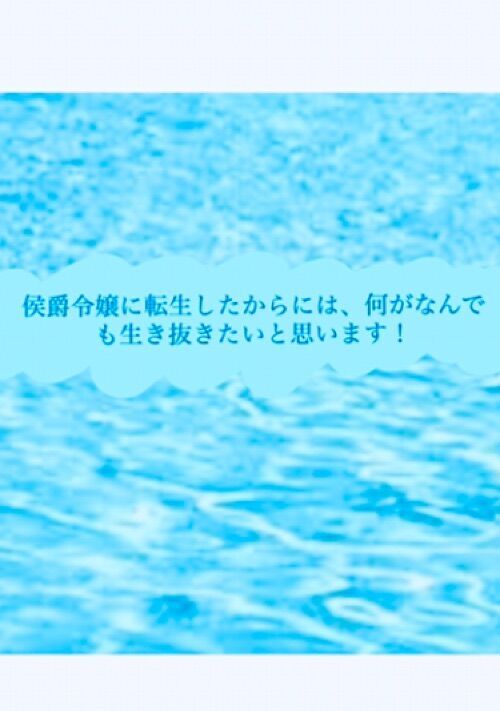
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

侯爵家の愛されない娘でしたが、前世の記憶を思い出したらお父様がバリ好みのイケメン過ぎて毎日が楽しくなりました
下菊みこと
ファンタジー
前世の記憶を思い出したらなにもかも上手くいったお話。
ご都合主義のSS。
お父様、キャラチェンジが激しくないですか。
小説家になろう様でも投稿しています。
突然ですが長編化します!ごめんなさい!ぜひ見てください!

妹はわたくしの物を何でも欲しがる。何でも、わたくしの全てを……そうして妹の元に残るモノはさて、なんでしょう?
ラララキヲ
ファンタジー
姉と下に2歳離れた妹が居る侯爵家。
両親は可愛く生まれた妹だけを愛し、可愛い妹の為に何でもした。
妹が嫌がることを排除し、妹の好きなものだけを周りに置いた。
その為に『お城のような別邸』を作り、妹はその中でお姫様となった。
姉はそのお城には入れない。
本邸で使用人たちに育てられた姉は『次期侯爵家当主』として恥ずかしくないように育った。
しかしそれをお城の窓から妹は見ていて不満を抱く。
妹は騒いだ。
「お姉さまズルい!!」
そう言って姉の着ていたドレスや宝石を奪う。
しかし…………
末娘のお願いがこのままでは叶えられないと気付いた母親はやっと重い腰を上げた。愛する末娘の為に母親は無い頭を振り絞って素晴らしい方法を見つけた。
それは『悪魔召喚』
悪魔に願い、
妹は『姉の全てを手に入れる』……──
※作中は[姉視点]です。
※一話が短くブツブツ進みます
◇ふんわり世界観。ゆるふわ設定。
◇ご都合展開。矛盾もあるかも。
◇なろうにも上げました。

人質から始まった凡庸で優しい王子の英雄譚
咲良喜玖
ファンタジー
アーリア戦記から抜粋。
帝国歴515年。サナリア歴3年。
新国家サナリア王国は、超大国ガルナズン帝国の使者からの宣告により、国家存亡の危機に陥る。
アーリア大陸を二分している超大国との戦いは、全滅覚悟の死の戦争である。
だからこそ、サナリア王アハトは、帝国に従属することを決めるのだが。
当然それだけで交渉が終わるわけがなく、従属した証を示せとの命令が下された。
命令の中身。
それは、二人の王子の内のどちらかを選べとの事だった。
出来たばかりの国を守るために、サナリア王が判断した人物。
それが第一王子である【フュン・メイダルフィア】だった。
フュンは弟に比べて能力が低く、武芸や勉学が出来ない。
彼の良さをあげるとしたら、ただ人に優しいだけ。
そんな人物では、国を背負うことが出来ないだろうと、彼は帝国の人質となってしまったのだ。
しかし、この人質がきっかけとなり、長らく続いているアーリア大陸の戦乱の歴史が変わっていく。
西のイーナミア王国。東のガルナズン帝国。
アーリア大陸の歴史を支える二つの巨大国家を揺るがす英雄が誕生することになるのだ。
偉大なる人質。フュンの物語が今始まる。
他サイトにも書いています。
こちらでは、出来るだけシンプルにしていますので、章分けも簡易にして、解説をしているあとがきもありません。
小説だけを読める形にしています。

高校からの帰り道、錬金術が使えるようになりました。
マーチ・メイ
ファンタジー
女子校に通う高校2年生の橘優奈は学校からの帰り道、突然『【職業】錬金術師になりました』と声が聞こえた。
空耳かと思い家に入り試しにステータスオープンと唱えるとステータスが表示された。
しばらく高校生活を楽しみつつ家で錬金術を試してみることに 。
すると今度はダンジョンが出現して知らない外国の人の名前が称号欄に現れた。
緩やかに日常に溶け込んでいく黎明期メインのダンジョン物です。
小説家になろう、カクヨムでも掲載しております。

異世界召喚でクラスの勇者達よりも強い俺は無能として追放処刑されたので自由に旅をします
Dakurai
ファンタジー
クラスで授業していた不動無限は突如と教室が光に包み込まれ気がつくと異世界に召喚されてしまった。神による儀式でとある神によってのスキルを得たがスキルが強すぎてスキル無しと勘違いされ更にはクラスメイトと王女による思惑で追放処刑に会ってしまうしかし最強スキルと聖獣のカワウソによって難を逃れと思ったらクラスの女子中野蒼花がついてきた。
相棒のカワウソとクラスの中野蒼花そして異世界の仲間と共にこの世界を自由に旅をします。
現在、第三章フェレスト王国エルフ編
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















