39 / 47
5.迫るタイムリミット
5-1
しおりを挟む"バカンスに行ってくる"
いつものようにそう告げて、出かけたシノさんはまだ帰って来ない。私は、高校3年生になって、綾瀬は大学院2年生になった。あの男は今も変わらず夜な夜な研究に励んでいる。瀬尾さんと一緒に、研究会や学会で発表する資料を作っている日もある。
だけど、シノさんは帰ってこない。携帯も繋がらない。
『……警察に、言った方がいいのかな』
寒さが厳しくて、縁側から見える庭の木々が泣いているように葉擦れを起こす。そんな夜に震える声で綾瀬に言った。冷やされた床板は、足先から身体全てを凍らせてしまう。
振り返って、私を射抜く男はいつものように無表情を貫く。だけどそれが冷たい、とはもう思わない。
『…お前も家出娘のくせして何言ってんの』
『、』
『お前はなんもしなくて良いよ』
『……でも、』
『警察には俺が行くから、ガキはもう寝ろ』
不安な表情を隠し切れない、私のそんな顔を見て綾瀬はふと笑う。ぐしゃぐしゃに髪を乱す男は、そう言って自分の部屋へと戻って行った。
"お前はいつまでここにいる気なの?"
綾瀬は、一度もそうは聞いて来なかった。あんなに最初は私を面倒くさいって言ってたくせに。シノさんを、待ってても良いのかと震える声のまま頼りなく尋ねた私に「今更何言ってんの?」と笑っただけだった。
それから、ずっと。
──私は、時限爆弾を抱えている。
もう、6月になった。シノさん、出会ってから1年が経とうとしてるよ。庭の桔梗が、また咲く季節になるよ。毎日ちゃんと手入れして育ててるのに、それを見ないってどういうこと?
新しいクラスは、りおとは離れてしまった。私達の噂は跡形もなく消えるなんてことは無い。だけど好奇心に煽られて膨らんだものは、萎んでいくのも速い。以前のような好奇の目を受けることは少なくなった。
それに少し、変わったこともある。新学期になった途端、女子2人が下駄箱近くで突然声をかけてきた。上履きの色から、2年生の子達だと分かる。
『梶先輩、園芸部に入ってくれませんか!?』
部員が足りなくて困っているらしく、私が高校近くの花屋でバイトをしているという何とも平和な噂を聞きつけてやって来たと言う。
『……私のこと、知らないの?』
『知ってます!!全然周りと群れずに、亜久津先輩といつもいらっしゃいますよね!麗しくてうちの学年では密かに"孤高の2人"って呼ばれてるんですよ!』
よく分からないが、輝く眼差しと圧に若干負けるようにして、体験だけ行こうと思っていたのに、あれよあれよという間に入部してしまった。3年生から部活に入るなんて、また何か噂をされそう。
でも太陽の下で、花壇の前で、仁美さんや光さんとは違う人達と花のことを話が出来るのは楽しかった。
──自分でやってみたいと思えたから、それで良かった。
『いや、2人の時点で孤高じゃなく無い?』
それを聞いた りおが金髪アッシュの髪を揺らしてケラケラ笑っていたのも。
『お前が部活ね』
何か言いたげに揶揄いの瞳だけを向ける綾瀬の腹の立つ顔も。
ねえ、シノさん。私はまだ、直接報告ができてないよ。
______
____
「進路調査票、来週までに提出なー」
帰りのHRに担任が、間延びした声で告げて配布した紙に視線を落とす。りおは、大学には行かないらしい。
「あたしのテキストを使う勉強は高校で終わった」と、全くぶれることなく、働きたいという意志がしっかりしていることが羨ましかった。
今日はバイトの前に園芸部の活動があって、少し遅くなってしまった。《家で待ってるよ、バイトがんば》と、りおからのメッセージを確認して足早に校門を出る。
「──桔帆」
「…橙生…」
曲がり角で直ぐに呼ばれた声に、急いでいた足が止まった。声の方へ顔を向けると、そこに佇んでいたのは、昔から何だってできて、優秀で、地方紙なんかにも登場してしまう、私の兄だった。質の良さそうなグレーのスーツ姿は、こんな学生の往来が大半を占める場所ではあまりに目立つ。
「久しぶり。元気?」
「……」
「お前、家出中らしいじゃん」
「……何しに来たの」
「可愛い妹の様子を見にきたんだろ。アホだねお前は。もっとうまいことやればいいのに」
「……私は橙生みたいに要領が良く無いんだよ」
「それは知ってるけど」
この男は、昔からいつも注目を集める、“優秀で完璧な男“だったけれど、その実態は割と腹黒い。爽やかな印象を必ず抱かせるであろう短い黒髪が風で少し揺れた。
「全然連絡とって無いんだろ」
「誰と?」と聞かなくても、流石に文脈から推測は出来る。俯いて唇を結んだままの私を見て、橙生は肯定と受け取ったらしい。1つ溜息を漏らした男は、私に近づいて頭を撫でる。
「…まあ、俺はあっちにも問題あるって思うよ。だからお前のことを連れ戻しに来たわけでも無い」
「……あの人たちは、もう私に興味は無いよ」
「ふうん、そうなんだ?」
一定の音調で出た言葉は、私に何かを促したりはしない。この男はいつも人当たりの良い笑顔を携えながら、冷静に物事を見ている気がする。
「…母さん、あんまり体調が良く無い」
「…え?」
「来週かな。検査入院するって」
突然の報告に言葉が詰まる。全身で嫌な脈を刻み始めれば、体温が着実に下がっていく。よく似てると散々言われた自分と同じ形の瞳が、真剣な眼差しで私を捕らえた。
「だからって、会いに来いって言ってるんじゃ無い。でも、お前はもう分かってるだろ?」
「…な、に」
橙生は、自分にも、他人にも甘く無い。ぬるい言葉は一切使わない。昔からそうだった。何を言われるかなんて、私は予言者じゃないから分からない筈なのに、どうしてだか、先行して身体が小刻みに震えていた。
──やめて、言わないで。
「お前はずっと今の場所にいられるわけじゃないよ」
真っ直ぐに伝えられた言葉が、目を逸らしてきた自分を容赦なく射抜いた。
0
お気に入りに追加
15
あなたにおすすめの小説

毎日告白
モト
ライト文芸
高校映画研究部の撮影にかこつけて、憧れの先輩に告白できることになった主人公。
同級生の監督に命じられてあの手この手で告白に挑むのだが、だんだんと監督が気になってきてしまい……
高校青春ラブコメストーリー

サンドアートナイトメア
shiori
ライト文芸
(最初に)
今を生きる人々に勇気を与えるような作品を作りたい。
もっと視野を広げて社会を見つめ直してほしい。
そんなことを思いながら、自分に書けるものを書こうと思って書いたのが、今回のサンドアートナイトメアです。
物語を通して、何か心に響くものがあればと思っています。
(あらすじ)
産まれて間もない頃からの全盲で、色のない世界で生きてきた少女、前田郁恵は病院生活の中で、年齢の近い少女、三由真美と出合う。
ある日、郁恵の元に届けられた父からの手紙とプレゼント。
看護師の佐々倉奈美と三由真美、二人に見守られながら開いたプレゼントの中身は額縁に入れられた砂絵だった。
砂絵に初めて触れた郁恵はなぜ目の見えない自分に父は砂絵を送ったのか、その意図を考え始める。
砂絵に描かれているという海と太陽と砂浜、その光景に思いを馳せる郁恵に真美は二人で病院を抜け出し、砂浜を目指すことを提案する。
不可能に思えた願望に向かって突き進んでいく二人、そして訪れた運命の日、まだ日の昇らない明朝に二人は手をつなぎ病院を抜け出して、砂絵に描かれていたような砂浜を目指して旅に出る。
諦めていた外の世界へと歩みだす郁恵、その傍に寄り添い支える真美。
見えない視界の中を勇気を振り絞り、歩みだす道のりは、遥か先の未来へと続く一歩へと変わり始めていた。

【完結】君の記憶と過去の交錯
翠月 歩夢
ライト文芸
第4回ライト文芸大賞にエントリーしています。よろしければ応援お願い致します。
学校に向かう途中にある公園でいつも見かける同じ春ヶ咲高校の制服を着ている男子。
その人をよく見てみるととてつもなく顔の整った容姿をしていた。ある日、その人に話しかけてみるとなんと幽霊であり自身の名前とこの町のこと以外は覚えていないらしいことが分かった。
主人公の桜空はその青年、零の記憶を取り戻す手伝いをすることを申し出る。だが、二人は共に記憶を探している内に、悲しい真実に気づいてしまう。
そして迎える結末は哀しくも暖かい、優しいものだった。
※エブリスタにも掲載しています。
表紙絵はこなきさんに描いて頂きました。主人公の桜空を可愛く描いてくれました。
追記
2021/9/13 ジャンル別ランキングに乗れました。ありがとうございます!

半径三メートルの箱庭生活
白い黒猫
ライト文芸
『誰もが、自分から半径三メートル以内にいる人間から、伴侶となる人を見付ける』らしい。
愛嬌と元気が取り柄の月見里百合子こと月ちゃんの心の世界三メートル圏内の距離に果たして運命の相手はいるのか?
映画を大好きな月ちゃんの恋愛は、映画のようにはなるわけもない?
一メートル、二メートル、三メートル、月ちゃんの相手はどこにいる?
恋愛というより人との触れ合いを描いた内容です。
現在第二部【ゼクシイには載っていなかった事】を公開しています。
月ちゃんのロマンチックから程遠い恍けた結婚準備の様子が描かれています
人との距離感をテーマにした物語です。女性の半径三メートルの距離の中を描いたコチラの話の他に、手の届く範囲の異性に手を出し続けた男性黒沢明彦を描いた「手を伸ばしたチョット先にあるお月様」、三十五センチ下の世界が気になり出した男性大陽渚の物語「三十五センチ下の◯◯点」があります。
黒沢くんの主人公の『伸ばした手のチョット先にある、お月様】と併せて読んでいただけると更に楽しめるかもしれません。
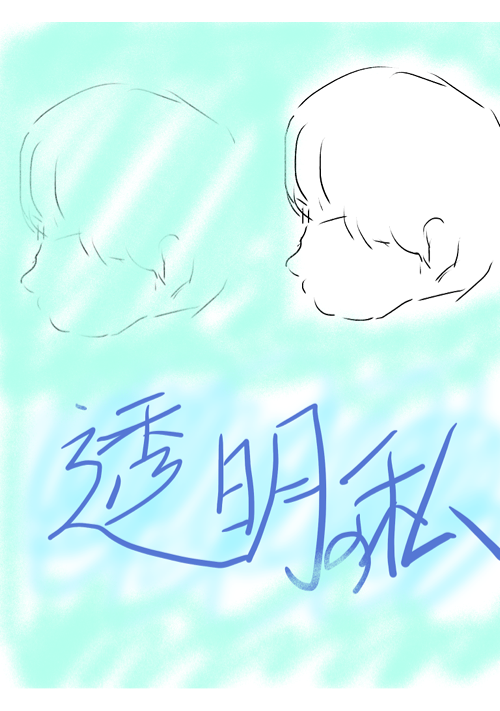
透明の私
ゆうゆ
ライト文芸
これは私が今まで生きてきたなかで、体験したことを元に、お話を書いてみました。
社会を恐れていた少女。平崎梨奈は、自分の意思を持たなかった。
そんなとき夏輝の存在がきっかけで、自分の色が無い梨奈は色付き始める。

同期の御曹司様は浮気がお嫌い
秋葉なな
恋愛
付き合っている恋人が他の女と結婚して、相手がまさかの妊娠!?
不倫扱いされて会社に居場所がなくなり、ボロボロになった私を助けてくれたのは同期入社の御曹司様。
「君が辛そうなのは見ていられない。俺が守るから、そばで笑ってほしい」
強引に同居が始まって甘やかされています。
人生ボロボロOL × 財閥御曹司
甘い生活に突然元カレ不倫男が現れて心が乱される生活に逆戻り。
「俺と浮気して。二番目の男でもいいから君が欲しい」
表紙イラスト
ノーコピーライトガール様 @nocopyrightgirl

きみと最初で最後の奇妙な共同生活
美和優希
ライト文芸
クラスメイトで男友達の健太郎を亡くした数日後。中学二年生の千夏が自室の姿見を見ると、自分自身の姿でなく健太郎の姿が鏡に映っていることに気づく。
どうやら、どういうわけか健太郎の魂が千夏の身体に入り込んでしまっているようだった。
この日から千夏は千夏の身体を通して、健太郎と奇妙な共同生活を送ることになるが、苦労も生じる反面、健太郎と過ごすにつれてお互いに今まで気づかなかった大切なものに気づいていって……。
旧タイトル:『きみと過ごした最後の時間』
※この作品はフィクションです。実在の人物・団体とは一切関係ありません。
※初回公開・完結*2016.08.07(他サイト)
*表紙画像は写真AC(makieni様)のフリー素材に文字入れをして使わせていただいてます。

COVERTー隠れ蓑を探してー
ユーリ(佐伯瑠璃)
ライト文芸
潜入捜査官である山崎晶(やまざきあきら)は、船舶代理店の営業として生活をしていた。営業と言いながらも、愛想を振りまく事が苦手で、未だエス(情報提供者)の数が少なかった。
ある日、ボスからエスになれそうな女性がいると合コンを秘密裏にセッティングされた。山口夏恋(やまぐちかれん)という女性はよいエスに育つだろうとボスに言われる。彼女をエスにするかはゆっくりと考えればいい。そう思っていた矢先に事件は起きた。
潜入先の会社が手配したコンテナ船の荷物から大量の武器が発見された。追い打ちをかけるように、合コンで知り合った山口夏恋が何者かに連れ去られてしまう。
『もしかしたら、事件は全て繋がっているんじゃないのか!』
山崎は真の身分を隠したまま、事件を解決することができるのか。そして、山口夏恋を無事に救出することはできるのか。偽りで固めた生活に、後ろめたさを抱えながら捜索に疾走する若手潜入捜査官のお話です。
※全てフィクションです。
※小説家になろう、カクヨムにも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















