1 / 3
プレリュードはエンドロールに響く
しおりを挟む
「言葉は呪文、音は魔法、絵という魔方陣に乗せて感動を広げる! 響け芸術! 魅せろ美学! 刮目せよ! これが私たちの世界だ!」
霜月三日の午前十時。監督が檀上で響かせた声は真っ直ぐに観衆の心に突き刺さったことだろう。あの日の俺たちのようにこれから起こる出来事に人生を奪われてしまうことだろう。
そう――春休み明けの始業式の日のように――
四月。始業式後に彼女は俺の教室を訪れた。強制連行のような形で連れられた俺は何一つ言葉を発する余裕すらも与えられずに放送室へ押し込められた。中にはすでに集められていた生徒が三人。俺も含めて全員が三年生。つまり今年受験を控えた人間だ。俺を除けば女子が二人と男子一人。それに俺の手を掴んでいる彼女と俺で合計五人。
いったいこれから何が起こるというのだろうか。
「君たちを集めたのは他でもない。私に譲ってほしいものがあるからだ!」
防音の放送室でこれ見よがしに大声を上げた主犯の彼女はホワイトボードを平手で叩くと、抜身の刀を振るうようにズバズバと書きなぐった。
アニメ――と。
「十一月三日の文化祭当日! 一本のアニメを上映したい! その為に諸君らの半年を私に譲って貰う!」
提案ではなく確定事項のように言い放った彼女の目には、迷いも気負いもその一切が無かった。やると決めたからやる――その意志しかなかった。俺はその迫力に委縮してしまって言葉が出ずに立ち尽くすばかり。
「は? ふざけてんの? 私ら受験生だし、そんな時間あるわけないじゃん。私が呼ばれたってことは棒人間アニメと適当なアフレコって訳じゃないんでしょ? ナシナシ。やんない」
気迫に当てられることなく反論したのは音峰鈴(おとみねすず)。学内のみならず、高校三年生ながら日本中で知る人ぞ知る音楽家だ。去年彼女が作詞作曲を手掛けた歌がアニメに使われたことで学内でも有名になった。
「音楽活動も今年は停止するつもりだし、そんな焦るような企画に手を付けたくない」
「わ、私も自信ない……かな」
音峰さんに乗るようにして言ったのは桧垣彩加(ひがきあやか)。彼女もまた知る人ぞ知る有名人。イラストサイトで名を馳せ、去年までは何年も連続で同人誌即売会にて壁を任される人物。俺みたいな絵描きをしている人間にとって羨むべき人間だ。
「俺は別にいいぞ。どうせ俺がやるのはアフレコだろ? 大して時間取られそうでもないし」
最後に言ったのは舞薗元気(まいぞのげんき)。彼は前述した二人ほど有名ではないが演劇部の部長として、昨年全国高等学校演劇大会に出場していた。
「報酬は? 受験失敗した時の将来の保証は? 私たちのメリットは? 私と舞薗はまだどうにかなるかもしれないわよ。でも、地獄を見る上に取り返しがつかないのは桧垣さんと佐藤でしょ? それにあんた。脚永(きゃくなが)さん。あんたの負担がデカすぎるんじゃない?」
脚永涼子(きゃくながりょうこ)。彼女は彼女で市民劇団の脚本を手掛け、この高校の演劇部にも作品を卸す脚本家。おそらく彼女が脚本、構成、演出、監督、その全てを担うことになるのだろう。到底今からできるとは思えない。
「本気でやるには時間が無さすぎるって言ってんの。受験が終わってからにしてくれる?」
「それじゃ遅いんだ! 今この時しかダメなんだ!」
「だから! 今から脚本とか――」
音峰さんが更に反論しようとした瞬間。脚永さんは足元のダンボール箱を持ち上げて机の上に置いた。激しくわざとらしく音が響くように三度繰り返した。
「脚本も構成も演出もラフ画もできてる! 私は本気だ! 私はこの世界を作るためにこの二年間を過ごしてきた!」
「ば、馬鹿じゃないの。これで私たちが首を縦に振らなかったら、あんたの何千時間かが無駄になったかもしれないっていうのに」
「これが叶わなければ、私は死の淵で何十年もの人生が無駄だったと言うかもしれない! 今しか……今しかないんだ……」
脚永さんは泣いていた。涙を流しながらすがるようにダンボールを叩いていた。音峰さんもその様子に心を打たれてしまったのか、伏し目がちになっていた。
「……桧垣さんと佐藤がやるっていうなら付き合ってあげるわよ」
そして遂に折れた音峰さんは桧垣さんと俺に選択を委ねるという迷惑な決断をしてくれた。
「私は……」
口ごもる様に言う桧垣さんは俺の顔色を何度も何度も伺っていた。先に発言することを促すと、桧垣さんより先に脚永さんが口を開いた。
「私はオタクだキモイだと言われ続けてきたアニメで世界を変えたい! 悔しいんだ――私が感動したものが、学んできたことが、没頭してきたものが否定される現実が! 私は声を高らかにして言いたい。これが私たちの世界だ、世界一美しい世界だと!」
風が吹いたような気がした――。体中を駆け巡る冷たい血潮が暖かくなるのを感じた。それと共に昔母に言われた言葉を思い出した。
『そんな絵を描いていたら馬鹿になるからやめなさい!』
物心ついた時から絵を描き続けてきた。正直なところ、辞められるなら今すぐにでも絵を描くことを辞めたいくらいに描き続けてきた。なのにどうしてだろう。今、無性に絵が描きたいのは――
「そ、そんな夢に私なんかの絵を使ってもいいの?」
「私なんか……だと? ふざけるんじゃない!」
脚永さんが上げた声は今日一番大きな叫び声で、詰め込める限りの怒りを込めた爆音だった。音峰さんですら気圧されて一歩下がっている。桧垣さんに至っては既に泣いてしまっている。舞薗くんは相変わらず飄々としているが……。
「私はな? 私が好きなものを否定する言葉が大嫌いなんだ! 私が好きになった君の絵を『なんか』という言葉で馬鹿にするんじゃない! 私が大切にしている物を貶すんじゃない!」
「ご、ごめんなさい……」
桧垣さんは脚永さんの怒号で、見ていられないほどに泣きじゃくってしまった。
「まあまあ、脚永さん。そこまで言わなくても」
舞薗くんが仲裁に入ったのは正直なところ意外ではあったが、脚永さんを落ち着かせることができたようで俺は安堵した。そんな気配を殺すようにして隅っこで立っているだけの卑怯な俺を差し置いて話は進む。
「すまない。しかし、これだけは分かってほしい。君の絵は何物にも代えがたい掛け替えのない素晴らしいものだということを」
「うん……うん……ありがとう。でも、私もオタクとかキモイとか……言われることが多かったから脚永さんの気持ちも分かるの。だから嬉しいと……思ったし。そんな志のある人と一緒にって思ったら感情的になっちゃって……。怒られて泣いたわけじゃないの。その……なんていうか……なんか分かんないけど……」
桧垣さんは嗚咽を漏らしながら自分の心境を告白した。
「私は一緒にやりたい」
「後は佐藤くんの返事だけだけど?」
泣きじゃくる桧垣さん以外の視線が集まる。隅っこで気配を消していた俺の下へ――
「えっと……何で俺を選んだのか教えてくれる?」
「中学生の時に国展で見た君の絵にインスピレーションを受けてこの脚本ができたからよ」
ドンと重い音を立てて叩かれるダンボール。中学二年の時に出展した国展――。俺の作品はコネによって出展されることになったようなもので、もちろん受賞も何もしなかった。学校では話に出したことも無いし、ましてや見た人がいるとは思わなかった。
受賞に至らなかったことを母に責められ、泣きながら家で引き裂いた事を覚えている。俺の思い出したくない思い出の一つだ。
「他にも良い絵はたくさんあったのに……と言っても脚永さんは俺の作品に感銘を受けたといって譲らないんだろうね。うん。いいよ。協力する。でも条件がある」
「なんだい? 私にできることなら呑もう」
「半年でアニメにするほどの絵を描くということは、俺は本業としての絵をほとんど書けなくなるんだと思う。そうなるとまあ……母親に縁を切られると思うんだ。中学生の時に母が望まない絵を描こうとしたり、絵の道から降りようとしたりした時……縁を切るって言われてるんだ。つまりまあ、最低でも高校卒業まで生活を保障してもらわないといけなくなる」
「さ、佐藤……あんたそこまでしないといけないなら断っても……」
音峰さんは彼女らしくない挙動で心配しながら俺に言う。
「ううん。いいんだ音峰さん。俺も脚永さんと同じように死の淵で後悔したくないだけだから。このまま嫌いな絵を描き続けて終わるくらいなら、昔大好きだった絵をまた好きになって夢中で描きながら死にたい……そう思っただけなんだ。でも、それをするにもせめて高校在学中の生活はどうにかしないといけないと思うから」
「な、なんであんたたちはそんなに死ぬとか人生とか言えるわけ? わけ分かんない」
「そう言うことなら私のウチに来ると良い」
「いや、脚永さん。流石に女子の家に上がり込ませるのは問題だろ。俺んち来いよ。部屋なら余ってるし親も何も言わない」
最後に助け舟……と言うか助け家を提供してくれたのは予想外にも舞薗くんだった。
「よし。では決まりだな。さっそく今日から動ける人は動いてもらおう。一秒が惜しい。音峰さんにはこれを」
そう言って渡されたのは一枚のDVDと辞書程の厚さの資料か何か。
「脚本とラフ画で作った紙芝居的なアニメ。今はこれだけだけど、作曲の方お願い」
「……十分よ」
「桧垣さんと佐藤くんにはこれ」
脚永さんそう言われて俺と桧垣さんはダンボール箱を一つずつ受け取った。
「桧垣さんはこの資料を基に原画約五百枚を三ヵ月で。佐藤くんは編集して使いまわすから大判の背景画を約百枚を同じく三ヶ月で」
「え、えっと……てことは一日当たり……原画五枚以上……?」
「やってくれるわよね?」
「は……はい」
「俺は一日一枚か……でクオリティは?」
「国展に出してたレベルかそれ以上で」
「りょ……了解です」
国展に出した作品は一年がかりで描いた代物なんだけど……とは言えなかった。
「あと、私のことは監督と呼ぶように」
「はい! 監督!」
いの一番にそう言ったのは舞薗くんだった。意外と悪乗りが好きなのかもしれない。
霜月三日の午前十時。監督が檀上で響かせた声は真っ直ぐに観衆の心に突き刺さったことだろう。あの日の俺たちのようにこれから起こる出来事に人生を奪われてしまうことだろう。
そう――春休み明けの始業式の日のように――
四月。始業式後に彼女は俺の教室を訪れた。強制連行のような形で連れられた俺は何一つ言葉を発する余裕すらも与えられずに放送室へ押し込められた。中にはすでに集められていた生徒が三人。俺も含めて全員が三年生。つまり今年受験を控えた人間だ。俺を除けば女子が二人と男子一人。それに俺の手を掴んでいる彼女と俺で合計五人。
いったいこれから何が起こるというのだろうか。
「君たちを集めたのは他でもない。私に譲ってほしいものがあるからだ!」
防音の放送室でこれ見よがしに大声を上げた主犯の彼女はホワイトボードを平手で叩くと、抜身の刀を振るうようにズバズバと書きなぐった。
アニメ――と。
「十一月三日の文化祭当日! 一本のアニメを上映したい! その為に諸君らの半年を私に譲って貰う!」
提案ではなく確定事項のように言い放った彼女の目には、迷いも気負いもその一切が無かった。やると決めたからやる――その意志しかなかった。俺はその迫力に委縮してしまって言葉が出ずに立ち尽くすばかり。
「は? ふざけてんの? 私ら受験生だし、そんな時間あるわけないじゃん。私が呼ばれたってことは棒人間アニメと適当なアフレコって訳じゃないんでしょ? ナシナシ。やんない」
気迫に当てられることなく反論したのは音峰鈴(おとみねすず)。学内のみならず、高校三年生ながら日本中で知る人ぞ知る音楽家だ。去年彼女が作詞作曲を手掛けた歌がアニメに使われたことで学内でも有名になった。
「音楽活動も今年は停止するつもりだし、そんな焦るような企画に手を付けたくない」
「わ、私も自信ない……かな」
音峰さんに乗るようにして言ったのは桧垣彩加(ひがきあやか)。彼女もまた知る人ぞ知る有名人。イラストサイトで名を馳せ、去年までは何年も連続で同人誌即売会にて壁を任される人物。俺みたいな絵描きをしている人間にとって羨むべき人間だ。
「俺は別にいいぞ。どうせ俺がやるのはアフレコだろ? 大して時間取られそうでもないし」
最後に言ったのは舞薗元気(まいぞのげんき)。彼は前述した二人ほど有名ではないが演劇部の部長として、昨年全国高等学校演劇大会に出場していた。
「報酬は? 受験失敗した時の将来の保証は? 私たちのメリットは? 私と舞薗はまだどうにかなるかもしれないわよ。でも、地獄を見る上に取り返しがつかないのは桧垣さんと佐藤でしょ? それにあんた。脚永(きゃくなが)さん。あんたの負担がデカすぎるんじゃない?」
脚永涼子(きゃくながりょうこ)。彼女は彼女で市民劇団の脚本を手掛け、この高校の演劇部にも作品を卸す脚本家。おそらく彼女が脚本、構成、演出、監督、その全てを担うことになるのだろう。到底今からできるとは思えない。
「本気でやるには時間が無さすぎるって言ってんの。受験が終わってからにしてくれる?」
「それじゃ遅いんだ! 今この時しかダメなんだ!」
「だから! 今から脚本とか――」
音峰さんが更に反論しようとした瞬間。脚永さんは足元のダンボール箱を持ち上げて机の上に置いた。激しくわざとらしく音が響くように三度繰り返した。
「脚本も構成も演出もラフ画もできてる! 私は本気だ! 私はこの世界を作るためにこの二年間を過ごしてきた!」
「ば、馬鹿じゃないの。これで私たちが首を縦に振らなかったら、あんたの何千時間かが無駄になったかもしれないっていうのに」
「これが叶わなければ、私は死の淵で何十年もの人生が無駄だったと言うかもしれない! 今しか……今しかないんだ……」
脚永さんは泣いていた。涙を流しながらすがるようにダンボールを叩いていた。音峰さんもその様子に心を打たれてしまったのか、伏し目がちになっていた。
「……桧垣さんと佐藤がやるっていうなら付き合ってあげるわよ」
そして遂に折れた音峰さんは桧垣さんと俺に選択を委ねるという迷惑な決断をしてくれた。
「私は……」
口ごもる様に言う桧垣さんは俺の顔色を何度も何度も伺っていた。先に発言することを促すと、桧垣さんより先に脚永さんが口を開いた。
「私はオタクだキモイだと言われ続けてきたアニメで世界を変えたい! 悔しいんだ――私が感動したものが、学んできたことが、没頭してきたものが否定される現実が! 私は声を高らかにして言いたい。これが私たちの世界だ、世界一美しい世界だと!」
風が吹いたような気がした――。体中を駆け巡る冷たい血潮が暖かくなるのを感じた。それと共に昔母に言われた言葉を思い出した。
『そんな絵を描いていたら馬鹿になるからやめなさい!』
物心ついた時から絵を描き続けてきた。正直なところ、辞められるなら今すぐにでも絵を描くことを辞めたいくらいに描き続けてきた。なのにどうしてだろう。今、無性に絵が描きたいのは――
「そ、そんな夢に私なんかの絵を使ってもいいの?」
「私なんか……だと? ふざけるんじゃない!」
脚永さんが上げた声は今日一番大きな叫び声で、詰め込める限りの怒りを込めた爆音だった。音峰さんですら気圧されて一歩下がっている。桧垣さんに至っては既に泣いてしまっている。舞薗くんは相変わらず飄々としているが……。
「私はな? 私が好きなものを否定する言葉が大嫌いなんだ! 私が好きになった君の絵を『なんか』という言葉で馬鹿にするんじゃない! 私が大切にしている物を貶すんじゃない!」
「ご、ごめんなさい……」
桧垣さんは脚永さんの怒号で、見ていられないほどに泣きじゃくってしまった。
「まあまあ、脚永さん。そこまで言わなくても」
舞薗くんが仲裁に入ったのは正直なところ意外ではあったが、脚永さんを落ち着かせることができたようで俺は安堵した。そんな気配を殺すようにして隅っこで立っているだけの卑怯な俺を差し置いて話は進む。
「すまない。しかし、これだけは分かってほしい。君の絵は何物にも代えがたい掛け替えのない素晴らしいものだということを」
「うん……うん……ありがとう。でも、私もオタクとかキモイとか……言われることが多かったから脚永さんの気持ちも分かるの。だから嬉しいと……思ったし。そんな志のある人と一緒にって思ったら感情的になっちゃって……。怒られて泣いたわけじゃないの。その……なんていうか……なんか分かんないけど……」
桧垣さんは嗚咽を漏らしながら自分の心境を告白した。
「私は一緒にやりたい」
「後は佐藤くんの返事だけだけど?」
泣きじゃくる桧垣さん以外の視線が集まる。隅っこで気配を消していた俺の下へ――
「えっと……何で俺を選んだのか教えてくれる?」
「中学生の時に国展で見た君の絵にインスピレーションを受けてこの脚本ができたからよ」
ドンと重い音を立てて叩かれるダンボール。中学二年の時に出展した国展――。俺の作品はコネによって出展されることになったようなもので、もちろん受賞も何もしなかった。学校では話に出したことも無いし、ましてや見た人がいるとは思わなかった。
受賞に至らなかったことを母に責められ、泣きながら家で引き裂いた事を覚えている。俺の思い出したくない思い出の一つだ。
「他にも良い絵はたくさんあったのに……と言っても脚永さんは俺の作品に感銘を受けたといって譲らないんだろうね。うん。いいよ。協力する。でも条件がある」
「なんだい? 私にできることなら呑もう」
「半年でアニメにするほどの絵を描くということは、俺は本業としての絵をほとんど書けなくなるんだと思う。そうなるとまあ……母親に縁を切られると思うんだ。中学生の時に母が望まない絵を描こうとしたり、絵の道から降りようとしたりした時……縁を切るって言われてるんだ。つまりまあ、最低でも高校卒業まで生活を保障してもらわないといけなくなる」
「さ、佐藤……あんたそこまでしないといけないなら断っても……」
音峰さんは彼女らしくない挙動で心配しながら俺に言う。
「ううん。いいんだ音峰さん。俺も脚永さんと同じように死の淵で後悔したくないだけだから。このまま嫌いな絵を描き続けて終わるくらいなら、昔大好きだった絵をまた好きになって夢中で描きながら死にたい……そう思っただけなんだ。でも、それをするにもせめて高校在学中の生活はどうにかしないといけないと思うから」
「な、なんであんたたちはそんなに死ぬとか人生とか言えるわけ? わけ分かんない」
「そう言うことなら私のウチに来ると良い」
「いや、脚永さん。流石に女子の家に上がり込ませるのは問題だろ。俺んち来いよ。部屋なら余ってるし親も何も言わない」
最後に助け舟……と言うか助け家を提供してくれたのは予想外にも舞薗くんだった。
「よし。では決まりだな。さっそく今日から動ける人は動いてもらおう。一秒が惜しい。音峰さんにはこれを」
そう言って渡されたのは一枚のDVDと辞書程の厚さの資料か何か。
「脚本とラフ画で作った紙芝居的なアニメ。今はこれだけだけど、作曲の方お願い」
「……十分よ」
「桧垣さんと佐藤くんにはこれ」
脚永さんそう言われて俺と桧垣さんはダンボール箱を一つずつ受け取った。
「桧垣さんはこの資料を基に原画約五百枚を三ヵ月で。佐藤くんは編集して使いまわすから大判の背景画を約百枚を同じく三ヶ月で」
「え、えっと……てことは一日当たり……原画五枚以上……?」
「やってくれるわよね?」
「は……はい」
「俺は一日一枚か……でクオリティは?」
「国展に出してたレベルかそれ以上で」
「りょ……了解です」
国展に出した作品は一年がかりで描いた代物なんだけど……とは言えなかった。
「あと、私のことは監督と呼ぶように」
「はい! 監督!」
いの一番にそう言ったのは舞薗くんだった。意外と悪乗りが好きなのかもしれない。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


足跡を辿って
清水さわら
青春
桜宮雪路は苦悩の夜を過ごす。
中学を卒業し、ラノベを書き始めて三日でスランプに陥った彼はそれでも一か月もの間、夜から明け方にかけての時間を執筆に捧げた。
しかし、物語という化け物を御し切ることは出来ず。高校へ進学した桜宮は文芸部に入って停滞した状況を打破しようとする。
そこへ現れたのは同じ入部希望者の一人の少女。白鳥迦夜だった。
高校在学中に商業作家デビューを果たすと宣言する白鳥と、未だ苦悩の夜から抜け出せない桜宮が織りなす青春物語。
……のはず。


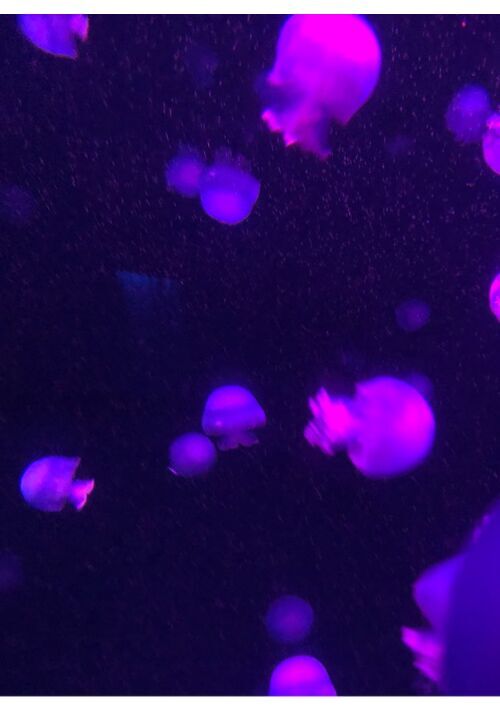
夜空の軌跡
スイートポテト
青春
社会福祉法人星空学園。森の中にひっそりとそれは建てられ、児童養護施設として運営されている。ここは「自由に挑戦。」をもっとうに、様々な理由で入所してくる子どもを預かる施設だ。業界でも名の高い施設で、入所した子ども達はイキイキとした生活を過ごしている。
そんな星空学園には、ある5人のエリート高校生達がいる…この物語は、そんな天才達が、入所してくる様々な子供達の問題を解決する、青春ラブコメディである。

あにめぶ! ~私立垣鳥高校アニメーション研究部~
輪島ライ
青春
私立垣鳥高校アニメーション研究部、通称アニメ部。そこでは4名+αの部員たちがアニメとその周辺について語り合っています。
※この作品は「小説家になろう」「アルファポリス」「カクヨム」「エブリスタ」に投稿しています。

全力でおせっかいさせていただきます。―私はツンで美形な先輩の食事係―
入海月子
青春
佐伯優は高校1年生。カメラが趣味。ある日、高校の屋上で出会った超美形の先輩、久住遥斗にモデルになってもらうかわりに、彼の昼食を用意する約束をした。
遥斗はなぜか学校に住みついていて、衣食は女生徒からもらったものでまかなっていた。その報酬とは遥斗に抱いてもらえるというもの。
本当なの?遥斗が気になって仕方ない優は――。
優が薄幸の遥斗を笑顔にしようと頑張る話です。

泣かないで、ゆきちゃん
筆屋 敬介
青春
【 彼女のお気に入りの色鉛筆の中で、一本だけ使われていないものがありました。
それは『白』。
役に立たない色鉛筆。 】
ゆきちゃんは、絵を描くことが大好きな女の子でした。
そんな絵も笑われてしまう彼女は、いつも独りでスケッチブックを開いていました。
得意なモノも無く、引っ込み思案のゆきちゃん。
でも、ゆきちゃんと白には、彼女たちだからこその『特別な力』があったのです。
高校生になったゆきちゃん。
ある日、独りで絵を描く彼女のもとに憧れの先輩が現れます。先輩は彼女自身も知らない魅力に気が付いて……。
1万4千字の短編です。お気軽にお読みくださいな。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















