29 / 36
第4部 「摩天楼の決戦編」
しおりを挟む
29話
「もういいよ、喋んなくていいから。今すぐ黙らせてやるから!」
「フフッ♪ じゃあ有言実行してもらおうかなぁッ!!」
バリバリッ
遊馬は人差し指から白く光る電撃を放つ。
桐生はタイミングを上手く見つけて回避する。
そのサイクルを繰り返す。
いつまでも電撃を避けるので精一杯の桐生に対し、遊馬は遠くからただ人差し指を桐生に向けて電気を放ち続ければいいだけなので、どちらがより早く体力を消耗するかなんてのは言わずもがなである。
「はぁ、はぁ・・。テメェもいい加減動けよ・・。」
「やっだよーー。だって疲れちゃうでしょー?」
桐生の能力は"相手に直接触れないと"発動しない。 つまり近接戦闘向きである。 それに対して遊馬は遠くから電撃を撃つだけの遠隔戦向きだ。
「 ・・らいなね。さっき人殺しが楽しいから戦ってるって言ったけど、戦いが好きな理由はもう一つあるの。それはね、『他人が一生懸命積み重ねてきた努力を簡単に、それでいて一瞬でぶち壊すことが出来る』から。
らいなの電撃さえあれば、例え相手が早かろうと鍛えていようと背が高かろうと、全てのハンデを塗り潰すことができる。
そしてらいなの電撃によってねじ伏せられた馬鹿どもの苦痛と悔恨の表情を拝めること。これ以上の娯楽はないね!
らいなにはこの電撃がある。どんな敵をも一瞬で葬り去るこの力があれば、最早らいなは
世界最強同然!! らいなに逆らえる奴はこの世のどこにもいな、 」
バキィッ!!
「ほぇ?」
遊馬から素っ頓狂な声が出た。
一瞬何があったのか理解が追いつかなかった。
遊馬はなぜか地面に仰向けになっていた。 目に映っているのは塔の天井だけだ。
おかしい。
桐生は確かに自分の電撃によって体力が消耗していたはずなのに。
おかしい。
何故か頰の辺りが痛い。口からはたらりと、一筋の鮮血が垂れている。
遊馬は口元の血を手で拭い取りしばらく見つめる。
「あ・・れ。らいな・・、ぶっ飛ばされたの・・?」
辛うじて上体のみを起こし、前方を見てみる。 そこには固く握られた拳を前に突き出して立ち尽くしている少年の姿があった。
「あは、あはは・・。おかしいな・・。」
遊馬は今でも信じられない。 桐生はやがて地面を寝っ転がっている遊馬の元にやってくる。 そして今度は桐生が遊馬を見下すようにして喋る。
「・・・俺はさ、実を言うと怖くないんだ。お前みたいな能力ばかりに依存してる類の奴って。そういう奴は戦いのどっかで油断するからさ。そう思った瞬間、お前のことが途端に弱くみえたんだ。 いや、むしろ可哀想に見えてきた。」
まるで虫ケラを見るような目で視線を浴びせてくる桐生に対して、遊馬はまだ理解ができていなかった。
「分からないよ・・。」
「だってそんな・・、おかしいよ。
らいなの電撃を喰らったら暫くは行動不能に陥るんだよ? 下手したら死んじゃうんだよ?
それなのになんで立ってられるの?」
桐生は呆れたようにため息をつく。
「分からないのか? まあ無理もないか。お前みたいな人間には一生分からないだろうな。」
「な・・に?」
「お前のその雷撃は確かに強い。いや、無敵と言っても過言じゃない。 けどな。お前のやっているそれは『戦闘』じゃない。ただの『人殺し』だ。
その力の威力が強すぎるが故にお前は『屠殺』を『戦闘』だと錯覚してしまった。」
「可哀想な目をして・・・、このらいなを、らいなを・・ッ!! 馬鹿にすんじゃねェよこのクソザコがぁああああああ!!」
遊馬の口調は先程までに比べて豹変していた。
遊馬の指先から最大出力の雷撃が桐生めがけて繰り出される。 そして攻撃は直撃した。
直撃したはずなのに・・。
「倒れないッ!?」
桐生は電撃を喰らっても平然として立っていた。身体中がボロボロになっているのにも関わらず。
「・・痛くねぇんだよ。 テメエの『弱さ』に気付いちまったせいでな・・!」
遊馬・桐生間の距離は五メートル程である。
「ふんっ♪ならばもう一度 "雷電の拳" で・・」
拳を握り銀のグローブに雷を集約させる遊馬。
「早くッ、早くチャージをッ・・!!」
しかし焦りからか遊馬の体から平常通りの電力が働かない。
その瞬間だった。
シュンッという音が遊馬の耳に入った瞬間
蹴りを放った桐生の靴底が目に映った。
ドガッッ!!
「ぶふゥッ・・・!」
遊馬の身体は高く打ち上げられ、そのまま頭から地面に墜落した。
「そんな・・。らいなの・・負け・・?」
遊馬は地面に沈んだまま、目と口は開きっぱなしだった。彼女の頭はまだ脳内処理が追いついていなかった。
「ああそうだ。 そしてお前は立ち上がる土俵を間違えた。」
桐生は自らの勝利を確信する。
「そうか。これが"敗北" というものなんだね・・・。」
遊馬はやがて目を閉じ、全身から力が抜ける。
ビーーーーーーーッ
『試合終了!! 準々決勝を制したのは桐生選手です!!!』
桐生は体についた埃を軽く払い、振り返る。
するとそこには予想外な人物が立っていた。
「お前、なんでここに!?」
その少年は緑のコートに革靴を履いた宿敵だった。
「君は僕を見るたびに一々驚くんだね。」
一ノ瀬佑太郎だ。
「お前確か今日コンビニのバイトの日だったんじゃ・・。」
「ああ、クビにされた。」
「即答かよ!! 」
「だから一日暇になってしまってね。 君の試合を見物させてもらったってわけさ。」
「なんでお前はいっつも上から目線なんだよ。」
「・・しっかしそれにしてもさっきの少女ときたら実に醜いね。 」
一ノ瀬はそっけなく誤魔化す。
「ああ。それについては同意だ。お前と意見が合うなんて一生無いと思ってたがな。」
「人を殺すだけしか能の無い戦士なんて三流以下だね。 僕のようなある程度の美意識を備えた人間じゃないと、 高みを目指す事など出来やしないさ。 折角の彼女の端麗な容姿が勿体無いくらいだ。」
「自分で言うか?それ・・」
「兎にも角にも残りの試合、と言ってももう僅かだが、せいぜい僕を失望させないでくれよ。」
「もとよりそんなつもりは無いさ。」
"宿敵"は言うだけ言ってワープの能力で観客席に戻っていった。
優勝まであと・・・ 二戦!
To Be continued..
「もういいよ、喋んなくていいから。今すぐ黙らせてやるから!」
「フフッ♪ じゃあ有言実行してもらおうかなぁッ!!」
バリバリッ
遊馬は人差し指から白く光る電撃を放つ。
桐生はタイミングを上手く見つけて回避する。
そのサイクルを繰り返す。
いつまでも電撃を避けるので精一杯の桐生に対し、遊馬は遠くからただ人差し指を桐生に向けて電気を放ち続ければいいだけなので、どちらがより早く体力を消耗するかなんてのは言わずもがなである。
「はぁ、はぁ・・。テメェもいい加減動けよ・・。」
「やっだよーー。だって疲れちゃうでしょー?」
桐生の能力は"相手に直接触れないと"発動しない。 つまり近接戦闘向きである。 それに対して遊馬は遠くから電撃を撃つだけの遠隔戦向きだ。
「 ・・らいなね。さっき人殺しが楽しいから戦ってるって言ったけど、戦いが好きな理由はもう一つあるの。それはね、『他人が一生懸命積み重ねてきた努力を簡単に、それでいて一瞬でぶち壊すことが出来る』から。
らいなの電撃さえあれば、例え相手が早かろうと鍛えていようと背が高かろうと、全てのハンデを塗り潰すことができる。
そしてらいなの電撃によってねじ伏せられた馬鹿どもの苦痛と悔恨の表情を拝めること。これ以上の娯楽はないね!
らいなにはこの電撃がある。どんな敵をも一瞬で葬り去るこの力があれば、最早らいなは
世界最強同然!! らいなに逆らえる奴はこの世のどこにもいな、 」
バキィッ!!
「ほぇ?」
遊馬から素っ頓狂な声が出た。
一瞬何があったのか理解が追いつかなかった。
遊馬はなぜか地面に仰向けになっていた。 目に映っているのは塔の天井だけだ。
おかしい。
桐生は確かに自分の電撃によって体力が消耗していたはずなのに。
おかしい。
何故か頰の辺りが痛い。口からはたらりと、一筋の鮮血が垂れている。
遊馬は口元の血を手で拭い取りしばらく見つめる。
「あ・・れ。らいな・・、ぶっ飛ばされたの・・?」
辛うじて上体のみを起こし、前方を見てみる。 そこには固く握られた拳を前に突き出して立ち尽くしている少年の姿があった。
「あは、あはは・・。おかしいな・・。」
遊馬は今でも信じられない。 桐生はやがて地面を寝っ転がっている遊馬の元にやってくる。 そして今度は桐生が遊馬を見下すようにして喋る。
「・・・俺はさ、実を言うと怖くないんだ。お前みたいな能力ばかりに依存してる類の奴って。そういう奴は戦いのどっかで油断するからさ。そう思った瞬間、お前のことが途端に弱くみえたんだ。 いや、むしろ可哀想に見えてきた。」
まるで虫ケラを見るような目で視線を浴びせてくる桐生に対して、遊馬はまだ理解ができていなかった。
「分からないよ・・。」
「だってそんな・・、おかしいよ。
らいなの電撃を喰らったら暫くは行動不能に陥るんだよ? 下手したら死んじゃうんだよ?
それなのになんで立ってられるの?」
桐生は呆れたようにため息をつく。
「分からないのか? まあ無理もないか。お前みたいな人間には一生分からないだろうな。」
「な・・に?」
「お前のその雷撃は確かに強い。いや、無敵と言っても過言じゃない。 けどな。お前のやっているそれは『戦闘』じゃない。ただの『人殺し』だ。
その力の威力が強すぎるが故にお前は『屠殺』を『戦闘』だと錯覚してしまった。」
「可哀想な目をして・・・、このらいなを、らいなを・・ッ!! 馬鹿にすんじゃねェよこのクソザコがぁああああああ!!」
遊馬の口調は先程までに比べて豹変していた。
遊馬の指先から最大出力の雷撃が桐生めがけて繰り出される。 そして攻撃は直撃した。
直撃したはずなのに・・。
「倒れないッ!?」
桐生は電撃を喰らっても平然として立っていた。身体中がボロボロになっているのにも関わらず。
「・・痛くねぇんだよ。 テメエの『弱さ』に気付いちまったせいでな・・!」
遊馬・桐生間の距離は五メートル程である。
「ふんっ♪ならばもう一度 "雷電の拳" で・・」
拳を握り銀のグローブに雷を集約させる遊馬。
「早くッ、早くチャージをッ・・!!」
しかし焦りからか遊馬の体から平常通りの電力が働かない。
その瞬間だった。
シュンッという音が遊馬の耳に入った瞬間
蹴りを放った桐生の靴底が目に映った。
ドガッッ!!
「ぶふゥッ・・・!」
遊馬の身体は高く打ち上げられ、そのまま頭から地面に墜落した。
「そんな・・。らいなの・・負け・・?」
遊馬は地面に沈んだまま、目と口は開きっぱなしだった。彼女の頭はまだ脳内処理が追いついていなかった。
「ああそうだ。 そしてお前は立ち上がる土俵を間違えた。」
桐生は自らの勝利を確信する。
「そうか。これが"敗北" というものなんだね・・・。」
遊馬はやがて目を閉じ、全身から力が抜ける。
ビーーーーーーーッ
『試合終了!! 準々決勝を制したのは桐生選手です!!!』
桐生は体についた埃を軽く払い、振り返る。
するとそこには予想外な人物が立っていた。
「お前、なんでここに!?」
その少年は緑のコートに革靴を履いた宿敵だった。
「君は僕を見るたびに一々驚くんだね。」
一ノ瀬佑太郎だ。
「お前確か今日コンビニのバイトの日だったんじゃ・・。」
「ああ、クビにされた。」
「即答かよ!! 」
「だから一日暇になってしまってね。 君の試合を見物させてもらったってわけさ。」
「なんでお前はいっつも上から目線なんだよ。」
「・・しっかしそれにしてもさっきの少女ときたら実に醜いね。 」
一ノ瀬はそっけなく誤魔化す。
「ああ。それについては同意だ。お前と意見が合うなんて一生無いと思ってたがな。」
「人を殺すだけしか能の無い戦士なんて三流以下だね。 僕のようなある程度の美意識を備えた人間じゃないと、 高みを目指す事など出来やしないさ。 折角の彼女の端麗な容姿が勿体無いくらいだ。」
「自分で言うか?それ・・」
「兎にも角にも残りの試合、と言ってももう僅かだが、せいぜい僕を失望させないでくれよ。」
「もとよりそんなつもりは無いさ。」
"宿敵"は言うだけ言ってワープの能力で観客席に戻っていった。
優勝まであと・・・ 二戦!
To Be continued..
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

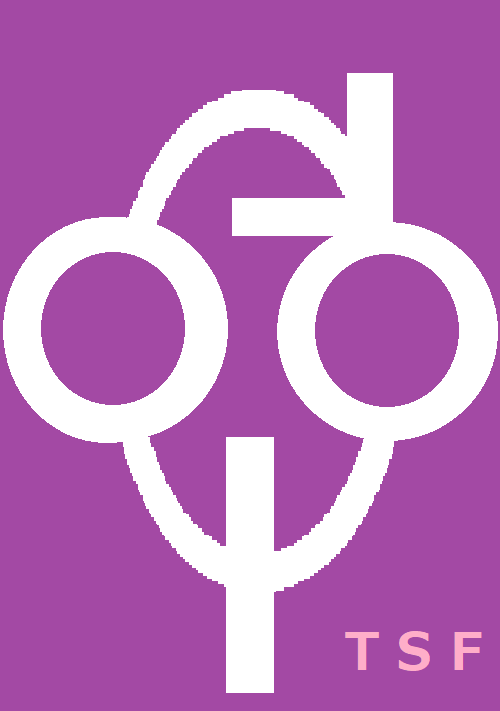

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。



求めていた俺 sequel
メズタッキン
SF
「求めていた俺」の続編。戦いは正念場へと突入する・・・
桐生は意識を失い病室のベットに横たわっていた。皇楼祭最後の戦いにて、『冥王』の『システムディスターバー』を辛くも攻略することが出来たが、桐生が受けた身体的、精神的ダメージ、疲労は極めて深かった。そして一ヶ月の入院生活を終えたある夜、桐生は謎の黒服の男に追われているクラスメイトの馬場コウスケを自宅に匿うことに。
・・・この行動が後に桐生の全てを踏みにじった男、祠堂流星との思いがけぬ邂逅を引き起こしてしまう。

フォトンの記憶
小川敦人
SF
少年時代、水泳部の仲間だったサトシ、田村、有馬の三人は、ある夏の日に奇妙な青白い光を目撃する。
その後、彼らの能力は飛躍的に向上し、全国大会で輝かしい成績を収めた。
しかし、その奇跡のような出来事を境に、彼らの人生は穏やかな日常へと戻っていく。
それから61年後——。
居酒屋で酒を酌み交わしながら、彼らはふと呟く。
「あれ以来、特別なことは何もなかったな」
「けど、平凡な人生を送れたことこそが奇跡なのかもしれない」。
静かに杯を交わす三人。その時、店の外には、かつて見たような青白い光がふわりと舞い上がっていた——。
SFとノスタルジーが交錯する、運命のひとときを描いた物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















